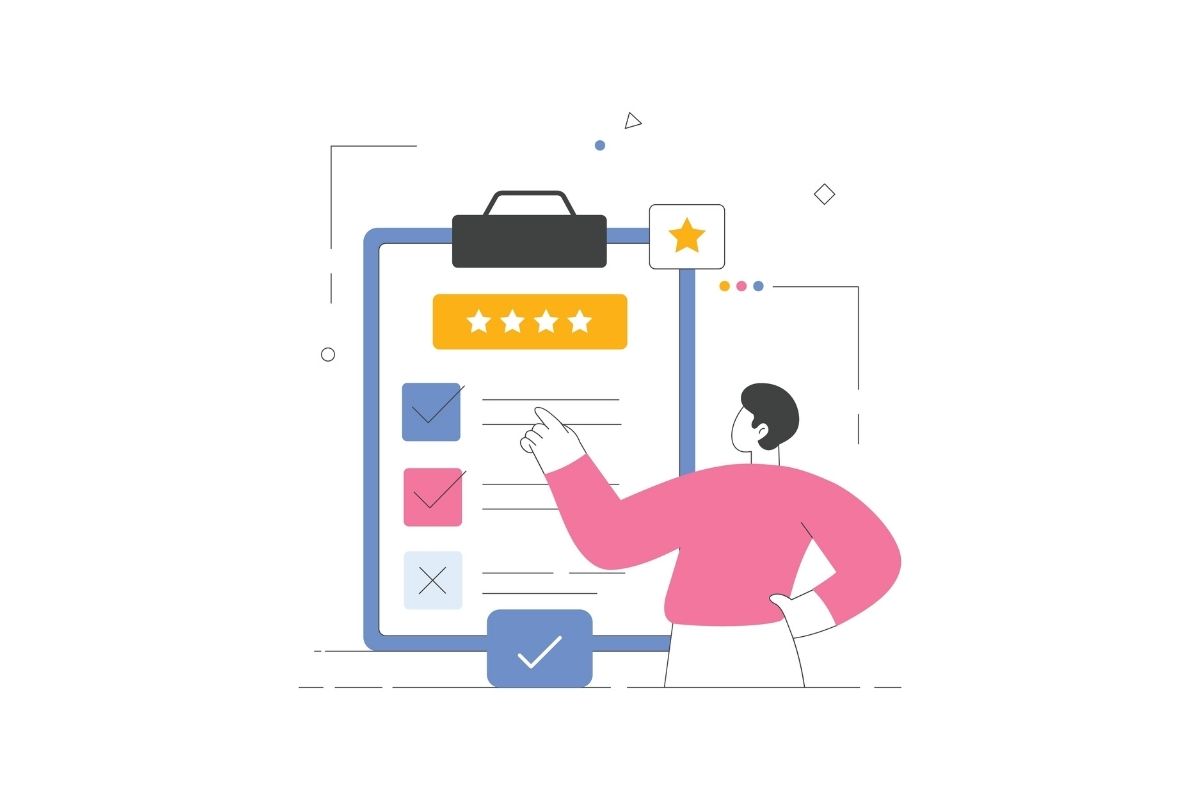人材育成研修とは?研修の目的や種類、設計方法を詳しく解説
更新日: 2025.10.30 公開日: 2025.4.14 jinjer Blog 編集部

人材育成研修は、社員一人ひとりの能力を引き出し、組織全体の成長を促すために欠かせない取り組みです。
多くの企業では体系的な人材育成研修を実施し、社員の能力開発を支援しています。研修の種類や内容は多岐にわたるため、自社に適した研修を選ぶことが重要です。
とはいえ、初めて人材育成研修をおこなう場合、どのような研修手法を選べばいいかわからないという担当者の方もいるのではないでしょうか。効果的な研修を設計・実施するには、人材育成をおこなう目的や研修の種類を把握しておく必要があります。
ここでは、人材育成研修の基本的な流れや目的、階層別に分かれた研修の種類について詳しく解説します。
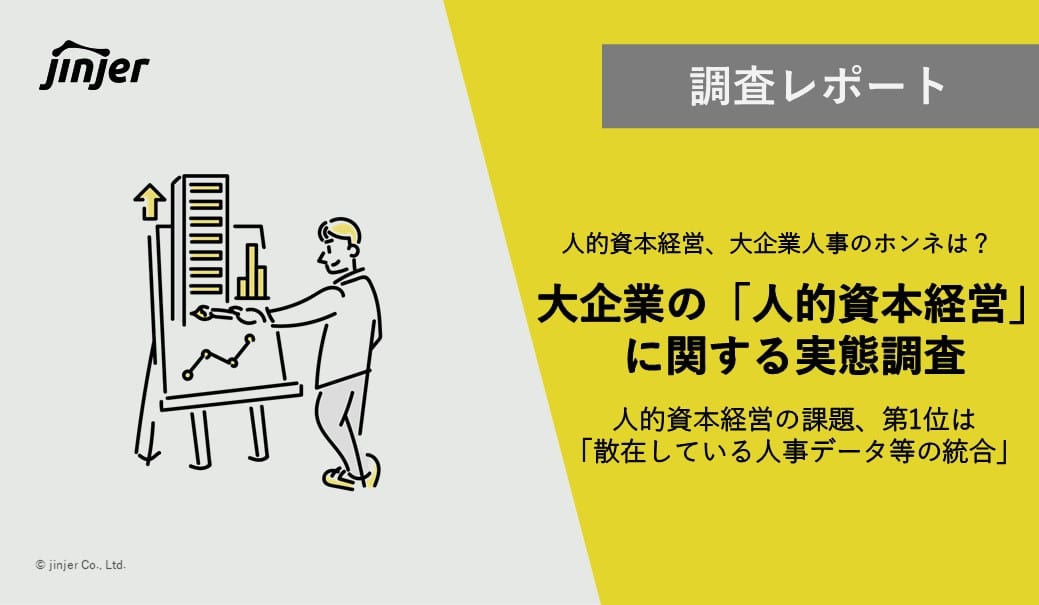
人的資本の情報開示が義務化されたことで人的資本経営への注目が高まっており、今後はより一層、人的資本への投資が必要になるでしょう。
こういった背景の一方で、「人的資本投資にはどんな効果があるのかわからない」「実際に人的資本経営を取り入れるために何をしたらいいの?」とお悩みの方も、多くいらっしゃるのが事実です。
そのような方に向けて、当サイトでは人的資本経営に関する実際調査の調査レポートを無料配布しています。
資料では、実際に人事担当者にインタビューした現状の人的資本経営のための取り組みから、現在抱えている課題までわかりやすくレポートしています。
自社運用の参考にしたいという方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
1. 人材育成研修とは

人材育成研修とは、企業が目標を達成するために、従業員のスキルや知識を向上させる取り組みのことです。
企業の成長には、従業員一人ひとりの能力向上が欠かせません。企業は人材育成研修を通じて、必要なスキルを体系的に習得させ、業務の効率化や生産性向上を図ります。
例えば、新入社員研修では、企業理念やビジネスマナーを学び早期の戦力化を促します。人材育成研修は単なる教育ではなく、企業戦略の一環として重要な役割を果たしているのです。
1-1. 人材育成研修の内容
人材育成研修の内容は、主に以下のように分けられます。
- 集合研修(外部講師)
- 集合研修(内部講師)
- ミニ集合研修(部内・課内研修)
- 0JT(現場教育)
- 自己啓発(通信教育)
- 公開講座(外部講師)
- eラーニング
外部講師による研修は専門的な知識を体系的に学べるのがメリットです。しかし、コストやスケジュール調整が課題となるでしょう。また、内部講師の研修は、企業独自のノウハウを伝えられる反面、講師育成の手間が発生します。OJTは実践的ですが、指導者のスキルによって効果に差が出るでしょう。
このように研修によって内容が異なるので、企業の目的や状況に応じて適切な研修方法を選択することが重要です。
1-2. 人材育成研修の流れ
人材育成研修は、計画から実施、振り返りまでの一連のプロセスを通じて、従業員の成長と組織の発展を図るものです。
具体的な流れとしては、まず人事部や研修担当者で「どのような人材を育てたいか」「どのようなスキルが必要か」などを話し合い、目的や目標を明確にします。次に、対象者や研修テーマを設定し、最適な研修方法(集合研修・eラーニング・OJTなど)を選定します。
研修の実施するには、講師の選定や教材の用意など事前準備が必要となるので、育成担当者と受講者のスケジュールの調整をしながら、スムーズにスタートできるようにしてください。
研修が終わった後は、アンケートやフィードバックをもとにした振り返りや効果測定をおこないます。また、受講者が実際の業務に研修内容を活かしているかどうかを確認する「フォローアップ」も欠かせません。
このように、人材育成研修は「計画」「実施」「評価・改善」の3ステップが主な流れになりますが、研修の手法を確認して抜けがないようにしっかり準備することが重要です。
2. 人材育成研修の目的とは

人材育成研修の目的は企業によって異なりますが、従業員が課題解決力を高め、企業の業績向上に貢献できるようにするというのが一般的です。研修を通じてスキルや知識を身につけることで、業務効率や生産性が向上し、企業全体の成長につながります。
新入社員には業務の基本を、中堅社員には専門性やリーダーシップを、管理職にはマネジメント能力を育成するなど、キャリアの段階に応じた研修をおこなうことで、各ポジションでの成果を最大化できます。また、社員自身の成長意欲を刺激し、モチベーションの向上や離職防止にもつながる点も大きなメリットです。
さらに、コンプライアンスやハラスメント対策などのテーマに取り組むことで、職場の健全性を高め、組織全体のリスクマネジメントにも効果を発揮してくれます。
人材育成研修というのは、ただスキルや知識を習得するだけの場ではなく、「人を育てることで組織を強くする」ための戦略的な施策と言えるでしょう。
3. 人材育成研修の種類

人材育成研修の種類はいろいろありますが、下記の7つが主流となっています。
- 新入社員研修
- 中堅社員研修
- 管理職研修
- コンプライアンス研修
- ハラスメント研修
- マーケティング研修
- コーチング研修
ここでは、育成研修の種類について詳しく解説します。
3-1. 新入社員研修
新入社員研修は、社会人としての基本的なマナーやビジネススキルを習得し、職場にスムーズに適応することを目的とした研修です。具体的には、挨拶や名刺交換、敬語の使い方などのビジネスマナー、報連相(報告・連絡・相談)の重要性、会社の制度や就業規則多岐にわたる内容が含まれます。また、近年はSNSの影響力が増しています。不適切な発信が企業のブランドイメージを損なうリスクがあるため、デジタルリテラシーの指導も重要です。
さらに、配属先での業務に入る前に企業の理念やビジョンを理解してもらうことで、自社への帰属意識やモチベーションを高める効果もあります。最近ではオンライン研修やグループワークを取り入れる企業も増えており、双方向のコミュニケーションを通じた学びの場が重視されています。
新入社員研修は、社会人としての土台を築く最初のステップであり、研修で得た知識や姿勢は今後の成長に大きく影響するので、長期的な視点で人材を育成していくことが重要です。
3-2. 中堅社員研修
中堅社員研修は、管理職と一般社員の橋渡し役を果たすために、必要なスキルやマインドを習得する研修で、業務経験を積んだ社員がより高いレベルで活躍できるように支援する目的でおこないます。
中堅層は現場の中心として実務をこなし、後輩の指導も担うポジションです。そのため、リーダーシップ力や課題解決能力、コミュニケーションスキルの強化が重視されます。また、自分の仕事だけでなく幅広い視点を持たせるために、全社的な戦略理解や他部門との連携力を高める内容も有効です。
近年では、心理的安全性やダイバーシティに関する研修を取り入れ、中堅層から組織風土改革を推進していく企業も増えています。
中堅社員の成長は、組織全体の底上げに直結します。業務だけでなく、人間関係やマネジメント面の課題にも焦点をあてることで、より実践的で効果の高い研修を実現できます。
3-3. 管理職(マネジメント)研修
管理職研修は、部下のマネジメントや組織の経営に必要な知識を習得し、変化する環境に適応できるリーダーを育成する研修で、経営的視点と人材育成スキルを身につけさせることを目的としています。
管理職には、業務推進だけでなく、部下の育成やチーム運営、部門の成果責任など、幅広い役割が求められます。そのため、研修では目標管理(MBO)や部下へのフィードバック技法、評価制度の理解、リスク管理、労務管理など実務に直結した内容が中心となるのが特徴です。
また、変化に対応できる柔軟な思考力や、心理的安全性の高いチームづくりに必要な知識も、管理職(マネジメント)研修の重要なテーマとなります。
管理職の研修を充実させることは、組織のパフォーマンス向上と離職率の低下に直結するので、管理職は常に学び続け、知識のアップデートが求められます。
3-4. コンプライアンス研修
コンプライアンス研修は、法令遵守や社内規定の理解を深め、企業としてのリスク管理を強化することを目的としている研修で、近年ではほとんどの企業で実施されています。企業は、情報漏洩や不正会計、ハラスメントなどのリスク抱えているので、定期的な実施が必要です。
研修では、会社の就業規則や個人情報保護法、公正な取引、社内通報制度などの基本的な知識を中心に、過去の事例をもとにしたケーススタディ形式でおこなわれることが多いようです。コンプライアンスに関する認識というのは人によって異なることが多く、またアップデートも必要となるので、社員一人ひとりが当事者意識を持ち、日々の業務において適切な判断ができるよう促します。
コンプライアンス研修は企業の信頼性を支える土台なので、形式的なものにならないよう、現場目線での工夫を取り入れることが重要です。
3-5. ハラスメント研修
ハラスメント研修は、職場におけるパワハラ・セクハラ・マタハラなどの防止と、安心して働ける環境づくりを目的に実施される研修です。現在、ハラスメントは企業に対して防止措置がが義務付けられているので、ハラスメント研修はすべての社員が対象となります。
研修では、ハラスメントの定義や具体例、加害者・被害者にならないための対応策、相談窓口の案内などを丁寧に説明します。また、管理職向けの研修には、初期対応や再発防止の方法をなどの内容も盛り込むことが重要です。
ハラスメントを防止することは、職場の人間関係の悪化やメンタルヘルス不調の予防にもつながるりますが、企業全体での積極的な取り組みが必要なので、参加しやすく理解を深められる研修をおこないましょう。
3-6. マーケティング研修
マーケティング研修は、顧客ニーズを捉えた商品・サービスの企画・販売戦略の立案力を育成することを目的としています。営業部門や商品開発部門、企画部門だけでなく、全社員がマーケティング思考を持つことで、企業の競争力は大きく向上します。
研修では主に、「製品・価格・流通・プロモーション」の基礎から始まり、マーケット分析やペルソナ設定、ブランド戦略、デジタルマーケティングの活用など実践的な内容が扱われます。
研修をおこなうことで、自社の強みと市場の変化を正しく捉える力を養うというのは、将来の成長戦略のポイントになります。業種や部門に応じて内容をカスタマイズすることで、学びの定着度が高まります。
3-7. コーチング研修
コーチング研修は、部下の自主性や成長意欲を引き出すマネジメントスキルを高める目的でおこなう研修です。近年の職場環境というのは、指示命令型ではなく対話型の関わり方がスタンダードになっています。そのため、従来のトップダウン型で業務をおこなっている管理職やリーダーには、コーチング研修が必要です。
研修では、傾聴・承認・質問といった基本スキルを中心に、実際のシチュエーションを想定したロールプレイ形式で実践力を養うのが一般的です。コーチングというのは、失敗をすると部下と馴れ合いの関係になってしまいます。しかし研修をおこなうことによって、部下と一線を引きながらも、上から目線ではなく寄り添った指示・指導が可能になります。
部下との信頼関係を築き、主体的な行動を促すコミュニケーションスキルは、今後の組織運営において不可欠な要素です。
4. 人材育成研修の設計方法

人材育成研修の設計は、以下の流れでおこないます。
- 研修の目的や目標を明確にする
- 研修担当者を決定する
- 研修方法を決定する
- 具体的な研修内容を決定する
- 研修を実施する
- 研修を振り返る・報告書を作成する
それでは各工程を詳しく見ていきましょう。
4-1. 研修の目的や目標を明確にする
効果的な研修を実施するためには、目的や目標を明確にすることが大切です。研修は単なる学習の場ではなく、企業が抱える課題を解決し、社員の成長を促すために実施されます。
目的とは「なぜ研修を実施するのか」、目標とは「研修を通じてどのような成果を期待するのか」というゴールの設定です。例えば「新入社員にビジネスマナーを身につけさせる」「中堅社員にリーダーシップを養成する」といった目的を定めたら、それに応じた到達目標「電話応対ができる」「1on1の進行ができる」などを具体的に設定しましょう。
目的や目標が曖昧なままでは、受講者にとっても意味のある学びにならず、企業の成長にもつながりません。人事や現場の声も取り入れて、自社がどのような人材を求めているか、社員がどのようなスキルや知識を必要としているかを把握しましょう。
4-2. 研修担当者を決定する
研修の成否は、誰がその企画・運営を担うかによって大きく左右されるので、適切な研修担当者を決定しましょう。担当者が明確でないと、研修の運営がスムーズに進まず、十分な効果を得られない可能性があるためです。
研修担当者は、研修の企画・運営を円滑に進めるために必要な役割を担います。具体的には、スケジュール調整・研修対象者の選定・内容の企画・講師との連携など多岐にわたる業務を担当するので、研修の目的や対象者を理解した上で、適切な指導ができる人物を選ぶことが重要です。
社内研修の場合、研修の進行役として受講者を適切に導くスキルが求められます。一方、外部委託する場合は研修会社との連携を円滑に、企業のニーズに沿った研修を実施できるよう調整する能力が必要です。
4-3. 研修方法を決定する
研修の目的や対象者の課題に応じて、最適な研修方法を選定することが重要です。適切な手法を選ぶと、受講者の学習効果が高まり、実務に活かせるスキルが身につきます。
研修方法は、大きく分けて「OJT(On-the-Job Training)」と「OFF-JT(Off-the-Job Training)」の2種類です。OJTは実務を通じた学習を重視するため、経験を積みながらスキルを習得できます。
一方、OFF-JTは座学やワークショップを活用し、理論や知識を体系的に学ぶのに適した方法です。研修の目的によって手法を使い分けると、より効果的な人材育成ができるでしょう。
4-4. 研修内容を具体的に決める
研修内容は、企業が抱える課題や人材育成の方針に基づいて具体的に決定しましょう。受講者のスキルや知識レベルに応じて内容を調整しなければ、効果的な研修にはなりません。
研修の効果を最大限に引き出すには、対象者のニーズに合わせて「何を教えるか」を明確にし、具体的なカリキュラムを設計することが重要です。例えば、新入社員にはビジネスマナーや会社の理念、中堅社員にはリーダーシップや問題解決力、管理職には部下育成や業績管理の手法というように、階層に応じた内容を設計する必要があります。
内容の決定にあたっては、現場の上司や本人からヒアリングをおこない、現状の課題や期待される役割を明確にします。その上で、講義・演習・グループワーク・ケーススタディなど、学びやすく実践的な構成に仕立てると効果的です。
4-5. 研修を実施する
研修内容が決まったら、実際に研修を実施します。研修実施の段階では、事前に計画した内容や進行スケジュールに基づいて、スムーズに進行することが重要です。また、研修を成功させるためには、参加者が学びやすい環境を整え、研修の目的を明確に伝えることが重要です。どれだけ準備しても、実施段階で適切な進行ができなければ、研修の効果は十分に発揮されません。
また、講師は一方的な講義に終始せず、受講者との対話や質問の時間を確保するなど、双方向のコミュニケーションを意識することも大切です。
実施当日は、トラブルがあっても柔軟に対応できる体制を整えておくことに加え、実施後の振り返りやフォローに向けて、アンケートの配布などもこの段階でおこなっておきましょう。
4-6. 研修を振り返る・フィードバックを作成する
研修の実施が終わったら、成果や改善点を洗い出すための「振り返り」と「フィードバック作成」をおこないましょう。
研修が終わったら、受講者に振り返りの時間を作ってもらいます。研修を受けること自体が目的ではなく、その内容を実務に活かし、組織全体の成長につなげることが重要だからです。研修を実施しただけで終わると、学びが定着せず、一時的な知識にとどまる可能性があります。研修を振り返ると、受講者は学びを整理し、実務への応用方法を考えられるでしょう。
まずは受講者アンケートや簡易テストを通じて、理解度や満足度を把握します。どの内容が役立ったのか、難しかったのか、今後の業務にどう活かせると感じているかなどの情報を収集します。
加えて、講師や研修担当者による振り返りミーティングをおこない、当日の進行状況や運営面の課題を洗い出すこと忘れないでください。得られたフィードバックは、次回以降の研修設計に活かすだけでなく、研修報告書として経営層や関係部門に共有することで、社内の育成方針に一貫性を持たせることができます。
5. 人材育成研修を成功させるポイント

人材育成研修を成功させるポイントは、下記の4点が挙げられます。
- 研修目的を周知する
- 現場で必要な研修をおこなう
- 育成担当者はマネジメントスキルを身につけておく
- 目標は達成できるように設定する
ここでは、これらのポイントについて解説していきます。
5-1. 研修目的を周知する
研修を成功させるためには、受講者はもちろん研修担当者や管理者に対しても、「研修の目的」や「期待される成果」をしっかり周知することが重要です。目的を全員で共有しないまま研修を実施してしまうと、参加者が学ぶ意欲を持てないことが多く、内容が十分に吸収されません。
「なぜこの研修を受けるのか」「どう活かしてほしいのか」を事前に説明することで、学びへの姿勢が前向きになります。
また、研修担当者や管理者に目的を周知し、現場でのフォローを依頼することで、研修の学びが職場で定着しやすくなります。可能であれば、目的とともにゴールのイメージや活用例も伝えると、理解を得やすくなります。
目的の周知は、上司からの説明や全体説明会などをおこない、組織全体で共有することが効果的です。関係者全員で同じ方向を向くことが、研修の成果を最大化するカギとなります。
5-2. 現場で必要な研修をおこなう
人材育成研修は「現場の業務に直結する内容」であることが、受講者の実践意欲を高めるポイントです。
理論や一般論だけで終わるのではなく、実際の仕事で求められるスキルや知識をテーマにすることで、学びがそのまま行動に移されやすくなります。例えば、営業職には提案力や商談スキル、管理職には部下育成や目標管理の研修など各職種や役割に応じた「現場目線」の内容が求められます。
現場のニーズを把握するには、受講対象者本人やその上司へのヒアリング、業務分析などの事前調査が有効なので、必ず調査をおこなっておきましょう。現場と乖離した研修では効果が薄れるため、常に「現場で使えるか」を意識した研修が成功のポイントです。
5-3. 育成担当者はマネジメントスキルを身につけておく
人材育成研修を実施・支援する側の「育成担当者」や「現場の上司」は、マネジメントスキルを身につけておくことが重要です。当然ですが研修をおこなう側にいは、一定のマネジメントスキルやファシリテーション能力が求められます。これらの能力がないと、個人的な価値観や判断が研修内容に影響を与えてしまうので、必ずマネジメントスキルを身につける研修をおこないましょう。
具体的には、部下の特性を把握しながら成長を促すコーチングやフィードバックの技術、進捗管理やモチベーション維持の手法などが含まれます。また、育成に関わる担当者自身が研修を体験し、講師の伝え方やプログラム設計のポイントを学ぶことで、自身の育成力向上にもつながります。
社内に教育担当を置く場合は、事前にその担当者のトレーニングをおこない、育成に関する基本スキルを習得してもらうとよいでしょう。
5-4. 目標は達成できるように設定する
研修の効果を高めるには、受講者が達成できる現実的な目標を設定することが大切です。目標が高すぎる達成できないと、逆にやる気をなくしたり挫折を招いたりするリスクがあります。また、逆に低すぎると成長意欲を刺激できません。
大切なのは、現在のスキルや業務レベルを踏まえた「達成可能かつ成長を実感できる目標」を設定することです。
目標は「業務で◯◯をできるようにする」「1ヶ月以内に学んだ内容を活用した◯◯をおこなう」など、具体的で成果を可視化できるものにするのが効果的です。また、研修開始前に目標を明示し、終了後にはどの程度達成できたかを振り返ることで、受講者自身が成長を実感できます。
達成感が得られる仕組みを整えることで、学びが継続しやすくなり、研修の成果が職場に定着しやすくなります。
6. 適切な人材育成の研修で会社の目標を達成しよう

人材育成研修は、企業の成長に不可欠な取り組みといえます。研修の目的は、社員のスキル向上と業務効率の改善です。具体的には、業務に必要な知識や技術を習得させることを目指します。
研修にはさまざまな種類があるため、座学型や実務研修・オンライン研修など、企業のニーズに応じて選びましょう。研修内容には、リーダーシップやコミュニケーションスキル、専門的な技術や業務知識などが含まれます。
人材育成は短期的な成果ではなく、長期的な視点で継続することが重要です。企業の課題や目的と連動させながら、定期的に見直しをおこない、柔軟に研修内容を進化させることも成功のポイントです。適切な研修設計と運用を通じて、従業員と組織の成長を実現しながら会社の目標を達成していきましょう。
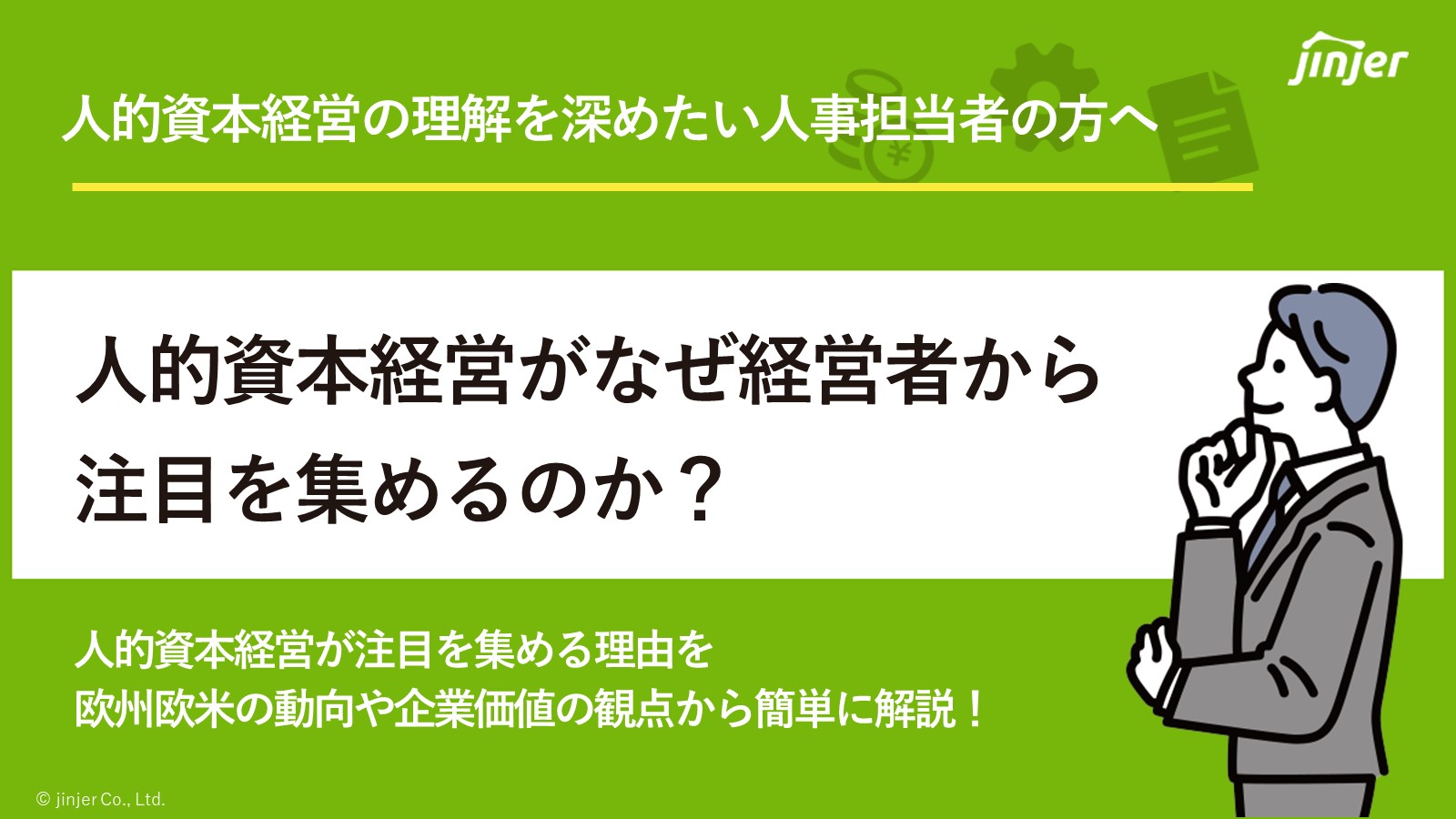
企業価値を持続的に向上させるため、いま経営者はじめ多くの企業から注目されている「人的資本経営」。
今後より一層、人的資本への投資が必要になることが想定される一方で、「そもそもなぜ人的資本経営が注目されているのか、その背景が知りたい」「人的資本投資でどんな効果が得られるのか知りたい」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて、当サイトでは「人的資本経営はなぜ経営者から注目を集めるのか?」というテーマで、人的資本経営が注目を集める理由を解説した資料を無料配布しています。
資料では、欧州欧米の動向や企業価値を高める観点から、人的資本経営が注目される理由を簡単に解説しています。「人的資本経営への理解を深めたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
タレマネの関連記事
-

離職防止ツールとは?目的・メリット・種類・選び方をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2026.01.15更新日:2026.01.14
-

従業員の状態を可視化するコンディションサーベイとは?選び方も解説
人事・労務管理公開日:2026.01.05更新日:2025.12.26
-

人事データに必要な項目とは?データ構築のメリットやポイントとともに詳しく解説
人事・労務管理公開日:2025.08.26更新日:2025.10.21