雇用保険被保険者証とは?必要になるケースや発行のタイミングも解説
更新日: 2024.7.11
公開日: 2022.4.11
OHSUGI
会社に初めて入社したときに発行される雇用保険被保険者証は、さまざまなシーンで必要になる書類です。
労働者が必要としたときに速やかに手続きできるよう、雇用保険被保険者証の基礎知識をしっかり押さえておきましょう。
今回は、雇用保険被保険者証の概要や必要になるケース、発行のタイミング、有効期限、再発行の可否などについて解説します。
関連記事:雇用保険とは?給付内容や適用される適用事業所について
目次
社会保険の手続きガイドを無料配布中!
社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 雇用保険被保険者証とは、雇用保険加入時に発行する書類のこと
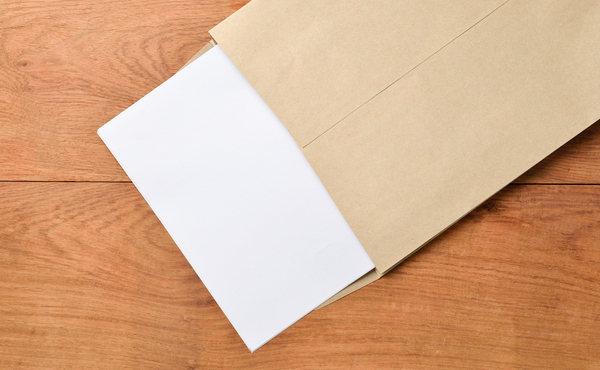
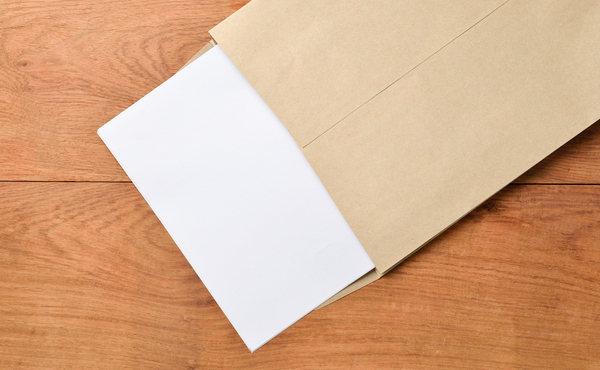
雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入した際、ハローワークが発行する書類のことです。
労働者を雇用する事業は、原則として業種や規模を問わず、すべて雇用保険の適用事業となります。以下の1と2の要件に該当する労働者を雇うときは、雇用保険の加入手続きをしなくてはいけません。[注1]
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者(以下いずれかに該当する場合)期間の定めがなく雇用される場合
a. 雇用期間が31日以上である場合
b. 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
c. 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用され、31日以上雇用された実績がある場合 - 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
以上の要件に該当する労働者を雇い入れるときは、たとえ1人でも雇用保険の加入手続きをおこない、雇用保険被保険者証を発行してもらう必要があります。
[注1]雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!|厚生労働省
1-1. 雇用保険被保険者証の記載内容
雇用保険被保険者証に記載されている内容は次のとおりです。
- 被保険者番号
- 被保険者の氏名
- 被保険者の生年月日
雇用保険被保険者資格等確認通知書(被保険者通知用)と一体になっており、横210mm、縦77mmとシンプルかつ小さな書類です。被保険者(労働者)が雇用保険の適用事業者に雇用される限り使用するものなので、紛失しないよう大切に取り扱わなければなりません。
なお、雇用保険被保険者証はハローワークが発行して事業者に交付された後、紛失などを防止するため、そのまま会社で保管することが多いです。
1-2. 離職票との違い
労働者が退職する際にわたす書類には、雇用保険被保険者証のほかに離職票があります。離職票とは、労働者が退職したことを証明する公的な書類です。
労働者が失業手当を受け取る際に必要な書類ですが、退職するすべての労働者に発行する必要はありません。希望する労働者のみ、会社が発行手続きをおこなえば良いとされています。
一方で、雇用保険被保険者証は、加入条件を満たす労働者に必ず発行しなくてはいけないものです。書類の性質や発行義務に違いがあるので、混同しないよう注意しましょう。
2. 雇用保険被保険者証が必要なケース


雇用保険被保険者証は、会社側と労働者側で必要となってくる場面がそれぞれ異なります。
ここでは、雇用保険被保険者証が必要になるケースを、企業・労働者別に解説します。
2-1. 会社が雇用保険被保険者証を必要とするケース
会社が雇用保険被保険者証を必要とするケースは、新たに労働者を雇い入れる時です。
雇用する労働者が新卒者(初めて雇用保険に加入する人)の場合、事業者は必要書類を揃えた上で、所轄のハローワークにて雇用保険の加入手続きをおこなう必要があります。
一方、雇用する労働者が転職者(すでに雇用保険に加入している人)の場合は、労働者が前の職場から受け取った雇用保険被保険者証を提出してもらい、雇用保険の加入手続きをおこなうことになります。
加入手続きをおこなった後に雇用保険被保険者証を会社で保管する場合は、労働者が退職するまで厳重に管理をおこないましょう。
2-2. 労働者が雇用保険被保険者証を必要とするケース
労働者が雇用保険被保険者証を必要とするケースは、大きく分けて3つあります。
2-2-1. 転職するとき
まず1つ目は、今いる会社を退職し、他の会社に転職するときです。
雇用保険被保険者証は、被保険者個人に発行するものなので、働く場所が変わっても同じ被保険者番号(雇用保険被保険者証)を使用することになります。
そのため、転職先で雇用保険に加入する場合は、退職時に前の職場から雇用保険被保険者証を返却してもらい、入社時に転職先の会社へ提出する必要があります。
2-2-2. 教育給付金の申請手続きをするとき
2つ目は、教育訓練給付の支給申請をおこなうときです。
教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的に整備された雇用保険の給付制度です。[注2]
雇用の安定または再就職のために厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、これを修了した場合、教育訓練給付の支給申請をおこなえば、教育訓練施設に支払った経費の一部を支給してもらうことができます。
なお、教育訓練は再就職を目指す離職者だけでなく、スキルアップを狙う労働者(雇用保険に3年以上加入している人に限る)も受けることが可能です。そのため、場合によっては在職中の労働者から雇用保険被保険者証の返却を求められることもあります。
[注2]教育訓練給付制度|厚生労働省
2-2-3. 厚生年金保険の決定請求をするとき
3つ目は、65歳未満の人が老齢厚生年金を前倒しで請求するときです。
65歳未満で年金を受給する場合、毎月の給与額に応じて年金額の減額が決まるため、在職状況をハローワークへ確認するために雇用保険被保険者証が必要となります。
万が一紛失してしまった場合は再発行するか、または「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」いずれかの書類で代用することも可能です。
3. 雇用保険被保険者証の発行のタイミングと有効期限


初めて雇用保険に加入する労働者を雇い入れる場合、その労働者が被保険者となった日(入社日など)の属する月の翌月10日までに、ハローワークにて雇用保険被保険者資格取得届の手続きをおこなう必要があります。[注3]
事業を立ち上げたばかりで、初めて労働者を雇用する場合は所轄のハローワークで「事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を、その後に新たに労働者を雇用する場合は、その都度「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することになります。
雇用保険被保険者資格取得届の手続きは、ハローワークの窓口、オンライン、郵送のいずれかでおこなえますが、それぞれ発行のタイミングが異なります。
最も早く発行できるのはハローワークの窓口で、手続きをした当日に雇用保険被保険者証を発行してもらえます。
一方、ハローワークのインターネットサービスを利用して申請した場合の発行タイミングは2~3開庁日が目安です。最も発行タイミングが遅いのは郵送手続きで、ハローワークに書類が届くまでに時間がかかること、紙媒体の書類なので手続きが遅れることなどから、申請(郵送)から発行までに1週間程度の時間がかかる可能性があります。
また、郵送の場合は切手代などのコストや、ポストに投函する手間もかかるところがネックです。なるべく早く発行したいのならハローワークの窓口、手間と時間を節約したいのならオンライン申請を利用するのがおすすめです。
3-1. 雇用保険被保険者証の有効期限
雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号は、原則として労働者1人に1つ割り当てられるものです。
転職によって職場が変わったとしても、被保険者番号は変更されず、前の職場で発行された雇用保険被保険者証を引き続き使用することになります。
ただし、離職によって雇用保険の資格を喪失してから7年以上が経過すると、労働者に割り当てられていた被保険者番号がハローワークのデータから抹消されてしまいます。
7年以上のブランクがある労働者を雇用する場合、ハローワークに提出する雇用保険被保険者資格取得届の「取得区分」は、これまで雇用保険に加入したことがない人同様、「新規」となりますので注意しましょう。
本記事では、雇用保険の資格取得手続きについて解説しましたが、資格喪失時や雇用保険以外の保険の資格取得時にも手続きが必要になります。本章で解説したように、発行には期限が決まっているので忘れずに対応するようにしましょう。
当サイトでは、上述した雇用保険や社会保険の加入するタイミングや手続き、担当者の気を付けるポイントなどをまとめた資料を無料で配布しております。手続きの期限や手続き内容に関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。
4. 雇用保険被保険者証の変更が必要なケース


労働者を新規採用した場合以外でも、雇用保険被保険者証の手続きが必要となるケースがあります。次のいずれかに該当する場合は、雇用保険被保険者証の変更手続きが必要です。
- 事業所の名称や所在地に変更があった場合
- 労働者の異動や転勤があった場合
事業所名や所在地に変更があった際には、「雇用保険事業主事業所各種変更届」を変更日の翌日から10日以内に提出します。また、労働者の異動や転勤に関しては「雇用保険被保険者転勤届」を、異動または転勤の事実があった日の翌日から10日以内に提出して、それそれ変更手続きをおこないます。
5. 雇用保険被保険者証は再発行できる?


雇用保険被保険者証を紛失、あるいは損傷した場合は、ハローワークで「雇用保険被保険者証再交付申請書」を提出して手続きすれば、再発行することが可能です。
手続きは一般的に、雇用保険被保険者証を紛失または損傷した本人(被保険者)がおこないます。ただし、在職中に会社で保管していた雇用保険被保険者証を紛失・損傷した場合は、事業主が再交付申請をおこなうことも可能です。
雇用保険被保険者証再交付申請書には、申請者の氏名や住所、現在雇用されている事業所、最後に被保険者として雇用されていた事業所(前の職場)、取得年月日、被保険者番号、紛失または損傷の理由などを記載する項目があります。
なお、紛失で被保険者番号がわからないという場合でも、前の職場の名前と所在地を記載すれば、ハローワークのデータベースを検索することによって被保険者番号を確認することができます。
一方、離職してから7年が経過していてハローワークにデータが残っておらず、かつ雇用保険被保険者証を紛失している場合は、新たに発行し直さなくてはいけません。
再発行手続きは、窓口で行う場合は原則として即日発行してもらえますが、オンライン申請の場合は数日かかることもあります。そのため、新しく雇用した労働者から「雇用保険被保険者証が見当たらない」と申し出を受けた場合は、なるべく早めに再発行申請をおこなうよう通達しましょう。
6. 雇用保険被保険者証は労働者を雇用する際に必要となる書類


雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを証明する書類です。
前職で雇用保険に加入したことがある人を雇う場合は、加入手続きにあたって、労働者から雇用保険被保険者証を提出してもらう必要があります。
紛失・損傷によって雇用保険被保険者証を提出できない場合は、入社日までにハローワークの窓口またはオンライン申請により、再発行申請を済ませてもらいましょう。
社会保険の手続きガイドを無料配布中!
社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08





















