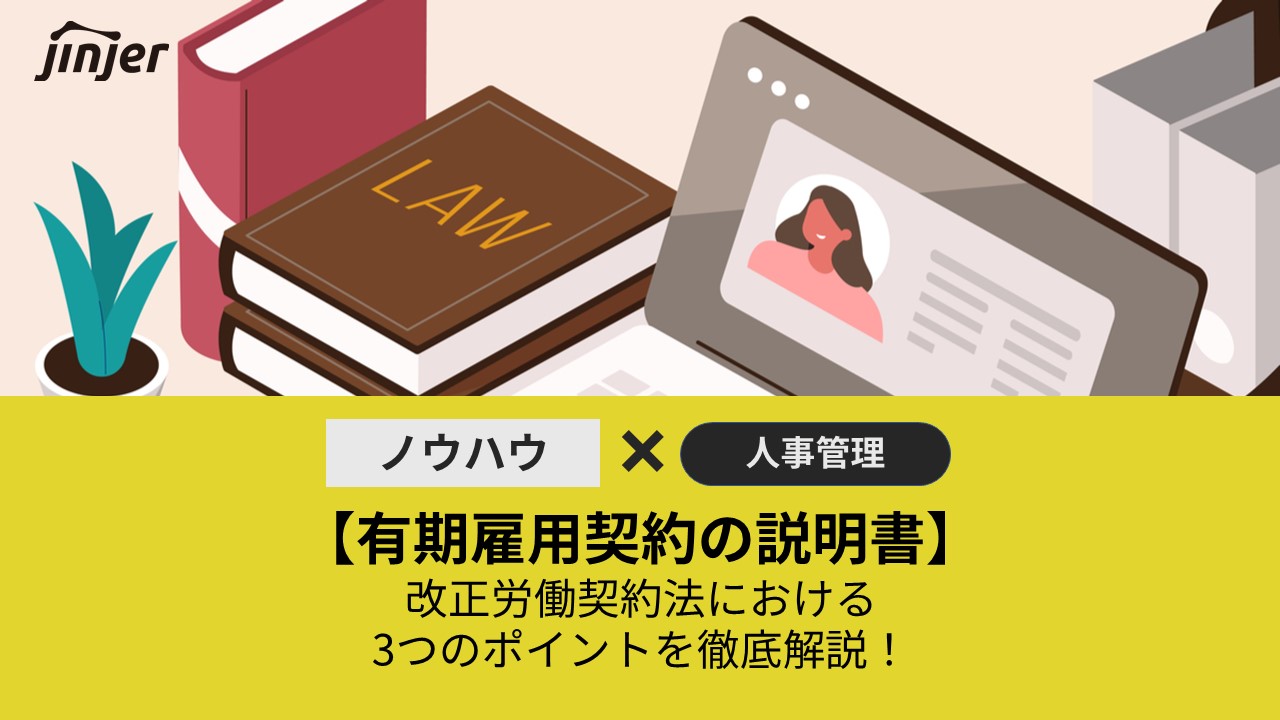労働契約法5条による「労働者の安全への配慮」の意味や注意点
更新日: 2024.1.16
公開日: 2021.10.2
OHSUGI
 労働契約についての基本的なルールが定められた労働契約法は、労働紛争の解決をはかる法律として、平成20年3月に施行されました。この契約法の中で、労働者の健康管理や教育・指導、職場の安全衛生の確保などを定めているのが労働契約法第5条「労働者への安全配慮」です。企業がこの義務を怠ると、損害賠償請求などのトラブルが発生するリスクがあるので、担当者は義務の内容について正しく把握しておく必要があります。
労働契約についての基本的なルールが定められた労働契約法は、労働紛争の解決をはかる法律として、平成20年3月に施行されました。この契約法の中で、労働者の健康管理や教育・指導、職場の安全衛生の確保などを定めているのが労働契約法第5条「労働者への安全配慮」です。企業がこの義務を怠ると、損害賠償請求などのトラブルが発生するリスクがあるので、担当者は義務の内容について正しく把握しておく必要があります。
ここでは、労働契約法5条で明文化されている「労働者の安全への配慮(安全配慮義務)」について、詳しく解説します。
▼そもそも労働契約法とは?という方はこちらの記事をご覧ください。
労働契約法とは?その趣旨や押さえておくべき3つのポイント
目次
【有期雇用契約の説明書】
1. 労働契約法5条「労働者の安全への配慮」とは?

労働契約法では、労働契約に関するさまざまなルールが明記されています。特に労働契約法5条「労働者の安全への配慮」では、労働者の事故防止や健康面の管理をおこなうため、企業が講じるべき措置を細かく規定しています。
そのため、「労働者の安全への配慮」を実施するには、いくつかのポイントをおさえた対策が必要になるので、しっかり把握しておきましょう。
1-1.「労働者の安全への配慮」を実施するために必要なこと
企業側が「労働者の安全への配慮」を実施するためには、労働環境や業務内容を加味し、具体的な対策を講じなければなりません。
労働者の安全を確保するためには、以下の2点に重点を置きましょう。
- 労働者の作業環境を整える
- 労働者の健康管理を行なう
以下、それぞれについて詳しく説明します。
1. 労働者の作業環境を整える
労働者が安全に作業可能となる環境の整備は、「労働者の安全への配慮」において最も重要な点となります。
具体的な対策として、日常的に利用される機器の整備や点検のほか、安全に配慮した作業手順の見直し、また、事故の要因となりうる作業環境の確認および対策などが挙げられます。
このほかにも、機器の使い方に関する指導や安全保護具についての知識共有、災害時の対応方法についての研修などの実施なども重要です。いずれも労働者の作業中のトラブル発生を未然に防ぎ、最適な作業環境を提供するために必要な要素となります。
2. 労働者の健康管理をおこなう
労働者に安全な労働環境を提供するためには、労働者自身の健康管理を企業側で実施することも重要です。
労働者の健康管理とは、心と体、両面での管理のことを指します。もちろん、事故や怪我のほか、内蔵疾患の発見やメンタルの不調についても早期に発見し、対応していかなければなりません。
具体的な対策としては、以下のようなことが挙げられます。
- 産業医や産業保健スタッフといった専門知識をもった人材と連携を行い職場の巡回を実施する
- 健康診断やメンタルヘルスチェックを積極的に行い、早期に不調を発見する
- ハラスメントやいじめが発生することの無いよう、研修の実施や相談窓口を設置する
- 労働者の労働時間を企業側できちんと把握し、長時間労働をなくす努力をする
1-2.「労働者の安全への配慮」で配慮すべき対象者とは
「労働者の安全への配慮」で配慮すべき労働者とは、自社の正社員だけとは限りません。外部から自社へ出向き、働いている労働者についても同様に配慮が必要となりますので注意が必要です。
「労働者の安全への配慮」で正社員のほかに配慮する労働者は、下請け企業の労働者と派遣労働者になります。
これらの労働者については、自社と直接の労働契約はなくても、自社側で安全配慮義務を負わなければなりません。義務を怠った場合は、正社員への義務を怠ったことと同じになるので、必ず安全配慮義務を実施しましょう。
2. 労働契約法5条「労働者の安全への配慮」の注意点

労働契約法5条「労働者の安全への配慮」は「義務」となっているので、軽視してしまうことがあるかもしれません。しかし、義務を怠ってしまうと従業員からの損害賠償請求や企業のイメージダウンなど、企業にとってのリスクが発生する可能性があります。
ここでは、労働契約法5条による「労働者の安全への配慮」の注意点について詳しく解説するので、担当者の方は確認しておきましょう。
2-1. 損害賠償請求のリスク
「労働者の安全への配慮」に違反した場合、労働契約法の条文には罰則に関する記載はありません。しかし、民法715条では使用者責任に対して、以下のような規定を設けています。
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。引用:民法|e-Gov法令検索
つまり、安全配慮義務違反に該当している場合、労働者側から損害賠償請求をされるリスクがあるのです。義務違反が故意ではないと証明できれば問題ありませんが、証明できなければ企業側が損害賠償請求に応じる必要があるので注意しましょう。
2-2. 企業のイメージダウン
企業が「労働者の安全への配慮」に違反したことで、大きな事故を起こしてしまったりパワハラ認定をされたりした場合、報道などによって企業名が公になる可能性があります。当然ですが、事故やパワハラのニュースで企業名が知れ渡ると、企業側のイメージダウンになります。
イメージがダウンすると、売上の減少や顧客離れはもちろん、求人募集をしても人が集まらない、優秀な人材の離職などが起こるリスクもあるので、企業にとって大きなマイナスになるので注意が必要です。
3.労働契約法5条「労働者の安全への配慮」違反への罰則
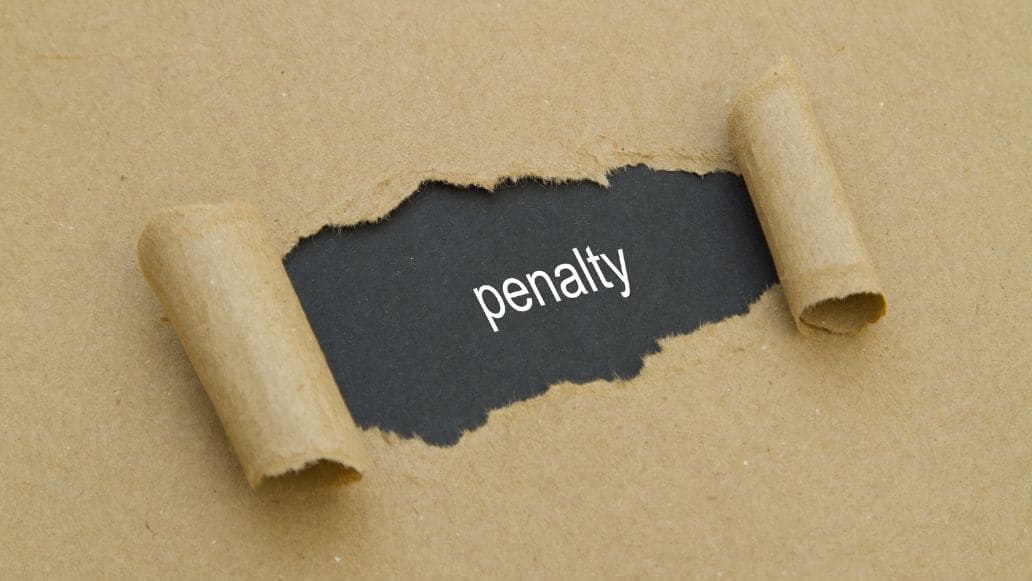
結論からいうと、「労働者の安全への配慮」義務に違反をしたとしても、労働契約法における罰則規定はありません。そのため、「損害賠償を請求されてもいい」「イメージダウンをしてもいい」という場合は、義務を守らなくて良いとも言えます。
しかし、労働基準法違反の可能性があるパワハラなどが発覚した場合には、労働基準監督署や官庁からの調査が入る可能性があるので注意しなければなりません。悪質性や故意が認められると、指導や勧告を受けることがあります。
指導、勧告に従わなかったり、悪質性が高かったりした場合は企業名を公表されることもあるので、法的な罰則はなくても社会的制裁を受ける可能性があることは覚えておきましょう。
4.労働契約法5条「労働者の安全への配慮」を守るポイント

労働契約法第5条による、「労働者の安全への配慮」を守るためには、以下5つのポイントに重点をおいて対策を実施する必要があります。
- 労働時間に関する規定を作り、管理を徹底する
- 安全衛生管理の体制を整備する
- 積極的なメンタルヘルス対策を実施する
- 労働災害や事故防止対策を徹底させる
- いじめ・ハラスメントに対する適切な措置を実施する
以下、それぞれのポイントについて説明します。
4-1. 労働時間に関する規定の作成・管理を徹底する
長時間労働や過労による健康被害を抑制するためにも、労働時間に関する規定を作成して管理をおこなう必要があります。雇用者側が労働時間を正確に管理することは、健康被害の防止につながります。具体的には、「残業の際には必ず上司への申請をおこなう」「承認を受けない限り残業できない」などの対策が有効です。
また、労働時間の規定は労働者だけでなく、管理者にも当てはまります。管理者自身が規程を遵守すれば、労働時間に対する従業員の意識を高める効果が期待できるでしょう。
4-2. 安全衛生管理の体制を整備する
部署や現場ごとに、安全衛生管理の体制の整備をおこないましょう。業種によっては、危険性の高い機器による事故も起こることがあるので、誤操作を防ぐための安全装置の設置なども必要になるかもしれません。さらに、安全装置の動作チェックや機器のマニュアル管理、研修環境を整備するなども重要な対策です。
機器を扱わない業種の場合は、「衛生管理者や安全衛生推奨者を設置する」「安全衛生教育の実施」などをおこなう必要があります。また、労働者の健康管理のため、定期的な健康診断の実施もおこないましょう。
4-3. 積極的なメンタルヘルス対策の実施
労働者のメンタルヘルスに関する問題は、近年、企業側でも積極的に関わっていかなければならない課題のひとつとなっています。適切に対処していくためにも、心身の健康相談ができる社内にカウンセラーや、健康診断結果の確認や職場巡視などをおこなう産業医などプロフェッショナルな人材を配置するのが望ましいでしょう。
会社の規模によってはプロフェッショナルな人材配置が難しいかもしれませんが、そのような場合は、労働者へのメンタルヘルスに関する情報の提供・教育などをおこなうという施策が必要です。
4-4. 労働災害や事故防止対策の徹底
作業中の事故は、企業側で未然に防止していかなければなりません。作業内容や危険性に応じて安全装置の設置をおこなったり、安全確保の意識を高めるために定期的な研修を実施したりしましょう。
安全装置の設置は、従業員が安全に働くことができる環境づくりに必須の対策です。労働の場所ごとに必要な安全装置を適切な形で設置し、従業員を保護しなければなりません。
具体的には、身を守るための安全ヘルメットや転落を防ぐ防護柵などが挙げられます。ただし、安全装置を設置するだけではなく、定期点検やメンテナンスをしっかりおこなって、正常に稼働するか常にチェックしておきましょう。
4-5. いじめ・ハラスメントに適切な措置を実施する
職場でのいじめやハラスメントに対しては、企業側で被害に関する報告や相談の窓口を設けるなど、適切な措置を講じる必要があります。どのような形であれ、いじめやハラスメントは許されないという毅然とした態度で臨みましょう。
このほかにも、企業側で定期的にいじめやハラスメントに対する教育を実施するなど、社内でも意識の共有をはかっていくことも必要です。
5.「労働者の安全への配慮」を遵守して安全な労働環境を提供しよう

今回は、労働契約法5条で規定されている「労働者の安全への配慮」の概要や注意点、法令遵守のためのポイントについてご紹介しました。
「労働者の安全への配慮」は、労働者へ安全な労働環境を提供するための企業側の責任でもあります。義務の遵守を怠った場合の企業側のリスクを理解し、遵守のためのポイントをおさえた対策を実施していくことが重要です。
現時点で安全配慮義務が実施できていないようであれば、自社の業務内容や作業の危険性などの状況を正確に把握して、最適な安全対策をおこなっていきましょう。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16
労働契約法の関連記事
-

労働契約申込みみなし制度とは?禁止事項や企業への影響について
人事・労務管理公開日:2022.03.23更新日:2024.01.15
-

労働契約法18条に定められた無期転換ルールを分かりやすく解説
人事・労務管理公開日:2021.10.04更新日:2024.10.21
-

労働契約法16条に規定された「解雇」の効力と無効になるケース
人事・労務管理公開日:2021.10.04更新日:2024.10.09