労働契約書の保管期間や正しく保存する方法を紹介
更新日: 2024.4.15
公開日: 2021.11.12
OHSUGI

企業に入社する際には企業と雇用者の双方が労働契約書に押印する必要があります。契約内容に納得した上で契約を結びますが、この労働契約書はあとからいつでも確認できるようにしておく必要があります。この労働契約書には保管期間が定められています。勝手に廃棄しないように注意しましょう。
雇用契約は法律に則った方法で対応しなければ、従業員とのトラブルになりかねません。
当サイトでは、「自社の対応が適切か確認したい」という人事担当者様に向け、雇用契約の方法から、雇用契約についてよくある質問までをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しております。
雇用契約業務を適切に進めるための参考としてご利用いただけますので、気になった方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 労働契約書の保管期間は何年?
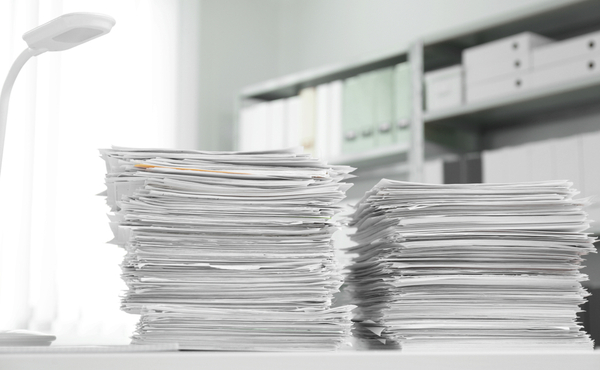
労働契約書も、他の契約書類や決算書類と同様に保管期間が決まっています。誤って捨てることがないよう、適切に管理しましょう。
1-1. 労働契約書の保管期間は5年(当面の間は3年)
労働契約書は基本的に契約者が退職、または死亡してから5年間(当面の間は3年)は保管しておかなければなりません。
退職したその日、死亡したその日から5年間(当面の間は3年)です。
これは労働基準法で定められた期間ですので、これ以内に勝手に破棄しないようにしましょう。
賃金の未払いや残業代に問題がある場合、契約者が死亡し過労死などの可能性がある場合、この労働契約書などを参考に捜査されることになります。
労働契約書だけでなく労働者名簿、賃金台帳、そしてタイムカードと時間外労働計算書も5年間(当面の間は3年)保管しなければなりません。健康診断書は原則5年間の保管義務があります。
1-2. 2020年の法改正で保管期間が変わった
労働契約書の保管期間は、労働基準法が改正される前は3年間でした。
しかし、2020年4月1日からは保管期限が5年に延長されたため、これまでよりも長期間の保管が企業には義務付けられています。
この変更には民法の改正により、賃金の債権が消滅する時効が2年から5年に延長されたことが関係しています。誤って処分しないように注意しましょう。
2. 労働契約書の保管で注意すること
 労働契約書を保管する際に注意しなければならない点について解説します。
労働契約書を保管する際に注意しなければならない点について解説します。
労働契約書さえ保管できていればいい、期間内に保管しておけばいいというわけではないため、いつ提出を求められてもすぐに用意できるようにしておきましょう。
2-1. タイムカードなどの書類も保管しなければならない
労働契約書は単体で保管すればよいわけではなく、その契約者のタイムカードや賃金台帳、労働者名簿、時間外労働計算書を一緒に保管しておく必要があります。
退職後に労働の内容に問題が発覚する可能性もあり、訴訟などに至った場合にこれらが証拠になるからです。
不利になる恐れがある場合でも、破棄してしまうと余計に不利になってしまいます。
また、提出を求められた際に破棄済みで提出できなかった場合は、罰則が科せられる可能性もあるので注意しましょう。
2-2. 保管期間が違う書類もある
労働契約書をはじめとした契約に関する書類の保管期間は5年間(当面の間は3年)ですが、それ以外にも各書類の保管期間は法律で定められています。
健康保険や厚生年金関連の書類の保管期間は2年間です。
労災保険に関連する書類、労働保険徴収や納付の書類は3年間です。
税法上の扶養控除等(異動)申告書や源泉徴収簿は7年間の保管が義務付けられています。
他にも法律で定められた保管期間のある書類はたくさんあるため、破棄していいか迷ったときは必ず確認しておきましょう。保管期間が定められていない書類に関しては企業が確定させられるため、適宜適切な期間保管した上で破棄するようにしましょう。
3. 労働契約書の正しい保存方法
 労働契約書を保管する際の正しい保管方法について解説します。
労働契約書を保管する際の正しい保管方法について解説します。
保管しているつもりでも正しく保管できていなければ証拠としては成立しません。特に電子データとして保管する場合は注意しましょう。
3-1. 基本的には書面で保管
労働契約書の書類は、書面で交付した場合は基本的に書面で保管しなければなりません。
現在日本だけでなく世界中でペーパーレス化が進んでおり、テレワークの推進などで今後もさらにペーパーレス化が早まっていくことが予想されます。
しかし、書面でのやり取りが未だに多いのも事実です。
従業員が多い、入れ替わりが激しい企業では労働契約書の保管にもスペースや管理コストがかかりますが、書面での契約書は書面のまま保管するようにしましょう。
退職年や入社年、氏名順など、各企業にとって見やすい方法で書類を保管しておき、いつでもすぐに提出できるようにしておきましょう。
3-2. 期間を過ぎたら廃棄して問題ない
保管期間が定められている書類は、規定の保管期間が過ぎれば廃棄するようにしましょう。
念のためと長く保管しておいたり、破棄の作業が面倒だからと放置しておいたりすると返ってさまざまなリスクが高まります。
個人情報の漏洩や保管スペースが確保できなくなるかもしれません。ファイリングするためのファイルやラックなどの購入費用もかかってくるでしょう。
契約書を管理する人を配置する人件費もかかるなど、長期間すぎる書類の保管はデメリットが多いです。
面倒かもしれませんが、保管期間を過ぎた書類は定期的に確認して廃棄しましょう。
廃棄の際はシュレッダーを利用し、個人情報が漏洩しないよう注意してください。
3-3. 電子契約書の場合は条件を確認する
近年は書面ではなく電子契約書を選択する企業も増えていますが、どのような場合でも利用できるわけではありません。さまざまな条件があるため、導入前に確認しましょう。
条件にはまずタイムスタンプや社内規定があることです。その電子書類が本物であることの証明するために重要です。電子書類の管理に関するマニュアルも作成しておかなければなりません。
他にもデータ検索ができるようになっている書類、パソコンなどの画面ですぐに確認できる、紙にプリントできるデータであることなども条件です。
3-4. 電子契約書のメリット、デメリットを把握しておく
労働契約書を電子契約書にするメリットはたくさんあります。
保管する場所を取らないため、狭い社内が圧迫される恐れや、倉庫をレンタルする必要がありません。
距離的に離れていても契約ができるため、リモートワークや業務委託などでも郵送などの時間を取らずにすぐに契約ができます。
デメリットとしてはセキュリティ対策が必要という点があります。社内の誰でもアクセスできるような状況では、個人情報が簡単に漏洩してしまいます。
社内でのデジタル化が進んでいない場合は整備までの手間やコストがかかり、なかなか着手できない場合もあるでしょう。
そもそも労働契約書の電子交付は、雇用者本人が同意しない限りは交付できません。あらかじめ本人に確認し、拒否された場合は書面での交付、保管が必要です。
4. 労働契約書は保管期間と保管方法を守って取り扱おう
 雇用内容を詳しく記載した労働契約書は、契約者が退職、または死亡した日から数えて5年間(当面の間は3年)は保管しておかなくてはいけません。
雇用内容を詳しく記載した労働契約書は、契約者が退職、または死亡した日から数えて5年間(当面の間は3年)は保管しておかなくてはいけません。
以前は3年の保管期間が定められていましたが、延長されている点に留意して正しく保管するようにしましょう。
保管する際は真実性を確保し、すぐに閲覧できるようにしておくことが重要です。特に電子データで保管する際は要件を確認し、証拠として有効な形で保管しましょう。
雇用契約は法律に則った方法で対応しなければ、従業員とのトラブルになりかねません。
当サイトでは、「自社の対応が適切か確認したい」という人事担当者様に向け、雇用契約の方法から、雇用契約についてよくある質問までをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しております。
雇用契約業務を適切に進めるための参考としてご利用いただけますので、気になった方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08



























