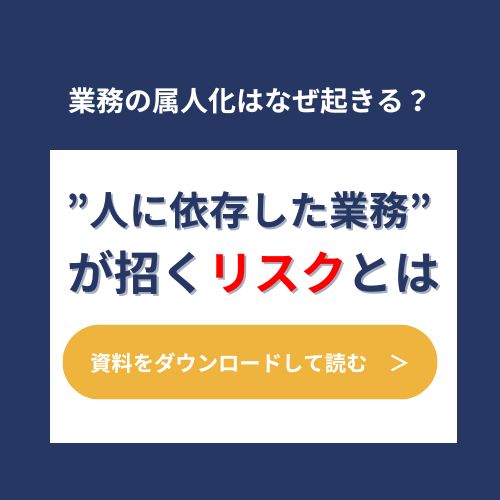企業が就業規則の閲覧を求められたら?労働者の権利と会社の義務に基づいた対応方法とは

就業規則は本来、閲覧を許可するものではなく、従業員が自由に見られるようにしなければならず、周知されていないなら効力自体発揮しません。
閲覧方法も事業所内への掲示や書面での交付、パソコンでの閲覧など詳細が定められています。
この記事では、就業規則の閲覧を求められた場合の正しい対応方法や、閲覧の注意点を解説します。
▼就業規則について1から理解したい方はこちら
就業規則とは?人事担当者が知っておくべき基礎知識
目次
「組織拡大にともない、従業員情報を管理できておらず困っている」
「人事情報をアナログ管理しているため、工数がかかって大変」
「人事管理を電子化したいがどう進めていけば良いかわからない」 など労務管理に関して困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そのような方に向けて当サイトでは「理想的な従業員情報の管理」という資料を無料配布しております。
最終的にどのような従業員管理が良いのかという理想形の解説から、従業員管理の方法を電子化した時の実際のイメージまでわかりやすく解説しています。人事担当者にとっては大変参考になる資料となっておりますので、こちらからダウンロードの上ぜひご覧ください。
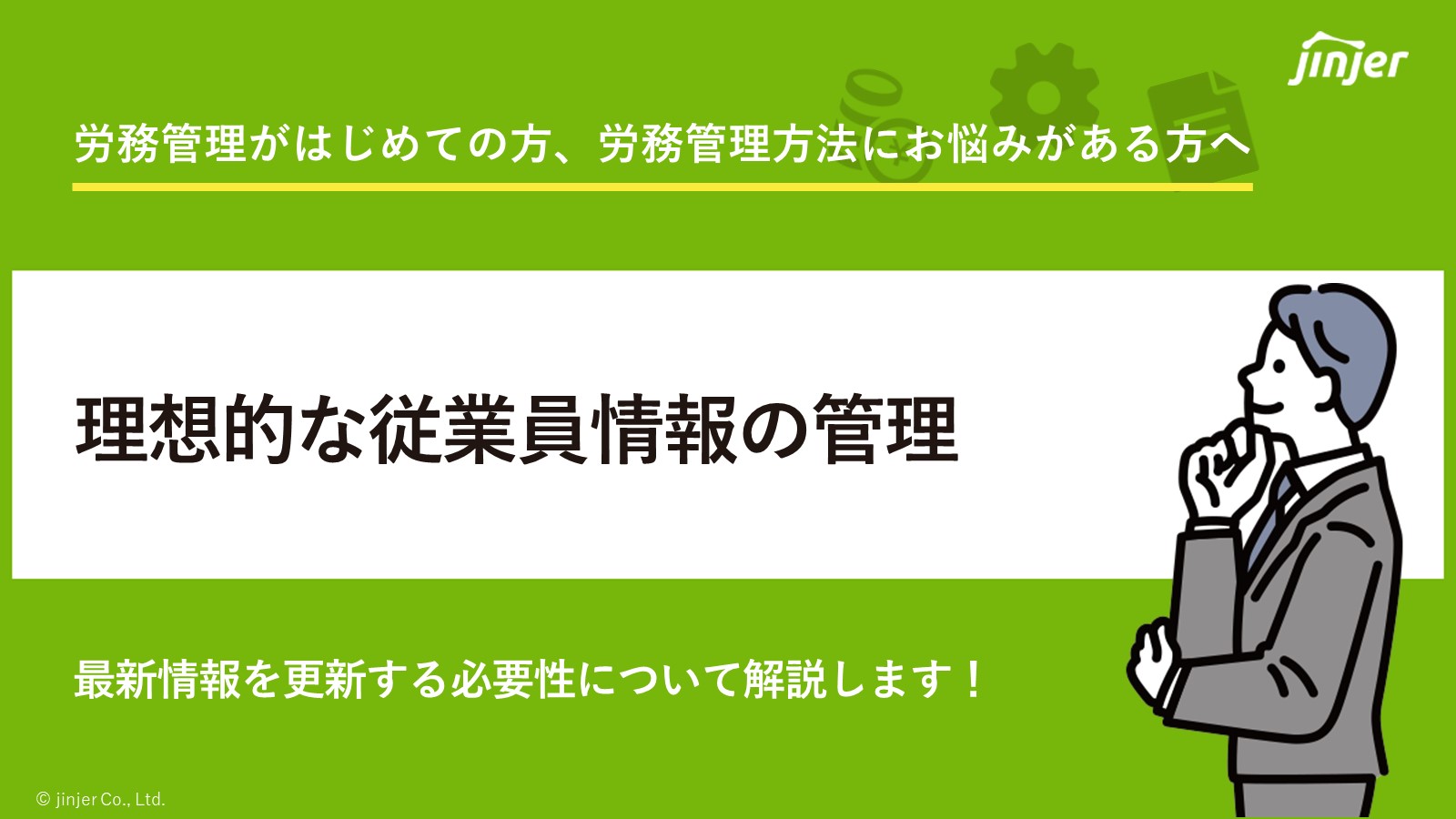
1. 就業規則とは
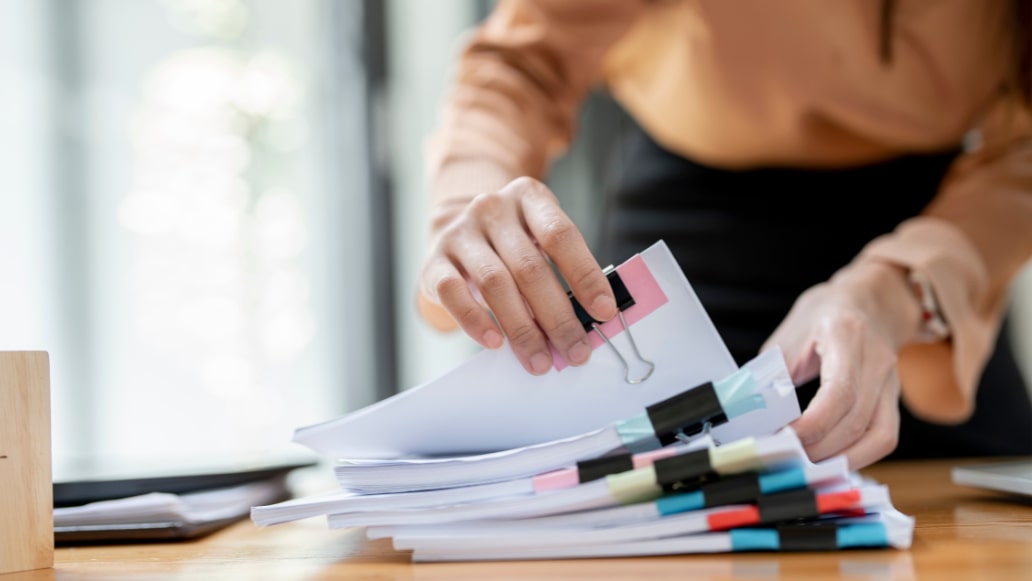
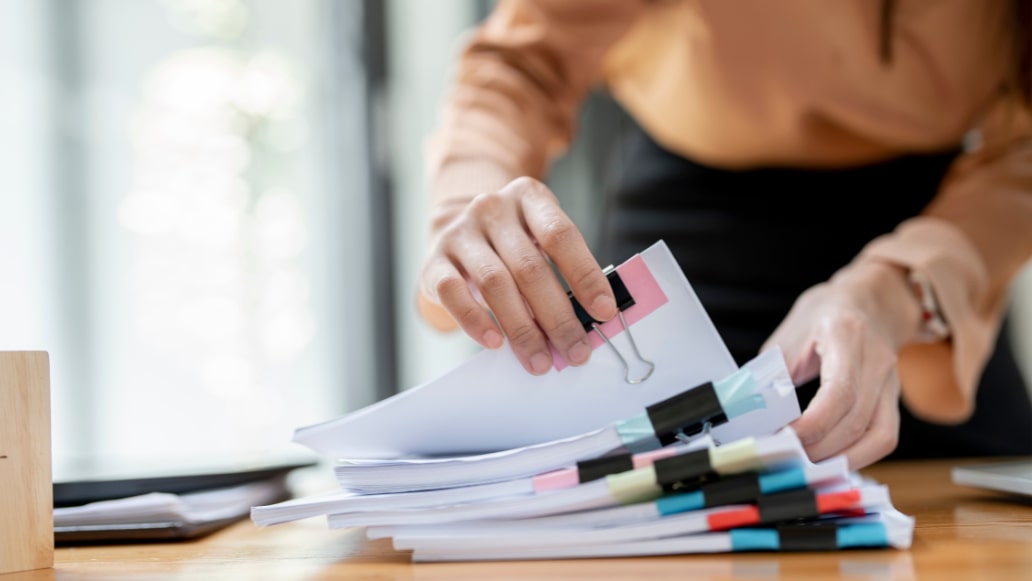
就業規則とは、従業員(労働者)の給与や労働時間といった労働条件、従業員として守るべき社内のルールや罰則などをまとめた規則です。
厚生労働省では、「モデル就業規則」を作成し、ホームページでこれを公開しています。モデル就業規則は英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語でも作られ、多様化する労働の状況に合わせて就業規則を作成できるように工夫されています。
参考:モデル就業規則|厚生労働省
1-1. 就業規則を作成する目的
就業規則は、主に以下のような目的のために作られます。まず、企業内の秩序を保つことです。大勢の人たちが働く企業内では、決められたルールを守ることが秩序の維持につながります。次に、トラブル防止です。正しい規則を示し罰則を明確にすることで、不正行為やハラスメントの防止にも寄与します。
また、企業の利益を守ることも重要です。ルールを守ることで業務効率の低下やトラブルを防ぎ、企業利益の保護につながります。最後に、社会的責任を果たすことも目的の一つです。環境問題や人権問題への対応を明示することで、ステークホルダーとの良好な関係を維持します。
2. 就業規則の閲覧は労働者の権利であり会社の義務


従業員には就業規則を自由に閲覧できる権利があります。これは会社の義務であり、法律に則った企業運営をする上で正しく理解しておくことは重要です。詳しく解説します。
2-1. 労働基準法に定められた「就業規則の周知義務」
就業規則には労働基準法第106条により定められた「就業規則の周知義務」があります。つまり閲覧制限をかけて、閲覧させないということは認められません。周知義務違反を理由に、労働基準監督署から指導が入ることもあり、悪質な場合は30万円以下の罰金が科されるケースもあります。
2-2. 就業規則の作成・届出義務がある会社の要件
常時10人以上の労働者を使用する者(経営者や事業主など)は、就業規則を作成した上で労働基準監督署に届け出をしなければならないという義務を負います(労働基準法第89条)。
就業規則の作成・届出義務は、常時雇用する労働者の数は「事業場ごと」に判断されます。したがって、常時10人以上の労働者を使用する事業場についてのみ、就業規則の作成・届出義務が生じるという点に注意が必要です。
事業場単位で9人以下である場合、会社全体として常時10人以上の労働者を使用していても、事業場単位で9人以下であるケースでは就業規則の作成・届出義務は発生しません。また、常時10人以上であることが要件なので、繁忙期のみ10人以上雇い入れる場合も同様です。一時的に10人を下回る場合も、常態として10人以上雇用していれば義務は継続します。
2-3. 従業員に周知されていない就業規則は無効
就業規則は従業員に周知されて、初めて効力を発揮します。例えば、従業員が自由に閲覧できない就業規則を理由に解雇しようとしても、認められないケースも出てきます。
そのため、従業員から求めがあった場合はもちろん、就業規則は常に全従業員が把握できる状態にしておかなければなりません。
3.就業規則の閲覧を求められた際の対応方法


就業規則の周知方法は、労働基準法第106条1項、労働基準法施行規則第52条の2によって、下記のように定められています。
- 常時作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける。
- 書面を労働者に交付する。
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。
そのため、従業員から就業規則の閲覧を希望された場合は、該当する方法で開示するとよいでしょう。
それぞれの方法を、具体的に解説します。
3-1. 作業場などの見やすい場所に常に掲示する
就業規則を小冊子などでまとめている場合は、従業員が手に取り、自由に見られる場所に掲示しましょう。自由に閲覧できるのであれば、事務所内や事業所だけでなく、休憩場所などでも問題ありません。
また、本社以外に支店や工場など、別事業所がある場合は、事業所ごとに見やすい場所に備える必要があります。
3-2. 書面で交付する
入社時などに就業規則のコピーを配布しても問題ありません。
ただし、就業規則の社外への持ち出しを禁止しているケースや、従業員数の多い企業では、書面での公布も困難でしょう。
その場合は、1や3の方法を利用するとよいでしょう。
3-3. デジタルデータは全員がアクセスできるようにする
就業規則はパソコンのデジタルデータで周知することも可能です。その場合は、全員がアクセスできる共有フォルダに格納したり、社内イントラネットに掲載したりして、全員が閲覧できれば問題ありません。
4. 就業規則を公開するに際の注意点


就業規則の閲覧許可の範囲や、取り扱いに関する注意点を解説します。
4-1. 雇用形態にかかわらず、就業規則を閲覧できるようにする
雇用形態に関わらず、すべての就業規則をみれるようにすることが望ましいでしょう。従業員が就業規則を閲覧できるようにする手段としては、従業員の目の付く場所へ掲示する、全社で共有のドライブやファイルサーバーに格納する、各拠点に就業規則のファイルを置いておくなどの方法が挙げられます。
4-2. 就業規則のコピーを希望された場合の対応
コピーを従業員に交付することは、会社が就業規則の周知義務を果たす方法の1つではあります。しかし、従業員がコピーを求める権利は一般的には認められていません。会社は就業規則の重要性と情報管理を考慮し、自社の方針で対応することが可能です。
4-3. 経営者から閲覧を拒否された場合
就業規則を経営者が保管しており、人事担当者が閲覧を希望したところ拒否され、さらに周知義務について説明しても理解を得られない。
このように、どうしても会社での閲覧が難しい場合は、労働基準監督署に閲覧請求をおこなうことができますので、まずは相談してみましょう。
4-4. 会社が保管する就業規則を紛失してしまった場合
万が一、データを削除した、冊子を廃棄したなど、就業規則をなくしてしまった場合は、労働基準監督署に経緯を説明することで、閲覧申請をおこなうことができます。
ただし、上記の事態は会社の信頼を損なうことにもつながるため、就業規則の保管は入念におこないましょう。
5. 就業規則を閲覧させない会社がある背景とは


一部の会社では就業規則の閲覧を制限する傾向が見られます。労働者の権利を守り、企業としての信頼性を高めるためには、就業規則の管理・公開を適切に行うことが重要ですが、その就業規則を閲覧させない会社がある背景には、いくつかの要因が存在します。詳しくみていきましょう。
5-1. 従業員からの権利行使を抑制したいため
残業代の支払い等に不満を持ち、退職後に会社に対して何らかの請求を検討している従業員が、請求を検討するための資料として就業規則の閲覧を求めることがあります。
そのような場面で、会社が閲覧を認めたがらないのは、そのような権利行使の検討資料にされたくないという会社の意向が背景にあります。労働者が権利を行使する可能性を抑制したいという意図が存在するのです。しかし、このような対応は労働基準法に違反する可能性が高いため、会社は適切に対応すべきです。
5-2. 就業規則どおりに会社が運営されていないため
就業規則を従業員に閲覧させたがらない背景として、会社が就業規則どおりに運営されていないためという問題が存在します。
例えば、就業規則に明記されている手当が実際には支払われていなかったり、賃金制度が就業規則と一致していない場合があります。
このような乖離が発生すると、従業員にその事実を知られたくないという理由から、企業は就業規則の公開に消極的になることがあります。
このため、就業規則どおりに会社が運営されていない場合は、その矛盾点を隠匿するために規則の閲覧を制限する企業も少なくありません。
5-3. 条項への問題点指摘を恐れているため
会社が就業規則を閲覧させない背景には、条項への問題点指摘を恐れていることがあります。
特に、企業の人事担当者や法務担当者にとって、労働者の権利を正確に反映し、法令に則った就業規則の管理・公開方法は重要ですが、自身の規則内容に自信がない場合、公開をためらうことがあります。しかし、このような状況でも、企業が在職中の従業員に対して就業規則を閲覧させないことは違法です。
企業としては、条項への問題点を指摘される可能性があるのであれば、早急に専門家に依頼し、就業規則を整備することが必須です。規則の整備と公開の両方を適切に行うことで、従業員の信頼を得るだけでなく、法的トラブルを未然に防ぐことが可能となります。
6. 就業規則の閲覧を拒否した際のデメリット


会社が従業員からの就業規則の閲覧を拒否すると、重大なデメリットが生じます。まず、労働基準法上の周知義務を果たしていないこととなり、労働基準法違反として30万円以下の罰金が科せられる可能性があります(労働基準法120条1号)。
これだけでなく、他にもどんなトラブルに成り得るのか見ていきましょう。
6-1. 問題社員に対して懲戒処分ができない
就業規則を周知していない場合、従業員の問題行動があっても、懲戒解雇をはじめとする懲戒処分を科すことができません。
企業が従業員に懲戒処分を科すためには、あらかじめ就業規則に懲戒の種別や懲戒事由を定めて周知しておくことが必要とされています。懲戒解雇を含む懲戒処分は、問題社員の問題行動にけじめをつけさせ、社内の規律を維持するために重要です。
6-2. 会社のルールがあいまいになり統率がとれない
就業規則を閲覧させない場合の問題点として、「服務規律を明確にできない」ということもあげられます。
「服務規律」とは、従業員が勤務するうえで守るべき会社のルールのことをいいます。例えば、セクハラやパワハラの禁止、営業秘密や個人情報の正しい取り扱い、タイムカードの正しい打刻、取引先からリベートを受け取ることの禁止などがあります。従業員に就業規則を閲覧させないと、服務上のルールが不明確になり、ルールのない会社と同様の状態になってしまいます。
6-3. 無許可の副業により会社が不利益を被る可能性がある
会社に勤めながら副業をする人が増えていますが、無許可で副業をすることで本業の勤務に支障が出たり、競合他社に情報が漏えいするリスクがあります。
就業規則を周知し、副業を許可制にすることで、このリスクを管理することが可能です。しかし、就業規則が周知されていなければ、副業に関するルールがなくなるため、無許可の副業が横行し、会社に不利益をもたらす可能性があります。
6-4. 定年の規定がない会社になってしまう
就業規則では定年についても定めることが通常です。雇用契約書で定年を定めていない場合、就業規則が周知されていなければ、定年のない雇用契約となり得ます。その結果、従業員が高齢になり、就業が難しくなっても、退職の申し出がない限り雇用を継続しなければならない可能性があります。
6-5. 私傷病休職者への対応ができない
多くの会社では病気休職者への対応について就業規則で定めています。
休職期間や復職条件を明示し、休職中に復職ができない場合は退職にするなどが一般的です。就業規則が周知されていなければ、病気休職のルールが不明確となり、従業員が病気になった時の対応をめぐりトラブルが生じる危険があります。
6-6. 給与減額ができない
成績不良などを理由に従業員を降格させて給与を減額することは、就業規則に規定がなければできません。
就業規則が周知されていないため、その効力が認められず、成績に見合わない高給与を支払い続けるなどの問題が発生する可能性があります。
7. 就業規則の閲覧についてよくある質問


また就業規則の閲覧について関連してよくある細かい質問をまとめました。ケースごとに正しい対処ができるよう確認しておきましょう。
7-1. 入社前から就業規則を閲覧できる?
入社前の従業員から就業規則の閲覧を求められる例があります。新たに入社する従業員に就業規則を適用するためには、労働契約の締結までに周知させる必要があります。
労働契約法では、労働契約の内容は周知された就業規則によるものとされており、厚生労働省の通達でも労働契約の締結時には就業規則を周知することが要請されています。内定者が就業規則を閲覧できるようにしておくことが必要です。
7-2. 休職中も就業規則を閲覧できる?
休職中であっても在職中である以上、会社は就業規則の閲覧を認める義務があります。ただし、閲覧方法としては、作業場の見やすい場所に掲示する、電子媒体で確認できるようにするなどが認められています(労働基準法施行規則52条の2)。休職者に対しても通常の周知方法で対応すれば問題ありませんが、自宅での閲覧に対応する義務まではありません。
参考:労働基準法施行規則|e-GOV法令検索
7-3. 退職後も就業規則を閲覧できる?
就業規則の周知義務は、あくまでも在職中の従業員に適用されます。そのため、退職した従業員から就業規則の閲覧を求められた場合は、必ずしも、すべて開示する必要はありません。
ただし、もし退職後に就業規則の規定を巡って争いとなっている場合は、権利関係の規定は開示する必要があります。
7-4. 第三者も他社の就業規則を閲覧できる?
第三者が他社の就業規則を閲覧できるかどうかは、会社が認めない限り難しいです。社外の第三者に対して就業規則を閲覧させる義務は会社にはありません。Webサイトで公表している場合を除き、第三者が閲覧することはできません。
7-5. 法律に違反する就業規則の条項に効力はある?
労働基準法で定められた内容は、労働契約(雇用契約)における最低ラインとされています。法律に違反する就業規則の条項は、労働基準法上の最低ラインに満たない労働条件を定めるものである場合、その部分は無効となります(労働基準法第13条)。
つまり、労働基準法に違反する規定は労働契約の一部として成立せず、労働基準法上の最低ラインに修正されることになります。したがって、労働者に不利益を及ぼす就業規則の条項が有効となることはありません。企業の人事担当者や法務担当者は、就業規則の策定および管理において労働基準法を厳守し、従業員の権利を適正に保護することが重要です。
8. 労働基準監督署での就業規則閲覧について


従業員10名以上の事業場がある会社が就業規則を作成または変更した場合、労働基準監督署長に届け出る義務があります(労働基準法89条)。
労働基準監督署では、管轄内の各社の就業規則が保存されています。会社が就業規則の閲覧を拒否する場合、従業員が労働基準監督署で閲覧することは可能です。通達によれば、在職中の従業員については、勤務先での周知義務が果たされていない場合に限り、労働基準監督署で閲覧できます。
退職者についても、一定の紛争がある場合に限定して閲覧が許可されます。労働基準監督署は、このような状況が確認された場合、会社に周知義務を果たすよう指導することもありますので正しく理解しておきましょう。
9. 労働者の権利を守り就業規則を自由に閲覧できる環境作りを


就業規則は、従業員が自由に閲覧できる状態でなければ効力を発揮しません。
また、閲覧方法についても、法律で詳細が定められています。
一部の従業員だけ見られるようにする、許可制にするなどは法令違反となる可能性もあるため、就業規則の閲覧方法には十分注意しましょう。
「組織拡大にともない、従業員情報を管理できておらず困っている」
「人事情報をアナログ管理しているため、工数がかかって大変」
「人事管理を電子化したいがどう進めていけば良いかわからない」 など労務管理に関して困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そのような方に向けて当サイトでは「理想的な従業員情報の管理」という資料を無料配布しております。
最終的にどのような従業員管理が良いのかという理想形の解説から、従業員管理の方法を電子化した時の実際のイメージまでわかりやすく解説しています。人事担当者にとっては大変参考になる資料となっておりますので、こちらからダウンロードの上ぜひご覧ください。
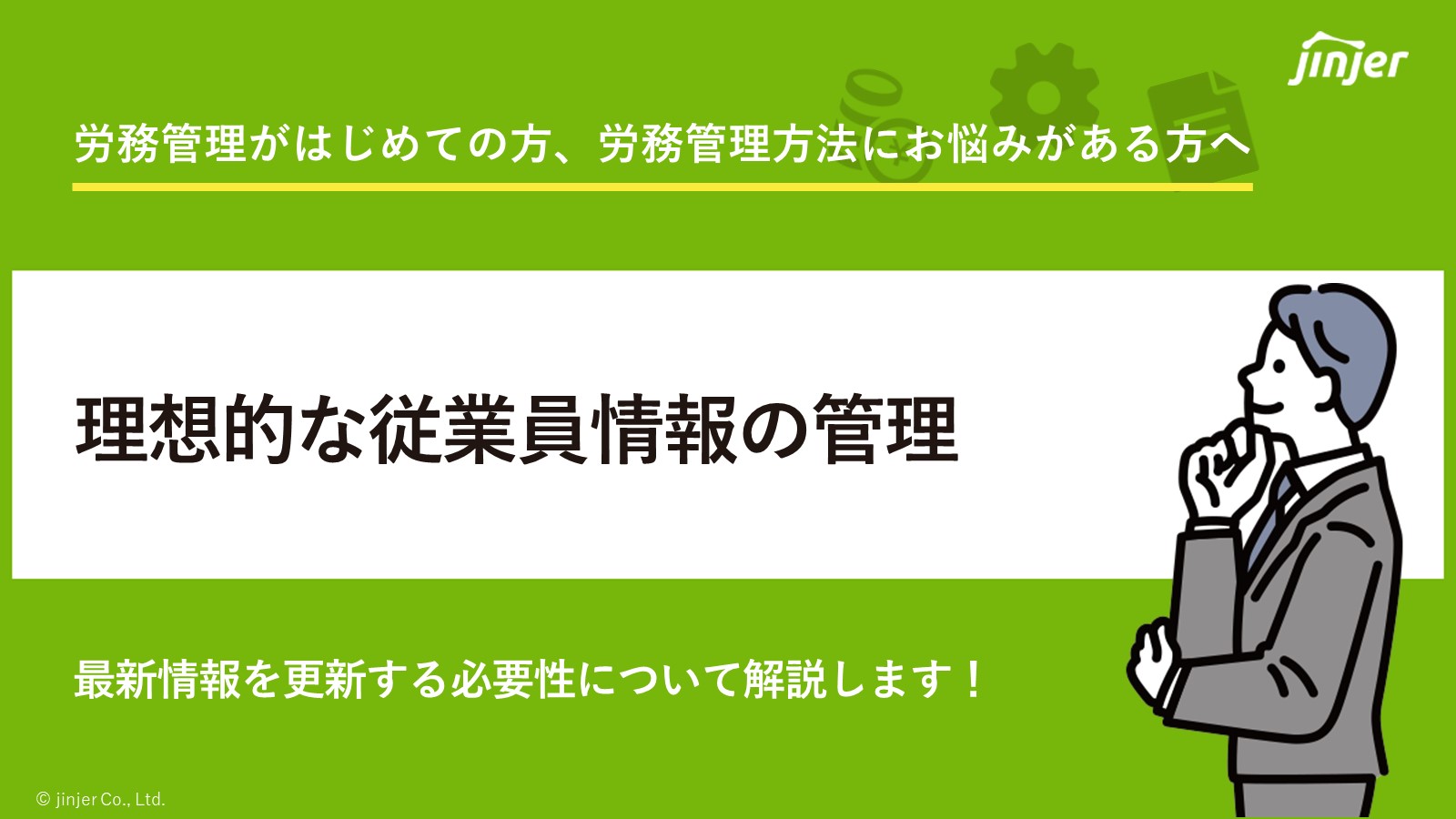
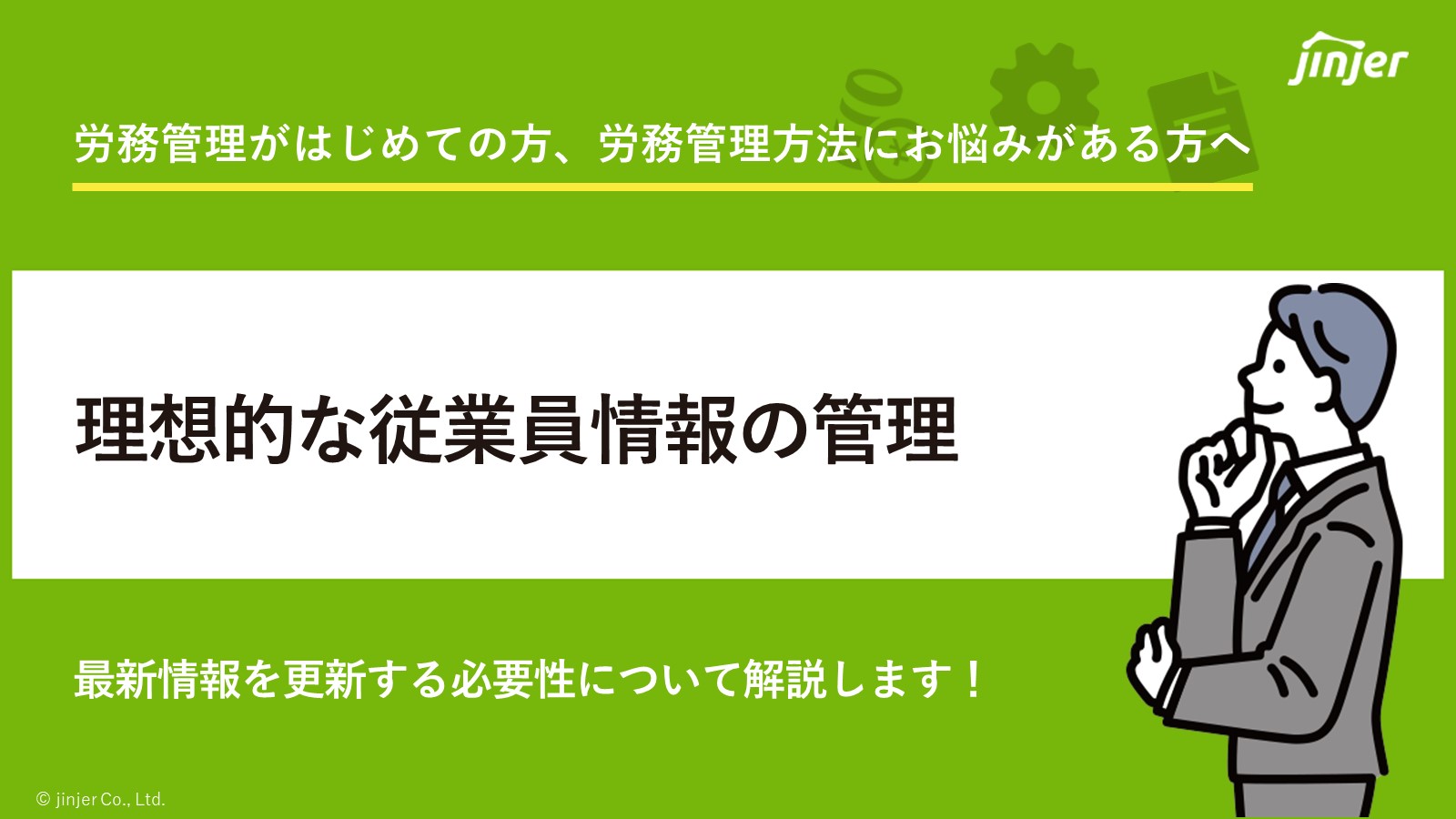
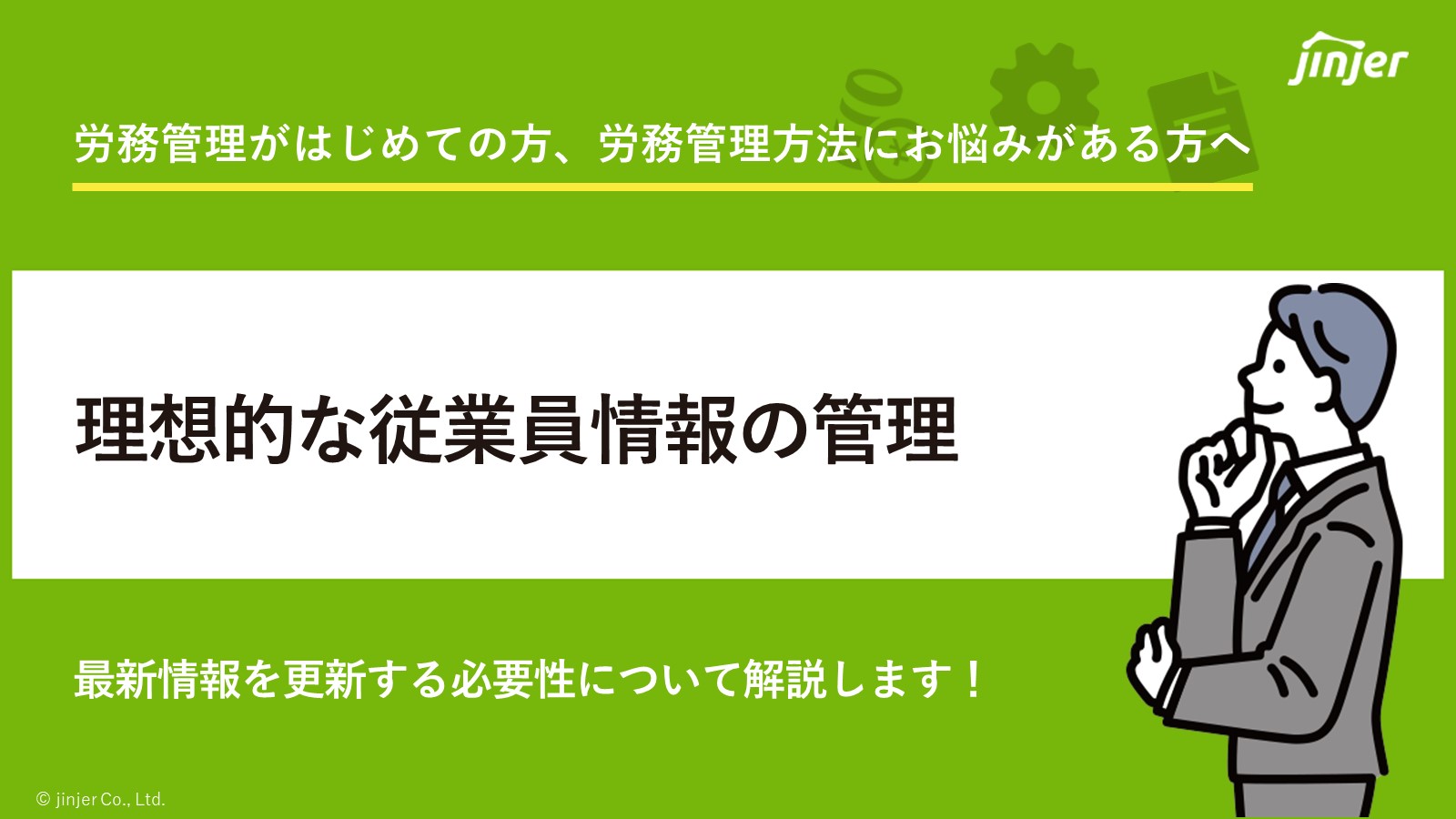
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08