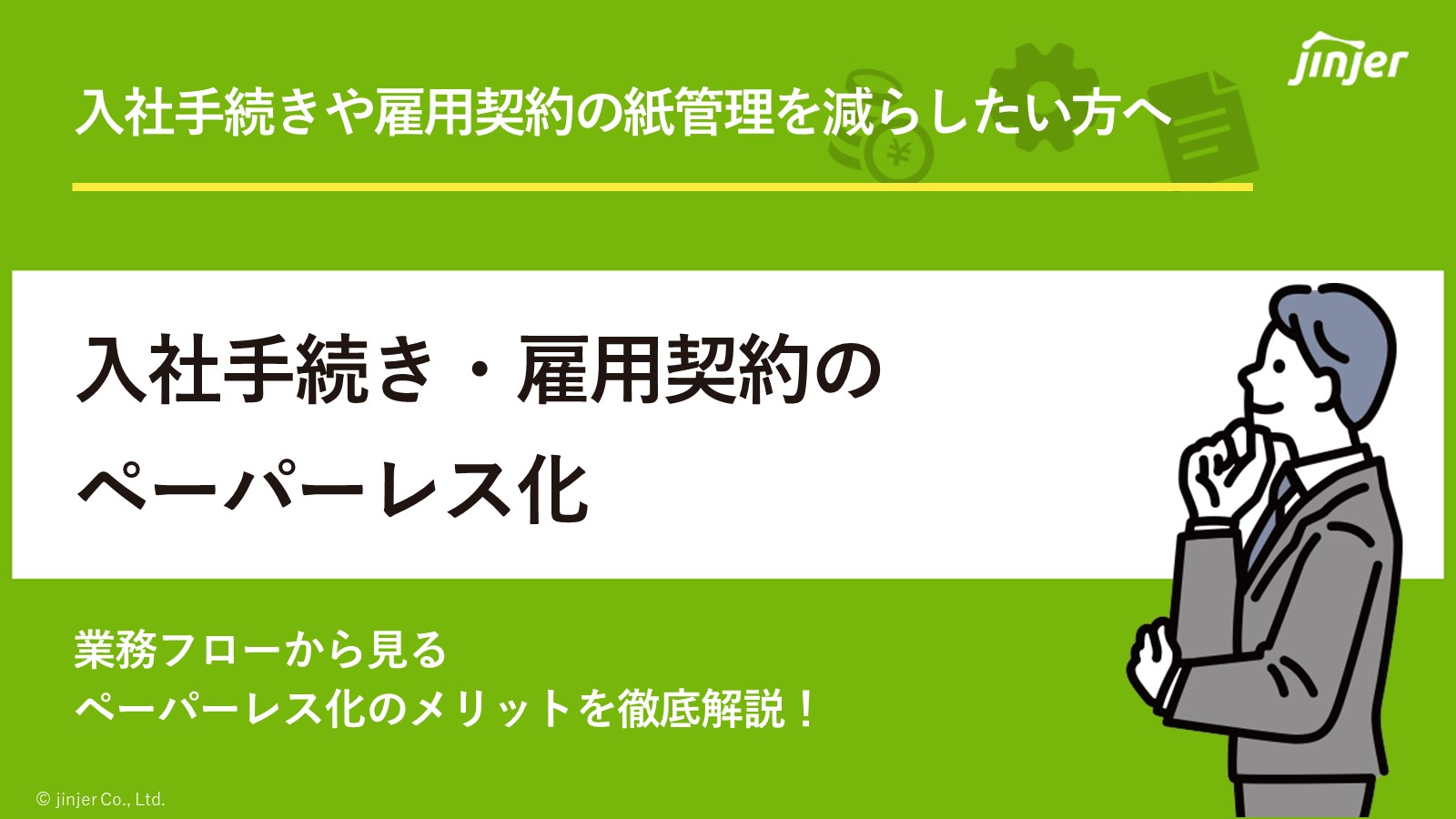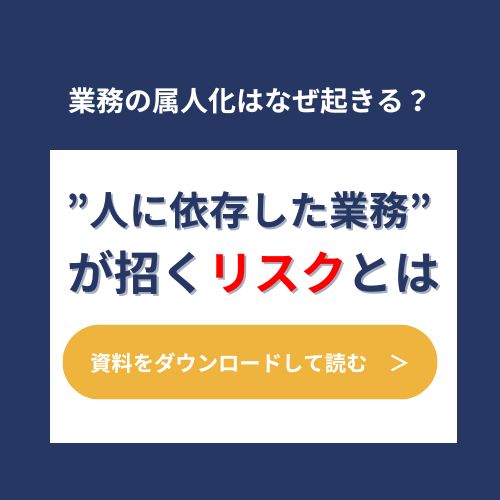就業規則の不利益変更とは?実施する際の4つの注意事項
更新日: 2024.7.11
公開日: 2021.10.31
OHSUGI

通常、従業員の不利益となるような就業規則の変更は、法律上禁止されています。
しかしながら、経営状態の悪化など、合理的でやむを得ない理由があり、なおかつ、労使間の合意があれば、不利益変更も可能となります。
この記事では、不利益変更の概要と注意事項、変更をする際のポイントを解説します。
▼就業規則について1から理解したい方はこちら
就業規則とは?人事担当者が知っておくべき基礎知識
デジタル化に拍車がかかり、「入社手続き・雇用契約の書類作成や管理を減らすために、どうしたらいいかわからない・・」とお困りの人事担当者様も多いでしょう。
そのような課題解決の一手として検討していきたいのが、入社手続き・雇用契約のペーパーレス化です。
システムで管理すると、雇用契約の書類を作成するときに、わざわざ履歴書を見ながら書類作成する必要がありません。書類作成に必要な項目は自動で入力されます。
また、紙の書類を郵送する必要がないので、従業員とのコミュニケーションが円滑に進み、管理者・従業員ともに”ラク”になります。
入社手続き・雇用契約のペーパーレス化を成功させるため、ぜひ「3分でわかる入社手続き・雇用契約のペーパーレス化」をこちらからダウンロードしてお役立てください。
1. 就業規則の不利益変更とは?


就業規則の不利益変更とは、賃金の引き下げや手当のカット、福利厚生の廃止など、従業員にとって不利益な方向に、就業規則を変更することです。
労働契約法第9条により、使用者は従業員の不利益となるような労働条件の一方的な変更は、原則禁止とされています。
ただし、労働者の過半数で組織する労働組合、または、労働者の過半数代表者との合意があれば、不利益な方向への変更も認められています。従業員の中に反対者がいたとしても、変更理由が「合理的である」と判断される場合には変更することが可能です。
なお、「合理的である」か否かは、労働契約法第10条の下記の基準に照らし合わせて判断されます。
- 従業員の受ける不利益の程度
- 労働条件を変更する必要性
- 変更後の就業規則の内容の相当性
- 労働組合などとの交渉の状況
- 上記以外の就業規則の変更に係る事情
そのため、就業規則の不利益変更の際は、一つひとつの事例を詳しく確認することが必要です。
労働者にかかる不利益の程度と、就業規則を変更する妥当性を検討しましょう。
2. 就業規則の不利益変更をする際の4つの注意事項


就業規則の不利益変更は、労使の合意があれば問題はないものの、合理的でかつ従業員一人ひとりに変更理由の理解を促すことが大切です。
理解を得られないことで、思わぬ訴訟に発展するケースもあるため注意しましょう。
2-1. 不利益変更が必要な理由を説明する
不利益変更が必要な理由は、従業員一人ひとりに説明しましょう。
変更前の労働条件と比べて、どこが、どのように、どの程度変わるのか、それにより従業員にはどのような不利益が生じるのか、具体的な説明が必要です。
また、不利益変更が必要となる経緯についても具体的に述べ、理解を促しましょう。
説明の際は、書面と口頭、どちらも合わせておこなうことが望ましいです。従業員から十分な理解を得られないことで、労働争議に発展する可能性も考えられるため、特に丁寧な説明が必要です。
2-2. 賃金の引き下げでは経営資料に基づいた判断が必要
賃金や退職金の引き下げでは、特に合理性のある判断が求められます。労使間で話し合いをする際は、経営資料などを元に必要性を十分協議しましょう。
- 多額の損失を計上している
- 損失を埋めるための措置をすでにおこなっている
- 同業他社に比べて賃金水準が高い
- 複数回にわたり労働組合に説明をおこなっている
- 説明の際は経営資料なども提示している
すでに賃金引き下げ以外の方法はおこなっているなど、上記の理由が必要となります。
≪参照判例≫
シオン学園事件(東京高等裁判所平成26年2月26日判決)
学校法人早稲田大阪学園事件(大阪高等裁判所平成29年4月20日判決)
2-3. 休日の変更では賃金変動や同業他社との違いも確認する
休日を減少する場合は、それにより賃金にどのような影響がでるかを、従業員に具体的に説明する必要があります。
基本給は据え置き、休日のみ削減すれば、実質的な賃金カットと変わりがありません。そのため、労働日数を増やす具体的な理由と、同業他社と比べた休暇日数などを考慮する必要があります。
- 人件費以外の経費はすでに削減している
- 休日の削減により、従業員が受ける不利益の程度を説明している
- 同業他社と比べて休日日数は妥当か
- 同業他社が休日としている日を削減していないか
変更の際は、自社だけでなく、同業他社との比較も必要です。
≪参照判例≫
フェデラルエクスプレスコーポレーション事件(東京地方裁判所平成24年3月21日判決)
2-4. 従業員により不利益が偏る場合は、調整手当の導入などが必要
人事評価制度の変更など、就業規則の変更により、一部の従業員に不利益が偏る場合は、「調整手当」などの導入が必要となります。
- 人事評価制度を変更する必要性
- 労使間の交渉に応じていること
- 調整手当を導入し不利益の緩和をおこなっていること
- 人件費自体の減額を目的としていないこと(生産性の向上が主目的であるなど)
過去の判例では、調整手当は3年以上の支給が合理性を争ううえで、ポイントとなります。
≪参照判例≫
三晃印刷事件(東京高等裁判所平成24年12月26日判決)
3. 就業規則の不利益変更をおこなう際のポイント


就業規則の不利益変更では、従業員から反発があったとしても、労使間の合意があれば法律上は問題ありません。
とはいえ、反対をそのままにしておけば、業務を遂行するうえでも支障となります。理解が得られるよう、交渉を続けることが大切です。
3-1. 不利益変更後の就業規則は周知を徹底する
就業規則は、周知されて初めて効力を発揮します。
これは、不利益変更をおこなった就業規則でも同じことのため、変更後は周知を徹底しましょう。
変更後の周知がなされていないために、就業規則が無効となったケースもあります。
従業員の理解を促すためにも、変更前・変更後を並べて掲示するなどの対処が必要です。
3-2. 就業規則の不利益変更は、同意しない従業員にも適用される
就業規則の不利益変更は、必ずしも全従業員の合意が必要なわけではありません。合理性が認められる場合、変更に同意していない社員にも、不利益変更後の就業規則が適用されます。
とはいえ、就業規則の変更は従業員のモチベーションにも影響します。一人ひとりに十分な説明をおこない、可能であれば同意書を書いてもらうことも有効でしょう。
≪参照判例≫
秋北バス事件(最高裁昭和43年12月25日大法廷判決)
関連記事:労働条件変更同意書の記載事項や記入のポイントについて
3-3. 労使の合意を得られない時は、粘り強く交渉を続ける
就業規則の不利益変更で労使の合意を得られないケースもあるでしょう。その際は複数回にわたり、粘り強く交渉を続けましょう。
過去の判例からも、労使の交渉が十分におこなわれているか、経営資料を用いた具体的な説明がなされているかなどが、就業規則の不利益変更の合理性を争う上でポイントとなっています。
会社側が不利益変更を押し通してしまった場合、就業規則が無効となるケースもあるため、時間がかかったとしても、交渉を続けることが大切です。
3-4. 経過措置を設ける
不利益変更をおこなう際は、経過措置を設けたり、運用スケジュールを開示したりして、従業員の心理的負担を軽減しましょう。
新しい制度の運用は経済的にだけでなく、精神的にも負担が大きくなります。
そのため、運用スケジュールを作成したり、複数回にわたる説明をおこなったりして、徐々に制度に慣れてもらうことも有効です。
4. 就業規則の不利益変更では従業員の理解を促そう


就業規則の不利益変更は、客観的に合理的であり、なおかつ労使の合意があれば法律上は問題ありません。
しかしながら、従業員の反発をそのままにしておけば、士気の低下にもつながります。
そのため、不利益変更をする際は、従業員の理解を促し、経過措置を導入するなどして、精神的な負担が少なくなるような配慮も求められます。
デジタル化に拍車がかかり、「入社手続き・雇用契約の書類作成や管理を減らすために、どうしたらいいかわからない・・」とお困りの人事担当者様も多いでしょう。
そのような課題解決の一手として検討していきたいのが、入社手続き・雇用契約のペーパーレス化です。
システムで管理すると、雇用契約の書類を作成するときに、わざわざ履歴書を見ながら書類作成する必要がありません。書類作成に必要な項目は自動で入力されます。
また、紙の書類を郵送する必要がないので、従業員とのコミュニケーションが円滑に進み、管理者・従業員ともに”ラク”になります。
入社手続き・雇用契約のペーパーレス化を成功させるため、ぜひ「3分でわかる入社手続き・雇用契約のペーパーレス化」をこちらからダウンロードしてお役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08