労働基準法第16条の賠償予定の禁止とは?違反の罰則や例外を解説
更新日: 2024.7.19
公開日: 2021.10.4
OHSUGI

企業にとって多額の費用を掛けて留学させた社員が早期に退職してしまうことは大きな痛手です。できることなら留学終了後に一定期間の勤務を義務付け、そのスキルで会社に利益をもたらしてほしいと考えるでしょう。しかし、違約金による労働者の足止めは、労働基準法第16条に抵触する違法行為です。
この記事では労働基準法第16条における「賠償予定の禁止」について解説します。関連する問題である「退職者に対する研修費・留学費の返金請求」のポイントについても触れています。ぜひ参考にしてください。
そもそも労働基準法とは?という方はこちらの記事をまずはご覧ください。
労働基準法とは?雇用者が押さえるべき6つのポイントを解説
目次
労働基準法総まとめBOOK
1. 労働基準法第16条は賠償予定の禁止について定めた条文


労働基準法第16条は、労働者に対する「賠償予定の禁止」について定めたものです。以下その条文を引用します。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
具体的にどのようなことを指しているのか、詳しく解説します。
1-1. 労使契約で「違約金」「賠償金」の支払いを約束させてはならない
労働基準法第16条では、契約の不履行による違約金や損害に対する賠償金の規定を労使間で定めてはならないとしています。経営者が労働者に対して「違約金」や「賠償金」の支払いを予め約束させることはできません。これを「賠償予定の禁止」といいます。
賠償予定の禁止に該当するのは以下のような項目です。
- 退職時には違約金として○○万円を支払うこと
- 会社に損害を与えた際は損害額に関係なく○○万円の賠償金を支払うこと
上記のような項目が労使協定に盛り込まれていた場合は違法であり、罰則の対象となります。同様に、労働者の身元引受人に対して賠償予定を約束させることも禁止です。経営者には労使契約において「賠償予定の禁止」を遵守することが求められます。
1-2. 労働者の「退職の自由」を奪ってはならない
「賠償予定の禁止」は労働者の退職の自由を保証することがその目的です。経営者は違約金によって労働者に対して労使関係を強要してはなりません。特に、近代の日本では違約金による労働者の身分の拘束は大きな問題でした。
現代社会においても、退職者に対する「研修費・留学費の返金請求」が労働者の身分拘束に該当するが問われるケースが多発しています。研修費・留学費の返金請求とは「研修期間終了後に一定期間の継続勤務を義務付け、その期間内に退職した場合は研修費の返却を請求する」というものです。
労働基準法第16条の観点から、上記内容を労使契約で規定することは違法とされます。しかし、例外として研修費・留学費の返金請求が認められた事例も多く、経営者としては判断に迷うところです。研修費・留学費の返金請求の例外については次章で詳しく解説します。
関連記事:労働基準法に定められた「退職の自由」の意味を分かりやすく解説
1-3. 労働者に対する賠償請求を禁止するものではない
労働基準法第16条は、労働者に対する賠償金の請求を全面的に禁止するものではありません。禁止されるのは一定の金額の賠償を予め規定しておくこと、つまり罰金のことです。労働者の責で発生した損害に対し、経営者が法的な手続きを踏んで賠償金を請求することは認められます。
例えば、労働者が社用車で事故を起こした場合、法的な手続きを取れば労働者に修理代を請求することが可能です。しかし、労使契約の中で「事故を起こした場合は損害額に関わらず10万円の修理代を請求する」定めることはできません。これは具体的な金額を指定していることで罰金とみなされるためであり、労働基準法違反に該当します。
ただし、労働者に賠償請求ができると言っても、その損害額の全ての請求が認められることは稀です。会社の管理下で発生した損害である以上、労働者が起こした問題について会社も責任を負わなければなりません。
一般的に、労働者に請求できる賠償金は損害額の2割程が限度と言われます。なお、損害の理由が法に触れるものであったり、明らかに悪質であったりする場合はその限りではありません。
2. 研修費・留学費の返金請求は労働基準法16条に違反する?


原則として、退職時に研修費や留学費の返金を規定することは「賠償予約の禁止」に該当する違法行為です。
しかし、その請求が労使関係の強要に関連しないと判断された場合に限り、例外的に研修費・留学費の返金が認められることがあります。そのため、一概に 研修費・留学費の返金請求は労働基準法16条に違反するという訳ではなく、条件に合えば認められるケースもあります。実際のケースを見ていきましょう。
3. 研修費・留学費の返金請求が認められるケース


原則として、退職時に研修費や留学費の返金を規定することは「賠償予約の禁止」に該当する違法行為です。しかし、その請求が労使関係の強要に関連しないと判断された場合に限り、例外的に研修費・留学費の返金が認められることがあります。
ここでは労働基準法第16条に関連する「研修費・留学費の返金請求問題」について、その返金が認められるためのポイントを解説します。ただし、経営者の請求が労使関係の強要に該当するか否かは様々な観点から複合的に判断されるものであり、明確な基準はありません。過去の判例の基準を参考にしたものである点に留意してください。
3-1. 金銭賃貸契約により費用を負担している場合
過去、返金が認められた事例では、研修や留学の費用を労使契約ではなく「金銭賃貸契約」で定めていた点が共通しています。これは労使契約と返金請求の関連性を否定する上で最も重要なポイントです。
金銭賃貸契約で研修・留学の費用を拠出することにより、労働者には借金の返済義務が生じます。その上で一定期間の継続勤務により返済義務を免除するという特約を設ければ、継続勤務する労働者に負担は掛かりません。
「研修・留学の費用援助は純然な金銭賃貸契約であり、労使契約とは一切の関連がない」と認められれば、労働基準法第16条には抵触しないと判断されます。
3-2. 本人の意思で研修・留学に参加している場合
2つ目のポイントは「本人の意思で研修・留学に参加していること」です。これにより、労働者本人が希望する学びの費用を会社が負担したという関係性が成立します。退職するのであれば研修・留学費用は返金してしかるべき、という評価に結びつきやすくなります。
一方、本人が希望しない留学に会社の命令で参加させた場合、返金請求が認められる可能性は低いでしょう。これは会社都合の支出であり返金の義務はない判断されやすくなるためです。会社が強要する研修・留学であれば、当然その費用は会社が負担しなければなりません。
3-3. 教育内容と業務の関連性が低い場合
3つ目のポイントとして、「教育内容と業務の関連性が薄い」ことが挙げられます。理由としては前項目と同様で、業務との関連性が低ければ自主的な学びの機会と判断されやすくなるためです。
反対に、教育内容と業務内容がリンクする研修・留学は注意が必要です。会社都合による支出とみなされる可能性が高く、返金の判断基準としてはマイナスです。
3-4. 返金免除となる勤務期間が適切である場合
労使関係との関連性を否定するため、金銭賃貸契約の返却義務免除期間は適切な長さを設定するとよいでしょう。明確な基準はありませんが、5年10年という長い期間を設けていると、実質的な労使関係の強要とみなされる恐れがあります。
3-5. 金銭賃貸契約の範囲内で請求しよう
返金請求は金銭賃貸契約で貸し付けた費用に対して行うものですので、契約の範囲内の金額を請求しなければなりません。貸付額以上の金額を請求することは労働基準法第16条で禁止されています。
4. 労働基準法第16条に抵触した場合の罰則
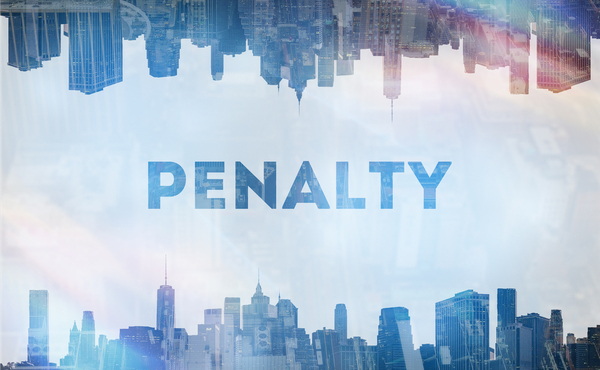
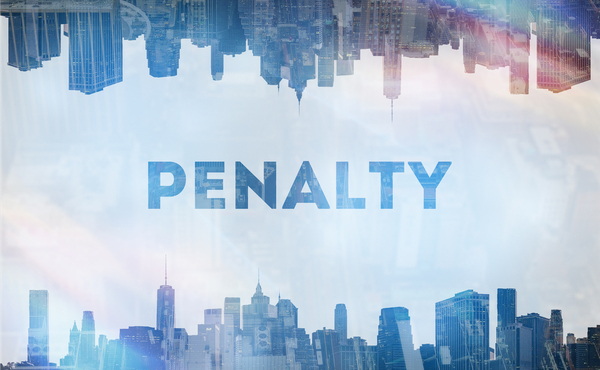
労働基準法第16条に抵触した場合の罰則は、同じく労働基準法第119条にて規定されています。
これによると、労働基準法第16条が定める「賠償予定の禁止」に違反した経営者には6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。
「賠償予定の禁止」は労働基準法で定められた法令です。労働者保護の観点からも、経営者には法令を遵守した企業経営が求められます。
5. 労働基準法第16条の内容や禁止事項を正しく理解しておこう


労働基準法第16条における「賠償予定の禁止」の規定により、労使契約の中で違約金や罰金の規則を定めることは禁止されています。特に、近年の社会では研修・留学費用の返金請求において「賠償予定の禁止」に抵触するケースが多く見られます。いかなる理由があれ、経営者が不当に労働者の退職の自由を妨げることは違法です。労働基準法を遵守し、労働者の権利を保証しましょう。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08






















