看護休暇は無給でも問題ない?取得条件・メリット・給与計算・注意点を解説
更新日: 2025.7.7 公開日: 2025.7.4 jinjer Blog 編集部
 「看護休暇は無給でも問題ない?」
「看護休暇は無給でも問題ない?」
「看護休暇の給与計算方法は?」
上記のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
看護休暇は法律上、無給であっても問題ありません。実際、多くの企業が無給で運用しています。
本記事は、看護休暇の賃金の取扱いをはじめ、取得条件や無給でも活用するメリット、給与計算方法をまとめました。看護休暇を無給で付与する際の注意点も解説するので、ぜひ参考にしてください。

雇用契約の基本から、試用期間の運用、契約更新・変更、万が一のトラブル対応まで。人事労務担当者が押さえておくべきポイントを、これ一冊に凝縮しました。
法改正にも対応した最新の情報をQ&A形式でまとめているため、知識の再確認や実務のハンドブックとしてご活用いただけます。
◆押さえておくべきポイント
- 雇用契約の基本(労働条件通知書との違い、口頭契約のリスクなど)
- 試用期間の適切な設定(期間、給与、社会保険の扱い)
- 契約更新・変更時の適切な手続きと従業員への合意形成
- 法的トラブルに発展させないための具体的な解決策
いざという時に慌てないためにも、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 看護休暇は無給でも問題ない|有給・無給の扱いは企業判断


看護休暇は、無給であっても法律上の問題はありません。
育児・介護休業法では、看護休暇中の賃金について明確な定めがなく、有給とするか無給とするかは企業の判断に委ねられています。
実際、厚生労働省「令和3年度雇用均等基本調査」によると、看護休暇の賃金の取扱いは以下のとおりです。
| 無給 | 65.1% |
| 有給 | 25.7% |
| 一部有給 | 7.4% |
このように、多くの企業が「無給」で看護休暇を運用しているのが実態です。
法律上の義務はないものの、看護休暇の運用方針を明確にし、就業規則や説明資料などで社内に周知することが重要です。
参考:令和3年度 雇用均等基本調査事業所調査結果概要|厚生労働省
2. 看護休暇の取得条件
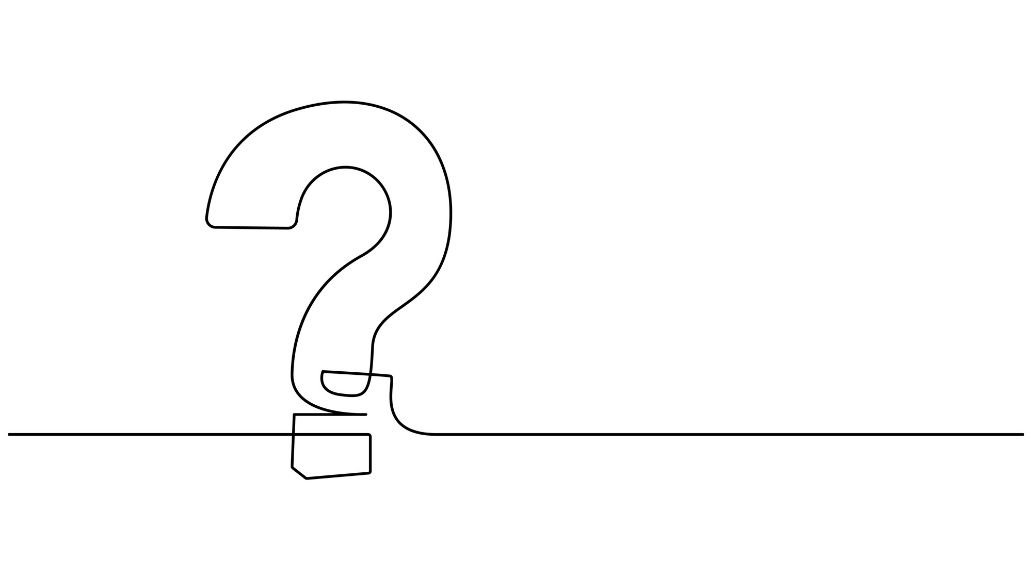
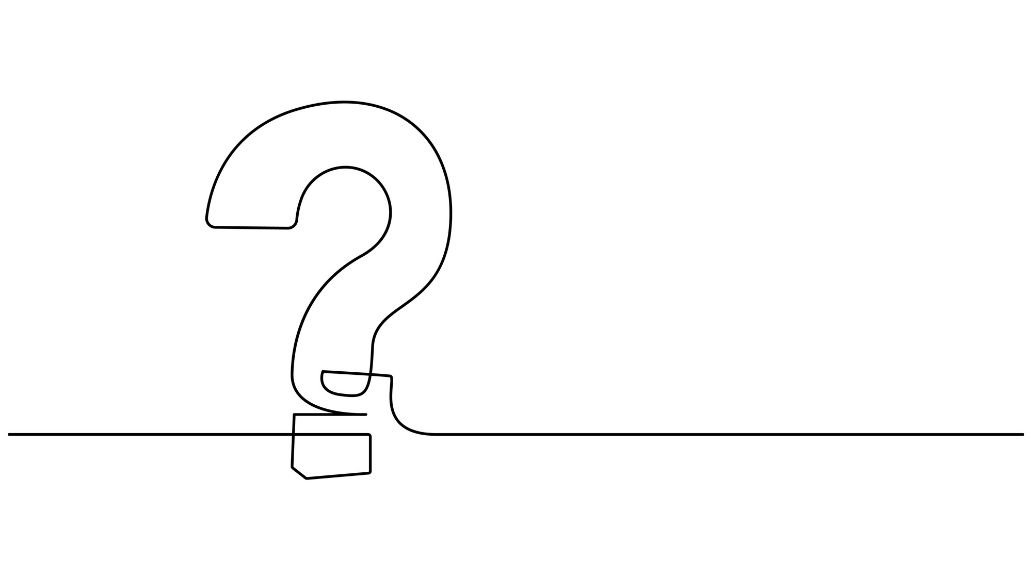
看護休暇の取得条件について、以下の表にまとめました。
| 対象者 | 小学校就学前の子どもを養育するすべての労働者
※週所定労働日数が2日以下の労働者は、労使協定で適用除外が可能 |
| 対象となる子の範囲 | 小学校3年生が修了するまで |
| 取得自由 | ・病気、けが
・予防接種、健康診断 ・感染症に伴う学級閉鎖など ・入園式、入学式、卒園式 |
| 休暇日数 | 子ども1人につき年5日(2人以上で最大年10日) |
| 取得単位 | ・1日単位
・半日単位 ・時間単位 |
| 賃金の取扱い | 法律上の定めなし(企業の任意) |
看護休暇は、原則として従業員の申請にもとづいて取得されます。
ただし、子どもの病気やけがは急を要することも多いため、当日の申請も柔軟に対応できる体制を整えることが望ましいです。
なお、2025年4月1日から病気やけがに加え、以下の事由も看護休暇の対象に加わりました。
- 感染症に伴う学級閉鎖など
- 入園式、入学式、卒園式
最新の制度内容を把握したうえで、対象者や取得方法などをわかりやすく周知しておきましょう。
参考:育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の2024(令和6)年改正ポイント|厚生労働省
3. 無給でも看護休暇を活用してもらうメリット


無給でも看護休暇を活用してもらうメリットは、以下の3つです。
- 有給休暇を使い切った従業員でも子どもの看病に対応できる
- 優秀な人材の定着につながる
- 助成金を獲得できる
3−1. 有給休暇を使い切った従業員でも子どもの看病に対応できる
看護休暇は無給であっても、年次有給休暇を使い切った従業員が、子どもの看病のために安心して休めるメリットがあります。
年次有給休暇とは別に与えられる法定休暇であるため、制度が整っていれば「欠勤扱いになる?」「給与が減る?」などの不安を軽減できます。
実際、看護休暇の制度がない場合、有給休暇を使い切った従業員が子どもの看病などで休むと「欠勤」扱いになります。その結果、給与や評価への影響を不安に感じることも少なくありません。
制度として設けておくことで、たとえ無給であっても正当な枠の中で休みを取得できます。従業員の精神的負担を減らすとともに、働きやすい職場づくりにもつながるでしょう。
3−2. 優秀な人材の定着につながる
看護休暇は無給であっても制度を整えることで、育児と仕事の両立がしやすい環境を実現し、優秀な人材の定着にもつながります。
柔軟に休暇を取得できる環境があるかどうかは、子育て世代にとって職場選びの大きな判断材料となるためです。
株式会社第一生命経済研究所の調査によると、制度整備が不十分であることによる就業調整などで失われる所得は年間6,350億円、企業活動への経済損失は約1兆1,741億円にのぼると報告されています。
こうした損失の背景には、出産や育児による離職・キャリア断絶が企業にもたらす影響の大きさがあるといえるでしょう。
看護休暇制度を整え、従業員の子育てを支援することは、離職率の低下や再採用コストの削減など、企業にとって重要な取り組みといえます。
参考:出産退職の経済損失1.2兆円〜退職20万人の就業継続は何が鍵になるか?〜|株式会社第一生命経済研究所
3−3. 助成金を獲得できる
看護休暇を無給で運用したとしても、一定の制度を整備すれば「両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)」を申請可能です。
両立支援等助成金は、子育てと仕事の両立を支援する取り組みをおこなう企業に対して支給される制度です。
主な要件を以下にまとめました。
- フレックスタイム制度・時差出勤・テレワーク・短時間勤務制度・看護休暇などの制度から2つ以上を導入
- 制度利用に関する方針を社内周知
- 対象従業員との面談を実施し、利用計画を作成・実行
- 制度開始から6ヵ月以内に、一定基準以上の利用実績があること
上記の条件を満たした場合、以下の助成金を受け取れます。
- 2制度導入+利用:20万円
- 3制度以上導入+利用:30万円
なお、看護休暇単独では対象外となるため、複数制度の導入を前提に計画することがポイントです。
看護休暇の制度整備を検討する際は、助成金の活用も視野に入れることで、コスト負担を抑えながら制度導入を進めやすくなるでしょう。
参考:2025(令和7)両立支援等助成金のご案内|厚生労働省・都道府県労働局
4. 看護休暇の給与計算方法


看護休暇の給与計算方法を、以下の流れで解説します。
- 無給で付与する場合
- 有給で付与する場合
4−1. 無給で付与する場合
看護休暇を無給で付与する場合、欠勤と同様に給与を日割りで控除する形で運用するのが一般的です。
看護休暇中の賃金について法的な支払い義務がないため、企業判断で無給とした場合には「不就労分の控除」として扱えるためです。
具体的には、以下の計算式で1日あたりの給与額を算出し、取得日数に応じて控除額を求めます。
月給 ÷ 所定労働日数 × 看護休暇取得日数 = 控除額
例えば、月給25万円・所定労働日数20日の従業員が1日看護休暇を取得した場合の控除額は、次のとおりです。
250,000円 ÷ 20日 × 1日 = 12,500円(1日の控除額)
なお、看護休暇は1日単位のほか、半日単位や時間単位でも取得できます。そのため、取得単位に応じた金額で正確に控除することが重要です。
4−2. 有給で付与する場合
看護休暇を有給で付与する場合、年次有給休暇と同様に給与を支払う形式が一般的です。
企業の方針により、以下のいずれかの計算方法から選択されるケースが多く見られます。
- 通常賃金(通常勤務時の賃金と同額)
- 平均賃金(直近3ヵ月の平均)
- 標準報酬月額の30分の1(社会保険上の基準)
中でも最も多く採用されているのが「通常賃金方式」です。
ほかの方法より支給額が高くなる場合もありますが、計算がシンプルで事務処理の負担を軽減できる点がメリットです。
以下はパート従業員の方が看護休暇を取得した際の例となります。
- 時給:1,200円
- 所定労働時間:1日5時間
- 1日分の看護休暇賃金: 1,200円 × 5時間 = 6,000円
いずれの方法を採用する場合でも、就業規則への明記が必要です。
5. 看護休暇を無給で付与する際の注意点


看護休暇を無給で付与する際の注意点は、以下のとおりです。
- 看護休暇の賃金取扱いは就業規則に明記する
- だれもが取得しやすい制度運用を目指す
5−1. 看護休暇の賃金取扱いは就業規則に明記する
看護休暇の賃金の取扱いについては、たとえ無給で付与する場合でも、必ず就業規則に明記する必要があります。
賃金の決定・計算・支払い方法は、労働基準法上の「就業規則の絶対的必要記載事項」に含まれるためです。
看護休暇を有給にするか無給にするかは、企業が自由に決定できます。しかし、内容を明文化しておかないとトラブルの原因になりかねません。
以下は、無給で運用する場合の就業規則記載例です。
| 本制度の適用期間中の給与は、別途定める給与規程に基づき、勤務がなかった時間に応じて減額された額を支給するものとする。 |
上記はあくまで一例です。有給で運用する場合は、「通常の賃金を支給する」旨を明記してください。
看護休暇の賃金の扱い方を決定したら、速やかに就業規則へ反映し、従業員にも周知することが重要です。
5−2. だれもが取得しやすい制度運用を目指す
看護休暇を無給で付与する場合でも、だれもが安心して取得できるような運用体制を整えることが重要です。
制度を設けるだけでなく、実際に利用しやすい職場の雰囲気や仕組みを整えることが、企業としての責務といえるでしょう。
職場全体で制度を活用しやすくするには、以下のような取り組みが有効です。
- 取得しやすい雰囲気づくり
- 代替要員が確保できる体制の構築
- 制度や利用方法の周知
例えば、管理職が率先して制度を利用することで、取得への心理的ハードルが下がります。
また、業務の属人化を防ぐマニュアルを整備しておけば、休暇取得時の業務引き継ぎもスムーズになり、周囲の理解も得やすくなります。
6. 看護休暇への理解を深めて従業員の子育てと仕事の両立を支援しよう


看護休暇は、たとえ無給であっても有給休暇とは別に休暇を取得できる法定休暇であり、子育てと仕事を両立しやすくする重要な制度です。
社内で正しく理解を広めることが、従業員の満足度向上や職場の信頼感の醸成にもつながるでしょう。
ただし、無給で付与する場合は就業規則への記載が必須です。制度を整えるだけでなく、実際に取得しやすい環境づくりも重要となります。
制度の周知や取得しやすい雰囲気づくりを通じて、従業員の仕事と子育ての両立を支援しましょう。



雇用契約の基本から、試用期間の運用、契約更新・変更、万が一のトラブル対応まで。人事労務担当者が押さえておくべきポイントを、これ一冊に凝縮しました。
法改正にも対応した最新の情報をQ&A形式でまとめているため、知識の再確認や実務のハンドブックとしてご活用いただけます。
◆押さえておくべきポイント
- 雇用契約の基本(労働条件通知書との違い、口頭契約のリスクなど)
- 試用期間の適切な設定(期間、給与、社会保険の扱い)
- 契約更新・変更時の適切な手続きと従業員への合意形成
- 法的トラブルに発展させないための具体的な解決策
いざという時に慌てないためにも、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-



雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2025年6月改正法成立後の動向や必要な対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2026.02.27
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
書類配布(人事)の関連記事
-


雇用契約書に印鑑は必要?押印の法的効力・ルールと電子化を解説
人事・労務管理公開日:2025.08.04更新日:2025.08.04
-


契約書の甲乙とは?優劣はある?雇用契約書・業務委託での使い方や注意点
人事・労務管理公開日:2025.08.04更新日:2025.08.04
-


リーガルチェックとは?人事労務部門の対象書類・依頼先、雛形管理のポイントを解説
人事・労務管理公開日:2025.08.04更新日:2025.08.04




















