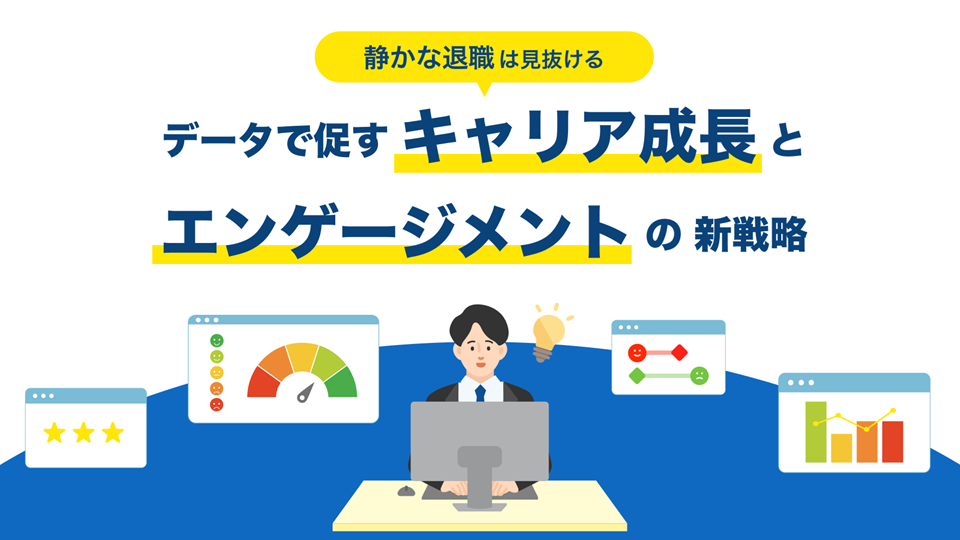帰属意識がない人の特徴は?企業にとってのデメリットや高める方法を解説
更新日: 2025.12.18 公開日: 2025.3.30 jinjer Blog 編集部

「帰属意識がない人には、どのような特徴があるの?」
「帰属意識がない人には、どのようなデメリットがある?」
上記のような疑問を持っている経営者や人事担当者も多いでしょう。
帰属意識がない人の特徴として、コミュニケーションを避けたり、仕事への熱意が感じられなかったりすることが挙げられます。帰属意識が低い従業員が増えると、組織全体の生産性や雰囲気に悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。
本記事では、帰属意識がない人の特徴や理由、企業が取るべき対策を詳しく解説します。従業員一人ひとりが組織の一員としての自覚を持ち、いきいきと働ける環境づくりをするためにも、ぜひ参考にしてみてください。
\この疑問を解決する、人事データ活用方法とは/
- 会社全体のプロジェクトを立ち上げても、希望者が集まらない
- なんとなく、会社全体の雰囲気が良くない気がする
- 原因不明の若手や中堅層の退職が増えた
そんなお悩みはありませんか?
当サイトでは、「消極的な従業員が生まれないようにするためにはどうしたら良いの?」「なぜ、従業員のモチベーションを保つ必要があるか知りたい」という人事担当者の方に向けて、従業員のモチベーションが低いことのデメリットや予兆を検知する方法、モチベーションを下げないための対策を解説した資料を無料配布しています。
従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、ルールの見直しにお役立てください。
1. 帰属意識がない人の特徴


帰属意識がない人の主な特徴は、以下の通りです。
- 上司や同僚との関わりを避けている
- 仕事のクオリティが低下する
- 仕事を頼んでも断られる
- 前向きな議論をしない
それぞれ具体的に解説します。帰属意識がない人の特徴を理解して、自社に当てはまる人物がいないか適切に判断できるようになりましょう。
1-1. 上司や同僚との関わりを避けている
帰属意識がない人は、上司や同僚との関わりを積極的に避ける傾向があります。職場でのコミュニケーションを最小限に抑え、必要最低限の情報交換以外はおこなわないことが多いです。
自分が所属している組織をただ「お金を稼ぐための場所」としか見ていないことが、理由として挙げられます。チームワークや協力を必要とする状況でも一人で対応しようとする従業員がいる場合、その人は帰属意識が低いと考えてよいでしょう。
1-2. 仕事のクオリティが低下する
帰属意識がない人は、仕事のクオリティも低下する傾向があります。組織に対する愛着や貢献意欲の欠如が、業務パフォーマンスに直接影響を与えるためです。
通常、帰属意識の高い従業員は、自分の仕事が組織にどのように貢献できるのかを理解し、高い品質の成果を出そうと努力します。しかし、帰属意識が低下すると、仕事に対する関心が薄れて自分の仕事の価値を見出せなくなるのが特徴です。
以前は高いクオリティを維持していた仕事でも、突然ミスが増えたり締め切りを守れなくなったりする可能性が高くなります。「ある程度の完成度でいいだろう」と細部までこだわらなくなった従業員は、帰属意識が低下していると考えてよいでしょう。
1-3. 仕事を頼んでも断られる
帰属意識がない人の特徴の一つとして、仕事を頼んでも断られることが挙げられます。帰属意識がないと「会社のために頑張ろう」との意識が薄く、自分の利益や都合を優先する傾向があるためです。
会社を単にお金を得るための手段と捉えているため、追加の仕事や責任を負うことを好みません。上司や同僚から仕事を依頼されても積極的に引き受けようとせず、できるだけ関与を避けようとするでしょう。
1-4. 前向きな議論をしない
前向きな議論をしないことも帰属意識がない人の特徴のひとつです。帰属意識が低い人は最低限の成果を出せばよいと考えていることが多く、新しいアイデアや業務改善につながるような意見を出してくれることは少ないでしょう。
議論にも積極的には参加せず、ただ話を聞いているだけという人もいるかもしれません。
以前は積極的に話し合いに参加していたのに急に消極的になった場合は、帰属意識が低下している可能性もあるため注意しましょう。
2. 帰属意識がない人によくある理由


帰属意識がない人によくある理由は、主に以下の3つです。
- 自身の役割がわからない
- 企業のビジョンに共感できない
- 企業の評価・サポートを実感できない
それぞれの理由について簡単に確認しておきましょう。
2-1. 自身の役割がわからない
企業やチームの中で自分がどのような位置づけにあり、どのような役割や責任を負っているのかがわからない場合、帰属意識は低下しがちです。
自分の仕事と同僚の仕事がどのように関わっているのか、事業を進めるうえでどのような意味があるのか、といったことを理解できていないと、企業やチームの一員であるという意識は生まれないでしょう。
また、自分の仕事の意義や重要性を理解できないと、単なる歯車のように感じ、組織への愛着や貢献意欲が薄れます。
2-2. 企業のビジョンに共感できない
企業のビジョンに共感できていないことも帰属意識が低下する理由のひとつです。企業の理念や目標に共感できていないと、仕事に積極的に取り組む意識が生まれず、モチベーションや帰属意識は低下してしまうでしょう。
そもそも企業のビジョンがわかりにくく、従業員にうまく伝わっていないことも帰属意識の低下につながります。
2-3. 企業の評価・サポートを実感できない
企業の評価やサポートを実感できないことも、帰属意識の欠如につながる要因の一つです。努力や成果が適切に評価されていないと感じたり、困ったときに支援を受けられなかったりすると、組織への信頼感が薄れます。
「自分が組織にとって重要な存在ではない」と感じると、帰属意識の欠如につながるでしょう。
3. 帰属意識がない人がいるデメリット


企業・組織内に帰属意識がない人がいることで考えられるデメリットは、主に以下の4つです。
- 生産性・業務効率の低下
- コミュニケーションの希薄化
- 離職率の上昇
- 企業文化の弱体化
各デメリットの詳細は以下の通りです。
3-1. 生産性・業務効率の低下
帰属意識の低い従業員は、組織の目標や自身の役割に対する関心が薄くなりがちです。自分の仕事が会社や顧客にどのように貢献しているのかを考えずに業務をこなすようになり、生産性や業務効率の低下につながります。
また、モチベーションの低下が周囲の従業員にも悪影響を与え、組織全体の生産性が低下してしまうケースもあるでしょう。
3-2. コミュニケーションの希薄化
コミュニケーションが希薄化することも帰属意識の低い従業員がいるデメリットです。組織や同僚への関心が薄れることで積極的に情報を共有しなくなると、業務に必要な情報が滞る可能性も高くなります。
コミュニケーションの機会が減ることで、人間関係を構築できなくなることも大きな問題です。協力体制を構築できず、仕事がスムーズに進まなくなるケースもあるでしょう。
3-3. 離職率の上昇
帰属意識がない従業員がいることで、離職率が上昇する可能性もあります。帰属意識が低下している従業員は、長く働く気持ちをもっていないため、すぐに転職してしまいがちです。
すぐに新しい人材を補充できれば問題ありませんが、残った従業員が仕事を引き継ぐことになり、負担が大きくなるケースもあるでしょう。その結果、ストレスを感じた従業員が離職するなど、連鎖的に離職者が増えてしまう可能性もあります。
3-4. 企業文化の弱体化
企業文化が弱体化してしまうことにも注意しなければなりません。
前述の通り、帰属意識が低い従業員は前向きに働いたり意見を出したりしないため、チームワークの弱体化や新しいアイデアの創出機会の減少につながります。
その結果、企業文化が弱体化し、組織の革新性や問題解決能力の低下につながるでしょう。
4. 帰属意識を高めることで得られる効果


従業員の帰属意識を高めると、主に以下の4つの効果が期待できます。
- 離職率が低下する
- 生産性・業務効率が向上する
- 組織力が強化されてイノベーションが促進する
- 企業のイメージアップにつながる
それぞれ順に解説します。上記のなかに自社が抱える課題が含まれている場合は、ぜひ帰属意識の向上を実施しましょう。
4-1. 離職率が低下する
帰属意識を高めると、離職率の低下が期待できます。
従業員の帰属意識が高まると、企業に対する愛着や思い入れが強くなり、長期的に組織に貢献したいという意欲が芽生えるためです。安易に転職を考えることが少なくなり、組織への定着率が向上します。
また、帰属意識の高い従業員が増えることで職場全体の雰囲気が改善され、「働きやすい」と感じる人が増加する可能性も高いです。企業の魅力として知られるようになれば、新たな人材の獲得にもよい影響を与えるでしょう。
4-2. 生産性・業務効率が向上する
帰属意識を高めることは、企業の生産性と業務効率の向上にも大きく影響します。帰属意識が高くなると、従業員が組織の一員であると自覚をもち、自発的に業務に取り組む傾向が強くなるためです。
単に与えられた仕事をこなすだけでなく、常に「効率を上げるにはどうすればいいか」を考えながら仕事に臨めるようになります。業務プロセスの改善や新しいアイデアの創出につながり、結果的に生産性の向上をもたらすでしょう。
4-3. 組織力が強化されてイノベーションが促進する
帰属意識を高めることで、組織力の強化とイノベーションの促進も期待できます。従業員が単に与えられた仕事をこなすだけでなく、企業・組織の目標達成に向けて積極的に貢献しようとするためです。
企業・組織全体のコミュニケーションが活性化し、部門や階層を超えた協力体制が構築されやすくなります。情報や知識の共有が円滑になることでさまざまな視点や意見が交わされ、新しいアイデアや解決策が生まれやすくなるでしょう。
4-4. 企業のイメージアップを図れる
企業のイメージアップを図れることも従業員の帰属意識を高めるメリットです。
従業員の帰属意識を高めれば定着率も向上するため、働きやすい企業というイメージが社会に浸透します。その結果、応募者が増加し、採用活動がスムーズに進むことを期待できるでしょう。
また、企業のイメージが向上することで、売上アップや取引先との関係強化も期待できます。
5. 帰属意識を高めるために企業ができること


帰属意識を高めるための取り組みとして、以下のようなことが挙げられます。
- 組織のビジョン・方向性を共有する
- 社内交流の機会を提供する
- 福利厚生を充実させる
- 従業員の役割・業務内容を明確にする
- 心理的安全性を高める
- 評価制度を見直す
それぞれ詳細に解説します。帰属意識の高め方を理解して、帰属意識がない人に適切な対処ができるよう準備しましょう。
5-1. 組織のビジョン・方向性を共有する
帰属意識を高めるためには、組織のビジョンや方向性を従業員と共有することが重要です。
ビジョンや方向性を明確にして従業員全員で共有することで、一人ひとりが自分に何が求められているかを理解できます。自分の仕事が組織全体にどのように貢献しているかを認識できれば、高いモチベーションで業務に取り組めるようになるでしょう。
経営層からのメッセージを定期的に発信したり、上司と部下で会社の方向性について話し合う機会を設けたりすることが効果的です。社内報や掲示板など、目に入りやすい形で提示することも有効な手段といえます。
5-2. 社内交流の機会を提供する
従業員の帰属意識向上のために効果的な方法として、社内交流の機会を積極的に提供することも挙げられます。単に従業員の親睦を深めるだけでなく、従業員同士の信頼関係を構築し、組織に一体感をもたらすためです。
具体的な例として、オフィス内にカフェスペースやラウンジを設置し、従業員が自由に利用できるようにすることが考えられます。何気ない会話から新たなアイデアが生まれる可能性を期待できるでしょう。
5-3. 福利厚生を充実させる
企業が従業員の帰属意識を高めたいなら、福利厚生の充実も効果的です。給与以外で従業員の生活をサポートする制度や取り組みを実施することで、従業員は会社に大切にされていると実感できます。
福利厚生を充実させる際は、従業員のニーズを適切に把握することが重要です。アンケートや面談を通じて得た従業員の声をもとに制度を設計することで、より効果的な福利厚生を提供できます。
定期的に制度の見直しをおこない、社会情勢や従業員のライフステージの変化に柔軟に対応することも忘れないようにしましょう。
5-4. 従業員の役割・業務内容を明確にする
従業員の役割と業務内容を明確にすることも、帰属意識を高めるうえで重要な施策の一つです。組織内での各個人の位置づけや責任範囲が明確になることで、従業員は自分の存在意義や貢献度を実感しやすくなります。
役割・業務内容を明確にするなら、職務記述書(ジョブディスクリプション)の作成や、定期的な業務の棚卸しが効果的です。業務フローや指示系統を可視化することで、組織全体の中での自分の役割を理解しやすくなるでしょう。
5-5. 心理的安全性を高める
心理的安全性を高めることも帰属意識の向上につながります。心理的安全性とは、自分の意見やアイデアを素直に発信しても問題ないという状態のことです。
心理的安全性が低いと発言する機会が減ってしまい、人間関係を構築しにくくなったり、モチベーションが低下したりしてしまいます。
逆に心理的安全性を高めれば、誰もが意見やアイデアを発信しやすくなり、議論に参加しているという気持ちや企業に貢献しているという意識が高まるでしょう。
5-6. 評価制度を見直す
帰属意識を高めるためには、評価制度を見直すことも重要です。頑張っても評価が上がらない、成果を出しても給与や待遇に反映されない、といった状態では、企業に貢献する気持ちは生まれないでしょう。
とくに上司の主観で評価している場合や、評価項目が明確になっていない場合は、従業員の不満が増え、帰属意識も低下してしまいます。従業員の成果を平等かつ正確に評価できるような仕組みを整えていきましょう。
6. 帰属意識がない人の特徴を把握したうえで職場環境を改善しよう


今回は、帰属意識がない人の特徴や帰属意識を高めるための方法などを紹介しました。
帰属意識がない従業員は、組織への愛着や貢献意欲が低く、コミュニケーションを避けたり仕事の質が低下したりする特徴があります。自身の役割が不明確であることや、企業ビジョンへの共感不足、適切な評価・サポートの欠如など、帰属意識が低下する原因はさまざまです。
帰属意識を高めるためには、社内交流の機会の提供や福利厚生の充実、従業員の役割の明確化などの施策が求められます。従業員が活き活きと働ける環境づくりを目指し、企業の持続的な成長と発展につなげましょう。
\この疑問を解決する、人事データ活用方法とは/
- 会社全体のプロジェクトを立ち上げても、希望者が集まらない
- なんとなく、会社全体の雰囲気が良くない気がする
- 原因不明の若手や中堅層の退職が増えた
そんなお悩みはありませんか?
当サイトでは、「消極的な従業員が生まれないようにするためにはどうしたら良いの?」「なぜ、従業員のモチベーションを保つ必要があるか知りたい」という人事担当者の方に向けて、従業員のモチベーションが低いことのデメリットや予兆を検知する方法、モチベーションを下げないための対策を解説した資料を無料配布しています。
従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、ルールの見直しにお役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
タレントマネジメントの関連記事
-



プレゼンティーイズムとは?原因と企業に与える損失額・対策をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2026.01.19更新日:2026.01.19
-



メンタルヘルスサーベイとは?ほかのサーベイとの違い、実施の目的や流れを解説!
人事・労務管理公開日:2026.01.16更新日:2026.01.14
-


企業におけるメンタルヘルスケアとは?4つのケアや事例を紹介
人事・労務管理公開日:2025.11.18更新日:2025.12.19