人事評価の目的とは?明確化すべき5つの目的と人事評価制度の最新手法を解説!
更新日: 2025.4.10 公開日: 2022.4.25 jinjer Blog 編集部

人事評価とは、従業員の能力や実績を評価し、給与・賞与・昇進などの査定をおこなうことを意味します。国家公務員法18条の2第1項では、人事評価を「任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上でおこなわれる勤務成績の評価」と定義しています。
しかし、人事評価制度を導入したものの、思うような成果が出ない企業が少なくありません。人事評価制度の導入で失敗しないためには、「目的の明確化」が重要です。この記事では、人事評価の目的を明確化する重要性や、代表的な人事評価制度の目的について詳しく解説します。
参照:人事評価|人事院
目次

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
1. 人事評価の明確化すべき5つの目的

人事評価制度がうまく機能しない原因として、「なんのために人事評価を導入するのかが考え抜かれていない」「人事評価の導入目的が従業員に伝わっていない」の2点が挙げられます。人事評価制度を機能させるには、制度設計の段階で人事評価をおこなう目的を明確化し、社内で広く意思決定・合意形成を目指すことが大切です。
一般的な企業が人事評価制度を採用する目的は5つあります。他社の事例を参考にしながら、まずは人事評価の導入目的を明確化しましょう。
関連記事:人事評価の「目標設定」の重要性や代表的な手法について解説
1-1. 給与・賞与の査定をおこなうため
国家公務員法で定義されている通り、人事評価制度は従業員の能力や実績を把握し、勤務成績を評価するための制度です。
そのため、多くの企業が、給与・賞与の査定に役立てるため、人事評価制度を導入しています。人事評価制度を導入し、人事評価項目を設定することにより、客観的な査定をおこなうことができます。
従業員にとっても、評価期間の頑張りが給与や賞与として反映されるため重要な機会です。
1-2. 昇格・昇進を最適なタイミングでおこなうため
昇格や昇進のタイミングは、従業員のモチベーションに大きな影響を与えます。そのため、最適なタイミングで辞令を出す必要があるのです。
そのために、定期的な人事評価に基づく明確な基準が必要なため、人事評価の中でも重要な目的となります。評価者は従業員の業務パフォーマンスや成長を観察し、昇格の判断材料とすることで、時期を逃さず昇進を促すことが可能になります。
一方で、急な昇進は従業員の負担や不安を招くことがあるため、タイミングを推し量ることも重要です。十分な準備と支援をおこなう必要があります。
1-3. 能力を可視化し人材育成や人材配置に役立てるため
人事評価制度の導入目的は、従業員の勤務成績を評価することだけではありません。人事評価制度を取り入れ、従業員の能力や働きぶりを可視化する仕組みをつくることで、社内の人材育成に活かすことができます。
また、優れた能力を持つ従業員や、突出した成果を挙げた従業員を適切に評価することで、従業員のモチベーションを高め、成長に向けた動機づけの効果も期待できます。
1-4. バリューやクレドを浸透させ、企業文化を醸成する
企業文化を醸成する目的で、人事評価制度を導入するケースもあります。組織を活性化させ、まとまりのあるチームを生み出すため、「バリュー(行動規範)」や「クレド(行動方針)」を重視する企業が増えてきました。
人事評価制度を導入し、バリューやクレドに基づいた人事評価を取り入れることで、経営層の信条や考え方をより深く根付かせることができます。このように人事評価制度を導入するときは、企業のビジョンや経営方針から逆算し、制度のアウトラインを設計していくことが大切です。
さらに採用活動へのフィードバックを強化するため、人事評価制度を導入する企業も少なくありません。人事評価制度を導入する過程で、企業は従業員の能力や働きぶりを評価するための項目を洗い出し、制度のアウトラインを設計していきます。
したがって、人事評価制度を整備すれば、「自社にとって望ましい、好ましい人物像」を明確化できます。また、採用候補者に人事評価制度について説明し、自社で活躍できる人材のイメージを伝えることで、人材採用のミスマッチを防ぐ効果も期待できます。
1-5. 従業員のモチベーションを上げ組織を活性化する
労働人口が減少傾向にある中、従業員のモチベーションを上げて人材流出を防ぐことは、企業にとって大きな課題です。この課題を解決するために、人事評価を導入するケースも少なくありません。
人事評価をおこない適切な処遇を与えることで、従業員のモチベーションを上げて、会社とのエンゲージメントを高める効果が期待できます。これにより、従業員の突然の退職を防ぐことができるでしょう。それだけでなく、従業員のモチベーションが上がることで生産性が向上し、組織全体の活性化につなげることもできます。
2. 人事評価の目的を明確化することで得られる4つのメリット

人事評価制度の導入がうまくいかない企業は、まず人事評価の目的を明確化し、人事制度への理解を深める場を用意することが大切です。
具体的には、評価者向けの研修や勉強会の実施、人事担当者向けのポリシー策定やマニュアルの整備、被評価者向けの説明会などが挙げられます。人事評価の目的を明確化することによって、企業は4つのメリットを得られます。
2-1. 会社のビジョンや経営方針が社内全体に伝わる
人事評価制度の導入目的を明確化することで、会社のビジョンや経営方針がより具体的に社内に浸透します。
人事評価制度をただ導入するだけでなく、「人事評価制度をなぜ導入するのか」「経営層は人事評価制度を通じ、どんな従業員を育てたいと考えているか」など、制度設計の背後にある思いを従業員に伝えることが大切です。人事評価の意図が浸透すれば、より人事評価制度が機能しやすくなります。
また、人事評価のプロセスを通じて、会社のビジョンや経営方針に賛同する従業員が増加し、組織活性化につながります。
2-2. 人事評価エラーを防止し、より公正に人事評価をおこなえる
人事評価制度のリスクとして、公正な人事評価がおこなわれない「人事評価エラー」が挙げられます。代表的な人事評価エラーとして、たとえば次のようなものがあります。
| ハロー効果 | 特定の印象に引きずられ、他の項目への評価が歪んでしまう傾向 |
| 中心化傾向 | 5段階評価における3など、無意識的に中央値で評価してしまう傾向 |
| 寛大化傾向 | 全体的に評価が寛大で、なんとなく甘い評価をつけてしまう傾向 |
| 逆算化傾向 | 結果ありきで評価をおこない、被評価者の特徴にかかわらず評価を歪めてしまう傾向 |
こうした人事評価エラーの要因として、人事評価制度についての理解が不足しており、評価者が主観や印象で評価してしまうケースが挙げられます。評価者向けの研修や勉強会を実施し、人事評価制度の目的を明確に伝えることで、人事評価エラーを抑止できます。
2-3. 運用ルールが整備され、従業員の待遇をよりスムーズに決められる
人事評価制度の導入目的が明確であれば、制度のポリシーやコンセプトに基づき、運用ルールを具体的に整備できます。
たとえば、「人事評価のフィードバックを通じ、上司と部下の上下関係を活性化させる」のが導入目的であれば、フィードバックについてのルールや、人事評価の事後調査についてのルールをより具体的に決めることができます。運用ルールを整備することで、従業員の待遇をよりスムーズに決められ、適材適所の人材配置を実現できます。
2-4. 期待成果や期待行動が明確化され、仕事のパフォーマンスがアップする
人事評価制度は、企業が従業員に対して期待する成果や行動を可視化するための制度でもあります。人事評価制度の目的を明確化すれば、「企業が求める人物像はなにか」「どのような成果や行動を実現すれば、キャリアアップにつながるか」といった経営層の思いが伝わり、従業員のモチベーションアップにつながります。
人事評価制度の目的は、給与・賞与・昇進などの査定だけではありません。人事評価制度の目的を明確化し、社内に浸透させることで、組織全体の生産性やパフォーマンスの向上にもつながります。
ここまで、人事評価をおこなうメリットについて解説してきました。きちんとした人事評価制度を実際に導入したいけれど、どんな項目を作成し、何を基準に評価をつければ良いのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当サイトでは、そのような方に向けて、人事評価に関する情報をまとめた「わかりやすい!人事評価の手引き」というガイドブックをお配りしています。
人事評価制度の作成から導入、結果をどのように活用していくのかなど、人事考課に関する基礎知識がこれ一冊にまとまっているので、こちらから無料でダウンロードして、人事評価の参考書としてご活用ください。
3. 人事評価を構成する要素と評価基準

人事評価の目的、その目的を明確化することで得られるメリットを説明したところで、人事評価を導入する際に押さえておくべき人事評価の基本構成や評価基準について説明します。
3-1. 人事評価を構成する要素
人事評価を構成する要素は、主に「等級制度」「評価制度」「報酬制度」の3つです。以下にわかりやすく説明します。
| 概要 | 説明 | |
| 等級制度 | 社員の能力や職務責任を示すもので、等級と役職に分かれている | 等級は社員の技術力や経験を反映し、役職はその社員が担う職務の名称を指します。同一の役職に異なる等級が存在することもあり、企業の経営戦略に合わせた設計が求められます。 |
| 評価制度 | 社員の評価を金銭的な処遇や昇進に利用する重要な要素 | 企業の業績向上にもつながるため、適切に活用することが重要です。 |
| 報酬制度 | 金銭報酬と非金銭報酬に分かれている | 金銭報酬は基本給や手当など直接的な金銭的な利益を含む一方、非金銭報酬は仕事環境や認知、キャリアアップの機会など、より感情的な側面に影響を与えるため、社員のモチベーションを高める上で大切です。 |
3-2. 人事評価の評価基準
人事評価制度の基礎をなす評価基準は、「成果評価」「能力評価」「情意評価」の三つの要素から成り立っています。これらの基準を明確にすることで、評価の公正性や透明性が向上し、従業員の理解と納得を得やすくなります。以下にわかりやすく説明します。
| 説明 | |
| 成果評価 | 従業員が創出した成果や達成した業績を評価すること |
| 能力評価 | 知識やスキルなど、従業員の業務遂行能力を評価すること |
| 情意評価 | 業務対する従業員の熱意や働きぶりを評価すること |
これらの基準を統合的に用いて評価を行うことで、組織全体のパフォーマンス向上に寄与することが期待できます。
関連記事:人事評価の基準はどうやって決める?考慮すべき3つの要素を解説!
4. 人事評価制度の最新手法

人事評価制度の種類は先述の、能力評価、情意評価、成果評価だけではありません。ここでは、4つの評価手法を取り上げ、それぞれ特徴について解説します。
4-1. 目標管理制度(MBO)
目標管理制度(MBO)は、個人や部署が目標を決めて、目標に対する達成度を評価する手法を指します。組織の目標にリンクするように従業員自身に目標を決めさせるため、目標達成に向けた自主的な行動を促しやすいのが特徴です。
一方で、目標の達成度が評価と結びつくことから、従業員があえて達成しやすい目標を選んでしまうこともあるため、目標設定の際は上司がチェックをするなどのフォローが必要となります。
4-2. コンピテンシー評価
コンピテンシー評価では、高い実績を出している人材に共通する行動特性を評価項目とするのが特徴です。そのため、従業員がもつ能力や行動特性を客観的に評価することができます。
また、コンピテンシー評価は高い実績を出している人材を効率よく育成することが可能です。しかし、実績を出している従業員の行動分析に時間がかかってしまいます。
4-3. 360度評価
360度評価とは、上司・部下・同僚などさまざまな立場から評価をおこなう手法のことです。多角的な視点から評価できるため評価の偏りを防止でき、また被評価者にとっても客観的にみた自分の特性に気付ける点がメリットです。
しかし、被対象者との関係性によっては必ずしも本音が得られるとは限りません。
4-4. バリュー評価
バリュー評価は、行動規範など企業が大切にしている価値観(バリュー)の浸透度を評価項目とする手法です。バリュー評価は客観的な評価が難しいものの、自社の風土や文化に根差した強い組織づくりに効果的です。
関連記事:人事評価の方法6種類を紹介!評価制度の導入が失敗する理由と対策も解説
5. 人事評価制度を導入する際の注意点
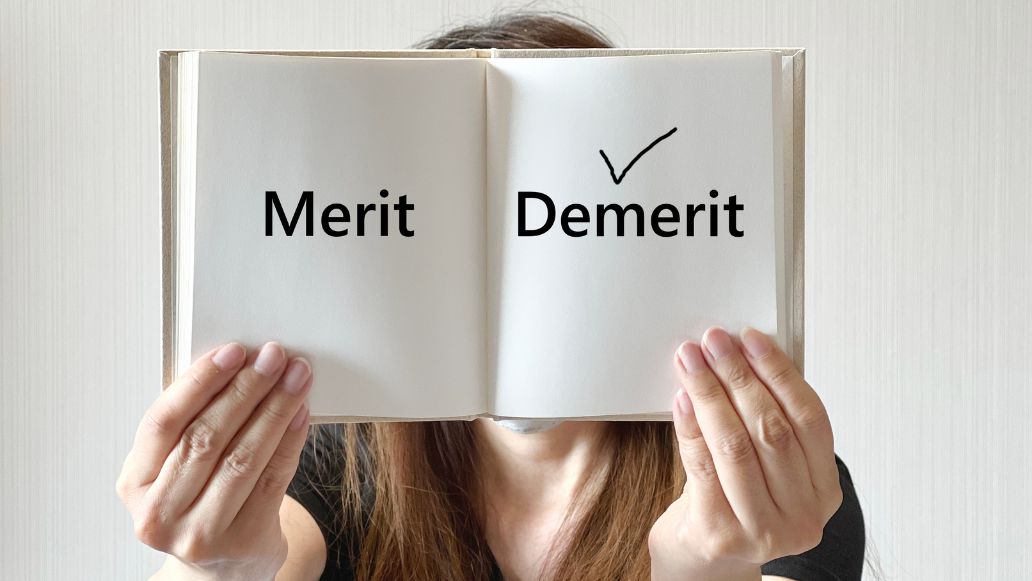
続いて、人事評価制度を導入する上で注意しておくべきポイントを説明します。導入後失敗したということがないよう、しっかりと注意点を理解しておきましょう。
5-1. 人材開発の視野が狭まる可能性がある
人事評価制度を導入することで、人材開発の視野が狭まる可能性があります。例えば、厳格な評価制度を用意してしまうと、従業員の能力が画一化されてしまうかもしれません。その結果、組織に活発化しなくなります。
また、新たな事業やプロジェクトに取り組もうとした際に、適した人材が見つからないというリスクにもつながりかねません。
そのため運用のしやすい人事評価制度であることも大切ですが、従業員の可能性を見落とすことがないよう広い視野で評価できる制度構築が必要です。
5-2. 評価の範囲外となる業務に支障が発生する
人事開発の視野が狭まるように、人事評価制度によって生じる注意点が、評価範囲外の業務への対応です。評価の範囲外となる業務が発生した際に、積極的に対応する従業員が現れない可能性があります。評価の範囲外となる業務に着手しないことで、全体の業務が停滞しかねません。
そのため、バリュー評価などを検討し業績の観点だけではない多角的な評価の仕組みを作ることを意識しましょう。
5-3. 生産性が低下する恐れがある
人事評価制度は適切に運用できていないと、従業員の生産性低下を招く可能性があります。例えば、評価者が公正に評価を下していないのであれば、従業員は評価に対して不満を抱くでしょう。その結果、モチベーションが下がり生産性の低下につながります。
なかには、評価への不満を理由に離職してしまう従業員もいるかもしれません。そういったことがないよう、予め評価制度の導入時には従業員への説明会をおこなうなど段階的にわかりやすく導入を進める必要があります。
5-4. 面談や1on1で正しくフィードバックを伝える
定期的な面談を実施せず、適切なフィードバックを行わない場合、評価基準に対する理解が不足し、従業員のモチベーションが低下する恐れがあります。
また、フィードバックが不十分な場合、従業員は自分の業務や成果について正確な認識を持てず、成長の機会を逃すことになります。これにより、組織全体のパフォーマンスや生産性にも悪影響を及ぼすことが考えられます。さらに、コミュニケーション不足は、信頼関係の希薄化を招き、従業員の離職率が上昇する可能性もあります。
このため、定期的な面談や1on1を通じて、雇用者と従業員の間でスムーズな情報共有を図り、効果的なフィードバックを行うことが不可欠です。これにより、従業員の成長を促し、組織の目標達成に貢献することができるでしょう。
6. 人事評価の目的を明確化し、組織の生産性やパフォーマンスを改善しよう

人事評価制度の導入で失敗しないためには、まず「目的の明確化」に取り組むことが大切です。人事評価制度の導入目的として、たとえば「待遇の決定」「人材育成」「採用活動へのフィードバック」「組織活性化」などが挙げられます。人事評価制度の導入目的から逆算し、制度設計に反映させましょう。
人事評価の目的を明確化し、研修や説明会などを通じて社内の理解を得ることで、より人事評価制度が機能しやすくなります。会社のビジョンや経営者の思いが社内全体に伝わり、組織の生産性やパフォーマンスを改善することが可能です。
関連記事:人事評価はなぜ必要?導入して考えられるメリットやデメリット
関連記事:人事評価とは?制度概要や評価基準・実施する目的や課題、導入方法を解説

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
人事評価の関連記事
-

派遣でも部署異動はさせられる?人事が知っておくべき条件・注意点・手順を解説
人事・労務管理公開日:2025.06.03更新日:2025.12.18
-

賞与の決め方とは?種類と支給基準・計算方法・留意すべきポイントを解説
人事・労務管理公開日:2025.05.26更新日:2025.05.27
-

賞与の査定期間とは?算定期間との違いや設定する際の注意点を解説
人事・労務管理公開日:2025.05.25更新日:2025.12.18































