抜擢人事とは?成長企業で導入される理由とメリットを解説
更新日: 2025.5.1 公開日: 2023.6.13 jinjer Blog 編集部

年齢や勤続年数によらず、優秀な人材を重要なポジションに任命することを抜擢人事といいます。人材育成やキャリアアップの重要性が高まり、年功序列を重んじていた日本企業でも抜擢人事が盛んにおこなわれるようになりました。
本記事では組織内での優秀な人材を適切に評価し、キャリアアップの機会を提供する抜擢人事のメリットや運用の要点を解説します。
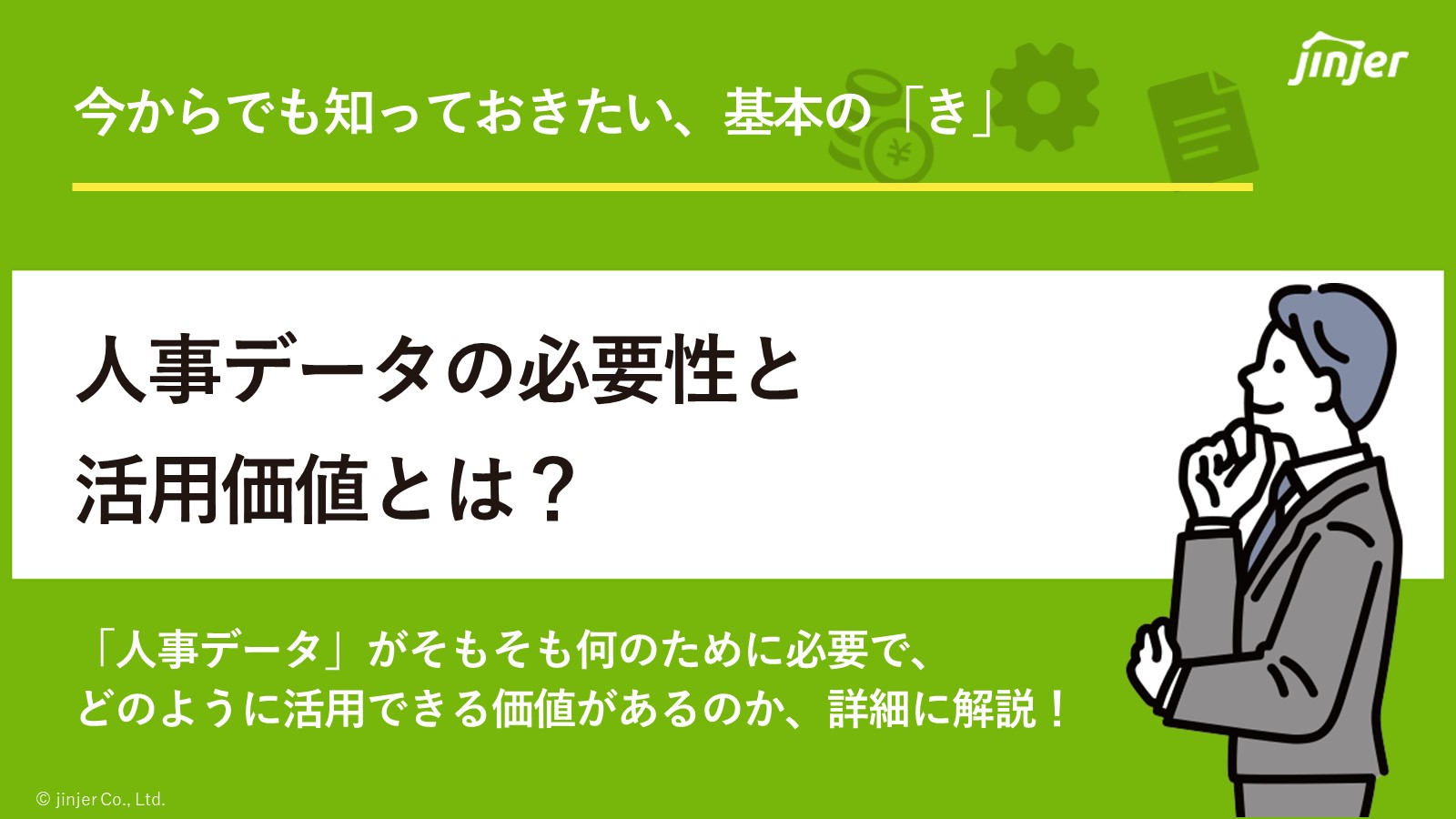
企業として人事データを適切に管理することはとても重要ですが、そもそもなぜ人事情報の管理が必要であり、その先に大きな活用価値があることについても、正しく理解できていますか?
当サイトでは、人事データ活用の「基本のき」から、事業成長に繋げるためのポイントまでを解説した資料を配布しています。
◆この資料で得られるメリット
-
経営層が納得する、根拠に基づいた人事戦略を立案できる
-
勘や経験に頼らない、データに基づいた人材配置・育成のヒントを得る
-
散在したデータを整理し、戦略的な意思決定に繋げるためのステップ整理が可能
貴社の人事データを「戦略資産」へと変えるために参考になりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
1. 抜擢人事とは


1-1. 実力重視で出世や昇進させる制度
「抜擢人事」とは、優れた能力や実績を持つ人材を出世や昇進の形で選抜し、管理職や役職など重要なポジションに任命することを指します。勤続年数や学歴、性別は問わず、個々の人材を実力で評価し昇進やキャリアアップの形で人事に役立てる制度です。
若手社員でも役職や重要なポジションに就ける可能性のある人事であるため、後輩の社員が先輩社員よりも先に出世して上司になるケースもあります。もちろん女性や外国人が抜擢されることもあるため、これまでの年功序列とは違う考え方や方針で業績アップや業務の効率化を狙うことも可能です。
ただし、ベテランの社員や先輩社員が「追い抜かされた」という感覚に陥りやすく、反感や嫉妬といったマイナスの感情が発生することもあるため、抜擢人事をおこなう際は配慮も必要です。
1-2. 抜擢人事で登用すべき人物の条件
抜擢人事で登用する従業員は、能力やスキルが高いだけでなく、人望もあるようなほかの従業員が納得できる人物でなければなりません。どのような人物を抜擢すればよいのか、具体的な条件を見ていきましょう。
経験とスキル
適切な職務を遂行するにあたり、必要な経験とスキルを持っていることが抜擢人事で登用する人材の条件です。候補者に対する期待だけで判断せず、ポストに適した知識やスキルを持っていることを確認するために、適切な試験や面接をおこないましょう。
ポテンシャル
プレーヤーとしてのスキルはもちろん重要ですが、候補者には将来的にリーダーシップやマネジメントのポジションに昇進できる可能性があることが望ましいでしょう。人格、コミュニケーション能力(部下のモチベーションを高められる能力)、問題解決能力、判断力、協調性などを総合的に評価することが大切です。
イニシアチブ
主導権を持って自発的に業務を進められることも条件のひとつです。より高度なタスクを遂行するために、報告、連絡、相談を密にできるかどうかも判断材料になります。
カルチャーマッチ
勤続年数や年齢を飛び越えて、新たな人材を重要なポストに登用するからには、企業の文化に合致する人物であることが必要です。企業の目標やビジョンに共感し、自分の役割を果たすために他の従業員と協力し、チームの成果に貢献できる能力があるかどうかも見極めましょう。
抜擢人事ではこれらの条件を総合的に評価し、企業の将来的なニーズに合わせて、適切な候補者を選択することが重要です。
1-3. 抜擢人事と年功序列の違い
年功序列は、従業員の年齢や勤続年数に応じて、昇進や報酬などの待遇を決定する考え方です。つまり、経験年数が長ければ長いほど、より高い地位や報酬を得ることができます。年功序列の人事では、従業員の年齢や経験が尊重される一方で、若手社員の成長や能力発揮の機会が限られるという問題も指摘されています。
一方抜擢人事は、従業員の能力や成果に基づいて、昇進や報酬などの待遇を決定する考え方です。つまり、能力や実績が優れている人には、年齢や勤続年数に関係なく、高い地位や報酬を与えることができます。しかし、年齢や経験に基づいた評価がおこなわれないため、勤続年数が短い従業員や若い従業員が上司になることから、従業員のモチベーションや意欲低下を招く可能性もあるとされています。
抜擢人事と年功序列は、人材の登用や昇進に関する考え方が異なるため、それぞれのメリットやデメリットを理解し、組織の状況や目的に合わせた適切な採用や人事政策を選択することが重要です。
関連記事:年功序列と成果主義はどう違う?それぞれの特徴を詳しく比較
1-4. 抜擢人事導入が進む背景
近年、抜擢人事制度を導入する企業が増えていますが、その背景には少子高齢化による労働力の減少があります。
少子高齢化は企業内でも進んでおり、中高年の従業員が増え、若い世代の従業員は不足している状態です。そのため、人件費は膨れ上がる反面、能力やスキルにそぐわない待遇の若い従業員は離職するという課題が生まれ始めています。年功序列制度をそのままにしておくと、将来的に必要な人材が減り続けることが考えられるのです。
抜擢人事を導入すれば、若い人でも中途採用者でも能力次第で処遇や待遇が決まるため、優秀な人材の確保につながります。少子高齢化対策はすぐに結果がでるものではないため、このような背景から抜擢人事を導入する企業は今後も増加することが考えられます。
2. 抜擢人事を導入する理由と目的


抜擢人事導入の目的は、「新しいリーダーの育成」「企業の活性化」「人材不足の解消」の3点が挙げられます。
2-1. 新しいリーダーの育成ができる
年功序列の人事制度では、勤続年数や年齢でリーダーが決まるため、能力や資質がある若い人材を育成できません。
抜擢人事制度を取り入れれば、リーダーに適した人間性やスキルを持つ若い人に重要なポジションを任せることができます。早い段階から責任のあるポストでの経験を積むことで、固定概念に縛られない、新しいリーダーを育成できるでしょう。
また、若いうちに将来的に人を率いる立場になるという認識が生まれると、それに向けたスキルアップや人脈の形成もしやすくなります。年齢だけでなく、経験やスキル、人望も兼ね備えた魅力的なリーダーの育成も抜擢人事の目的といえます。
2-2. 企業の活性化ができる
年功序列制度における出世や昇進は、営業成績や能力だけで決まるものではないため、優秀な人材であっても能力を活かせるポジションに就くことはできません。適材適所に配置されない人事制度は、従業員のモチベーションを下げ、能力がある人材は転職を選ぶこともあり企業を衰退させるリスクがあります。
抜擢人事であれば年齢も経験も関係なく、能力次第でポジションが決まるため、若い人でも出世や昇進を目指すことが可能です。その結果、従業員の士気が上がり、企業全体の活性化が期待できます。
2-3. 人材不足の解消につながる
抜擢人事では、年次、学歴、職歴、入社形態に左右されず、能力のある人材を上位のポストに昇進させることができます。企業が抜擢人事を進めれば管理職の人材不足が解消され、組織単位での問題解決がスムーズになるでしょう。
また、女性管理職の比率を増やすためにも抜擢人事は有効です。女性はライフステージの変化に伴いキャリアの分断が起きやすく、年功序列を基本とする人事制度では出世が遅くなる傾向にあります。抜擢人事を進めれば、女性を含む既存人材のパフォーマンスを最大化できるうえ、優秀な人材の採用にも好影響がもたらされるでしょう。
3. 抜擢人事のメリットとデメリット


3-1. 抜擢人事のメリット
抜擢人事のメリットは、優れた人材を重要なポジションに配置することで、組織の業績向上や競争力の強化などが期待できることです。また、ほかにも下記のようなメリットがあります。
適材適所の人材配置がしやすい
抜擢人事は勤続年数や性別などを考慮せずに異動をおこなうため、適材適所の人材配置がしやすくなります。「〇年以上この業務をしないと部署異動はできない」などのルールにも縛られず、柔軟性のある異動ができるため、従業員も能力を発揮しやすくなり生産性が向上するでしょう。
若手のモチベーション維持・成長促進につながる
実力や成果によって抜擢人事がおこなわれることが従業員に伝わっていれば、出世を目指して自己研鑽に励む従業員が出てきます。
また、若手が重要なポジションに就けば本人のモチベーションも高くなり、同期や先輩社員にも刺激になって負けじと成果をあげようと邁進するでしょう。
市場や時代の変化に迅速に対応できる
企業を取り巻く状況は常に変化し続けており、市場や時代の変化に合わせて常に新しい取り組みをしなければ生き残れません。
既存の部署だけでは対応できなくなった場合、新規開拓する分野や拡充するサービスに強い従業員を抜擢人事できれば、迅速に変化に対応することができます。
勢いのある若手を登用すれば、流行に乗った業績アップも狙えるかもしれません。
3-2. 抜擢人事のデメリット
抜擢人事のデメリットとしては、以下の2点が挙げられます。
人が減った現場の負担が増えてしまう
優秀な人材が現場の第一線から離れると、それまで一緒に働いていた人材が穴を埋めなければならず、現場の負担が増加することがあります。抜擢人事による部署移動がある場合は、採用による人材の補充や業務のアウトソースもセットで考えましょう。
対立が激化して人間関係が悪化する恐れがある
抜擢人事をおこなうことで、従業員間の競争や対立が激化することがあります。人間関係でのストレスや、精神的なハラスメントが生じないよう、十分な配慮が必要です。また、選抜基準や選考プロセスが不透明だったり、公正性に欠けたりする場合は、不満や不信感が生じやすくなります。
中堅やベテラン従業員のモチベーション低下
抜擢された従業員が誰もが認める優秀な人物で、人望もあり、周囲の人が全員納得する人事であることは少ないです。
抜擢されなかった従業員は「なぜあの人なのだろう」「自分の方が経験が豊富なのに」などの不満を抱え、モチベーションの低下を招いてしまうことがあります。
特に後輩に追い抜かされる形になる中堅やベテラン従業員は、自分が正当に評価されていないと感じてやる気を失ってしまうかもしれません。
4. 抜擢人事を失敗させないためのポイント


4-1. 評価プロセスや評価基準をオープンにする
抜擢人事をおこなう際には、評価プロセスと評価基準をオープンにしましょう。
抜擢人事導入に賛成している人でも、年下の従業員がいきなり上司になったり、新人がリーダーになったりするのはおもしろくないかもしれません。しかし、「その人が選ばれた理由」が分かれば、人事にも納得できるのでモチベーションが下がることはないでしょう。
抜擢人事は、「公平な評価によって人事が決まること」が従業員のモチベーションアップにつながります。このメリットを得るためにも、評価プロセスはオープンにして不平・不満があがらない人材配置をおこないましょう。
4-2. 評価の客観性と公平を維持する
抜擢人事では、評価の客観性と公平性を従業員に十分に理解してもらわなければなりません。
年功序列制度は、勤続年数や年齢など登用基準が分かりやすいため、その年数に達していない従業員から不満がでることはありません。しかし、抜擢人事制度で評価基準があいまいだと、「人事担当者のお気に入りなのでは」「評価方法が偏っているのでは」などの不満がでてきます。
不満は企業への不信感につながるため、抜擢人事に必要なスキルや成果など能力を明示し、公平性を維持することが大切です。
そしてその基準を従業員に周知して把握してもらうことも重要です。周知しておかないと、後からトラブルに発展しかねないため、面倒でも全員に周知して、丁寧な説明をおこなうことが失敗しないポイントです。
4-3. 抜擢されなかった社員のフォローをする
年功序列制度のままであれば、重要なポストに就くはずだった従業員が抜擢人事により異なる立場になるケースは多々見られます。そうなると当然該当の従業員は不満を抱えてしまい、人間関係の悪化やモチベーションの低下を招きます。そのような事態を避けるには、以下のようなフォローをしましょう。
フィードバックの提供
抜擢されなかった従業員に対してもフィードバックの提供などのフォローをしましょう。どのような点を改善すれば会社から高く評価されるか、従業員と認識を揃えることがモチベーションの維持にもつながります。
キャリアアップの機会の提供
抜擢人事で登用できるポストに限りがあると、不公平感が生じることがあります。会社全体でキャリアアップの機会を増やすなど、従業員が自身の能力を最大限に活かせる環境を整備することが重要です。
関連記事:評価制度への不満が発生する原因と適切な対応方法を解説
5. 抜擢人事を成功させて企業全体の活性化につなげよう


プレーヤーと管理職では期待される役割が異なるだけでなく、業務内容や責任範囲も異なるため、新しいポストが候補者の描くキャリアとマッチするかどうかも抜擢人事を成功させるための重要なチェックポイントです。従業員にスキルとポテンシャルがあり、意向が会社の目標と沿う場合、攻めの抜擢人事は組織の風通しを良くするきっかけになるでしょう。
過去の成果や実績をこれからの職務にどのように活かせるかを考慮しながら、個々の従業員が能力を最大限に発揮できる人事制度を検討しましょう。
関連記事:情意評価とは?導入のメリットや注意点をわかりやすく解説
関連記事:成果評価とは?能力評価・情意評価との違いを詳しく解説
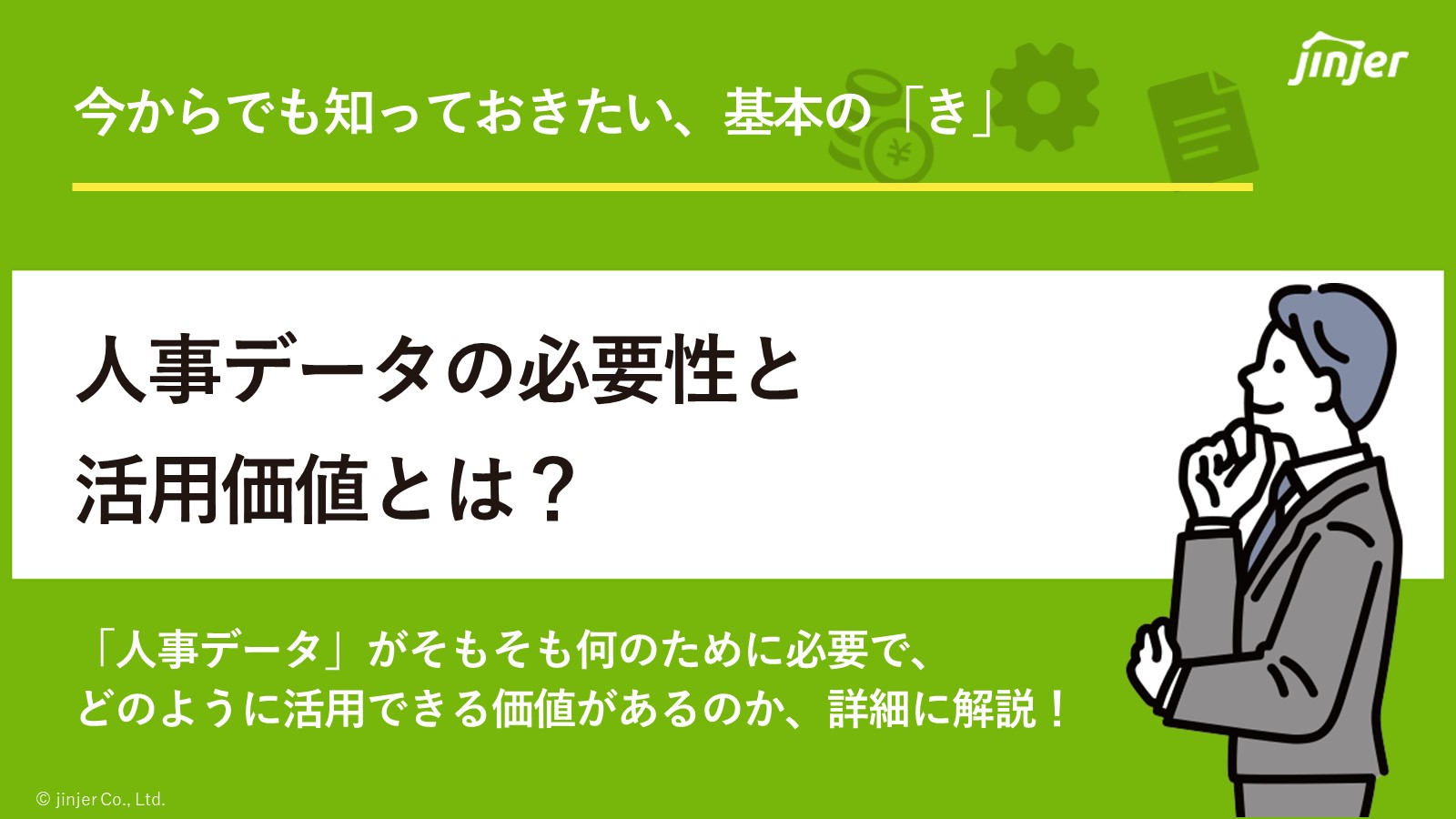
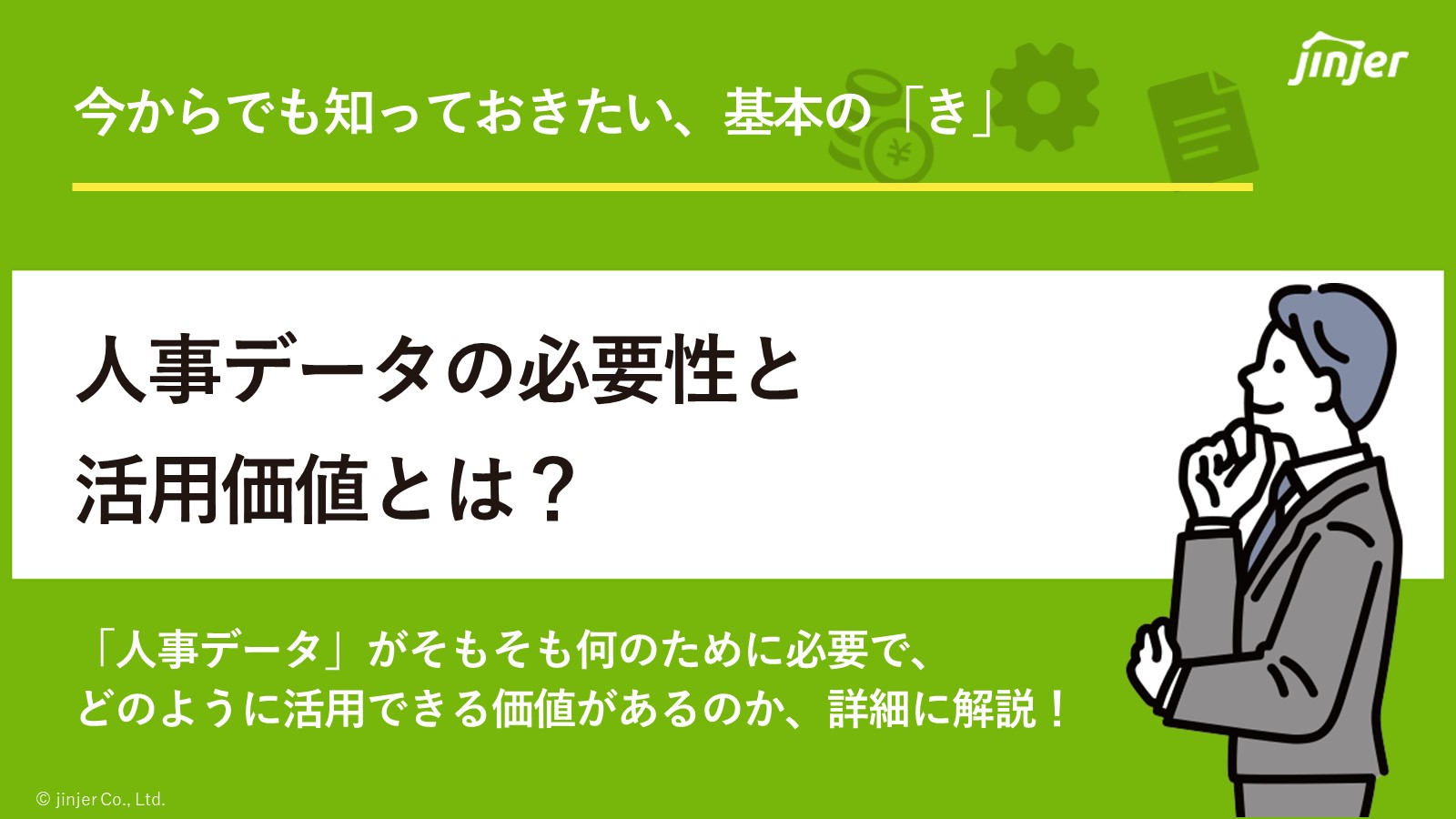
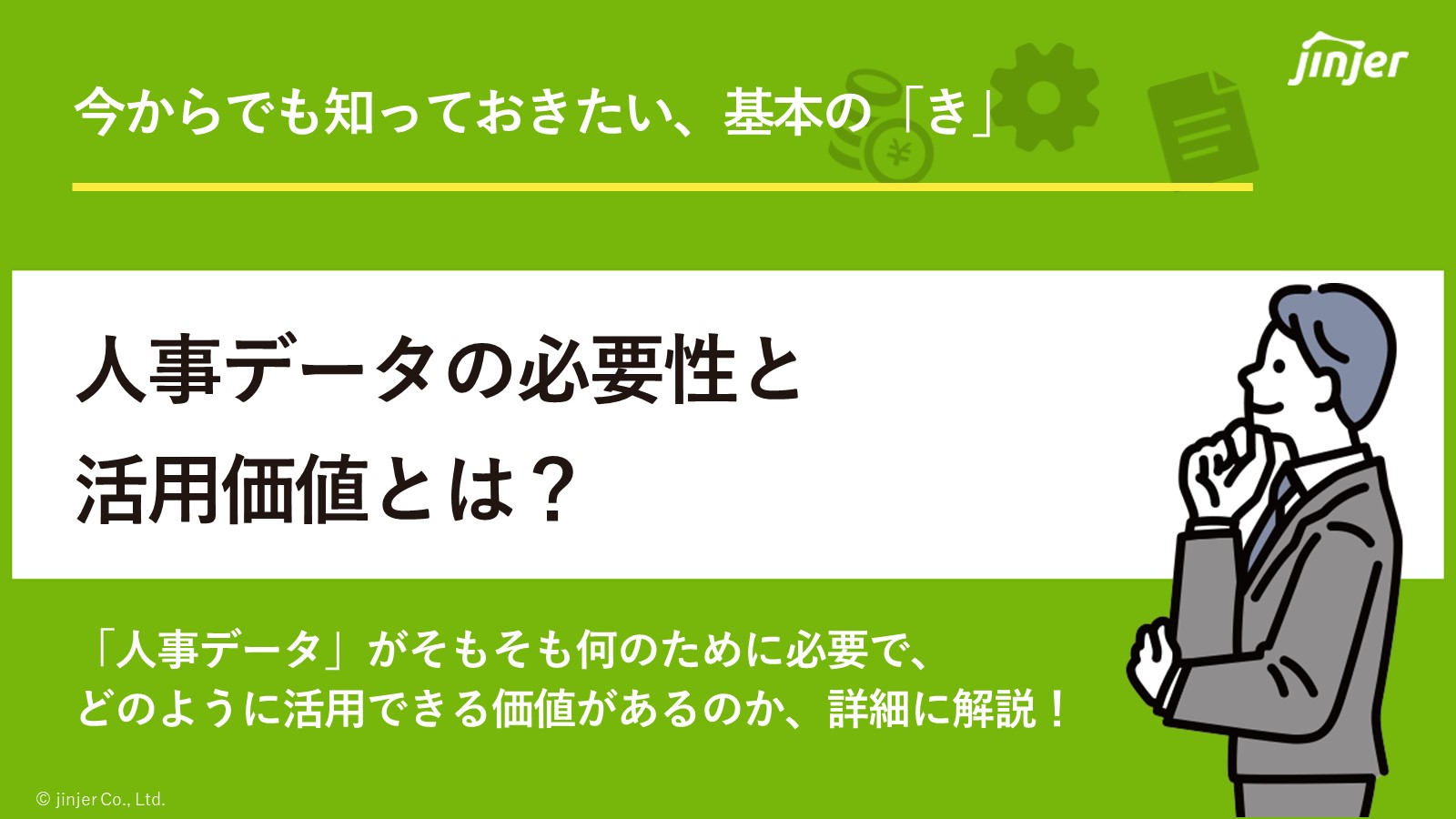
企業として人事データを適切に管理することはとても重要ですが、そもそもなぜ人事情報の管理が必要であり、その先に大きな活用価値があることについても、正しく理解できていますか?
当サイトでは、人事データ活用の「基本のき」から、事業成長に繋げるためのポイントまでを解説した資料を配布しています。
◆この資料で得られるメリット
-
経営層が納得する、根拠に基づいた人事戦略を立案できる
-
勘や経験に頼らない、データに基づいた人材配置・育成のヒントを得る
-
散在したデータを整理し、戦略的な意思決定に繋げるためのステップ整理が可能
貴社の人事データを「戦略資産」へと変えるために参考になりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
人事評価の関連記事
-


派遣でも部署異動はさせられる?人事が知っておくべき条件・注意点・手順を解説
人事・労務管理公開日:2025.06.03更新日:2025.12.18
-


賞与の決め方とは?種類と支給基準・計算方法・留意すべきポイントを解説
人事・労務管理公開日:2025.05.26更新日:2025.05.27
-


賞与の査定期間とは?算定期間との違いや設定する際の注意点を解説
人事・労務管理公開日:2025.05.25更新日:2025.12.18






















