定量評価とは?定性評価との違いや具体的な方法を紹介
更新日: 2024.5.22
公開日: 2023.5.17
OHSUGI

人事評価で使われる「定量評価」とは、どのような評価方法を指すのでしょうか。定量評価は数値や数量で評価判定をするので、人事担当者の主観が評価に反映されず、人事評価制度の客観性を高めるといわれています。
数値化によって判定をおこなう定量評価と、数値化できない業務を斑点する定性評価を組み合わせることで、より公平な人事評価制度を構築することが可能です。本記事では、定量評価の意味や定性評価との違い、定量評価を実施するときの流れをわかりやすく解説します。
目次
人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
1. 定量評価とは?数値や数量で表せるものを評価すること

定量評価とは、従業員の行動や成果を数値化し、客観的に評価する方法を指します。辞書で「定量的」という言葉を引くと、以下の意味が出てきます。
【定量的】
- 数量に関するさま。ある物質にその成分がどれだけ含まれるかを表す場合などに用いる。「―測定」
- 数値・数量で表せるさま。「―な目標を設定する」
人事評価制度における定量評価は、売上や案件獲得数、コストの削減率など、数値や数量で表せるものに着目するのが特徴です。従業員の目標設定をおこなうときは、数値化可能な「定量目標」を設定し、その達成度を数字で評価します。そのため、定量評価は人事担当者の主観が評価に反映されず、客観性が高い評価方法だとされています。
1-1. 定量評価の具体例
定量評価に使われる主な項目としては、以下のようなものが挙げられます。
- 売上
- 利益率
- 新規発注数
- リピート契約の件数
- クレームの発生率
- 人件費の削減率
- 材料費の削減率
- 経費の削減率
- WebサイトのPV数
- TOEICなどの資格の点数
- 業務にかかった平均時間
定量評価というと、成果を数字で表しやすい営業部門やマーケティング部門で採用されているイメージがあるかもしれません。しかし、最近は事務部門や管理部門などでも定量評価が取り入れられています。
例えば、事務職の場合だと書類作成にかかった平均時間、ミスや手戻りの削減率、消耗品費などのコストの削減率といった項目を定量評価として設定することが可能です。
2. 定量評価と定性評価の違い

定量評価と対照的な評価方法が「定性評価」です。定量評価と定性評価の違いを表にまとめると、以下のとおりです。
| – | 定量評価 | 定性評価 |
| 定義 | 数値や数量で表せるものを評価すること | 数値化できないものを評価すること |
| 強み | 評価者の感覚に左右されず、客観的に評価できる | 定量化しにくい項目も人事評価に反映させることができる |
ここでは、定性評価の定義や、定量評価と定性評価の違いを詳しくみていきます。
2-1. 定性評価は数値化できないものを評価すること
定性評価とは、勤務態度やコミュニケーションなど、数値や数量で表せないものを評価する方法を意味します。辞書で「定性的」という言葉を引くと、以下の意味が出てきます。
ていせい‐てき【定性的】 の解説
[形動]1 性質に関するさま。ある物質にその成分が含まれるかどうかを表す場合などに用いる。「—検査」⇔定量的。
2 数値・数量で表せないさま。「人事の—評価」⇔定量的。
たとえば、顧客満足度という評価項目に対して、「クレーム件数を●●%削減する」「アンケートの満足度●●%以上を達成する」という数値目標を設定する場合、定量評価にあたります。
一方、「明るく元気に接客し、お客様を笑顔にする」といった数値化できない目標を立てる場合は定性評価に当たります。
2-2. 定量評価との違いは評価者の感覚に左右されるかどうか
定量評価と定性評価のもっとも大きな違いは、評価者の感覚に左右されるかどうかです。
さきほどの顧客満足度に関する例でいうと、「クレーム件数を●●%削減する」「アンケートの満足度●●%以上を達成する」といった目標を達成できたかどうかは、客観的な数字で測ることができます。しかし、「明るく元気に接客したかどうか」「お客様を笑顔にしているかどうか」は、評価者の感覚に左右され、判断がわかれる可能性があります。
そのため、人事評価の客観性という点では、定性評価よりも定量評価のほうが優れています。
2-3. 定量化しにくい項目も定性評価なら評価できる
評価制度では、下記のような項目も必要です。
- 勤務態度
- コミュニケーション
- 主体性
- 積極性
- チャレンジ精神
- チームワーク
会社のルールやモラルを守り、社風や人間関係を見出さないために必要なこれらの項目は、数値化が難しく、定量評価ではうまく評価できません。そのため、定性評価は定量化しにくい項目を評価するために使われています。定量評価と定性評価を組み合わせ、両者のよいとこ取りをしながら人事評価制度を構築することが大切です。
3. 定量評価のメリット
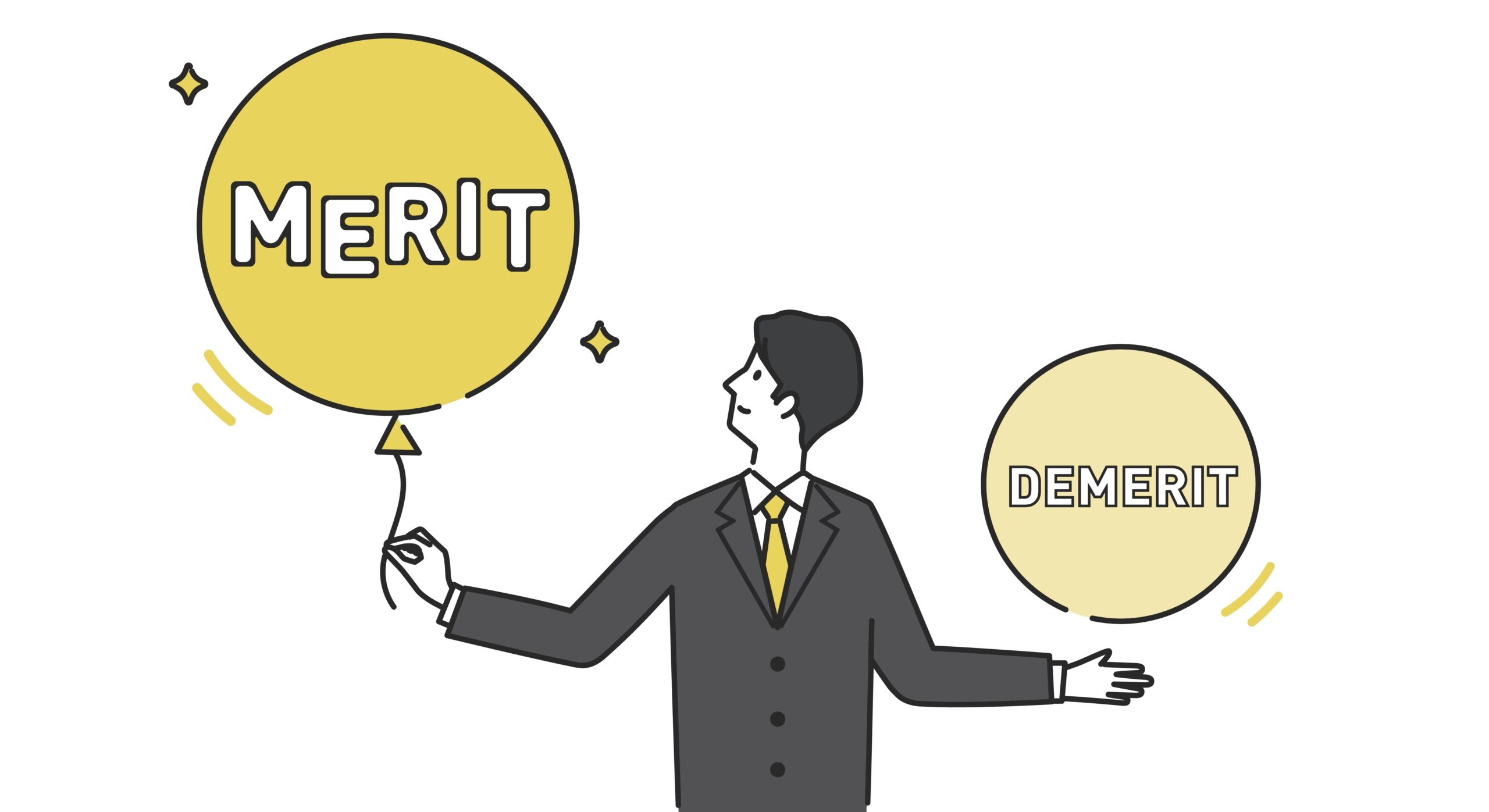
定量評価は、評価項目を作成する際に数値を設定しなければなりません。簡単にクリアできるような数値では評価基準になりませんが、クリアできないような数値ではモチベーションが上がらないので、設定が難しく面倒に感じることもあるでしょう。しかし、定量評価を取り入れることで得られるメリットがあります。
ここでは3つのメリットを紹介するので、導入の際の参考にしてみてください。
3-1. 評価基準が明確でわかりやすい
定量評価の評価軸は「数値」なので、誰でも評価基準を理解できます。数値以外の基準というのは、個人の感覚や価値観によって受け取り方が異なることもあるため、認識に相違が生まれてしまいます。認識の違いによって、評価結果に不満を持つ従業員が出てくるかもしれません。
しかし、シンプルに「数値」で基準が明確になっていれば、認識の相違もなく結果に不満を抱くこともないでしょう。
ただし、数字はシンプルでわかりやすい反面、無機質な印象を与えることがあります。成績が優秀な従業員であればモチベーションアップにつながりますが、思うような成果がでない従業員の場合はモチベーションが下がってしまう可能性があります。このような場合は、評価面談以外にフィードバックの機会を設けて、アドバイスやフォローをすることで「数値」によるメリットを得られるようにしましょう。
3-2. 数値で判断できるので公平性がある
定量評価は、数値で結果を判断できるので公平性があるというのもメリットです。
評価制度が従業員の不満の原因になるのは、不公平さを感じることです。例えば、ノルマを達成している従業員が、ノルマを達成していない従業員より評価が低い場合、「なぜこのような評価になるのか」という不満を抱きます。理解できない従業員に対して、フィードバック面談で経緯を説明しても、納得させることは難しいでしょう。また、不満を持っていると、「業務に集中できない」「やる気がなくなる」という状態になることも少なくありません。
しかし、定量評価は数値による結果となるため、従業員が「不公平だ」と感じることもなく、フィードバック面談もスムーズに進められます。また、会社や評価者への不信感も払拭できるでしょう。
3-3. 自分で目標を立てられる
定量評価は「数値」によって結果を出すので、達成度や成績が一目でわかります。基準がなければ、成果発表は「優秀な人材」と「優秀ではない人材」を可視化しているだけの状態です。このような場合、成績が悪い従業員はやる気を削がれてしまいます。
しかし、達成度や順位が低くても、定量評価は評価基準が明確なので、自分で目標を立てられるというメリットがあります。1位を目指すのは難しいですが、評価基準をクリアすればいいだけなので、「次は必ず基準を超える」「もっと順位を上げよう」など、従業員本人が目標を設定しやすくなります。押し付けられるのではなく、自分自身で目標を立てられれば、自発的な成長にもつながるでしょう。
4. 定量評価のデメリット
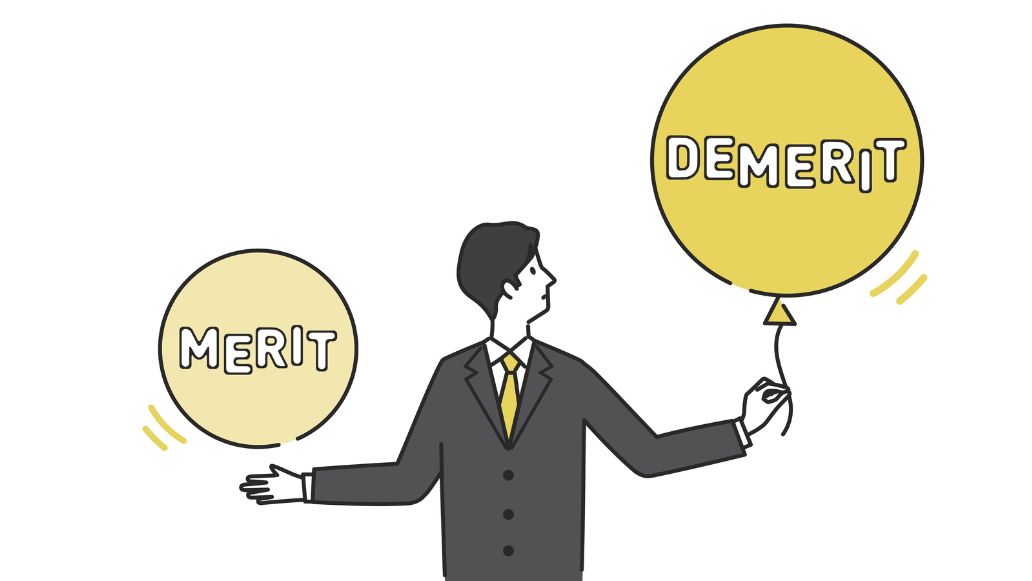
定量評価には、メリットがある反面デメリットもあります。
定量評価は、評価制度でもっとも重要な「公平性を保てる」というメリットがありますが、職種によっては公平性が保ちづらいことがあるので要注意です。デメリットを把握しておかないと、導入後にトラブルが起こるリスクもあるので、担当者の方はしっかり確認しておきましょう。
4-1. 職種によっては公平性が保ちづらい
定量評価は、職種によっては公平性が保ちづらいというデメリットがあります。その理由は、メリットとなる「評価基準が数値化できる」ということにあります。
業務というのは、すべてが数値化できるわけではありません。例えば、総務部や経理部などの事務職、オペレーターやエッセンシャルワーカー、受付などの職種は、定量化しにくい業務なので、数値化が難しく公平性が保ちづらいです。
このような場合は、コミュニケーション力や勤務態度などで評価をおこなう定性評価を導入すると良いでしょう。また、公平性のために定量評価を導入したい場合は、事務職なら業務の処理時間、オペレーターなら接客時間などで評価をするのもおすすめです。
4-2. プロセスや努力は評価対象にならない
定量評価は、「数字」で評価をおこうため、成果を出すためのプロセスや努力が評価対象にならないというのもデメリットです。「結果がすべて」というのはビジネスの基本ですが、定量評価を重視しすぎると単なる「ノルマ」になってしまいます。これでは評価制度のメリットが得られませんし、真面目に頑張っているのにまったく評価されないということに、不満を持つ従業員もいるでしょう。
また、数字だけの評価では、意欲を持って業務をおこなっている従業員を見逃してしまう可能性もあります。こういった人材は、部署を変えれば能力を発揮できるかもしれません。今や、人材確保は重要な業務の1つなので、数字による結果主義に偏らないように、定性評価も併せて導入することが望ましいでしょう。
5. 定量評価の具体的な方法

定量評価を行うときの流れは以下のとおりです。
- SMARTの法則を活用し、定量目標を設定する
- 目標の達成度をフィードバックする
- 3カ月ごとに定量目標を修正する
定量評価では、定量目標の設定とフィードバックを繰り返し、目標の達成度を数字で評価していきます。定量目標は3カ月を目安にしてリセットし、前回の取り組みをもとにして修正することが大切です。
5-1. SMARTの法則を活用し、定量目標を設定する
定量評価を設定するときは、SMARTの法則を意識しましょう。
- 具体的な(Specific)
- 測定可能な(Measurable)
- 実現可能な(Achievable)
- 企業の目標と関連した(Relevant)
- 期限が決まった(Time-bound)
定量目標は、具体的で測定可能であり、十分に実現可能なものの必要があります。また、目標を具体的な数字で表すだけでなく、達成までの期限を決めることが大切です。
自社の事業と関係のない目標を設定しても意味がないため、企業の目標と連動させることも大切です。
5-2. 目標の達成度をフィードバックする
定量目標を設定したら、目標の達成度について必ずフィードバックを実施しましょう。定量評価は「数字がすべて」の人事評価ではありません。成果を追求することも大切ですが、目標の数値を達成するための努力やチャレンジの部分を評価するのも人事担当者の仕事です。目標の数値に届かなかった場合は、うまくいかなかった原因を探し、フィードバックを通じて改善点を伝えましょう。
5-3. 3カ月ごとに定量目標を修正する
従業員に課す定量目標は、定期的にリセットし、現在の能力やスキルセットに合わせて細かく修正することが大切です。少なくとも、3カ月を目安に定量目標を見直しましょう。従業員に合った適度な目標を設定することで、より意欲やモチベーションを引き出し、スキルアップにつながります。
6. 定量評価の特徴や具体的な方法を知り、人事評価に取り入れよう

定量評価とは、売上や利益率、契約件数など、数値や数量で表せるものを評価する方法です。数値化できる定量評価とは対照的に、勤務態度やコミュニケーションなど、数値化できないものを評価する方法を定性評価とよびます。
定量評価を実施する流れは、まず数値化可能な定量目標を設定し、達成度の評価とフィードバックを実施します。定量目標を設定する際は「SMARTの法則」を活用し、具体的で実現可能な目標を選びましょう。期間に決まりはありませんが、3カ月を目安に定量目標をリセットすることで、従業員の成長につながりやすくなります。
定量評価は人事担当者の主観が反映されず、客観的に従業員の行動や成果を評価できる方法です。定量評価の特徴や定性評価との違いを知り、人事評価制度に取り入れましょう。
人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08




























