成果主義とは?能力主義との違いや導入時の注意点を紹介
更新日: 2024.4.5
公開日: 2023.4.6
OHSUGI

成果主義は従来の年功序列や学歴、職歴を基準とする評価に対して、存在する人事評価制度のひとつです。仕事の成果に応じて評価する制度ですが、詳しい内容や評価の基準についてはあまり知られていません。
導入する会社も増えつつあり、会社をより成長させるためのポイントになり得る制度です。
本記事では成果主義について詳しく解説します。
目次
人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
1. 成果主義とは?

成果主義とは、会社における人事評価の考え方のひとつです。成果主義を採用している会社では、社員が仕事であげた成果や成績、実力などを参考に評価をおこなっています。会社によっては学歴や職歴、経験などを重視して評価をおこなっているケースもあり、成果主義は対極の存在です。
成果や成績を評価に反映させるのは当然のように思えるかもしれません。しかし、従来の会社は学歴や経験などを重視して評価をしているケースが多く、成果主義という考え方は比較的珍しいものでした。
1-1. 成果主義が導入された背景
成果主義の考えが普及した背景には、1990年代に起こったバブル崩壊にあります。それまではどの会社も業績が好調であり、年功序列で給料を支払っていれば、不平不満が出ることはありませんでした。
しかし、バブル崩壊によって業績が悪化すると、仕事をしている社員に給料を支払うべきという考えが一般的になります。勤続年数が長く、仕事をしていない社員に対する人件費の増加は大きな問題でした。
このような背景から成果主義が生まれたと考えられています。現在では成果主義をベースにして、フリーランスや派遣、請負といった働き方が生まれており、給料を支払う基準が「会社に所属しているか」ではなく「給料に見合う仕事をしているか」に変わっていきました。
1-2. 成果主義の特徴
成果主義において勘違いされやすい点に「成果のみが判断基準となる」というものがあります。成果は評価のポイントのひとつですが、それだけが判断基準になるわけではありません。
成果に至るまでにどのようなプロセスがあるのかも評価されます。そのため、成果主義において数字だけを参考にするということはほとんどありません。
数字とは社員の成果が正直に表れます。成果主義で社員を評価する場合は、数字だけで判断してもいいように思えるでしょう。
しかし、数字だけを基準に社員を評価すると、数字で評価できない部分に対しての取り組みが蔑ろになってしまいます。具体的には、勤務中の態度や素行などが数値で評価できない部分です。
成果を出していればいいと社員が思うと、そういった部分への意識が薄くなってしまう可能性が考えられます。そのため、成果主義の場合も、成果だけに頼って評価するケースは少ないと覚えておきましょう。
2. 成果主義と能力主義の違い

成果主義と能力主義は似ている点が多くありますが、異なるポイントもあります。混同されやすいため、どういった点が異なるのかは正しく理解しておきましょう。
2-1. 能力とは成果に限らない
能力主義における「能力」の定義は考え方によって異なります。しかし、一般的には成果に限らず仕事を遂行するうえで有用である知識や技術、仕事に取り組む姿勢なども能力に含まれると考えられています。
一方で成果主義における「成果」とは、一般的に該当期間の個人の業績のことです。成果主義と能力主義では、社員を評価するための判断の軸が違うといえます。
2-2. 若手社員が評価されやすいのは成果主義
一般的に能力主義は、等級や役職で区切られて評価されることが多いです。成果が評価されないわけではありませんが、等級や役職で区切られている以上、評価には限界があります。
しかし、成果主義には立場による区分けは存在せず、どのような業績を残したかで判断されます。つまり、会社での立場が低い若手社員でも、成果主義であれば評価されやすいです。
2-3. 成果主義と年功序列の違い
成果主義と比較されるのが年功序列です。成果主義は従業員の実績に応じて給与や役職が決定します。一方、年功序列は勤続年数や年齢を基準に給与や役職が決まります。年功序列は日本独自の人事制度です。成果主義では勤続年数や年齢は評価の基準として含まれません。
2-4. 成果主義に対応できる従業員の特徴
成果主義に対応できる従業員の特徴は向上心の強さです。向上心の強い従業員や上昇志向の強い従業員は成果主義に対応しやすいでしょう。また、他人と競い合って切磋琢磨したいと考えている従業員も成果主義に対応しやすい傾向にあります。
3. 成果主義のメリット

成果主義のメリットは次のとおりです。
- モチベーション向上
- コスト削減
- 年功序列制度の廃止
- 人材の育成
3-1. モチベーション向上
成果主義のメリットとしてモチベーション向上が挙げられます。年功序列の場合、若い従業員は成績が良くても給与や役職に反映されづらい傾向にあります。一方、成果主義であれば年齢に関係なく従業員の成果次第で給与や役職があがっていきます。そのため、若手をはじめ従業員のモチベーション向上が期待できるでしょう。
3-2. コスト削減
年功序列の場合、勤続年数や年齢に応じて給与が高まります。そのため、成果を出せていない従業員であっても、年齢や勤続年数によっては高い給与を得ているかもしれません。一方、成果主義であれば成果を出している従業員の給与を高くし、成果を出せていない従業員の給与を高くしないため、無駄なコストを削減できます。
3-3. 年功序列制度の廃止
成果主義を取り入れることで年功序列制度の廃止というメリットにつながります。成果主義を推進することで、年功序列制度の廃止につながるため、コストの削減や従業員のモチベーション向上などが期待できるでしょう。
3-4. 人材の育成
成果主義は成果に応じて給与や役職が設定されます。より高い給与、役職を希望するのであれば高い成果を残さなければなりません。そのため、成果主義であれば従業員は成果を出すためにスキルアップを図ろうとします。その結果、人材の育成につながるでしょう。
4. 成果主義のデメリット
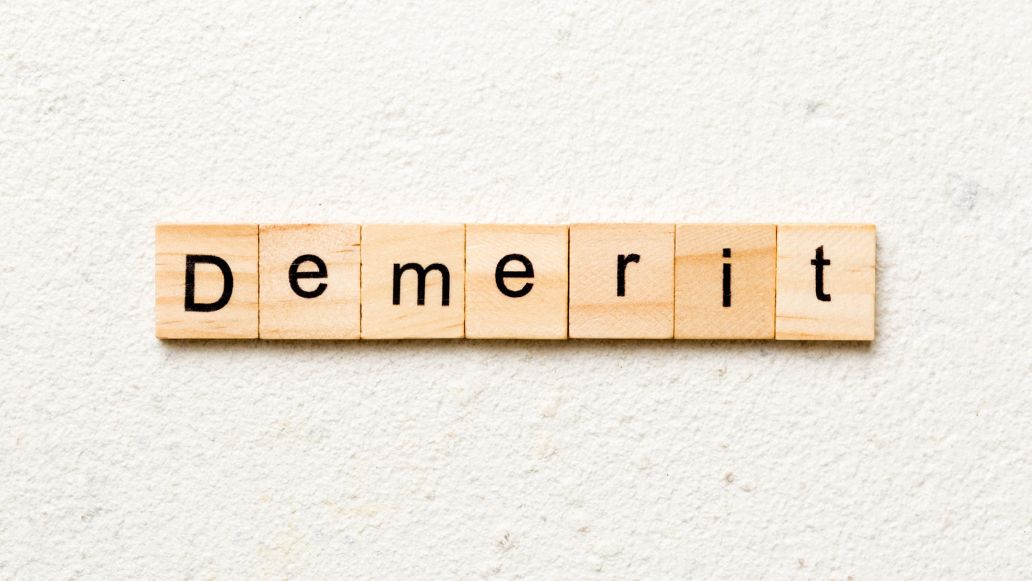
成果主義はメリットだけではありません。次のようなデメリットもあります。
- 公正に評価できない部署がある
- スタンドプレーが発生する可能性がある
- 外的要因のリスクがある
- 離職率が増加する可能性がある
4-1. 公正に評価できない部署がある
成果主義はすべての部署で公正に評価できるわけではありません。例えば数字で成果が分かる営業部であれば成果主義の導入は適しています。一方、数字で成果が判断できないような部署の場合、成果主義では公正に評価できない可能性があります。
4-2. スタンドプレーが発生する可能性がある
成果主義の場合、従業員によるスタンドプレーが発生しかねません。成果主義の場合、従業員は自分の成果ばかりを追求する可能性があります。その結果、他の従業員との協力を拒否するかもしれません。スタンドプレーが発生すると従業員同士のコミュニケーションが活発化しません。そのため、スタンドプレーを防ぐようなルールを作成しましょう。
4-3. 外的要因のリスクがある
成果主義は従業員ではなく、外的要因のリスクでも成績が低下する可能性があります。例えば、法律の改正や社会的な影響、取引先のミスなど、自社や従業員では対応しきれない外的要因で業績が低下しかねません。成果主義を導入するには外的要因のリスクに対応できるルールを作成しておきましょう。
4-4. 離職率が増加する可能性がある
離職率の増加も成果主義導入のデメリットです。例えば成果主義にも関わらず成果を残せなかった従業員はモチベーションが低下しかねません。成果が出なければ給与や役職も上がらないため、モチベーションが低下し続けて離職につながる可能性があります。
5. 成果主義を導入するときのポイント

成果主義は導入すれば必ず効果が出るというわけではありません。ポイントを押さえてより高い効果が期待できるようにする必要があります。
5-1. 社員に納得してもらう
成果主義を導入する際は、社員からの納得感を得ることが欠かせません。今まで評価されなかった人が評価されるようになる一方で、自分にとって不利な評価制度であると感じる方もいるでしょう。
とくに勤続年数の長い社員の立場からすると、年功序列で評価を受けたほうが都合がよいケースもあります。成果指標も部署によって異なるため、明確な基準を定めておかなくてはいけません。
曖昧な基準によって不当に評価されていると社員に思われないような工夫が必要です。評価結果に応じて、給料がどのように変化するかも明らかにしておきましょう。
5-2. 数値化が難しい業務の評価方法を定める
仕事にはさまざまな種類があり、そのすべてが数字で評価できるとは限りません。事務職やバックオフィス部門などは、数値化が難しい業務があります。しかし、その業務がなくてもよいというわけではありません。
そのため、何をもって成果とするのかはよく考えておく必要があります。具体的な評価基準について定めておかないと、社員はもちろん、管理する側も混乱する結果になってしまいます。
数値で判断できる業務だけを評価するのが成果主義ではありません。一部の方だけが有利になるような評価にならないようにすることが大切です。
5-3. 評価者の訓練
成果についての基準を定めたとしても、それを判断するのは評価者です。そのため、評価者の個人的な感情が入ってしまう可能性は否めません。理想としては、評価者が変わったとしても同じ基準での評価が受けられる状態です。
その状態にするために、評価者を訓練することは欠かせません。
6. 成果主義を導入するときの注意点

成果主義を導入する際には、注意しなければならないポイントがあります。実際に有名企業でもこれらのポイントがおろそかになった結果、成果主義の導入を失敗したというケースがあります。
6-1. 一部の業務のみに注力される
自分がどれだけ成果をあげたかが評価の基準になると、実力本位になりすぎてしまう可能性があります。
具体的には人材育成をおこなったとしても、評価をされずほかの仕事に注力したほうが評価されやすいだろうと社員が感じてしまい、一部の業務のみに注力されるなどです。
仕事の内容によって評価が変わるのは当然です。しかし、一部の業務だけに意識が向いてしまう状態は健全ではないため、会社のためになる取り組みであれば幅広く評価するという姿勢を見せることが大切です。
6-2. 目標設定が甘くなる
個人の目標を達成できているかどうかを評価の基準とした会社では、目標設定を甘くして高く評価してもらおうとする社員が増える可能性があります。目標を達成することは大切ですが、自分にとって適度に困難であり、達成することでスキルや実力アップが見込めるものでなければ効果が薄いです。
目標を達成しているかを評価の基準にするのは問題ありません。しかし、どのような目標を達成したのかという部分をより評価するようにしましょう。
7. 成果主義の導入で会社を次のステージへ
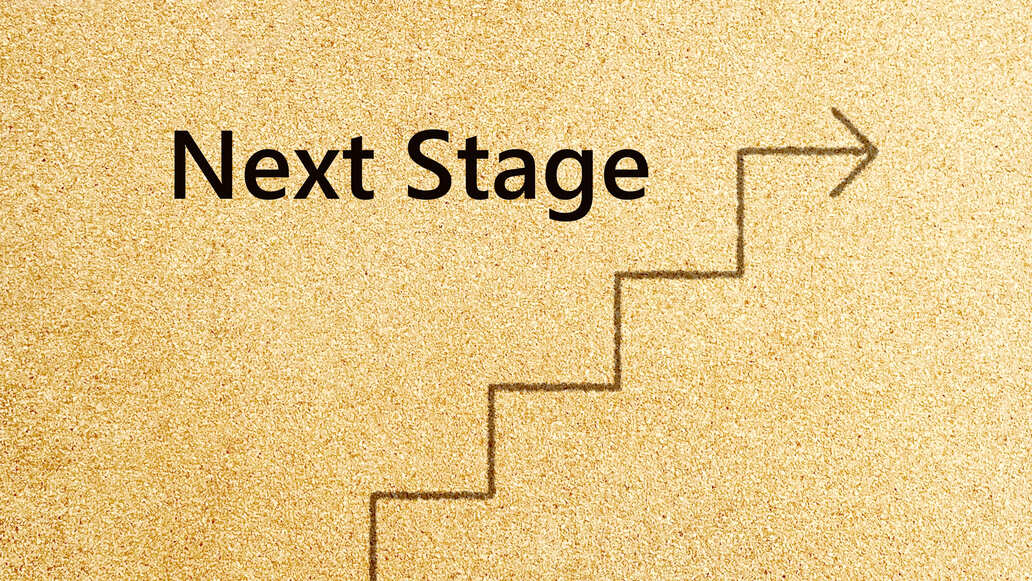
社員に目標を立てさせて、それに取り組ませることでレベルアップを図っている会社は多いでしょう。しかし、実際には思っているようにうまくいっていないケースもあります。
成果主義を導入することで社員の意識が変わり、会社がよりレベルアップできるかもしれません。ぜひ、成果主義の導入を検討してみてください。
人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08




























