成果主義のメリット・デメリットや浸透させるコツを徹底解説
更新日: 2024.4.3
公開日: 2023.4.6
OHSUGI

成果主義を導入する会社は増えつつあります。しかし、すべての会社が成果主義を導入して成功しているわけではなく、失敗して元の評価制度に戻したというケースも少なくありません。
成果主義をうまく活用するために、メリットに加えてデメリットを理解して自社に適した方法を見つけましょう。
人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
1. 成果主義のメリット

成果主義のメリットは数多くあります。会社が抱えている問題と、成果主義の導入によるメリットを照らし合わせて、実際に会社で採用するかどうかを検討してください。
1-1. 適正な報酬が支払われる
成果主義を導入すると、社員の給与の基準は「どれだけの成果を上げたか」に変化します。仕事に対する積極性がなく、活躍をしていない社員に多額の報酬が振り込まれたり、頑張って成果を上げている社員の給料が安かったりといったケースがなくなるのは大きなメリットでしょう。
一般的な企業は、年齢を重ねるごとに昇給していく年功序列型です。そのため、社員が高齢化すると人件費も増加してしまいます。しかし、成果報酬であれば、業績が悪いのに人件費だけが増加するということはありません。社員が成果を上げてくれれば、必然と業績がよくなり、高い報酬を支払うことができるでしょう。
1-2. 生産性が高まる
成果主義を導入すると、より効率よく仕事をこなしたほうが評価されるという認識が社員の中で一般的になります。その結果、労働時間や業務の無駄を自然と削減しようという意識が働くようになります。
会社にとって生産性を向上させることは欠かせません。いろいろな施策を導入している会社も多いです。しかし、成果主義を導入すれば、社員の業務に対する意識が変わり、自然と生産性の向上が期待できます。
1-3. 個人やチームのモチベーションが上がる
会社を退職する理由のひとつに仕事へのモチベーション低下があります。仕事がつまらない、面白くないと感じてしまい、会社をやめるという方は少なくありません。
成果主義を導入することで、社員それぞれを正しく評価することが可能になります。より評価されるために仕事を頑張ろうと思える社員も多くなるでしょう。
結果として、退職者が減少し、社内でどんどん社員が成長していくため、より組織としてのパワーが高くなります。
しかし、これは力がない社員に対してどうアプローチできるかで変わってきます。成果主義がプレッシャーになってしまい、退職を決意するという方も少なくありません。
そういった社員に対してどのようなアクションを起こすかで、メリットにもデメリットにもなり得るでしょう。
1-4. 社員の自主性が高くなる
資格取得のために休日を返上して勉強したり、セミナーに自発的に参加したりすることに抵抗感がある社員は少なくありません。その理由は、それらの行動をとったとしても自分に返ってくるメリットが少ないためです。
しかし、自己成長することでより多くの成果が上げられ、それが評価されるならば、積極的に取り組もうとする社員も多くなるでしょう。会社がアクションを起こさなくても、社員が自分で行動して成長してくれるのは大きなメリットです。
2. 成果主義のデメリット

成果主義には数多くのメリットがある一方で、デメリットもあります。導入する前にはデメリットについても理解しておき、不満を持つ社員が少しでも少なくなるように配慮しなくてはいけません。
2-1. 評価基準を設けるのが難しい
成果主義において欠かせないのが明確な評価基準です。評価基準がないと、人によって評価が異なってしまい、不公平さを感じさせる要因になります。
仕事の中には数字で測れないものもあります。たとえば「今月の営業成績」は数字で成果が表れるため、明確な基準を設けて評価することが可能でしょう。しかし「上司の命令でコピーを取った」「新入社員を現場まで送り迎えした」などは、数字で成果を判断することができません。
こういった業務に対しても、正当な評価をすることが必要です。そのため、どのような観点から評価基準を設けて、公平生が本当に保たれるかはよく考えなくてはいけません。
客観的に見ても納得ができるような評価方法にしておく必要があります。
2-2. チームワークが悪化する可能性がある
成果主義は個人的な成果を上げることに注力しやすくなる傾向にあります。結果として、チーム同士で顧客を奪い合ったり、ノウハウを秘匿したりといった行動につながる可能性もゼロではありません。
よきライバル関係になれるのならよい刺激になりますが、足の引っ張り合いが発生すると大きなデメリットになります。
社員が個人で努力をした場合でも、チームでの活動は欠かせません。そのため、数字だけを評価するのではなく、チームでの活動においてどのような成果を残したかも判断材料として取り入れることが大切です。
2-3. 人材が育たず離職者が増える恐れがある
成果主義は個人のメリットをより重視する傾向を生む可能性があります。これによって個人の評価には関係しない人材育成に力を入れない社員が増える可能性があります。
成果を上げることは大切ですが、会社としてはより優秀な社員が育つように働きかけていかなくてはいけません。人材育成にどれだけ力をそそいだかも評価の基準として設けることができれば疎かになることは少ないでしょう。
2-4. 残業時間が増えることがある
思ったような成果が得られない従業員は、成果主義の元ではなんとか成果を上げようと躍起になることがあります。残業時間を増やしてでも業績を伸ばそうとする人も発生するでしょう。
その結果全体的な残業時間が増えてしまい、人件費が増大する可能性があります。従業員個人の行動でコントロールが難しい部分ではありますが、残業を非推奨とする流れを作ったり、時間効率を上げる方向に従業員の意識が向くようにしたり、何らかの対策を考えなければいけません。
3. デメリットを減らす方法

成果主義にはメリットが多い反面、デメリットもあることがわかりました。デメリットを少しでも減らすには、導入時や評価者に対して以下の注意をすると効果的です。
3-1. 公正で納得感のある評価基準を設ける
従業員を評価する際にわかりやすいのがさまざまな数字です。顧客の獲得数や売上た金額など、いずれも数字になりわかりやすく評価がされます。
しかし、そうした数字のみを成果測定の基準にするのはよくありません。数字にならない成果、例えば仲間に対するサポートや協調性、業務の正確さなども評価できるようにすることが大切です。
数字に直接かかわらない従業員でも、そうした部分を評価されれば公正さや納得感を感じられます。その結果、個人プレーや必要以上の競争心が発生しにくくなり、チームワークの悪化や人材育成の軽視など、人間関係に関連するデメリットを減らすことが可能です。
3-2. 評価者のトレーニングをおこなう
成果主義のデメリットを減らすためには、評価者のトレーニングも欠かせません。
評価者が未熟である場合、多角的な見方ができなかったり、評価に感情が入ってしまったりする恐れがあります。そのような評価は不公平感を招きます。
また、評価者に十分なトレーニングがされていないと、評価をする目的を見失いやすく、正確な評価もできないでしょう。
加えて評価する行為が時間的や精神的な負担になることもあり、パフォーマンスの低下や離職につながる可能性もゼロではありません。評価される従業員だけでなく、評価者の負担も考えて適切な人選やトレーニングをおこないましょう。
4. 成果主義をうまく浸透させるコツ

成果主義のメリットだけを生かし、デメリットをなるべく少なくするためには、社内にしっかりと浸透させることが大切です。導入の仕方次第で成果主義の効果は大きく異なります。
4-1. 成果はひとりで得られないことを認識させる
社員には成果がひとりで得られないということを認識させましょう。成果主義の問題点に社員が個人での成果に注力しすぎるというものがありました。
しかし、厳密には個人での成果というものは存在せず、誰かの助けによって個人の仕事は成り立っています。自分だけで仕事をしているという考えを持ってしまうと、独りよがりな仕事ぶりになってしまうかもしれません。
会社に所属している人たちの支えによって、自分の仕事が成り立っていることを強く認識させましょう。
4-2. 心理的報酬を与える
力が発揮できない社員も一定数存在するでしょう。同期が数字という形で成果を上げているのに、自分は何もできていないと思ってしまうと、「自分には能力が足りない」や「自分には合わない」と判断して退職するという判断につながりかねません。
もちろん、力が及んでいないのは事実ですが、努力をしていないわけではありません。褒めるべき部分を見つけて、心理的報酬を与えるのも成果報酬には欠かせません。こういった対応によって、社員はより努力しようと行動できるようになります。
4-3. 評価者に対する不信感を少なくする
成果主義を導入すると、評価者が正しい評価をしていないと考える方が一定数出てきます。そのため、評価者は社員からの信頼が厚い存在にして、客観的に評価をおこなっていることを明確にしておきましょう。
個人面談の際には、どういった基準で評価しているのか具体的に説明できるとベストです。明確な理由があれば、不満を持つ社員も少なくなるでしょう。
5. 成果主義のデメリットを把握して導入は慎重に検討しよう
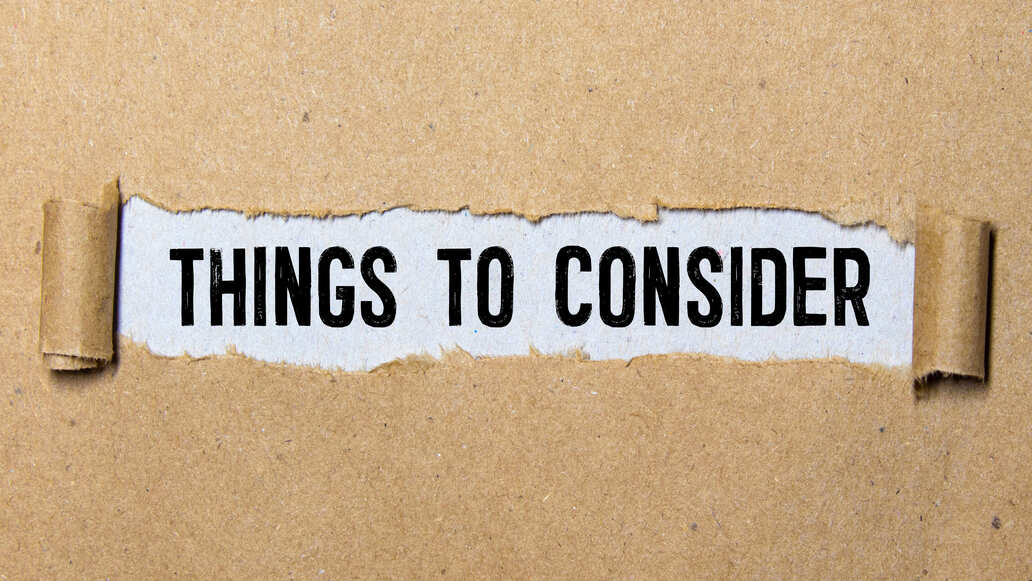
成果主義には数多くのメリットがあるため、導入したいと考える会社は多いでしょう。しかし、導入した結果、思うようにいかなければ、元の評価制度に戻すことも起こり得ます。そのため、現在の制度を撤廃して導入する必要があるのかはよく考えなくてはいけません。
とくに社員から納得を得られるか、不公平さを感じさせないような仕組みを作れるかという点には注意してください。
人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08




























