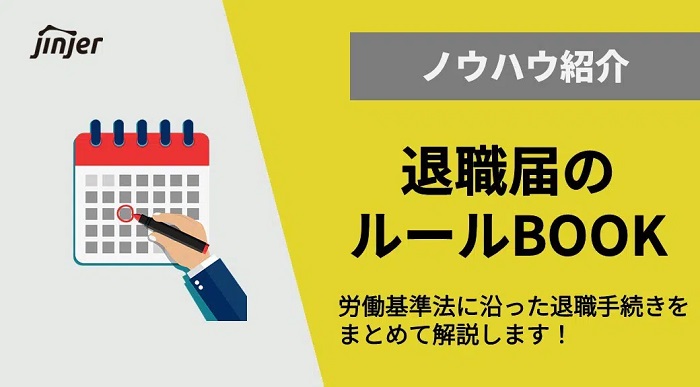退職手続きで会社側は何をする?手続き一覧と流れをくわしく解説

社員が退職届を提出してきた場合、会社側は雇用保険や社会保険の手続きをおこなわなければなりません。
提出期限が決められているものもあるため、退職手続きは正しく把握しておく必要があります。
本記事では、退職手続きに必要な会社側のするべき対応だけでなく、スムーズにおこなうポイントや注意点についても解説しています。
※労働基準法における退職の定義と手続き方法を分かりやすく解説した記事もあわせてご覧ください。
労働基準法では、従業員が退職を申し出て2週間が経過すれば、雇用契約が終了するとされていますが、これに基づき会社独自のルールを定める場合もあります。
そこで今回は、労働基準法に定められた退職のルールから退職届のフォーマット、退職に際してよくあるトラブルの対処法まで網羅的に解説しています。
「退職に関するルールを定めたい」「トラブルを防止したい」という方は、ぜひこちらからダウンロードしてご活用ください。
1. 退職手続きに必要な会社側の対応


社員の退職が決定したとき、会社側は迅速にいくつかの手続きをおこなう必要があります。
それぞれの手続き内容や対応すべきことについて詳しく解説します。
1-1. 雇用保険の手続き
雇用保険の手続きで必要な書類は2つです。
会社側は社員の退職後、10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」をハローワークへ提出します。
雇用保険被保険者離職証明書は退職者が失業給付金を受け取るために必要な書類であるため、転職先が決まっている場合や、本人から求めがないときは提出する必要はありません。
ただし退職者が59歳以上の場合は、本人からの希望がなくても必ず用意します。
10日以内に提出をしないと退職者に不利益が生じる可能性もあり、トラブルが起こる原因にもなりますので、必ず期間内に提出しましょう。
「雇用保険被保険者資格喪失届」のひな型は、以下よりダウンロードが可能です。
参考:雇用保険被保険者資格喪失届|ハローワークインターネットサービス
1-2. 社会保険の手続き
退職することで会社の社会保険から脱退することとなりますので、退職後5日以内に「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」を年金事務所に届け出ます。
扶養家族分がある場合は保険証をすべて回収して返却します。
厚生年金と健康保険は、退職日の翌日が資格喪失日となるため、末日が退職日の場合資格喪失日が月をまたいでしまいます。
保険料は資格を失った日の前月まで生じるため注意が必要です。
「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」のひな型は、以下よりダウンロードが可能です。
1-3. 住民税や所得税の手続き
住民税が給与から天引きされる「特別徴収」だった場合、退職すると「普通徴収」に切り替えるための手続きが必要です。
社員退職後の翌月10日までに、「給与支払い報告に係る給与所得異動届」を役所に提出しましょう。
納税額は、前年の1月1日から12月31日までの所得で決まり、普通徴収で支払う場合は毎年6月に自宅へ納税通知書が届きます。
所得税に関しては、退職日までに徴収した所得税が記載された源泉徴収票を退職日から1ヶ月以内に本人宛に送付します。
通常の源泉徴収に退職金は含まれないため、退職金が支給されている場合は「退職所得の源泉徴収票」を別で発行しなくてはいけません。
総務省が公開している「給与支払い報告に係る給与所得異動届」のひな型は、以下よりダウンロードが可能です。各自治体で展開されている場合もありますので、適宜ご確認ください。
1-4. 従業員から回収するもの
従業員は退職の際、会社から借りているものや支給されているものを返却しなければなりません。
そのため、会社側は業務データも含め退職者から必要なものを回収しましょう。
具体例を挙げておきます。
・健康保険証
・貸与物
・社員証
・名刺
・業務で使用していたデータや書類など
退職届は雇用保険の手続きの際に必要になる場合もありますので、必ず受け取っておきましょう。
2. 退職手続きで会社側が滞りなくおこなうポイント


従業員の退職に必要な手続きや提出書類は多々あるため、手作業でおこなっている場合、記入漏れやミスが起こる可能性があります。
そこで、退職手続きを滞りなくおこなうための方法やポイントについてご紹介します。
2-1. 労務管理システムを導入する
労務管理システムとは、入社・退職の手続きや勤怠管理、給与計算、社会保険の手続きなどを効率よくおこなうことのできるシステムです。
システム化することで書類の作成や申請作業の負荷の軽減が期待できるため、従業員の多い会社では広く導入されています。
労務管理システムでは、社会保険や雇用保険の資格喪失届、源泉徴収票の作成ができるため、退職手続きを従来よりも簡単におこなうことができます。
法律の改正に伴い変動する税率や保険料などにも対応しているため、非常に効率的です。
2-2. 電子申請を利用する
労務管理システムを導入しなくても、政府が提供する「e-Gov(イーガブ)」を利用すれば、退職手続きに関する書類を電子申請することが可能です。
退職手続きに関する書類作成から申請の一連の流れが全てWeb上でおこなえるため、生産性も上がるでしょう。
手作業で書類を作成すると、期間や金額の計算など複雑な部分が多く間違いやすいですが、電子申請なら入力データをチェックしながら作業ができるため、ミス防止対策にもつながります。
2-3. チェックリストを作成する
従業員の退職手続きは、作成する書類の種類や作業が多いことから、手続きの漏れが生じやすくなります。
滞りなく手続きを進めるためにも、事前に必要な書類や手続きを洗い出し、チェックリストを作成しておきましょう。
チェックリストは人事側だけでなく、社員側で提出が必要な書類や手続きについてもリスト化するのがおすすめです。
社員にもチェックリストを渡しておけば、双方でチェックしながら作業が進められるため、手続きの漏れを防ぐことができます。
3. 退職手続きで会社側が注意すべきこと


退職手続きはどの従業員も同じパターンで進められるとは限りません。
「こんな場合どうしたらいいのだろう」と悩むこともあるでしょう。
特に外国人が退職する場合や、退職者が財形貯蓄、社内融資を利用している時には注意が必要です。
3-1. 財形貯蓄制度を利用している場合
財形貯蓄制度とは、給与から決まった金額が天引きされる福利厚生のひとつで、毎月確実に貯蓄ができる制度のことです。
従業員は退職日以降この制度を利用することはできなくなるため、解約手続きをしなければなりません。
しかし、退職者が転職先で積み立てを継続する場合は、勤務先異動申告書の提出が必要ですので、その旨を説明する必要があります。
3-2. 従業員貸付制度を利用している場合
従業員貸付制度とは、会社からお金を借りることができる制度のことです。
退職者がこの制度を使っていた場合、退職に合わせて完済する決まりとなっています。
残りの返済金額や期間を確認した上で、退職者に伝えましょう。
3-3. 外国人従業員が退職する場合
外国人であっても退職時は基本的に日本人と同様の対応をおこないます。
しかし、退職の申し出の期間や就業規則などのルールについて理解していない可能性もありますので説明する必要があるでしょう。
雇用保険、社会保険、住民税など、手続き内容は同じですが外国人特有の手続きもあります。
2020年3月1日以降に採用した外国人が退職する場合は、「在留カード番号記載様式」をハローワークに提出します。
退職日の翌日から10日以内の提出が求められていますので忘れないようにしましょう。
日本人の場合、退職者から求められた場合のみ「退職証明書」を発行しますが、外国人は転職の際に入国管理局に提出しなければならないので、会社側は最初から交付しなければなりません。
3-4. 従業員から有給休暇の申請があった場合
退職前に従業員から「有給休暇を全て消化したい」と申し出があった場合、基本的に会社側は断ることができません。
業務上の都合により、退職希望者が退職日までに有給を取得できない場合は、例外として有給の買い取りが認められています。
しかし、有給の買い取りは「退職までに消化しきれない場合に限り認められている」というだけであり、必ずしも会社が買い取りに応じなければならないわけではありません。
就業規則で退職時の有給の買い取りや金額などを定めている場合に限り、規定に従って応じる必要があります。
3-5. 個人情報は3年間の保管が必要
個人情報の取り扱いについても注意しましょう。
労働基準法109条において、従業員の個人情報など重要な書類は5年間(当分の間は3年間)保管しなければならないと定めています。
保管期間を知らず退職後すぐに破棄したり、あるいは必要以上に長い期間保管していたということのないよう、各法律で決められた保管期間を把握しておきましょう。
4. 退職手続きは速やかにおこないましょう


従業員から退職届を受け取ったら、会社側は退職に関する各種手続きを迅速におこなうことが求められます。
手続きで必要な書類は種類も多いため、ミス防止のために労務管理システムを導入したり電子申請を利用した方が効率よく作業を進めることができるでしょう。
スムーズに対応するためにも、退職手続きの際の注意点についても理解しておくことが大切です。
労働基準法では、従業員が退職を申し出て2週間が経過すれば、雇用契約が終了するとされていますが、これに基づき会社独自のルールを定める場合もあります。
そこで今回は、労働基準法に定められた退職のルールから退職届のフォーマット、退職に際してよくあるトラブルの対処法まで網羅的に解説しています。
「退職に関するルールを定めたい」「トラブルを防止したい」という方は、ぜひこちらからダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16
労務管理の関連記事
-


【2024年最新】労務管理システムとは?自社に最も適した選び方や導入するメリットを解説!
人事・労務管理公開日:2024.08.22更新日:2024.08.22
-


【2024年4月】労働条件明示のルール改正の内容は?企業の対応や注意点を解説
人事・労務管理公開日:2023.10.27更新日:2024.10.18
-


社員の離職防止の施策とは?原因や成功事例を詳しく解説
人事・労務管理公開日:2023.10.27更新日:2024.09.03