SMARTの法則とは?目標の立て方や活用するメリットを解説
更新日: 2024.10.18 公開日: 2024.6.1 jinjer Blog 編集部

「SMARTの法則とは?」
「SMARTの法則を用いた目標の立て方は?」
「SMARTの法則は時代遅れと聞いたけどメリットは?」
上記のような疑問をお持ちではありませんか。
SMARTの法則の読み方は「スマートの法則」です。この法則は目標そのものと過程を明確化し、目標達成につなげる手法です。
今回は、SMARTの法則を用いた目標の立て方やメリット、活用時のポイントなどを紹介します。SMARTの法則を取り入れようと思っている人は、ぜひ参考にしてください。
目次

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
1. SMARTの法則を用いた目標の立て方

SMARTの法則を用いた目標の立て方は以下の通りです。
- Specific|具体的か
- Measurable|計量できるか
- Achievable|達成できるか
- Relevant:何に関連するか
- Time-bound|期限はいつか
そもそもSMARTの法則とは、上記5つの基準に則って目標を立てる手法のことです。それぞれの基準とともに、目標の立て方を詳しく解説します。
1-1. Specific|具体的か
SMARTの法則では、具体性を持った目標にすることが重要です。
抽象的な目標だと、目標を達成するための過程も曖昧になります。結果的に目標を達成できない恐れもあるので、まずは具体的な目標を立てましょう。
1-2. Measurable|計量できるか
計量可能性を持った目標にするのも、SMARTの法則のポイントです。
計量可能性がある目標なら、明確な数値目標をもとにした評価ができます。評価から最終目標を修正できるため、現実的な目標を立てやすくなるでしょう。
1-3. Achievable|達成できるか
SMARTの法則を活用する際は、イメージしている目標が達成可能かを考慮する必要もあります。
非現実的な目標だと、目標の達成が困難になるためです。内部リソースと外部リソースを評価し、現実的な目標かを確認しましょう。
1-4. Relevant|何に関連するか
SMARTの法則の法則では、関連性のある目標にすることも大切です。
具体的には、目標達成後に何があるか、なぜ目標を達成するかといった関連性をチェックします。関連性がハッキリすることで、モチベーションの維持と向上を実現できるでしょう。
1-5. Time-bound|期限はいつか
SMARTの法則で目標を立てる際は、期限を設けましょう。
期限を設けずに目標を達成しようとしても、過程でダラダラとしてしまいがちです。目標に期限を設けることで、効率的かつ無駄のない行動を実現できます。
2. SMARTの法則による目標設定の例

SMARTの法則による目標設定の例を以下の要素ごとに紹介します。
- 新卒採用や中途採用の目標設定
- 人材育成や人材開発の目標設定
- 人材配置や人事評価の目標設定
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1. 新卒採用や中途採用の目標設定
新卒採用や中途採用の目標設定の具体例として、「社員を増やす」にSMARを活用すると以下になります。
| Specific(具体性) | 3年以上の実務経験があり即戦力となる中途社員 |
| Measurable(計量性) | 20人 |
| Achievable(達成可能性) | 業界の市場拡大と流動性の高まりを踏まえると達成可能な範囲である |
| Relevant(関連性) | 事業規模に向けて新たに5つのチームを編成する計画に関連 |
| Time-bound(期限) | 再来年度まで |
| 最終的な目標 | 3年以上の実務経験があり即戦力となる中途社員を再来年度までに20人採用する |
ほかに、面接頻度や内定辞退者数、採用者の在籍期間などが指標になるケースもあります。
2-2. 人材育成や人材開発の目標設定
人材育成や人材開発の目標設定の例として、「新入社員に業務知識を習得させる」にSMARを活用すると以下になります。
| Specific(具体性) | 新入社員の業務基礎テストの内容 |
| Measurable(計量性) | 80点以上 |
| Achievable(達成可能性) | 研修日数や理解度チェックにより問題なく達成できる程度の点数である |
| Relevant(関連性) | 「新人研修終了後に社員が個別に設定した目標の達成度が70%以上となるようにする」の目標に関連 |
| Time-bound(期限) | 研修終了から3ヵ月以内 |
| 最終的な目標 | 新入社員が新人研修終了から3ヵ月以内に業務基礎テストで80点以上を取得できるようにする |
研修の参加率や資格取得数、TOEICのスコアなどが指標になるケースもあります。
2-3. 人材配置や人事評価の目標設定
人材配置や人事評価の目標設定の例として、「人事評価の満足度を上げる」にSMARを活用すると以下になります。
| Specific(具体性) | 社内で運用している人事評価の満足度のアンケート調査 |
| Measurable(計量性) | 10点満点中7点以上 |
| Achievable(達成可能性) | 評価フィードバックの機会を設けたので満足度が向上する見込みである |
| Relevant(関連性) | 「社員の生産性20%向上」の目標に関連 |
| Time-bound(期限) | 1年後に実施される人事評価後のアンケート調査 |
| 最終的な目標 | 1年後に実施される人事評価後のアンケート調査にて、人事評価の満足度が10点満点中7点以上となるようにする |
空きポジションの充足率や異動希望者数などが目標になるケースもあります。
3. SMARTの法則を活用するメリット

SMARTの法則を活用するメリットは以下の通りです。
- 明確な評価基準を設けられる
- 業務のモチベーションが向上する
- 将来のキャリアプランを意識できる
- 作業の効率化が期待できる
- チームワーク向上が期待できる
それぞれ詳しく解説します。
3-1. 明確な評価基準を設けられる
SMARTの法則で目標を立てると、明確な評価基準を設けられます。
企業を問わず、社員を公平に評価できる状態を作ることが人事評価において重要です。ハッキリとした目標設定により、部下が納得できる評価を上司がおこなえるようになるでしょう。
3-2. 業務のモチベーションが向上する
SMARTの法則で目標を立てれば、業務に対するモチベーションが向上します。
「何をするべきか」がハッキリとし、効率的な行動を実現できるためです。社員全体のモチベーションが高まることで、組織力の向上にもつながるでしょう。
3-3. 将来のキャリアプランを意識できる
SMARTの法則には、将来のキャリアプランを意識した働きを実現できる利点もあります。
SMARTの法則に則った目標設定の習慣化により、将来の明確なビジョンを考える力が備わるからです。目標の過程を詳細に計画することで、目標達成に向けて自主的な行動を起こせるようになります。
3-4. 作業の効率化が期待できる
SMARTの法則を活用することで作業の効率化が期待できます。SMARTの法則によって目標が明確になっていれば、どのように作業を進めていけばよいのか適切に配分可能です。また、目標達成のために必要なタスクも理解しやすくなるため、優先順位をつけやすくなります。
3-5. チームワーク向上が期待できる
SMARTの法則によってチームワーク向上も期待できるでしょう。SMARTの法則を活用すれば、何をどのようにすればいいのかチーム内で共有されています。そのため、チーム内で協力体制と一体感の高まりにつながります。チームワークが向上すれば、パフォーマンスの向上にもつながるでしょう。
4. SMARTの法則を活用する際のポイント
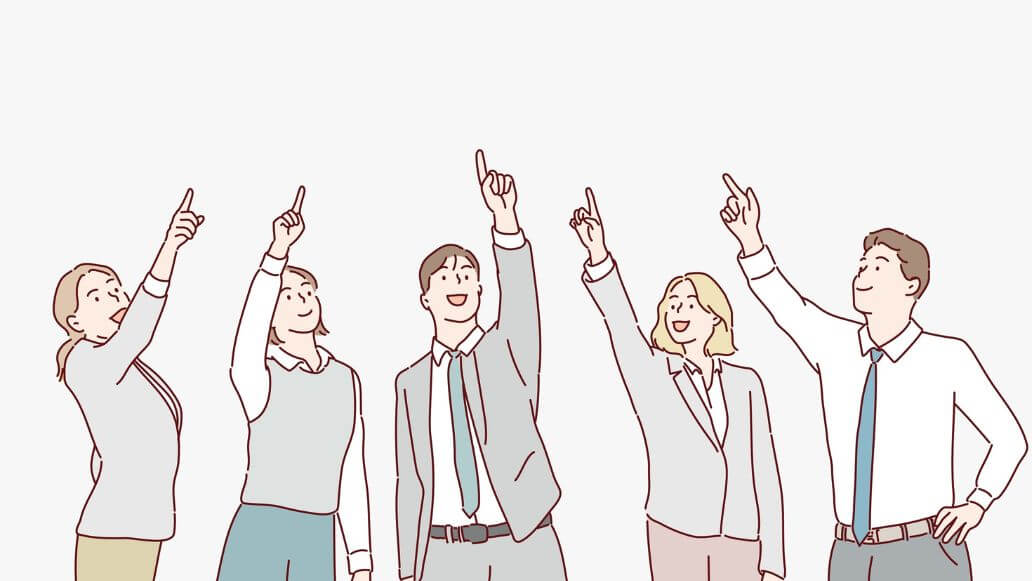
SMARTの法則を活用する際のポイントは以下の通りです。
- すべての基準を満たす目標を立てる必要はない
- SMARTの法則に則ったテンプレートを用意する
- 成果目標と行動目標を設定する
それぞれ詳しく解説します。
4-1. すべての基準を満たす目標を立てる必要はない
SMARTの法則で目標を立てる際は、すべての基準を満たす必要がない点に注意しましょう。
現在進行形で運用中の目標管理とSMARTの法則に相違が生じたときは、なぜ目標を達成したいのかを再確認します。再確認したあと、SMARTの法則の中で取り入れるべき基準を判断することがベストです。
4-2. SMARTの法則に則ったテンプレートを用意する
SMARTの法則に沿った目標設定をスムーズに実施するため、以下のようなテンプレートを用意しましょう。
| Specific(具体性) | 定義を具体的にする |
| Measurable(計量性) | 数字で表す |
| Achievable(達成可能性) | 達成可能であるかを示す |
| Relevant(関連性) | ほかの目標や計画との関連性を示す |
| Time-bound(期限) | いつまでに達成するかを示す |
| 最終的な目標 | 上記をまとめて一つの目標にする |
テンプレートを用意することで、SMARTの法則を1つずつ確認しながら目標を立てる手間が減ります。それぞれの目標を効率的に立てられるようになり、結果的に業務効率の向上につながるでしょう。
4-3. 成果目標と行動目標を設定する
SMARTの法則で目標を立てる際は、成果目標と行動目標を設定します。
成果目標とは、最終的に達成するべき目標です。「中途社員を20人採用する」などが例として挙げられます。
行動目標とは、成果目標を達成するための手段です。「中途社員を20人採用する」が成果評価なら「200人の採用面接をする」などのように設定します。
行動目標の達成は成果目標の達成につながるため、どちらか一方でも欠けてはいけません。必ず両方の目標を立てましょう。
5. SMARTの法則を発展させたフレームワーク

SMARTの法則を発展させたフレームワークとして以下が挙げられます。
- SMARTER
- SMARTTA
- SMARRT
5-1. SMARTER
SMARTの法則に「評価(Evaluate)」「承認(Re-evaluate)」を足したのがSMARTERです。評価と承認を加えることで、目標達成の途中であっても評価と調整が可能になります。部下が設定した目標が適切であるか、管理者が評価することで適切な人事評価が可能になるでしょう。
5-2. SMARTTA
SMARTTAはSMARTの法則に「追跡(Trackable)」と「納得(Agreed)」が追加されています。「追跡(Trackable)」と「納得(Agreed)」はそれぞれ次のような意味です。
- 追跡:目標に対する取り組みの経過を追えるかどうか
- 納得:チームメンバーが納得して取り組める目標かどうか
全員が納得できる目標を立てたうえに、進捗をチームで共有できれば団結力の向上が期待できるでしょう。
5-3. SMARRT
SMARTTAはSMARTの法則に「現実的(Realistic)」を追加した法則です。SMARTの法則にも「実現可能な(Achievable)」は存在しています。しかし、「現実的(Realistic)」は「実現可能な(Achievable)」よりも具体的かつ合理的な目標設定を促す要素です。
6. SMARTの法則を活用して目標の達成につなげよう

SMARTの法則は、5つの基準に則って目標を立てる手法です。目標そのものや達成までの過程が明確化され、目標を達成しやすくなります。
業務のモチベーションが向上したり、将来のビジョンを考える力が備わったりするのもメリットです。
達成したい目標がある人は、SMARTの法則を活用した目標設定を意識してみてください。

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
タレントマネジメントの関連記事
-

プレゼンティーイズムとは?原因と企業に与える損失額・対策をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2026.01.19更新日:2026.01.19
-



メンタルヘルスサーベイとは?ほかのサーベイとの違い、実施の目的や流れを解説!
人事・労務管理公開日:2026.01.16更新日:2026.01.14
-


企業におけるメンタルヘルスケアとは?4つのケアや事例を紹介
人事・労務管理公開日:2025.11.18更新日:2025.12.19



























