SMARTの法則は時代遅れ?具体例やFASTの法則との違いを解説
更新日: 2025.4.30 公開日: 2024.6.2 jinjer Blog 編集部

SMARTの法則は目標設定の際に用いられる有名なフレームワークです。しかし近年では時代遅れではないかと指摘され、FASTの法則といった別のフレームワークも提唱されています。
「SMARTの法則は本当に時代遅れなのか」「代わりになるフレームワークはあるのか知りたい」と考える人も多いでしょう。
本記事ではSMARTの法則が時代遅れとされている理由と、活用する際のポイント・具体例などを解説します。SMARTの代わりに提唱されているFASTの法則との違いについても解説するので、ぜひ目標設定の参考にしてください。
目次

人事評価制度は、従業員のモチベーションに直結するため、適切に設計・見直し・改善をおこなわなければ、最悪の場合、従業員の退職に繋がるリスクもあります。
しかし「改善したいが、いまの組織に合わせてどう変えるべきか悩んでいる」「前任者が設計した評価制度が古く、見直したいけど何から始めたらいいのかわからない」という方もいらっしゃるでしょう。
当サイトではそのような企業のご担当者に向けて「人事評価の手引き」を無料配布しています。
資料では、人事評価制度の基本となる種類の解説や、導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。自社の人事評価に課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. SMARTの法則は時代遅れではない

よく「SMARTの法則は時代遅れ」といわれることがありますが、決して時代遅れではありません。SMARTの法則は、普遍的な目標設定の手法として有効に活用できるためです。
そもそもSMARTの法則とは、目標設定の際に考慮すべき次の5つのポイントを指します。
| Specific(具体的) | 目標は具体的に定義されているか |
| Measurable(測定可能) | 目標は数値として測定可能か |
| Achievable(達成可能) | 目標は現実的で、達成可能か |
| Relevant(関連性) | 設定した目標と、目標を達成した先にあるゴールには関連性があるか |
| Timed(時間的制約) | 目標を達成する具体的な期限は設定されているか |
上記のポイントはビジネスやプライベートで幅広く活用可能であり、実際に現在でも多くの企業で取り入れられています。時代遅れではなく、現代においても十分に活用可能な法則といえるでしょう。
ただし、SMARTの法則が有効ではない・不十分な場面も確かに存在します。なぜ時代遅れといわれているのか、理由を踏まえて別の法則と使い分けることも重要でしょう。
2. SMARTの法則が時代遅れといわれる3つの理由
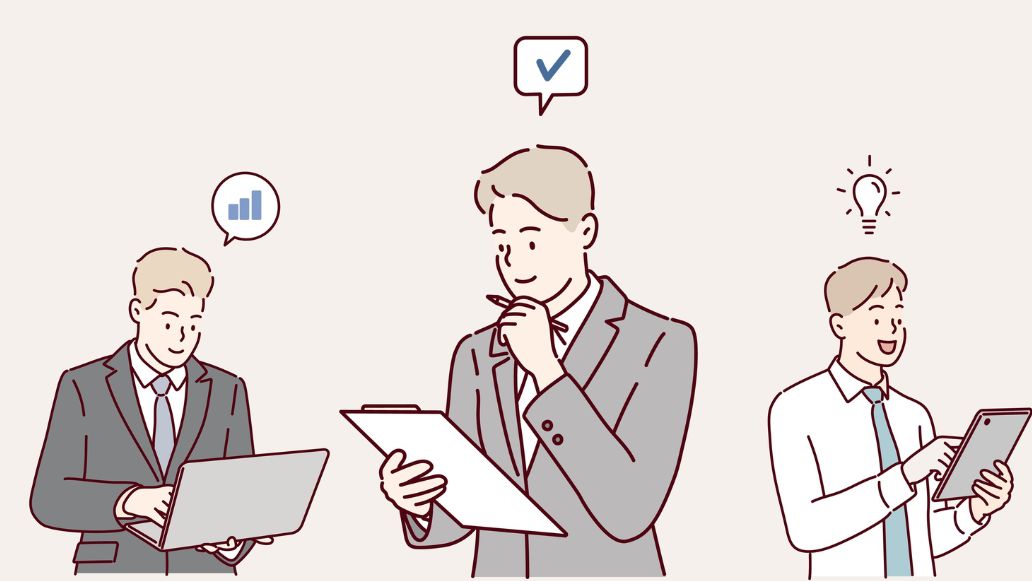
SMARTの法則が時代遅れといわれる理由は、次の3つです。
- 提唱されたのが40年前であるため
- 状況の激しい変化に対応しにくいため
- SMARTの法則の派生形が提唱されるようになったため
以下において、それぞれの理由を詳しく説明します。
2-1. 提唱されたのが40年前であるため
SMARTの法則が時代遅れといわれている理由として、提唱されたのが40年も前であることがあげられます。
SMARTの法則は、ジョージ・T・ドラン氏が1982年に発表した論文で提唱されました。発表された当時と比べると、40年間で社会情勢や科学技術は大きく変化しています。例えばIT技術の進歩により、人間の仕事をロボットが肩代わりするようになったことは特徴的な変化です。
結果として、「40年も前に提唱された法則が、現代でも通用するのか」と指摘されています。しかし企業経営には技術が進歩しても変わらない普遍的な部分もあるため、決して時代遅れとは言い切れないでしょう。
2-2. 状況の激しい変化に対応しにくいため
SMARTの法則は状況の激しい変化に対応しにくいことも、時代遅れといわれている理由の一つとされています。抽象的で測定が難しく、非現実的で期限設定のしにくいような目標は設定しにくいためです。
例えば新しい事業を立ち上げる際には、市場の変化や顧客のニーズの変化に応じて目標を設定しなくてはなりません。このように、目標を頻繁に修正しなくてはならない場合、SMARTの法則は不向きといえるでしょう。
SMARTの法則が扱いにくいと感じた場合は、別のフレームワークを検討する必要があります。以下に紹介するSMARTの法則から派生した法則や、FASTの法則を活用しましょう。
2-3. SMARTの法則の派生形が提唱されるようになったため
SMARTの法則が時代遅れといわれている理由として、次のような派生形が提唱されていることもあげられます。
派生形は、SMARTの法則にそれぞれ次の要素を付け加えたものです。
| SMARTERの法則 | Evaluated(他者から評価されているか)とRecognized(認識・承認されているか)を加えた法則 |
| SMARRTの法則 | Realistic(現実的な目標か)を加えた法則 |
| SMARTTAの法則 | Trackable(目標は追跡可能か)とAgreed(合意が取れているか)を加えた法則 |
上記の法則は、SMARTの法則では目標設定に不十分と感じる際に有効とされています。業界の特徴や仕事内容、組織としてどのような目標を目指すのかを考慮して、適した法則を活用しましょう。
3. SMARTの法則を用いて目標を立てる2つのメリット

SMARTの法則を用いて目標を立てることには、次の2つのメリットがあります。
- 従業員を評価するときの基準が明確になる
- 従業員のモチベーション向上につながる
以下において、それぞれのメリットについて詳しく解説します。
3-1. 従業員を評価するときの基準が明確になる
SMARTの法則を活用すると、従業員の評価基準が明確でわかりやすくなることが大きなメリットといえます。従業員を評価するうえで、公平で納得性のある目標は非常に重要な要素のためです。
人事担当者や上司が従業員の実績を評価する際は、評価をつけた理由を説明する必要があります。非現実的かつ抽象的な基準で評価をしても従業員は納得せず、企業への不信感にもつながるでしょう。
具体的かつ現実的で、測定可能な目標を設定すると、従業員に説明しやすくなります。従業員自身の業務が企業にどのように関連しているのかがわかると、企業に対する貢献感も育ちやすくなるでしょう。
3-2. 従業員のモチベーション向上につながる
従業員のモチベーション向上につながることも、SMARTの法則を使うメリットの一つといえます。具体的で測定可能な目標を立てると、実行に移すべきことが明確になるためです。
非現実的で抽象的な目標では、従業員も何をしたらいいのかがわからず、モチベーションが低下するでしょう。現実的な目標を設定すると、従業員は迷いなく業務に取り組めます。
また、目標を達成して成功体験を積み重ねると、仕事に対する自信を育むことにもつながるでしょう。
4. SMARTの法則を使った目標設定の具体例
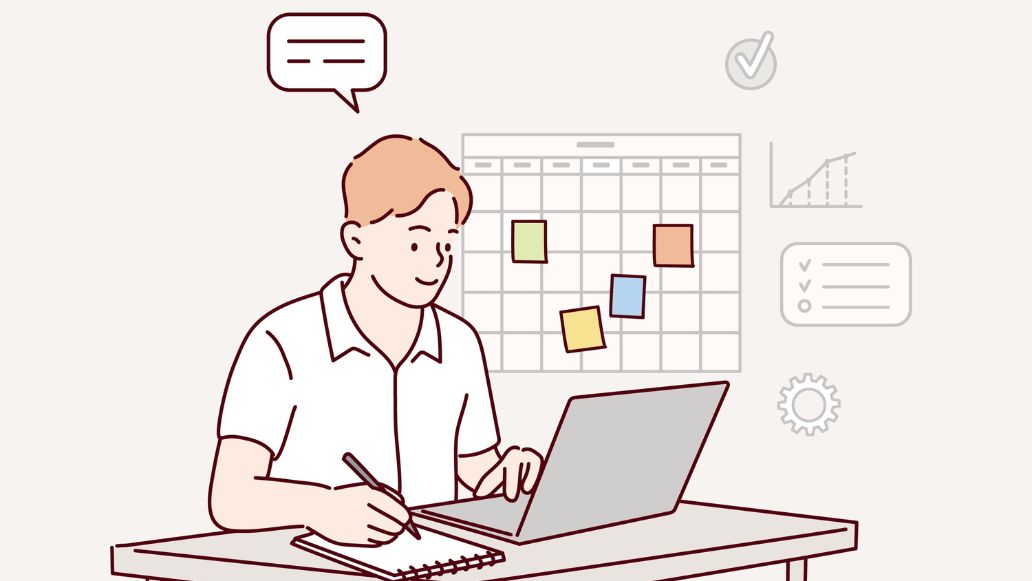
SMARTの法則を利用した目標設定として、次の3つの具体例を解説します。
- 労務担当者の具体例
- 人事担当者の具体例
- 総務担当者の具体例
それぞれについて良い例と悪い例の両方を紹介するので、ポイントをおさえて目標設定の参考にしてください。
4-1. 労務担当者の具体例
労務担当者の目標設定は、社内制度や福利厚生を改善し、働きやすい職場環境を整備することが最終的なゴールです。
具体的な目標としては、以下のような例があげられます。
| 良い例 | ・今年度の有給休暇の消化率を40%から60%にする
・6ヵ月間で開発部門の時間外労働を10%削減する |
| 悪い例 | ・有給休暇を取得するよう全社的に呼びかける(測定できない)
・みんながいきいきと働ける職場にする(抽象的すぎる) |
職場環境を改善する方法は多岐に渡るため、どの施策を実行することが最も実効的なのか見極めて目標を設定しましょう。
4-2. 人事担当者の具体例
人事担当者の目標設定は、人材を採用し育成することによって組織の生産性を向上させることがゴールになります。
具体例としては、以下の通りです。
| 良い例 | ・上半期の社内セミナーへの参加率を50%から75%にする
・3月~5月の新卒採用のエントリー数を前年度比10%増加させる |
| 悪い例 | ・新しい人事制度を提案し、改正する(抽象的すぎる)
・将来の会社を担うような優秀な人材を採用する(現実性がない) |
人事担当者は人材という不確定要素を扱う部門のため、目標を達成するための具体的なプロセスまで想定しておくことが重要でしょう。
4-3. 総務担当者の具体例
総務担当の目標設定は、経費を削減して業務を効率化することで、企業全体の利益率を向上させることがゴールです。
具体的には以下のような例があげられます。
| 良い例 | ・上期の消耗品の費用を20%削減する
・今期中に会議時間を全社的に10%短縮する |
| 悪い例 | ・事務処理における紙の使用枚数を前年度比10%にする(達成不可能・関連性が薄い)
・業務に必要の無いデータは随時消去するように呼びかける(具体性がない) |
総務部門の目標が行き過ぎると他部門から反感を買い、効率性を下げる可能性もあるでしょう。企業の現状を正しく認識して、現実的な目標を設定することを意識する必要があります。
5. SMARTの法則を使った目標設定の3つのポイント

SMARTの法則を活用するうえで、重視するポイントは次の3つです。
- 無理に5つの要素をすべて満たそうとしない
- 達成目標に加えて行動目標も設定する
- 目標と計画は定期的に見直して修正する
以下において、それぞれのポイントを詳しく説明します。
5-1. 無理に5つの要素をすべて満たそうとしない
目標設定する際、無理に5つすべての要素を満たす必要はありません。無理に当てはめようとすると違和感が生じ、達成しにくい目標になるためです。
SMARTの法則は、あくまでも効果的な目標を設定するための一つの指標にすぎません。目標を達成した先のゴールは何なのかを見極めて、どの要素を取り入れるのかを判断しましょう。
5-2. 達成目標に加えて行動目標も設定する
SMARTの法則を活用して目標設定をする際には、達成目標と行動目標を両方設定しましょう。目標を達成するための行動が伴わないと、現実離れした目標になるためです。
達成目標とは最終的に達成したいゴールであり、行動目標とはゴールに向かうために具体的に実行する目標を指します。人事担当者の例をあげると次の通りです。
| 達成目標 | 今年度の採用エントリー数を前年度比10%増加させる |
| 行動目標 | ・会社説明会の回数を◯回増やす
・新卒募集のSNS広告費を◯万円増やす |
上記のように、具体的な行動目標を設定すると、SMARTの法則をより効果的に活用できるでしょう。
5-3. 目標と計画は定期的に見直して修正する
目標を設定した後でも、目標と計画を定期的に見直し、修正を加えましょう。SMARTの法則は、状況の激しい変化に対応しにくいといわれているためです。
現代は、変化が激しく状況を見通すことが困難な「VUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)」の時代といわれています。長期的な目標を立てた場合でも、定期的に進捗状況を確認しましょう。
目標を見直す際にもSMARTの法則を活用し、現実的で測定可能、達成可能な目標を立てることが重要です。
6. SMARTの法則の代わりになるFASTの法則とは

FASTの法則とは、SMARTの法則の代わりになるとされている目標設定のためのフレームワークです。具体的にFASTの法則においては、次の4つの原則を考慮するべきとされています。
| Frequent(頻繁) | 目標は頻繁に議論される必要がある |
| Ambitious(野心的) | 目標は不可能でない範囲で野心的な目標である |
| Specific(具体的) | 目標は具体的か |
| Tranparent(透明性) | 組織の全員から見られる程度の透明性があるか |
FASTの法則はSMARTの法則が時代遅れといわれているなか、Donald Sull氏とCharles Sull氏によって2018年に提唱されました。現代の状況に即した目標設定の基準といえるでしょう。
参照:With Goals, FAST Beats SMART|MIT Sloan
7. SMARTの法則とFASTの法則の違い

FASTの法則とSMARTの法則の違いは、FASTの法則が野心的に目標設定をおこなう点にあります。野心的な目標によって従業員のモチベーション・パフォーマンスを発揮させるためです。
SMARTの法則には、Achievable(達成可能か)という基準があります。しかし、達成できるかどうかにとらわれて低い目標を設定しては、従業員の成長につながりません。
FASTの法則で不可能ではない範囲で野心的な目標を立てることで、従業員のモチベーション・生産性の向上につながるでしょう。
一方で、あまりにも高い目標を立てると目標が形骸化する可能性もあります。FASTの法則を活用する場合には、組織全体で合意したうえで目標を立て、定期的に目標を確認して見直す必要があるでしょう。
8. SMARTの法則が時代遅れといわれる理由を踏まえて最適化しよう

本記事では、SMARTの法則が時代遅れといわれる理由と、活用するうえでのポイントや具体例、代わりとなる法則を紹介しました。
SMARTの法則は目標設定をするうえでの普遍的な原則であり、決して時代遅れではありません。時代遅れといわれている理由は、提唱されたのが40年前であり、激しい状況の変化に対応しにくく、派生系がいくつも提案されているためです。
SMARTの法則を活用する際には無理にすべての要素を満たそうとせず、達成目標に加えて行動目標を設定する必要があります。代わりに提唱されているFASTの法則の活用も検討し、最適な目標を設定しましょう。

人事評価制度は、従業員のモチベーションに直結するため、適切に設計・見直し・改善をおこなわなければ、最悪の場合、従業員の退職に繋がるリスクもあります。
しかし「改善したいが、いまの組織に合わせてどう変えるべきか悩んでいる」「前任者が設計した評価制度が古く、見直したいけど何から始めたらいいのかわからない」という方もいらっしゃるでしょう。
当サイトではそのような企業のご担当者に向けて「人事評価の手引き」を無料配布しています。
資料では、人事評価制度の基本となる種類の解説や、導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。自社の人事評価に課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
タレントマネジメントの関連記事
-

プレゼンティーイズムとは?原因と企業に与える損失額・対策をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2026.01.19更新日:2026.01.19
-



メンタルヘルスサーベイとは?ほかのサーベイとの違い、実施の目的や流れを解説!
人事・労務管理公開日:2026.01.16更新日:2026.01.14
-


企業におけるメンタルヘルスケアとは?4つのケアや事例を紹介
人事・労務管理公開日:2025.11.18更新日:2025.12.19



























