従業員サーベイとは?目的や実施するときの注意点を紹介
更新日: 2024.7.5
公開日: 2022.11.14
OHSUGI

従業員サーベイとは、従業員が職場環境や仕事内容、待遇などに満足しているかを調べ、人事制度や就業規則の改定など人事施策に活かすための調査です。
従業員は、会社に対して隠れた不満を持っている場合があります。この不満を把握していないと、優秀な人材が離職したり生産性が下がったりするリスクが高まります。
離職を事前に防ぐためにも、生産性をアップさせるためにも、従業員の本音を知るサーベイの実施は欠かせません。
本記事では、従業員サーベイの目的やメリット・デメリット、実施の流れや注意点を解説していきます。
従業員の定着率の低さなどが課題の企業の場合、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
従業員満足度を向上させることで、従業員の定着率向上や働くモチベーションを上げることにもつながります。
しかし、従業員満足度をどのように測定すれば良いのか、従業員満足度を知った後どのような活用をすべきなのかわからないという人事担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは、「従業員満足度のハンドブック」を無料でお配りしています。
従業員満足度調査の方法や調査ツール、調査結果の活用方法まで解説しているので、従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方はこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 従業員サーベイとは?


従業員サーベイとは人事制度や就業規則を改定する際に、実施されるサーベイの1つです。
人事制度や就業規則は、改定するべき事項がないとおこなわれません。例えば「現在の人事制度では不公平が生じている」「この就業規則はわかりづらい」など、改善するべき事項が明確になっていなければ改定はおこなわれないのが一般的です。
しかし、そのためには、現在の人事制度では不公平が生じているのかを確認しなければなりません。現在の人事制度に不公平があることを仮説として立てた課題とするならば、本当にその認識が正しいのかを検証する必要があるのです。
その際に利用されるのが、従業員サーベイです。事実情報を集めることで、客観的に課題を検討することができるようになります。
ちなみに、人事部が主体となっておこなう調査の総称を従業員サーベイと呼ぶこともあり、会社によって従業員サーベイの意味は異なるので注意してください。
2. 従業員サーベイは無意味?
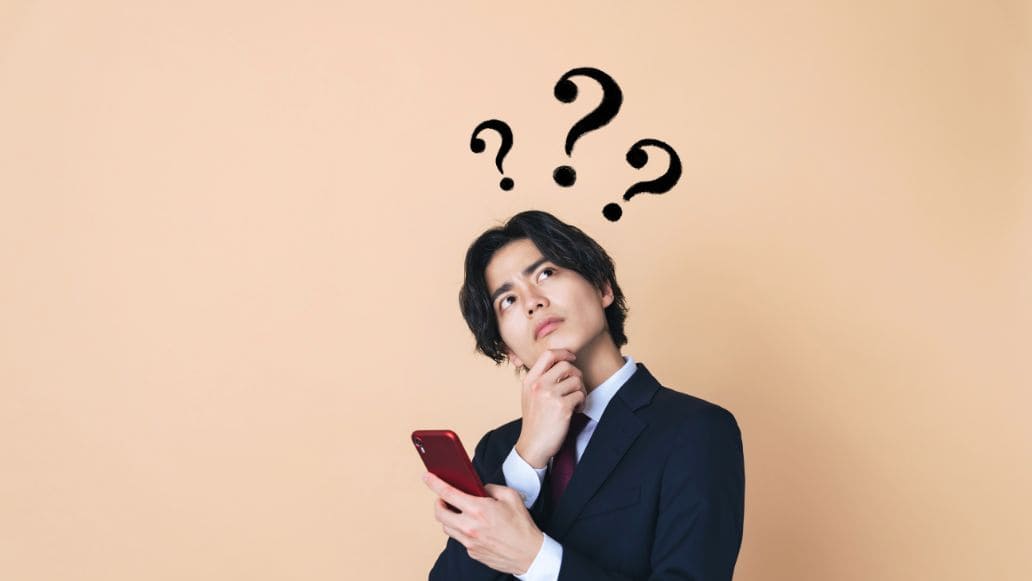
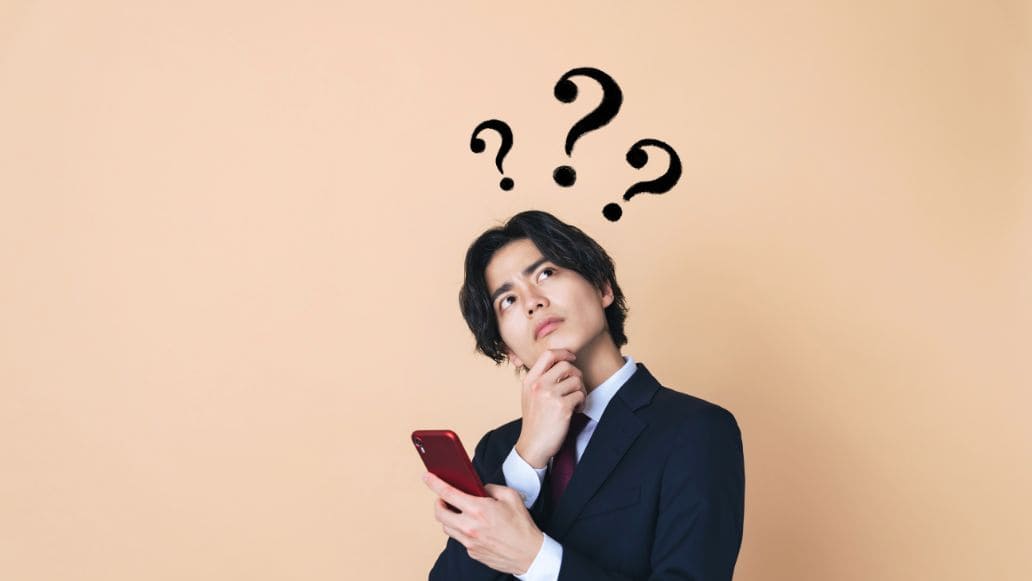
従業員サーベイは無意味、やっても無駄と思っている企業もあるようですが、そのように考えるのは調査結果を活かしていないことが原因です。
この調査は、結果を分析して課題を把握し、改善していくことで初めて効果が得られます。調査を実施して結果をまとめて終り、という状態では、当然ですが改革に活用できていないので「無意味」と感じてしまうでしょう。
しかし、従業員サーベイをせず、従業員の本音を聞かないままでは、待遇や福利厚生が適切なのか、働く意欲を感じられる業務なのかがまったくわからない状態です。
これを放置すると、従業員のやる気が低下し生産性が落ちてしまうので、従業員サーベイは無意味ではなく必ずやるべき調査なのです。
3. 従業員サーベイの目的


従業員サーベイの一番の目的は、人事や管理職が立てた仮説を検証することですが、他にも下記のような目的があります。
- 会社と従業員との間のずれを知る
- 従業員のリアルな声を聞く
- 人事戦略に活用する
ここでは、それぞれのの目的について解説していきます。
3-1. 会社と従業員との間のずれを知る
従業員サーベイをおこなうことで、今まで見えていなかった会社と従業員との間のずれが明らかになります。
例えば、会社側が「従業員が喜ぶだろう」と思って、福利厚生の一貫に社員旅行を設けていたとしましょう。しかし、従業員の大半は社員旅行に乗り気ではなく、仕方なく参加しているといった状態だったとします。
会社側が従業員に対して社員旅行について尋ねてみても、正直に行きたくありませんと答える人はいないでしょう。なぜなら、従業員は会社に悪い意味で目をつけられたくないからです。自分の本当の気持ちを押し殺してでも、社員旅行は楽しみですと答える人が多いと思います。
ここで従業員サーベイを実施すると、従業員が本当はどのように思っているのかを知ることができます。従業員が社員旅行を面倒だ、不必要だと思っているのであれば、会社として実施する必要はありません。むしろ、社員旅行にかかっていた費用を別のところに回すことで、よりよい福利厚生を導入できるでしょう。
このように、会社の考えと従業員との間でずれが生じることはよくあります。そのずれを知るために従業員サーベイは活用できるのです。
3-2. 従業員のリアルな声を聞く
従業員のリアルな声を聞くことも、従業員サーベイの目的です。
例えば、従業員の中に正当な評価を受けていないと思っている人がいたとしましょう。自分は頑張って仕事をしているのに評価されない、そういった気持ちを抱いてしまうと離職に繋がります。
そう感じてしまう理由の1つが、人事評価制度の理解が得られていないことです。一般職と管理職では、人事評価制度の理解に差がある場合があります。そのため、正当な評価をしていたとしても、従業員が不満を抱いてしまう可能性があるのです。
しかし、その不満を表現できる従業員は少ないのが実情です。
自分の意見をしっかりと伝えられる従業員ばかりであれば、問題があったとしてもすぐに発覚するのですが、そういった人たちばかりが働いているわけではありません。納得のいかない気持ちを抱えたまま、業務に取り組んでいる人もいます。
ずっと不満を持ちながら仕事をしていると、当然ですが離職を考えるようになるかもしれません。
従業員サーベイを実施すれば、従業員が何を思っているか、何を不満に感じているか、リアルな声を聞けるので、離職を早期に防ぐことができます。
3-3. 人事戦略に活用する
従業員サーベイは人事戦略に活用してこそ意味があります。従業員サーベイを実施して、課題が明確になったとしても、そのままにしておいては意味がありません。
従業員サーベイは実施が目的ではなく、人事戦略に活かしてこそ初めて意味を持つのです。
従業員サーベイを実施している会社は増えつつありますが、それをうまく活用できていない会社もあります。
従業員サーベイを実施した時点で従業員の不満を解消したと思ってしまい、実際には何も変わっていないというケースもあるので注意しなくてはいけません。
これらが従業員サーベイを実施する目的です。従業員のことを深く知り、よりよい会社を作っていくために従業員サーベイは存在しています。従業員の気持ちを理解しているつもりでも、実は不満を抱いているかもしれません。従業員サーベイを実施して、客観的に従業員のことを分析してみてください。
とはいっても、具体的にどのように活用すればよいのかわからないといったお悩みをお持ちの人事担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトでは、そのような方に向けて、従業員サーベイを活用する方法を例を用いて解説した資料を無料でお配りしています。
調査結果の運用方法を検討している方は、こちらから「従業員満足度のハンドブック」をダウンロードして参考にしてみてください。
4. 従業員サーベイの種類


従業員サーベイにはいろいろな種類がありますが、主に下記の4つが挙げられます。
- エンゲージメントサーベイ
- モラールサーベイ
- パルスサーベイ
- 組織サーベイ
ここでは、これらのサーベイについて解説していきます。
4-1. エンゲージメントサーベイ
エンゲージメントサーベイは、従業員の会社への愛着心や仕事への熱量などエンゲージメントを測る調査です。
サーベイの種類の中では、もっともダイレクトに従業員の本音を把握できる調査なので、採用している企業も多いようです。
「やりがいを持って働けているか」「上司との関係はうまくいっているか」などの質問項目でアンケートを実施し、会社に対する意見や感情を集め、その結果から課題を可視化することを目的としています。
この調査では、従業員と会社側の意識の違いも把握できるので、より適切な改革をおこなえます。
4-2. モラールサーベイ
モラールサーベイは、勤労意欲調査や意見調査で、主に従業員満足度を上げる目的で実施されます。
面接もしくは質問シート形式により、労働環境や仕事内容、同僚や上司、待遇に対してどのような感情や認識を持っているのかを調べます。
基本的には、詳細な質問項目を設定し「はい」「いいえ」で答えてもらいますが、面接の場合は自由に意見が述べられる環境を整えることが重要です。
4-3. パルスサーベイ
パルスサーベイも他の調査と同じように、仕事や人間関係に関する意見調査をおこないますが、1つ大きな違いがあります。
それは、調査をおこなう期間です。
モラールサーベイやエンゲージメントサーベイも定期的に実施しますが、一般的に6ヵ月以上のスパンを空けておこなわれます。しかし、パルスサーベイは毎日や週に1回、月に1回など短期間でおこなうため、従業員の意識変化や改善策による効果などがわかりやすいというのが特徴です。
短期間でおこなう代わりに、数分で答えられる簡単な質問しかしませんが、それでも従業員には負担となる点には注意が必要です。
4-4. 組織サーベイ
組織サーベイとは、組織の状態を可視化するための調査です。
組織内では、企業側からしてわかりやすい(見えやすい)状況とわかりづらい(見えにくい)状況があります。わかりづらい状況の中でトラブルが起こると、従業員のモチベーションの低下や社内環境の悪化などにつながるので、見えない部分を調査によって明らかにしていきます。
職場環境や上司・同僚とのコミュニケーション、企業理念の理解などについて従業員の意見を集め、結果分析をして課題を見つけるというのが目的です。
5. 従業員サーベイのメリット


従業員サーベイのメリットは、社内の課題を的確に見極められることです。
会社側がどんなに「従業員のために」と思ってシステムや福利厚生を導入しても、従業員のニーズにあってなければ意味がありません。また、「社内の人間関係は上手くいっている」「適材適所の人員配置ができている」と思っていても、実際のところはパワハラやモラハラが起こっているかもしれず、それを認知できていないことになります。
課題が的確に見極められなければ、従業員に不満が溜まり、人材流出や生産性の低下などが起こります。
従業員サーベイをおこなえば、従業員の真のニーズを把握できるので、人材確保や業績アップなどにつながるというのが一番のメリットといえるでしょう。
6. 従業員サーベイのデメリット
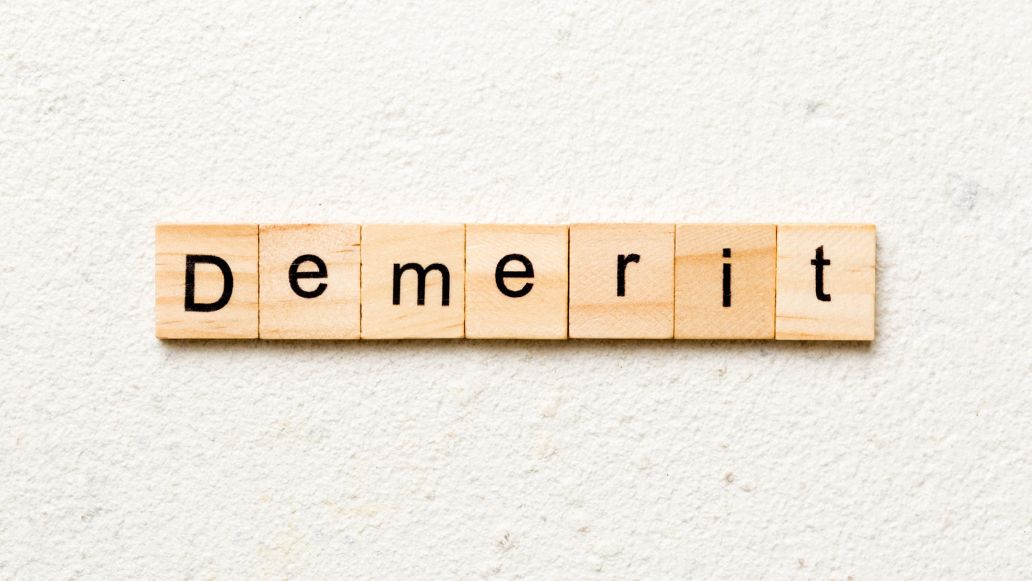
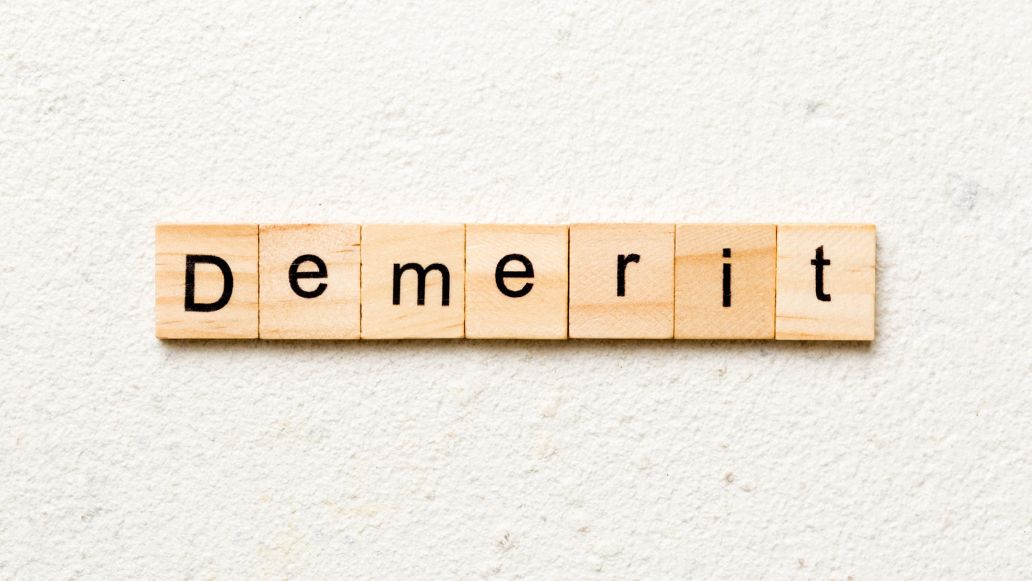
調査は仕事中におこなうため、従業員の業務を中断させてしまいます。そのせいで残業が増えたりすると、従業員のためにおこなっていることでも負担となります。
また、サーベイの結果が非公開だったり、どのような改革がおこなわれるのかを周知しなかったりすると、従業員の信頼も失ってしまう恐れがあります。
このようなことにならないためにも、質問項目は厳選して短時間で回答できるようにする、サーベイの活用方法を明確にするなど、従業員が不満を持たない実施方法をしっかり考えることが重要です。
7. 従業員サーベイの流れ


- 従業員への質問項目を設定する
- 従業員アンケートの実施
- アンケート結果の分析
ここでは、これらの流れについて解説していきます。
7-1. 従業員への質問項目を設定する
従業員サーベイは、従業員にアンケートをおこなうので、まずは質問項目を設定しましょう。
質問項目は、調査をおこなう目的にあった内容にしてください。従業員が現状の待遇に満足しているかを調査したいのか、業務へのモチベーションがどれぐらいあるのかなど、知りたい内容を絞り込み、求める回答が得られるように質問を設定しましょう。
サーベイのフォーマットを使ってもいいのですが、目的にあっていないと課題を正確に把握出来ない可能性があるので注意してください。
サーベイの失敗を回避するには、テストサーベイをおこなうのがベストです。テストは、担当部署や管理職でおこなってもいいのですが、専門機関を利用すれば質問を精査できるので濃い内容の項目を設定できます。
質問項目を設定したら、従業員に調査を実施する旨と目的を周知し、負担のないスケジュールを組みましょう。
7-2. 従業員アンケートの実施
実施スケジュールを決めたら、実際に従業員アンケートを実施します。
アンケートは、基本的に無記名でおこないます。記名式にしてしまうと、「人事評価に響くかもしれない」「上司に嫌がらせをされるかもしれない」と不安になってしまう従業員が多いようです。
本音で回答してもらえなければ、調査結果を分析しても、的確な課題から逸れてしまうことになります。
これではサーベイの意味がなくなってしまうので、どの従業員も平等に扱えるように無記名でおこなうようにしましょう。ただし、部署名がないと分析ができないので、部署名は必ず記入、本人が特定できないようであれば担当業務も記入してもらうのがベストです。
7-3. アンケート結果の分析
回答が集まったら、アンケート結果の分析をおこないます。
結果をもとに、従業員が不満に思っているのはどんなことなのか、不満の原因は何なのか、どのような施策をおこなえば改善できるのかを1つずつクリアにしていきます。
ここで重要なのは、回答結果を多角的な視点で考えることです。
例えば、「業務がスムーズに進まない」という回答があった場合、一昔前であれば「本人の努力が足りない」と一蹴してしまうところですが、「システムを導入すれば良いのか」「業務を割り振った方がよいのか」「本人のスキルアップをサポートすればいいのか」などあらゆる視点で改善策を考えましょう。
8. 従業員サーベイを実施するときの注意点


従業員サーベイを実施する際には、注意するべきポイントが3つあります。
- 経営メンバーに連絡をしておく
- 従業員に協力を仰ぐ
- サーベイの乱立を防ぐ
実施をする前に、これらの注意点を理解しておきましょう。
8-1. 経営メンバーに連絡をしておく
従業員サーベイは実施が目的ではなく、結果を踏まえたうえで経営戦略や人事戦略を改善していくことが目的です。
つまり、経営メンバーの合意を得ないまま従業員サーベイをおこなってしまうと、その後の戦略に活かしづらくなってしまう可能性があるので注意してください。
従業員サーベイ実施後の取り組みが円滑に進むように、あらかじめ経営メンバーには連絡をしておき、合意を得るようにしておきましょう。
8-2. 従業員に協力を仰ぐ
従業員サーベイは、従業員の労働時間内で実施するため、実施が決まったことを周知するだけでなく「協力してもらう」という姿勢が大切です。
また、「従業員サーベイの結果が評価に影響しない」こともあわせて伝えましょう。会社にとってマイナスな意見を伝えてしまうと、今後の評価に影響が出るのではと不安に感じる従業員は多いです。
従業員の不安を取り除いておかないと、正直な回答を得られず、従業員サーベイの意味が薄れてしまいます。
従業員サーベイの実施目的を説明し、不安点を払拭したうえで実施するようにしてください。また、従業員サーベイのタイミングは、なるべく従業員にかかる負担が少ないときにおこなうなどの工夫をしましょう。
8-3. サーベイの乱立を防ぐ
従業員サーベイ以外にも、サーベイにはいろんな種類があります。
インターネットを使ったサーベイツールも増えてきており、簡単にアンケート調査ができるようになりました。その結果、アンケートが乱立してしまうという問題が起こる可能性があります。
アンケートの数があまりにも多いと、従業員の業務に支障をきたす可能性があります。また、結果を集計・分析する担当者の業務負担も増えるので、結果を活かせるサーベイを厳選しておこなうことが重要です。
大企業であればあるほどこういった問題が起こる傾向にあるので注意してください。
9. 従業員サーベイを理解して大切な財産を守ろう


従業員サーベイは、社内の風通しをよくするために欠かせません。
会社にとって従業員は何よりの財産なので、職場環境や人間関係、仕事内容に不満がないかを把握することはとても大切なことです。また、モチベーションや満足度を高めるためにも従業員サーベイは必要不可欠です。
従業員の不満を把握して解消できれば、離職率を下げるだけでなく生産性の向上にも繋がります。
会社の規模を大きくするうえでも従業員サーベイは役立つので、このツールを活用してよりよい職場環境を構築していきましょう。
従業員の定着率の低さなどが課題の企業の場合、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
従業員満足度を向上させることで、従業員の定着率向上や働くモチベーションを上げることにもつながります。
しかし、従業員満足度をどのように測定すれば良いのか、従業員満足度を知った後どのような活用をすべきなのかわからないという人事担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは、「従業員満足度のハンドブック」を無料でお配りしています。
従業員満足度調査の方法や調査ツール、調査結果の活用方法まで解説しているので、従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方はこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08























