源泉徴収票とは?正しい見方やいつどこで発行できるのかわかりやすく解説
更新日: 2024.10.22
公開日: 2022.8.24
OHSUGI

「源泉徴収票」は重要な書類で、正しい見方や計算方法を十分に把握しておかなくてはなりません。作成するときはもちろんですが、従業員から質問があった場合も答えられるように理解を深めておきましょう。
本記事では、源泉徴収票とはどのような書類なのか、いつ発行するのかなど詳しく説明します。
目次
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」
「令和6年の年末調整における定額減税への対応方法が知りたい」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 源泉徴収票とは?

源泉徴収票は毎年会社が作成する書類の一つで、通常は年末調整のあとに発行します。まずは源泉徴収票がどのような内容の書類なのか、源泉徴収票の概要についておさらいしておきましょう。
1-1. 給与額や所得税額が記載された重要書類
源泉徴収票とは、1年間に会社から支払われた給与等の金額や、自分が納付した所得税額などが記載された書類です。
企業に勤めている場合には、所得税を納付は自分自身では納付せずに、給与から算出された金額を会社が天引きという形で代わりに納付しています。
この天引きされていることを「源泉徴収」といい、源泉徴収票では自分が1年間に支払を受けた給与等に対して、所得税がいくら課税されたのかを確認できます。また、その所得税の計算の基礎となった情報も源泉徴収票で確認できます。
なお、会社が従業員に対して発行する源泉徴収票には、「給与所得の源泉徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」の2種類があります。
1-2. 源泉徴収票の対象期間
源泉徴収の対象期間は、その年の1月から12月までの12ヵ月間です。
対象期間中に従業員が受け取った給与に関して年末調整をおこない、その結果を源泉徴収票に記載しますが、会社によっては12月分の給与が翌月に振り込まれる場合もあります。
その場合、1月に振り込まれた給与は原則として翌年の源泉徴収の対象になります。
そもそも源泉徴収制度は、毎月の給与支払い時に所定の方法によって所得税額を計算し、給与から天引きして国に納付する仕組みです。しかし、収入の変動や扶養親族の異動などによって、納税者が本来支払うべき金額よりも所得税を多くもしくは少なく納付してしまうこともあります。年末調整は、このような不一致を調整するためにおこなわれています。
2. 源泉徴収票の正しい見方

源泉徴収票の見方で特に頭を悩ませるのが金額です。源泉徴収票には金額を記載する欄が4つありますが、金額のちがいを把握できていないと、源泉徴収票を誤って作成してしまう恐れがあり注意が必要です。
ここでは、「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」4つの金額についてそれぞれ詳しく見方を解説していきます。
2-1. 支払金額
支払金額は受け取った人の「年収」に該当するものです。基本給だけでなく、残業代や休日出勤手当、賞与などさまざまな収入を含めた1年間の合計金額です。
ただし、非課税になる手当(旅費交通費・見舞金・祝い金など)は含まれません。
2-2. 給与所得控除後の金額
給与所得控除後の金額は、前述した「支払金額」から「給与所得控除額」を引いた後の金額を示しています。給与所得控除額は、一定の経費を年収から差し引いて納税する税金の額を抑えてくれる制度です。
給与所得控除額は収入金額に応じて、以下のように一定の金額が定められています。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
| 162.5万円以下 | 55万円 |
| 162.5万円超180万円以下 | 収入金額×0.4-10万円 |
| 180万円超360万円以下 | 収入金額×0.3+8万円 |
| 360万円超660万円以下 | 収入金額×0.2+44万円 |
| 660万円超850万円以下 | 収入金額×0.1+110万円 |
| 850万円超 | 195万円 |
2-3. 所得控除の額の合計額
所得控除の額の合計額は、前述した給与所得控除以外に控除される金額です。以下のような控除があります。
| 控除の種類 | 概要 | 控除額 |
| 雑損控除 | 災害・盗難・横領による損害を受けた際に適用 |
次のうちいずれか多い方 |
| 社会保険料控除 | 健康保険や国民年金など各種社会保険料に対して適用 ※生計を一にする家族も含む |
全額 |
| 小規模企業共済等 掛金控除 |
小規模企業共済の掛金に対して適用 | 全額 |
| 生命保険料控除 | 生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に適用 |
一定の計算に基づき算出された額の最大12万円 |
| 地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合に適用 | 一定の計算に基づき算出された額のうち最大5万円 |
| 寄附金控除 | ふるさと納税や特定公益増進法人等への寄付金に対して適用 | 「特定寄附金の合計額」または「所得×40%」のいずれか低い金額-2,000円 |
| 障害者控除 | 納税者や同一生計配偶者または扶養親族が障害者である場合に適用 | ・障害者:27万円 ・特別障害者:40万円 ・同居特別障害者:75万円 |
| 寡婦控除 | 納税者が寡婦である場合に適用 | 27万円 |
| ひとり親控除 | 納税者がひとり親である場合に適用 | 35万円 |
| 勤労学生控除 | 納税者が勤労学生の場合に適用 (合計所得額が75万円超は適用除外) |
27万円 |
| 配偶者控除 | 配偶者の合計所得が48万円以下の場合に適用(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) | ・一般控除対象配偶者:最大38万円 ・老人控除対象配偶者:最大48万円 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得が48万円超133万円以下である場合に適用 (納税者の合計所得が1,000万円超の場合は適用除外) |
配偶者の所得金額によって 最大48万円 |
| 扶養控除 | 16歳以上の子どもや両親などを扶養の場合に適用 | ・一般控除対象扶養親族:38万円 ・特定扶養親族:63万円 ・老人扶養親族:最大58万円 ※特定扶養親族は19歳以上23歳未満の扶養親族に適用 |
| 医療費控除 | 一定額以上の医療費を支払った場合に適用(生計を一にする配偶者やその他の親族も含む) |
(支払った医療費-保険金等の補填額)-10万円(※) |
| 基礎控除 | すべての人に適用 | 合計所得金額に応じて最大48万円 |
適用される控除は個人の事情によって大きく異なります。いずれかの控除が適用される場合は、その合計額がここに記載する金額です。
2-4. 源泉徴収税額
源泉徴収税額は、1年間ですでに納めている所得税(源泉徴収済みの金額)の合計金額で、次の計算式によって求められます。
源泉徴収税額 = 所得額 × 税率 -控除額
所得額は前述の②給与所得控除後の金額から③所得控除の額の合計額を引いた額です。また、適用する税率と控除額は所得額に応じて次のとおり変わります。
| 課税対象となる所得額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円~1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
平成25年から令和19年までは、さらに復興特別所得税(2.1%)も加算されます。
毎月の給与から少しずつすでに差し引いているもので、税務署にすでに納付済みの所得税になります。年末調整をおこなうことで、この源泉徴収税額の過不足を調整することになります。
3. 源泉徴収票が必要になるタイミング

源泉徴収票は重要な書類ですが、普段の業務の中で利用するようなものではありません。
源泉徴収票が必要になるのは、主に以下のようなときです。
- 転職や再就職をしたとき
- 確定申告をするとき
- 収入の証明が必要なとき
それぞれについて、説明します。
3-1. 転職や再就職をしたとき
年の途中で新しい勤務先に就職したとき、その勤務先で年末調整をすることが多いです。
年末調整というのは、その人の1年間の給与等の総額に対して、納めるべき税金を計算します。そのため、前職の勤務先での給与等の内容が必要になり、新しい勤務先へ源泉徴収票を提出します。
なお、年をまたいで転職や再就職した場合には、前年分の給与等について年末調整をしないことになります。転職先でおこなわれる年末調整のタイミングには間に合いません。このような場合は、従業員は自ら確定申告をして調整をしなければなりません。
3-2. 確定申告をするとき
上述したように、退職した後に年をまたいで転職や再就職した場合は、所得税を多く源泉徴収されたままになることがあります。この場合は、納税者本人が確定申告することで清算できます。
他にも、副業による収入が20万円を超える場合や医療費控除・住宅ローン控除を受ける場合、ワンストップ特例制度を利用せずにふるさと納税をおこなう場合などは、納税者本人で確定申告をする必要があります。
これらの確定申告をするときに、源泉徴収票が必要です。
源泉徴収票には、確定申告書を作成する際に必要な収入金額や所得税の金額が記載されている重要な書類です。確定申告をおこなう予定がある場合は大切に保管しておきましょう。
3-3. 収入の証明が必要なとき
ローンやクレジットカードなどの申し込みをするときは、支払能力を証明するために収入を証明する書類が求められます。
源泉徴収票は、確定申告書や所得証明書などと並んで、自分の収入が分かる書類として利用することができます。
なお、確定申告は毎年おこなうタイミングが決まっているものの、転職やローン申し込みなどのタイミングがいつになるかは分からないものです。
そんなとき、源泉徴収票を保管していなかったような場合には、源泉徴収票の再発行が必要になります。
4. 源泉徴収票はいつどこで発行できる?

源泉徴収票はいつどこで発行できるのか解説していきます。
転職等がない従業員のケースと退職した従業員では発行される時期が異なりますが、発行されるのは会社からです。それぞれ発行時期について詳しく見ていきましょう。
4-1. 基本的な発行時期は翌年の1月31日まで
年末調整の計算をしたのち「給与所得の源泉徴収票」を、翌年の1月31日までに発行して従業員に渡さなくてはいけません。正社員はもちろん、パートやアルバイトであっても交付の対象となるので注意しましょう。
年末調整の結果に基づく源泉徴収票は、従業員にとって非常に重要な書類となります。特に、源泉徴収票には1年間の収入額や納税額が記載されており、転職や住宅ローンの申し込み、確定申告時に必要となることが多いため、発行時期に正しく配布しましょう。
4-2. 退職所得の源泉徴収票は退職後1ヵ月以内
また、退職をする従業員に対しては、その年の1月1日~退職日までの給与に基づいた「退職所得の源泉徴収票」が必要です。退職時に支給された退職手当にかかる所得税が記載されたもので、これは給与所得の源泉徴収票とは違う種類の源泉徴収票です。
退職所得の源泉徴収票は12月に退職した場合は12月の給与明細と一緒に配布しますが、それ以外の場合は退職後1ヵ月以内に配布するのが一般的です。
5. 源泉徴収票を発行しないと会社はどうなる?
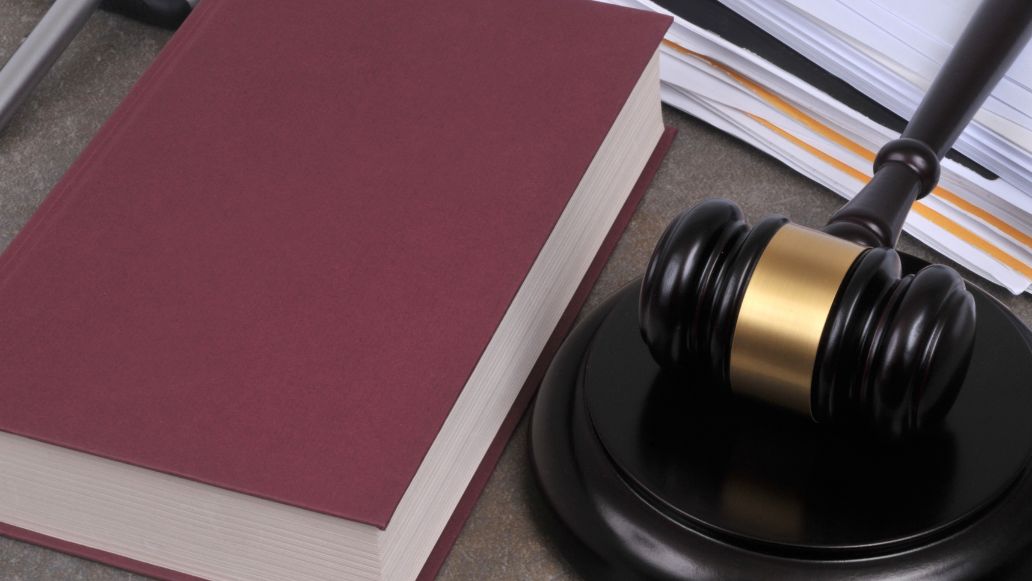
源泉徴収票の発行は、所得税法226条によって給与の支払いを受ける者への交付が義務付けられています。そのため、交付は正社員だけでなくパートやアルバイトであっても必要です。
これは従業員からの請求がなくても発行しなければならないもので、年末調整をしない場合も発行しなければなりません。発行しなかった場合は所得税法違反となり「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される恐れがあるため注意しましょう。
ただし、給与ではなく報酬として支払っている場合は給与所得に該当しないため、源泉徴収票が必要ありません。税理士や弁護士など、顧問契約をしている場合はこれに該当することがあります。その際は賃金の支払調書が必要になり、源泉徴収票の発行は必要なくなります。
関連記事:給与所得とは?給与収入・手取りとの違いと計算方法をわかりやすく解説
5-1. 会社が倒産してしまったケース
年末調整を行う前に会社が倒産してしまった場合、源泉徴収票が発行されない可能性が高くなります。
このようなケースでは、まず倒産した会社の事後処理を担当している破産管財人に源泉徴収票の発行を依頼することが有効です。それでも解決しない場合は、所轄の税務署に相談することを検討しましょう。その際には、「源泉徴収票不交付の届出書」を提出する必要があります。これにより、納税者としての権利を守る手続きを進めることが重要です。
5-2. 前職の源泉徴収票が年末調整に間に合わないケース
前職の源泉徴収票が新しい職場の年末調整に間に合わない場合、確定申告を行う必要があります。
通常、確定申告には源泉徴収票が必要ですが、退職した会社にその発行を依頼することが最優先です。もしその発行が難しい場合は、所轄の税務署に相談し、必要な手続きを行うことが重要です。これにより、正確な納税額をもとに適切に税務処理を行うことが可能になります。
5-3. 退職後に紛失や再発行の希望があったケース
退職後に源泉徴収票を紛失した場合、再発行が必要となります。
企業はこの要求に応じなければならず、元従業員が正確な納税を行うための重要な書類を確保する責任があります。もし会社が再発行に応じない場合、元従業員は税務署に相談し、適切な手続きを行う際に必要な情報を得ることが難しくなります。
また、法的な問題を引き起こす可能性もあり、会社の信頼性に関わることとなります。従って、退職後に源泉徴収票の再発行希望があった場合は、迅速かつ適切に対応することが重要です。
6. 源泉徴収票と給与支払報告書の違い

源泉徴収票と給与支払報告書は、しばしば混同されることがあります。
しかし、税金の種類と提出先が異なるまったく別の書類です。以下の違いを正しく理解しておきましょう。
| 書類 | 関連する税金 | 提出先 |
| 源泉徴収票 | 所得税 | 管轄の税務署 |
| 給与支払報告書 | 住民税 | 会社がある地区の市区町村 |
このように源泉徴収票と給与支払報告書には明確な違いがあります。このほかにも必要になるタイミングや記載内容の一部、対象範囲などにも違うため、それぞれの役割を正しく理解しておきましょう。
7. 源泉徴収票では収入額と納税額が確認できる

源泉徴収票は、毎年12月におこなわれる年末調整の後、もしくは退職するタイミングで発行される書類で、1年間に会社から支払われた給与等の金額および、自分が納付した所得税額が記されています。
源泉徴収票を確認することで1年間でどれくらいの所得税を納めているかを確認できますが、月ごとの所得税額を算出したい場合は国税庁が公開している「令和5年分 源泉徴収税額表」を用いて計算しましょう。
また、年末調整機能を兼ね備えた給与計算システムであれば、手計算しなくとも簡単に源泉徴収票が作成できます。源泉徴収票の作成を簡易化させたい場合は、こういったシステムの活用を検討してみても良いでしょう。
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」
「令和6年の年末調整における定額減税への対応方法が知りたい」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16
年末調整の関連記事
-

法定調書合計表とは?|書き方や提出方法、注意点を徹底解説
人事・労務管理公開日:2022.08.26更新日:2024.05.22
-

配偶者控除等申告書とは?書き方や提出義務について詳しく紹介
人事・労務管理公開日:2022.08.26更新日:2024.10.04
-

扶養控除等(異動)申告書の書き方や注意事項について解説
人事・労務管理公開日:2022.08.26更新日:2024.10.04































