年末調整の仕訳と勘定科目を解説!パターン別の仕訳も紹介
更新日: 2024.5.8
公開日: 2021.10.29
OHSUGI

年末調整に関する業務は、限られた時間でさまざまな処理をおこなわなければなりません。しかし、年末調整に関する業務は複雑なため、何かと間違いが発生しやすいものです。
年末調整の計算や納税をスムーズに進めるためには、仕訳についてあらかじめしっかり理解しておく必要があります。
そこで今回は、年末調整の仕訳と勘定科目について、具体的に「還付金が発生する場合」と「追加徴収が必要となる場合」の2パターンに分け、それぞれ詳しく解説します。
関連記事:年末調整とは?やり方や計算方法、確定申告との違いをわかりやすく解説
目次
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 年末調整の仕訳と勘定科目とは

年末調整を正しく実施するためには、年末調整で仕訳をおこなう意味と、年末調整の仕訳で使う勘定科目について確認しておかなければなりません。
ここでは、それぞれについて詳しく説明します。
1-1. 年末調整の仕訳は還付・追加徴収で必要となる作業
まずは、年末調整という作業について理解し、そこで仕訳をおこなう意味について確認しておきましょう。
年末調整とは、パートやアルバイトも含んだ従業員に支払っている毎月の給料から、前もって差し引いている源泉所得税を正確な所得税一年間分の額に再計算し、過不足分を調整する作業のことです。
従業員から本来徴収すべき額よりも多く徴収していた場合は、その額を従業員に返還(還付)しなければなりません。また、逆に少なかった場合には、不足分を精算して追加徴収する必要があります。
仕訳は、月々の給与からの源泉所得税の天引きから、年末調整をおこなう際に発生する還付や追加徴収で必要となる作業です。
1-2. 年末調整の仕訳では勘定科目「預り金」を使用する
年末調整で仕訳をおこなう際には、適切な勘定科目を使用しなければなりません。従業員から現金を預かり、税務署へ納税する際は、基本的に「預り金」という勘定科目を使います。
スムーズな会計処理をおこなうためにも、「預り金」の勘定科目で正確に計算しましょう。
2. 年末調整で使用する勘定科目「預り金」について

先ほど、年末調整で仕訳をおこなう際に利用する勘定科目として「預り金」があると説明しましたが、実際に「預り金」として仕訳をおこなう取引についても確認しておきましょう。
「預り金」勘定として、仕訳をおこなう取引には次の3つが挙げられます。
- 従業員の給料から差し引く社会保険料・雇用保険料・源泉所得税
- 税理士・弁護士などに支払う報酬に必要となる源泉所得税
- 講師料・原稿料など特定の報酬に必要となる源泉所得税
これら「預り金」として仕訳をおこなうものについては、会社側で毎月正しく管理しなければなりません。現金を預かった際には「預り金」としてその都度計上し、納付・支払いをおこなった場合もマイナスの「預り金」として忘れず計上しましょう。
毎月の管理を怠ると、残高が正確かどうかわからなくなってしまいます。そのため、とくに「預り金」の正確な管理を徹底すべきです。
3. 月々の給料の仕訳と勘定科目を確認

年末調整での仕訳と勘定科目を説明する前に、月々の給料でどのような仕訳と勘定科目となっているかをみていきましょう。
◇仕訳例
従業員の給与を50万円支払い、社会保険料を7万円、源泉所得税等を4万円、住民税を2万円差し引いた。翌月に源泉所得税等4万円を現金納付した。上記の場合、具体的な仕訳と勘定科目は以下のとおりです。
【給与支払い時の仕訳方法】
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 摘要 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 給与 | ¥500,000 | 給与 | 普通預金 | ¥370,000 |
| – | – | 社会保険料 | 預り金 | ¥70,000 |
| – | – | 源泉所得税等 | 預り金 | ¥40,000 |
| – | – | 住民税 | 預り金 | ¥20,000 |
通常、給与支払い時には、社会保険料・源泉所得税等、また住民税については勘定科目「預り金」での処理をおこないます。
【源泉所得税納付時の仕訳方法】
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 摘要 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 預り金 | ¥40,000 | 源泉所得税等納付 | 現金 | ¥40,000 |
毎月の給与から源泉所得税を納付した際は、勘定科目「預り金」で納付し、仕訳をおこないます。
4. 年末調整で還付金ありの場合の仕訳と勘定科目

年末調整で還付金がある場合、仕訳をおこなうのは従業員に返金したタイミングです。還付金の額が判明した時点では、仕訳をおこなう必要はありません。
従業員に返金する方法としては、12月の給与で精算するか、還付金を直接従業員に手渡すかになります。
以下、年末調整で還付金が発生するときの仕訳と勘定科目について、「給与で精算する場合」と「還付金を手渡す場合」の2つのパターンに分けて紹介します。
◇仕訳例
従業員の給与を50万円支払い、社会保険料を7万円、源泉所得税等を4万円、住民税を2万円差し引いた。還付金が2万円発生した。上記の場合、「給与で精算する場合」と「還付金を手渡す場合」それぞれの具体的な仕訳と勘定科目は、以下のとおりです。
【給与で精算する場合】
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 摘要 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 給与 | ¥500,000 | 給与 | 普通預金 | ¥390,000 |
| 預り金 | ¥20,000 | 年末調整還付金 | – | – |
| – | – | 社会保険料 | 預り金 | ¥70,000 |
| – | – | 源泉所得税等 | 預り金 | ¥20,000 |
| – | – | 住民税 | 預り金 | ¥40,000 |
【還付金を手渡す場合】
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 摘要 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 給与 | ¥500,000 | 給与 | 普通預金 | ¥370,000 |
| – | – | 社会保険料 | 預り金 | ¥70,000 |
| – | – | 源泉所得税等 | 預り金 | ¥40,000 |
| – | – | 住民税 | 預り金 | ¥20,000 |
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 摘要 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 預り金 | ¥20,000 | 年末調整還付金 | 現金 | ¥20,000 |
なお、還付金が発生する場合は年末調整還付金として、勘定科目「預り金」で処理します。
5. 年末調整で追加徴収が必要な場合の仕訳と勘定科目

年末調整で追加徴収が必要となった場合も、従業員と不足額を精算した時点で仕訳をおこないます。年末調整で追加徴収が必要となる場合の仕訳と勘定科目については、以下の例を使って説明します。
◇仕訳例
従業員の給与を50万円支払い、社会保険料を7万円、源泉所得税等を4万円、住民税を2万円差し引いた。源泉所得税等に1万円の不足があった。
このような場合、通常は12月の給与支払い時に不足分を天引きで徴収します。具体的な仕訳と勘定科目は、以下のとおりです。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 摘要 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 給与 | ¥500,000 | 給与 | 普通預金 | ¥360,000 |
| – | – | 社会保険料 | 預り金 | ¥70,000 |
| – | – | 源泉所得税等 | 預り金 | ¥40,000 |
| – | – | 住民税 | 預り金 | ¥20,000 |
| – | – | 年末調整不足額 | 預り金 | ¥10,000 |
追加徴収が必要となる税額については年末調整不足額として、勘定科目「預り金」で処理します。
6. 年末調整の仕訳と勘定科目を理解して慌ただしい年末調整を乗り越えよう
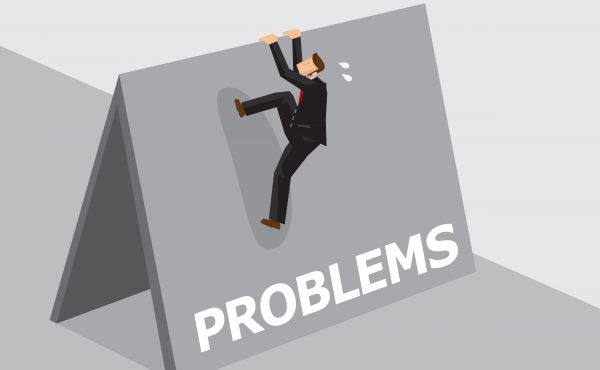
今回は、年末調整の仕訳と勘定科目について、還付金が発生する場合と、追加徴収が必要となる場合のパターンに分けて紹介しました。
年末調整は限られた時間でおこなわなければならないうえ、細かな間違いが発生しがちです。しかし、年末調整は1つの誤りが納税漏れなどにつながる可能性もあるため、正確な処理が求められます。
本記事の内容を参考に、正しい年末調整の仕訳を理解し、慌ただしい年末調整を乗り越えましょう。
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08




























