年末調整の社会保険料控除とは?対象となる保険や計算方法を解説
更新日: 2024.7.16
公開日: 2021.3.1
OHSUGI

年末調整の社会保険料控除についてきちんと理解していないと節税の機会を失う可能性があります。年末調整の社会保険料控除について正しい知識を身につけましょう。そこで今回は、年末調整の社会保険料控除について説明します。
目次
1. 年末調整の社会保険料控除とは?

納税者が自分又は自分と同じ生計で暮らしている配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
年末調整では社会保険料以外にも複数の所得控除が可能です。所得控除のなかには控除額の上限が設けられいているものがあります。しかし、社会保険料は控除額に上限がありません。1年で支払った社会保険料の全額の控除が可能です。年末調整の申告書の書き方は、各機関から送られてきた控除証明書の内容を転記しましょう。
2. 年末調整の社会保険料控除の対象となる保険

社会保険料控除の対象となる社会保険料は、国税庁のホームページで次のとおり紹介されています。
- 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
- 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
- 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
- 介護保険法の規定による介護保険料
- 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
- 国民年金基金の加入員として負担する掛金
- 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
- 存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金
- 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金又は納金等
- 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
- 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
- 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
- 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
- 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額
引用:社会保険料控除|国税庁
いずれも年末調整では、その年の1月1日〜12月31日までに収めた保険料が対象です。なお、配偶者や親族などの国民年金保険料などを控除する場合は社会保険料控除証明書が添付書類として必要です。
3. 年末調整における社会保険料控除の計算方法

ここまで、社会保険料控除についてや対象の保険について解説してきました。本章では、実際に保険料控除を受ける方法や控除額の計算方法ついて解説します。
3-1. 社会保険料控除を受ける方法
年末調整の社会保険料控除を受けるためには、給与所得者の保険料控除申告書を記載の上、会社に提出します。また、社会保険料のうち国民年金保険料等については、その支払金額を証する書類を1部添付してください。
国民年金保険料等以外の社会保険料については、支払金額を証する書類の添付の必要はありません。
3-2. 社会保険料控除額の計算方法
社会保険料控除額の計算方法は、その年に収めた社会保険料全額を所得から差し引きます。例えば、1ヵ月の国民年金保険料が1万6,540円で1年間納めた場合は、次の額を所得から差し引きます。
1万6,540(円)×12(ヵ月)=19万8480円
社会保険料以外にも控除可能なものがあれば所得から差し引き、最終的に残った金額に対して課税が発生します。
4. 社会保険料控除申告の注意点

社会保険料控除の申告にあたっては次のような注意点を把握しておきましょう。
- 退職~再就職が年をまたいだケース
- 被扶養者の公的年金から保険料が特別徴収されているケース
- 自分以外の社会保険料を支払ったケース
注意点を把握して、従業員から質問をされたときにスムーズに回答できるようにしておくことが大切です。
4-1. 退職~再就職が年をまたいだケース
従業員のなかには年内に退職し、翌年に再就職するという人もいるでしょう。このように退職から再就職が年をまたぐケースでは、退職後に従業員自身で支払った社会保険料だけでなく、会社が天引きした社会保険料も含め、確定申告で申告してもらう必要があります。そのため会社は忘れずに源泉徴収票を発行しましょう。
4-2. 被扶養者の公的年金から保険料が特別徴収されているケース
社会保険料が従業員の被扶養者の公的年金から特別徴収されているケースがあります。例えば、介護保険料が公的年金から特別徴収されているということが考えられるでしょう。このようなケースにおいて、特別徴収されている社会保険料を納めているのは被扶養者です。そのため、申告者である従業員の社会保険料控除の対象とはならないので注意しましょう。
このように、控除を受ける場合は添付書類が必要なものがあります。どの控除で何の添付書類が必要なのかを確認して、抜け漏れのないように対応しましょう。当サイトでは、控除に必要な添付書類を一覧にまとめた資料を無料でお配りしています。年末調整業務を抜け漏れなくおこないたい方は、こちらから「年末調整ガイドブック」をダウンロードして、必要な添付書類がそろっているかご確認ください。
4-3. 自分以外の社会保険料を支払ったケース
社会保険料の控除は、従業員本人と生計を同じくする配偶者、その他の親族が負担すべき社会保険料を支払ったケースであっても受けられます。例えば国民年金への加入義務が発生する20歳の子どもがいる場合、従業員が保険料を支払っていれば控除が認められます。
5. 年末調整の社会保険料控除の正しい手続きをおこなおう
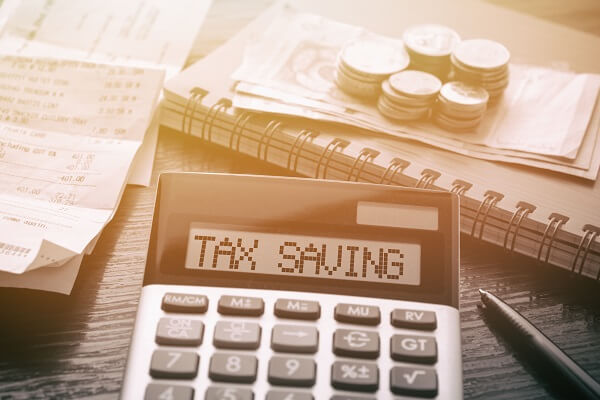
ここまで、年末調整の社会保険料控除、年末調整の社会保険料控除の対象となる保険、年末調整の社会保険料控除を受けるための手続について、説明してきました。年末調整の社会保険料控除について、しっかりと理解できたという方もいらっしゃることでしょう。
年末調整の社会保険料控除の正しい手続きをおこないましょう。
▼保険料控除申告書を電子化して作業効率を上げたい方は要チェック
年末調整の電子化はここまで進んでいる!気になる手続きの方法
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08




























