年末調整の電子化のやり方やメリット・デメリットをわかりやすく解説!
更新日: 2024.7.16
公開日: 2021.3.22
OHSUGI

2018年の税制改正により、2020年10月から年末調整に関する書類の電子化が可能となり、電子化を取り入れる企業も増えてきました。
ご存じの通り、従来の年末調整の手続きは複数枚の紙に従業員が手書きで手続きをおこなうため、修正依頼や書類の配布・改修など時間のかかる手続きでした。
電子化することで手続きのスピードが向上するだけでなく、入力ミスも軽減でき、担当者と従業員の双方に大きなメリットをもたらします。
本記事では、年末調整の電子化について概要や電子化した際の年末調整の手続きがどのような流れになるか、年末調整を電子化する方法について説明します。
関連記事:年末調整とは?やり方や計算方法、確定申告との違いをわかりやすく解説
「システム化で変わる年末調整の解説BOOK」を無料配布中!
「書類収集から計算、提出など面な業務が多い」
「電子化の義務化に対応したい」
「拠点が多く、紙の配布や回収に時間がかかりすぎる」
などの理由から、年末調整の電子化をお考えではありませんか?
しかし、電子化といっても、これまでのやり方と異なるため具体的なイメージがつかないご担当者様も多いのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトではシステムを導入して電子化することによって、年末調整の業務がどのように変わり、工数削減ができるのかまとめた資料を無料で配布しております。
実際のシステムの画面をご確認いただけるため、電子化の具体的な方法についてイメージを付けたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
目次
1. 年末調整の電子化とは?

年末調整の電子化は業務の効率化ができることに加え、義務化も少しずつ進んでいます。まずは年末調整の電子化の基本を知り、理解を深めていきましょう。
ここでは、年末調整の電子化が義務づけられている対象や電子化できる書類の種類などについて解説します。
1-1. 年末調整は電子化が可能
平成30年度税制改正により、令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先へ電子データにより提供できるようになりました。
これによって従業員に紙の申告書を配布したり、システムへの手入力をしたりする手間が削減され、業務の効率化がしやすくなっています。
当初は年末調整を電子化するか否かの判断は企業に委ねられていましたが、2021年1月提出分の年末調整より、一部企業において電子化が義務付けられました。
この流れにより、年末調整の電子化を進める企業が増えてきたと同時に、年末調整を電子上で完結できるシステムの提供も普及しています。
1-2. 電子化が推進されている背景
平成30年(2018年)の税法改正は、働き方改革の一貫でおこなわれました。納税環境を整えるための施策が政府によって進められており、電子化もそのひとつです。そして、電子化の具体策のひとつに年末調整手続きの電子化が含まれています。
年末調整以外にも電子化が可能な書類は増えており、納税環境を整えるとともに企業の業務負担を減らすことも働き方改革の一部として推進されています。業務負担が減れば激務や残業も減り、労働環境が改善されるからです。
こうした背景があるため、電子化は今後も推進され、義務化も進んでいくことが予測されます。企業はこの流れに乗り遅れないように、会社の規模や従業員数に合わせた対応が必要です。
1-3. 一部企業では電子化する義務がある
本章の冒頭で、一部企業において電子化が義務付けられましたとお伝えしましたが、具体的には以下の条件に当てはまる企業が年末調整の電子化が義務付けられています。
- 前々年度(2年前)に発行した法定調書が、種類ごとにみて100枚以上である
この1点のみですが、あてはまる場合はe-Tax、光ディスク等、またはクラウド等を使用して提出することが義務づけられています。
たとえば2021年1月に提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上だった場合、その2年後である2023年1月に提出する給与所得の源泉徴収票は電子化しなければなりません。
関連記事:年末調整手続きの電子化は義務?令和3年からの改正内容を解説
参考:法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又はクラウド等による提出義務|国税庁
1-4. 電子化が可能な年末調整の書類一覧
年末調整に必要な申告書類や添付書類のうち、電子化できる書類は以下のとおりです。
- 給与所得者の扶養控除等申告書
- 従たる給与についての扶養控除等申告書
- 給与所得者の配偶者控除等申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
- 所得金額調整控除申告書
- 退職所得の受給に関する申告書
- 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
電子化を進める場合は、年末調整に限定せずに可能な範囲で切り替えていくと効率がよいです。連携システムやアプリも使えば、大幅な業務効率化も狙えるでしょう。
しかし、急に重要な書類を電子化すると、慣れるまでに時間がかかったり、ついていけない従業員が発生したりする恐れがあります。
複数の書類を電子化する際は、事前の周知や勉強会などをおこなって従業員のスキル面にも目を向けることが大切です。
2. 年末調整を電子化するメリット

年末調整の手続きを電子化した場合、会社だけでなく従業員にもさまざまなメリットがあります。ここでは、具体的に電子化によってどのようなメリットがあるのか、従業員と会社の立場からそれぞれ解説します。
2-1. 従業員(納税者)にとってのメリット
従業員は、手書きによる手続きを省略できるため、年末調整申告書の作成を簡素化して業務負担を減らすことができます。
また、書面で提供を受けた控除証明書等を紛失する心配もなくなります。紛失した場合は、保険会社等に対し、再発行を依頼しなければいけないためこの手間がなくなるのはメリットの1つです。
さらに、従業員が「マイナポータル連携」を利用している場合はメリットが増えます。年末調整申告書データの作成中に、民間送達サービスに送達された複数の控除証明書等データをマイナポータルを通じて一括取得できるため、複数の控除証明書等を一度の処理で取得することが可能です。
2-2. 会社にとってのメリット
会社は、従業員が年調ソフトで作成した年末調整申告書データを利用することにより、控除額の検算が不要になります。
また、控除証明書等データを利用した場合、添付書類等の確認に要する事務が削減されます。さらに、納税者が年末調整申告書作成用のソフトウェアを利用して控除申書を作成するため、ヒューマンエラーを減らすことができるでしょう。
電子化して紙のデータが減れば、書類を保管する手間やスペースも削減できる点もメリットです。
加えて、年末調整の電子化のメリットには、申請書類をシステム上で配布・回収できる点もあげられます。
年末調整の資料提出を促したり、資料の内容を確認したりすることは担当者の大きな負担です。当サイトでは、電子化によって年末調整業務がどのように変わるか、実際のシステムの画面を用いて図解した「システム化で変わる年末調整」をご用意しました。
申請書類をフォーム化して配布し、従業員の回収によって申請書が作成できるシステムの概要を詳しく解説しています。
電子化のイメージをより明確にしたい方は、こちらから無料で資料をダウンロードできますので、是非ご一読ください。
▼ペーパーレス化にまつわる記事はこちら
関連記事:年末調整のペーパーレス化とは?その背景や課題を詳しく解説
3. 年末調整を電子化するデメリット
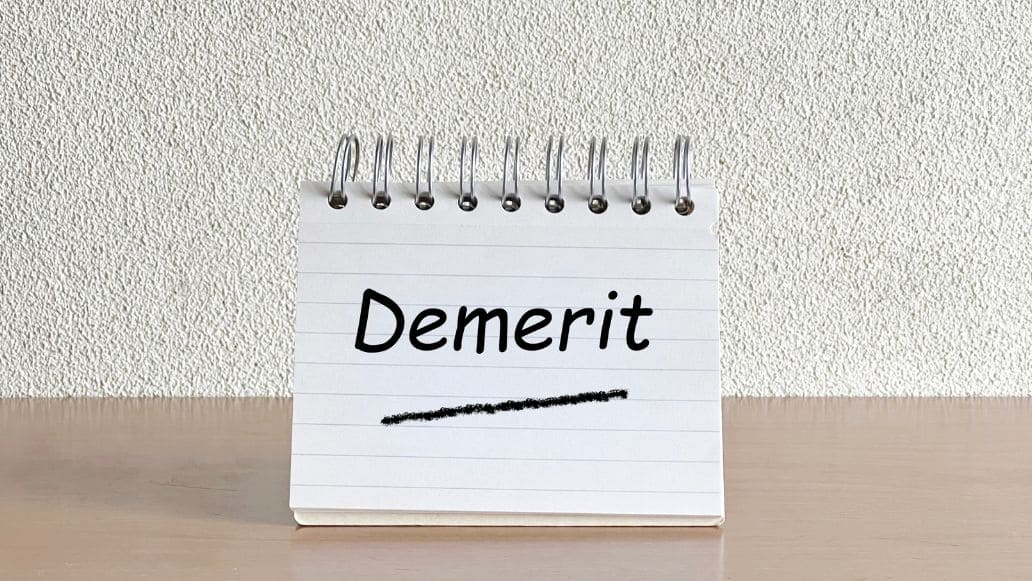
年末調整を含め、今までアナログな方法で進めていた手続きを電子化する場合はデメリットも発生します。
業務の効率化が可能になる電子化ですが、どれくらい効率化ができるかは従業員のスキルや環境に大きく左右されます。
そのため、社内で電子化のルールを決めたり、従業員の教育をしたりする手間とコストがかかる点が主なデメリットです。また、ネットやIT環境が十分でない場合はその準備にもコストが発生します。
電子化が完了して運用がスムーズになればデメリットはありませんが、運用前の業務負担やコスト増があるという点は十分に理解しておきましょう。
4. 電子化した際の年末調整手続きの流れ

年末調整手続きが電子化された場合、年末調整に関連する書類の配布や回収などの業務はなくなります。どのような流れになるのか見ていきましょう。
| 1 |
従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領する。 |
| 2 |
従業員が、国税庁ホームページからダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに、住所・氏名等の項目を入力し、1で受領した電子データをインポートして年末調整申告書の電子データを作成する。 電子データをインポートする際、自動入力と控除額の自動計算がおこなわれます。年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)とは、年末調整申告書について、従業員が控除証明書等データを活用して簡便に作成し、勤務先に提出する電子データ又は書面を作成する機能を持つ、国税庁が無償で提供するソフトウェアのことです。 |
| 3 |
従業員が、2の年末調整申告書データ及び1の控除証明書等データを会社に提供する。 |
| 4 |
会社が、3で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算する。 |
このような流れになり、ほとんどの業務がソフトウェア上でおこなわれ、自動的に計算がされます。
従業員が基本情報を入力したり、システムへのインポートが必要になったりする手順はありますが、アナログな方式よりも大幅に業務が減ることがわかりました。
なお、この流れは導入しているソフトウェアやシステム、会社が決めている流れなどによって変化するものです。
5. 年末調整を電子化するやり方とポイント
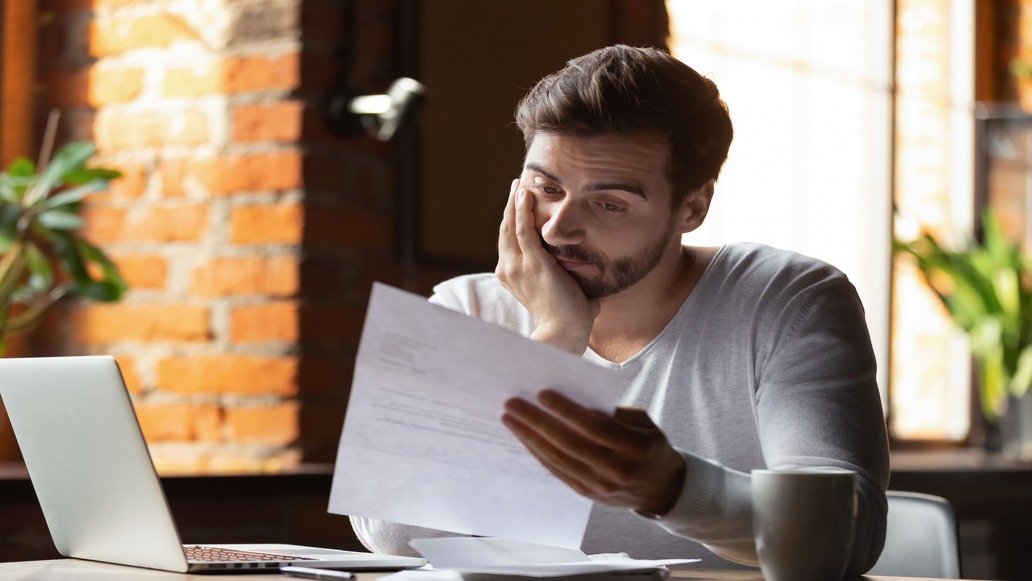
年末調整を電子化する場合は、会社が独断で進めると失敗する恐れがあります。従業員への周知からはじめ、適切な手順で進めるようにしましょう。電子化する際の流れと手順を解説します。
なお、電子化に向けて必要な手続きは複雑な部分もあるため、詳細は下記内容をご確認ください。
▼電子化に向けて必要な手続きはこちら
関連記事:年末調整をネットで手続きするために必要な準備・方法
5-1. 従業員への周知
会社は、年末調整申告書を電子データにより提供を受ける上で、法律上、事前に従業員から同意を得ることは必須ではありません。
しかし、電子化にあたっては、従業員も保険会社等から控除証明書等データを取得するようにしなければならないなど、事前準備が必要です。そのため、電子化する際には、従業員へ早めに周知をおこなった方がよいでしょう。急に告知すると準備が間に合わない恐れがあります。
告知をする際は以下の3点をわかりやすく伝えると安心です。
- 1で決定した納税者が使用する年末調整申告書作成用のソフトウェアや事務手順
- マイナポータル連携により控除証明書等データを取得することができること
- 納税者のマイナンバーカードの取得が間に合わないなどにより、マイナポータル連携による取得ができない場合は、その納税者が契約している保険会社等のホームページ等から控除証明書等データを取得できること
ITやネットの取り扱いが苦手な従業員がいる場合は、個別のフォローや勉強会なども検討しなくてはいけません。十分な周知と準備をまずはおこないましょう。
5-2. システムやアプリケーションの導入・改修
会社は電子化にあたり、従業員から年末調整申告書データや控除証明書等データを受け取ったり、給与システム等にインポートしたりする必要があります。
これまでアナログな方式で手続きをしていた場合は、そうした基本的なシステムやアプリケーションの導入や構築もしなければなりません。
すでにシステムを導入している会社でも、令和2年分からの所得金額調整控除の額については会社側で計算することになったため、それに係る改修も必要です。
5-3. 管轄税務署に承認申請書を提出する
納税者から年末調整申告書に記載すべき事項を電子データにより提供を受けるためには、会社があらかじめ所轄税務署長に承認を受ける必要があります。
「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、必要な手続きを済ませておくようにしましょう。
6. 年末調整の電子化を進めて業務の正確性と効率を上げよう

年末調整は毎年必ずおこなうもので、繁忙期に重なる企業も少なくありません。
少しでも業務負担を減らすには電子化がおすすめですが、電子化を進める場合はメリットとデメリットを理解したうえで従業員への告知をおこないましょう。
電子化は無理に進めると業務効率を落としたり、業務が停滞してしまったりすることもあります。十分な準備をし、導入基盤を整えてから進めることが大切です。
▼作業効率を上げたい方はこちらをチェック
関連記事:年末調整がめんどくさい4つの理由と楽にするコツを解説
「システム化で変わる年末調整の解説BOOK」を無料配布中!
「書類収集から計算、提出など面な業務が多い」
「電子化の義務化に対応したい」
「拠点が多く、紙の配布や回収に時間がかかりすぎる」
などの理由から、年末調整の電子化をお考えではありませんか?
しかし、電子化といっても、これまでのやり方と異なるため具体的なイメージがつかないご担当者様も多いのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトではシステムを導入して電子化することによって、年末調整の業務がどのように変わり、工数削減ができるのかまとめた資料を無料で配布しております。
実際のシステムの画面をご確認いただけるため、電子化の具体的な方法についてイメージを付けたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
<!– wp:pa
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08


























