総勘定元帳の書き方とは?仕訳帳から転記する際のポイントや具体例も紹介
更新日: 2024.7.5
公開日: 2022.5.13
jinjer Blog 編集部

総勘定元帳には決まった書き方がありますが、その際に必要になるのが仕訳帳です。
総勘定元帳は仕訳帳から転記して作成するため、必ず仕訳帳と結びついていなくてはいけません。該当する取引が仕訳帳のどのページに記載されているかを総勘定元帳からわかるようにしておく必要があります。
仕訳帳の記入はそれほど難しくはありませんが、総勘定元帳に関しては間違えやすい部分が多く、誤りがあると追徴課税のペナルティーを受けることもあるため注意しなければなりません。
ここでは、総勘定元帳の書き方や転記する際のポイントなどについて解説していきます。
関連記事:総勘定元帳とは?作成する理由や転記方法、保存期間や形式など網羅的に解説
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 総勘定元帳の書き方


総勘定元帳には主に2つの書き方があります。
1.貸方と借方にわけて記載をする標準式
2.記帳のたびに残高を計算していく残高式
標準式は、貸方と借方を明確に分けて記載しているため、どのような取引であったかがすぐに判断できます。一方、残高式は普通預金や売掛金などをすぐに確認できるというのが特徴です。ここでは、それぞれの書き方を詳しく解説していきます。
1-1. 標準式の書き方
標準式は、「借方」と「貸方」に分けて記載しますが、内容はシンプルです。
標準式で記載する項目は、以下の5つになります。
- 日付
- 借方科目
- 借方金額
- 貸方科目
- 貸方金額
日付はお金の動きがあった日、借方科目は売上の減少や資産増加に該当する科目を記載し、借方金額は取引によって発生した借方の金額を記載します。貸方科目は売上の増加や資産減少などに該当する科目を記載し、貸方金額には取引で発生した貸方の金額を記載しましょう。
標準式の総勘定元帳の一例は、以下のようになります。
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
| 4/11 | 現金 | 7,000 | 借入金 | 7,000 |
| 4/12 | 仕入 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
| 4/13 | 現金 | 10,000 | 売上 | 10,000 |
1-2. 残高式の書き方
残高式は、標準式よりも記載項目が多く、また書き方も複雑になので正しい記載方法を理解しておきましょう。
残高式で記載しなければならないのは、下記の6項目になります。
- 日付
- 摘要
- 仕丁
- 貸方
- 借方
- 借/貸
- 残高
日付は取引がおこなわれた日付、摘要には現金や売掛金、地代家賃など勘定科目の種類を記載します。
貸方と借方は、取引の内容によって貸方・借方が異なるので、どちらで取引をおこなったかがわかるように記載をします。そして借/貸では貸方、借方のどちらでプラスになっているのかがわかるように記載してください。
残高は、取引が完了した後の残高を計算します。総勘定元帳は上から残高が並んでいるので、貸方・借方のプラスを残高に反映すれば、現在の金額を知ることができます。
この方法で作成をした総勘定元帳は、以下のようになります。
| 日付 | 摘要 | 仕丁 | 借方 | 貸方 | 借/貸 | 残高 |
| 4/10 | 現金 | 5 | 100,000 | 借 | 500,000 | |
| 4/11 | 売掛金 | 5 | 150,000 | 借 | 650,000 | |
| 4/12 | 地代家賃 | 6 | 100,000 | 借 | 550,000 | |
| 4/13 | 売掛金 | 6 | 300,000 | 借 | 850,000 | |
| 4/14 | 買掛金 | 7 | 150,000 | 借 | 700,000 |
これはあくまで一例ですが、こちらの表に記載のある情報については最低限記入しないといけません。また、会計ソフトを使う場合は、表の内容が少し変わります。
例えば、取引の内容を摘要欄に記載できるようになっていたり、ソフト上で仕訳帳のページに画面を移すことが可能なので、仕丁の項目がなかったりします。さらにソフト上ではマイナスの金額がそのまま記載されることが多いため、プラスとマイナスを判断する借/貸の項目がありません。
仕訳で使用する勘定科目については、当サイトで無料配布している「勘定科目と仕訳のルールBOOK」で解説しています。なかなか勘定科目を覚えられない経理初任者の方はもちろん、丁寧に教える余裕がなくてお困りの先輩社員の方にもおすすめの資料となっています。興味のある方はこちらからダウンロードしてご覧ください。
2. 仕訳帳から転記する際のポイント


仕訳帳から転記をする際には、転記先の総勘定元帳の該当ページを記載します。その後、仕訳帳から総勘定元帳の該当ページに関係する項目をすべて書き写し、残高の計算をおこない、総勘定元帳の仕丁欄に仕訳帳の該当ページを記載して完了になります。
これだけ見ると、特に難しい所はないように思えるかもしれません。しかし、少しでも間違いがあるとペナルティが課せられてしまうので注意が必要です。
ここでは、仕訳帳から転記する際のポイントを解説していきます。
2-1. 仕訳帳と総勘定元帳を関連づける
転記する際に、一番気を付けなければならないポイントは「仕訳帳と総勘定元帳を関連づける」ということです。
仕訳帳を見れば総勘定元帳のページがわかるように、逆に総勘定元帳を見れば仕訳帳のページがわかるように「仕丁」に必ず記載しましょう。
特に、相手勘定科目が「諸口」の場合、取引内容の詳細は総勘定元帳だけでは確認できないので、仕訳帳と照らし合わせながら確認をすることになります。そのため、仕丁で必ず関連づけるようにしておくことが重要です。
2-2. 「賃借」の計算方法
もう一つのポイントは、「貸・借」の違いにおけるプラスマイナスの計算方法です。
転記をする際、勘定科目の分類によって「貸」がプラスになるのか、「借」がプラスになるのかが異なるので正確に理解しておきましょう。
基本的に「借」がプラスになるのは資産や費用に分類される勘定科目で、現金や売掛金、仕入などが該当します。「貸」がプラスになるのは、資本や収益に分類される勘定科目であり、買掛金や借入金などが該当します。
プラスマイナスの計算を間違えてしまうと、残高の合計がずれて所得税額が変わってしまうので注意してください。
取引の数が多いと、後から間違いを探すのも大変になります。そのため、取引内容を記載する際にはその都度間違えがないかをよく確認することが大切です。
3. 相手勘定科目が複数あるケース


相手勘定科目が複数ある場合は、仕訳帳上では勘定科目ごとに金額を記載します。しかし、総勘定元帳では勘定科目を複数記載することができません。そのため、諸口とまとめて記載をおこないます。
先ほども説明したように、仕訳帳と総勘定元帳は紐づけられています。そのため、総勘定元帳で諸口とまとめられていても、仕訳帳を確認すれば勘定科目がわかります。このようにしておけば相手勘定科目が複数あったとしても、問題なく総勘定元帳を作成することが可能です。
4. 具体例から見る作成方法


ここまで紹介してきた方法を踏まえて、実際に総勘定元帳の作成を行います。具体例としては4月1日に時計が10,000円で売れたとします。
まずは仕訳帳の作成です。この場合の仕訳帳は以下のようになります。
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
| 4月1日 | 現金 | 10,000円 | 売上 | 10,000円 | 時計 |
この場合の勘定科目は現金と売上の2つになります。そのため、これら2つについて総勘定元帳を作成しなくてはいけません。
総勘定元帳(現金)
| 日付 | 相手勘定科目 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 残高 |
| 前月より繰越 | 10,000円 | ||||
| 4月1日 | 現金 | 時計 | 10,000円 | 20,000円 |
総勘定元帳(売上)
| 日付 | 相手勘定科目 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 残高 |
| 前月より繰越 | 310,000円 | ||||
| 4月1日 | 売上 | 時計 | 10,000円 | 320,000円 |
これで仕訳帳からの転記は完了です。
このように、後から見直したときにお金の流れがわかるようになっていることが重要です。また、借方、貸方のどちらに該当しているかについても間違えないようにしてください。
これはあくまでも例なので、最初に紹介した仕丁と借/貸については割愛してあります。会計ソフトを利用するとこれらは割愛される場合もあるので、ソフト上だとこのような総勘定元帳となるケースも多いです。
この場合だと総勘定元帳の売上を見れば、時計が10,000円で売れたことで残高が10,000円増えたことがわかります。作成した後に表を見直してみて、取引の内容がそこから理解できれば完成です。
実際に総勘定元帳を作成する際は、手書きでも問題ありませんが会計ソフトの利用が便利であるためおすすめです。
手書きで総勘定元帳を記載しようとすると、取引の数が多くなるにつれ作業量が膨大になります。最初のうちは問題ないかもしれませんが、後から手間がかかってきます。そのため、早めに会計ソフトを使った総勘定元帳の作成に慣れておくと良いでしょう。
5. 総勘定元帳の書き方を理解してミスを防ごう
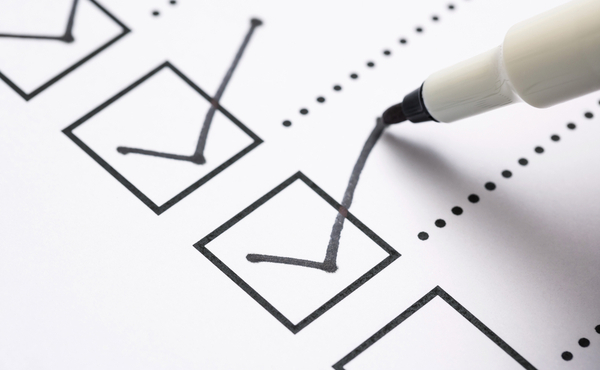
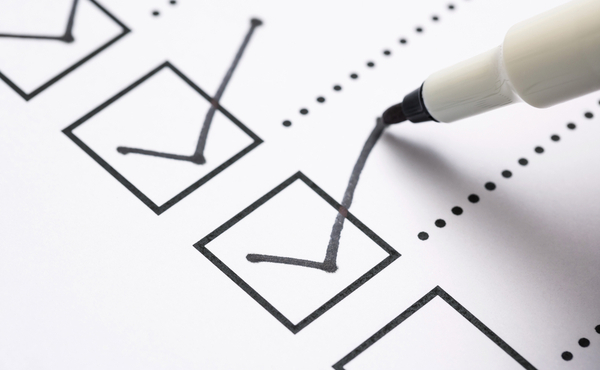
総勘定元帳は、所得税を申告する際に欠かせない書類であり、勘定科目の残高を把握したり財務状況を正確に分析したりできるので、経営戦略にも必要不可欠な帳簿です。また、財務諸表を作成する基礎資料という重要な役割も持っているため、正確に記載することが求められます。
特に転記する際には、残高のプラスマイナスなど間違いやすい部分が多いので、内容をしっかりと理解して記載することが大切です。また、計算間違いも起こりやすいので、人的なミスを防ぎ適切に管理をおこなうには、会計ソフトの導入を検討することをおすすめします。
会計ソフトを活用すれば、簿記の知識がなくても帳簿作成ができる、自動で仕訳できるなどのメリットがあるので、担当者の業務負担を軽減し、効率よく総勘定元帳の作成がおこなえます。
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
経費管理のピックアップ
-


電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理公開日:2020.11.09更新日:2024.10.10
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-


小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理公開日:2020.12.01更新日:2024.10.07
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理公開日:2020.10.07更新日:2024.10.07
-


経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理公開日:2020.01.28更新日:2024.10.10
書き方の関連記事
-


報告書の書き方とは?基本構成やわかりやすい例文を解説
人事・労務管理公開日:2024.05.10更新日:2024.05.24
-


顛末書とは?読み方・書き方・社内外向けテンプレートの作成例を紹介
人事・労務管理公開日:2024.05.09更新日:2024.05.24
-


回議書とは?様式・書き方や稟議書との違いをわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2024.05.01更新日:2024.09.26
仕訳の関連記事
-


交際費の控除対象外消費税の計算方法や仕訳をわかりやすく解説
経費管理公開日:2024.03.18更新日:2024.05.29
-



レンタカーの経費、ガソリン代、保険料の勘定科目と仕訳方法を解説
経費管理公開日:2023.05.16更新日:2024.05.08
-



接待ゴルフの費用は経費になる?判断基準と仕訳方法を解説
経費管理公開日:2023.05.16更新日:2024.05.08
会計 の関連記事
-



レンタカーの経費、ガソリン代、保険料の勘定科目と仕訳方法を解説
経費管理公開日:2023.05.16更新日:2024.05.08
-



接待ゴルフの費用は経費になる?判断基準と仕訳方法を解説
経費管理公開日:2023.05.16更新日:2024.05.08
-


立替精算とは?精算方法や仕訳を解説
経費管理公開日:2023.05.15更新日:2024.05.08





















