仕訳帳とは?書き方や記載項目、注意点を解説
更新日: 2024.7.5
公開日: 2022.5.13
jinjer Blog 編集部
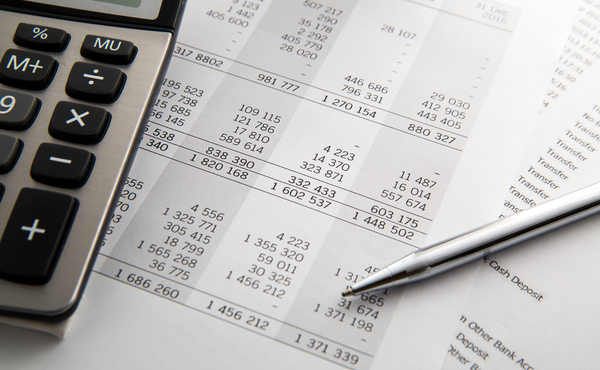
会社で決算書を作成する際には、簿記上の仕訳という作業を最初におこないます。その仕訳を記録する帳簿を仕訳帳といい、簿記において重要な主要簿と呼ばれるものに分類されます。
仕訳帳には、会社で起きた「お金の発生する全ての取引内容」を記録する必要があり、仕訳帳を見ることで「いつお金が動いた」かを把握できるようにしておかなければなりません。
重要な役割を持っている仕訳帳は、記録の仕方に細かいルールが定められています。
そこで、今回は仕訳帳の扱い方や書き方、記載する際の注意点などについて詳しく解説していきます。
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 仕訳帳とは


仕訳帳とは、会社でお金が動く取引が発生した順番(日付順)に、取引内容を記録していく帳簿をいいます。
取引が発生した場合、まずは仕訳という作業をおこない、取引内容を借方と貸方に分類します。このように、日付や借方・貸方に仕訳したものをまとめて記録する場所が仕訳帳です。
取引内容を記録する会計帳簿は他にもありますが、仕訳帳は主要簿ともいわれるほど重要な帳簿です。貸借対照表や損益計算書などを作成する際にも使用するので、会社法で作成と保存が義務付けられています。
なお、会計帳簿には「現金出納帳」や「仕入れ帳」、「売上帳」など補助簿といわれる帳簿もあり、主要簿を補完するために作成しなければなりません。ただし、補助簿は種類が多いので、企業ごとに必要となる補助簿を作成するのが一般的です。
関連記事:仕訳とは?借方・貸方の考え方や仕訳の手順をわかりやすく解説
1-1. 仕訳帳の保存期間
仕訳帳の保存は会社法によって義務付けられていますが、保存期間は法人税法により7年と義務付けられています。なお、仕訳帳を含む会計帳簿だけでなく、取引関係の書類も同様の期間保存しなければなりません。
ここで注意しなければならないのは、法人税法では保存期間は7年となっていますが、会社法では10年となっていることです。法律で定められている保存期間を守らないと、過去のデータが確認できなくなってしまうため、財務上で不利益な扱いを受けることがあるので、法人の場合は必ず「10年」の保存期間を遵守しましょう。
2. 仕訳帳と総勘定元帳の違い


仕訳帳と総勘定元帳、どちらも複式簿記をおこなうために必要な書類であり、法律でも作成が義務付けられているという共通点があります。また、勘定科目を記載する帳簿なので同じものと思うかもしれません。
しかし、仕訳帳は日付順に記載されている帳簿で、総勘定元帳は勘定科目ごとにまとめられている帳簿という大きな違いがあります。
仕訳帳は、取引が発生した順番で記載するので、「いつ、どのような取引をおこなったのか」がわかります。しかし、勘定科目ごとの流れを確認する作業には手間がかかるため、勘定科目ごとにまとめる総勘定元帳を作成する必要があるのです。
つまり、時系列でお金の流れを確認できるのが「仕訳帳」、勘定科目ごとにお金の流れが確認できるのが「総勘定元帳」というように、使用用途にも違いがあるのです。
3. 仕訳帳の書き方


ここでは、仕訳帳をどのように書けば良いのかを解説していきます。
3-1. 手書きやエクセル・無料テンプレートを活用する
仕訳帳の作成方法には決まりがないので、初めて作成する場合は手書きやエクセルで始めてみるとよいでしょう。
ただし、取引が多い場合は手書きだと作業の負担が大きいので、エクセルを使う方がよいかもしれません。エクセルであれば、書式自体をすべての行で同じようにすることで列ごとの集計が簡単にできますし、フィルタ機能を使えば特定の勘定科目の金額だけを集計することも可能です。
エクセルを使いこなせる担当者がいない場合は、無料のテンプレートを活用するという方法もあります。検索をすれば、会計帳簿の無料テンプレートがあるので、活用してみましょう。
それでも業務負担が大きいという場合は、仕訳作業や申請・承認などをクラウド上で処理できる会計管理システムの導入を検討してみましょう。
3-2. 会計基準に従い取引を記録する
仕訳帳を書くには、まずは「仕訳」をおこなわなければなりません。
仕訳というのは、会計基準に従って取引を記録することです。企業が事業をおこなう際に発生する取引に関しては、すべて仕訳をする必要があります。仕訳をおこなう際には、取引の内容を表わす勘定科目に振り分け、「借方」と「貸方」に分けて記載しなければなりません。
勘定科目は、誰が帳簿を見てもお金の動いた理由がわかるようにするためのものです。法律で決まっているわけではなく、会社によって自由に決められますが、基本となるのは「資産」「負債」「純資産」「費用」「収益」の5グループなので、適切に仕訳をおこないましょう。
仕訳帳の勘定科目一覧
勘定科目はそのまま決算書(貸借対照表や損益計算書)にも使用されますので、誰にでも伝わりやすい項目をつくるのが良いとされますが、基本となるのは下記の勘定科目です。
【勘定科目一覧】
| グループ | 勘定科目 |
| 資産 | 固定資産、現金、預金、受取手形、売掛金、商品など |
| 負債 | 未払金、借入金、買掛金、支払手形など |
| 純資産 | 資本金、繰越利益剰余金など |
| 費用 | 給与、仕入、水道光熱費、消耗品費など |
| 収益 | 売上、受取利息、受取配当金など |
帳簿の記入は、勘定科目によって借方・貸方のどちらに記入するかがわかれています。資産と費用は左側の「借方」、負債と純資産と収益は右側の「貸方」と定位置が決まっており、増えた場合は定位置のほう(借方か貸方)に記入することになっています。
「資産」は会社の財産となるもので、現金・当座預金・建物・受取手形等が含まれます。資産は借方に定位置が決まっていますので、先ほどの例で「現金が500円増えた」ことを仕分ける際に左側の借方に「現金 500」と記入したこととつながります。
「負債」はいずれ支払わなければならない義務があるお金で、買掛金(後で支払うことを約束したお金)・借入金・支払手形などが含まれます。
「純資産」は会社の資産から負債を引いて手元に残るお金のことです。
「収益」は事業によって得た収入などをいい勘定科目の売上などが含まれ、「費用」は収益を得るためにかかったお金ですので、給料・家賃などが勘定科目です。
また、あまり使わない勘定科目の仕訳方を忘れてしまうこともあるでしょう。
当サイトではそういったお困りごとが発生した際に使っていただける「勘定科目と仕訳のルールブック」という無料ガイドブックを作成しました。
この資料では、どんな取引をどんな勘定科目をもちいて仕訳をするのかを一覧表にして記載しています。勘定科目の疑問や不安をすぐに解消できる内容になっております。興味のある方は、こちらから無料でダウンロードしてぜひご覧ください。
関連記事:仕訳帳の項目ごとの書き方や仕訳する際の考え方を紹介
3-3. 仕訳帳の記載項目
仕訳帳の書き方や様式は企業によって異なりますが、基本的に下記の記載項目が決められています。
- 日付
- 借方
- 貸方
- 元丁
- 摘要
ここでは、それぞれの項目の意味や記載しなければならない内容を解説します。
日付
日付の項目では、名前のとおり取引がおこなわれた日付を、月・日の順番で記入します。
借方
借方の項目は、借方の勘定科目とその金額を記載します。
貸方
貸方の項目には、貸方の勘定科目とその金額を記載します。
元丁
元丁の項目には、総勘定元帳の転記先のページ数を記載します。仕訳帳は日付順で記入していくため、勘定科目でまとめる総勘定元帳に転記をした場合、確認作業をする際にどこに記載されているかわからなくなってしまうことがあります。
元丁を記入しておけば、総勘定元帳と簡単に照らし合わせることができますし、「転記が済んでいる」という証にもなるので2重記載を防ぐことも可能です。
摘要
摘要の項目には、取引内容のシィウサイと勘定科目を記入します。書き方としては、「借方勘定科目」「貸方勘定科目」「取引の内容」の順番で記載するのが一般的です。
4. 仕訳帳の実際の記入例


それでは、仕訳・仕訳帳・勘定科目・借方と貸方を理解したところで、実際に仕訳した記録を仕訳帳に記入していきます。
先ほどと同じ取引を例に挙げ、作成していきます。
・2022円4月1日に500円の商品を売り上げて現金が500円増えた
| 日付 | 借方 | 貸方 |
| 2022年4月1日 | 現金 500 | 売上 500 |
先ほどは、この仕訳作業をおこないました。
この仕訳をした表を仕訳帳に書き写すと、以下のようになります。
| 2022年 | 摘要 | 元丁 | 借方 | 貸方 | |
| 4 | 1 | (現金) | 1 | 500 | |
| (売上) | 3 | 500 | |||
| △△商品の売り上げ | |||||
- 日付…日付を必ず記入する。
- 摘要欄…摘要欄に勘定科目を()を付けて記入し、勘定科目1つにつき1行を使う。勘定科目の下に、取引内容を簡潔に記入する。
- 元帳…仕訳帳の次に作成する「総勘定元帳」の勘定口座の番号を記入する。総勘定元帳は、勘定科目ごとに取引内容を記録するもの。各勘定科目ごとの記録する場所を「勘定口座」といい、それぞれに番号が振られている。
仕訳帳のルールに従って記入すれば、いつ・どのような取引で・いくらお金が動いたかが一目でわかるようになります。
5. 仕訳帳を記入するうえでの注意点


仕訳帳を記入するうえでの注意点は、大きく2つあります。
- 摘要欄は勘定科目1つにつき1行使用する
- 「貸借対照表」「損益計算書」への記入ルールを理解する
ここでは、これらの注意点について詳しく解説していきます。
5-1. 摘要欄は勘定科目1つにつき1行使用する
仕訳をおこなっていると、1つの取引で勘定科目が3つ以上出てくることもあります。
このような場合、仕訳帳の記入が複雑になり、摘要欄の記入のやり方も少し変わるため注意が必要です。
例えば、下記のような取引があった場合の仕訳は、以下のようになります。
・2022年4月5日にA社から10,000円の商品を仕入れて、5,000円現金で支払い、残りは後日払うことにした
| 日付 | 借方 | 貸方 |
| 2022年4月5日 | 仕入 10,000 | 現金 5,000 |
| 買掛金 5,000 |
このように、支払い方法が2種類の場合は、勘定科目も2つにわけて記録します。
仕入は勘定科目の「仕入」で費用のグループ、「現金」は資産のグループ、後日支払う代金は勘定科目の「買掛金」で負債のグループに分類されます。
こちらの仕訳を仕訳帳に書き写します。
| 2022年 | 摘要 | 元丁 | 借方 | 貸方 | |
| 4 | 5 | (仕入) 諸口 | 4 | 10,000 | |
| (現金) | 1 | 5,000 | |||
| (買掛金) | 5 | 5,000 | |||
| A社から商品の仕入 | |||||
勘定科目が増えても、必ず勘定科目ごとに1行を使用します。
勘定科目が2つ以上ある場合は、勘定科目の上に「諸口」と記入するルールがありますので、忘れずに記入しましょう。
5-2.「貸借対照表」「損益計算書」への記入ルールを理解する
仕訳帳の取引は「貸借対照表」や「損益計算書」に反映されるた、え、それぞれの記入ルールを理解しておく必要があります。決算書の科目には、「資産」「純資産」「負債」「収益」「費用」があり、これらのグループが「貸借対照表」と「損益計算書」のどちらに反映されるのかを理解していれば、間違えるリスクを減らせます。
まず、賃借対照表のルールは下記のようになります。
| 借方 | 貸方 |
| 「資産」が増える場合は借方に記入する |
「負債」が増える時は貸方に記入する 「純資産」が増える時は貸方、減る時は借方に記入する |
損益計算書の記入ルールは以下のようになります。
| 借方 | 貸方 |
| 「費用」が増える時は借方、減る時は貸方に記入する | 「収益」が増える時は貸方、減る時は借方に記入する |
最初は混乱するかもしれませんが、理解しておけば仕訳もスムーズに進みます。
6. 仕訳帳は勘定科目とルールを守って記入する


仕訳帳は日々の取引を細かく記録する作業で、どんな小さな金額でもお金が動いた場合は仕訳帳に記録しなければ、決算書の作成時に金額が合わなくなってしまう可能性があります。
ルールや勘定科目、借方・貸方を覚えてしまえばそれほど難しい作業ではありません。しかし、会社の取引発生回数は非常に多いため、人の手で作業をするとミスが起こってしまう可能性が高いです。
人為的ミスを防ぐには、管理システムの導入がおすすめです。管理システムは、細かい仕訳作業をミスなくスピーディーにおこなってくれるため、経理の負担が軽減されます。
申請や承認はオンラインで簡潔でき、確認作業に時間をとられることもなくなりますので、経理全体の効率アップにつながるでしょう。また、紙の書類ではなくオンライン上でのやり取りやデータの管理をするため、コスト削減にも貢献できるので、ぜひ管理システムの導入を検討してみてください。
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
経費管理のピックアップ
-


電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-


小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-


経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04





















