会計基準とは?改正に伴う変更や会計基準一覧を種類別にわかりやすく解説
更新日: 2024.5.23
公開日: 2022.4.18
jinjer Blog 編集部
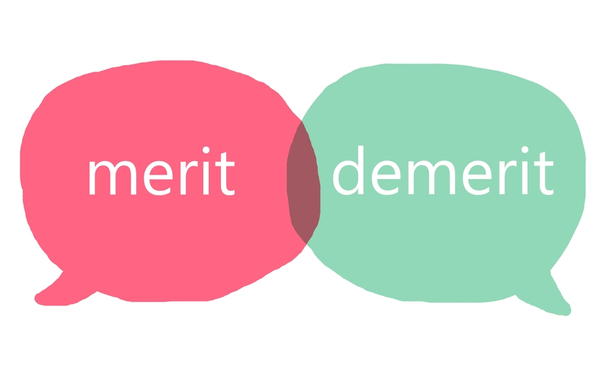
会計基準は、損益計算書や貸借対照表などの財務諸表の作成際に重要なものです。
会社法や金融商品取引法でも定められているように、一般に公正妥当な企業会計の慣行に従うためには会計基準に則った財務諸表を作成しなくてはなりません。
日本企業に馴染みが深いのは日本会計基準ですが、海外進出する企業にとっては国際会計基準など海外で認められた会計基準の採用が必須です。
今回は日本会計基準と国際会計基準の違いや、国際会計基準導入のメリット・デメリットについて解説します。
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 会計基準とは?について分かりやすく解説


そのため、企業は会計基準に則った財務諸表を作成する必要があります。
日本には現在4つの会計基準が存在するため、各企業は自社にあった基準を選択して財務諸表を作成します。
2. 日本で認められている会計基準は4つ


日本で認められている会計基準は以下の4つです。
- 日本会計基準
- 米国会計基準
- 国際会計基準(IFRS)
- J -IFRS
| 会計基準 | 特徴 | 導入傾向 |
| 日本会計基準 | 日本独自の基準 | 多くの日本基準 |
| 米国会計基準 | アメリカで採用されている会計基準 | アメリカで上場している企業 |
| 国際会計基準(IFRS) | 世界共通の会計基準を目指して国際会計審議会が作成 |
・海外の投資家から資金調達をおこないたい企業 ・海外に子会社が多い企業 |
| J-IFRS | 国際会計基準の日本版 | ・IFRSへの移行に積極的だが、ピュアIFRSへの移行に懸念がある企業 |
ここからは、それぞれの会計基準について一つずつ、解説していきます。
2-1. 日本会計基準
日本会計基準は日本独自の基準で、企業会計原則(1949年公表)をベースにしたものです。
2001年からは企業会計基準委員会が社会の変化に合わせて会計基準を設定しています。
日本の企業にもっとも馴染みのある会計基準であり、一般的な国内企業は日本会計基準を採用しているケースがほとんどです。
しかし、国際市場では影響力が低く、アメリカのように日本会計基準で作成された財務諸表を認めていない国もあります。
2-2. 米国会計基準
米国会計基準はアメリカで採用されている会計基準で、米国内で上場している日本企業はこの会計基準に基づいた財務諸表の作成が義務付けられています。
米国財務会計基準審議会(FASB)が発行しているもので、財務会計と税務会計が独立し、それぞれ都合のいい基準を選べるのが特徴です。
2-3. 国際会計基準(IFRS)
国際会計基準(IFRS=International Financial Reporting Standards)は、国際会計基準審議会が世界共通の会計基準を目指して作成されました。
2005年からEU域内の上場企業に対して導入が義務化されており、海外に子会社が多数ある企業にとっては採用必須な会計基準です。
2-4. J-IFRS
J-IFRS(JMIS/修正国際基準とも呼ばれる)は国際会計基準の日本版と位置付けられるもので、2016年3月期末より適用されています。
のれんの償却など、IFRSへの移行の懸念点となる要素を日本会計基準に寄せて計上できるのが特徴です。
国際会計基準の内容を日本国内の経済状況に合わせて調整したものですが、国際会計基準で得られるメリットは少なくなってしまうのが難点です。
3. 日本会計基準と国際会計基準(IFRS)の違いは3つ


日本会計基準と国際会計基準には3つの違いがあります。
3-1. 主義が異なる
日本会計基準は細則主義で、国際会計基準は原則主義で作られています。
細則主義は、処理方法が細部までしっかり決められているため、ブレが生じにくく企業間でも比較しやすいでしょう。
しかし、細則主義は形式的に要件を満たしやすく、粉飾決算の温床となりやすいのが難点です。
一方で国際会計基準は原則主義の考え方から、基本的な枠組みだけを規定して細部は企業ごとに基準の趣旨を変えられます。
会計処理の担当者が会計基準を理解していれば、その企業に最適な会計処理が採用できますが、同じ取引でも企業によって処理が異なる可能性があります。
関連記事:会計公準とは?3つの原則と7つの一般原則について解説
3-2. 収益認識基準(売上計上基準)が異なる
日本会計基準では、収益が実現した時点で計上する実現主義が採用されています。
国際会計基準では、履行義務が充足された時点で収益と認識されます。
ただし、2021年4月1日以降に開始する事業年度の期首より、日本会計基準でも履行義務充足時点で収益を認識(企業会計基準第29号・収益認識に関する会計基準の強制適用による)するようになりました。
関連記事:会計期間(事業年度)とは?決める際のポイントや累計期間との違いを解説
3-3. 会計的思考が異なる
会計的思考において、日本会計基準では損益計算書を重視する収益費用アプローチを、国際会計基準では貸借対照表を重視する資産負債アプローチをとっています。
国際会計基準では、資産から負債を差し引いた純資産を利益と考えます。
他にも固定資産の耐用年数では、日本会計基準は法人税法の耐用年数が採用されるのに対して、国際会計基準では企業が固定資産を使用する予定の期間と定められています。
また、老舗などの「のれん」に対しては日本会計基準では20年以内で減価償却が認められていますが、国際会計基準では非償却などの違いがあります。
重視する部分が異なるため、さまざまなケースで必要な経理処理も変わってくるため注意が必要です。
関連記事:会計とは?業務の流れや経理・財務・簿記との違いを解説
4. 日本における会計基準の動向と改正


経済のグローバル化が進み会計基準の収斂が進んでいます。2005年、EU圏内の上場企業にIFRSの導入が義務付けられてから、金融庁は上場企業に対するIFRSの導入促進を積極的に進めています。
日本における近年の会計基準の動向を見ていきましょう。
4-1. 会計基準をめぐる動向
日本政府の動向は以下の通りです。
| 年 | 出来事 | 概要や影響 |
| 2007 |
ASBJ及びIASB「東京合意」 |
日本の会計基準をIFRSに収斂(コンバージェンス)させる方針を発表 |
| 2009 |
企業会計審議会「我が国における国際会計基準の取扱い(中間報告)」 |
・IFRS強制適用も視野に入れつつIFRS任意適用を開始 ・連結財務諸表のみIFRSを適用 ・米国会計基準の使用期限(2016年3月末)の設定 |
| 2011 | 金融担当大臣談話「IFRS適用に関する検討について」 |
・東日本大震災の影響も踏まえIFRSの強制適用見送りを発表 ・米国会計基準の使用期限を撤廃 |
| 2013 |
企業会計審議会「国際会計基準への対応のあり方に関する当面の方針(当面の方針)」 |
・IFRSの強制適用の再検討の必要性の提示 ・IFRS任意適用企業数の引き上げに注力する方針の発表 ・JMISの導入 ・単体開示の簡素化 |
| 2014~2016 | 日本再興戦略の閣議決定と各年における改定 |
IFRSの任意適用企業拡大 |
| 2017~2018 | 未来成長戦略の閣議決定と改定 | 日本再興戦略とほぼ同義 |
| 2018 | 「収益認識に関する会計基準」の公表 | 「収益認識に関する会計基準」IFRS-15の強制適用時期を決定 |
| 2021 | 上場企業及び上場準備企業に対して「収益認識に関する会計基準」IFRS-15の強制適用開始 | 企業は財務諸表作成時の会計基準に関わらず、収益認識のために顧客との契約に基づく取引に関してはIFRS-15に則った収支報告をおこなう義務が発生 |
4-2. 会計基準の改正に伴う変化
「収益認識に関する会計基準」だけでなく、「時価の算出に関する会計基準」でもIFRSの一部項目を適用して算出するように会計基準を改正する動きが見られます。
これによって、対象となる大企業は自社の財務諸表作成時の会計基準に関わらず、一部の項目に対しては強制的にIFRSを適用した報告をおこなう必要が出てきます。
つまり、IFRSを導入していない企業については収支報告書類の作成が二度手間になってしまうことになります。そのため強制適用を機に会計基準をIFRSに変更する企業が増えることが期待されています。
中小企業については現状会計基準の変更の必要はありませんが、大企業の子会社等は上記の対象に含まれているため、注意が必要です。
5. 国際会計基準(IFRS)を導入する3つのメリット


国際会計基準を導入するメリットは以下のとおりです。
5-1. 国外子会社の財務情報がわかりやすく把握できる
日本国内では日本会計基準、国外の子会社では国際会計基準を採用する場合、財務情報の把握が難しくなるでしょう。
国内外どちらも国際会計基準に統一することで、均一で正確な財務情報の比較が可能となり、運営方針も決めやすくなります。
5-2. 海外向けに財務諸表の書き換えが不要
国際取引に関する財務諸表を作成する場合、日本会計基準では認められないため、その都度書き換えが必要です。
世界標準である国際会計基準を導入することで、相手国の会計基準に合わせて変換することなく提出可能となります。
事務コストも抑えられます。
5-3. 海外からの資金調達が期待できる
投資家は企業の財務諸表をみて投資を決めるため、世界基準の会計基準が適用された財務諸表を作成することで、海外の投資家からの理解も得やすくなるでしょう。
資金調達の幅が広がることも期待できます。
6. 国際会計基準(IFRS)を導入する3つのデメリット


国際会計基準を導入することで考えられるデメリットは以下のとおりです。
6-1. 適用まで時間・コスト・労力がかかる
現状の会計基準を変更することで財務システムの変更も必要です。
また、馴染みが薄く難しい会計制度や英語などを理解するために担当者の教育のために専門家を雇用するなど時間やコストがかかるでしょう。
6-2. 財務報告の変換が必要
国際会計基準を適用していても、個別財務諸表を日本基準で作成する必要があります。
日本基準で作成した個別財務諸表を国際会計基準に変換する必要もあるため、時間と労力面で事務処理担当者の負担が大きくなるでしょう。
また、国際会計基準は原則主義であるため、説明責任を果たすために大量の注記が求められたり、日本基準で会計処理を行っている他者との比較が難しくなります。
関連記事:会計報告書の書き方は?部活や町内会で必要な際の記載項目も解説
6-3. 資産や負債の範囲が広くなる
国際会計基準を導入する際は、今までの基準では不要だった資産も範囲に含まれます。
資産を時価で評価し直す必要もあるため、負担が大きくなるでしょう。
7. 国外との取引をする場合は国際会計基準(IFRS)の導入が必須


現在日本で認められている会計基準は4つあり、国外へ進出したり、海外企業と取引する場合には世界標準の会計基準である国際会計基準の導入が必須です。
日本企業に馴染みの深い日本会計基準とは異なる点も多く、導入コストや時間・労力は大きくデメリットも多いですが、海外投資家からの資金調達が期待できるなどのメリットも大きいでしょう。
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
経費管理のピックアップ
-


電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-


小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-


経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04





















