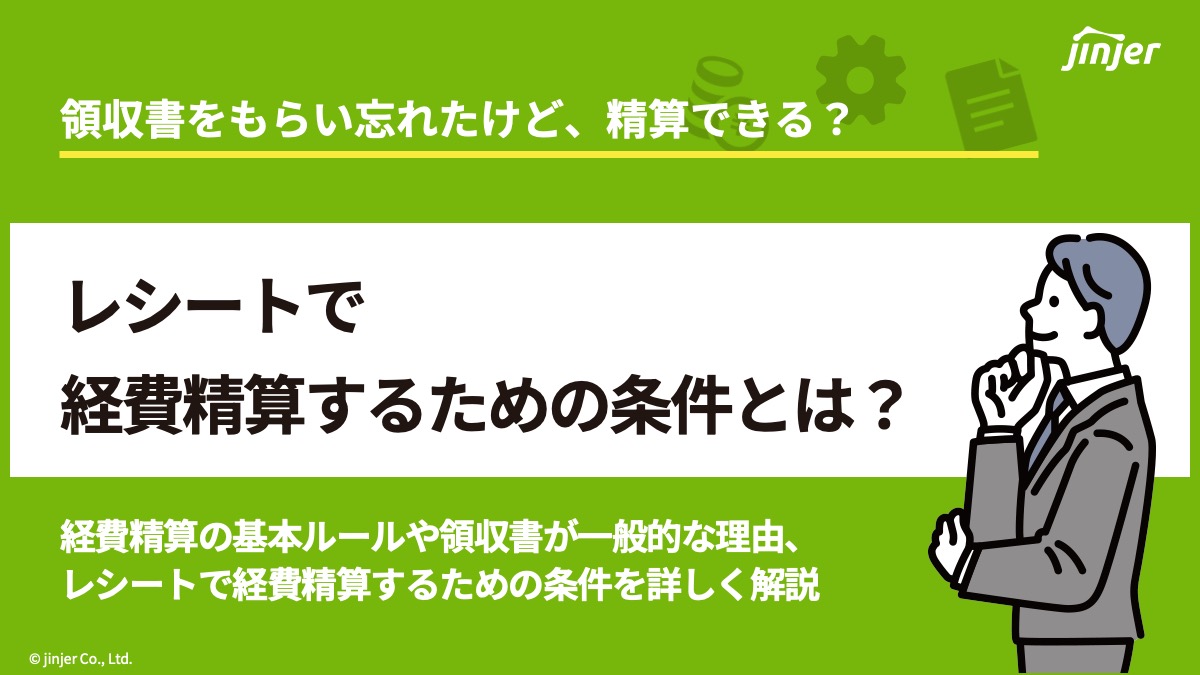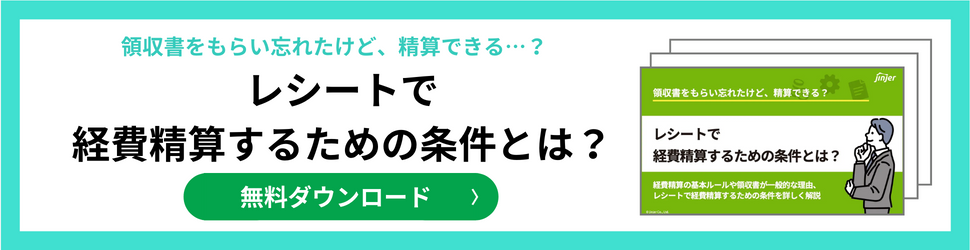レシートは領収書の代わりにできる?違いや法的効力を解説
更新日: 2024.3.8
公開日: 2021.1.12
jinjer Blog 編集部

多くの会社では経費精算に領収書の提出が求められ、レシートだと受け付けてもらえないことも珍しくはありません。
しかし、実はレシートであっても経費精算に使える場合があるのです。
本記事では、レシートと領収書の違いと、経理上・税法上での取り扱いについて解説します。
こんなとき、レシートで精算しても良いの?
経費は領収書で精算することが一般的ですが、なかには「領収書をもらい忘れて、レシートしか手元にない…」と相談しにくる従業員もいるでしょう。
どちらも、お金のやり取りを証明する書類であり、レシートで精算しても問題ないように感じるかもしれません。
しかし、消費税法では「証憑書類には宛名が必要」としています。そのため、原則として宛名のない領収書では精算できないことに注意しましょう。
とはいえ、一定の条件を満たせば、レシートであっても経費精算できる場合があります。
「レシートで精算できる場合の例を知りたい」
「レシートと領収書の違いを知りたい」
「宛名がない場合は領収書でも精算できないの?」
など、経費精算をおこなう際の基礎知識を詳しく解説しています。経費精算の流れについても解説しているので、興味がある方はぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
目次
1. レシートと領収書の違い
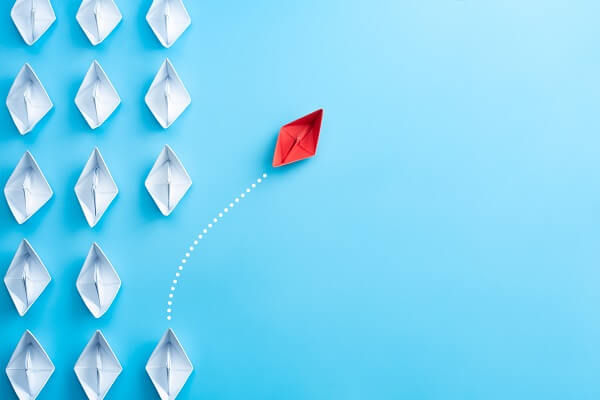
レシートと領収書を英語で表記すると、どちらも「receipt」といいます。このことから分かるように、海外ではレシートも、領収書も同じ意味のものなのです。実際、アメリカやイギリスなど多くの国では、小売店やタクシーを利用した際に、領収書が発行されることはありません。
領収書は「日本ならではの文化」なわけですが、レシートとどこが異なるのかというと、それは「記載内容」です。
レシートには店名、日付、購入(利用)した商品(サービス)の品目、単価などが印字されます。対して、領収書にはレシートに印字される情報に加えて「宛名(購入者は誰なのか)」が記載されます。この「宛名の有無」がレシートと領収書の大きな違いです。
2. レシートにおける経理上、税法上の考え方

多くの会社では経費精算に「領収書が必須」とされます。
そのため、「領収書じゃないとダメ……」と認識している方が多いようですが、実は、レシートが使える場合もあります。
2-1. 経理上は領収書もレシートも有効
経理上、領収書もレシートも有効になる場合が極めて多いです。
注意点として、会社の規則で領収書のみという記載がある場合は領収書を発行する必要があるので、会社の規則を確認しておきましょう。
2-2. 消費税法上では経費書類に「宛名」が求められる
消費税法において、経費精算に必要な証拠書類には、以下の要件が定められています。
- 書類作成者の氏名又は名称(店名)
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(宛名)
つまり、経費精算には「原則として宛先が必要」とされているわけです。
関連記事:宛名なしの領収書って経理や法律上まずい?ケースごとに解説
2-3. 「宛名」を省略してもいい場合がある
ただし、「宛名」の必要性については例外が存在しています。
例えば、以下の業種を利用した際の領収書に関しては、宛名が記載されていなくても大丈夫です。
- 小売業
- 旅客運送業
- 旅行業
- 飲食業
- 駐車場業
つまり、コンビニでの買い物や、取引先との会食、タクシーでの移動など日常の多くの場合では、領収書を発行してもらわなくても、レシートで十分に代用できます。
2-4. 「お買い上げ票」なども領収書の代わりとして使える
国税庁が公開している「金銭又は有価証券の受取書、領収書」によると、レシートの他にも領収書の代わりとして、受領事実を証明できる証拠書類がいくつかあります。
- 受取書
- 領収証
- 預り書
- お買い上げ票
- 「代済」「相済」「了」などと記載された請求書や納品書
領収書が発行されないなどで領収書を保管することが難しい場合は、これらの書類を保管するようにしましょう。
2-5. レシートの方が証拠書類として信憑性が高いことがある
記載内容によっては、領収書の証拠書類としての信憑性が疑われる場合があります。
例えば、宛名が「上様」や、詳細が「お品代」と記載内容が省略されている場合です。
その点、レシートには宛名はないものの、店名、日付、品目、単価など証拠書類として必要な項目が機械的に印字されます。
人の手による「改ざんの可能性がない」ことから、記載内容が省略されている領収書よりも、レシートの方が税務調査では疑われることがありません。
参照:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁
3. 会社がレシートより領収書を重視する理由
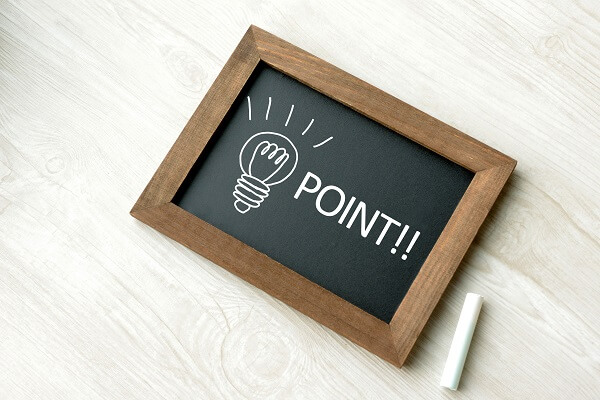
消費税法上は経費精算の際にレシートが使える場合が多々あるわけですが、それでも多くの会社が領収書を重視しています。
その理由としては、税務調査での対策が関係してきます。
3-1. 飲食のレシートは本当に会社で利用したかを疑われやすい
コンビニでの買い物やタクシーでの移動などでは、レシートでもまず問題ありません。しかし、小売や運送などと同様に「宛名が不要」なはずの飲食に関しては注意が必要です。
というのも、取引先との会食があまりに高額であったり、頻繁に開催されていたりすると、税務官から本当に会社に関係しての飲食なのかを疑われることがあります。場合によっては、税務署から対象の飲食店に問い合わせなどがあり、調査期間の長引くこともあるでしょう。
そのため、税務調査で不要な疑いをかけられないよう、調査期間の長引くことがないよう、あらかじめ経費精算には宛名のある「領収書が必須」としている会社が多いわけです。
このように、経費精算において領収書が必要な理由は様々あります。
しかし、「領収書には明細がないので、仕訳がしにくい」という悩みや「私用のものも混じっているのでは?」と疑われる領収書もあるでしょう。
そこで当サイトでは、レシートで経費精算できる条件をまとめた資料を用意しました。「できればレシートで経費精算したい」と思っている方はもちろん、領収書の紛失や宛名が空欄だった場合などのイレギュラー対応について知りたい方にもおすすめです。
レシートと領収書の違いやレシートや領収書以外で証憑にできる書類についても詳しく解説しているので、興味のある方はぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。
4. レシートと領収書の保存期間は原則7年

レシートであれ、領収書であれ、1人分でも相当な枚数になります。
それが会社規模ともなると保管管理をどうするのかが問題です。
しかし、領収書は「証憑書類(取引を証明する書類)」とされ、一定期間の保管が義務付けられているため、勝手に破棄することはできません。
では、いつまで保管する必要があるのかですが、法人の場合は会社規模に関わらず「7年間」になります。
ただし、ここで注意したいのが、この「7年間」というのはレシートや領収書が発行されてからではなくて「法人税申告期限(決済日の翌日から2ヶ月後)」からの期間です。
また、個人事業主の場合は青色申告の方だと法人と同様に「7年間」、白色申告の方だと「5年間」となります。
青色申告の方でも前々年の所得が300万円以下の場合は、白色申告と同様に「5年以下」です。
そして、青色申告・白色申告いずれの場合も「確定申告の期日」を起点に保管しなければならないので、注意しましょう。
関連記事:領収書の保管期間は5~10年!知らないとまずい基礎知識
4-1. 過去の領収書を電子保存する場合は、事前に税務署に申告が必要
電子帳簿保存法により、紙で受領した領収書もスキャナ保存することができます。
以前は事前に申請書を提出しなければ保存できず、スキャナ読み込みできる期限も短かったため、紙媒体での保管が一般的でした。
しかし、2020年の改正後は申請不要でスキャナ保存できるようになっただけでなく、入力期間も最長2ヶ月と7日間に延長されたため、電子データで保存するハードルが下がったと言えるでしょう。
ただし、電子保存を開始する前に作成・受領した書類(過去分重要書類)を電子保存する場合は、引き続き税務署長の承認を得る必要があります。
参考記事:【2023年版】電子帳簿保存法とは?概要と改正内容をわかりやすく解説
5. レシートでも経費精算に使えるケースがある

本稿では、経費精算に関して、レシートと領収書の違いについてまとめてきました。
レシートと領収書の大きな違いは、記載内容に「宛名」があるのか、ないのかです。
そして、小売・旅客運送・旅行・飲食・駐車場の利用では、レシートも証拠書類として使えるとのことでした。
つまり、コンビニでの買い物やタクシーでの移動など、日常の多くの場合ではレシートで十分なわけです。
しかし、会社によっては税務調査をスムーズに進めるために、宛名のある「領収書が必須」としている場合も多く、基本的には会社内のルールに則ることが求められます。
こんなとき、レシートで精算しても良いの?
経費は領収書で精算することが一般的ですが、なかには「領収書をもらい忘れて、レシートしか手元にない…」と相談しにくる従業員もいるでしょう。
どちらも、お金のやり取りを証明する書類であり、レシートで精算しても問題ないように感じるかもしれません。
しかし、消費税法では「証憑書類には宛名が必要」としています。そのため、原則として宛名のない領収書では精算できないことに注意しましょう。
とはいえ、一定の条件を満たせば、レシートであっても経費精算できる場合があります。
「レシートで精算できる場合の例を知りたい」
「レシートと領収書の違いを知りたい」
「宛名がない場合は領収書でも精算できないの?」
など、経費精算をおこなう際の基礎知識を詳しく解説しています。経費精算の流れについても解説しているので、興味がある方はぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
経費管理のピックアップ
-


電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-


小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-


経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04