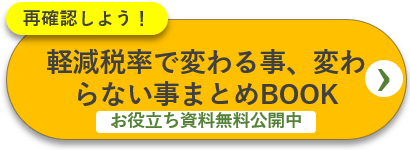軽減税率におけるレシート。記載なしや記載ミスの対応方法を解説
更新日: 2024.4.5
公開日: 2020.12.21
jinjer Blog 編集部

軽減税率が導入されたことによって、事業者にはさまざまな対応が求められています。軽減税率に対応したレシートに変更することも、事業者がおこなうべき対応のひとつです。
しかし、慣れない軽減税率によって、記載のミスや記載漏れも発生してしまうこともあるかと思います。また、8%と10%2種類の税率があることで、どのようなレシートを発行したらよいのか悩んでいる事業者も多いでしょう。
この記事では、軽減税率の記載漏れや記載ミスの対応方法や、軽減税率によるレシートの記載内容の変更点、複数税率に対応したレシートを発行するためのポイントなどを解説していきます。
2019年10月に軽減税率制度が実施されました。
軽減税率の導入によって、経理業務に変化を強いられた企業も多いのではないでしょうか。
その中で、「軽減税率が導入されたけど、結局経理業務の何が変わって何が今までと変わってないんだ・・・?」と疑問を抱いている方も少なくないでしょう。
そのような方のために、今回軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをご用意いたしました。
資料には、以下のようなことがまとめられています。
・軽減税率制度の概要について
・軽減税率導入によって変化する経理業務
・引き続き管理しなければならない経理業務
軽減税率導入後の変化を簡単に理解して対応ができるように、ぜひ、軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをご参考にください。
1. 軽減税率の導入によって変わったレシートの記載内容


軽減税率が導入される前のレシートには、取引年月日や発行者の名称とともに、購入された商品名とその金額だけを記載すれば問題ありませんでした。
しかし、2019年10月1日以降は、軽減税率制度に対応したレシートを発行しなければなりません。ここでは、軽減税率導入後の正しいレシートの書き方を解説します。
1-1. 軽減税率の対象品目を明記して税率ごとの合計金額
2019年10月1日以降は、区分記載請求書等保存方式に従ってレシートを発行するのが基本です。
この方式では、軽減税率の対象品目に「※」などのマークを付け、「※は軽減税率対象品目」といった説明を記載することが求められます。
どのようなマークを使用するかについての決まりはないため、「軽」「軽減」といったマークを付けても問題ありません。
区分記載請求書等保存方式では、税率8%のものと税率10%のもの、それぞれの税込合計金額を表示することも求められています。
軽減税率導入前と同様、取引年月日や発行者の名称なども記載しましょう。この方式に従ってレシートを発行すると、以下のような形式になります。
| きゅうり(※) ¥108
じゃがいも(※) ¥216 ピーマン(※) ¥108 ミネラルウォーター(※) ¥108 ビール ¥210 ———————————– 10%対象 ¥210 8%対象 ¥540 合計 ¥750 お預り ¥1,000 お釣り ¥250 ※印は軽減税率対象品目 |
関連記事:軽減税率の導入で領収書に記載なしの項目・記載ありの項目
1-2. 適格請求書発行事業者の名称などを記載する
2023年10月1日よりインボイス制度が導入されているため、請求書の保存方式は「区分記載請求書等保存方式」から「適格請求書等保存方式」に変更されています。
適格請求書等保存方式では、区分記載請求書等保存方式よりも細かな内容を記載する必要があります。従来の項目に加え、以下の内容を記載しなければなりません。
- 登録番号(適格請求書発行事業者のもの)
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
従来の区分記載請求書にこれらの項目を加えれば、適格請求書の要件を満たすことができます。適格請求書発行事業者の登録番号に関しては、消費税の課税事業者が税務署にて登録することで発行してもらえます。ただし、小規模な業者や個人事業主で、消費税の課税事業者ではない場合は登録番号を発行してもらえません。
発行されないと登録番号を記載できないため、インボイス方式による正式なレシートは作成できないことを覚えておきましょう。
参考:No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)|国税庁
2. 軽減税率のレシート対応で必要なこと


軽減税率制度では、取り扱う商品を軽減税率対象商品と対象外商品で区別しなければなりません。また、飲食店の場合は、テイクアウト(お持ち帰り)は軽減税率対象、店内での飲食は対象外となっているため、レシート内容も複雑になっています。
ほとんどの場合、レジに打ち込めば自動的に区別されますが、新たに事業を始めた方やあいまいなまま対応している場合は、レシートのミスが発生するリスクがあるため注意が必要です。ここでは、基本となるレシート対応を紹介します。
2-1. 軽減率対象・対象外の商品を確認
もっとも基本的なことですが、まずは取り扱っている商品が軽減率対象商品なのか、対象外の商品なのかを確認しましょう。
対象外商品は幅が広いので、対象商品を重点的に確認することが重要です。軽減率対象商品は下記の2つになります。
- 酒類・外食を除く飲食料品
- 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
この2つの対象商品の中で、もっともわかりづらいのが「酒類・外食を除く飲食料品」です。
「酒類」にあたるのは、アルコール度数1%以上のものすべてなので、基本的にノンアルコール以外の酒類は対象外となります。ここで複雑になるのが、アルコール度数1%以上の「みりん」は標準消費税(10%)で、1%以下の「みりん風調味料」は軽減税率対象商品となることです。また、おもちゃやおまけなどとセットになっている飲食料品で、価格が税込10,000円を超えているもの、もしくは飲食料品の価値が付録の1/3未満の「一体資産」となる商品も軽減税率対象外商品となるので注意しましょう。
「外食」はレストランやフードコートなどでの飲食だけでなく、ケータリングや出張料理サービスも該当します。また、医薬品や医薬部外品、医療再生品等は「飲食料品」の該当しないので、10%の課税が必要です。
2-2. 担当者への周知
軽減税率制度は、実際にレジで対応する従業員やレシート管理、仕入担当者、経理業務をおこなう従業員なども理解しておく必要があります。
例えば、レジが故障した場合、レジ対応の従業員は手作業で入力をしなければなりません。このとき、炯然税率対象商品と対象外商品を理解していないと、税率を間違えてしまう可能性があります。仕入れのレシートの税率が間違っていた場合でも、経理担当者が理解していなければ、間違いに気が付きません。そのため、「軽減税率」の区別については担当者への周知を徹底することが重要です。
また、テイクアウトできる商品を販売している場合、同じ商品でも店内飲食とテイクアウトで税率は変わります。お客様の中には、「店内で少し食べて後はお持ち帰りをするから消費税は8%」と考える人もいるかもしれません。
しかし、例え少しでも店内飲食をするのであれば10%課税になります。税率に「お持ち帰りの量」は関係ないので、精算時に課税率が決まることもしっかり周知しておきましょう。
3. 軽減税率を間違えたレシートへの対処法

正しい税率が記載されていないレシートを受け取った場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
ここでは、軽減税率の間違いやトラブルが起きたケースを想定し、仕入者が取るべき2つの対応を紹介します。
3-1. レシートに軽減税率の「記載がない」場合
軽減税率の導入にともない、レシートや請求書は「区分記載請求書等保存方式」か「適格請求書等保存方式」に準じた様式で作成する必要があります。
2023年9月30日までは区分記載請求書、2023年10月1日からは適格請求書への移行が必要です。たとえば、区分記載請求書の場合、以下のような要件があります。
- 軽減税率の対象品目がどれかわかるようにする
- 軽減税率・標準税率それぞれの小計を記載する
もし、相手方から受け取ったレシートや請求書に、上記いずれかの「記載がない」場合、相手方に再発行を求める必要があります。ただし、軽減税率の「記載がない」場合に限り、請求書を受け取った事業者が追記をおこなうことも可能です。
3-2. レシートに軽減税率の「誤りがある」場合
それでは、相手方から受け取ったレシートや請求書の軽減税率の計算に「誤りがある」場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。
軽減税率の「記載がない」場合と違い、「誤りがある」場合は事業者側での追記対応ができません。そのため、相手先にレシートや請求書を再発行してもらう必要があります。
しかし、正しい軽減税率が記載された請求書が再発行されない場合、原則として仕入税額控除を受けられません。
ただし、次の2つの条件のいずれかに当てはまる場合、「請求書」ではなく「帳簿」のみを保存することで、仕入税額控除を受けられるケースがあります。
請求書の支払い対価が3万円未満の場合
請求書を受け取った事業者が、正しい税率で帳簿に記帳するだけでよい
請求書の支払い対価が3万円以上の場合
正しい税率で帳簿に記帳するだけでなく、請求書の再発行ができなかった「やむをえない理由」と、相手先の「住所または所在地」の2点を記載する
関連記事:軽減税率を間違えた(間違えられた)場合どうすればいいの?対処方法を解説
4. 軽減税率制度を理解して正しいレシートを発行しよう!

軽減税率制度の導入により、日本で初めての複数税率が実施されています。軽減税率の対象商品は、項目だけで見ると2つですが、商品の規定が細かく決められているので、理解して把握するためには時間がかかることもあるかもしれません。
また、2023年10月からはインボイス制度も導入されたため、レシートに記載する必要事項が増えたり、適格請求書発行事業者の登録をしなければならくなったり、さらなる対応が必要となっています。
レシートには軽減税率の対象品目を明示することや、それぞれの税率の合計金額を表示することなどが求められるため、複数税率に対応したレジを導入したうえで、レジ担当者の教育もしっかりとおこないましょう。
関連記事:【2021年最新版】軽減税率はいつまで?6月情報に注意!今後の流れを解説
軽減税率はすべての企業が関係します!
2019年に制定された軽減税率制度によって、税率が混在した経費処理が必要になりました。軽減税率でこれまでよりも仕訳が複雑になることに加えて、引き続き手間に感じている業務も続けなくてはなりません。
また、2023年にはインボイス制度への対応が待ち受けており、今後も対応しなければならないことが増え続けるでしょう。
「軽減税率をしっかりと理解した上で、今後どのような管理が必要なんだろう・・・」とお悩みの方は軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをぜひご覧ください。
資料では
・軽減税率制度の概要について
・軽減税率導入で変わること、変わらないこと
・今後、手間をかけずに経理業務の効率化を進めるための方法
など、軽減税率をはじめとした経理業務の効率化に関する内容を総まとめで解説しています。
「軽減税率の導入で経理業務の何が変化し、どのような管理が今後も必要になるのか知りたい」という経理担当者様は軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをぜひご覧ください。。
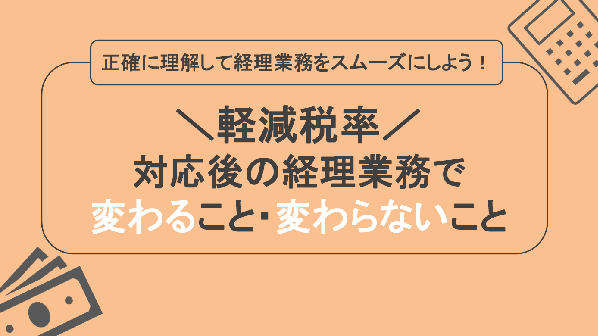
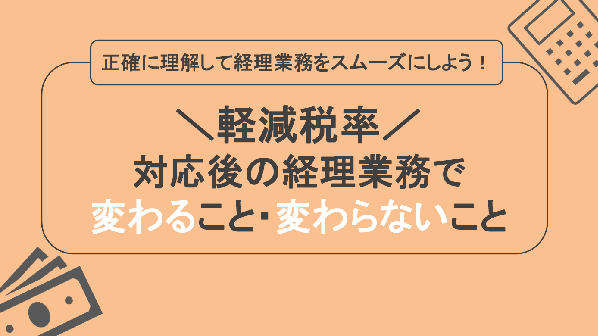
経費管理のピックアップ
-


電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-


小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-


経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04