軽減税率の導入による簡易課税制度への影響を解説
更新日: 2024.3.8
公開日: 2020.12.1
jinjer Blog 編集部
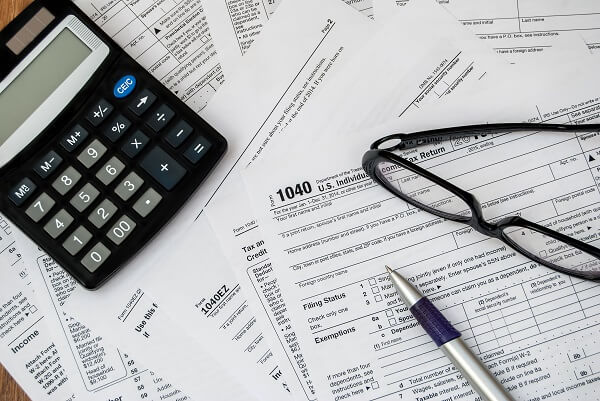
2019年10月1日から軽減税率制度が導入されたことにより、消費税の納付金額の計算方法も変更されました。
軽減税率制度においては、10%と8%という2つの税率が存在するため、それぞれの税率に分けて計算したうえで合計するのが基本です。
この記事では、軽減税率の導入による簡易課税制度への影響や、計算方法の変化について詳しく解説します。正しい税額を算出できるよう、ぜひチェックしておきましょう。
2019年10月に軽減税率制度が実施されました。
軽減税率の導入によって、経理業務に変化を強いられた企業も多いのではないでしょうか。
その中で、「軽減税率が導入されたけど、結局経理業務の何が変わって何が今までと変わってないんだ・・・?」と疑問を抱いている方も少なくないでしょう。
そのような方のために、今回軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをご用意いたしました。
資料には、以下のようなことがまとめられています。
・軽減税率制度の概要について
・軽減税率導入によって変化する経理業務
・引き続き管理しなければならない経理業務
軽減税率導入後の変化を簡単に理解して対応ができるように、ぜひ、軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをご参考にください。
1. 簡易課税制度とは


まずは簡易課税制度がどのようなものか、正しく知っておきましょう。必ずしも簡易課税制度を選択するのがよいとは限らず、事業規模や売上に合わせて選ぶことが大切です。
1-1. 中小事業者の納税業務負担を減らす消費税の計算方法
簡易課税制度は、要件を満たした事業者に限定して「みなし仕入れ率」を使って消費税額を計算できる制度です。
消費税の原則課税(一般課税・本則課税)では、売り上げにかかる消費税額から仕入れの消費税額を控除し、差額を納付する必要があります。
一方で簡易課税では売上の消費税額を基準に簡単に仕入れの消費税額を算出できるようになり、消費税に関連する業務負担を大きく減らすことが可能です。
しかし、還元が受けられない点や納税額が増える可能性があることなど、デメリットも存在します。
1-2. 軽減税率の導入による税率の変化
簡易課税制度を利用する場合は、軽減税率の影響を受けることはありません。軽減税率が導入される依然と同様に、みなし仕入れ率を使って計算します。
ただし、農業・林業・漁業の3業種で、軽減税率の対象になる品目を取り扱う場合は、仕入れ率が70%から80%に変更されています。
この点には注意して計算をするようにしましょう。
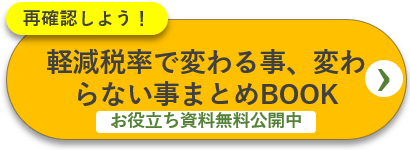
2. 簡易課税制度を利用するメリットとデメリット


簡易課税制度は適した活用をすれば業務負担を軽減できる制度です。しかし、デメリットもあることを知り、原則課税と簡易課税のどちらを選ぶか十分に検討しましょう。
2-1. 簡易課税制度を利用するメリット
簡易課税制度を利用するメリットとしてまず挙げられるのは、消費税に関連する事務作業が軽減できるという点です。
前項でも少し触れたように、簡易課税制度ではみなし仕入れ率を使いシンプルな計算で消費税の納税額を算出できます。
原則課税では消費税の非課税取引を除外する必要がありましたが、この作業がなくなるだけでも経理担当者の業務負担は大きく変わるでしょう。
加えて、消費税の納税額も想定しやすくなります。
資金に余裕がない中小企業や、開業したばかりの企業にとってはこの点も経営を安定させるうえでのメリットになり得ます。
2-2. 簡易課税制度を利用するデメリット
簡易課税制度を利用するうえで知っておきたいデメリットは、原則課税よりも納税額が増える場合があるという点です。
業種や売り上げの規模、経費によって結果は変わりますが、簡易課税制度を利用しない方が節税になることも少なくありません。
また、事業を複数営んでいる場合は、業種別に異なるみなし仕入れ率を使って計算する必要があります。そのため、計算が複雑化するケースもあります。
3. 軽減税率に対応した原則課税と簡易課税の計算方法

納税すべき消費税額の計算方法は、原則課税と簡易課税に分けられます。ここでは、軽減税率に対応したそれぞれの計算方法をチェックしていきましょう。
3-1. 原則課税の計算方法
軽減税率導入後の原則課税の計算では、10%と8%それぞれの税率に分けて計算しなければなりません。具体的には以下の手順で計算します。
(1)売上税額を算出する
まずは、売上税額を以下のとおり計算します。
売上税額(軽減税率分)= 課税売上高(軽減税率分)× 6.24/108
売上税額(標準税率分)= 課税売上高(標準税率分)× 7.8/110
売上税額 = 売上税額(軽減税率分)+ 売上税額(標準税率分)
(2)仕入税額を算出する
次に、仕入税額を以下の計算式で算出します。
仕入税額(軽減税率分)= 課税仕入高(軽減税率分)× 6.24/108
仕入税額(標準税率分)= 課税仕入高(標準税率分)× 7.8/110
仕入税額 = 仕入税額(軽減税率分)+ 仕入税額(標準税率分)
海外との取引があった場合は、外国貨物の取引に係る消費税額を別途計算し、仕入税額に加算しなければなりません。
(3)納付税額を算出する
ここまでの計算が完了したら、最終的な納付税額を計算します。
消費税額 = 売上税額 – 仕入税額
地方消費税額 = 消費税額 × 22/78
納付税額 = 消費税額 + 地方消費税額
3-2. 簡易課税の計算方法
簡易課税における納付税額の計算には、軽減税率導入前と同様、みなし仕入率を用います。計算式も、以下のとおり軽減税率の導入前と同様です。
納付税額 = 課税売上に係る消費税額 – (課税売上に係る消費税額 × みなし仕入率)
みなし仕入率についても基本的には同じ数値を用いますが、第三種事業のなかの農業・林業・漁業で、軽減税率の対象となる品目を扱う業者については、仕入率が70%から80%へ変更されました。
4. 簡易課税制度を利用するための3つの要件

消費税の納付税額を簡単に計算できる簡易課税制度ですが、利用するためにはいくつかの要件を満たす必要があります。ここでは、満たすべき3つの要件を解説します。
4-1. 前々年または前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下
簡易課税制度は、課税売上高が5,000万円以下である事業者しか利用できません。簡易課税制度は、中小企業の事務的作業の負担軽減を目的としているためです。大企業などでは利用できないケースもあるため注意しましょう。
4-2. 事前に届出を提出している
簡易課税制度を利用するためには、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の税務署長へ提出しておかなければなりません。制度を利用したい課税期間の開始日の前日までに提出する必要があるため注意しましょう。
4-3. 基本的に2年間は変更できない
簡易課税制度を利用し始めた年度から2年間は変更できない、ということにも注意が必要です。消費税の納税について、事前に長期的な計画を立てておくことが重要です。
簡易課税制度と原則課税、どちらが適した方法であるかは、事業内容や会社の規模によっても異なります。
しっかりとシミュレーションをおこなったり、事業計画を立てたりして、最適な選択をしましょう。必要に応じて税理士などに相談してみることも大切です。
関連記事:軽減税率の導入によるメリット・デメリットを徹底解説
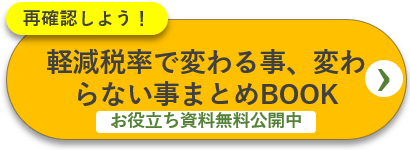
5. 簡易課税制度とインボイス制度
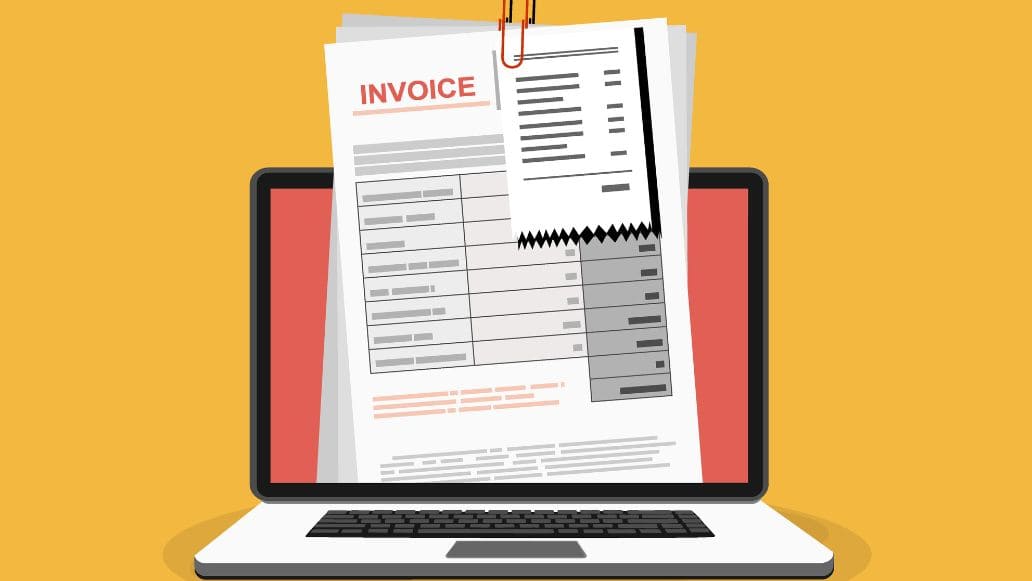
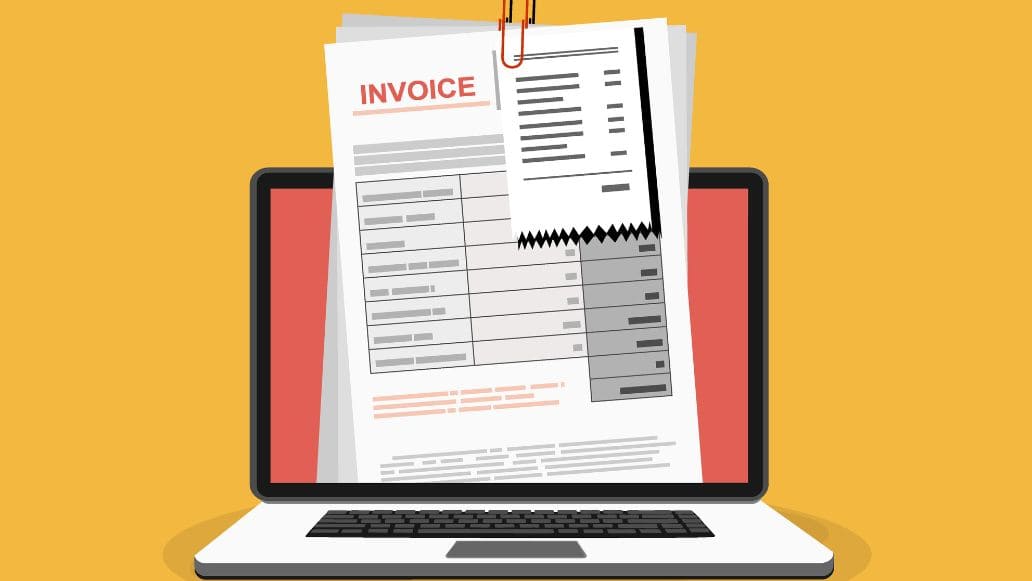
2023年10月から始まったインボイス制度は、簡易課税制度にも関係しています。
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるには適格請求書が必要です。しかし、すべての事業者が適格請求書を発行できるわけではありません。
適格請求書を発行できない免税事業者との取引では、取引相手は仕入税額控除を受けられません。そのため、免税事業者との取引が多い場合は仕入税額控除分の負担が大きくなる恐れがあります。
そのような場合や、適格請求書の発行依頼や保管の業務負担が大きい場合は、原則課税から簡易課税制度に切り替えた方がよい可能性があります。
インボイス制度の開始によって簡易課税制度に変更はありませんが、変化した仕入税額控除を受ける条件に気をつけて対応しなければいけません。
6. 簡易課税制度を利用する場合も軽減税率を正しく計算して納税しよう

今回は、軽減税率の導入による簡易課税制度の変化や計算方法について解説しました。10%と8%の税率があるため、簡易課税の計算においても一般課税の計算においても、複雑な処理が求められます。
軽減税率の対象となるかどうかについても細かな基準があるため、しっかりと把握しておかなければなりません。正しい納付税額を算出できるよう、軽減税率制度について理解を深めておきましょう。
関連記事:軽減税率の対策。補助金の内容や手続きについて詳しく紹介
軽減税率はすべての企業が関係します!
2019年に制定された軽減税率制度によって、税率が混在した経費処理が必要になりました。軽減税率でこれまでよりも仕訳が複雑になることに加えて、引き続き手間に感じている業務も続けなくてはなりません。
また、2023年にはインボイス制度への対応が待ち受けており、今後も対応しなければならないことが増え続けるでしょう。
「軽減税率をしっかりと理解した上で、今後どのような管理が必要なんだろう・・・」とお悩みの方は軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをぜひご覧ください。
資料では
・軽減税率制度の概要について
・軽減税率導入で変わること、変わらないこと
・今後、手間をかけずに経理業務の効率化を進めるための方法
など、軽減税率をはじめとした経理業務の効率化に関する内容を総まとめで解説しています。
「軽減税率の導入で経理業務の何が変化し、どのような管理が今後も必要になるのか知りたい」という経理担当者様は軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをぜひご覧ください。
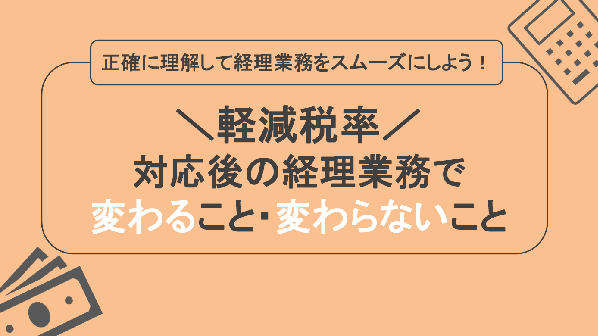
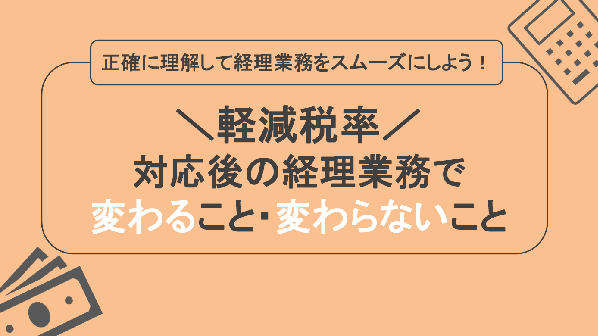
経費管理のピックアップ
-


電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-


小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-


経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04





















