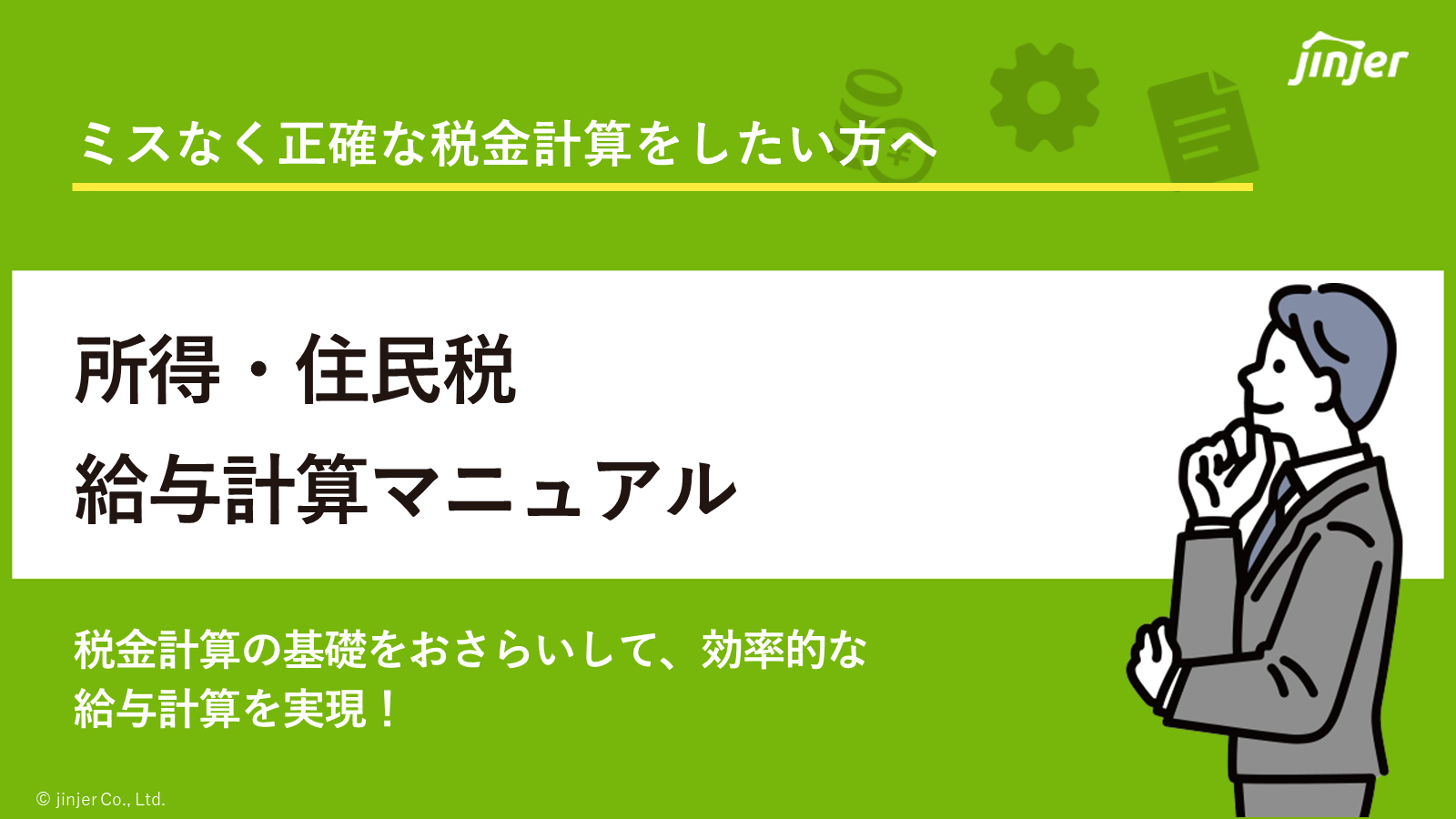所得税は年収いくらから?年収103万を超える場合や年収の壁について解説
更新日: 2024.3.5
公開日: 2022.3.17
OHSUGI

人事部や経理部署であれば、所得税がいくらからかかるかしっかり把握しておかなければなりません。
給与所得者における所得税は、年収103万円を超えた所得金額に対して課税されます。103万とは、基礎控除48万+給与所得控除55万円の合計額です。
年収103万円以上の収入を得た場合は、超えた分の金額に所得金額に応じた税率が適用された所得税が課せられます。また、年収103万円を超えると、106万、130万、150万円と、年収が上がるたびにさまざまな影響が発生します。
今回は、年収103万円を超えたときの所得税や、そのほかの年収の壁について解説します。
関連記事:所得税とは?納税方法や確定申告が必要な人・不要な人について解説
給与計算業務は税務リスクや労務リスクと隣り合わせであるため、
・税額が合っているか不安
・税率を正しく計上できているか不安
・自社に合った税金計算方法(システム導入?代行依頼?)がわからない
というような悩みをお持ちのご担当者様は多いと思います。
そのような方に向け、当サイトでは所得税と住民税の正しい計算方法、税金計算時によく起きるミスとその対策をまとめた資料を無料で配布しております。
本資料にて、税金計算のミスを減らしたり、効率化が図れる給与計算システムの解説もあるので、税金計算をミスなく効率的に行いたいという方は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 所得税は年収いくらまでかからない?
 所得税は、1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に対してかかる税金です。所得税がかかる年収のボーダーは103万円です。
所得税は、1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に対してかかる税金です。所得税がかかる年収のボーダーは103万円です。
パートやアルバイトなどで月収8万8,000円を超えてしまうと、毎月の給与から強制的に一定の所得税を徴収しますが、年収が103万円を超えていない場合は、年末調整の際に納めた所得税を還付しなくてはいけません。
1-1. 年収103万円以下なら基礎控除と給与所得控除で所得税がゼロになる
所得税には、扶養家族の人数や経済状況など、個人の事情を考慮して適用される所得控除という制度があります。その年の全ての所得から所得控除を差し引いた金額が課税対象となります。
所得控除には15種類あり、所得者の事情を考慮して税の負担を調整します。なかでも基礎控除は全ての所得者に適用される控除で、所得金額に応じて控除額が異なります。2,400万円までは48万円で、2,500万円を超えると控除額は0円です。
また、会社員や公務員、パート・アルバイトなどの給与所得者の場合は、給与所得控除が適用されます。給与所得控除の額は収入金額によって異なり、年収162万5,000円以下は55万円です。
基礎控除48万円+給与所得控除55万円=控除額103万円であることから、年収103万円以下は課税所得がゼロになり、所得税が発生しないということになります。
参考:所得税のしくみ|国税庁
2. 年収103万を超えると所得税はどうなる?
 年収103万円を超えた場合、所得金額に適用される所得控除や給与所得控除を差し引いた額が課税対象となり、所得税がかかります。所得税額は課税所得金額に応じた税率(5%〜45%)を適用して計算します。
年収103万円を超えた場合、所得金額に適用される所得控除や給与所得控除を差し引いた額が課税対象となり、所得税がかかります。所得税額は課税所得金額に応じた税率(5%〜45%)を適用して計算します。
たとえば、年収130万円の場合の所得税は、超えた27万円に対して税率5%をかけた1万3,500円です。なお、令和19年度までは、復興特別税として所得税額に2.1%が適用されます。
課税所得金額ごとの所得税の速算表は次のとおりです。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超1,8000万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
このほかにも、年収103万円の壁を超えることで、所得税に関してさまざまな影響が発生します。
参考:No.2260 所得税の税率|国税庁
関連記事:所得税率は所得金額で変わる!税率改定の影響や注意すべきポイント
2-1. 扶養控除から外れる
扶養控除とは、配偶者以外の所得税法上の控除対象扶養親族(16歳以上で生計を一にしている)がいる場合に受けられる所得控除です。
従業員の扶養家族に入っている子供がアルバイトで年間103万円以上の収入を得た場合、税制上の扶養から外れるため扶養控除が受けられなくなり、所得税や住民税が高くなります。
子供自身の所得税に関しては、子供が学生で一定の条件を満たしていれば、27万円の勤労学生控除が適用されるため、年収130万円まで所得税はかかりません。
扶養家族のいる従業員から、所得税の計算方法や年収の壁について相談を受ける可能性があるため、税金に関する知識は正しく覚えておきましょう。
また、当サイトでは、税金(所得・住民税)の計算方法や気を付けるべきポイントについて解説した資料を無料で配布しておりますので、税金に関する知識で不安な点があるご担当者様は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご確認ください。
3. 年収103万以外の壁とは
 所得税には、年収103万円の壁以外にも、所得者の税負担に大きく影響する106万円、130万円、150万円の壁があります。ここでは、パート従業員が、夫の勤務先の社会保険に加入している場合を例として説明します。
所得税には、年収103万円の壁以外にも、所得者の税負担に大きく影響する106万円、130万円、150万円の壁があります。ここでは、パート従業員が、夫の勤務先の社会保険に加入している場合を例として説明します。
3-1. 年収106万円の壁:超えると社会保険加入義務が発生する
パート従業員の年収が106万円を超えると、勤務条件によっては社会保険の加入義務が発生し、毎月の給与から保険料を差し引かなくてはいけません。
社会保険加入条件は次のとおりです。
- 週の所定労働時間が20時間以上である
- 毎月の給与が8万8,000円以上である
- 雇用期間が2か月(見込み含む)を超える
- 学生(昼間学校)ではない
- 従業員が101人以上の企業に勤務
さらに、2024年10月以降は「従業員数51人以上」の企業にも社会保険の適用範囲が拡大されるため、該当企業に当てはまる場合は、加入漏れが生じないよう注意が必要です。
3-2. 年収130万円の壁:超えると夫の社会保険から外れてしまう
年収106万以上で社会保険加入条件に該当しない場合でも、年収130万円を超えてしまうと夫の勤務先の社会保険の扶養から外されてしまいます。
この場合も、パート従業員が社会保険の加入条件を満たしていれば、加入手続きをしなくてはいけません。
夫の社会保険の扶養から外れずに働きたいと従業員が希望する場合は、年収106万円、130万円の壁を意識するだけでなく、勤務日数や労働時間にも気を配る必要があるでしょう。
3-3. 年収150万円の壁:超えると配偶者特別控除額が減額される
所得控除のなかには、配偶者の年収が103万円以下の場合に38万円の控除が適用される配偶者控除があります。
配偶者控除は年収103万円を超えると適用されなくなりますが、年収150万円以下であれば38万円の控除が受けられる配偶者特別控除が適用されます。
そのため、妻がパートで年収130万円を超えてしまった場合、妻の所得は課税対象になってしまいますが、引き続き配偶者控除は受けられるため、夫の税負担が増えることはありません。
配偶者特別控除は年収201.6万円までは適用されますが、150万円以上になると、所得金額に応じて控除額が減額されます。上限額38万円の控除を受けたいのであれば、年収150万円を意識して働く必要があるでしょう。
なお、配偶者特別控除は夫の年収が1,000万円を超える場合には適用されず、900万円以上になると控除額が減額されます。
4. 所得税の徴収漏れによるリスクとは

年収が103万円を超えると所得税が発生するため、年末調整時に未徴収分を精算しなくてはいけません。万が一、徴収が漏れた場合にどのような罰則があるのかについても、ここで押さえておきましょう。
年末調整をおこなわなかった際は所得税法違反となり、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。また、年末調整をおこなったにも関わらず、所得税を納税しなかった場合は「10年以下の懲役または200万円以下の罰金」の適用を受けます。
この他、納税額に不足があったり、納付期限を過ぎたりした場合は、過少申告加算税や延滞税がそれぞれ加算される恐れがある点にも注意が必要です。
罰則が適用されないためにも、経理担当者は103万円の所得税のボーダーラインを意識しておく必要があるでしょう。
5. 年収の基準を押さえて正しく所得税を計算しよう

会社員やパート、アルバイトなどの給与所得者は、基礎控除と給与所得控除の合計額103万円を超える年収を得た場合に所得税が発生します。
また、従業員の扶養家族の年収が103万円を超えると、扶養控除が適用とならなくなる点にも注意が必要です。
なお、年収106万円、130万円の壁には社会保険加入義務の問題、150万円には配偶者特別控除の問題が発生します。夫の扶養に入っているパート・アルバイト従業員がいる場合にも、特に年収の壁には気をつけなくてはいけないでしょう。
従業員には一人ひとりさまざまな事情があり、働き方を調整している可能性があります。そのため、人事担当者や経理担当者は、年収の壁について把握しておかなければなりません。
配偶者特別控除についても押さえておくべきです。そのため、いくらから所得税がかかるか、社会保険加入義務が発生するかなどをしっかり確認しておきましょう。
関連記事:所得税の計算方法は?計算を効率良くおこなう方法や年収が変わった場合について
給与計算業務は税務リスクや労務リスクと隣り合わせであるため、
・税額が合っているか不安
・税率を正しく計上できているか不安
・自社に合った税金計算方法(システム導入?代行依頼?)がわからない
というような悩みをお持ちのご担当者様は多いと思います。
そのような方に向け、当サイトでは所得税と住民税の正しい計算方法、税金計算時によく起きるミスとその対策をまとめた資料を無料で配布しております。
本資料にて、税金計算のミスを減らしたり、効率化が図れる給与計算システムの解説もあるので、税金計算をミスなく効率的に行いたいという方は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25