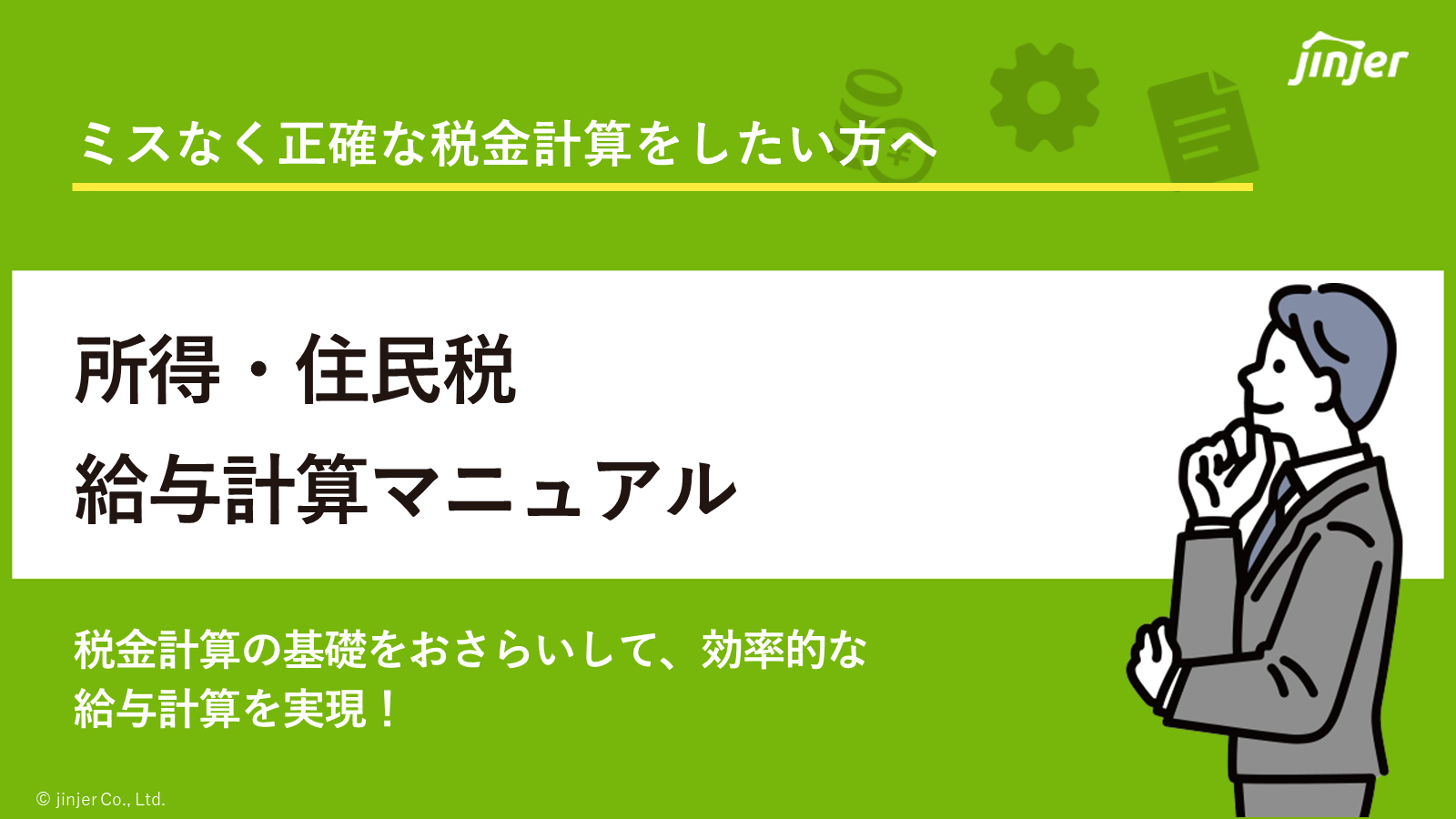所得税が毎月変わる理由とチェックするべき項目は?標準報酬月額も解説
更新日: 2024.3.5
公開日: 2022.3.15
OHSUGI

企業などと雇用契約を結んで働いている会社員や公務員などの場合、受け取る給与から源泉徴収として毎月所得税を納税しています。
給与明細を確認してみると、毎月納めている所得税額が月によって異なっている場合があります。
場合によっては、実際に支払われている金額は変わっていないものの、月々の納税額が変動していることもあります。
今回は、所得額が変わっていないにもかかわらず、月々の納税額が左右される理由や変動した際にチェックするべき項目、そして合わせて覚えておきたい社会保険の標準報酬月額について、それぞれ解説します。
関連記事:所得税とは?納税方法や確定申告が必要な人・不要な人について解説
給与計算業務は税務リスクや労務リスクと隣り合わせであるため、
・税額が合っているか不安
・税率を正しく計上できているか不安
・自社に合った税金計算方法(システム導入?代行依頼?)がわからない
というような悩みをお持ちのご担当者様は多いと思います。
そのような方に向け、当サイトでは所得税と住民税の正しい計算方法、税金計算時によく起きるミスとその対策をまとめた資料を無料で配布しております。
本資料にて、税金計算のミスを減らしたり、効率化が図れる給与計算システムの解説もあるので、税金計算をミスなく効率的に行いたいという方は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご覧ください。
1. 所得税が毎月変わる理由

所得税とは、給与や売上などで収入があった際に、その額に応じて発生する税金です。
自営業の場合、年度ごとに収入と支出を差し引きして所得額を計算し、納めるべき税金を税務署に申告します。これが確定申告です。
会社員や公務員など、雇用契約を結んで働いている場合、確定申告をおこなう必要はありません。
給与を受け取る際に、あらかじめ所得税が天引きされているためで、これを源泉徴収といいます。
その年の所得税が確定するのは12月31日です。その年の収入と支出が確定するためですが、毎月源泉徴収で差し引きして支払っていると、納めるべき税額が誤ってしまう場合があります。これを調整するのが年末調整です。
年末調整をおこなった結果、源泉徴収であらかじめ支払っていた所得税を払いすぎていた場合は還付され、逆に不足していた場合は追徴課税されます。
源泉徴収では、給与からざっくりとした所得税額を算出して天引きします。
こう聞けば、給与が変動しなければ、源泉徴収で引かれる所得税額は月々変動しないはずです。
しかし、変動する場合があるのが、所得税のポイントです。
変動する理由として、以下4つの理由が考えられます。
1-1. 一定の期間における給与が増えた
源泉徴収される金額は、受け取る支給総額から社会保険料をまず差し引きし、さらに扶養人数を踏まえたうえで、税額表に基づき決定します。
社会保険料の金額は、基本的にその年の4~6月の3ヵ月における給与額に基づいて決定します。
この際、残業代や休日出勤手当なども含め、3ヵ月にわたる給与を平均したものから社会保険料が算出されます。
もし、4~6月の間に受け取った給与がほかの月と比べて変動していた場合、社会保険料の額が変わるため、連動して天引きされる所得税も左右されます。
1-2. 課税所得金額の変動
所得や扶養人数が変動すると、合わせて課税所得金額も変わってきます。
そのため、天引きされる所得税も変わります。
残業や休日出勤などが多くあった結果、働いた分が給与に反映されれば、その分所得額も増えることになります。
そのほか、昇進あるいは昇格で基本給が上がった場合も同様です。
このように受け取る給与が増えれば、それだけ課税対象も増加されるので、天引きされる所得税は大きくなります。
また、所得税を算出するうえで重要な控除の1つとして扶養人数が挙げられます。
結婚や出産によって、扶養家族が増えたのであれば、控除額が大きくなるため、所得税は少なくなります。
逆に子どもの成長などによって扶養から外れれば、扶養人数が減って控除額が少なくなるので、所得税は増えることになります。
1-3. 税制改正がおこなわれた
所得税の決定に重要な控除額や各種税率といったものは、常に一定というわけではありません。
社会情勢などを加味したうえで、毎年変更される可能性があります。
昨今実施された大きな税制改正として、復興特別所得税が挙げられます。
これは東日本大震災の被害から復興のために、2037年まで適用される所得税です。
そのほかにも、2020年には基礎控除の引き上げや給与所得に対する控除の引き下げといった制度の改正がなされています。
所得税が変化した場合は、こういったことも想定されますので合わせて税制改正についても確認してみましょう。
1-4. 給与明細が間違っている
昨今ではデジタル化が大きく進んでおり、給与や勤怠に関する管理がシステム化されているケースが多いです。
そのため、給与明細に間違いが発生するケースは、極めて稀と考えられます。
しかし、人力でデータ入力していたり、万が一の可能性で誤りが発生する恐れがあります。
ほかにも、給与計算を外部に依頼していた場合、連絡事項に誤りが発生することもあるかもしれません。
前項の1~3のどれにも当てはまらないのであれば、給与明細の間違いの可能性があることも覚えておきましょう。
当サイトでは、本章で解説した毎月変わる理由を考えるうえで重要になる、所得税の年税額の決定方法や計算方法などを解説した資料を無料で配布しております。
税金の計算方法や税金に関する基礎知識で不安な点があるご担当者様は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご確認ください。
2. 所得税が変わった際のチェックするべき項目

所得税の金額が変わった際は、の1~4のどれかが理由であるケースが多いです。
もし、所得税が変わったのであれば、まずは以下2点について確認してみてください。
2-1. 社会保険料
社会保険料の金額は、先述のとおり4~6月までの3ヵ月における給与の平均額を算出して計算されます。
そして、この結果が社会保険料の額に反映されるのは、計算をおこなった年の9月から来年の8月までです。
もし、9月の給与から所得税が変わったと思われるのであれば、社会保険料の金額が変わったかどうかを確認してみましょう。
関連記事:給与計算における社会保険料の計算方法を分かりやすく解説
2-2. 残業や休日出勤手当
受け取る金額が増えれば、当然それだけ所得税は増加します。
残業や休日出勤によって普段よりも多くの給与が発生したのであれば、それだけ課税対象が増えるので、結果的に所得税は増えます。
もし、9月以外で所得税が増えたのであれば、残業や休日出勤に対する手当について確認してみてください。
3. 一緒に覚えておきたい社会保険の標準報酬月額

社会保険料とひとまとめにしていますが、厳密にいえば厚生年金保険料や健康保険料、介護保険料といったものが該当します。
所得税の金額を算出するにあたって重要な社会保険料は、標準報酬月額に基づいて計算されます。
一人ひとりの給与や所得に対して細かく計算するのは大変な作業です。
そこで、計算をしやすくするために用いるのが標準報酬月額です。
4~6月の3ヵ月における給与の平均額に基づいて、標準報酬月額の区分が決定します。
これを定時決定といい、その年の9月から来年の8月まで適用されます。
一度、定時決定されたものの給与が大きく変動して標準報酬月額を見直す必要があった場合、改定するための仕組みが設けられています。
これを随時改定といいます。
4. 所得税が変わった際は社会保険料や残業・休日出勤手当を確認すべき

天引きされる所得税は、変動する場合があります。
所得税は、所得額に対して課税されるため、もし納税額がいつもよりも変わったと感じるのであれば、給与に変化があったためかもしれません。
とくに、9月を境に所得税が変わったのであれば、4~6月における給与の平均額が昨年よりも大きく変わったために、税額にも影響があったと考えられます。
4~6月以外の月で所得税が変わった際は、残業や休日出勤などによって、普段よりも多くの給与を受け取っていた可能性があります。
ほかにも、税制改正や給与明細の記載が誤っているといった可能性もあります。
引かれている額に大きな違和感を覚えた際は、その理由について確認することをおすすめします。
給与計算業務は税務リスクや労務リスクと隣り合わせであるため、
・税額が合っているか不安
・税率を正しく計上できているか不安
・自社に合った税金計算方法(システム導入?代行依頼?)がわからない
というような悩みをお持ちのご担当者様は多いと思います。
そのような方に向け、当サイトでは所得税と住民税の正しい計算方法、税金計算時によく起きるミスとその対策をまとめた資料を無料で配布しております。
本資料にて、税金計算のミスを減らしたり、効率化が図れる給与計算システムの解説もあるので、税金計算をミスなく効率的に行いたいという方は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21
-



36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17
所得税の関連記事
-


所得税における累進課税制度とは?基礎知識や税率一覧を解説
勤怠・給与計算公開日:2022.04.18更新日:2024.05.22
-


所得税における通勤手当の課税・非課税ルールとは?交通費のとの違いも解説
勤怠・給与計算公開日:2022.03.27更新日:2024.03.05
-


所得税率は所得金額で変わる!税率改定の影響や注意すべきポイント
勤怠・給与計算公開日:2022.03.24更新日:2024.03.05