給与明細の「その他控除」って何?具体例や法定控除との違いを解説
更新日: 2025.8.4 公開日: 2025.4.16 jinjer Blog 編集部

「給与明細に記載するその他控除に何を含めてよいのかわからない」
「その他控除の計算方法がわからない」
上記のお悩みはないでしょうか。その他控除は法定外控除などともいい、法律で定められた法定控除とは区別して給与明細を作らなければいけません。
本記事では、その他控除と法定控除の違いやその他控除に該当する控除の例、その他控除の計算方法などを解説します。
控除額のミスを予防する方法も解説するので、正確な給与明細を作るための参考にしてください。
目次

労務担当者の実務の中で、給与計算は出勤簿を基に正確な計算が求められる一方で、Excelからの手入力や別システムからのデータ共有の際、毎月のミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、昇格や人事異動に伴う給与体系の変更や、給与計算に関連する法令改正があった場合、更新すべき情報も多く、管理方法とメンテナンスにお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな担当者の方には、人事労務から勤怠管理までが一つになったシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
-
勤怠データをワンクリックで取り込めるため、勤怠の締めから給与計算までをスムーズに自動化できる
-
昇格や異動に伴う給与体系の変更も、人事情報と連携しているため設定漏れを防ぐことができる
-
Web給与明細で印刷・封入コストがゼロ・ 発行ボタン一つで、全従業員へ給与明細を配布可能
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。
1. 給与明細のその他控除とは
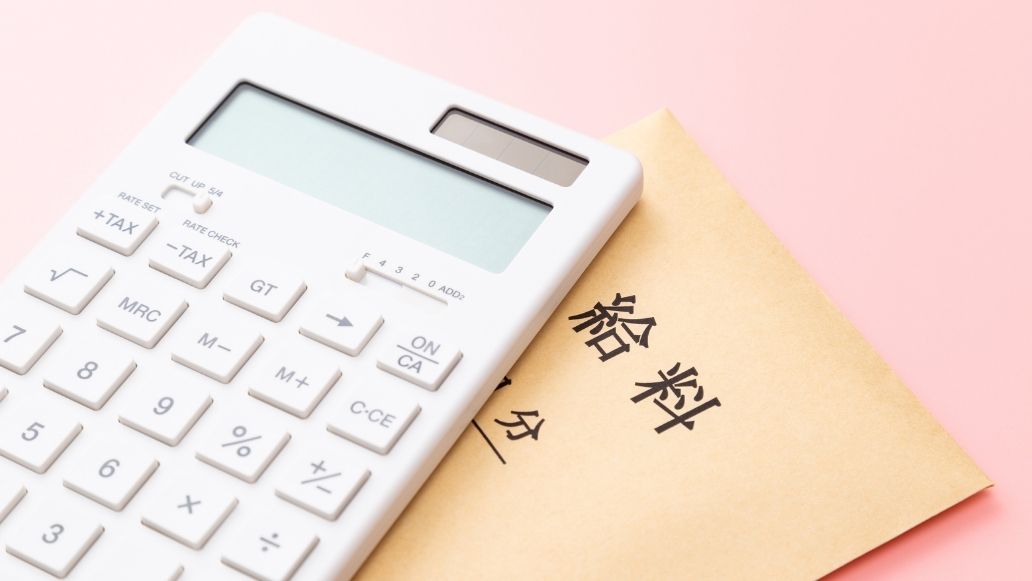
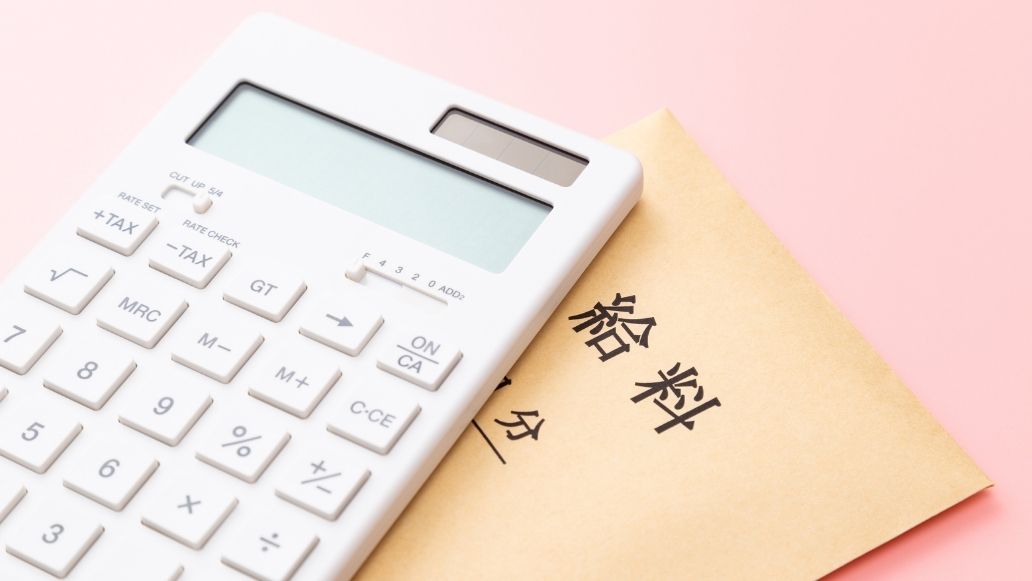
給与明細のその他控除とは、会社が独自に控除する項目です。「法定外控除」や「協定控除」ともいいます。社会保険料や所得税などとは違い、法律で定められた控除項目ではありません。
その他控除を適用するには、労働基準法24条にもとづき、給与控除に関する労使協定が必要になります。会社と労働者代表の間で書面での締結がなされない限り、会社側は勝手にその他控除の項目を決められません。
その他控除に関する労使協定書には、以下の内容が必要です。
- 控除対象の具体的項目
- 控除をおこなう賃金の支払日
- 協定の有効期間
必ず労使協定書の内容に含めましょう。
2. その他控除と法定控除の違い


その他控除と法定控除の違いは、法律で控除が定められているかどうかです。
その他控除は法律で定められている項目ではなく、労使協定によって会社と労働者が独自に内容を取り決めます。そのため具体的な項目や金額は会社によりさまざまです。
一方、法定控除は法律で控除するよう決められており、主に以下が該当します。
- 雇用保険料
- 厚生年金保険料
- 健康保険料
- 介護保険料
- 所得税
- 住民税
法定控除は社会保険料と税金で構成されています。社宅費や労働組合費など、社会保険や税金に当てはまらないものはすべてその他控除です。
3. その他控除に該当する9つの控除の例
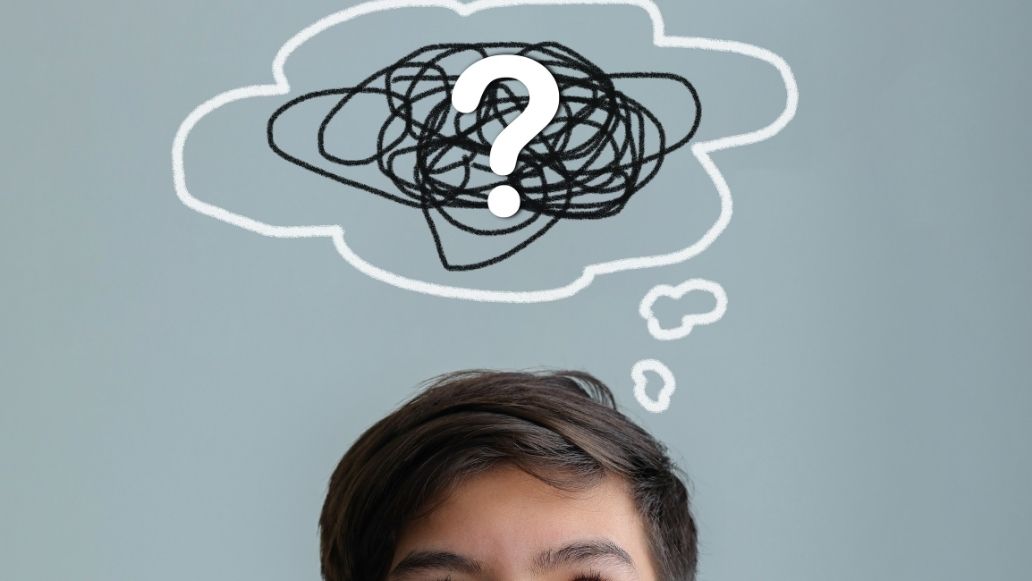
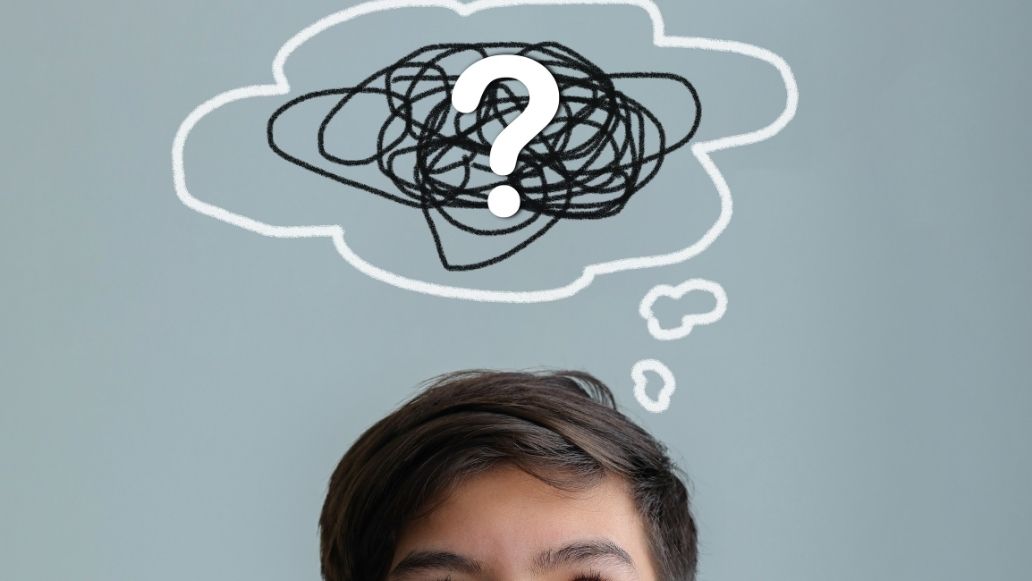
その他控除に該当する控除の例は以下のとおりです。
- 寮費・社宅費
- 労働組合費
- 財形貯蓄
- 持株会費
- 社内預金
- 親睦会費
- 社内旅行の積立金
- 会社が一時的に立て替えた際の返済金
- 従業員貸付制度の返済金
なお、会社によっては適応できない控除項目もあります。労使協定で明記していない場合は控除できない点を理解しておきましょう。
3-1. 寮費・社宅費
会社が従業員用の寮や社宅を保有している場合は、家賃や光熱費などをその他控除として給与から天引きします。利用条件や負担割合は企業ごとに異なるため、事前の確認が必要です。
3-2. 労働組合費
会社に労働組合があり、従業員が労働組合に加入している場合は、組合費もその他控除に該当します。組合費は組合の活動費や組合員の福利厚生などの原資として活用されます。
3-3. 財形貯蓄
従業員が勤労者財産形成促進制度を利用している場合は、資産形成の一つとして給与から毎月控除し、契約先の金融機関に積み立てます。財形貯蓄には主に「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」の3種類があります。
3-4. 持株会費
会社に従業員持株会があり、従業員が会員である場合は、保有口数に応じて控除します。従業員の長期的な資産形成の手段にもなるため、福利厚生の一環として導入している企業も多いです。
3-5. 社内預金
従業員が社内預金を利用する場合は、給与から控除して会社が従業員の預貯金を管理します。社内預金は、厚生労働省により下限利率が定められており、一般的な預金よりも利率が高めであるのが特徴です。
3-6. 親睦会費
親睦会のある会社では、会員を対象にその他控除として親睦会費を控除することがあります。使い道は親睦のための行事運営費や歓送迎会費、忘年会費、従業員の冠婚葬祭時の慶弔金などです。
3-7. 社員旅行の積立金
社員旅行のある会社では、従業員の給与から積立金を毎月控除し、社員旅行の宿泊費や交通費にあてる場合があります。
3-8. 会社が一時的に立て替えた際の返済金
給与の前貸しや休職中の社会保険料など、会社が従業員に対して立て替えた費用がある場合は、返済金をその他控除として給与から控除します。
3-9. 従業員貸付制度の返済金
従業員が会社からお金を借りられる「従業員貸付制度」がある場合は、返済金をその他控除として天引きする場合があります。貸付金は、従業員や家族の入院費や葬儀費など使途が定められているのが一般的です。
4. その他控除の計算方法


その他控除の計算方法は、会社と労働者が合意した協定内容によって異なります。法律で計算方法が決まっている法定控除と違い、会社による計算方法の指定が可能です。
一般的なその他控除の計算方法として、寮費や社宅費は実際の家賃に合わせて控除額を計算しましょう。財形貯蓄や社内預金などは従業員の希望に合わせて計算してください。
親睦会費や社員旅行の積立金などは、必要な総額に合わせて会社側である程度自由に控除額を決められます。ただし、従業員全員が納得できる計算方法を設定し、控除額が具体的に何に使われるのか説明できるようにしましょう。
なお、具体的な控除項目に関係なく、その他控除はあらかじめ結んだ労使協定に従って計算しなければいけません。
労使協定の内容と異なる項目や金額を控除すると労働基準法違反となるため、人事担当者は自社の労使協定をよく理解し、正しい計算方法で給与を計算しましょう。
5. 控除額のミスを防ぐ6つの方法


控除額のミスを防ぐ方法は以下のとおりです。
- チェック体制の整備
- スケジュールの見直し
- 適材適所の人事
- 研修の実施
- 専門家への依頼
- 給与計算システムの利用
5-1. チェック体制の整備
控除額のミスを防ぐには、社内のチェック体制を整えましょう。
どれだけ経験の長い従業員でも、計算ミスをすることはあります。作業中のミスを完全に防ぐことは難しくても、ミスを発見できる体制を作ることで、毎月正しい控除額を算出可能です。
人為的なミスを防ぐため、ダブルチェック、できればトリプルチェックまでできる体制を整えましょう。
給与計算をおこなう従業員が一人しかいない場合は、チェックリストを作成してください。業務をおこなう際は必ずチェックリストで確認するよう習慣づけさせ、計算ミスや漏れを防ぎましょう。
5-2. スケジュールの見直し
控除額のミスを予防するには、締日から支給日までのスケジュールを見直しましょう。
締日から支給日までがタイトなスケジュールだと、余裕をもって作業ができず計算ミスの原因になります。
例えば、25日締め当月30日払いの場合、給与計算の時間が5日しかありません。どうしても当月払いにする場合は、控除額は翌月の給与から引くなどすると、経理や人事の担当者が余裕を持って控除額を計算できます。
翌月払いにしている会社でも、締日を過ぎてからの勤怠の変更があるなど、計算を複雑にする悪い習慣がないか確認しましょう。
5-3. 適材適所の人事
控除額のミスを防ぐには、従業員の適正を考慮した適材適所の人事を心がけましょう。
人には得手不得手があり、何かの分野で非常に優れている人も、苦手な作業ではミスを連発することがあります。法務や購買などで活躍している人も、控除額の把握など給与計算は苦手かもしれません。
本人の希望や適性検査の結果などをふまえ、適材適所の人事により控除額の計算ミスを予防しましょう。
5-4. 研修の実施
控除額のミスを防ぐため、とくに新入社員を対象に給与計算に関する研修をおこないましょう。
給与計算は単に出勤日数をもとに計算すればよいのではなく、労使協定や社会保険の知識に基づいた正しい処理が必要です。
さまざまなルールを理解したうえで支給額や控除額を計算できるよう、研修など学習の機会を設けてください。
一度の研修で終わるのではなく、定期的に理解度テストを実施したり、要点をまとめた資料を配布したりして、正しい知識を身につけさせましょう。
5-5. 専門家への依頼
控除額のミスを予防するには、専門家への依頼も方法の一つです。
税理士や社労士、経理代行サービスなど、給与計算を代理でおこなっている専門家は多数います。外注費は発生しますが、ミスが起きるリスクを大きく下げられる点がメリットです。
社内に給与計算に関する業務に適した人材がいない場合や、チェック体制が整えられない場合などに利用するとよいでしょう。
5-6. 給与計算システムの利用
控除額のミスを防ぐには、給与計算システムの利用も検討しましょう。
給与計算システムを使えば、控除額や税金の計算が自動でできるため、人為的なミスを予防できます。勤怠管理システムやソフトと連携できるものであれば、データの反映ミスもないためより正確な給与明細の作成が可能です。
コストや機能を比べ、自社に適した給与計算システムを使ってみましょう。
6. その他控除の内容を理解して正確な給与明細を作ろう


その他控除は会社が独自に控除する項目で、具体的な項目や計算方法は会社によって異なります。ただし会社が勝手に控除してよいのではなく、給与控除に関する労使協定の締結が必要な点に注意しましょう。
その他控除や法定控除など、控除額のミスを防ぐにはチェック体制の整備や給与計算システムの利用などがあります。
その他控除に該当する項目や計算方法をよく理解し、ミスのない正確な給与明細を作りましょう。



労務担当者の実務の中で、給与計算は出勤簿を基に正確な計算が求められる一方で、Excelからの手入力や別システムからのデータ共有の際、毎月のミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、昇格や人事異動に伴う給与体系の変更や、給与計算に関連する法令改正があった場合、更新すべき情報も多く、管理方法とメンテナンスにお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな担当者の方には、人事労務から勤怠管理までが一つになったシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
-
勤怠データをワンクリックで取り込めるため、勤怠の締めから給与計算までをスムーズに自動化できる
-
昇格や異動に伴う給与体系の変更も、人事情報と連携しているため設定漏れを防ぐことができる
-
Web給与明細で印刷・封入コストがゼロ・ 発行ボタン一つで、全従業員へ給与明細を配布可能
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-



有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27
-


社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07
給与計算の関連記事
-


雇用保険の休職手当とは?受給条件や申請方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.06.18更新日:2025.08.28
-


パート従業員にも休職手当を支給できる?支給条件や注意点を解説
人事・労務管理公開日:2025.06.17更新日:2025.08.28
-


休職手当はいくら支払う?金額や支給条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2025.06.16更新日:2025.08.28





















