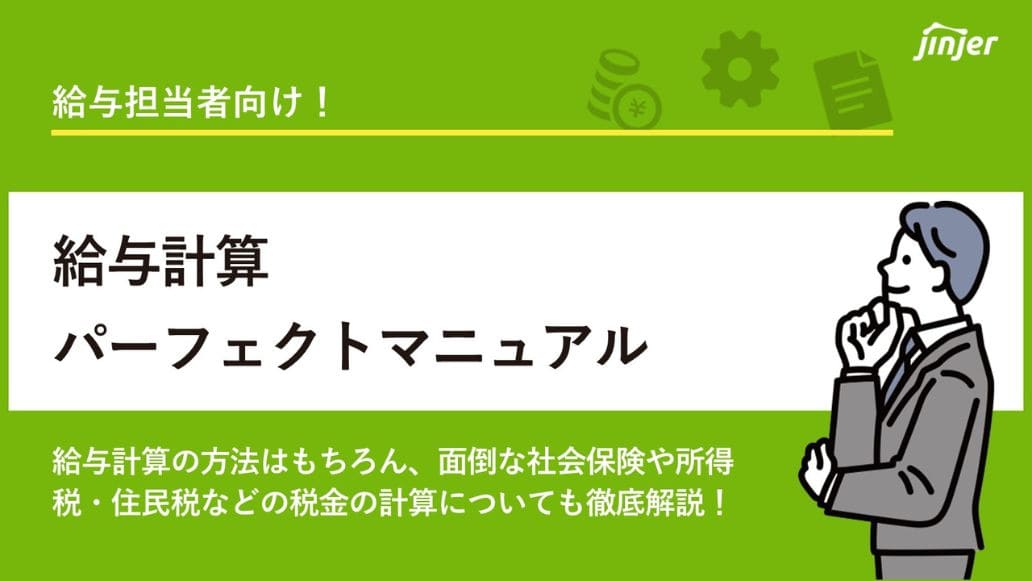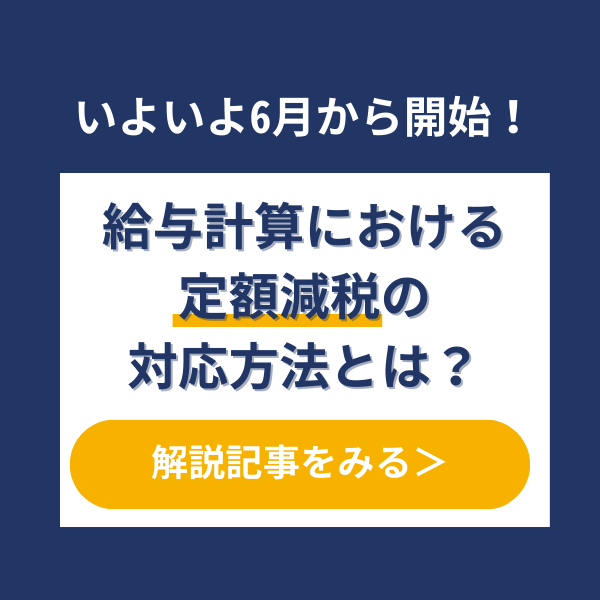役職手当とは?相場・金額の決め方をわかりやすく解説

「ポジションごとに金額設定が異なる役職手当の相場は?」
「役職手当の金額は何を基準に決めたらいい?」
そのようなお悩みを抱えていないでしょうか。
役職手当は、法律で義務付けられているものではありません。しかし、導入している企業は多く、役職手当を設定することで従業員のモチベーションに好影響を与えることが可能です。
本記事では、役職手当の相場や金額の設定方法をはじめ、注意点やメリット・デメリットについて解説します。役職手当の導入や金額設定にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
1. 役職手当とは


役職手当とは、「役職」に応じて従業員に支給する賃金のことです。「役付手当」「管理職手当」などさまざまな名称があり、企業によって呼び名は変わります。
役職手当は、基本給とは別に「手当」として支給される賃金です。
ただし、役職手当の支給に関しては法律で定められていないので、支給の有無や支給額は企業で自由に設定できます。そのため、企業によっては手当をつけない場合もありますし、同じ役職でも地域や業界の違いで支給額が異なることがあります。
支給される場合は、責任が重くなればなるほど報酬が高くなることが一般的なので、昇進や降格があれば金額も変動します。
役職手当は、役職に就くことで特別な責任が伴ったり、役割が与えられたりすることへの「対価」ともいえるでしょう。
2. 役職手当の相場


役職手当の金額は、企業が自由に決めることができます。しかし、いくら自由であっても、手当が低すぎれば従業員のモチベーションを上げることができません。逆に、高すぎると人件費によって経営が圧迫される可能性もあるので注意が必要です。
ここでは、役職ごとの手当の平均相場を紹介していくので、手当導入を検討している場合は適切な金額を知っておきましょう。
参考:役職手当|厚生労働省
参考:中小企業の賃金・退職金事情(2023年/令和5年版)|統計・調査|東京都産業労働局
2-1. 「主任クラス」の役職手当相場
主任クラスの役職手当は、正確な集計は出ていませんが、およそ5,000円から10,000円が相場となっています。
主任クラスの役職名は、他に「チーフ」や「リーダー」などがあります。主任クラスというのは決裁権がほとんどなく、職責も発生しないのが一般的で、新しく入社した従業員が最初に就くことが多い「役職」です。そのため、業務量も一般従業員とほとんど変わりがないことから、手当も高くない傾向にあるようです。
ただし、一般従業員よりも業務量をこなしたり、店舗運営などでシフト作成やサポートなどをおこなったりするなど、企業にとって重要な役割をこなす場合は平均相場よりも高めに設定するなど、業務に応じた手当をつけるのが一般的です。
2-2. 「係長クラス」の役職手当相場
係長クラスの役職手当の相場は、中小企業の賃金・退職金事情(2023年/令和5年版)によると26,165円となっています。ただし、会社の規模や「同一役職の支給額は同じ」か「同一役職の支給額は異なる」としている企業ごとに平均相場が異なるので、以下の表で見ていきましょう。
| 係長クラスの役職手当相場 | 従業員数 | 同一役職の支給額は同じ | 同一役職の支給額は異なる |
| 10人~49人 | 25,443円 | 27,828円 | |
| 50人~99人 | 25,438円 | 15,911円 | |
| 100人~299人 | 28,345円 | 23,143円 |
「同一役職の支給額は同じ」という企業の場合は、従業員数が多くなるほど手当も高額になります。その反面、「同一役職の支給額は異なる」企業の場合はばらつきがあることがわかります。
参考:中小企業の賃金・退職金事情(2023年/令和5年版)|統計・調査|東京都産業労働局
2-3. 「課長クラス」の役職手当相場
課長クラスの役職手当の相場は、中小企業の賃金・退職金事情(2023年/令和5年版)によると57,621円となっています。ここでも、会社の規模や「同一役職の支給額は同じ」か「同一役職の支給額は異なる」としている企業ごとに平均相場が異なるので、以下の表で見ていきましょう。
| 課長クラスの役職手当相場 | 従業員数 | 同一役職の支給額は同じ | 同一役職の支給額は異なる |
| 10~49人 | 46,620円 | 52,143円 | |
| 50~99人 | 50,252円 | 54,670円 | |
| 100~299人 | 86,985円 | 70,007円 |
課長クラスの場合は、「同一役職の支給額は同じ」の企業も「同一役職の支給額は異なる」企業も、会社の規模に比例して手当の金額が高くなっていきます。
参考:中小企業の賃金・退職金事情(2023年/令和5年版)|統計・調査|東京都産業労働局
2-4. 「部長クラス」の役職手当相場
部長クラスの役職手当の相場は、中小企業の賃金・退職金事情(2023年/令和5年版)によると83,916円となっています。部長クラスも、会社の規模や「同一役職の支給額は同じ」か「同一役職の支給額は異なる」としている企業ごとに平均相場が異なるので、以下の表で見ていきましょう。
| 部長クラスの役職手当相場 | 従業員数 | 同一役職の支給額は同じ | 同一役職の支給額は異なる |
| 10~49人 | 73,443円 | 90,851円 | |
| 50~99人 | 80,724円 | 107,998円 | |
| 100~299人 | 111,675円 | 126,224円 |
部長クラスの場合は、「同一役職の支給額は同じ」の企業よりも「同一役職の支給額は異なる」企業の手当の方が高額になっていることがわかります。
参考:中小企業の賃金・退職金事情(2023年/令和5年版)|統計・調査|東京都産業労働局
3. 役職手当の決め方
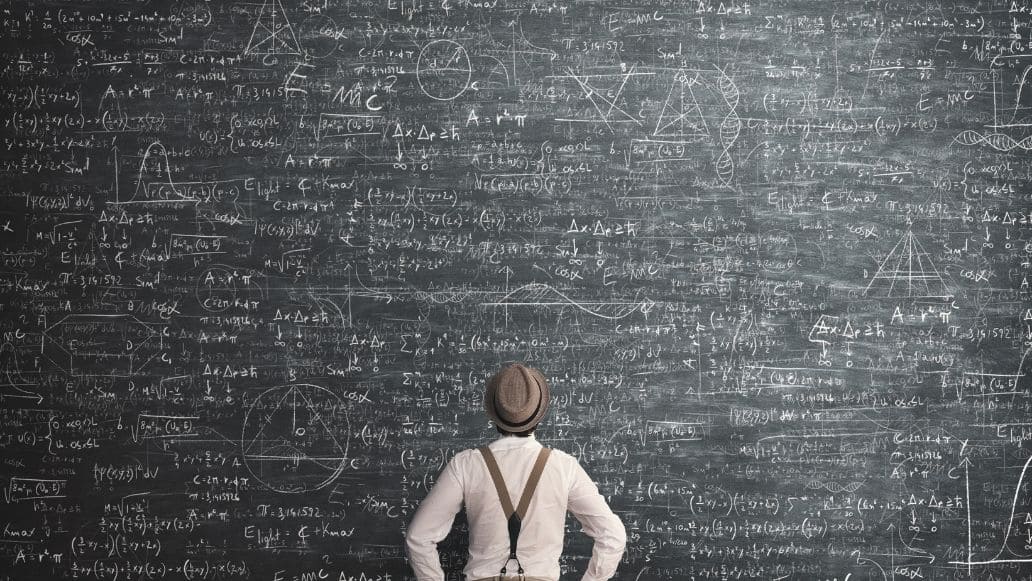
役職手当の決め方はいろいろありますが、基本となるのは以下の要素です。
- おおよその基準値を決める
- 他の役職とのバランスを考える
ここでは、それぞれの決め方を具体的に解説していきます。
3-1. おおよその基準値を決める
役職手当の決め方には細かい基準やルールは存在しないので、何を基準にするのかをあらかじめ決めておきましょう。金額を設定する際に参考にしたい項目は以下の通りです。
- 業務に関する責任の重さ
- 業務の量
- 従業員(部下)の数
- 同じ業界や同じ規模の会社のデータを参考にする
厚生労働省が発表しているデータによると、企業の規模が大きいほど、役職手当の報酬はアップする傾向にあります。
最終的な金額設定は最後に調整するので、最初は仮設定で問題ありません。ポイントは、相場金額を参考に最初におおまかな金額設定をすることです。
3-2. バランスを考える
支給額の仮設定をしたら、役職ごとに金額の差が出るようにバランスを調整していきます。ポイントは、役職の最上位・最下位どちらかの支給額を先に決めてしまうことです。どちらか一方の金額を適切に設定することで、役職ごとの支給額の設定がしやすくなります。
金額のバランスが取れていないと、手当をつけても不平不満が出てくるかもしれません。特に、最上位の役職の手当が異常に高いと、それ以降の役職のやる気がなくなってしまう可能性があります。役職についている従業員のやる気が下がると、その部署の業績にも悪影響を及ぼします。
せっかく役職手当をつけるのですから、バランスが悪くならないよう、仮決定で慎重に進めていくのがよいでしょう。
4. 役職手当を決める際の注意点


役職手当を決める際の注意点は以下の2つです。
- 就業規則に記載しなければいけない
- 役職手当は基本的に減額できない
ここでは、それぞれの注意点を具体的に解説します。
4-1. 就業規則に記載しなければいけない
役職手当は「賃金」として支給するため、具体的な役職名や手当の定義などを就業規則に明記する必要があります。これは、労働基準法で定められており、企業の義務となっているので注意してください。
また、すでに明記をしていても、役職名の変更や追加など記載内容を変更する場合は、所轄の労働基準監督署長へ届出なければいけません。
就業規則に明記するのは面倒かもしれませんが、企業側には「役職に就けば給与がいくら昇給するのか明確になることで従業員の動機づけになる」、「新しい役職に対して手当を支給する場合スピーディーに対応できる」などのメリットが得られます。
具体的な金額を明記する必要はありませんが、明記することで従業員は分かりやすくなります。これから役職手当を導入するもしくは内容を変更する場合は、届出を経て就業規則に記載しましょう。
参照:1 就業規則に記載する項 2 就業規則の効力|厚生労働省
4-2. 役職手当は基本的に減額できない
企業の都合で、役職手当の金額を減らすことは基本的にできません。従業員の不利益になる労働条件の変更を、企業側は勝手におこなえないためです。
とはいえ、無断欠勤を繰り返したり、ミスや失敗が多かったり、セクハラ発言やモラハラ発言などコンプライアンス違反に該当するような行為など、役職にふさわしくない行動がある場合は減給や降格処分の対象とすることは問題ありません。
「減額できない」のは、仮に従業員が不祥を起こしたとしても、原則として一方的に役職手当の減額はできないということです。
ただし、従業員側の合意がある場合や人事評価の結果による場合は可能です。合意もしくは人事評価による降格や役職の変更、金額の変更があった場合は、就業規則を変更し社内に通知しなければいけません。
5.役職手当のメリット


役職手当の最大のメリットは、「従業員のモチベーションがあがる」ことです。
企業側が役職手当を導入していれば、従業員が役職に就くと毎月の所得が上がります。企業側の役員に対する「期待」や「評価」を手当という形で見える化することで、従業員のモチベーションの向上につながるでしょう。
従業員のモチベーションは、セミナーや講習などでもアップできますが、その効果は一時的でしかありません。しかし、毎月の「手当」であれば維持することが可能です。
従業員のモチベーションがあがれば、商品やサービスの質に与える影響も大きくなることが考えられます。その結果、顧客からの信頼や評価も高まり、企業の業績アップやイメージアップの効果も期待できます。
6. 役職手当のデメリット


役職手当のデメリットは、金額の設定が難しいことです。
適切な金額を設定しないと、「頑張っているのに評価されていない」「対価が少なすぎる」など、従業員の不満の原因となりかねません。設定する金額次第では、役職手当を支給することの最大のメリットが一転し、デメリットになる可能性もあります。役職付きの従業員が不満を持っていると、役職に就きたくないという従業員が出てくるかもしれません。
このデメリットを回避するには、金額設定の際に忖度や個人的な感情を入れないように、じっくり時間をかけて慎重に決めることが重要です。
また、多くの役職が混在する企業では、金額設定が曖昧になっていることも珍しくありません。「名ばかり役職」があることで、業務内容や金額を細かく調整しなければいけなくなることもあるでしょう。
役職を整理したり、統合したりすることで、デメリットの解消につながります。
7. 役職手当に関するよくある質問


役職手当に関するよくある質問は以下の5つです。
- 役職手当に残業代は含まれるのか
- 役職手当を支給しないと違法になるのか
- 役職手当は賞与の金額と関係あるか
- 役職手当は課税されるか
- 退職前に役職手当をカットしてもいいのか
ここでは、それぞれの質問に対する答えを解説していきます。
7-1. 役職手当に残業代は含まれるのか
役職手当に残業代は含まれません。残業代が発生した場合は、別途で支給する必要があります。
なお「管理監督者」の場合は、残業代の支払い対象外になるので注意が必要です。
7-2. 役職手当を支給しないと違法になるのか
役職手当は、法律に定められている手当ではありません。そのため、支給しなくても違法にならないので、問題はありません。しかし、先述したとおり、役職手当を支給するということは従業員のモチベーションアップにつながります。
企業にもたらすメリットもあるため、検討する価値は十分にあるといえるでしょう。
7-3. 役職手当は賞与の金額と関係あるか
役職手当は、賞与(ボーナス)の金額に影響しません。役職手当は、基本給とは別で支給される賃金のためです。
賞与の計算方法は会社によって異なります。たとえば賞与は「基本給×〇ヵ月分」として計算される場合には役職手当を支給しても賞与に影響はありません。
7-4. 役職手当は課税されるか
役職手当は賃金の一部のため、支給額に応じた所得税が発生します。
7-5. 退職前に役職手当をカットしてもいいのか
役職手当は、企業が任意で支給している賃金なので、退職前にカットすることに対する法的な規制はありません。
ただし、役職手当に関することは就業規則に明記することが定められているため、「退職前にカットする」ことを明記していない場合は、勝手にカットすることはできません。
カットをする場合は、事前に就業規則に明記しておくか、明記していない場合は就業規則を変更する必要があります。役職手当のカットは「不利益変更」にあたる可能性がありますが、就業規則の変更を労働者に周知し、変更内容に合理性が認められれば変更できます。
8. 役職手当の金額設定は入念に検討しよう


役職手当の支給の有無は、企業の判断に委ねられています。労働基準法などの法令で定められている手当ではありませんが、従業員のモチベーションアップや企業の利益につながる可能性が十分考えられるでしょう。
ただし、企業の判断で支給する賃金だとしても、勝手に金額を変更したり減額したりすることはできません。そのため、むやみに高額な手当を設定したり、たくさんの役職を設けてしまったりすると、後々変更の手間が生じることになるので注意してください。
役職手当の金額を決める場合は、それぞれの役職の責任の重さや企業の規模などを入念に検討し、公正かつ公平な金額設定を心がけることが大切です。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25