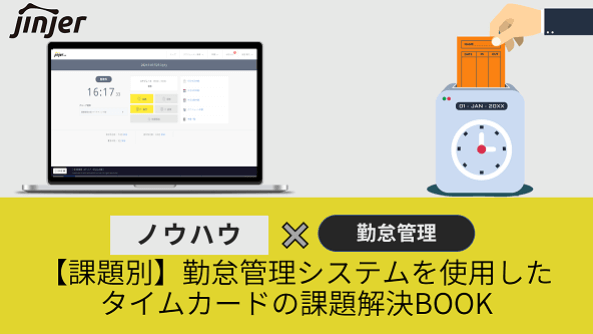タイムカードの改ざん・不正打刻は違法!懲戒処分できる?正しい対処や防止策とは
更新日: 2024.7.4
公開日: 2020.1.29
OHSUGI

タイムカードで勤怠管理をおこなう場合、従業員は出退勤時にタイムカードを通すだけで出退勤情報を記録できるため、手軽に従業員の勤怠情報を管理することができます。
一方で、タイムカードで管理する際に、『勤怠時間の集計に時間がかかる』『他人が簡単に打刻できてしまう』といったデメリットがあります。
従業員による不正打刻が発覚した場合、企業がどのような対策を取るべきなのでしょうか。また、そのようなことを発生させないためには、どのような対策を講じるべきなのでしょうか。
今回は、タイムカードの改ざんへの対策について解説します。
【関連記事】最新のタイムカード機5選!買い替え時に一緒に見ておきたい勤怠管理システムもご紹介
タイムカードによる勤怠管理で頭を悩ませるのが、タイムカードのズレです。
タイムカードのズレは様々な原因によって発生しますが、勤怠管理システムを利用すれば以下の理由による打刻時間のズレを減らすことができます。
・出勤と退勤ボタンの押し間違いによるズレ
・印字ミスや二重打刻によるズレ
・不正打刻によるズレ
「システムで打刻のズレを減らせるのはわかったけど、実際にタイムカードでの労働時間管理とどう違うのかを知りたい」という人事担当者様のために、タイムカードの課題を勤怠管理システムでどのように解決できるのかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。
目次
1. タイムカードの不正打刻とは


タイムカードの不正打刻とは、従業員が故意に虚偽の勤務時間を会社に報告することを指します。
例えば本来であれば残業をしていないにも関わらず、残業後の時刻でタイムカードを不正に打刻するようなケースなどがあたります。
タイムカードの不正打刻は悪質なケースであれば、懲戒処分に値する可能性もあるでしょう。
一方、管理者がタイムカードを改ざんするケースもあるでしょう。本来であれば時間外労働が発生しているにも関わらず、管理者が該当の従業員を定時退勤したことにすることも、不正打刻といえます。
2. 勤怠管理上で違法にあたる不正打刻の事例


そもそもタイムカードの改ざんはなぜ起きてしまうのでしょうか。
タイムカードは仕様がシンプルなため、誰でも使いやすく手軽に出退勤情報を記録することができるというメリットがあります。しかし、誰でも使いやすい仕様であるため、不正が起こりやすいことも事実です。それでは実際に発生したタイムカードの改ざんの事例をご紹介します。
2-1. 従業員の都合でタイムカードを改ざんするケース
遅刻しそう…
遅刻しそうなAさんは、既にオフィスに到着している同僚のBさんに連絡して、Bさんが代わりにAさんのタイムカードを打刻機に通しました。すると、Aさんは実際には遅刻したものの、記録上は定時前に出社したことになっています。勤怠管理者が月末の集計時に改ざんされていることに気づくことができなかったため、Aさんは処罰の対象にはなりませんでした。
タイムカードの改ざんにより従業員へ与えられる可能性のある罰則
ただし、その分多く給与を受け取るという事実は他人を欺いて金品をだまし取る「詐欺」にあたる可能性があります。今回のケースのように、不正打刻で逮捕されることは多くはありませんが、刑法において詐欺罪は、最大10年の懲役または50万円以下の罰金に処されるので決して軽い罪ではありません。
参考:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律|e-GOV法令検索
2-2. 会社の都合でタイムカードを改ざんするケース
残業していた際に上司から言われて…
Aさんが勤務する企業では、45時間の残業代が含まれた上で給与が算出される「見込み残業制」を採用していました。繁忙期であった3月に、Aさんの残業時間は月の半ばの時点で1ヵ月の残業時間が45時間を超えてしまうことがわかりました。すると、上司から「今日から月末まで定時を回ったらすぐにタイムカードを打刻機に通すように」と指示があり、Aさんは記録上は毎日定時で退社していることになっていましたが、実際は夜遅くまで残業をしていました。
タイムカードの改ざんにより会社へ与えられる可能性のある罰則
上記の場合、タイムカードの改ざんに加えて残業代未払いという問題点があげられるでしょう。また、残業代を支払われない場合は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金を課される場合があります。後々のトラブルにも繋がりかねないため、注意が必要です。
【労働基準法第37条第1項目】「労働時間を延長し、又休日に労働させた場合においては、割増賃金を支払わなければならない」【労働基準法第114条】「第37条の規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる」
3. 従業員がタイムカードの改ざんをおこなった場合の対処方法

従業員がタイムカードで不正打刻をおこなった場合、企業は実際にどのような対応を取るべきなのでしょうか。
3-1. 過剰支給分の賃金の返還手続きをする
タイムカードの改ざんが発覚したら、企業は過剰支給分の賃金を該当従業員に請求することができます。自社の就業規則で何かしらルールがある場合、該当従業員に対して、減給・降格・解雇などの罰則を与えることが可能です。
3-2. 従業員に対して勤怠管理の重要さを周知する
従業員によるタイムカードの不正打刻が発覚した場合は、社内で勤怠管理の重要さを周知し、再発防止を徹底しましょう。タイムカードの不正打刻や改ざんは立派な犯罪です。再発防止をするために、タイムカードを改ざんすることは違法であると従業員に認識を持たせることが重要です。
ここまで紹介してきた3点は長期的な取り組みで効果が出る内容が多いと思います。以下の記事にて、不正や改ざん等により修正が必要になった場合の対処法をまとめております。「ずれる理由を記載する」や「印字ミスを修正する」など、今日から取り組めるものもありますので、気になる方は関連記事をご覧ください。
【関連記事】タイムカードの打刻時間と労働時間のずれに関する対処法を解説
4. 不正や改ざんをした従業員に懲戒処分は可能?
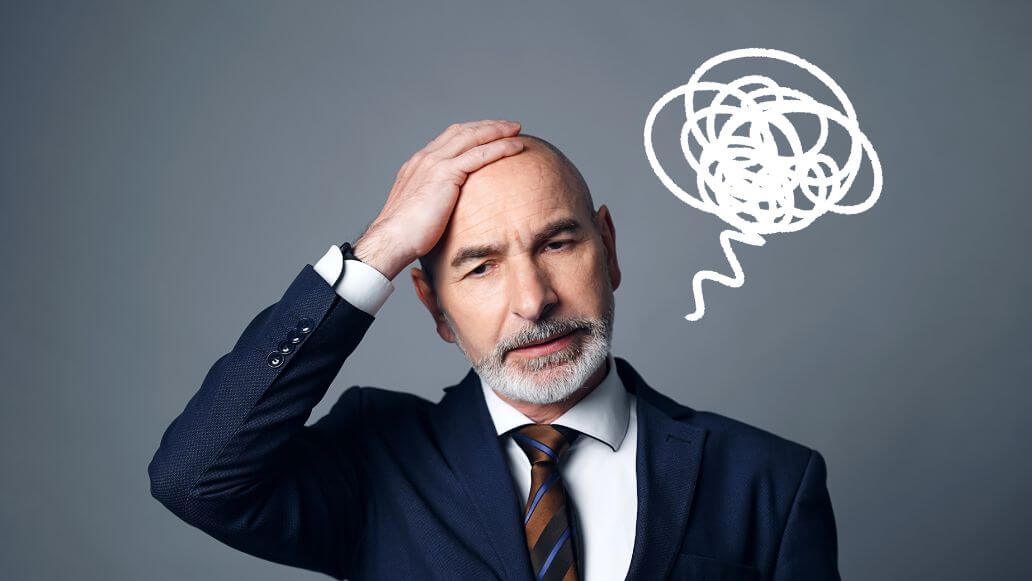
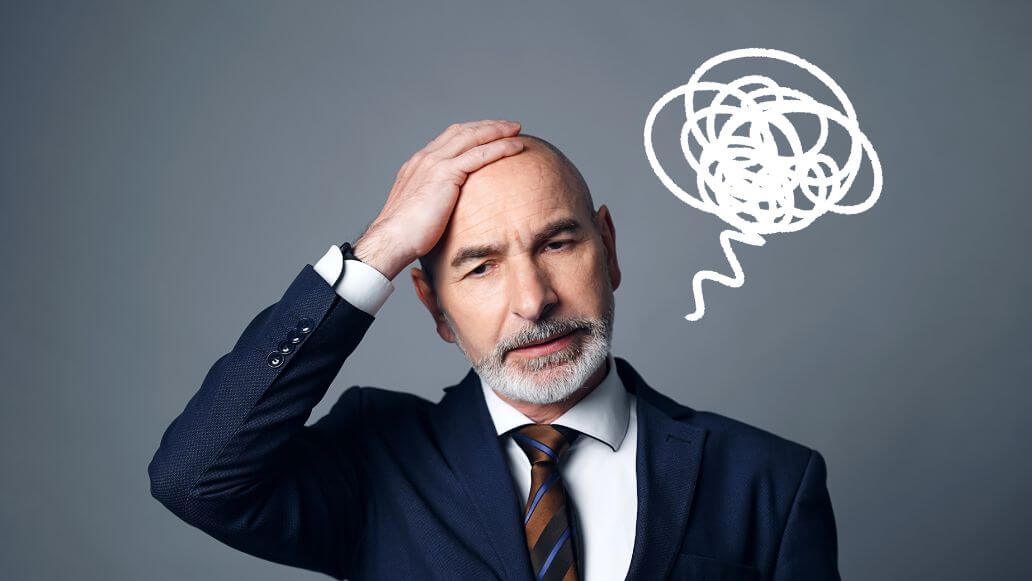
過払い分の報酬返還手続きをおこなうと同時に、タイムカードの不正打刻や改ざんをした従業員に対して、しかるべき処分を下すべきです。一般的に降格、減給、懲戒解雇などの処分が考えられますが、過度な懲罰や不当な解雇はトラブルになりかねないので注意が必要です。
4-1. 会社の勤怠管理に問題がある場合懲戒解雇はできない
ただし、会社の勤怠管理に問題がある場合、不正打刻があっても懲戒解雇は難しいとされています。例えば、タイムカードに虚偽の時刻が記録されている場合でも、会社のずさんな管理が原因であり、不正打刻と断定できないこともあります。また、残業時間が長くなるよう打刻されたケースと短くなっているケースが混在し、不正の意図が明確でない場合も同様です。
さらに、会社が不正打刻に気付いているにもかかわらず、注意や指導をしなかった場合や、長時間の離席者を放置するなどずさんな勤怠管理が行われている場合も問題です。タイムカードを打刻しない従業員に対する指導が行われていないケースや、過去の不正打刻者に対する処分が軽く、今回の懲戒解雇と均衡を失するケースもあります。
これらの場合は、懲戒解雇は不当と判断される可能性が高く、減給や出勤停止などの処分にとどめるべきです。中小企業の経営者や人事担当者は、この点を十分理解し、自社の勤怠管理体制の見直しを行うことが賢明です。
4-2. 懲戒処分する場合は証拠の確保が必要
タイムカードの不正打刻に対する懲戒処分を行う際は、証拠の確保が重要です。不正を本人に指摘する前に、確固たる証拠を揃える必要があります。証拠確保のために重視すべきポイントは以下の通りです。
まず、タイムカードの時刻設定を確認しましょう。タイムカードの時刻設定が実際の時間と一致しているか確認することは基本です。不正打刻の証拠としてタイムカードの打刻時間と実際の退勤時刻の不一致を指摘する場合、時刻設定が正確でないと議論が複雑になります。もし時刻設定がずれている場合は正しい時刻に合わせ、その日時を記録しておきましょう。
次に、退勤時刻の証拠を取りましょう。上司の目視による退勤確認や退勤時刻の毎日の記録、監視カメラの記録、PCのログ等が有力な方法です。また、電車通勤者の場合は乗車用ICカードの乗車時刻を、車通勤者の場合は駐車場の防犯カメラの映像を活用しましょう。これらの情報をもとに、タイムカードの記録と実際の退勤時刻の差異を確認することが重要です。
このように、確固たる証拠を確保することで、法的にも適切な懲戒処分が可能となります。
5. タイムカードで勤怠をアナログ管理するリスク


タイムカードで勤怠管理していると不正打刻に起こるリスクがあります。タイムカードによる勤怠管理のリスクは不正打刻の発生だけではありません。
タイムカードで勤怠管理している場合、集計作業に時間がかかってしまいます。また、集計作業中のミスも懸念されるでしょう。集計作業にミスが発生してしまうと、従業員に支払うべき賃金に誤差が発生しかねません。
これらのリスクを考慮するとタイムカードの廃止を検討するのもおすすめです。
6. タイムカードの廃止を考えるタイミングとは

勤怠管理の主な方法といえば、タイムカードを挙げる方は多いのではないでしょうか。前項まででご説明してきた通り、タイムカードは誰でも使いやすいというメリットがある反面、不正打刻・タイムカードに記載されている情報の改ざんがしやすいといったデメリットがあります。
近年では、働き方改革の推進で、勤怠管理が義務化されたことによって企業が従業員の勤怠管理をおこなうことが義務化されたり、テレワークやリモートワークといった柔軟な働き方を導入する企業が増加しています。
こうした社会の変化から、従来の勤怠管理の手法では対応することが難しい場面があるでしょう。それでは、どういったタイミングでタイミングでタイムカードを廃止し、より管理が容易になる勤怠管理システムの導入を検討するべきなのでしょうか。
6-1. 労務管理を強化したい場合
ブラック企業や過重労働が社会問題となっているなか、人事担当者は労務管理に気を抜くことができません。問題を防止することはもちろんですが、実際に問題が発生してしまった場合に、きちんと説明責任を果たすことが求められます。そのためには、勤怠情報や給与情報といった労務関係の書類をあらかじめきちんと管理しておくことが重要です。
タイムカードは、月末に集計をすることが一般的であり、月の半ばで集計することは仕様上難しいでしょう。これでは正確な残業時間を管理、把握することは難しいでしょう。また、定期的に勤怠情報を確認することができないと、「気づいたら残業時間の上限を超えていた」といった事態になりかねません。
6-2. 複数の拠点を展開している場合
複数の拠点を展開しており、勤怠管理の集計や給与計算を一箇所で集約している場合、全従業員のタイムカードを収集するだけでもかなりの工数と時間がかかってしまいます。
勤怠管理システムであれば、全従業員の勤怠情報をすべてクラウド上で管理しているため、場所と時間を問わずにデータを確認することができます。
また、給与計算システムと自動連携可能のものが多いため、勤怠管理から給与管理までを一貫しておこなうことができます。
6-3. テレワークやリモートワークを導入検討している場合
働き方改革やさまざまな外部要因の影響から、テレワークやリモートワークといった柔軟な働き方を導入する企業が増加傾向にあります。タイムカードでの勤怠管理をおこなっている場合、オフィス以外の場所で打刻をすることが難しいでしょう。
勤怠管理システムでは、自宅やカフェで仕事をしている場合であっても、インターネットに接続されたデバイスがあれば場所を問わず打刻が可能です。
また、打刻をおこなった場所を記録するGPS機能が搭載されているため、不正打刻をおこなうことが難しいといったメリットがあるため事前に情報収集をおこないましょう。
ここまで、システムの導入は不正打刻を防ぐことに役立つことや、クラウド上にデータが集まるのでいつでも確認できるというようなメリットがあると紹介してきましたが、他にもメリットが数多くあります。
当サイトでは、勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」を例に、実際の使用感や導入のメリットを管理画面を用いて解説した資料を無料で配布しております。自社で導入することで具体的にどのように変わるのか知りたい方は、こちらの資料をダウンロードしてご確認ください。
7.タイムカードの改ざん・不正打刻にはシステムを導入して対応しよう
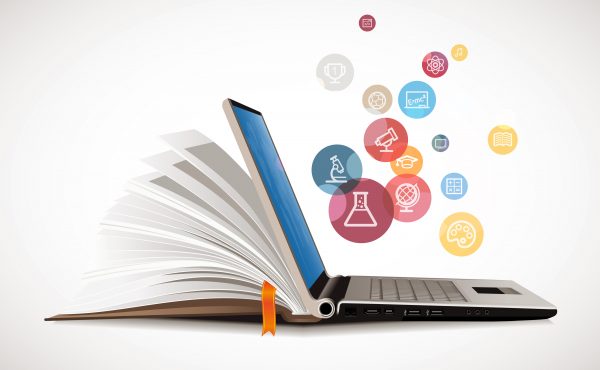
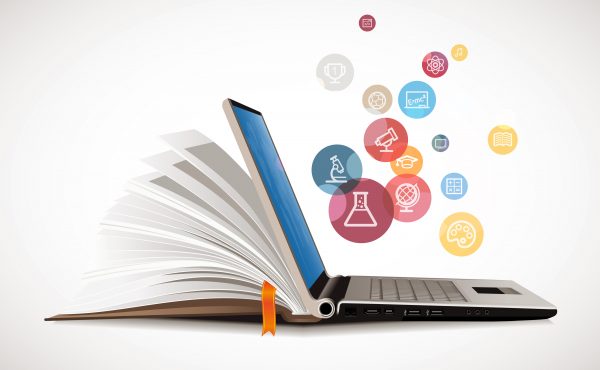
ここまで、タイムカードによる改ざんがどのように生じるのか、事例をもとに解説してきました。
タイムカードは手書きが可能であったり、他人に押してもらうことが容易にできてしまうため改ざんが生じてしまうという原因は理解していただけましたか。
今では勤怠管理システムを導入する企業も増加傾向にあり、法律違反のリスクや社内トラブルの対策という面でも、タイムカードからの変更は効果的といえるでしょう。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25