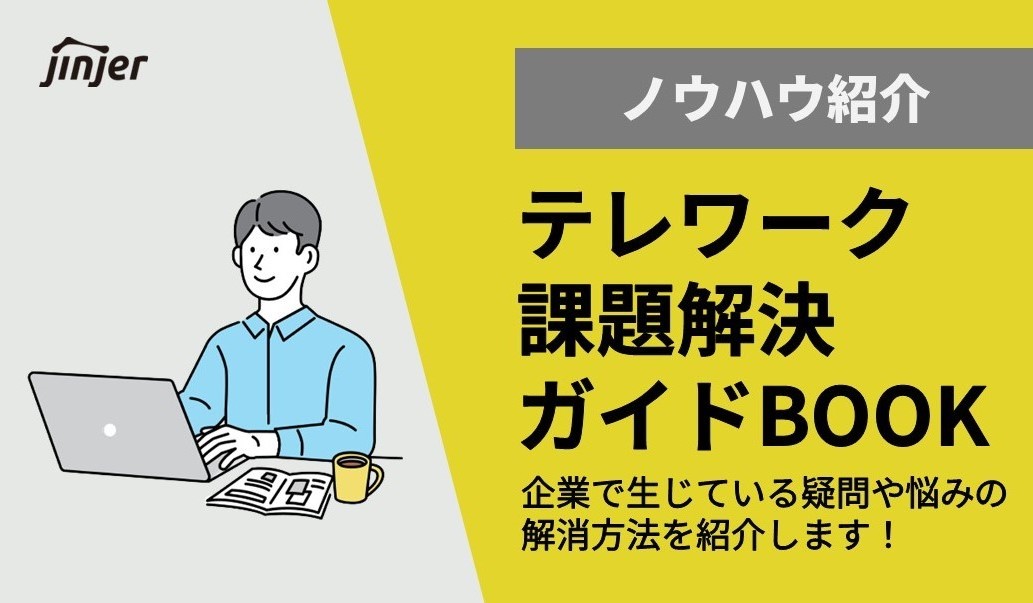在宅勤務の導入でもらえる補助金とは?申請先や方法を紹介
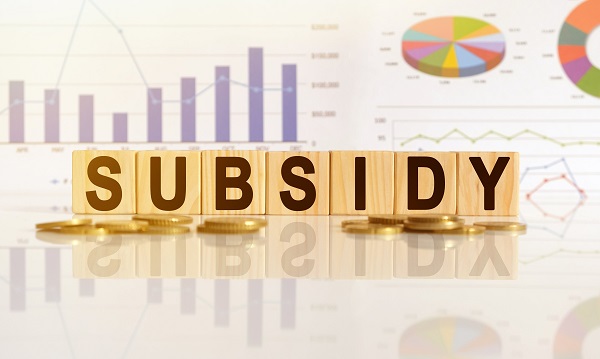
社員の在宅勤務(テレワーク)環境を整え、実際に在宅勤務に切り替えた場合、厚生労働省や各自治体から補助金が受け取れる可能性があります。
実際に在宅勤務に切り替える場合には、社員一人ひとりに対してパソコンや周辺機器を用意したり、ネットワーク環境を整えたり、セキュリティ体制を万全にしたり、企業側にかかる負担が増えるのが難点でもあります。
そこで企業がより在宅勤務を促進できるように導入されたのが、在宅勤務向けの補助金です。
補助金の受給には業種や社員数、導入環境などの条件が定められていますが、幅広い業種・規模の企業に適用できるように設定されています。
ここからは在宅勤務によって受けられる、補助金に関して詳しく解説していきます。
▼在宅勤務・テレワークについて詳しく知りたい方はこちら
在宅勤務の定義や導入を成功させる4つのポイントを解説
1. 在宅勤務の導入でもらえる補助金とは?

在宅勤務でもらえる補助金には、補助金を支出する団体によってさまざまなものがあります。
経済産業省や厚生労働省、総務省など政府機関を筆頭に、地方でも在宅勤務を導入しやすいよう、各地方自治体も独自に在宅勤務向けの補助金を支援しています。
補助金の種類や対象者、内容、条件等は支援を実施する機関ごとに異なります。
また、現在は募集をおこなっていない補助金もあるので、注意が必要です。
1-1. 政府が発表している在宅勤務の補助金
政府機関の中では、経済産業省・厚生労働省・総務省などが在宅勤務に向けて補助金を打ち出しています。
例えば、経済産業省から発表されたものを挙げると以下のものがあります。
- IT導入補助金 通常枠(A・B類型)
- IT導入補助金 体感染リスク型ビジネス枠
経済産業省の補助金は小規模の事業~中小企業などに向けて開催され、30万円~450万円まで、条件に合った額が給付されます。
補助金の対象となるのは、在宅勤務のために導入したソフトウェア費や、導入に関連する費用です。
1-2. 地方自治体で実施している在宅勤務の補助金
厚生労働省や経済産業省だけでなく、地域ごとに在宅勤務の補助金支援をおこなっている場合もあります。
東京都では以下の2つをおこなっています。
- テレワーク促進助成金
- テレワーク道入ハンズオン支援助成金
在宅勤務支援をおこなっている自治体の中でも、通勤で混雑しやすい関東圏が活発で、品川区・栃木県・埼玉県・千葉県市原市・千葉県船橋市・群馬県・神奈川県などで補助金支援がおこなわれています。
ただし、中にはすでに募集を終了している自治体もあるので、自治体公式のホームページ参照のもと、しっかり確認する必要があります。
1-3. 令和5年12月現在で開催中の在宅勤務向け補助金
先ほどまではすでに募集を終了している支援金も含めてご紹介しましたが、本章では令和5年(2023年)12月現在、実際に募集中の在宅支援向け支援金をご紹介します。
条件をよく確認し、当てはまる場合には申し込んで、よりお得に在宅切り替えをおこないましょう。
「2023年12月現在実施中の在宅勤務支援金(一般社団法人 日本テレワーク協会)」
- 厚生労働省「人材確保等支援助成金テレワークコース」
- 経済産業省「IT導入補助金」
- 東京都「テレワーク課題解決コンサルティング」
- 東京都「テレワーク促進助成金(令和5年度)」
- 山梨県「オフィス移転等に対する新たな助成制度」
- 北海道富良野市「ワーケーション実証費用助成金」
- 秋田県「リモートワークで秋田暮らし支援金」
- 秋田県「ワーケーション実践団体奨励金」
上記以外にも在宅勤務向けの補助金を実施している可能性があります。
自治体サイトの情報をよくお確かめください。
当サイトでは、在宅勤務の導入に興味があるご担当者様向けに、テレワークを導入することのメリットやデメリット、導入前後で起きうる課題、課題の解決方法をまとめた資料を無料で配布しております。導入をどうするかまずは資料を見て検討したいという方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください
2. 在宅勤務の導入でもらえる補助金の申請先

在宅勤務導入で補助金を受け取るには、抜け目なく申請をおこなう必要があります。
補助金の申請は、開催している機関または、機関が補助金給付を一任している団体・機関に対しておこないます。
補助金申請に伴い、条件や申請の流れが記載された情報が公開されているので、間違いのないようしっかりチェックをおこないましょう。
ここでは経済産業省と厚生労働省の申請先を確認していきます。
2-1. 厚生労働省「人材確保支援助成金テレワークコースの申請先」
支援を受けるにあたって、まずは「テレワーク実施計画」を作成します。
提出期限があるので、テレワーク実施計画句と添付書類を合わせて「管轄労働局」に提出します。
管轄労働局がテレワーク実施計画を認めると、実際に支援を受けられる条件が整います。
認定後はテレワークを実施し「機器等導入助成にかかる支給申請」を管轄労働局に提出します。
その後、再びテレワークを実施し、「目標達成助成にかかる支給申請」も、同じく管轄労働局に提出します。
2-2. 経済産業省「IT導入補助金申請先」
在宅勤務を導入する際、新たにIT機器を購入すると「IT導入補助金」が支給される可能性があります。
実際にはIT導入支援事業者に相談しながら、よりよいITツールを選択し、その導入費用を一部負担する仕組みです。
申請には「gBizIDプライム」アカウントを取得し、交付申請をおこないます。
交付先は事務局で、事務局の審査を経て給付の可否が決まります。
補助金の給付が決まってから導入するのがポイントです。
3. 在宅勤務の導入でもらえる補助金の申請方法

続いて、在宅勤務導入によって受け取りができる補助金の申請方法を解説していきます。
先ほど同様、該当者が多い以下2種類の解説をおこないます。
- 厚生労働省:人材確保支援助成金テレワークコース
- 経済産業省:IT導入補助金
3-1. 厚生労働省:人材確保支援助成金テレワークコースの申請方法
令和3年度人材確保支援助成金テレワークコースの申請手順と方法はつぎのとおりです。
- 「テレワーク実施計画」を管轄労働局に提出する
- 管轄労働局がテレワーク実施計画を認定する(約1ヵ月)
- テレワークで使用する機器の購入・導入
- テレワーク実施状況を評価(3ヵ月)[機器等導入助成]
- 「機器等導入助成の支給申請」を管轄労働局に提出する
- テレワーク実施にあたり、制度や労働規約・就業規則を見直す
- テレワーク実施状況を評価(3ヵ月)[目標達成助成]
- 「目標達成助成の支給申請」を管轄労働局に提出
関連記事:在宅勤務の就業規則の在り方や見直しのポイントを解説
3-2. 経済産業省:IT導入補助金の申請方法
経済産業省が実施するIT導入補助金の申請手順と方法はつぎのとおりです。
- IT導入補助金を理解する
- IT導入支援事業者を選び、アドバイスに従って導入するツールを選ぶ
- 「gBizIDプライムアカウント」を取得する
- SECURITY ACTIONを実施する
- IT導入支援事業者と共同で、交付申請を作成・提出する
- 事務局が交付を決定する
4. 在宅勤務を導入する際は補助金の有無をチェックしよう!

実際に在宅勤務を導入するには、社員分のIT機器をそろえたり、ネットワーク環境を整えたり、セキュリティやモラルを再確認したり、企業側に大きな負担がかかるのが特徴です。
特に、負担の大きな費用は助成金を利用して、よりお得に済ませるのがおすすめです。
助成金によっては一部だけでなく、かかった費用全てを支給するものもあり、少しの負担で在宅勤務を導入できます。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25