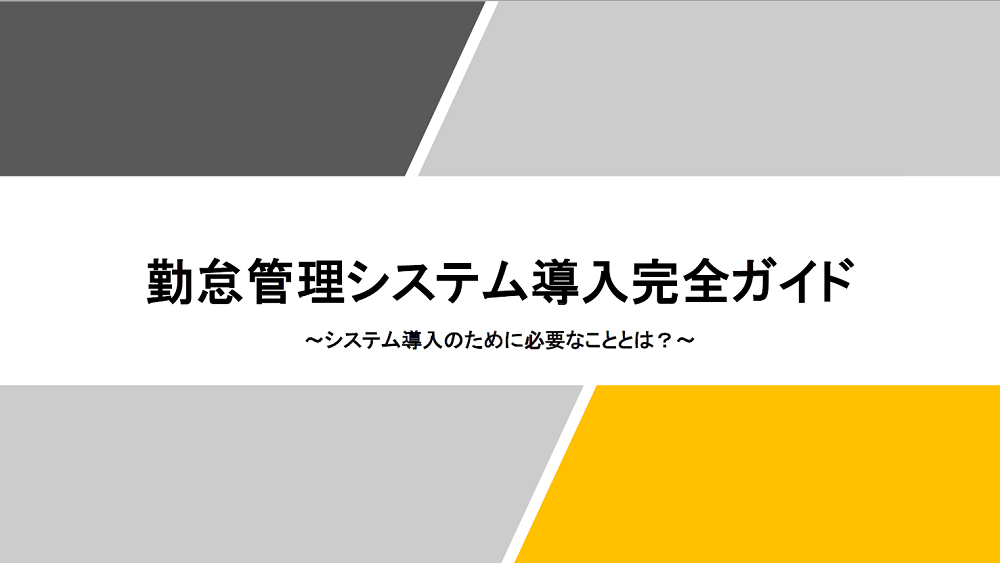労働時間の端数処理で企業が注意すべきポイント
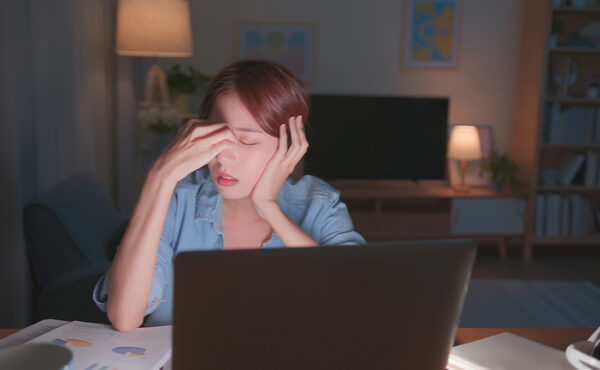
労働時間管理の原則として、企業は従業員の労働時間を1分単位で記録し、1か月単位の合計時間で給与を計算する必要があります。
そこで問題になってくるのが、「5分の遅刻はどう処理するのか」「残業時間の端数はどうすればよいのか」といった悩みです。毎日定時の出社時刻と退社時刻は就業規則で決められていても、実際には日々の残業や早出・早退などで端数が出ます。
このとき、生じた端数を一方的に切り捨ててしまうと、労働基準法違反になる場合もあるので気をつけましょう。この記事では、労働時間の端数処理で企業が意識すべきポイントについて解説します。
労働時間でよくある質問を徹底解説
この記事をご覧になっているということは、労働時間について何かしらの疑問があるのではないでしょうか。
ジンジャーは、日々に人事担当者様から多くの質問をいただき、弊社の社労士が回答させていただいております。その中でも多くいただいている質問を32ページにまとめました。
【資料にまとめられている質問】
・労働時間と勤務時間の違いは?
・年間の労働時間の計算方法は?
・労働時間に休憩時間は含むのか、含まないのか?
・労働時間を守らなかったら、どのような罰則があるのか?
労働時間に関する疑問を解消するため、ぜひ「【一問一答】労働時間でよくある質問を徹底解説」をご参考にください。
目次
1. 労働時間の端数処理をするうえでおさえておくべきポイント

労働時間の計算をするうえで、端数処理は重要な要素です。労働時間の管理や給与計算における公平性や正確性に関わるため、間違いのないよう処理することが求められます。
まず労働時間の端数の概要や、通達内容に沿った処理方法、労働時間の管理における基本的な知識からおさらいしましょう。
1-1. そもそも労働時間の端数とは?
労働時間の端数は、労働時間の計算において生じる小数点以下の部分を指します。
例えば、1時間30分の労働時間においては、1時間は整数部分であり、30分が端数部分となります。
勤怠においては、従業員の出勤や退勤時間、休憩時間などの記録が労働時間の計算に使用されます。
勤怠の端数処理は、労働時間の端数をどのように取り扱うかを指します。一般的には、切り上げ・切り捨て・四捨五入などの方法が用いられます。例えば、15分刻みで切り捨てる場合、1時間40分は1時間30分として計算されます。
ただし、労働時間を端数処理するには以下のルールもあわせて押さえておきましょう。
1-2. 従業員の残業時間を1分単位で管理する
労働時間管理の原則は、従業員の残業時間を1分単位で管理することです。
基本的に、「今日は5分遅刻したから30分の遅刻として処理する」「○時まで出社しなかった場合は半休になる」といった処理をすることはできません。
基本給を支払う労働時間も、割増賃金を支払う時間外労働時間についても、すべて1分単位で実際に働いてもらった時間を記録しておく必要があるため、ご注意ください。
【関連記事】1分刻みは常識!タイムカードで残業時間を正しく計算する方法
1-3. 1日の時間外労働(残業時間)を勝手に切り捨てると労働基準法違反となる
労働時間の端数処理をする際に、企業として注意すべきポイントは、「企業内のルールで好き勝手に残業時間の端数を切り捨ててはならない」ことです。
先述のとおり、企業は1分単位で残業時間を記録し、1か月の総労働時間を使って給与計算をする必要があります。
会社ごとの独自ルールで残業時間の切り捨てできるようにすると、企業側の意思ひとつでいくらでも人件費を圧縮できてしまうため、適切な給与支払いをすることができません。そのため、労働時間の端数の扱い方については各地の労働局などで労働時間の端数処理について説明もされており、適切な方法に則っていないと労働基準法に抵触してしまいます。
特に、通常の残業時間よりも時間給が高くなる残業時間の端数処理は、取り扱い方を誤ると従業員からも厳しく追求される可能性が高いです。
従業員側に不利益のある方法で端数処理をしていたため、従業員が退職する際に未払い残業代を一括請求されたというケースも少なくありません。
1-4. 端数を切り捨てる場合は、切り上げ処理もする必要がある
雇用主は、従業員に対して実際の労働時間に対して適切な賃金を支払う必要があります。そのため常に切り捨てのみをおこない、端数を切り上げないようにすることはできません。
もし1か月の残業時間の合計が30分未満である場合に切り捨てをおこなうなら、30分以上の端数は1時間に切り上げる必要があります。
労働時間の正確な処理と報酬の計算のために、切り捨てと切り上げの両方を適切に行う必要があることを押さえておきましょう。
端数処理以外にも労働時間を管理する際にふと疑問に思うことも多々あるのでないでしょうか?そのような方に向けて当サイトで「【一問一答】労働時間でよくある質問を徹底解説」という資料を無料配布しております。本資料では、「労働時間と勤務時間の違いは?」「労働時間を違反した場合の罰則は?」など労働時間に関するよくある質問を一問一答形式でわかりやすくまとめております。労働時間を管理している担当者の方にとっては大変参考になる内容となっておりますので、ぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
2. 労働基準法違反となるケース・違反の場合はどうなる?

労働時間の端数処理における計算ルールは、労働基準法という法律で決まっています。労働基準法は、働く人の権利を守るために制定されている法律です。ここからは労働時間の端数処理をするにあたって、労働基準法違反となるケースや違反した場合の対応について解説します。
2-1. 時間外労働手当(残業代)を支払わない場合違反になる
時間外労働手当(残業代)についても、労働基準法によって「全額を支払わなければならない」というルールが定められています。具体的には労働基準法第24条に以下のような記述があります。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」
条文後半の「その全額を支払わなければならない」とは、具体的には「1分単位で残業代を計算して残らず支給しなさい」ということです。
ただし、月給で賃金を計算している場合には、月の合計残業時間のうち30分未満については切り捨てることができるルールになっていることは、先述のとおりです。
2-2. 労働時間の端数処理で、労働基準法に違反した場合どうなる?
労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に違反していることが明らかになった場合、労働基準監督署から企業に対して是正勧告がなされることがあります。
是正勧告とは、サッカーでいうところの「イエローカード」のようなものです。是正勧告は法律的には行政指導ですので、もし従わなかったとしても刑事罰が課せられることはありません。
しかし、是正勧告をたびたび受けているにもかかわらず職場の環境を改めることがなかった場合には、会社に刑事罰が科せられ、書類送検を受ける可能性があります。
労働基準法に違反して刑事罰を受ける場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。刑事罰を受けた企業は、世論から非難を受ける可能性があります。
昨今はSNSなどで情報共有がすぐにできてしまうので、取引先の開拓や新入社員の採用活動で大きなダメージを受けるケースが少なくありません。違反した後のリスクを考慮した経営体制も重要です。
3. 法律を守って労働時間の端数を処理する方法

労働時間の端数処理は、労働基準法や就業規則に従う必要があります。端数処理の方法や基準は企業によって異なりますが、正確かつ公平な処理をおこなうための方法を把握してくことが重要です。
ここからは、法律に抵触することのないよう以下のポイントを確認していきましょう。
3-1. 1か月間の労働時間の端数はルールを決めて切り上げ・切り捨て処理できる
なお先述しているとおり、労働時間の端数処理をする場合は「1か月の総労働時間に対する端数」を処理しましょう。日々の労働時間自体を1分単位で管理しておき、1か月の総計を出したときに端数が出たら、社内ルールで切り上げたり切り捨てたりすることが可能です。
大抵の企業では、「労働時間の端数が30分未満なら切り捨てる」「労働時間の端数が30分以上ある場合は切り上げる」というルールを採用しています。
現実的な給与計算において、正確に1分単位での給与を求めると、給与額や源泉徴収額などの計算が複雑になってしまうため、特定条件下であれば端数処理が可能です。
3-2. 端数処理のルールは就業規則の作り込みが必要
労働時間や支払い給与の切り捨て・切り上げ、繰り越しといった処理をする場合、就業規則にどういう端数処理をするのかを盛り込んでおきましょう。
とくに注意したいのが、「遅刻に対する処罰」として労働時間を減らすという手立てを取るときです。たとえ遅刻であっても、5分の遅れに対して30分の労働時間削減を与えるといった対処は通常取ることができません。
しかし、社内の懲罰規定として遅刻などに対する労働時間の切り捨てや削減を決めておけば、ルールを守って端数処理をすることができます。
4. 労働時間の端数処理には正確な管理ができる勤怠管理システムが必要

時間外労働時間の端数処理をするためには、1分単位で日々の労働時間を正確に把握するシステムの導入が必要不可欠です。
手書きの出退勤管理だと正確な労働時間管理に限界があることに加えて、労働基準法の改正によって企業は客観的な労働時間把握が義務化されているため、タイムカードやパソコンのシステムを使った勤怠管理方式を取り入れましょう。
なかでもおすすめしたいのが、クラウド型の勤怠管理システムです。パソコンやスマホ、タブレット端末から手軽に出退勤や残業時間を打刻できるようにしておけば、出退勤時間の転記ミスや計算ミスを防げます。
近年、人手不足などの背景から、バックオフィス業務の効率化が多くの企業から注目されています。
タイムカードの集計は、集計時にExcelに入力する工数がかかりますし、有給休暇の管理は、従業員ごとに管理することが煩雑で、残有給日数を算出するのにも一苦労です。
どうにか工数を削減したいけど、どうしたらいいかわからないとお悩みの方は、勤怠管理システムの導入を検討してみましょう。
勤怠管理システムとは、従業員の出退勤をWeb上で管理できるシステムのことです。勤怠管理システムの導入を検討することで、
・多様な打刻方法により、テレワークなどの働き方に柔軟に対応できる
・リアルタイムで労働時間を自動で集計できるため、月末の集計工数が削減される
・ワンクリックで給与ソフトに連携できる
など、人事担当者様の工数削減につながります。
「導入を検討するといっても、何から始めたらいいかわからない」という人事担当者様のために、勤怠管理システムを導入するために必要なことを21ページでまとめたガイドブックを用意しました。
人事の働き方改革を成功させるため、ぜひ「勤怠管理システム導入完全ガイド」をご参考にください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21
-



36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17
労働時間の関連記事
-


副業を労働時間と通算しないケースや36協定の通算ルールを解説
勤怠・給与計算公開日:2022.02.20更新日:2024.10.15
-


労働基準法が定める副業・兼業の労働時間や注意点を解説
勤怠・給与計算公開日:2022.02.19更新日:2024.10.17
-


副業禁止は就業規則で定められる?トラブルの対処法も解説
勤怠・給与計算公開日:2022.02.18更新日:2024.10.17