基本給の決め方は?決める際のポイントや低いときのデメリットを解説
更新日: 2025.8.28 公開日: 2024.7.29 jinjer Blog 編集部

基本給とは、給与のベースとなる「基本賃金」のことで、残業代や通勤手当などの各種手当ては含みません。
基本給の決め方には法的な規定はないので、企業が自由に決めることが可能です。とはいえ、最低賃金というものは定められているので、それを下回らないようにする必要があります。
また、「下回らなければいい」という感覚で基本給を設定してしまうと、従業員の労働への対価に見合わず、離職者が増えたり求人募集をしても人が集まらなかったりするので、注意しなければなりません。
基本給は3つの決め方が主流になっているため、自社で決め方を選び、それに沿って適切な額を設定するのが重要です。
今回は、基本給の決め方や決める際のポイント、基本給が低いかどうかを判断する方法などについて解説します。
目次
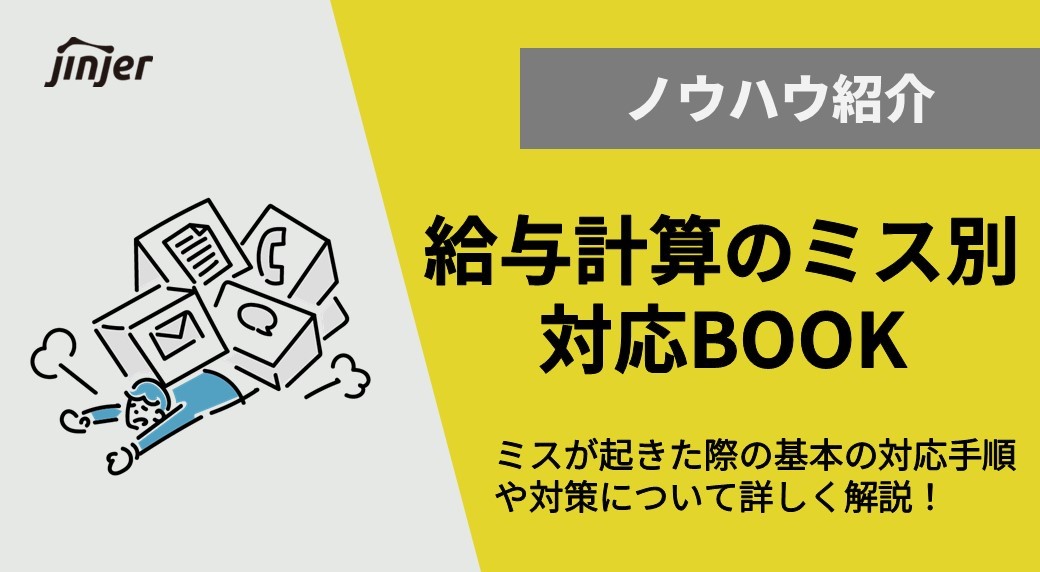
給与計算は、従業員との信頼関係に直結するため、本来絶対にミスがあってはならない業務ですが、計算ミスや更新漏れ、ヒューマンエラーが発生しやすいのも事実です。
当サイトでは、万が一ミスが発覚した場合に役立つ、ミス別に対応手順を解説した資料を無料配布しています。
資料では、ミス発覚時に参考になる基本の対応手順から、ミスを未然に防ぐための「起こりやすいミス」や「そもそも給与計算のミスを減らす方法」をわかりやすく解説しています。
◆この資料がおすすめできる方
・給与計算でミスが頻発していてお困りの方
・ミスをしないために、給与計算業務のチェックリストがほしい方
・根本的に給与計算のミスを減らす方法を知りたい方
いずれかに当てはまる担当者の方は、ぜひ「給与計算のミス別対応BOOK」をダウンロードの上、日々の実務にお役立てください。
1. 基本給とは
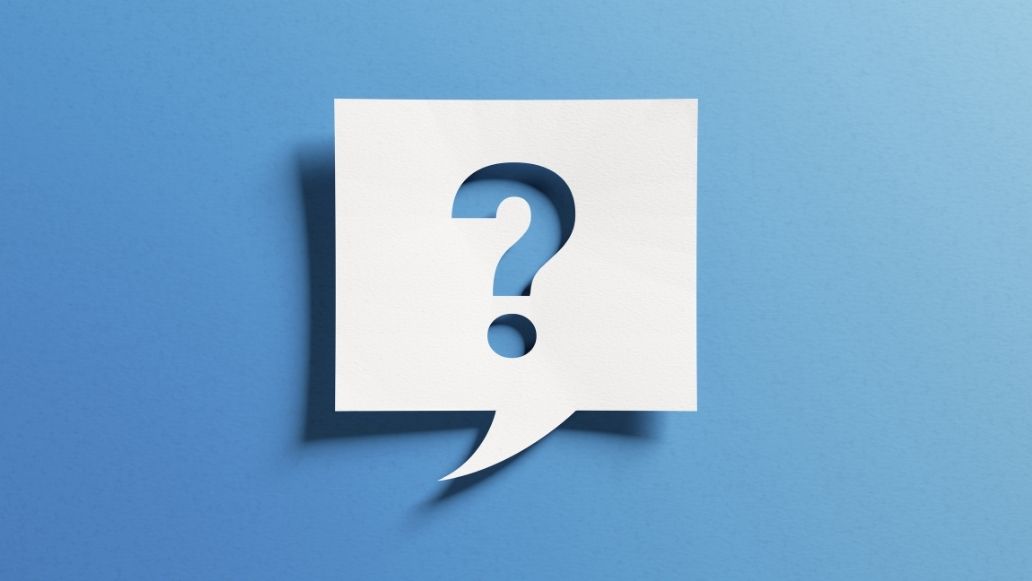
基本給とは、給与のベースとなる賃金です。
この「基本給」に残業代や役職手当、通勤手当などを加算し、住民税や保険料などを控除したのが「給与」となります。つまり、基本給が高くても各種手当が少なければ給与は低くなることがありますし、基本給が低くても手当が充実していれば給与は高くなるということです。
基本給の設定は企業によって異なり、業種の平均値に合わせる会社もあれば、計算する手間が少ない「勤続年数」を基本に決める会社などいろいろあります。
ただし、給与への直接的な影響がないとしても、従業員は毎月変動する各種手当よりも、安定している「基本給」を重視する傾向にあるので、適切な賃金制度で設定しましょう。
2. 基本給の3つの決め方

基本給の決め方は、主に以下の3つが挙げられます。
- 属人給|属人的要素で決定される
- 仕事給|労働者の実力を重視する
- 総合決定給|総合的な観点で決定される
ここでは、それぞれの決め方について詳しく解説します。
2-1. 属人給|属人的要素で決定される
属人給は、労働者個人の属人的要素によって決められる給与を指します。属人的要素に含まれるのは、主に「年齢」や「勤続年数」、「学歴」などです。
例えば、属人的要素を「勤続年数」にした場合は、勤続年数が長い従業員ほど基本給が上がる「年功給」という設定になります。
ただし、基本給の中でどの部分を属人級とするのかを区別するのは難しい傾向にあります。「勤続年数」だけで区別してしまうと、能力やスキルがあっても勤続年数が短いと基本給が低くなるため、職務に応じて決められる職務給を組み合わせる企業も多いです。
2-2. 仕事給|労働者の実力を重視する
仕事給は、労働者個人の能力や仕事内容、成果によって決められる給与です。この決め方であれば、勤続年数も年齢も関係ないので、本当に能力やスキルが高い従業員の基本給を上げられるので、会社にとって必要な人材を残すことができます。
仕事給に該当する給与は、以下のようなものが挙げられます。
- 目標の達成度によって決められる給与
- 労働者の職種や熟練度を基準とし労働市場などの相場で決められる給与
- 労働者個人の職務遂行能力を基準として決められる給与
- 責任の重さや職務の質によって決められる給与
いずれも労働の対価として支払われる賃金なため、実力を重要視した決め方といえます。
2-3. 総合決定給|総合的な観点で決定される
総合決定給は、属人給と仕事給の基準を総合的に見て決められる給与です。勤続年数や年齢などの個人的要素と、業績や職務内容などの仕事要素を組み合わせるので、比較的平等に基本給を決めることが可能です。
事業の規模が小さかったり雇用者数が少なかったりする企業では、総合決定給を採用するケースも少なくありません。
また、総合決定給はさまざまな要素を総合的に見て給与を決定するため、給与制度を柔軟に運用できるメリットがあります。一方で、給与の決定方法が不透明だと労働者から不満が出やすいので、どのような要素で決めるのかを明確しておくことが求められます。
3. 基本給を決める際のポイント

基本給を決める際のポイントは、以下の通りです。
- 基本給の賃金体系は従業員にわかるよう設定する
- 仕事給の詳細な金額を決める
- 仕事給の金額から属人給の金額を決定する
ここでは、それぞれのポイントを解説します。
3-1. 基本給の賃金体系は従業員にわかるよう設定する
基本給を決める際は、属人給と仕事給のどちらに重きを置いた賃金体系なのかが従業員にわかるようにしましょう。
例として、以下3つの基本給のパターンで考えてみます。
| パターン | 割合(内容) | 割合(数値) |
| ケース1 | 属人給:仕事給 | 3:7 |
| ケース2 | 属人給:仕事給 | 7:3 |
| ケース3 | 属人給:仕事給 | 5:5 |
ケース1では、仕事への貢献度が重視される賃金体系であると従業員に伝わります。
反対に、ケース2は属人的要素が大きく影響する賃金体系、ケース3は属人的要素と仕事への貢献度をバランスよく重視しています。
しかし、仕事への貢献度を重視するケース1を採用する際は注意しましょう。個人がどれだけ働いたかは主観で左右される要素も大きく、従業員に給与を下げるための賃金体系と誤解される可能性があるからです。
従業員が不満を抱かないよう、組織風土や賃金の運用方法を考慮した上で慎重に比率を決めましょう。
3-2. 仕事給の詳細な金額を決める
属人給と仕事給の比率が決まったら、仕事給の詳細な金額を決定していきます。
以下のように7段階の評価ランクを作り、上位にいくほど給料が上がるシステムにするのが一般的です。
| 評価ランク | 基本給の例 |
| SS | 180,000円 |
| S | 175,000円 |
| A | 170,000円 |
| B | 165,000円 |
| C | 160,000円 |
| D | 155,000円 |
| E | 150,000円 |
基本給を決める際には、評価ランクが1つ上がるごとに、どれだけ金額が上がるかをシミュレーションしながら決定していきましょう。基本的にはランクBの金額を軸とし、上下3ランクの金額を決めていきます。
3-3. 仕事給の金額から属人給の金額を決定する
仕事給の金額をもとに、属人給の金額を決めます。属人給は給与のばらつきを吸収しつつ新制度へ移行させやすくするために、各グレードの上限と下限の金額のみを決めましょう。
属人給の下限額と上限額は、属人給と仕事給の比率に合わせて決定します。例えば「属人給:仕事給=7:3」であれば、属人給と仕事給の上下限は7:3になるようにしてください。
属人給と仕事給を合計すると、各グレードの基本給になります。
4. 基本給が低いかを判断する方法

基本給が低いかを判断するために、以下のポイントを確認しましょう。
- 基本給には低いと判断できる目安がない
- 時給換算で最低賃金なら低い可能性がある
ここでは、低いかを判断するためのポイントを解説します。
4-1. 基本給には低いと判断できる目安がない
大前提として、基本給は「低い」と判断できる具体的な目安がありません。
基本給は給与の一部として考えられており、手当によって給与そのものが増えるためです。
例えば、以下のケースで考えてみましょう。
- 基本給13万円+固定手当7万円
- 基本給20万円(固定手当なし)
このケースでもわかるように、基本給が低くても固定手当があれば、基本給20万円と同じ給与になります。
4-2. 時給換算で最低賃金なら低い可能性がある
基本給が低いといわれる目安はないものの、給与そのものが低いかは時給換算で判断することができます。
自社の基本給が低いかどうかを知りたい場合は、手当を含む固定給や月給を所得労働時間で割ってみましょう。
求められた金額を地域で定められている最低賃金時間額と比較し、金額が近い場合は給与が低いといえます。
時給が最低賃金を下回ると法律違反になるため、最低賃金を上回るよう時給を設定しましょう。
5. 基本給が低いと起こりうるデメリット

基本給が低いと、以下のデメリットが懸念されます。
- ボーナスが少額になる
- 退職金が低くなる可能性がある
- 残業代が少額になる
- 各種手当を減額・廃止したときの減額幅が大きくなる
ここでは、これらのデメリットについて詳しく解説します。
5-1. ボーナスが少額になる
基本給が低いと、ボーナスの額が少なくなる可能性があるので注意しましょう。
ボーナスは法律で支給が義務づけられていないので、企業によって算定方法や支給の有無が異なります。しかし、ボーナスの規定がある企業は基本給をもとに掲載しているところが多いです。
基本給を基準にボーナスを決めるケースでは、基本給の上下限の差によってボーナスにも同じような差が発生します。
ボーナスが基本給の3ヵ月分と仮定し、総支給額が30万円のケースで考えてみましょう。
| 総支給額 | 基本給 | 固定手当 | ボーナスの額 |
| 30万円 | 20万円 | 10万円 | 60万円 |
| 30万円 | 15万円 | 15万円 | 45万円 |
| 基本給 | 手当 | ボーナスの額 |
| 20万円 | 10万円 | 60万円 |
| 15万円 | 15万円 | 45万円 |
上記の表を見るとわかるよう、月額の固定給が同じ30万円でも、基本給に差があるとボーナスで15万円の差が発生します。そのため、基本給が低いことで、従業員から不満の声が上がる可能性もゼロではありません。
5-2. 退職金が低くなる可能性がある
基本給が低くなると同時に、退職金も低くなる可能性があります。ボーナスと同様に、退職金も基本給を基準に算出するケースが多いためです。
一方で勤務年数に設定されたり、毎月の給与から一定額を積み立てたりするケースもあります。つまり、基本給の低さは必ずしも退職金の低さにつながらないということです。
また、退職金の支給は義務付けられていないので、少額もしくはない場合でも、法律上は問題ありません。しかし、「退職すると退職金がもらえる」とイメージしている人は多く、退職金を一般的な金額で受け取れない場合は、不満を覚えるでしょう。
そのため、基本給を安くするのを防いだり、金額の設定方法を工夫したりするのがベストです。
5-3. 残業代が少額になる
基本給が低くなると、残業代が安くなる可能性があります。「残業時間×1時間あたりの基本給や手当など×割増率」で残業代が算出されるためです。
ただ、賃金基礎額には諸手当が含まれるため、必ずしも基本給の低さが残業代の安さにつながるとは限りません。一方で諸手当がほとんどない企業では、基本給の低さがそのまま残業代の安さに反映されます。
残業代の減額を防ぐためには、安くない基本給に設定したり手当をつけたりする必要があるでしょう。
5-4. 各種手当を減額・廃止したときの減額幅が大きくなる
基本給を低く設定すると、各種手当てを減額もしくは廃止したときの減額幅が大きくなる可能性があります。
基本給は労働契約法の関係で簡単に減額できない一方、手当は企業次第で減額や支給廃止が可能です。
基本給の割合が小さく、少ない分を手当で補っているケースで考えると、手当がなくなれば給与を補っている分がなくなるので、給与そのものが大きく減額されます。
そのため、手当はやむを得ない事情でなくなる可能性も想定し、基本給はなるべく低くなりすぎないように設定するのがベストです。
6. 基本給の引き下げに関するルール

基本給は法律の関係で自由に引き下げられるものではないものの、ルールとして以下の目的では引き下げが可能です。
- 懲戒処分が目的であれば引き下げられる
- 会社の業績が悪化したときも引き下げ可能
ここでは、それぞれのルールを詳しく解説します。
6-1. 懲戒処分が目的であれば引き下げられる
基本給は、従業員に対する懲戒処分が目的であれば引き下げられます。労働組合や従業員代表が同意している就業規則に則った処分であるため、従業員の同意がなくても減額の実行は可能です。
ただし、従業員が就業規則で懲戒処分に当たる行為をおこなっており、処分内容に減給が明記されている場合のみに限ります。就業規則に記載していない場合は、勝手に減給することはできないので注意しましょう。
6-2. 会社の業績が悪化したときも引き下げ可能
会社の業績が悪化したときも、従業員の同意なしに基本給を下げることができます。ただし、基本給を下げるには業績の悪化を証明できるエビデンスが必要です。
さらに、経営陣への基本給の大幅な引き下げや報酬返上などを実施しても業績悪化を解消できない証明も用意しなければいけません。万が一業績が悪化し引き下げが必要な場合は、決定されているルール内で引き下げを実施するか、やむを得ない状況にあるとわかる証明を用意しましょう。
7. 基本給の決め方を理解して適切に給与設計しよう

基本給の決め方は、属人給と仕事給と総合決定給の3種類があります。どの決め方にするかは、自社と従業員に不利益にならないことを基本に、業種や業務内容にあった方法を選びましょう。
給与というのは、基本給をベースに各種手当を加算するため、手当が多ければ総支給額も多くなることから、従業員の不満も抑えることができるかもしれません。しかし、基本給が少ないと退職金やボーナスなどが低くなるデメリットも生まれます。結果的に従業員が不満を覚え、退職が相次ぐ可能性もゼロではありません。
まずは、基本給を時給換算し、少なくとも最低賃金を下回らないように設定し、適切に設計することが重要です。
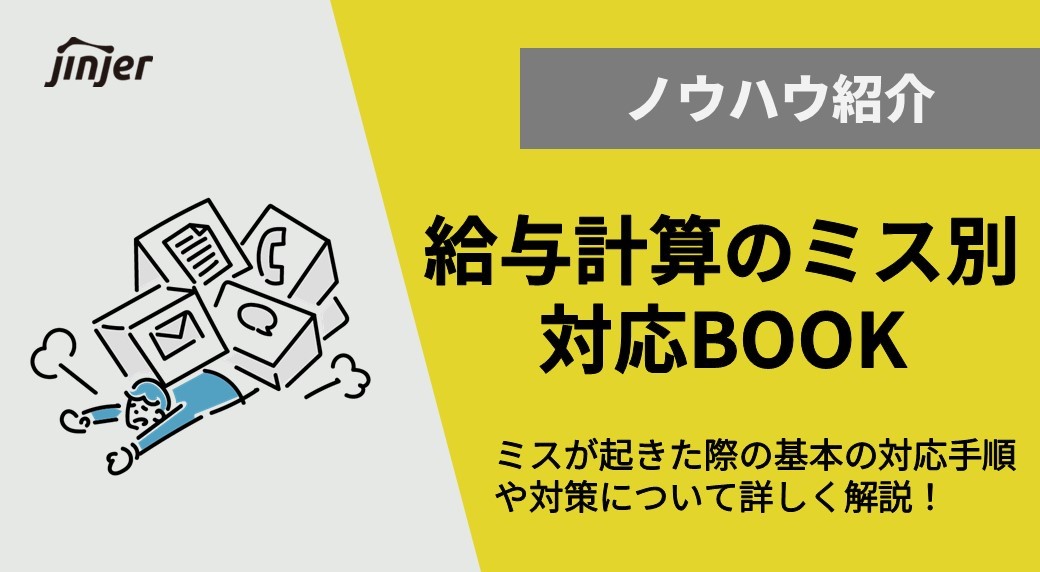
給与計算は、従業員との信頼関係に直結するため、本来絶対にミスがあってはならない業務ですが、計算ミスや更新漏れ、ヒューマンエラーが発生しやすいのも事実です。
当サイトでは、万が一ミスが発覚した場合に役立つ、ミス別に対応手順を解説した資料を無料配布しています。
資料では、ミス発覚時に参考になる基本の対応手順から、ミスを未然に防ぐための「起こりやすいミス」や「そもそも給与計算のミスを減らす方法」をわかりやすく解説しています。
◆この資料がおすすめできる方
・給与計算でミスが頻発していてお困りの方
・ミスをしないために、給与計算業務のチェックリストがほしい方
・根本的に給与計算のミスを減らす方法を知りたい方
いずれかに当てはまる担当者の方は、ぜひ「給与計算のミス別対応BOOK」をダウンロードの上、日々の実務にお役立てください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27
-


社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07
給与計算の関連記事
-


雇用保険の休職手当とは?受給条件や申請方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.06.18更新日:2025.08.28
-


パート従業員にも休職手当を支給できる?支給条件や注意点を解説
人事・労務管理公開日:2025.06.17更新日:2025.08.28
-


休職手当はいくら支払う?金額や支給条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2025.06.16更新日:2025.08.28






















