アニバーサリー休暇とは?導入するメリット・手順・事例を解説
更新日: 2025.9.25 公開日: 2024.12.5 jinjer Blog 編集部

アニバーサリー休暇とは、社員の個人的な記念日に休暇を取得できる制度を指します。社員の仕事への意欲を向上させるためにも、アニバーサリー休暇は欠かせない重要な制度です。
本記事では、アニバーサリー休暇の概要やメリット・デメリット、導入手順、事例を詳しく解説します。最後までご覧いただくことで、アニバーサリー休暇を導入すべきか判断しやすくなるでしょう。
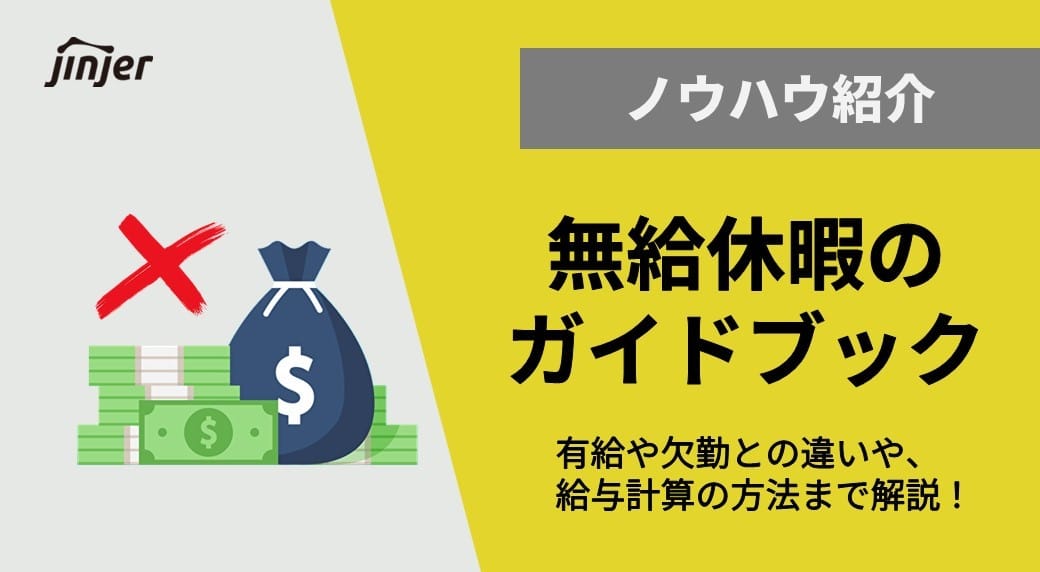
従業員からの「これって有給?欠勤扱い?」といった質問に、自信を持って回答できていますか。
無給休暇と欠勤の違いや特別休暇との関係など、曖昧になりがちな休暇のルールは、思わぬ労務トラブルの原因にもなりかねないため、正しく理解しておく必要があります。
◆この資料でわかること
- 無給休暇・有給休暇・欠勤の明確な違い
- 間違いやすい、無給休暇取得時の給与計算方法
- 慶弔休暇など、会社独自の「特別休暇」の適切な設定方法
- 会社都合で休業させる場合の休業手当に関する注意点
多様化する働き方に伴い、休暇制度の管理はますます複雑になっていますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. アニバーサリー休暇とは


アニバーサリー休暇とは、社員の個人的な記念日に休暇を取得できる制度です。一般的には、社員の誕生日や結婚記念日などがアニバーサリー休暇として設定されます。
アニバーサリー休暇は、特別休暇の一つで法律上明確な規定がないため、社員に記念日を自由に選ばせることも可能です。例えば、プロジェクトの完遂した日を記念日として設定することもできます。
また、ほかの慶弔休暇や病気休暇、夏季休暇などと併せて活用することで、社員の仕事とプライベートのバランスを整える効果が期待できます。
1-1. アニバーサリー休暇が普及した背景・理由
アニバーサリー休暇が普及した背景には、日本企業の有給取得率の低さが大きく影響しています。日本政府は、令和7年(2025年)までに有給取得率を70%とする目標を掲げていますが、現状はその数値に届いていません。
事実、令和6年(2024年)に厚生労働省が公表した調査によると、現状(令和5年会計年度)の有給取得率は65.3%(令和4年会計年度は62.1%)です。
また、以下の理由などから、有給を取ることに対して抵抗を感じている社員も多くいます。
- 周囲の社員に迷惑がかかると感じる
- 有給取得後が多忙になる
- 職場の雰囲気で取得しづらい
このような背景・課題から企業が社員に休暇を促進する一つの手段として、アニバーサリー休暇が普及し始めているのです。
1-2. アニバーサリー休暇(特別休暇)は有給?無給?
アニバーサリー休暇は、年次有給休暇のように法律で定められた休暇ではないため、会社で自由に制度を設計することができます。そのため、有給にすることも、無給にすることも可能です。
無給にする場合、「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき、アニバーサリー休暇中は賃金が支払われないこととなり、制度が利用されず形骸化してしまう可能性もあります。自社の目的にあわせて、有給・無給にするか、慎重に決めることが大切です。
関連記事:特別休暇とは?種類や日数の例、有給休暇との違い・取得した場合の給料を解説
2. アニバーサリー休暇のメリット


アニバーサリー休暇を導入することで、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。ここでは、アニバーサリー休暇を導入するメリットについて詳しく紹介します。
2-1. 有給取得率のアップが期待できる
アニバーサリー休暇を設ける一番のメリットは、有給取得率のアップを期待できることです。
アニバーサリー休暇は、企業が任意で設ける特別休暇の一種であり、たとえ有給であっても、法定の年次有給休暇とは異なるため、有給(年次有給休暇)取得率には含まれません。ただし、アニバーサリー休暇を取得する日に、年次有給休暇を充当する運用にすれば、年休取得実績としてカウントされるので、年次有給休暇の取得率向上につながります。
ちなみに、有給取得率の算出方法は以下のとおりです。
有給(年次有給休暇)取得率 = 社員が取得した有給取得日数 ÷ 会社が付与した有給付与日数
関連記事:有給休暇の取得率とは?現状や計算方法・メリット・向上させる方法を解説
2-2. 社員の仕事への意欲向上が期待できる
社員の仕事に対する意欲の向上が期待できる点も、アニバーサリー休暇を設けるメリットです。
仕事から離れて、1人の時間や大切な人との時間を過ごすことで、心身のリフレッシュにつながります。その結果、社員の仕事へのモチベーションが上がり、生産性の向上も大いに期待できるでしょう。
2-3. 採用活動時の惹きつけ材料となる
アニバーサリー休暇は、採用活動において求職者へのアピール材料の一つとなります。この制度により、「福利厚生が充実している」「社員を大切にしている」といった好印象を与えることができるためです。
アニバーサリー休暇を導入すれば、求人応募者数が増加し、優秀な人材を確保できる可能性が高まります。
3. アニバーサリー休暇のデメリット


アニバーサリー休暇の導入には、メリットだけでなく、デメリットもあります。ここでは、アニバーサリー休暇を導入するデメリットについて詳しく紹介します。
3-1. 休暇を取得する社員が重なると人手不足につながる
万が一、休暇を取得する社員が重なると現場が人手不足になる恐れがあります。
そのため、誕生日や記念日の当日のみならず、前日や翌日もアニバーサリー休暇の対象に含めるなどの工夫や柔軟性が大切です。
3-2. 仕組みによっては社内に浸透せず形骸化する
アニバーサリー休暇の仕組みによっては、社内に浸透しない恐れがあります。
例えば、アニバーサリー休暇を無給扱いにすると、社員にとっては休暇をわざわざ取得するメリットがあまりありません。アニバーサリー休暇を設ける際は、社員が取得するメリットについても意識することが求められます。
3-3. 不公平感をを生む恐れがある
アニバーサリー休暇の取得要件を限定し過ぎると、不公平感を生む恐れがあります。
代表的なものは、結婚記念日です。これでは、そもそも独身の人は利用できません。恋人の誕生日や両親の誕生日、ペットの誕生日など取得要件を幅広く設定することが大切です。
4. アニバーサリー休暇の導入手順


アニバーサリー休暇を導入する場合、就業規則に規定するなど、気を付けるべき点がいくつかあります。ここでは、アニバーサリー休暇を導入する際の手順について詳しく紹介します。
4-1. アニバーサリー休暇の必要性を検討する
まずはアニバーサリー休暇の必要性を検討することが大切です。なぜアニバーサリー休暇を導入するのか目的を明確にすることで、制度の設計もしやすくなります。
リフレッシュ休暇や夏季・冬季休暇など、ほかの特別休暇制度も比較し、アニバーサリー休暇を導入すべきかどうか慎重に判断しましょう。
関連記事:リフレッシュ休暇とは?導入するメリットや事例を解説
4-2. 休暇の対象とする記念日を決める
アニバーサリー休暇を導入する際は、休暇の対象とする記念日を明確に定める必要があります。一般的には従業員本人の誕生日を対象とするケースが多いようですが、既婚者や子育て中の社員が多い場合は、結婚記念日や家族の誕生日なども選択肢として検討するとよいでしょう。
ただし、対象者が限定される記念日を選ぶと、不公平感が生じて従業員の不満につながる可能性もあるため、公平性に十分配慮することが大切です。社内アンケートを実施して従業員の希望を把握したうえで対象日を設定すれば、ニーズに合った制度となり、満足度や取得率の向上が期待できます。
4-3. 制度の詳細を決める
次にアニバーサリー休暇の詳細な条件を決めましょう。具体的には以下の内容を明確にします。
- 有給扱いにするのか、無給扱いにするのか
- 対象となる社員の条件(入社◯年以上など)
- 申請方法やタイミング
- 年に何度取得できるのか
アニバーサリー休暇の制度内容をあらかじめ細かく定めておくことで、対象者や取得条件などをめぐる誤解や不満を防ぎ、従業員とのトラブルを未然に回避することができます。
4-4. 就業規則に明記する
労働基準法第89条に則り、従業員数が常時10人以上の企業は、就業規則の作成義務があります。就業規則には休日や休暇に関する定めを記載しなければなりません。アニバーサリー休暇のような特別休暇を導入する場合も、その内容を明記しておくことで、制度の適正な運用と労使トラブルの防止につながります。
また、就業規則を変更する際は、労働基準法第90条に基づき、労働者代表の意見を聴取する必要もあります。就業規則の変更が完了したら、労働者代表の意見書を添付し、所轄の労働基準監督署に届出もしなければならないので、手続きに注意しましょう。
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
(省略)
(作成の手続)
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
関連記事:就業規則の変更を届出る際の提出方法と気をつけるべき4つの注意点
4-5. 社員に周知する
就業規則の変更後は、労働基準法第106条により、その内容を従業員へ周知する義務があります。とくにアニバーサリー休暇のような新しい制度を導入した際は、従業員が制度を正しく理解し、積極的に活用できるよう、従業員に積極的にアニバーサリー休暇を活用してもらうためにも、説明会や社内セミナーの開催、案内資料の配布などの方法で丁寧に詳細を伝えることが重要です。
(法令等の周知義務)
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、(省略)に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
② 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
5. アニバーサリー休暇の導入事例2選


ここからは、アニバーサリー休暇の導入事例を2つ紹介します。
- A社のアニバーサリー休暇の導入事例
- B社のアニバーサリー休暇の導入事例
それぞれ順番に紹介します。
5-1. A社のアニバーサリー休暇の導入事例
A社は社員のオン・オフのメリハリを重要視しており、さまざまな休暇制度を設けています。その中の一つに、アニバーサリー休暇に相当する「メモリアル休暇」が1996年に導入されました。
このメモリアル休暇により社員は、年2日(事業所によっては3日以上)の記念日休暇を取得可能です。A社の社員は、主に結婚記念日や家族の誕生日、学校の卒業式などにこのメモリアル休暇を活用しているといいます。
こうした取り組みの影響もあり、年間休暇取得率が2%向上するなど、社員の休暇に対する意識を向上させることに成功しました。
5-2. B社のアニバーサリー休暇の導入事例
B社は社員に休暇を取らせることへの意識が高く、先程のA社と同様にさまざまな休暇制度を設けています。そしてその中で、アニバーサリー休暇に相当するものが「誕生日休暇」とよばれるものです。
誕生日休暇は、社員の誕生日に休暇が1日付与されます。誕生日が土日もしくは祝日である場合、前後に移動ができるなど、柔軟性を兼ね備えている点も特徴的です。
このB社の誕生日休暇は社内に十分に浸透しており、毎年7割の社員が休暇を利用しているといいます。
6. アニバーサリー休暇を活用して労働環境を充実させよう


アニバーサリー休暇は、社員の仕事への意欲を向上させると同時に、企業の有給取得率のアップも期待できます。
ただし、安易にアニバーサリー休暇を導入すると社内に浸透しない恐れがあるため、注意が必要です。社員のニーズをしっかりと把握したうえで、アニバーサリー休暇を導入してください。
アニバーサリー休暇を上手に活用できれば、今まで以上に社員にとって居心地のよい会社となるでしょう。
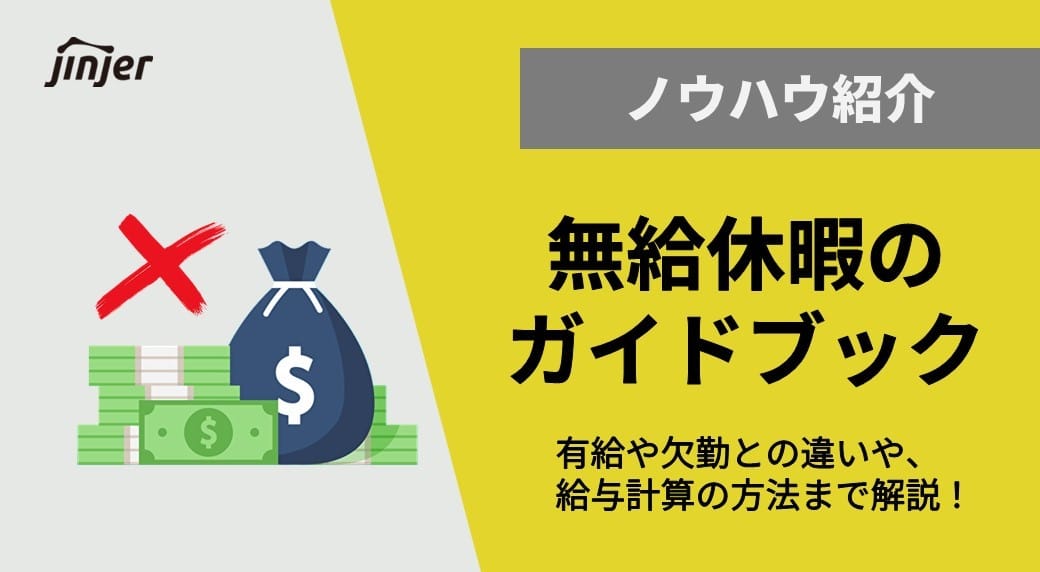
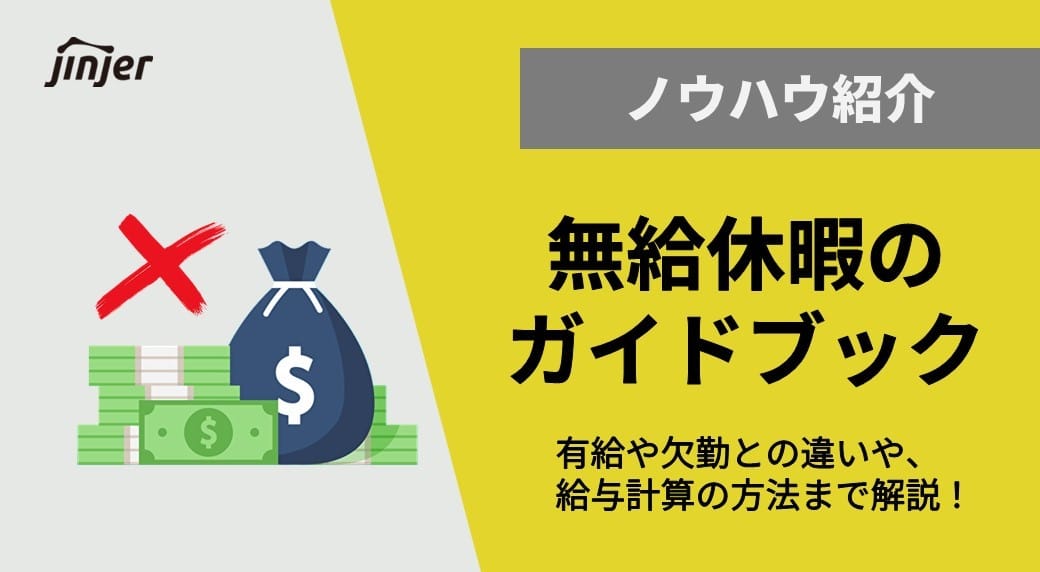
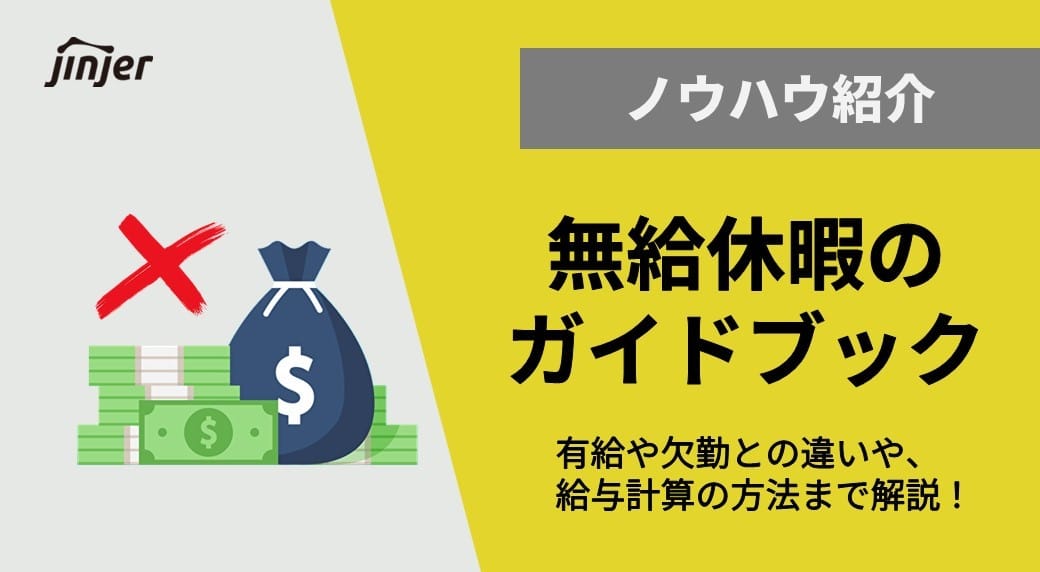
従業員からの「これって有給?欠勤扱い?」といった質問に、自信を持って回答できていますか。
無給休暇と欠勤の違いや特別休暇との関係など、曖昧になりがちな休暇のルールは、思わぬ労務トラブルの原因にもなりかねないため、正しく理解しておく必要があります。
◆この資料でわかること
- 無給休暇・有給休暇・欠勤の明確な違い
- 間違いやすい、無給休暇取得時の給与計算方法
- 慶弔休暇など、会社独自の「特別休暇」の適切な設定方法
- 会社都合で休業させる場合の休業手当に関する注意点
多様化する働き方に伴い、休暇制度の管理はますます複雑になっていますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
労務の関連記事
-


年収の壁はどうなった?2025年最新動向と人事が押さえるポイント
勤怠・給与計算公開日:2025.11.20更新日:2025.11.17
-


2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ
勤怠・給与計算公開日:2025.11.19更新日:2025.12.22
-


人事担当者必見!労働保険の対象・手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.09.05更新日:2026.01.30





















