健康診断の結果の保存期間は?保管までの流れや関連法律を解説
更新日: 2025.9.29 公開日: 2024.12.31 jinjer Blog 編集部
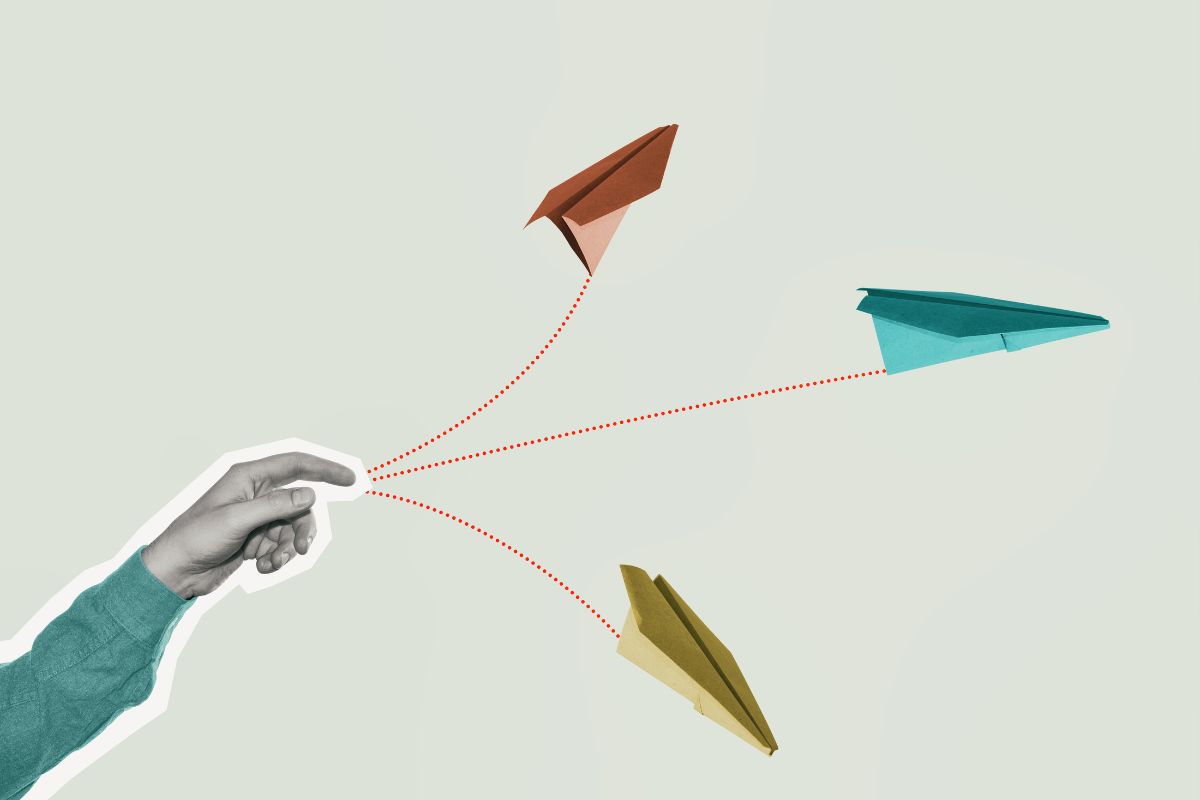
健康診断結果は、一般のもので5年、特殊なもので最大40年保存する必要があります。保存に関しては法律で義務付けられているものなので、勝手に破棄したり保存期間を短くしたりするのは違法になります。
企業には、従業員の健康管理のために健康診断の実施が義務付けられていますが、さらに健康診断結果の保存も義務となっています。健康診断結果は重要な情報になるため、保存期間が長いと管理に手間がかかるかもしれません。しかし、結果を保管しておけば、労災トラブルなどの対処もスムーズにおこなえるので、適切に扱えるようにしましょう。
ここでは、健康診断結果の保存期間や保管までの流れ、注意点を解説します。
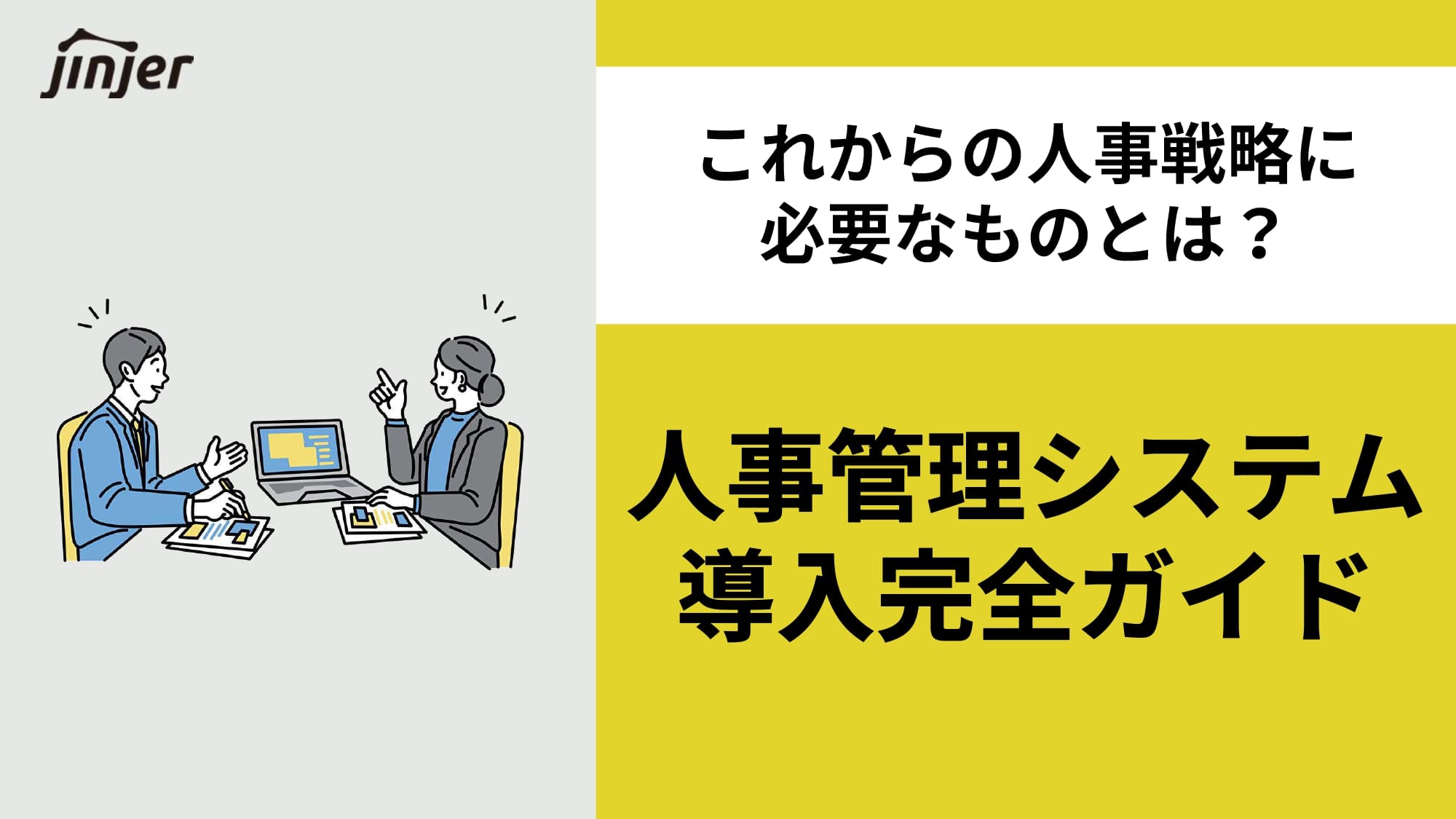
その人事データ、ただ入力するだけで終わっていませんか?
勤怠、給与、評価…それぞれのシステムに散在する従業員データを一つに集約し、「戦略人事」に活用する企業が増えています。
「これからの人事は、経営戦略と人材マネジメントを連携させることが重要だ」「従業員の力を100%以上引き出すには、データを活用した適切な人員配置や育成が必要だ」そう言われても、具体的に何から始めれば良いか分からない担当者様は多いでしょう。
そのような方に向けて、当サイトでは「人事管理システム導入完全ガイド」という資料を配布しています。
◆この資料でわかること
- 人事管理システムを活用した業務効率化の方法
- 人事データにはどのような活用価値があり、活用することで会社が得られるメリットは何か
- 正しい人事データを効率的に管理するためにはどんな機能が必要なのか
人事業務の電子化を検討している方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 健康診断結果の保存期間


健康診断結果の保存期間には、下記のようなルールがあります。
- 一般健康診断は5年
- 特殊健康診断書は40年
また、退職者の結果や廃棄についてもルールがあるので、それぞれを詳しく解説します。
1-1. 一般健康診断は5年
一般健康診断は、企業が5年間保管する義務があります。一般健康診断というのは、全従業員を対象にした健康診断のことを指します。
この保存期間は、労働基準法や労働安全衛生法によって決められていることです。
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
(健康診断の結果の記録)
第六十六条の三 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。
保存しなければならない理由は、従業員の体調に変化があった場合、正確に過去の記録を辿るために必要となるからです。。
ただし、ケースによっては、5年以上の保存が必要になる場合もあるので注意してください。
1-2. 特殊健康診断書は40年
特殊健康診断の保存期間は、5年から最大40年です。特殊健康診断というのは、有機物取り扱い業務や除染等業務など有害物質を扱う業務に従事する従業員を対象にした健康診断です。
長期的に労働者の健康状態を追跡し、今後の健康被害の発生を予防するために長期間の保存が義務付けられています。
健康診断の種類は業務内容によって異なりますが、種類による保存期間は下記のとおりです。
| 健康診断の種類 | 保存期間 |
| 四アルキル鉛健康診断 | 5年 |
| 有機溶剤健康診断 | 5年 |
| 特定化学物質健康診断 | 5年(特別管理物質の場合は30年) |
| 鉛健康診断 | 5年 |
| 高気圧業務健康診断 | 5年 |
| じん肺健康診断 | 7年 |
| 除染等電離放射線健康診断 | 30年 |
| 電離放射線健康診断 | 30年 |
| 石綿健康診断 | 40年 |
放射線やアスベストなどを扱う業務は、長期的な健康の影響が懸念されるため保存期間が長くなるということを理解しておきましょう。
1-3. 退職者の健康診断結果の保存期間について
退職者の場合、会社にはいなくなるので健康診断結果は不要と思うかもしれません。しかし、退職者であっても健康診断結果の扱いは雇用している従業員と同じく、一般健康診断は5年、特殊健康診断は最大40年の保存が義務付けられています。
その理由は、例え退職した後でも、何らかの健康被害が出た場合、在籍していた頃の健康診断結果が必要になる可能性があるからです。「もう辞めたから」と破棄してしまうと、在籍時の健康状態も確認できなくなりますし、そもそも違法になるので注意してください。
ただし、保存期間を過ぎたものは破棄しても良いので、個人情報を漏洩させないためにも、忘れずに消去しましょう。
1-4. 保存期間を過ぎたものは適切に廃棄する
保存期間を過ぎた健康診断結果は、適切に廃棄しなければなりません。保存期間を過ぎても廃棄しない場合、情報漏洩や悪用のリスクが高まるので注意しましょう。
適切な廃棄の方法は、以下のようなものが挙げられます。
- シュレッダーや溶解処理などで確実に廃棄する
- 複数人で廃棄作業をおこない相互チェックをおこなう
- 廃棄の日時や方法などの詳細を記録して適切に保管する
また、健康診断結果が電子データである場合は、復元不可能な方法で削除することが大切です。通常の操作で復元不可能な状態まで削除するのは難しいため、電子データで保管している場合は専用ソフトを使って廃棄してください。
2. 健康診断結果が出てから保管するまでの流れ
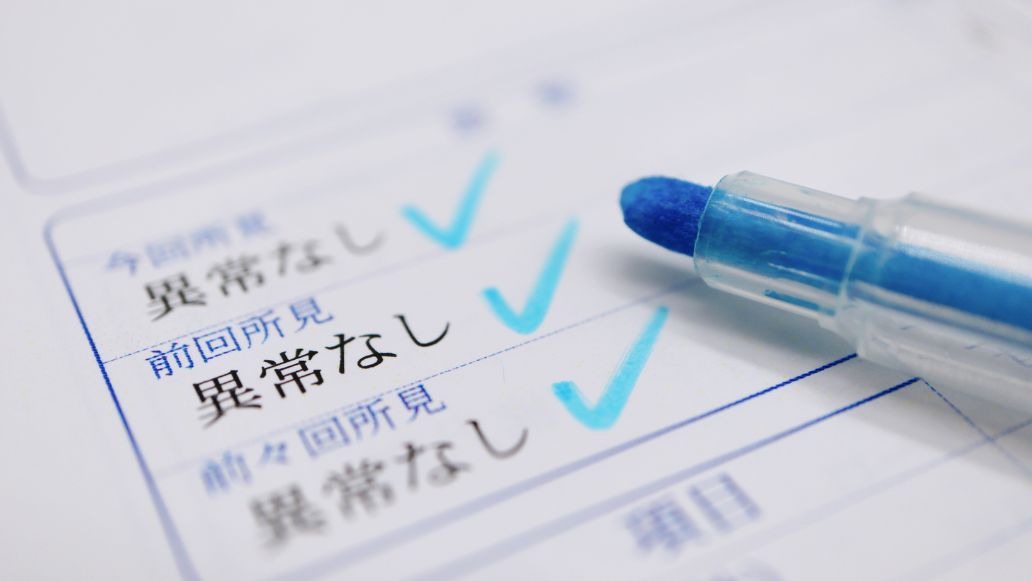
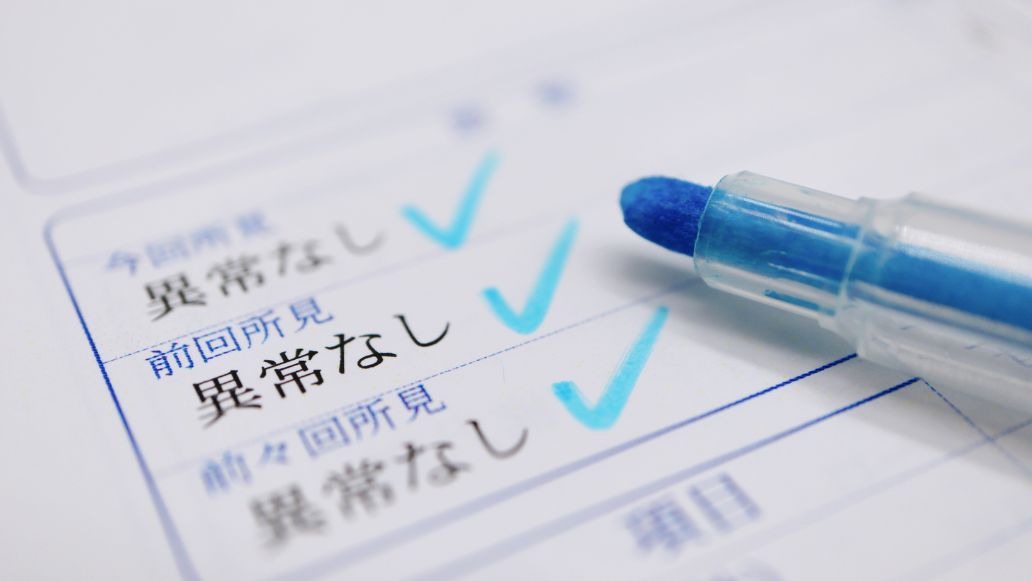
健康診断結果が出てから保管するまでの流れは、次のとおりです。
- 従業員へ通知する
- 事後措置と産業医と実施する
- 所轄監督署へ報告する
ここでは、それぞれの流れを詳しく解説します。
2-1. 従業員へ通知する
健康診断の結果が届き次第、受診した従業員へ通知します。
健康診断の結果は、一般的に「A:異常なし」~「E:要治療」の5段階で判定します。すべての検査項目が「A:異常なし」だった場合、健康状態は「良」となるので通知しなくても良いと思うかもしれません。
しかし、従業員本人が自分の健康状態に問題がないことを把握しておく必要があるため、必ず通知してください。
また、健康状態に異常がある従業員には、再検査を促したり業務内容を改善したりするなどの対策が必要です。どのような対策をおこなうかは本人と話し合うのがベストです。
2-2. 事後措置を産業医と実施する
健康に不安がある従業員がいる場合は、その旨を産業医に伝えて事後措置を実施します。事後措置とは、健康を維持しつつ勤務できるようにするための措置です。
具体的な措置は、以下のようなものが挙げられます。
- 産業医と従業員を面談させヒアリングする
- 安全衛生委員会で対応を相談する
上記をおこなう際は、労働環境や「基準値以上を示す検査項目数」の確認が必要です。
「今までと同じように働いても問題ないか」「問題があればどのように対応するか」を、産業医や安全衛生委員会に判断してもらいましょう。
2-3. 所轄監督署へ報告する
従業員規模が50人以上であれば、所轄監督署へ報告します。報告および「定期健康診断結果報告書」の提出は義務であるため、必ずおこないましょう。
以下は報告書の内容の例です。
- 対象年
- 健康診断年月日
- 受診労働者数
- 所見人数
- 医師の指示人数
「定期健康診断結果報告書」は1年1回提出する義務があるため、前回提出時から1年以上空かないよう注意しましょう。
3. 健康診断結果を適切に保存する方法


健康診断結果を適切に保存する方法は、次のとおりです。
- 個人情報を保護する
- 安全な方法で保管する
- 定期的に確認し更新する
ここでは、これらの方法について詳しく解説します。
3-1. 個人情報を保護する
健康診断結果には従業員の個人情報が含まれているので、企業が適切に保護する必要があります。保護をする理由は、個人情報の流出や悪用により、従業員が思わぬ被害を受けることを防ぐためです。
具体的な保護方法は以下を参考にしてください。
- アクセス権限を厳格に管理する
- 情報漏洩を防ぐために物理的なセキュリティ対策を実施する
- 電子データであれば暗号化技術を導入する
これらの措置をとることで、従業員のプライバシーを保護しつつ企業の信頼性を高められます。
3-2. 安全な方法で保管する
健康診断結果は、安全な方法で保管しましょう。
紙媒体と電子媒体はどちらもメリットとデメリットがあるため、企業にとって適切だと思う方法を選択することが大切です。
| 媒体 | メリット | デメリット |
| 紙 | みやすさに優れている
保存性に優れている |
物理的な損失のリスクがある |
| 電子 | 検索性に優れている
効率的に管理できる |
紙媒体を電子化する手間がかかる |
安全性を重視するなら、物理的な損失のリスクがない電子媒体が優れています。
3-3. 定期的に確認し更新する
健康診断結果の保管に使用するシステムは、定期的な確認と更新が重要といえます。その理由は、古いデータを見直して最新情報を追加することで、有効性を維持できるからです。
また、規則や法律の変更により、保存期間を見直さなければいけなくなる場合もあります。保存期間は法律で決められていることなので、規則や法律が変更になった場合は必ず対応しなければなりません。
特に、保存期間が延長になった場合、破棄してしまうことで違法性を問われることも考えられます。
保存期間の見直しに対応するためにも、健康診断結果のシステムは定期的な確認や更新は「適切な保存」に必要不可欠です。
4. 健康診断結果を扱う際に確認するべきポイント


健康診断結果を扱う際に確認するべきポイントは、次のとおりです。
- 結果は遅滞なく通知する
- 派遣労働者は派遣元事業者が管理する
ここでは、これらのポイントについて詳しく解説します。
4-1. 結果は遅滞なく通知する
健康診断結果は遅滞なく通知しましょう。速やかに通知することで、従業員が健康上に問題があった場合、病気の早期発見にやり素早い対処が可能になります。
過去には、健康診断結果の通知が遅くなったために病状が悪化したことが原因で、損害賠償を求めた裁判がおこなわれた事例があります。損害賠償の裁判に負けた場合は、企業側に賠償責任が生じるのはもちろん、裁判を起こされた会社というネガティブなイメージが付いてしまうリスクがあるので注意してください。
このような万が一のリスクも考慮して、健康診断結果はなるべく早く通知しましょう。
4-2. 派遣労働者は派遣元事業者が管理する
派遣社員の健康診断結果は、派遣元事業者が責任を持つというのが原則です。
派遣社員の雇用主は派遣元事業者になるので、派遣元が責任を持って健康診断を実施することから、派遣先企業では実施や保管の義務がないとされています。
ただし、派遣先の業務が有害物質を取り扱う場合は、派遣先が特殊健康診断をおこなわなければなりません。この場合、派遣先が特殊健康診断を実施するので、特殊健康診断結果の保存も派遣先企業の義務となっています。そのため、派遣労働者の健康診断結果の管理は、派遣先企業と、派遣先から送られた結果を派遣元事業者が一定期間保存するという管理方法になります。
5. 健康診断に関する法律


健康診断に関する主な法律は、次のとおりです。
- 個人情報保護法
- 労働安全衛生法令
ここでは、これらの法律についてそれぞれ詳しく解説します。
5-1. 個人情報保護法
個人情報保護法における「個人情報」は、下記のように定義されています。
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、
次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電
磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。
次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録
され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を
除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる
こととなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれる
健康診断には、名前や生年月日など「特定の個人を識別できる」情報が記載されています。そのため、健康診断結果を取り扱う際は、個人情報の扱いに気をつけなければなりません。万が一漏洩した場合は、悪用により大きい被害を生む可能性があるので、下記のような対策をおこないましょう。
- 個人情報保護法を遵守しつつ適切な管理体制を構築する
- 個人情報の重要性や取り扱い方法に関する教育を定期的におこなう
- 診断書へのアクセス権限を限定する
- 診断書の閲覧やコピーに関する記録を残して追跡可能な体制にする
5-2. 労働安全衛生法令
労働安全衛生法令では、健康診断を医師へ報告することを義務付けています。そのため、医師が従業員の健康診断結果に関する情報提供を求められた場合、企業側は情報を開示しなければなりません。
情報提供には、下記のような項目が挙げられます。
- 労働者の作業環境
- 作業態様
- 作業負荷状況
- 労働時間
深夜業の時間や回数本改正は、過重労働による健康損失の防止やメンタルヘルス対策が急務となった背景から、医師や産業医が効果的に措置を行うために実施されました。本改正によって、医師は従業員の勤務状況などを詳しく把握し、改善に向けてより適切な意見を述べられるようになります。
この法律は、健康被害防止や従業員のメンタルヘルス対策のために定められているもので、産業医が効率よく効果的に措置をおこなうために実施されています。
6. 健康診断結果の保存期間を把握し適切に保管しよう


健康診断結果の保存期間は、一般健康診断で5年、特殊健康診断となると最大40年です。保存期間は厚生労働省によって定められているので、自社の判断で破棄することはできません。
従業員数が多いと保管するのが大変かもしれませんが、保管方法は紙ベースだけでなく電子データでも可能なので、管理しやすい方法を選びましょう。
ただし、健康診断結果はとても重要な個人情報となるため、特に電子データの場合は情報漏洩などがないように保護しつつ安全な方法で保管してください。また、保管プロセスでは結果の受領・確認、管理だけでなく定期的な見直しや処分も含まれているので、保管期間が過ぎたものは適切に処理をしましょう。
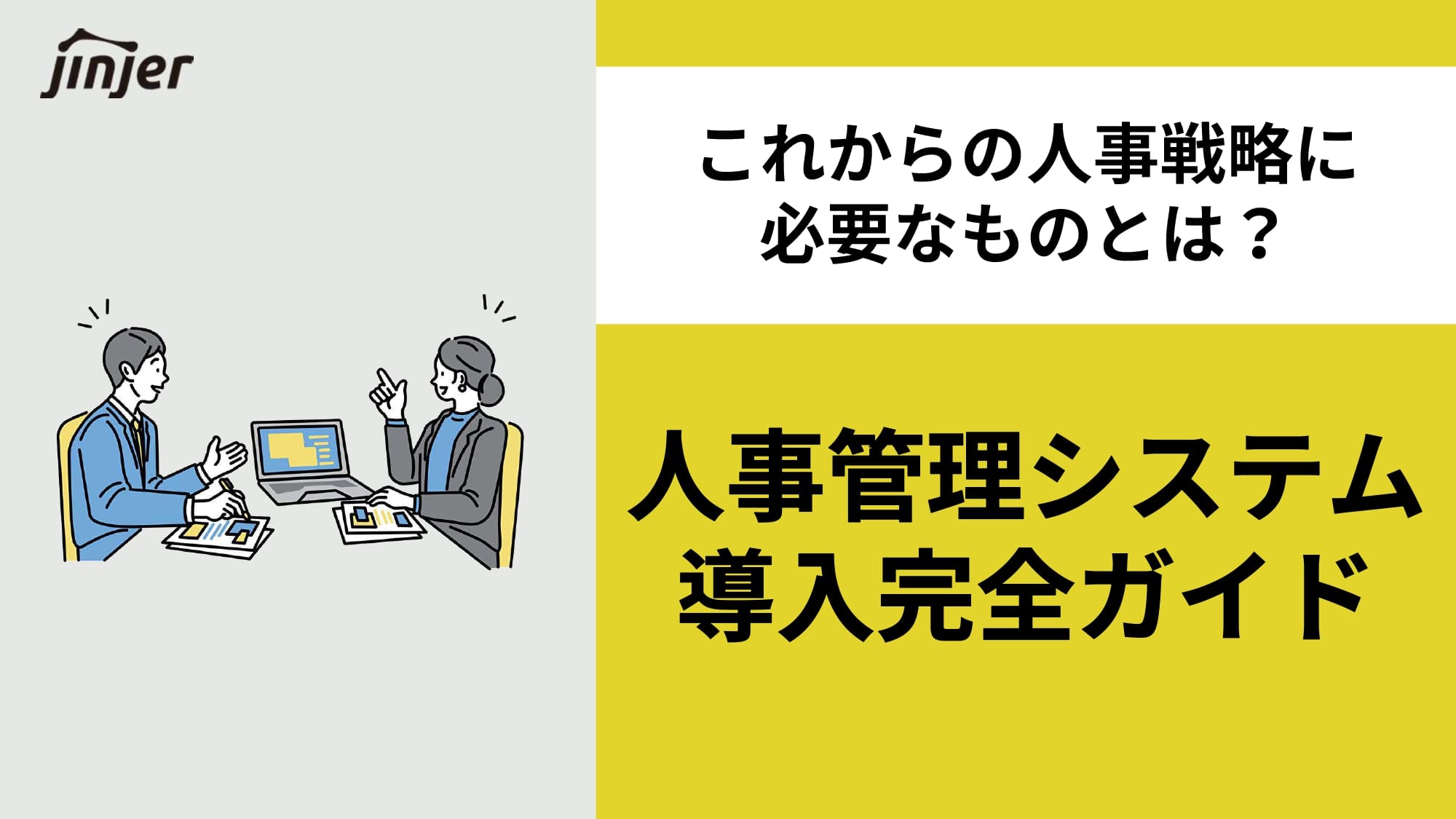
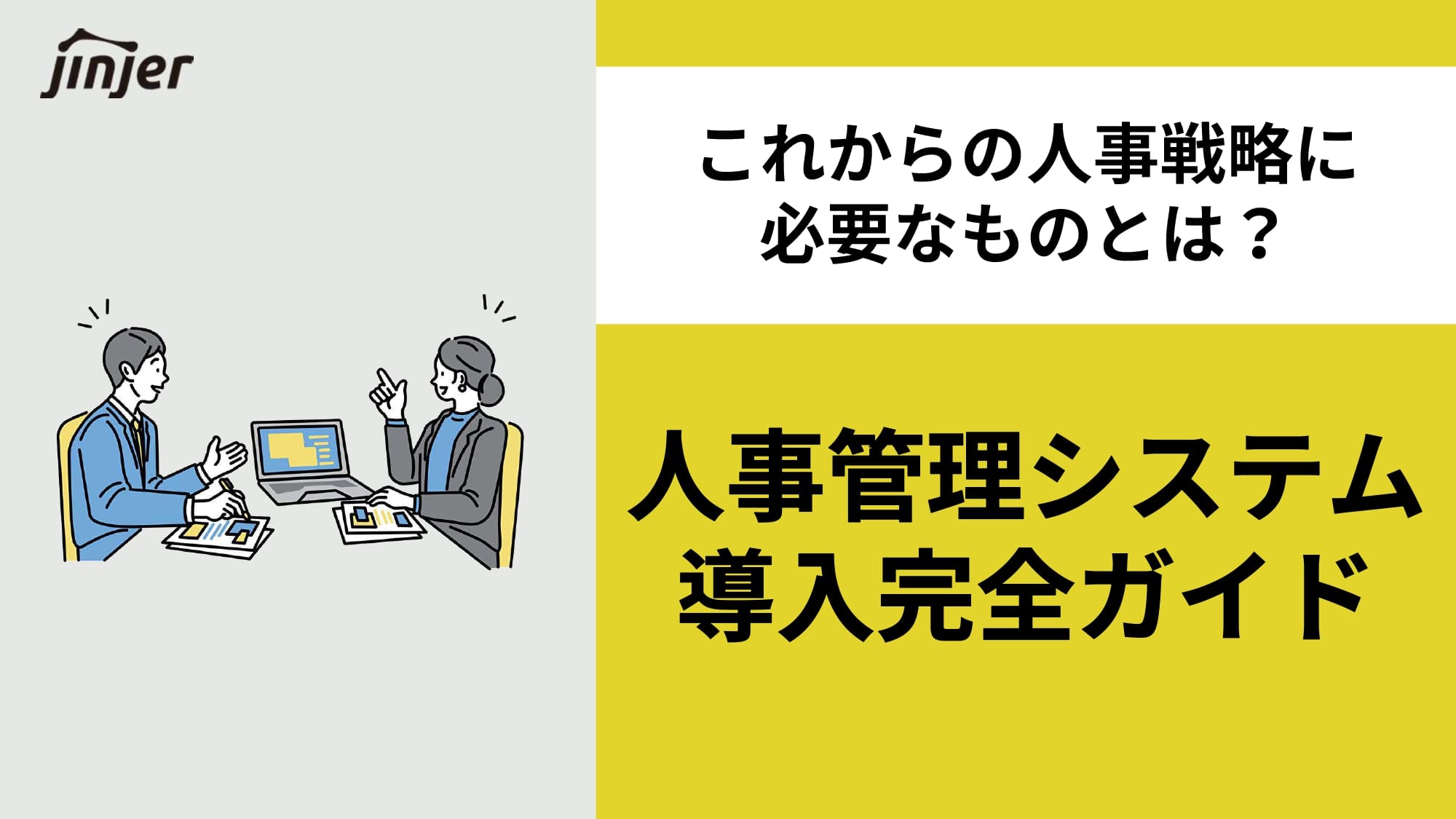
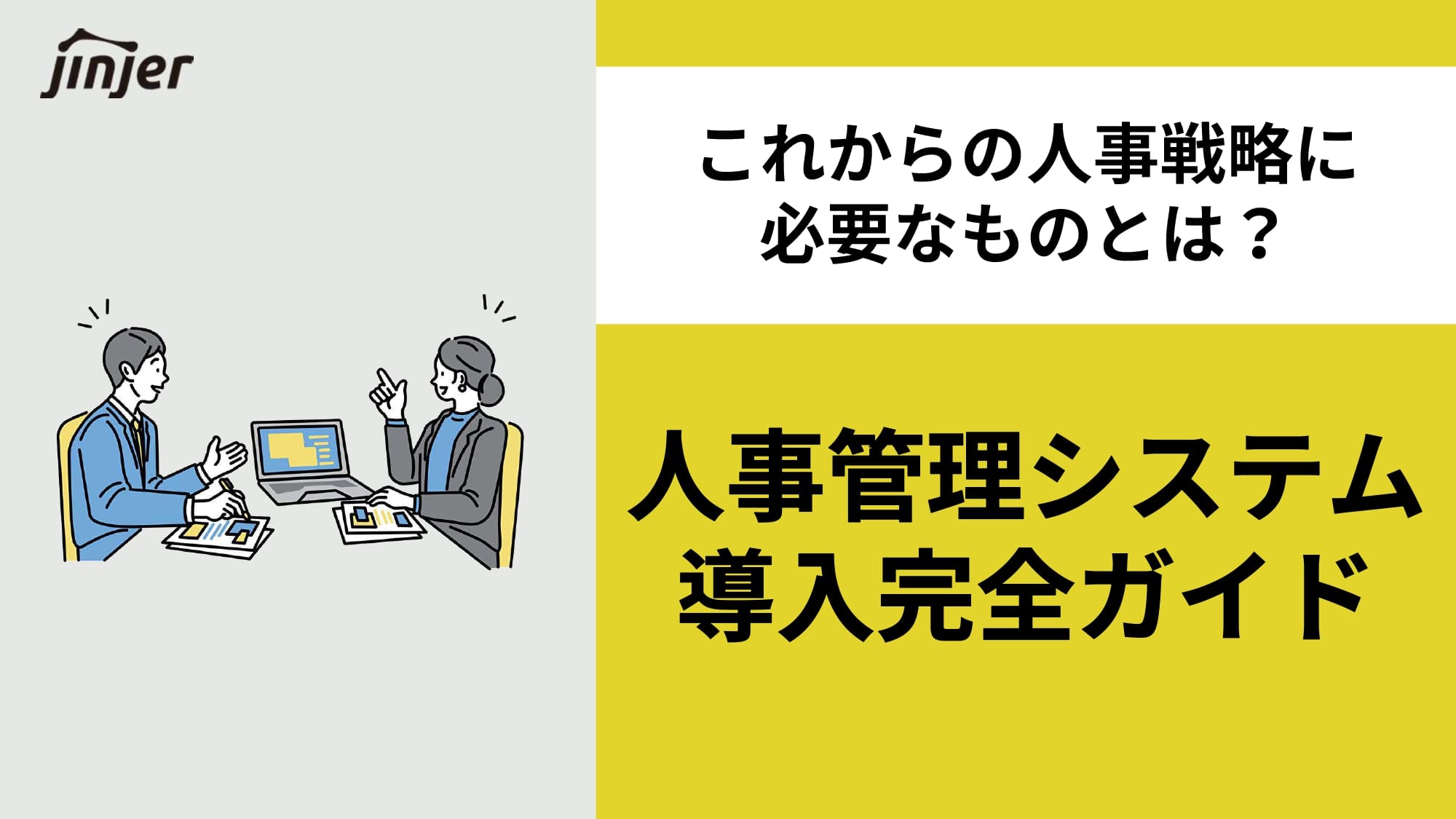
その人事データ、ただ入力するだけで終わっていませんか?
勤怠、給与、評価…それぞれのシステムに散在する従業員データを一つに集約し、「戦略人事」に活用する企業が増えています。
「これからの人事は、経営戦略と人材マネジメントを連携させることが重要だ」「従業員の力を100%以上引き出すには、データを活用した適切な人員配置や育成が必要だ」そう言われても、具体的に何から始めれば良いか分からない担当者様は多いでしょう。
そのような方に向けて、当サイトでは「人事管理システム導入完全ガイド」という資料を配布しています。
◆この資料でわかること
- 人事管理システムを活用した業務効率化の方法
- 人事データにはどのような活用価値があり、活用することで会社が得られるメリットは何か
- 正しい人事データを効率的に管理するためにはどんな機能が必要なのか
人事業務の電子化を検討している方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
労務の関連記事
-


年収の壁はどうなった?2025年最新動向と人事が押さえるポイント
勤怠・給与計算公開日:2025.11.20更新日:2025.11.17
-


2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ
勤怠・給与計算公開日:2025.11.19更新日:2025.12.22
-


人事担当者必見!労働保険の対象・手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.09.05更新日:2026.01.30






















