厚生年金は定年後どうなる?任意継続の可否や再雇用時の扱いを解説
更新日: 2025.9.29 公開日: 2025.2.4 jinjer Blog 編集部

「厚生年金は定年退職した後も任意で継続できる?」
「厚生年金を任意で加入する条件は?」
「定年退職した後に再雇用された人の年金はどうなる?」
定年後の厚生年金について、上記の疑問をもつ人事労務の担当者もいるのではないでしょうか。
厚生年金は、いわゆる3階建ての年金制度の2階部分として、定年退職後の従業員をサポートする制度です。国民年金だけでは老後の生活に不安があることから、なるべく長期間厚生年金の保険料を納め、老後の年金受取額を増やしたいと考える従業員もいるでしょう。
あるいは、保険料の払込期間が年金の受給資格に達するまで、厚生年金の支払いを続けたいと考える従業員もいるかもしれません。
しかし、厚生年金は個人の一存で継続可否が決まる制度ではありません。
本記事では、定年退職した後の厚生年金の扱いについて解説します。退職後に再雇用された人の年金の扱いや、厚生年金を任意で加入できる条件についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
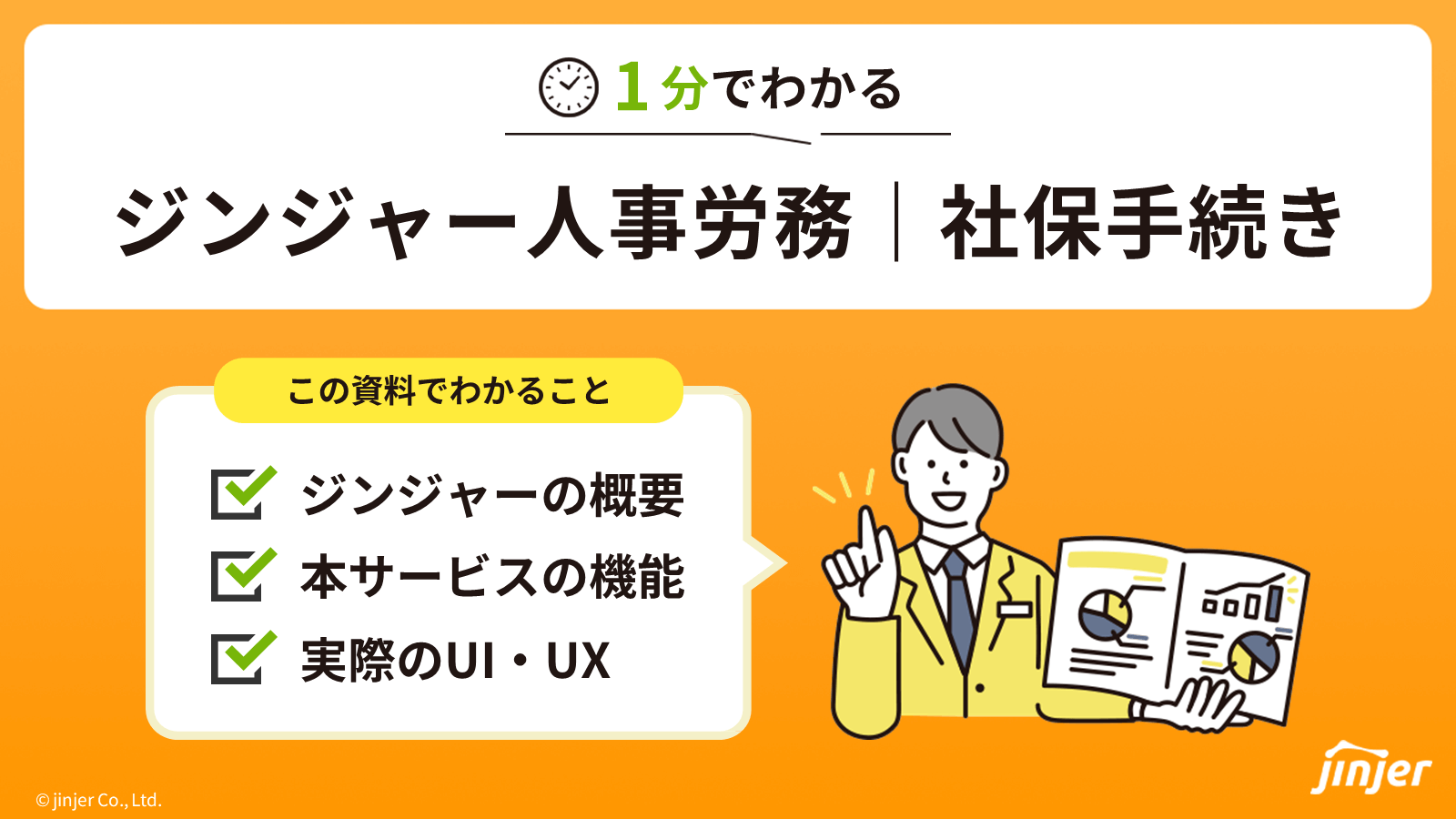
入退社のたびに発生する書類作成、行政機関への提出…。
書き損じや、手続きの度にキャビネットを埋め尽くしていく大量のファイル管理に時間を費やしていませんか?
その手間、電子申請で一気に解決できるかもしれません。
◆紙の書類管理から解放される3つのポイント
- 探す手間からの解放: 保管書類はデータで管理。検索すればいつでもすぐに検索可能。
- 手書き・転記からの解放: 人事データをもとに、面倒な申請書類を自動作成。
- 提出・保管からの解放: 作成した書類はオフィスから一括電子申請、物理的な保管場所も不要。
ペーパーレス化で実現する、新しい働き方の第一歩を提案していますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 厚生年金は定年後に任意継続できない


厚生年金(老齢厚生年金)は、定年退職した後は任意で継続できません。
厚生年金保険料の納付義務は、社会保険適用事業所において現在進行形で働く従業員とその企業に対して発生します。老後の年金受給額をなるべく増やしたいという単純な理由で、退職後も勝手に継続できるものではありません。
一方で国民年金は、20歳から60歳未満までが加入の対象となり、保険料を納付する義務があります。基本的にはこの期間外は加入できませんが、以下の条件に該当すれば、国民年金へ任意で加入可能です。
| 保険料の納付済期間の合算 | 加入年齢の上限 |
| 40年未満(満額受給に満たない場合) | 65歳未満まで |
| 10年未満(受給資格が無い場合) | 70歳未満まで |
なお健康保険制度に関しては、退職後の2年間は任意で企業の健康保険を継続可能です。一般的に企業の健康保険は国民健康保険と比較し、保険給付の内容が手厚いことから、退職後にも継続を希望する人が一定数います。
このような背景から誤解を生じることもありますが、厚生年金はあくまで企業で働く人のための制度であることを押さえておきましょう。
2. 厚生年金は退職後の再雇用によって継続可能
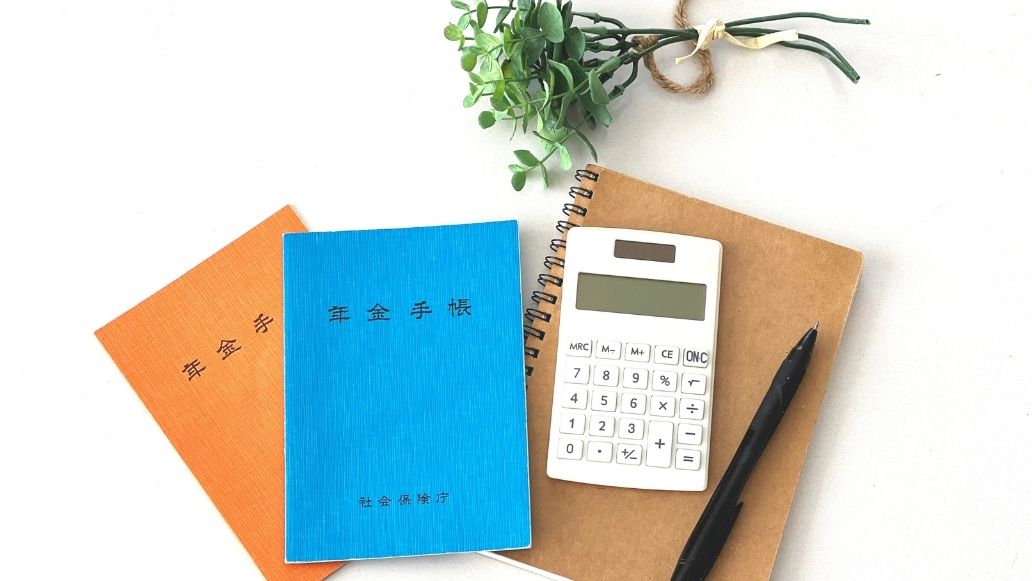
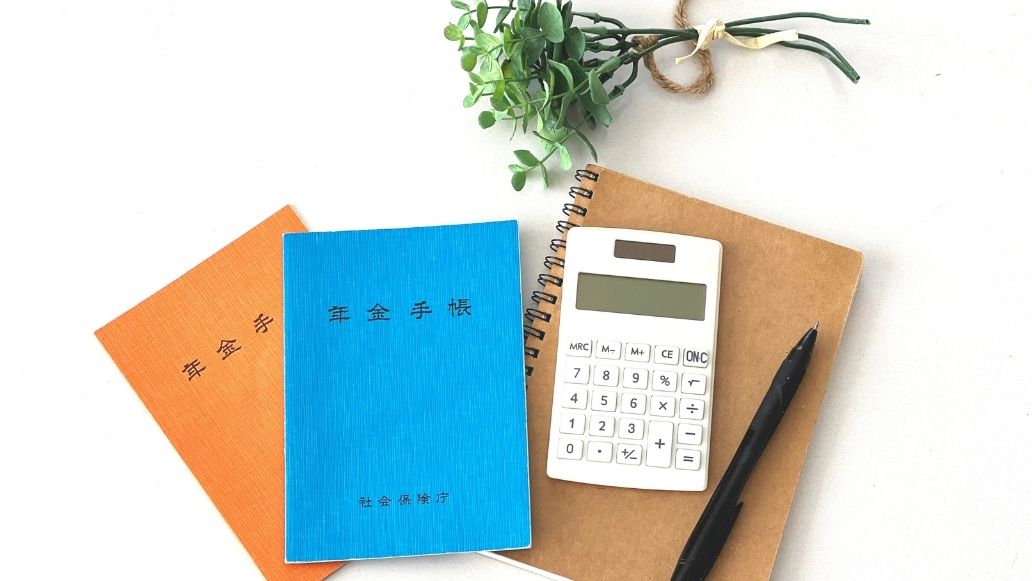
退職した人は、それ以降は厚生年金に加入できません。しかし再雇用されれば、再雇用先で再び加入可能です。
企業に勤めている人は、70歳になるまで厚生年金に加入できます。就職すると納付義務が発生するため、企業側は必ず手続きをしましょう。
70歳以上になると、通常であれば厚生年金の加入資格を失い、保険料の納付義務も失効します。
しかし一定の条件を満たした場合であれば、70歳以降であっても年金の継続が可能です。この制度は、厚生年金の高齢任意加入と呼ばれます。
3. 厚生年金の任意加入の条件


前述した高齢任意加入をおこなう条件は、年金の受給資格をもたないことです。
年金は、免除期間と合わせて10年以上納付していないと受給資格がありません。70歳時点でこの資格を満たしていないのであれば、条件に達するまで高齢任意加入が可能です。
再就職先の企業が社会保険適用事業所でなかった場合にも、企業側と厚生労働大臣が認めれば厚生年金へ任意で加入できます。
厚生年金の高齢任意加入を希望する場合には、書類での申請が必要です。
参考:70歳以上の方が厚生年金保険に加入するとき(高齢任意加入)の手続き|日本年金機構
4. 厚生年金へ任意加入で支払い継続する2つのメリット


従業員が厚生年金へ任意加入し、年金の支払いを継続するメリットは以下の2つです。
- 年金の受給資格が得られやすい
- 国民年金の任意継続より将来的な受給額が大きい
4-1. 年金の受給資格が得られやすい
従業員にとって、厚生年金を任意で続ければ、より確実に年金の受給資格に到達しやすいメリットがあります。不足している期間分の年金を後から継続的に納めていくことで、年金受給の資格に到達可能です。
国民年金も任意で続けられますが、70歳未満までの上限年齢が設けられています。一方の厚生年金は、社会保険適用事業所、もしくは企業と厚労大臣の許可があれば、資格を満たすまで高齢任意加入の形で継続が可能です。
企業で懸命に働き続けさえすれば、年金の受給資格を得られやすくなるのが、厚生年金の高齢任意加入の大きなメリットといえます。
企業側にとっても、働き続けることに高い意欲をもつ従業員を獲得できれば、企業運営に役立てられるでしょう。
4-2. 国民年金の任意継続より将来的な受給額が大きい
国民年金より将来的な受給額が大きいのも、厚生年金の任意加入を続ける従業員側の大きなメリットです。
厚生年金は、国民年金より支払う保険料は高いものの、将来的に受給する年金額の増額が見込めます。企業側が同意すれば、保険料の折半も可能です。
定年退職後、働かずに国民年金の支払いを継続していくのは、年金を受け取るまでの生活を圧迫しかねません。それよりも、働きながら厚生年金を続けた方が、年金を受け取る前も後も、経済的な余裕が生まれやすいでしょう。
5. 定年退職後の再雇用時の国民年金と厚生年金の扱い


定年退職後、再雇用された人の国民年金と厚生年金の扱いをまとめると、以下の表のとおりです。
| 国民年金 | 厚生年金 | |
| 年金支払い期間の条件を満たしている場合 | ・60歳以降は加入不可 | ・社会保険適用事業所で働く限り、70歳になるまでは加入義務あり
・70歳以降は加入不可 |
| 年金支払い期間の条件を満たしていない場合 | ・社会保険適用事業所の場合、国民年金ではなく厚生年金保険料を納付する
・上記に該当しない場合、支払い期間を満たすまで以下のとおり加入可能 ・満額受給に満たない場合:65歳未満まで ・受給資格が無い場合:70歳未満まで |
・社会保険適用事業所で働く限り、70歳までは加入義務あり
・70歳以降も、支払い期間を満たすまでは継続可能 |
日本の法律では、定年退職の年齢を60歳より以前に設定するのは原則的に違法です。そのため、年金の支払い期間の条件を満たしているケースでは、定年退職した後に国民年金を支払うことは基本的にはありません。
一方、厚生年金の支払い義務がなくなるのは70歳以降のため、社会保険適用事業所で働く限り、70歳までは保険料を納める必要があります。そのぶん将来受け取る年金額もアップするため、厚生年金の方がより老後に備えられるといえるでしょう。
なお、参考までに国民年金の話ですが、保険料を40年間納付した人は、10年間納付した人に比べ、およそ4倍の年金を受給可能といわれています。年金の納付期間は、将来の生活に大きく影響を及ぼすため、無理の無い範囲で制度を利用するのが賢明です。
6. 定年退職後の厚生年金に関する2つの注意点


定年退職した後の厚生年金の扱いに関して、注意すべき点は以下の2つです。
- 任意加入した厚生年金の保険料は企業との折半もしくは従業員の全額負担となる
- 年金の受給を開始する年齢には配慮する必要がある
具体的な内容は以下のとおりです。
6-1. 任意加入した厚生年金の保険料は企業との折半もしくは従業員の全額負担となる
70歳以降に厚生年金の任意加入を続ける場合、年金の保険料は企業との折半、もしくは従業員の全額自己負担となります。
保険料が企業と従業員の折半になるのは、以下のケースです。
- 社会保険適用事業所でない企業
- 社会保険適用事業所、かつ企業側が同意した場合
社会保険適用事業所でない企業の場合、そもそも企業側の許可を得て厚生年金への任意加入をおこなっています。そのため、年齢にかかわらず企業側へも保険料の支払い義務が生じる仕組みです。
社会保険適用事業所の場合、企業側が同意しなければ、70歳以降の厚生年金保険料は全額従業員の自己負担となります。自社の事情に合わせ、どこまで従業員をサポートするべきか決定しましょう。
6-2. 年金の受給を開始する年齢には配慮する必要がある
何歳から年金を受給するかについては、従業員に熟考をうながしましょう。
現在では、65歳から年金を受け取ることを基本としつつ、繰り上げ受給や繰り下げ受給が可能です。もしも定年退職後も再雇用で働くのであれば、年金(在職老齢年金)を受け取りながら厚生年金保険料を納め、さらに給与を受け取る選択肢もあります。
しかし、在職老齢年金と給与の合算が月々50万円(令和6年度の場合)を超えると、在職老齢年金の一部もしくは全額が支給停止される決まりです。将来に備えわざわざ再雇用で働いているのに受給額が減ることになりかねないため、従業員には事前にしっかり通達しておきましょう。
なお、この支給停止の判断基準となる金額は、俗に「年金カットの50万円の壁」といわれ、高齢者層の働き控えをまねく要因となっています。
現在、年金は75歳まで繰り下げて受け取れますが、人によっては80歳、90歳になってもまだまだ働く意欲があるものです。生きがいや健康維持のためにも、できれば長く働きたいと考える人も少なくありません。
近年、この壁を見直そうとの向きもあるため、制度の見直しには常に注目しておきましょう。
7. 定年退職後の厚生年金の仕組みを把握し従業員をサポートしよう


定年退職した後は、厚生年金は任意で続けられません。しかし、退職後に再雇用された人は、70歳に至るまでは厚生年金の加入対象者です。
年金の受給資格に満たない場合には、70歳以降であっても加入を続け、保険料を納められます。この際の保険料は、企業と従業員の折半、もしくは従業員の全額自己負担です。
年金制度は、従業員にとって老後の生活を左右する大切な制度といえます。しっかり仕組みを把握し、従業員をサポートしましょう。
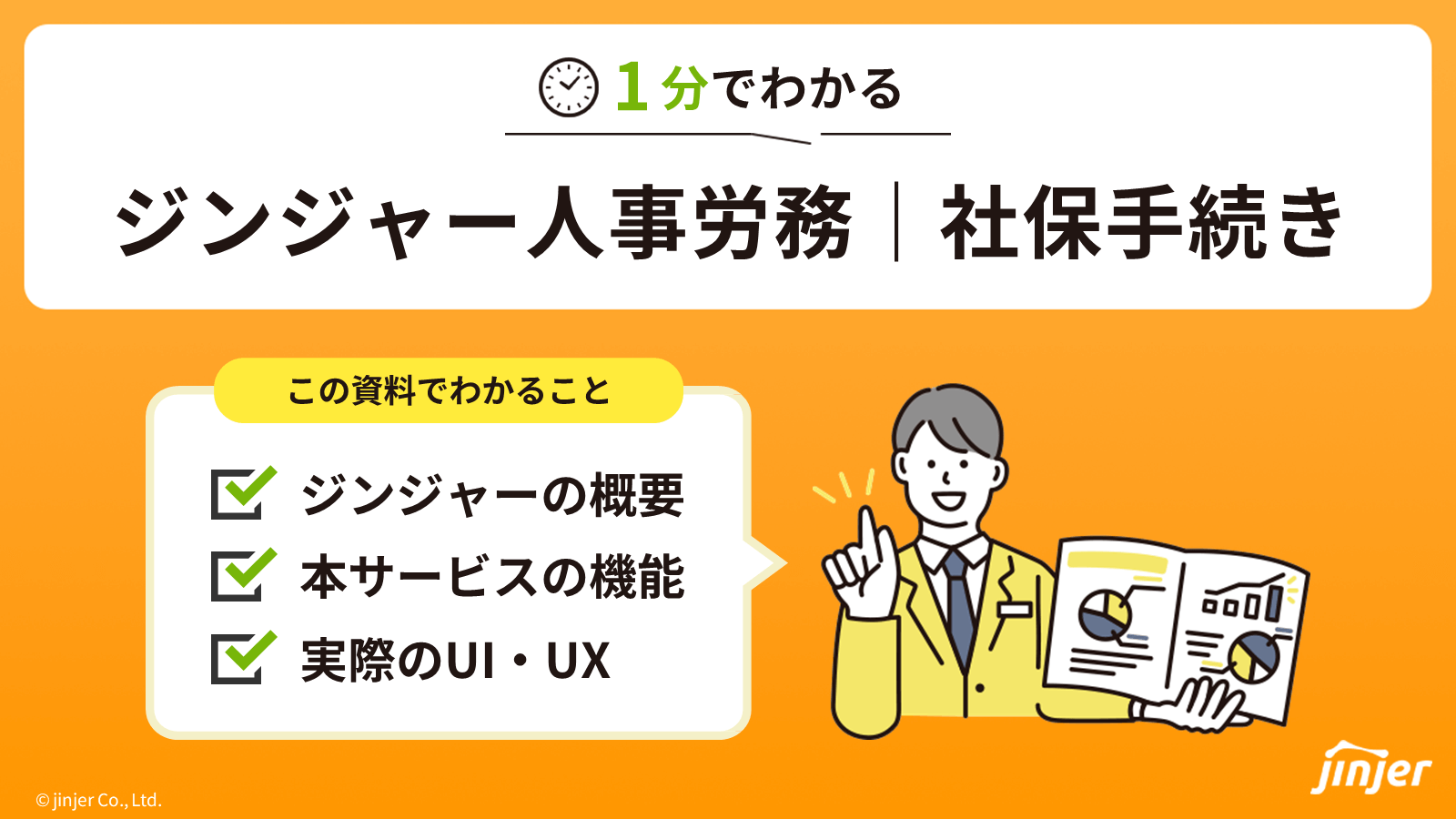
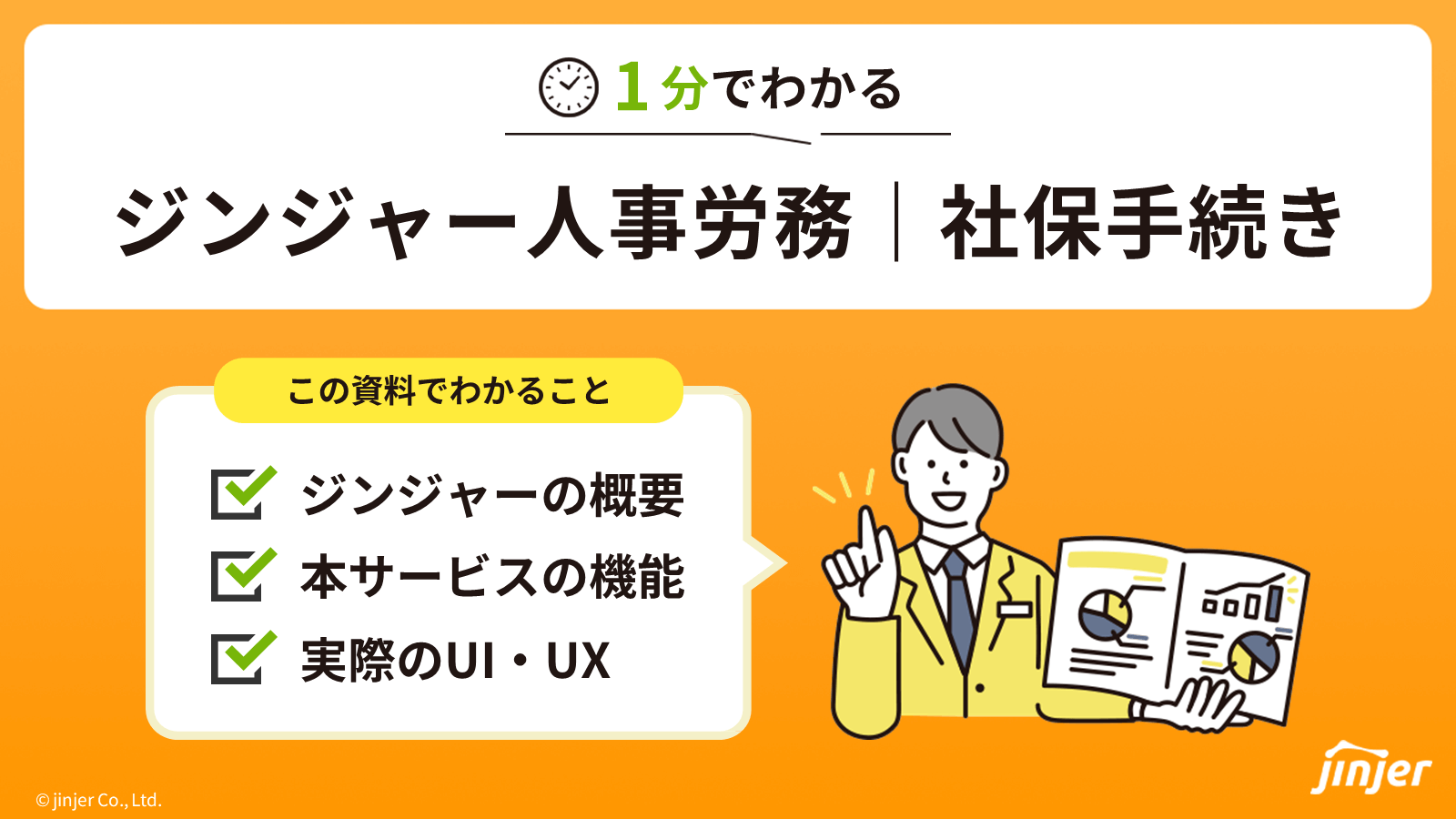
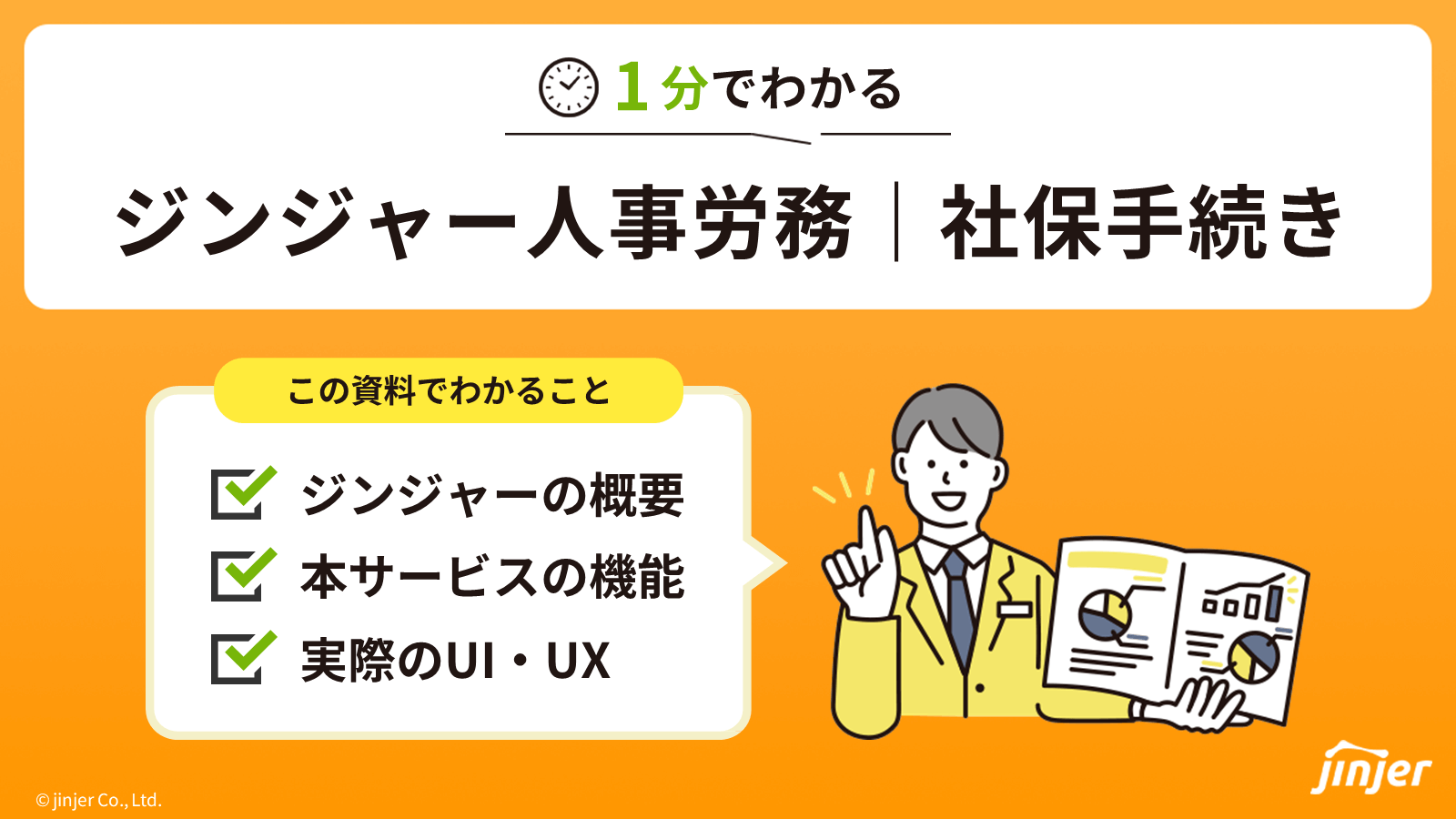
入退社のたびに発生する書類作成、行政機関への提出…。
書き損じや、手続きの度にキャビネットを埋め尽くしていく大量のファイル管理に時間を費やしていませんか?
その手間、電子申請で一気に解決できるかもしれません。
◆紙の書類管理から解放される3つのポイント
- 探す手間からの解放: 保管書類はデータで管理。検索すればいつでもすぐに検索可能。
- 手書き・転記からの解放: 人事データをもとに、面倒な申請書類を自動作成。
- 提出・保管からの解放: 作成した書類はオフィスから一括電子申請、物理的な保管場所も不要。
ペーパーレス化で実現する、新しい働き方の第一歩を提案していますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-



雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
労務の関連記事
-


年収の壁はどうなった?2025年最新動向と人事が押さえるポイント
勤怠・給与計算公開日:2025.11.20更新日:2025.11.17
-


2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ
勤怠・給与計算公開日:2025.11.19更新日:2025.12.22
-


人事担当者必見!労働保険の対象・手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.09.05更新日:2026.01.30




















