雇用契約書と就業規則の優先順位とは?見直す際の2つのポイントを紹介
更新日: 2024.6.12
公開日: 2020.11.19
OHSUGI
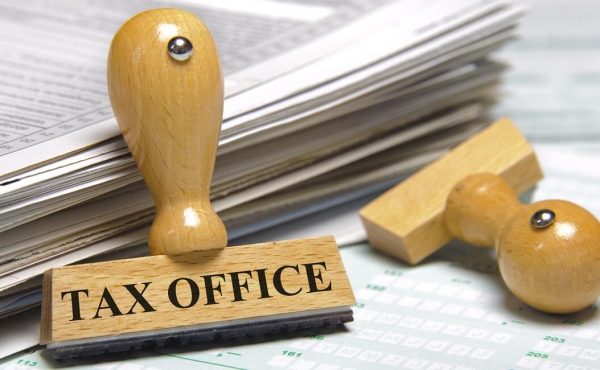
従業員と雇用契約を締結した場合、雇用主はその雇用契約書を作成し、その内容を守らなければなりません。しかし、なかには雇用契約書と就業規則の内容が異なるケースが存在します。
こういった事態は雇用契約書を見直すタイミングでもよく起こることで、人事担当者の方であれば、数年に一回の見直しをする際に困ることも多いのではないでしょうか。
本記事では、雇用契約書と就業規則の内容が異なる場合、どちらの内容を優先すべきなのか、見直すうえでのポイントなどに触れながら解説します。
関連記事:雇用契約の定義や労働契約との違いなど基礎知識を解説
雇用契約は法律に則った方法で対応しなければ、従業員とのトラブルになりかねません。 具体的には、労働条件明示ルールが設定されており、雇用契約の際に明記しておかなければならない項目が制定されていますが、このような法的なルールにも改正が多く情報収集に苦労されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「類似書類と雇用契約の違いが整理できておらず、雇用契約と法律の関係を今一度確認したい」
「最新の法改正で対応しなければいけないことが知りたい」 このような方に向けて、当サイトでは、雇用契約の基礎知識が得られるガイドブックとして、雇用契約の締結方法から注意点をまとめた資料を無料で配布しております。
2024年4月に改正された労働条件の明示ルールについても解説していますので、変更点を確認したい方は是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 就業規則と雇用契約書の違いとは?

まずは就業規則と雇用契約書の違いを把握して、それぞれの重要性や役割を理解しておきましょう。
1-1. 対象になる労働者の規模が違う
雇用契約書を見直す際、就業規則の内容を意識しないと後々労働者との間でトラブルが発生するケースがあるため注意が必要です。見直しにあたり、まずは雇用契約書と就業規則の違いや要点を押さえておきましょう。
それぞれの定義は以下の通りです。
- 就業規則
従業員が就業する上で守るべき規律や、労働条件に関する内容を定めた規則のこと。
会社と従業員全員の間で統一して定められている。 - 雇用契約書
雇用主と労働者間の雇用条件に関する内容が記載された契約書のこと。
会社と従業員それぞれの間で、個別の内容が定められている。
1-2. 就業規則がない場合は違法になる
就業規則の作成義務は労働基準法89条において、以下の通り定められています。
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
作成していない場合には30万円以下の罰金が科せられます。従業員数が10人以上になった場合に就業規則は必要になるため、小規模の会社が新規採用をした際は特に気をつけなければいけません。
また、作成していない場合、助成金をはじめ国に関連する手続きができなかったり、従業員とのトラブルのきっかけになったりします。こういったリスクを無くすためにも、就業規則は必ず作成しておきましょう。
なお、労働条件通知書と異なり、雇用契約書の作成は義務付けられていません。しかし、従業員と安定した雇用関係を保つためにも作成しておいた方が安心です。作成する場合、就業規則と内容が異なる部分がないか見直しをおこないましょう。
もし、雇用契約書と就業規則の内容が異なる場合には、労働者間のトラブルの火種になりやすく、会社側にとってリスクが生じるため、どちらが優先されるかを知っておかなければなりません。
次章では、各記載事項の優先順位について解説します。
関連記事:労働基準法第89条で定められた就業規則の作成と届出の義務
2. 就業規則と雇用契約書の内容が異なる場合の優先順位

ここでは、就業規則と雇用契約書の内容が異なる場合、どちらの内容が優先されるのかを解説します。
2-1. 従業員にとって有利な内容が優先される
労働契約法12条では、就業規則及び労働契約について以下の通り定めています。
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
よって、就業規則と雇用契約書では、従業員にとって有利なほうが優先されます。反対に、就業規則よりも雇用契約書が有利な場合は、その内容が優先されるため、注意しましょう。
関連記事:労働契約法12条による就業規則違反の労働契約を分かりやすく解説
2-2. 就業規則が雇用契約書よりも優先される例
就業規則の内容が雇用契約書よりも好条件になっている場合、基本的には就業規則が優先されます。
具体的に就業規則が雇用契約書よりも優先される例は以下の通りです。
【例1】就業規則で規定されている福利厚生が雇用契約書に含まれていない場合、就業規則に記載のある福利厚生が受けられる。
【例2】残業代の支払いについて、就業規則上には記載があるが、雇用契約書にはない場合、就業規則に記載のある残業代を支払う。
このような場合は、就業規則の内容がより有利であるため
2-3. 就業規則の内容が雇用契約書の内容を下回る場合
上記とは反対に、就業規則の内容が雇用契約書の基準よりも下回っている場合、基本的には雇用契約書が優先されます。
【例1】時給について、雇用契約書には1,000円、就業規則に900円と記載がある場合、雇用契約書に記載のある時給1,000円が優先される
【例2】雇用契約書に、就業規則には書かれていない手当を支給する旨が記載されている場合、雇用契約書に記載のある手当を支給することが優先される
より好条件である雇用契約書が優先されるため、労働者間とのトラブルになることは少ないです。
基本的には就業規則が優先されますが、場合によっては従業員に有利な方が優先されます。
3. 就業規則や雇用契約書と法律の内容が異なる場合の優先順位

就業規則や雇用契約書の内容のほかに、労働に関連する条件は法律や労働協約などによっても定められています。優先順位を知って有効になる条件を把握しておきましょう。
3-1. 法律がすべてにおいて優先される
説明するまでもありませんが、どのような内容の就業規則や雇用契約よりも、法律に記載されている内容が優先されます。優先順位を整理すると、以下のようになります。
1. 法律(労働基準法、労働契約法、民放など)
2. 労働協約(企業と労働組合が締結する取り決めのこと)
3. 就業規則、労働契約(雇用契約など)※就業規則と労働契約の内容が異なる場合は、従業員にとって有利な内容が優先
この優先順位を理解しておくことで、労働協約、就業規則、労働契約において、どの内容が無効となってしまうのかをおおよそ判断することができます。
とはいえ、すべての内容を確認するのにはかなりの手間がかかることは認識しておきましょう。
3-2. 法律に違反する内容は無効
法律に違反する内容の取り決めは、違反する部分のみ無効となり、代わりに法律の基準が適用されます。
また、従業員から労働基準監督署に申し出があった場合、対象企業に対して勧告が来るケースもあります。
このような事態を避けるためにも、新しく規則を作る場合や内容の見直しをおこなう場合には、専門家への確認を依頼した方がよいでしょう。
当サイトでは、雇用契約に関する禁止事項や適切な対応を解説した資料を無料で配布しております。相談する前に、禁止事項を犯していないかなど基本的なことを確認したいというご担当者様は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
4. 就業規則と雇用契約を見直す際の2つのポイント

見直しをする際のポイントは、雇用契約書を新しく作成する際と大きな違いはありません。しかし、万が一のリスクを負わないためにも最低限確認すべき内容をおさえておきましょう。
4-1. 絶対的明示事項と相対的明示事項
雇用契約書を労働条件通知書としても使用する場合には、必ず明示しなければいけない「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」があります。これは労働基準法第15条第1項で規定されたもので、すべての労働者を対象としたルールです。
・絶対的明示事項とは
絶対的明示事項は、労働者に必ず明示をしなければならない項目です。雇用契約書を見直す際はこちらが網羅されているか、今一度確認しましょう。
- 労働契約の期間に関する事項
- 期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること
- 就業場所、従事する業務に関すること
- 始業・終業時刻、残業、休憩、休日・休暇などに関すること
- 賃金の決定や計算方法、支払い方や支払い時期などに関すること
- 退職に関すること(解雇の事由を含む)
- 昇給に関すること
・相対的明示事項とは
相対的明示事項とは、もし会社で規定しているのなら交付すべき項目です。
- 退職手当に関すること
- 賞与などに関すること
- 食費、作業用品などの負担に関すること
- 安全衛生に関すること
- 職業訓練に関すること
- 災害補償や傷病扶助などに関すること
- 表彰や制裁に関すること
- 休職に関すること
現在では働き方改革や法改正を機に雇用契約書だけを変更し、後々就業規則との内容に相違があることが発覚する場合もあるため、見直しを行う際は厳密に確認するとよいでしょう。
なお、2024年4月からは労働条件明示のルールが変更されます。
雇用形態を問わず就業場所と業務変更の範囲を明示する必要があり、有期労働契約の場合は更新と無期転換についての内容が必須になります。現在よりも明示事項が増えるため、留意して備えておきましょう。
参照:労働契約締結時における労働条件の明示義務について|厚生労働省
4-2. 適用範囲の記載
正社員、契約社員、パート/アルバイト等、雇用形態が違えば労働条件も異なります。雇用形態ごとに就業規則と雇用契約書の見直しが必要です。
正社員であれば転勤の有無、契約社員であれば契約期間や契約更新の有無、パート/アルバイトであれば昇給や賞与の有無など、見直しをする点は違うため、必ず各雇用形態と就業規則に整合性があるか確認しましょう。
また、さまざまな雇用形態で雇っているのにもかかわらず、就業規則を1つしか作成していないケースもあります。基本的には就業規則の方が強い効力を持っているため、場合によっては契約社員やパート/アルバイトに正社員と同様の労働条件が適用されることもあります。その際は「どの雇用形態において適用するのか」等、適用範囲を明記するとよいでしょう。
就業規則と雇用契約書の内容が異なった場合、雇用主側が不利になるケースも存在します。そのため、就業規則と内容の整合性が取れるように留意しなければいけません。
また、就業規則においても一度作成すればいいというものでもなく、労働基準法等の法改正がおこなわれた際は適宜変更が必要となります。雇用契約書の見直しをする際は、同時に就業規則の見直しもするようにしましょう。
5. 雇用契約書と就業規則の内容が異なる場合は従業員に有利な方が優先される

これまでお話しした通り、就業規則と雇用契約書の内容が異なる場合、法律的には雇用契約書が就業規則に優先されます。しかし、雇用契約書の内容が従業員により有利な場合は、そちらが採用されることになります。会社側に不利益が発生しないように、整合性のある内容にしておくことが大切です。
雇用契約書も就業規則もない場合には、トラブルのもとになったり従業員のモチベーションが下がったりするなど会社にとっての不利益が数多く生じてきます。
雇用契約書も就業規則も重要な書類であることを認識し、法律に則って作成するようにしましょう。
▼雇用契約のカテゴリでおすすめの記事
パートタイマーの雇用契約書を発行する際に確認すべき4つのポイント
雇用契約は法律に則った方法で対応しなければ、従業員とのトラブルになりかねません。 具体的には、労働条件明示ルールが設定されており、雇用契約の際に明記しておかなければならない項目が制定されていますが、このような法的なルールにも改正が多く情報収集に苦労されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「類似書類と雇用契約の違いが整理できておらず、雇用契約と法律の関係を今一度確認したい」
「最新の法改正で対応しなければいけないことが知りたい」 このような方に向けて、当サイトでは、雇用契約の基礎知識が得られるガイドブックとして、雇用契約の締結方法から注意点をまとめた資料を無料で配布しております。
2024年4月に改正された労働条件の明示ルールについても解説していますので、変更点を確認したい方は是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08



























