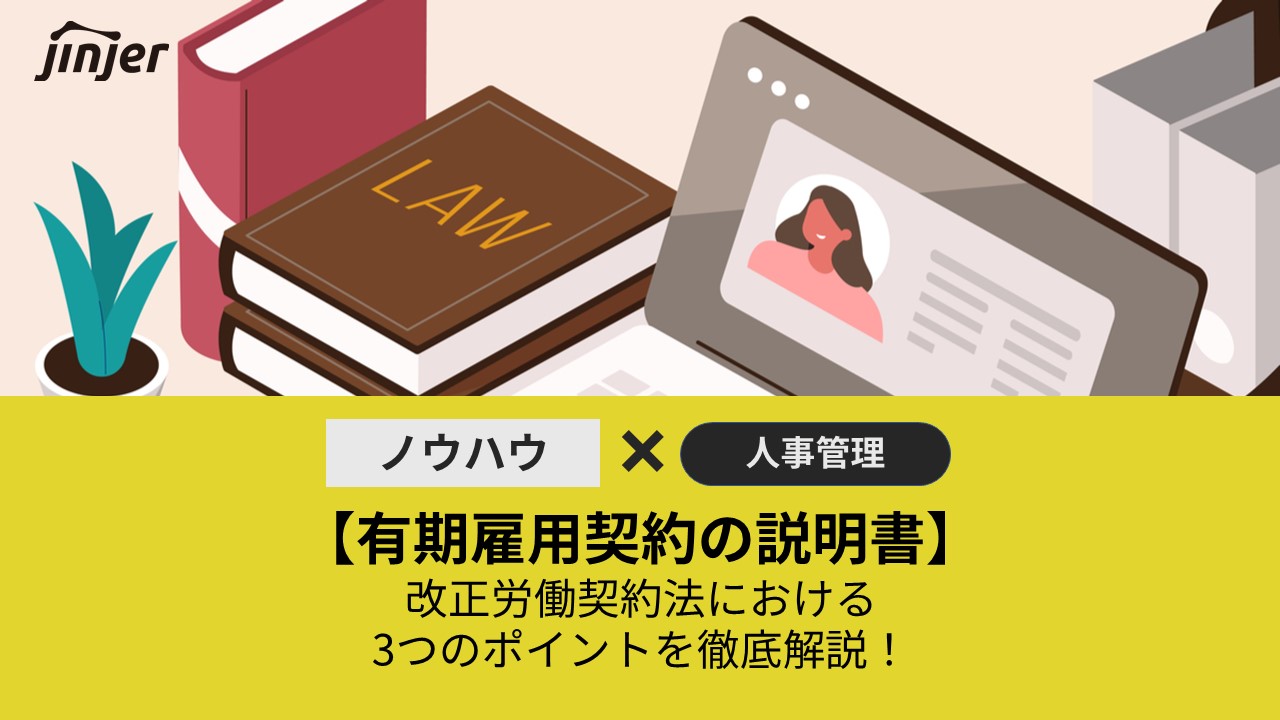労働契約法17条の「契約期間中の解雇」の意味は?業務実績などがやむを得ない理由になるのか解説
更新日: 2024.1.16
公開日: 2021.10.3
OHSUGI

会社側の都合でやむを得ず人員整理をおこなわなくてはならない場合、従業員の解雇に関しては慎重に判断しなければなりません。特に、契約社員やアルバイトといった有期契約労働者の場合は、法律で厳しく解雇について規定されています。
そこで本記事では、有期契約労働者の解雇に関する労働契約法17条について解説します。後で大きなトラブルに発展しないよう、正しい知識を身につけましょう。
▼そもそも労働契約法とは?という方はこちらの記事をご覧ください。
労働契約法とは?その趣旨や押さえておくべき3つのポイント
【有期雇用契約の説明書】
1. 労働契約法17条で規定されたやむを得ない理由による「契約期間中の解雇」とは?

労働契約法17条は、契約社員やアルバイトといった「契約期間」を設けられた有期契約労働者を保護するためにつくられた法律です。
この法律では、有期契約労働者をやむを得ない事由がない限り、契約期間中に解雇してはならないと定めています。
契約期間の途中で解雇されるのは、労働者にとっては予期せぬ出来事です。収入が突然途絶えると生活に大きな影響を及ぼすことから、このような法律が制定されています。
1-1. 契約期間にも配慮が必要
労働契約法17条では、雇用主は契約期間に関しても配慮すべきである旨が明記されています。具体的には、労働者を使用する目的に照らし合わせて、必要以上に短い契約期間を設け労働契約を反復させて更新するようなことがないよう、配慮しなくてはならないと明記されています。
例えば、1年かけて完成させるプロジェクトに従事させる有期契約労働者に、1ヵ月の契約期間を設けて更新を繰り返すようなことです。この場合は、プロジェクトの期間も考慮し、初めから1年間の契約期間を設けなければなりません。
1-2. 契約期間満了で解雇する場合はどうなる?
労働契約法17条によって、有期契約労働者を契約期間中に解雇することは、やむを得ない事由がない限り原則できないことになります。そのため、「契約期間満了をもって解雇すればいいのでは」という考える方も少なくないでしょう。
有期契約労働者を契約期間満了をもって、契約更新せずに解雇することは「雇止め」と呼ばれ、雇止めが濫用されないよう労働契約法19条によって規定されています。この規定は、以下に該当する有期契約労働者に適用となります。
- 過去に契約が反復更新されており、その雇止めが無期労働契約の解雇と同様である
- 契約の満了時に、契約更新がされると期待するような合理的な理由がある
上記に該当する有期契約労働者の雇止めは、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は無効とされます。
関連記事:労働契約法19条に定められた「雇止め法理の法定化」とは?
2. 労働契約法17条による「契約期間中の解雇」の有効性

労働契約法17条は、有期契約労働者の解雇に関する法律ですが、ほかにも解雇を規定する法律があります。
ここでは、ほかの法律との関係と、労働契約法17条による「契約期間中の解雇」の有効性について解説します。
2-1. 民法628条と労働契約法17条との違い
民法628条、労働契約法17条どちらも、労働者の解雇に関して規定している法律です。
ただし、民法628条は「雇用期間が決まっている場合でも、「やむを得ない事由があるとき」は、直ちに契約を解除できる」と規定していますが、「やむを得ない事由があるとき」に該当しない場合の取扱いについては、条文内で明らかにしていません。
このため、「やむを得ない事由があるとき」に該当しない場合の取扱いについても明らかにしておく必要があります。労働契約法17条で「やむを得ない事由があるとき」に該当しない場合は契約期間中に解雇できないと明言することによって、民法628条の不足部分についても補っているのです。
2-2. 労働契約法16条と労働契約法17条の関係
労働契約法17条では、正社員といった無期契約労働者の解雇に関して規定している労働契約法16条よりも、解雇事由を厳しく規定しています。
労働契約法17条に明記されている「やむを得ない事由」とは、「客観的に合理的な理由ある」、「社会通念上相当である」という労働契約法16条の解雇条件です。さらに、一般的には契約を終了せざるを得ないような、重大な事情が必須であると考えられています。
これは、雇用主と労働者双方の合意に基づいて労働期間を定めており、その労働期間は雇用主が雇用を保証したものだとみなされるためです。契約期間の定めのない無期契約労働者の解雇事由と比べても、厳しいものといえるでしょう。
関連記事:労働契約法16条に規定された「解雇」の効力と無効になるケース
2-3. 事前に契約期間内の解雇に合意があっても無効となる可能性がある
特定の事由が生じた際に、契約期間中であっても解雇する場合があるという取り決めを、雇用主と従業員双方で合意していたとしても、やむを得ない事由があるものと認められないとされています。
例えば、営業ノルマ未達成が5ヵ月続いたら契約期間中でも解雇するといった内容を雇用主と従業員で合意しているようなケースです。この場合は、
解雇事由の内容から、やむを得ない事由に該当するのか個別に判断されることになり、解雇に合意していたとしても無効とされてしまう可能性があります。
3. 労働契約法17条による「契約期間中の解雇」のよくある事例

最後に、過去の裁判例をもとに契約期間中の解雇でよくある事例をいくつか紹介します。
3-1. (事例1)労働者の行動を問題とした契約期間中の解雇
学校法人の塾長として4年間の有期労働契約を締結した労働者が、普段の行動に問題があることを理由に契約期間中に解雇されたため、解雇権の乱用であると主張し、労働契約上の地位確認等を求め提訴しました。
確かに問題となる行動はあったが、極めて不適切とまでは言い切れず、「やむを得ない事由」には該当しないとされ、契約期間中の解雇は無効とされました。
参考:独立行政法人 労働政策研究・研修機構:(93)期間途中の解雇
3-2. (事例2)派遣先企業の業績不振による契約期間中の解雇
6ヵ月の有期労働契約を締結し、派遣業務に従事していた労働者が、派遣先企業の経営状態悪化により、契約期間中に派遣会社から解雇を予告されましたが、当該労働者はこれを不服とし、契約期間満了までの賃金の仮払いを求める申し立てをしました。派遣会社が、他の派遣先を探すなどを努力をせず、契約期間中に一方的に解雇することは「やむを得ない事由」に該当しないとされ、契約期間中の解雇は無効となりました。
参考:独立行政法人 労働政策研究・研修機構:(95)派遣労働関係をめぐる法的課題
4. 解雇手続きは労働基準法17条に則っておこなわなければならない

労働契約法17条は、有期労働契約が契約期間中に不当に解雇されないよう保護するための法律です。この法律では「やむを得ない事由」がある場合でなければ、契約期間中に解雇することは認められないとされています。
有期契約労働者は、契約期間が雇用主の合意に基づいて保証されていることから、正社員に適用される労働契約法16条の内容よりも厳しく規定されています。
法律に則って解雇手続きがおこなわれないと、解雇が無効になるだけでなく、損害賠償の支払いを命じられる可能性もでてきます。労働契約法17条をはじめ、解雇に関する法律の知識をしっかりと身につけて、解雇をおこなう場合は慎重に手続を進める必要があるでしょう。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08