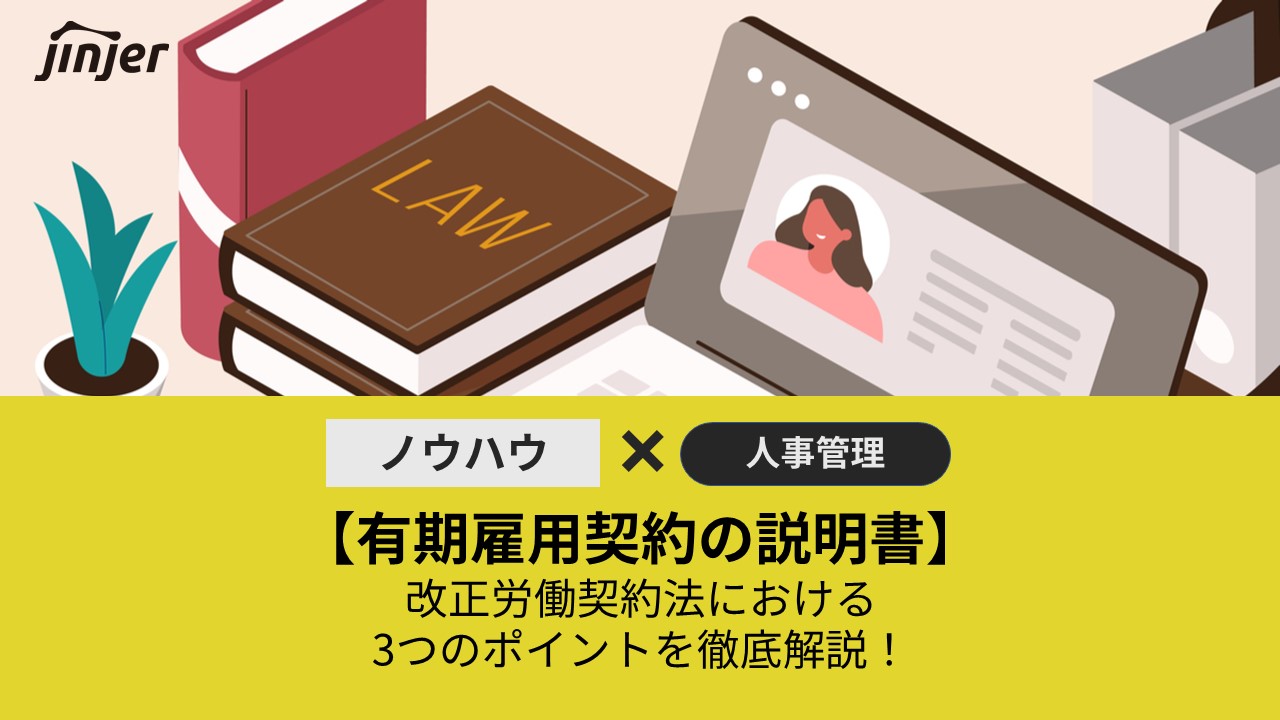労働契約法19条に定められた「雇止め法理の法定化」とは?
 労働契約法16条は解雇について定めれているのに対して、労働契約法19条の「雇止め法理」は、雇止めの法的制限を目的に定められました。16条、19条の違いはどこにあるのでしょうか。
労働契約法16条は解雇について定めれているのに対して、労働契約法19条の「雇止め法理」は、雇止めの法的制限を目的に定められました。16条、19条の違いはどこにあるのでしょうか。
今回は、労働契約法19条によって定められた「雇止め法理の法定化」の概要や対象となる契約、また、雇止め法理の法定化に規定された内容によりもたらされる効果について解説します。
▼そもそも労働契約法とは?という方はこちらの記事をご覧ください。
労働契約法とは?その趣旨や押さえておくべき3つのポイント
目次
【有期雇用契約の説明書】
1. 労働契約法19条による「雇止め法理の法定化」とは?

ここではまず、労働契約法19条による雇止め法理の法定化の概要について確認しておきましょう。
労働契約法19条「雇止め法理の法定化」とは、有期労働契約における契約期間満了にともなって発生する雇用契約終了(雇止め)に対し、一定の条件を満たす場合に限り、雇止めを無効とする「雇止め法理」をルール化して定めたものです。
これは過去の最高裁判所で確立した判例をもとに法定化されたもので、有期労働契約者を守るための法律として成立しました。
1-1. 労働契約法19条による「雇止め法理の法定化」の目的
雇止め法理の法定化の背景には、以前は企業側の都合による雇止めがおこなわれていたことがあります。労働者が有期労働契約の反復更新に際し、長期雇用や契約更新を期待させていたにもかかわらず、一方的に雇止めを通達されるケースもみられたようです。
つまり、労働契約法19条による「雇止め法理の法定化」は、主に労働者を保護する目的で定められたルールといえます。
2. 労働契約法19条で「雇止め法理」の対象となる契約

ここでは、労働契約法19条の対象となる有期労働契約について紹介します。
2-1. 労働契約法19条で「雇止め法理」の対象となる労働者
原則、対象となる労働者は、期間のある労働契約を締結している有期労働契約者です。具体的には、パートやアルバイト、契約社員、派遣社員の労働者が該当します。
また、パートナー社員、準社員といった独自の雇用形態を採用している場合でも、期間の定めがある契約を締結しているのであれば、「雇止め法理」の対象となるので注意が必要です。
関連記事:労働契約法18条に定められた無期転換ルールを分かりやすく解説
2-2. 労働契約法19条で「雇止め法理」の対象となる有期労働契約とは
労働契約法19条では、以下いずれかにあたる場合の有期労働契約を対象としています。
- 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの
- 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの
以下、それぞれについて詳しく説明します。
参考:労働契約法改正のあらまし-II 「雇止め法理」の法定化(第19条)|厚生労働省:
1. 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの
期間の定めがある労働契約がある場合でも、業務内容や更新手続きの状況などから、有期契約といえども期間の定めのない契約と同様の状況になっているものが挙げられます。
2. 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの
こちらは、長期にわたる更新が無く、1の事例にあたらないときでも、業務の内容や使用者・労働者間の認識から、労働者側が雇用の継続を期待するに足る合理的な理由がある場合が挙げられます。
2-3. 労働契約法19条で「雇止め法理」が適用される条件
労働契約法19条で「雇止め法理」が適用される条件には、次の2つが挙げられます。
- 契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合
- 契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合
上述の有期労働契約の「更新の申込み」および「締結の申込み」は、正式な契約書を要するわけではなく、雇止めに対し労働者側から何らかの反対を示せばよいということになっています。そのため、口頭による申立てでも認められると考えてよいでしょう。
また、紛争調整機関への申し立てなど、間接的な伝達も認められます。
3. 労働契約法19条で「雇止め法理」がもたらす効果

労働契約法19条で定められている「雇止め法理」によってもたらされる効果を確認しましょう。
まず上述にもあったように、「雇止め法理」の対象となる有期労働契約の場合、会社側が雇止めを実施することに対して「客観的かつ合理的な」理由がなく、社会通念上適当でなければ、雇止めは認められなくなります。
このように認められなかった場合には、以前と同じ労働条件で、有期労働契約の更新がおこなわれることとなります。
また条件を満たしてさえいれば、労働契約法18条の「無期転換ルール」が適応され、無期労働契約への更新がおこなわれることもあるでしょう。
4. 雇止めが認められる合理的な理由

ここまで、労働契約法19条「雇止め法理の法定化」について説明してきました。
しかし、正当な理由があれば、使用者側からの雇止めが認められる可能性があります。具体的には、次の2つの理由が挙げられます。
- 正社員に近い就労実態で通常の解雇と同様な理由がある
- 有期労働契約者でも会社の事情が発生して解雇が必要となった
以下、それぞれについて詳しく説明します。
4-1. 正社員に近い就労実態で通常の解雇と同等な理由がある
有期労働契約者であっても、正社員に近い就労実態となっている場合は、正社員を解雇するときと同等の理由が求められます。
具体的には、次のような3つの理由に該当する場合に、有期労働契約者でも通常解雇が可能です。
- 勤務怠慢が著しく認められる
- 能力不足が認められるだけでなく、改善の余地もない
- 体調不良・ケガが原因で就労できない
該当の有期労働契約者にこれら3つの理由が認められるだけでなく、改善が見受けられない場合には、通常の解雇が認められると考えてよいでしょう。
4-2. 有期労働契約者でも会社の事情が発生して解雇が必要となった
有期労働契約者の場合であっても、会社の事情によっては解雇可能な場合があります。
例えば、会社の経営が厳しくなり、雇用の継続が難しくなったというときには、雇止めによる解雇も認められます。
関連記事:労働契約法16条に規定された「解雇」の効力と無効になるケース
5. 「雇止め法理」における注意点

「雇止め法理」によって、企業は雇止めをおこなうことが難しくなっています。
従業員の雇止めをおこなう際にトラブルを起こさないようにするためにも、注意点を押さえておきましょう。
5-1. 不更新条項を定めておく
契約書で次回は契約更新をおこなわない旨に合意してもらうことで、雇止めがおこないやすくなります。
ただし、必ずしも雇止めが認められるとは限らないため注意しておきましょう。
なお、契約を結ぶ際には従業員とのトラブル起こさないように、丁寧な説明を心がけましょう。
5-2. 雇用期間の管理を徹底する
人事担当者は従業員の雇用期間を正確に把握し、必ず更新期間の1ヵ月以上前に契約満了の通達をおこないましょう。契約期間の自動更新が一度でもおこなわれている場合には、義務ではありませんが、退職合意書を交わすなどの対応も必要になるかもしれません。
5-3. 更新を期待させる言動は避ける
労働契約法19条における「有期労働契約が更新されると期待する合理的な理由があること」に当てはまる場合、「雇止め法理」が適応されてしまいます。
そのため、管理職クラスの従業員に対して、契約に関する言動への教育を徹底しておくと良いでしょう。
6. 「雇止め法理の法定化」を正しく理解し、労働者との雇用契約を締結しよう

今回は、労働契約法19条に定められた「雇止め法理の法定化」について、概要や対象となる契約などを中心に紹介しました。また、雇止め法理の法定化によって発生する効果や、注意点についても解説しました。
一度雇用契約を結んだ場合は、簡単に解雇することはできません。むやみに雇止めをおこなっていると損害賠償請求の対象ともなるため、注意が必要です。
労働者との雇用契約を結ぶ際には、あらかじめ雇止め法理を正しく理解しておくことが重要となります。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08