労働基準法における解雇とは?種類や方法・解雇が認められる理由から円満解雇するための秘訣を解説
更新日: 2024.7.17
公開日: 2021.10.4
OHSUGI

使用者(事業主)からの一方的な申し出により、雇用契約を解消することを「解雇」といいます。
労働者を解雇する理由はそれぞれですが、いつでも自由に行使できるわけではなく、労働基準法に基づく一定のルールを遵守していなければ不当な解雇となってしまいます。
場合によっては訴訟に発展することもありますので、解雇を検討する際は基本的なルールをしっかり把握しておきましょう。
今回は、労働基準法による解雇のルールや、円満解雇するための秘訣について解説します。
▼そもそも労働基準法とは?という方はこちらの記事をまずはご覧ください。
労働基準法とは?雇用者が押さえるべき6つのポイントを解説
目次
労働者保護の観点から、解雇には様々な法規定があり、解雇の理由に合理性が無ければ認められません。
当サイトでは、解雇の種類や解雇を適切に進めるための手順をまとめた資料を無料で配布しております。合理性がないとみなされた解雇の例も紹介しておりますので、法律に則った解雇の対応を知りたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. そもそも解雇とは?解雇の種類

解雇とは、会社側からの意思表示により労働契約を終了させることを言います。
しかし、一方的な意思表示で労働契約を終了させるとはいえ、会社側が自由に行えるものではなく、法律でルールが定められています。
実際に、労働契約法では以下のとおり定めています。
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) |e-Gov法令検索
「客観的に合理的な理由」があり、かつ「社会通念上相当である」と認められるだけの事由がなければ、解雇は無効とされてしまいます。「客観的に合理的な理由」や「社会通念上相当」に関しては、これという明確な基準はありませんが、解雇の事由によってその種類は大きく3つに区分されます。
参考:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) |e-Gov法令検索
参考:しっかりマスター労働基準法-解雇編-|厚生労働省
1-1. 普通解雇
後述する整理解雇・懲戒解雇以外の解雇のことです。
労働契約を継続することが困難な事情がある場合に行使されるもので、一般的には以下のようなケースがあります。
- 勤務成績が悪く、かつ指導をおこなっても改善の見込みがない場合
- 健康上の理由により、長期間にわたって職場復帰が見込めない場合
- 業務に支障を来すほど協調性に乏しく、指導をおこなっても改善の見込みがない場合
①、③については客観的に、誰が見ても勤務態度に問題がある場合に限られており、かつ使用者が改善のための指導をおこなっていたかどうかが焦点となります。
例えば、外回り営業中にサボってパチンコ通いを続けており、上司の指導および研修を実施したが、その後も態度が改められなかった…といった場合には、普通解雇が認められます。
一方②のケースですが、業務上の負傷や疾病については、その療養期間およびその後30日間は、解雇することができません。
ただし、事故の後遺症によって簡易な職務にも就けない場合や、長期の入退院を繰り返すような精神疾患にかかり、かつ回復の見込みがないと判断された場合などは、普通解雇が正当とみなされる場合もあります。
以上、普通解雇の代表的な事例をご紹介しましたが、正当な理由があった場合でも、使用者は労働者に対し、少なくとも30日前には解雇を予告しなければなりません。
天災事変などやむを得ない事情によって事業継続が困難になった場合はこの限りではありません。
参考:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) |e-Gov法令検索
1-2. 整理解雇
会社の経営悪化によって人員整理をおこなわなければならない場合の解雇です。
いわゆるリストラのことで、事業を継続するためのやむを得ない措置となりますが、整理解雇をおこなうには以下4点のいずれも満たすことが条件となります。
- 整理解雇することに客観的な必要性が認められること
- 解雇を回避するため、最大限の努力をおこなったこと
- 解雇の対象となる人選の基準、運用が合理的であること
- 労使間で十分に協議をおこなったこと
つまり、整理解雇は最終手段であり、企業側はそこに至るまでに八方手を尽くしたかどうかが重要なポイントになります。
1-3. 懲戒解雇
従業員がきわめて悪質な規律違反、非行をおこなった場合に、懲戒処分の一環としておこなう解雇のことです。
例えば、会社の名誉を著しくおとしめるような重大な犯罪行為をおかした場合や、長期間の無断欠勤、重大なハラスメント、度重なる懲戒処分などが認められた場合は、懲戒解雇が正当とみなされます。
なお、懲戒解雇をおこなうためには、就業規則や労働条件通知書にその要件を明示しておく必要があります。
2. 解雇に関連する労働基準法の条文
 それでは、実際に労働基準法で定められている解雇に関する条文から解雇に関するルールを解説していきます。重要なルールが定められていますので、抑えておきましょう。
それでは、実際に労働基準法で定められている解雇に関する条文から解雇に関するルールを解説していきます。重要なルールが定められていますので、抑えておきましょう。
2-1. 労働基準法第15条1項(解雇事由を含む労働条件の明示)
労働基準法第15条1項では、企業が従業員を採用する際に労働条件を明示する必要があるとされています。
労働基準法第15条1項
「第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
特に、解雇事由を明示することが求められています。これは、解雇の理由を明確にすることで、トラブル発生時の法的対応を円滑にするためです。この条項に基づき、労働基準法施行規則第5条1項4号では、解雇を含む労働条件の明示が義務付けられており、「雇用契約書」や「労働条件通知書」などで書面にて提供することが求められます。企業の経営者や人事担当者にとって、この手続きを遵守することは、従業員との信頼関係を築くための重要なステップとなります。従業員の解雇に際しては、事前に明示された条件に厳密に基づいて行うことで、労使間のトラブルを未然に防ぐことができます。
2-2. 労働基準法第19条(解雇制限)
労働基準法第19条では、特定の状況下での解雇に対する制限が詳細に規定されています。
労働基準法第19条
「第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。」
具体的には、業務上の怪我や病気で休業している期間と、その後30日間については原則として解雇が禁止されています。また、女性社員が産前産後の休業を取得している期間と、その後30日間についても同様に解雇が禁止されています。これらの規定は、患っている社員や妊産婦を法的に保護し、安心して治療や出産に専念できる環境を提供する目的があります。この「解雇制限」を理解し、適切に対応することは、企業の信頼性向上と法的リスクの回避に寄与します。
2-3. 労働基準法第20条(解雇の予告)
労働基準法第20条1項に基づき、企業が従業員を解雇する際には、少なくとも30日前にその旨を予告する義務があります。
労働基準法第20条
「第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。」
この「解雇予告」は、経営者や人事担当者が法律を遵守し、円満な解雇を実現するための重要な手続きです。解雇予告日から解雇日までの期間が30日未満であれば、不足する日数分の賃金、すなわち「解雇予告手当」を支払う必要があります。この手当を適切に支払うことで、法的トラブルを回避し、従業員との信頼関係を保つことができます。企業の経営者や人事担当者にとって、労働基準法第20条の理解と遵守は、健全な労使関係を築くために欠かせない要素です。
2-4. 労働基準法第22条(退職時等の証明)
労働基準法第22条では、労働者が解雇の理由等について証明書を請求した場合、事業者は速やかにその証明書を交付する義務があります。
労働基準法第22条
「第二十二条 条労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」
この法律は、労働者が後に再就職を検討する際や、職務履歴を証明する必要がある場合に重要な役割を果たします。企業の経営者や人事担当者においては、適切な手続きを遵守することが求められます。具体的には、解雇理由が明確かつ正当であることを記載することが重要であり、その内容によっては法的なトラブルを避けるための重要な証拠となります。
2-5. 労働基準法第89条(就業規則)
労働基準法第89条は、常時10人以上の従業員を擁する事業者に対して就業規則の作成と労働基準監督署長への届出を義務付けています。
労働基準法第89条
労働基準法第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
就業規則は職場のルールブックとも言えるもので、企業はその中に解雇の事由を明確に記載しなければなりません。これは従業員と企業双方の権利と義務を明確にし、トラブルを未然に防ぐために重要です。具体的には、どのような行為が解雇に該当するのかを明示することにより、不当解雇を防ぎ、健全な職場環境を維持することが求められます。企業の経営者や人事担当者は、この義務を遵守することで、円満解雇を実現し、法律に基づいた健全な労務管理を行うことができます。
2-6. 労働基準法第104条(監督機関に対する申告)
労働基準法第104条は、従業員が事業者の労働基準法違反を労働基準監督署に申告した場合、その従業員を解雇することを明確に禁止しています。
労働基準法第104条
「第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。」
具体的には、従業員が労働基準法に違反する行為を発見し、それを監督機関である労働基準監督署に報告したとしても、その報告を理由に解雇する行為は違法とされます。従業員が安心して違反を申告できる環境が整備されることで、職場内の労働条件の改善が期待されます。
2-7. 労働基準法第3条(その他)
労働基準法第3条では、労働者の国籍・信条・社会的身分を理由とする差別的な取扱いを厳しく禁止しています。
労働基準法第3条
「第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」
この条項は、解雇を含む全ての労働条件において適用されます。具体的には、労働者がその国籍または信条、社会的身分を理由に不当に解雇されることは法律違反となります。不当な扱いや差別的な解雇は、企業の信頼を損なうだけでなく、法的なトラブルに発展するリスクもあります。労働基準法第3条を順守することで、公平で円満な労働環境を維持することが可能となります。
3. 有効と認められる解雇の条件
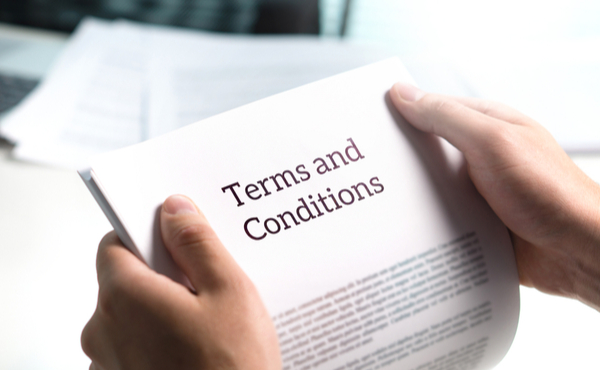
従業員を円満に解雇するためには、次の解雇が有効と認められる条件を満たさなければなりません。
①法律で解雇禁止事項に該当しないこと
②法律に則って解雇予告をおこなうこと
③就業規則の解雇の事由に該当していること
④解雇に正当な理由があること
⑤解雇の手順を守ること
上記の条件はくまなく理解しなければならないため、次から1つずつ解説していきます。
3-1. 法律で解雇禁止事項に該当しないこと
1つ目の条件は、「2-2. 労働基準法第19条(解雇制限)」で解説した項目に該当しないことです。
労働基準法に規定されている内容になるので、違反した場合、解雇が無効になるだけでなく、労働基準法違反として6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金も科されるので注意が必要です。
3-2. 法律に則って解雇予告をおこなうこと
2つ目の条件は、「2-3. 労働基準法第20条(解雇の予告)」にもある通り、労働基準法第20条の規定に則って解雇予告をおこなわなければなりません。
具体的には、30日以上前に労働者に解雇の予告をすること、ただし、もし予告ができない場合、30日分以上の平均賃金を支払うとうことが条件となります。
例えば、8月31日付けで解雇をする場合は、少なくとも8月1日までには解雇の予告をしなければなりません。もし8月10日(解雇日の21日前)に解雇予告をする場合は、9日分の平均賃金を支払えば、8月31日に解雇することが可能になります。
関連記事:労働基準法第20条に定められた予告解雇とは?適正な手続方法
3-3. 就業規則の解雇の事由に該当していること
労働基準法第89条にて、従業員が常時10名以上使用している場合は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。その就業規則の内容の中に、必ず記載しなければならない事項として「解雇の事由」があります。
就業規則は就労前に社員は必ず目を通すため、こちらの解雇の事由に、どのような場面において解雇される可能性が生じるのかということを明記しておくことで、労使間での認識の齟齬が起きづらく、トラブルは少なくなります。
10名以下の事業所の場合は、就業規則の提出は任意となっておりますが、明確な基準がないためトラブルへと発展するケースが多いです。
そのため、事業所の人数には関係なく、就業規則にて解雇の事由を明記しておくことが重要でしょう。
関連記事:労働基準法第89条で定められた就業規則の作成と届出の義務
3-4. 解雇に正当な理由があること
解雇には、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇の3種類あることを上述しましたが、それぞれの解雇理由が正当であるかどうかが重要になります。
これら3つの中でも普通解雇の理由は判断が難しく、あるAという業態では正当な解雇理由となる行動があったとしても、同様の行動をしてもBという業態では解雇に該当しないと判断されるケースも少なくありません。
そのため、解雇はあくまで最後の手段であることを忘れることなく、万が一解雇をおこなう場合には、弁護士などに相談した上で判断するようにしましょう。
3-5. 解雇の手順を守ること
解雇の手順については、解雇予告をおこなうまでの手順に気をつけなければなりません。
解雇についてのトラブルでよく起きるのが、「明確な理由もなしに、いきなり解雇された」というものです。こちらは、労使間の認識の齟齬が起きてしまっているため、その解雇とった事由がどれほどいけないことであったのか、労使間ですり合わせなどをおこなう必要があるでしょう。
このように、いきなり解雇予告をおこなうのではなく、口頭での注意と観察を定期的におこない、その行動に問題があるということを認識させることが重要です。それでも問題行動を繰り返しおこなう場合において、解雇という選択肢が生じます。
一見手間が多く見えますが、解雇というのは従業員からすれば非常に重たい処分であるため、細心の注意を払ったうえで対応するようにしましょう。
当サイトでは、整理解雇を例に解雇に向けた正しい進め方や、解雇が無効になった判例などを解説した資料を無料で配布しております。自社で解雇を検討しているが、不当解雇にならないか不安なご担当者は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
4. 労働基準法に則った従業員の解雇の方法
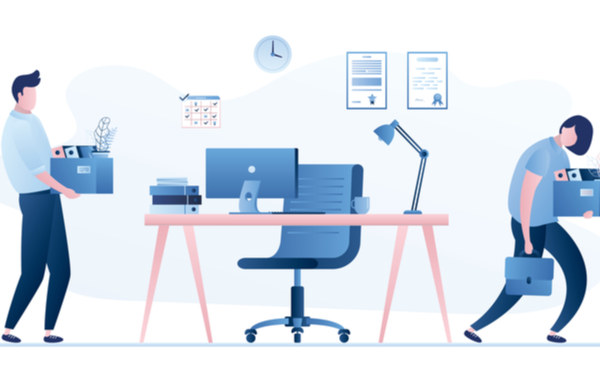
それでは実際に労働基準法に則って解雇をする方法として、何日前までに解雇を言い渡せばいいか分からない人もいるでしょう。会社が従業員を解雇する場合は、労働基準法第20条の規定により、下記のいずれかの方法が必要ですので解説していきます。
4-1. 30日以上前に労働者に解雇の予告をする
解雇の際には、事業者は従業員に対して30日以上前に解雇予告を行うことが法律で義務付けられています。具体的には、労働基準法第20条1項に基づき、解雇日の至少30日前に予告をしなくてはなりません。これが「解雇予告」です。解雇予告を怠ると、事業者は解雇予告手当として労働者に30日分以上の賃金を支払う必要があります。この手続きは、法律的なトラブルを避け、円満な解雇を実現するためには極めて重要です。
なお、例外的に解雇予告が不要となるケースは、下記のとおりとなります。
- 天災事変などのやむを得ない理由により事業の継続が困難なとき
- 労働者に落ち度や過失などがあるとき
とはいえ、会社が労働者を解雇するには、社会通念に照らし合わせて正当な理由がある時に限られますので注意しましょう。
4-2. 解雇予告手当を支払う
「30日以上前に労働者に解雇の予告をする」ができない場合、30日分以上の平均賃金を支払うことで解雇が可能になります。
また、1日分の平均賃金を支払えば、予告日数の短縮も可能です。このように解雇にあたって支払う賃金(費用)は解雇予告手当として知られています。
また、解雇が必要な行為を、あらかじめ就業規則に明記することも求められます。
労働者の立場は法律により手厚く保護されているため、万が一解雇を検討する際は、関連法規まで確認した上で、慎重に進めることが必要です。
解雇は試用期間であっても申し伝えることが可能です。試用期間スタートから14日間であれば即時の解雇ができます。しかし、14日を超えると30日前の解雇予告が必要です。
関連記事:労働基準法第20条に定められた予告解雇とは?適正な手続方法
参考:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) |e-Gov法令検索
5. 労働基準法により認められる解雇理由
 労働基準法に基づく解雇理由として、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当である」と認められることが重要です。
労働基準法に基づく解雇理由として、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当である」と認められることが重要です。
具体例を挙げると、社員の重大な法令違反や業務遂行に著しい支障をきたす行為がこれに該当します。また、業績不振に伴う整理解雇も認められる可能性がありますが、以下の4要件を満たす必要があります。
1. 企業の経営状態悪化が深刻であること
2. 従業員の選定が客観的かつ公平であること
3. 解雇回避のための努力(例えば転籍や配置転換)が行われたこと
4. 解雇対象者との十分な協議が行われたこと
これらの要件を満たさない解雇は、多くの場合、裁判で無効とされるため、十分な注意が必要です。企業経営者や人事担当者は、解雇理由の正当性と手続きの妥当性を確保することで、円満な解雇を目指すことが求められます。
6. 労働基準法における不当解雇の例

前節でも説明した通り、たとえ就業規則や労働条件通知書に要件が記載されていても、場合によっては「不当解雇」とみなされるケースもあります。
不当解雇の事例は、大きく分けて「解雇制限に該当するケース」と「客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められないケース」の2つがあります。
以下では、それぞれのケースごとに不当解雇の例について解説します。
6-1. 解雇制限(労災による傷病で療養中・産前産後期間)に該当するケース
労働基準法第19条では、「解雇制限」として、以下のケースでは労働者を解雇してはならないと定めています。
- 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
- 産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間
②のケースは、同法第65条によって定められた産前産後休業のことで、6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合および産後8週間を経過しない女性を就業させることは法律で禁じられています。
産前産後の休業取得を拒否するのはもちろん、その期間中に女性労働者を解雇することも労働基準法違反となりますので注意が必要です。
また、同法104条では、労働者が労働基準法または法に基づいて発する命令に違反する事実があることを行政官庁または労働基準監督官に申告した場合、その報復行為として解雇を言い渡すことを禁じています。
参考:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) |e-Gov法令検索
6-2.客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められないケース
労働契約法第16条にある「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」に該当するケースです。具体的には以下のものが該当します。
- 国籍や信条、社会的身分を理由とする解雇
- 労働組合の結成や加入を理由した解雇
- 女性労働者の婚姻・妊娠・出産を理由とした解雇
- 育児休業・介護休業の申請や利用を理由とした解雇
上記のような不当な解雇は、労働基準法だけでなく、労働安全衛生法、労働組合法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などにより認められません。トラブルを回避するためにも、事前に把握しましょう。
その他に、例えば経営不振にともなう整理解雇であっても、何の説明もなしに突然リストラされたり、整理解雇中なのに引き続き求人をおこなったりしているケースは、整理解雇で必須とされる「解雇を回避するために最大限の努力をおこなったこと」および「整理解雇することに客観的な必要があること」の要件を満たさないため、不当解雇となります。
特に普通解雇のケースは線引きが難しく、労働者が解雇事由に納得しない場合は訴訟に発展する可能性があります。
そのため、企業が労働者を解雇するためには、できるだけ円満に解決するよう努力する必要があります。
6-3. 労基法違反を労働基準監督署などに申告したケース
労働基準法第104条2項によれば、「労働基準監督署等への法令違反の申告を理由に解雇することはできない」という強力な保護規定が存在します。
例えば、従業員が「残業代が支払われていない」や「違法残業をさせられている」といった事業者の労働基準法違反を労働基準監督署に申告した場合、その行為を理由に解雇することは法律で厳しく禁じられています。経営者や人事担当者は、この法律をしっかりと理解し、従業員の権利を守るために適切な手続きを行う必要があります。具体的には、法令違反の申告があった場合、まずは調査し適切な対応を行うことで、円満な労働環境を維持することが求められます。したがって、法令違反の申告は労働者の正当な権利であり、それを理由に不当な解雇を行わないよう十分に留意してください。
関連記事:労働契約法16条に規定された「解雇」の効力と無効になるケース
7. 労働基準法に沿った円満解雇の秘訣
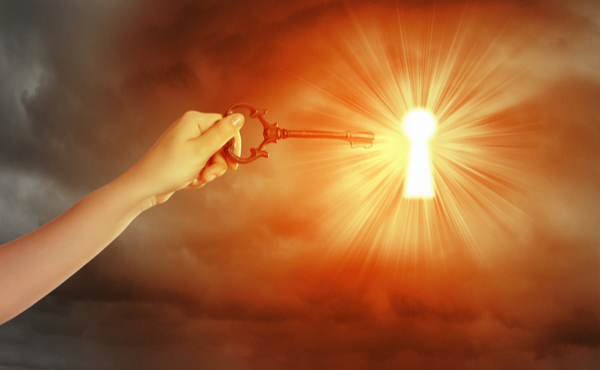
労使間でトラブルをおこさず、労働者を円満に解雇するために押さえておきたいポイントを3つご紹介します。
7-1. 十分な協議の場を設ける
解雇をめぐってトラブルが発生するのは、ひとえに「労働者が解雇の事由について納得していないため」です。
解雇を予告するにあたって十分な説明をおこなわなかったり、労働者の言い分を全く聞かなかったりすると、労働者の不満が募って訴訟に発展する可能性が高くなります。
解雇する場合は、まず該当の労働者と十分に話し合える場をセッティングし、相手が納得できるよう、しっかり説明することを心がけましょう。
7-2. 就業規則・労働条件通知書等の契約を見直す
就業規則や労働条件通知書には、解雇の事由を含む退職に関する事項を明示することが義務づけられています。[注6]
労働者を解雇するにあたっては、就業規則や雇用契約書にそのルールを明記し、労働者に周知させておかなければなりません。
解雇事由の説明が複雑だったり、わかりづらかったりすると、人によって解釈の違いが生まれてしまい、無用なトラブルを引き起こす原因となります。
就業規則や労働条件通知書に不備があると考えられる場合は、解雇する場合に備えて、あらかじめ見直しや変更をおこなっておきましょう。
関連記事:労働条件通知書とは?必要な理由や項目別の書き方について
参考:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) |e-Gov法令検索
7-3. 専門家に相談する
労働基準法における「客観的に合理的な理由」は線引きが難しく、解雇事由が正当なのかどうか見極めるのは困難です。
そんなときは、労働関係に強い弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談し、アドバイスを仰ぐようにしましょう。
専門家なら、法に関する知識はもちろん、これまでの判例に関する知識も豊富に持ち合わせているため、解雇事由に正当性が認められるかどうかを客観的に判断してくれます。
円満解雇に導くためのアドバイスも提供してくれますので、労働者の解雇に決まったらプロの意見を聞くことも検討してみましょう。
8. 労働者を解雇するときは、労働基準法をしっかり理解することが大切

企業は就業規則や労働条件通知書で「解雇」に関する規定を設けることができますが、労働基準法における「客観的に合理的な理由に欠き、社会通念上相当と認められない」ときは、たとえ就業規則に定められている事項でも、解雇が無効となる場合があります。
それ以外にも、法律で解雇を禁じられているケースがいくつかありますので、労働者を解雇するときは、労働基準法や労働契約法などにおける解雇のルールをしっかり理解しておくようにしましょう。
労働者保護の観点から、解雇には様々な法規定があり、解雇の理由に合理性が無ければ認められません。
当サイトでは、解雇の種類や解雇を適切に進めるための手順をまとめた資料を無料で配布しております。合理性がないとみなされた解雇の例も紹介しておりますので、法律に則った解雇の対応を知りたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08




























