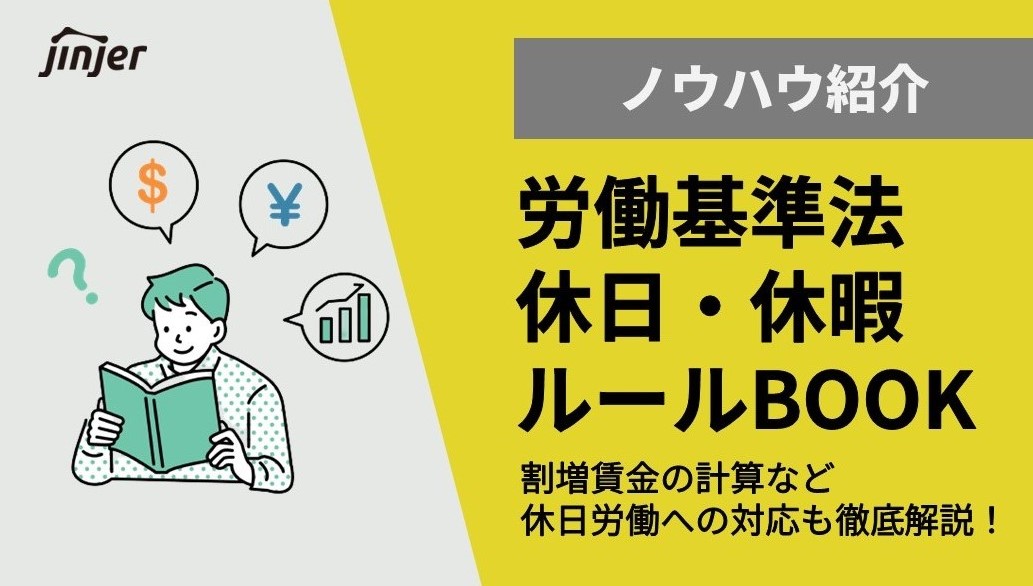生理休暇とは?労働基準法に則って企業に求められる対応|制度概要
更新日: 2024.6.4
公開日: 2021.10.4
OHSUGI
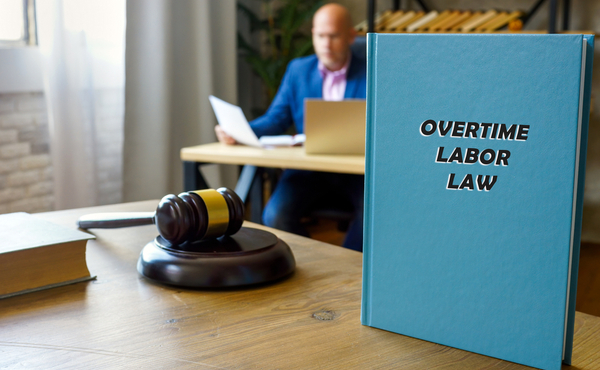
生理休暇は女性従業員特有のものであり、さらに各個人で症状もさまざまなので、企業としては取り扱いが非常に難しい制度の1つです。また労働者にとってもあまり浸透していないのが事実で、「男性の上司には言いにくい」「生理を理由に休むのは気が引ける」と感じているケースも少なくありません。
ただし生理休暇は労働者の権利なので、できるだけ自由に取得できる体制を整えることが必要です。そこで今回は労働基準法で定められている生理休暇について、企業として把握しておきたい基本的な考え方を解説していきます。
▼そもそも労働基準法とは?という方はこちらの記事をまずはご覧ください。
労働基準法とは?雇用者が押さえるべき6つのポイントを解説
【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK
従業員に休日労働をさせた場合、休日はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
本資料では、労働基準法にて定められている内容を元に、休日・休暇の決まりを徹底解説しています。
就業規則に休日・休暇に関する内容が明記されていないなどで労働者とのトラブルを生まないためにも、人事担当者の方は「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。
目次
1. 生理休暇とは


1-1. 生理休暇の目的
生理休暇の目的は、労働基準法に基づき、働く女性が健康を損なわずに安定して働ける環境を提供するために設けられています。生理の不快な症状が業務に悪影響を及ぼすと感じる女性労働者は多く、これは個人だけの問題ではなく、組織全体の生産性低下にもつながる可能性があるため、従業員の健康と労働効率を守る目的があります。
1-2. 生理休暇が定められている法律
生理休暇は、日本の労働基準法第68条に基づいて定められている法定休暇です。この法律により、月経困難症や頭痛、腹痛、倦怠感などの症状で出勤が困難な女性労働者には、休暇を取得する権利が与えられます。生理休暇は企業の任意で設置される法定外の福利厚生という誤解があるかもしれませんが、実際には法的に規定されているため、労働者から申請があったにもかかわらず却下することは法律違反となります。
1-3. 生理休暇の取得率の実態は非常に低いのが現状の課題
そもそも労働基準法にて、生理休暇が規定されていることを知らない労働者は少なくありません。また女性特有の制度で、まだまだ浸透していないのが現状です。実際に厚生労働省の調べでは、2015年時点において生理休暇の取得があった企業の割合は2.2%、さらに請求した労働者の割合でいえばわずか0.9%に留まっています。
出典:厚生労働省の調べ
女性の活躍が進んでいる中、生理休暇に対する注目度は低く、もっと働き方を多様化していくためには企業側からの喚起はまだまだ必要でしょう。
2. 労働基準法で定められている「生理休暇」の規定内容


2-1. 生理休暇の取得条件
生理休暇の取得条件は、月経に起因する体調不良で就業が困難な場合に適用されます。法律に基づくこの休暇制度は、すべての従業員が取得を請求する権利があり、正社員だけでなく、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど、雇用形態に関係なく利用可能です。
生理休暇の取得は自己申告制が基本であり、医師の診断書や証明書の提出は求められません。従業員が体調不良を理由に生理休暇を申請する場合、企業の人事担当者や経営者はこの権利を尊重し、適切に対応する義務があります。適切な対応により、労働環境を整え、従業員の健康と働きやすさを守ることが重要です。
2-2. 生理休暇を取得できる日数に上限はない
労働基準法に基づく生理休暇については、具体的な取得日数の上限は設定されていません。つまり、必要に応じて必要なだけ取得することが可能であり、企業側が取得日数を限定することはできません。また、生理休暇は1日単位だけでなく、半日や時間単位で取得させても問題はありません。これにより、従業員がその日の体調に応じて柔軟に休暇を取ることができます。
2-3. 就業規則がなくても労基法によって取得可能
各企業で会社の制度として休暇を設けている場合には、必ず就業規則にて定める必要があります。しかし生理休暇については、先ほども出てきたように労働基準法によって規定されている制度です。そのため仮に就業規則に記載していなくても、従業員から生理休暇の請求があれば応じなければなりません。
「就業規則に生理休暇の項目を載せていないから取得させない」といった対応は違法です。いずれにしても、いつどんな状況であっても生理休暇の取得は認可すべきであり、もし違反すれば30万円以下の罰金が科せられます。
3. 従業員が生理休暇を取得した際の給与計算


3-1. 法律上生理休暇は無給でも問題はない
生理休暇は産休や育休と同様に、有給にするのか無給にするのかについては、各企業の判断に任されています。当然ながら有給休暇と同じような扱いもでき、一定の割合に限定して有給とすることも可能です。
一方で無給としても問題はなく、厚生労働省の調べでは、実際に2015年時点で74.3%の企業が「無給」という結果が出ています。ここからも分かるように、現行の労働基準法では、今のところ生理休暇は確保するのが目的ともいえるでしょう。
出典:厚生労働省の調べ
関連記事:無給休暇とは?欠勤・有給休暇との違いや給料の有無を分かりやすく解説
3-2. 給与計算は従業員に不利が発生しない運用が必要
生理休暇については、無給でも問題はありませんが、例えば賞与額を算定する際に、生理休暇を欠勤にすることで従業員側に不利益が生じている場合など生理休暇の取得の妨げになるルールは原則不可とされています。取得を妨げるような運用は認められないのが原則と考えておくと無難でしょう。
明確にどこまでが違反というわけではありませんが、仮に従業員に提訴された場合には、裁判所に判断が委ねられます。もし不適切とされた場合には、結局は対象の従業員に相当額を支払わなければなりません。そのため生理休暇による欠勤は、各労働条件に深く関わるものには適用できないと認識しておくほうが良いでしょう。
4. 企業が生理休暇を導入するメリット


4-1. 社内のウェルビーイングを高める
生理休暇の導入は、従業員の心身の健康をサポートし、社内の幸福度を高めます。多くの女性が生理による不快な症状を抱えながらも、人手不足や収入面の理由で我慢して働いている現状があります。このような状態が続くと、従業員の健康を損なうだけでなく、メンタルヘルスにも悪影響を及ぼす可能性があります。生理休暇を適切に利用してもらうことで、従業員が安心して休むことができ、職場全体の幸福度が向上します。幸福度の向上は、従業員の満足感を高めるだけでなく、組織全体の生産性を高める結果にもつながるメリットがあります。
4-2. 従業員の生産性が高まる
生理の不快症状と仕事の生産性には密接な関連性があります。日本医療政策機構の働く女性の健康増進調査2018によると、生理に伴う不快な症状により仕事のパフォーマンスが半分以下に低下すると回答した女性は、全体の約半数に上りました。このデータは、生理休暇の導入が不可欠であることを示しています。
出典:日本医療政策機構の働く女性の健康増進調査
ヘルスリテラシーの向上も仕事のパフォーマンスに影響を与えるとされ、生理休暇の取得は従業員の心身の健康を守ることに寄与します。結果として、組織全体の生産性向上が期待できるのです。したがって、企業が生理休暇を導入することで、従業員が無理をせず安心して働ける環境が整い、長期的には業績の向上にも繋がるでしょう。
4-3. 会社に優秀な人材が集まりやすい
健康と働きやすさを重視する企業は、優秀な人材から選ばれやすい特徴があります。特に生理休暇を積極的に取得してもらうことは、その一環として役立ちます。生理痛がつらい女性にとって、生理休暇のとりやすさは就職や転職の際に有利に働く可能性があります。この制度の存在と利用状況が求人情報に明記されていれば、女性応募者は安心して応募できます。結果として、女性の応募が増加し、優秀な女性を採用しやすくなるでしょう。
5. 生理休暇の適切な取得を促すためのポイント


ここまでに見てきたように、生理休暇の的確な運用のためには、十分な策を練る必要があります。場合によっては生理だからといって、不当に休暇の申請が行われるケースも考えられるでしょう。そうなってしまうと、本当に生理休暇を取るべき従業員が取得しづらくなってしまう状況もできてしまいます。
こうした事態を防ぐためにも、正しく仕組化することが重要です。
5-1. 社内での生理休暇の理解を深める
生理休暇の理解を社内で深めることは、健康的な職場環境を育むために重要です。労働基準法に基づく生理休暇の適用方法や給与計算について理解を深めるとともに、性別や生理の症状の程度に関係なく生理休暇を職場全体の課題として捉える必要があります。
女性社員の中には生理痛などの症状が少ないため理解が浅い人もいます。そのため、生理に対する理解を深める研修を導入すると効果的です。加えて、テレワークの環境を整え働きやすい職場を構築することも大切です。
また、生理休暇の環境整備の一環として、生理に限らず利用できる新たな休暇制度を検討するのも一つの方法です。最近では「エフ休」や「ウェルネス休暇」といった取得要件を拡大する企業も増えてきました。柔軟なシフト調整などの配慮を行い、生理休暇を取得しても問題なく業務が進行する組織づくりを目指しましょう。
5-2. 生理休暇の取得手順を整える
生理休暇の取得手続きを整備することは、従業員がスムーズに申請するために非常に重要です。取得希望が請求しづらく、突発的になることが多い生理休暇の特性を考慮し、メールやオンラインフォームなど、請求しやすい方法を導入することが効果的です。会社所定のフローが明確に決まっていれば、従業員側も安心して請求できます。
そのほかにも「生理休暇は事後申請にて有給休暇にすることも可」など、あくまで従業員に不利益にならない手段で、制限をつけることも考慮しておくのがおすすめです。
また必要以上に症状を聞き出すことはハラスメントに繋がる恐れがあるため注意しましょう。こうした配慮を行うことで、従業員が安心して生理休暇を取得できる環境を整え、企業全体の働きやすさを向上させることができます。
5-3. 生理休暇について就業規則に記載する
就業規則に生理休暇に関する規定を明確に記載することは、企業の労働環境の透明性を高めるでしょう。具体的には、労働基準法に基づき「生理日の就業が著しく困難な女性から申請があった場合、必要な日数の休暇を与える」といったルールを明示することで、従業員に会社の姿勢を明確に伝えることができます。例えば、生理休暇の数日までは有給とする方法を取り入れると、従業員の経済的負担を軽減することができます。このような具体的な指示を含むことで、従業員からの信頼を獲得し、働きやすい環境を提供することができます。
5-4. 生理休暇について相談できる窓口を設置する
生理休暇の申請や相談がしやすいよう、企業は専用の窓口を設置することも有効でしょう。信頼できる相談相手を用意することで、従業員の安心感を高めるのみならず、ワークライフバランス支援策としても有効です。特に産業医や婦人科医、カウンセラーなどの専門家にサポートを依頼できる体制があれば、従業員も安心して働ける環境が整います。また、社内に相談窓口を設ける場合は、可能であれば担当者を人事部の女性にすると、さらに相談しやすい環境が作れます。”
6. 生理休暇を導入する際の注意点


そのため、生理休暇を正しく運用するためにも導入時の注意点を紹介します。
6-1. 診断書の提出等を求めない
生理休暇とは労働基準法第68条に規定されている法定休日で、「どうしても勤務するのが難しい」との申告があった場合には、必ず取得させなければなりません。当然ながら無理に出勤させたり、請求を認めなかったりするのは違法です。
なお生理休暇の取得にあたっては、特に診断書の提出などの手続きは必要なく、例えば口頭で伝えられただけでも速やかに応じる必要があります。生理休暇は、あくまで体調不良時におけるやむを得ない状況での対処と考えられているため、手続きの方法などによる制限もできません。
6-2. 取得日数を制限しない
法律上、労働基準法は生理休暇の取得日数に制限を設けておらず、企業側が独自に制限を設けることは禁止されています。そのため、従業員が必要とするだけの休暇を取得できるようにする必要があります。診断書などの客観的な証拠がないまま、口頭やメールでの申告だけで無制限に休暇を許可することに抵抗がある企業も多いかもしれませんが、生理のトラブルが何日続くかは人によって異なります。取得側と企業側との信頼関係を構築し、申請どおりに休暇を許可することが重要です。
6-3. 雇用形態を制限しない
雇用形態に関わらず、生理休暇の取得を認めることは重要です。生理休暇は正社員だけでなく、パートやアルバイトの女性にも平等に取得する権利があります。就業規則を作成する際に、「生理休暇の取得は正社員のみ」「パートやアルバイトの生理休暇取得は認めない」といった規定を設けることはできません。特に、パートやアルバイトの比率が高い企業や人手不足の現場では、生理休暇の申請を抑制するために雇用形態に基づく制限を設けることがあるかもしれませんが、これは避けるべきです。
7. 生理休暇に関するよくある質問


生理休暇に関して正しく理解するためによくある質問を紹介します。
7-1.半日や時間単位の取得を認める必要がある
労働基準法においては、生理休暇については暦日でなくても問題ないとされています。もし従業員側から、半日や時間単位での取得の申し出があれば、それに応じた生理休暇を認めれば法律上の要件は満たすことになります。
例えば「痛み止めを飲んで時間が経てば症状が落ち着くから、午前だけ休みたい」などの取得方法もできます。その逆に「急に生理が来て体調が悪くなってきたから早退したい」といった場合も、生理休暇として対応すればよいでしょう。
7-2. PMSでも生理休暇は取得できる?
PMS(経前症候群)は、生理前に現れる精神的および身体的な不快症状の総称です。具体的には、情緒不安定、抑うつ、イライラ感、睡眠障害、集中力低下、腰痛、頭痛、食欲変動、めまい、倦怠感、むくみ、腹部や乳房の張りなどがあります。これらの症状は個人差が大きく、生理の3~10日前に発生し、就業に支障をきたすこともあります。
労働基準法上、生理休暇におけるPMSの扱いに明確な言及はありませんが、PMSによる体調不良も生理休暇の対象と考えられます。企業の人事担当者や経営者としては、労働基準法に基づく正しい理解と適用が求められます。法律に明確な定めがない場合でも、企業独自の規定でPMSによる休暇を認めているケースもあるため、該当する社員への柔軟な対応が重要です。
従業員がPMSの症状で生理休暇を希望する場合、企業側への確認と適切な対応を推奨します。正確な情報を提供し、従業員が安心して休暇を取得できる環境を整えることが、企業全体の生産性向上につながるでしょう。
8. 生理休暇の制度をきちんと整えて時代を先取りした企業に


生理休暇は労働基準法に定められた労働者の権利であり、使用者側が取得を拒否できないのは大原則です。しかしながら法律的には、規定によって労働者を守っているといえる部分は少なく、各企業として独自に整備するのがベストでしょう。
また生理休暇が浸透している会社は現時点では非常に珍しく、きちんと制度を整えることで、より適切な労働環境に向けて先駆けた動きができます。女性従業員のさらなる躍進を支える意味でも、ぜひ一度、自社の生理休暇の取り扱いについて見直してみてはいかがでしょうか。
【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08