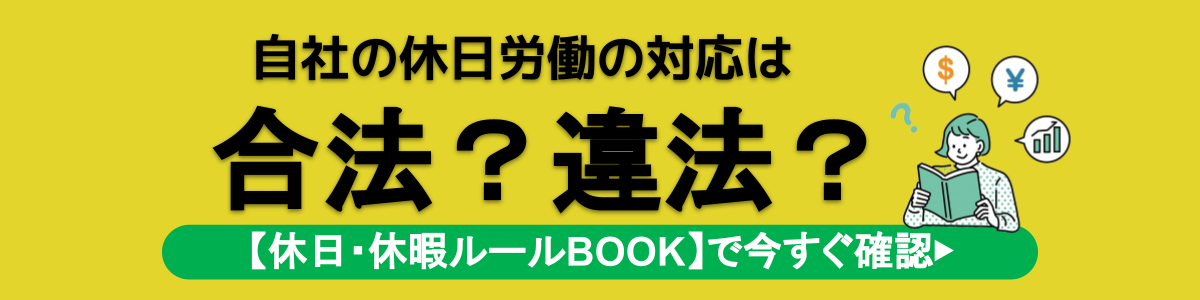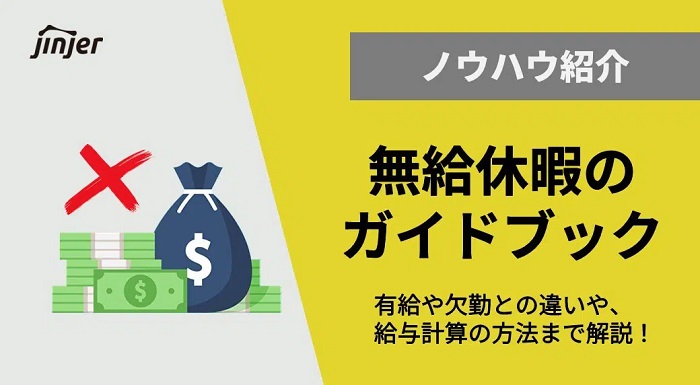無給休暇とは?欠勤・特別、有給休暇との違いや給料の有無をわかりやすく解説
更新日: 2024.6.28
公開日: 2021.9.6
OHSUGI

無給休暇は有給休暇の対義語で、給料が支払われない休暇のことです。会社によって異なりますが、無給のバースデー休暇や慶弔休暇などが無給休暇の一例として挙げられます。
この記事では、無給休暇の意味や問題点について詳しく説明します。言葉の意味を正しく理解して、適切に無給休暇を運用しましょう。
人事担当者の皆さまは、無給休暇の定義やルールを詳細に理解していますか?
「給与が出ないのはわかるけど、他の休みと何が違うの?」「どんな条件で取得できるの?」など、いざ聞かれると困ることもあるのではないでしょうか。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている休日休暇のルールをもとに、無給休暇の扱い方について本記事の内容をまとめた資料を無料で配布しております。
「無給休暇の正しい勤怠処理を知りたい」という人事担当者の方は「無給休暇のガイドブック」をぜひご一読ください。
1. 労働基準法における休暇とは働く義務が免除される日

無給休暇についてしっかりと理解するためにも、まずは労働基準法における休暇の定義について知っておきましょう。
休暇とは、雇用契約上では働く義務があるものの、申請によって免除される日のことです。無給休暇や有給休暇は、もちろんこの休暇に該当します。なお、休暇には以下の2つの種類があります。
- 法定休暇:年次有給休暇、育児休暇など法令で定められた休暇
- 特別休暇:慶弔休暇やバースデー休暇など、会社が独自に設ける休暇
それぞれについて詳しく解説します。
1-1. 法定休暇
休暇には法定休暇と特別休暇の2種類があります。
法定休暇とは、法律で定められているものであり、労働者の権利として取得できる休暇のことをいいます。
法定休暇には年次有給休暇、生理休暇、育児休業、介護休業などがあります。
(生理休暇、育児休業、介護休業は一般的に無給のケースが多いです。とはいえ無給休暇は欠勤とはことなり、休むことを認められている日になるので、評価には影響がありません。)
関連記事:法定休日と祝日の違いとは?出勤時は割増賃金になる?計算方法も詳しく解説
1-2. 特別休暇
特別休暇とは、法律に定めがなく企業が社員に対して福利厚生のひとつとして与える休暇のことを指します。
例えば、慶弔休暇、夏季休暇、冬期休暇、リフレッシュ休暇、アニバーサリー休暇、ボランティア休暇などが特別休暇にあたります。
関連記事:特別休暇とは?その種類や導入のポイント・注意点を解説
1-3. 休日(法定休日・所定休日)と休暇の違い
休暇と似ている言葉として、「休日」があります。
休暇とは、従業員の労働提供義務があるものの、労働の義務が免除される日のことです。
一方で休日は、労働の義務がそもそも課せられていない日のことです。休日は法定休日と所定休日にわけられます。
完全週休2日の会社の場合は1日が法定休日、残りの1日が所定休日というように設定されているケースが一般的です。
このように一般的な会社が休みとなる土曜日や日曜、祝日のことを休暇ではなく「休日」と呼ぶのは、そもそも言葉の定義が異なるためです。休日と休暇は全く意味が異なるので、きちんと区別しておきましょう。
法定休日
労働基準法では、原則として週に1日以上の休日を取らせることについて規定しています。この原則を「法定休日」と呼びます。
なお、法定休日に従業員を働かせると35%以上の割増賃金を支払う必要があります。
所定休日
この法定休日以外に企業が就業規則などで独自に設けた休日を「所定休日」と呼びます。(法定外休日)
所定休日に働かせると週40時間の法定労働時間を超えた場合には25%以上の割増賃金が必要になります。
本章で少し触れましたが、休日を考える際には割増賃金について考える必要があったり、休暇を考える際には法定休暇のように必ず与えなくてはならないものがあるため、担当の方は漏れなく理解する必要があります。
当サイトでは、休日・休暇の違いやそれぞれどのような種類のものがあるのかまとめた資料を無料で配布しております。定義など不安な時にすぐ確認したいという方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。労働基準法による「振替休日」や「代休」について再確認したい方にもおすすめです。
関連記事:所定休日と法定休日の違いや運用ルールを分かりやすく解説
2. 無給休暇とは?

休暇の定義について理解できたところで、ここからは無給休暇について詳しく見ていきましょう。まずは、言葉の定義について説明します。
2-1. 無給休暇では給料は発生しない
はじめにお伝えしたとおり、無給休暇は「給料が発生しない休暇」のことです。無給休暇には、休暇のうち会社が給料を発生させないと規定した「特別休暇」が含まれます。
たとえば、特別休暇の代表例として慶弔休暇があります。慶弔休暇を取れば、労働の義務は免除されますが、有給休暇のように給料は発生しません。
そのため無給休暇を取得すると実質、給料が減ることになります。
ただし、会社によってはこういった休暇にも給料が発生することもあるため、「特別休暇=必ず無給休暇」というわけではありません。
たとえば慶弔休暇の場合、子や配偶者、親が死亡した場合は有給をとりますが、そのほかの親族の場合は無給となるケースがあります。会社の福利厚生として求人にさまざまな休暇が記載されていても、そのすべてが必ずしも有給休暇だということではありません。
2-2. 無給休暇の運用に違法性はない?
無給休暇の運用において、給料が発生しないことについて違法性はありません。企業が無給休暇を採用することは、法的に問題がないとされています。これは、労働の提供がない場合に給与を支払う必要がない「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づいています。
参考:賃金に関する基本問題|成蹊せいけい大学法学部教授・中央労働委員会地方調整委員 原 昌登
労働者と会社の間でトラブルになりやすいため、一方的な運用は避け、特に従業員に不利益を与える形での実施は慎重に管理すべきです。さらに雇用契約書や就業規則に「有給なのか無給なのか」をしっかりと明記することが大切です。
関連記事:休日出勤を振替休日ではなく有給取得に変更できるケースとは
3. 無給休暇と有給休暇・欠勤・特別休暇の違い

無給休暇と関連する言葉として、「有給休暇」と「欠勤」があります。それぞれの言葉を正しく使用できるように、意味の違いについて具体的に紹介します。
3-1. 無給休暇と有給休暇の違い
有給休暇とは、給料がもらえる休暇のことを指します。両者の違いは、「給料が出るか、出ないか」というポイントです。
有給休暇については労働基準法の39条によって規定されており、以下の条件を満たした従業員には、勤続年数に応じた有給休暇を付与することが規定されています*。
- 6か月以上勤務している
- 勤務日の8割以上出勤している
労働基準法によって付与が求められている有給休暇を「年次有給休暇(年休)」といいます。有給のほかにも、福利厚生として会社が独自に規定した特別有給を与えることも可能です。
なお、2019年4月の働き方改革関連法案の施行により、会社の規模を問わず年10日以上の年休が付与される労働者に対しては、年5日の年休の消化が義務付けられました。会社は従業員の希望を考慮のうえ、時季を指定して年休を取得させなくてはいけません**。
有給休暇(年休)は法令によって規定された労働者の権利ですが、無給休暇はそうではありません。
そのため取得させることが義務付けられているわけではありませんし、会社が特定の無給休暇を用意しておく必要もないのです。
*参考:e-Gov|労働基準法
**参考:厚生労働省|年次有給休暇の時季指定
関連記事:年次有給休暇とは?付与日数や取得義務化など法律をまとめて解説
3-2. 無給休暇と欠勤の違い
無給休暇は、欠勤と非常に似ています。休暇を使い切ってしまい、風邪や用事で仕事を欠勤した経験がある方もいらっしゃるかもしれません。
欠勤とは、働く義務がある日に仕事を休むことを指します。
たとえ無給であっても、適切な手順を踏んで取った休暇であれば何の影響もありません。しかし、欠勤は昇給査定や賞与査定、出勤率の算定に影響するため注意しましょう。
欠勤を繰り返すと、会社からの評価が下がってしまったり、賞与に影響してしまったりする可能性があるのです。
また、欠勤すると給与から欠勤控除が引かれる恐れがあります。無給で仕事を休むという点では非常に似ていますが、「その後の影響の有無」が休暇と欠勤では全く異なります。
3-3. 無給休暇と特別休暇の違い
先にも紹介しましたが、特別休暇とは、法律に定めがなく企業が社員に対して福利厚生の1つとして与える休暇のことを指します。
特別休暇は法定休暇には該当しないため、給料が支払われるかどうかは企業によって異なります。
例えば、特別休暇の1つに慶弔休暇がありますが、慶弔休暇を取った社員に給料が支払われるかどうかは、企業が定めた就業規則に則ります。
そのため、従業員に周知するために給料が支払われない無給休暇に該当する場合は、休暇を取った社員から「給料が支払われていない」と疑問を持たないように、就業規則に明記しておくことをおすすめします。
関連記事:【図解付き】有給休暇付与日数の正しい計算方法をわかりやすく解説
4. 無給休暇を取得した際の給与計算方法


無給休暇を取得した場合の給与計算について詳しく解説します。基本給から無給となる日数分を控除する形で計算されます。具体的には、欠勤控除の計算方法を適用し、働いていない分の給与を差し引くことが必要です。
欠勤控除の計算方法は以下の通りです。まず、無給休暇を取得した月の給料は本来の月給から無給休暇の日数分の給料を差し引いた金額となります。具体的な計算式は「月給÷月の所定労働日数×無給休暇の日数」です。
例えば、月給20万円の従業員が10日間の無給休暇を取得した場合、その月の給与は月給を日給ベースに換算し、無給日数分を控除します。注意すべき点として、月給に各種手当が加算されている場合、手当を欠勤控除の対象とするかどうかを事前に社内で取り決めておくことが重要です。労働日数に応じて支払われる手当は、欠勤控除を適用することをおすすめします。
このようにして、無給休暇取得に伴う給与計算を正確に行うことで、企業運営においても透明性が保たれます。
5. 無給休暇に関する問題点

最後に、無給休暇に関する問題点について紹介します。
5-1. 無給休暇だからといって自由に休めるわけではない
無給休暇は給料が出ないため、「希望通りに取ることができる」と勘違いされやすいという問題があります。しかし、たとえ無給であっても、基本的に自由に休むことはできないことを理解しておきましょう。
雇用契約を締結している以上、会社には業務上の業務命令を行なう権利があり、従業員にはその命令や会社秩序を守る義務があります。
会社が理由もなく労働者の権利である休暇を禁じることはできませんが、労働者は少なくとも業務の状況を考慮のうえ、影響が少なくなるように配慮しながら休暇を取る必要があるのです。
会社は、無給だからといって自由に休みを取る従業員に対して、時季の調整などを要請することができることを押さえておきましょう。
5-2. 基本的に無給休暇を強制することはできない
通常、会社都合によって休業になった場合、会社は従業員に対して平均賃金の60%に当たる休業手当を支払わなくてはいけません。
基本的に会社は自己都合で無給休暇を強制することができず、休暇をとらせるときは従業員に対して手当を支払う義務があります。これは労働基準法26条によって規定されており、遵守しなくてはいけません。
ただし、会社が経営者として最大限の注意を尽くしても避けることができない休業である場合は、従業員に無給で休暇を取らせることが可能です。
近年は新型コロナウイルスの影響で、無給休暇に近い状況で従業員を休ませている会社も多いかもしれません。こういった影響による休業が無給休暇になるかどうかは、ケースバイケースです。
たとえば「客足が減ったから休業する」「在宅でもできる仕事だけど休業する」という場合は、休業手当が必要になります。どのようなケースで無給休暇を取らせることが可能で、どのようなケースで休業手当が必要になるかは、休業に「防止不可能性」があるかどうかで決まります。
判断に迷うときは、労働基準監督署へ相談すると確実でしょう。
5-3. 新型コロナウイルスの影響などで会社を休業せざるを得ない場合
近年、新型コロナウイルスの影響で会社や店舗を休業する事業者が増えています。
ここで問題に上がっているのが、会社や店舗を休業する場合、従業員に給料を支払うかどうかという点です。
労働基準法には「使用者の責めに帰すべき事由(会社都合)により労働者が休業した場合に、使用者は、当該労働者に対し休業手当を支払わなければならない」と記載されていますが、新型コロナウイルスの影響で休業せざるを得なくなった場合に休業手当が必要かは判断が分かれており、状況によっても異なるため、支払うかどうかは使用者によって異なっているのが現状です。
6. 無給休暇を正しく理解して勤怠管理をおこなおう

無給休暇は、給料が支払われない休暇のことです。
年次有給休暇を除き、どの休暇が有給・無給になるのかは会社によって判断が異なるため、トラブルを防ぐためにもしっかりと就業規則に規定のうえ、周知することが大切です。
給料が出ないとはいえ、労働者が自由に休暇を取ることはできません。また、正当な理由なく会社が休暇を強いることもできませんので、運用時は十分に注意しましょう。
関連記事:休日と休暇の違いとは?休みの種類や勤怠管理のポイント
人事担当者の皆さまは、無給休暇のルールを詳細に理解していますか?
「給与が出ないのはわかるけど、どうやって控除すればいいの?」など、案外適切な対応方法がわからないこともあるのではないでしょうか。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている休日休暇のルールをもとに、無給休暇の扱い方について本記事の内容をまとめた資料を無料で配布しております。
「無給休暇の正しい勤怠処理を知りたい」という人事担当者の方は「無給休暇のガイドブック」をぜひご一読ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25