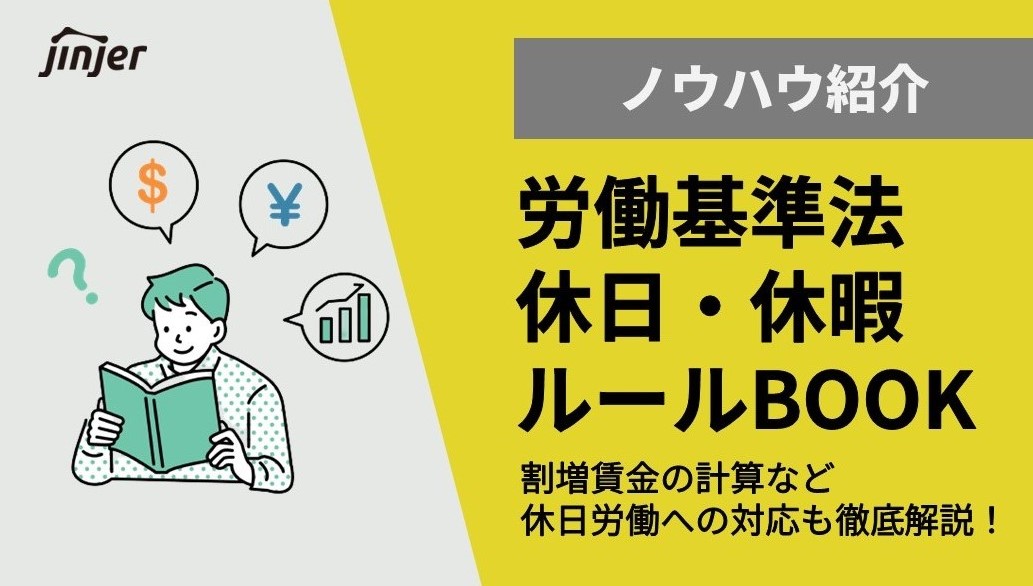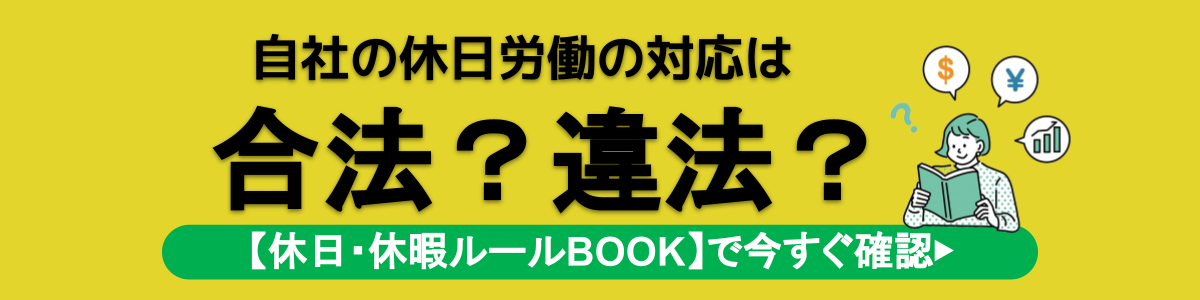特別休暇とは?有給休暇との違い、種類や導入するメリット・給与の計算方法を解説
更新日: 2024.6.27
公開日: 2021.9.6
OHSUGI

企業が従業員に休暇を与えるときは、法律で定められた年次有給休暇のほかに、企業が独自に設けた特別休暇を与えることができます。特別休暇は、福利厚生として企業価値を高めたり、従業員のワークライフバランスの実現を手助けしたりできる、メリットの多い休暇です。
ここでは、特別休暇の具体的な種類や導入のポイント、注意点を解説するので、特別休暇の効果的に運用に役立ててください。
目次
【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK
人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?
従業員に休日労働をさせた場合、休日はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、休日・休暇の決まりを徹底解説した資料を無料で配布しております。
「休日休暇の違いや種類、ルールを確認したい」という人事担当者の方はこちらから「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。
1. 特別休暇とは?
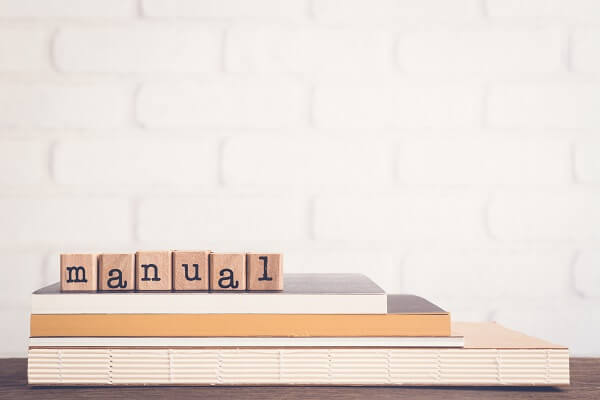
特別休暇とは、企業が自由に設定できる休暇のことです。福利厚生の一環として活用されており、付与する日数や休暇の内容については、各企業が独自に決定できます。
毎週与えられる法定休日や所定休日、有給休暇に加えて特別休暇を与えることで、以下のメリットが得られます。
- 従業員のワークライフバランスが向上する
- 従業員のモチベーションがアップして生産性が向上する
- 従業員からのエンゲージメントが向上して離職率が低下する
- 企業のアピールポイントとなって求人応募が増える
- 企業のイメージアップになる
このように、特別休暇は企業にとっても従業員にとってもメリットが豊富な休暇です。積極的に利用することで、企業の利益や社会的価値の向上が目指せるでしょう。
2. 特別休暇と有給休暇はじめ諸休暇との違い


特別休暇と似たものに、有給休暇があります。具体的な違いについて法定休暇と法定外休暇の観点から解説します。
2-1. 法定休暇
法定休暇は、法律で企業が従業員に必ず付与しなければならない休暇です。これにより、従業員は安心して働け、労働条件の向上が期待されます。法定休暇には年次有給休暇、産前産後休暇、育児休業があります。
年次有給休暇
有給休暇は、その名の通り給料が支払われる休暇のことです。一般的に有給休暇と呼ばれているのは、労働基準法で付与することが定められた「年次有給休暇」です。
労働基準法では、6か月以上かつ全労働日の8割以上出勤した従業員に対して、勤続年数に応じた年次有給休暇を与えることを義務付けています。
参考:昭和二十二年法律第四十九号労働基準法|e-Gov法令検索
対して、特別休暇は付与することが義務付けられておらず、有給にするか無給にするかについても企業の判断で決められます。このように、同じ休暇であっても両者はまったく異なる休暇の種類であり、給与計算にも関わってくるので注意してください。
生理休暇
生理休暇は女性従業員が月経時に取得できる休暇で、労働基準法第68条の規定により付与されます。この法律は、使用者が生理日で仕事が著しく困難な女性から休暇の請求があった場合、就労を免除する義務を課しています。生理休暇は有給ではないため、給料を支払う必要はありません。
日数は個人の症状により異なり、限られるべきではありません。さらに、1日単位だけでなく、半日や時間単位での取得も可能です。この制度の柔軟な運用は健康管理と業務効率を両立させるために重要です。人事担当者は生理休暇の具体的な規定や運用方法を理解し、従業員の健康と職場環境の改善に努めるべきです。
参考:昭和二十二年法律第四十九号労働基準法|e-Gov法令検索
育児休業・介護休業
育児休業・介護休業は、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づいて付与される休暇です。育児休業は、労働者が1歳に満たない子を養育するための休業と定義され、期間は子が1歳までの連続した期間とされます。
また、介護休業は、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業であり、要介護状態とは、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を指し、介護休業の期間は対象家族1人につき通算93日までと定められています。
企業の人事担当者や管理職にとって、これらの特別休暇を制度として理解し、適切に運用することは、従業員の福利厚生を高めるために極めて重要です。
参考:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律|e-gov法律検索
2-2. 法定外休暇
法定外休暇は法律で定められていない企業独自の休暇制度です。この休暇は従業員の福利厚生を向上させるために企業が自主的に設けるもので、特別休暇もその一つに該当します。特別休暇は従業員の生活の質を向上させ、職場の満足度を高める効果があります。
企業はこの休暇の設定や付与についての義務はなく、有給とするか無給とするかは自由に決定できます。特に人事担当者や企業の管理職にとって、法定外休暇の導入は従業員のモチベーション向上や離職率の低下に繋がる重要な施策です。法定外休暇の有効活用は企業の競争力を強化するための有力な手段となるでしょう。
このように休暇と休日の違いを明確に理解していないと、管理上で法律違反をしてしまう可能性があるため、違いをしっかりと把握しておきましょう。
そこで当サイトでは、休暇と休日の違いや休日出勤をさせた場合の対応などを、労働基準法に沿って解説した資料を無料で配布しております。休日と休暇について不安な点がある方は、こちらから「休日・休暇ルールBOOK」をダウンロードしてご確認ください。
参考:e-Gov|労働基準法
関連記事:年次有給休暇とは?付与日数や取得義務化など法律をまとめて解説
3. 特別休暇の主な種類と日数の目安

特別休暇は企業が独自に設定できるため、各企業でさまざまなものが運用されています。ここでは、多くの企業で導入されている特別休暇一例を紹介します。
3-1. 慶弔休暇
慶弔休暇は、結婚や出産、死亡などが休暇の付与事由になる休暇で、従業員やその親族の慶事や弔事に対して付与されます。休暇日数は、近親の程度によって異なるので、適切な日数を設定するのが望ましいでしょう。
慶弔休暇の日数の一例
- 従業員本人の結婚 5~7日間
- 配偶者の出産 5日間
- 実親の死亡 5~7日間
- 子の死亡 10日間
- 祖父母の死亡 3日間
3-2. 傷病休暇
傷病休暇は、通院のための休暇が必要な場合や長期治療が必要な場合など、病気の療養が付与事由となる休暇です。急な病気や怪我に対しては年次有給休暇を使うことができますが、有給以外で体調不良時に使える病気休暇を設けておくことで、万が一のときでも安心して働ける労働環境を整えられます。
日数の目安は企業によって異なり、3ヶ月程度程度の短い期間を設定している企業から、1〜2年と長い期間で設定すしている企業があります。
3-3. ボランティア休暇
ボランティア休暇は、従業員が自発的に無償で社会貢献活動をおこなうことを付与事由とした休暇です。地域貢献活動や自然環境保護活動など、ボランティア活動への関心は年々高まっており、積極的に参加したいという従業員を「休暇」で後押しすることで企業への信頼度を高めることができます。
日数の目安は27日程度となっており、活動内容に応じて変動するケースがあります。
ボランティアの休暇を与えることで休みが増え、生産性低下を懸念する企業も少なくないでしょう。しかし、さまざまな活動に参加することで、従業員の能力向上・スキルアップなど人材育成にもつなげられる可能性があります。また、「ボランティアに参加したい」という希望を叶えることで、仕事に対するモチベーション向上が見込めるので、結果的には好影響となるでしょう。
3-4. バースデー休暇
バースデー休暇とは、名前のとおり誕生日に休暇を取ることができる制度です。日数の目安はその当日の1日となっており、 企業によっては、従業員の誕生日だけでなく家族の誕生日でも休める制度を作っています。
誕生日は多くの人にとって特別な日なので、その日に有給休暇を取れるというのは従業員の満足度向上に役立ってくれるでしょう。
3-5. アニバーサリー休暇
アニバーサリー休暇は、従業員の記念日に休暇を付与する制度です。「結婚記念日」や「家族の誕生日」など記念日の設定をしている企業もありますが、最近では従業員が自由に取得できるようにあえて記念日を限定せず、「従業員にとっての記念日」に休暇を付与する企業も増えています。
日数の目安は1日から2日程度です。
3-6. リフレッシュ休暇
リフレッシュ休暇は、残業が続きや重要なプロジェクトを担当していているなど、心身の疲労が見られる従業員に付与する休暇です。心身の疲労が溜まってしまうと、労働意欲の減退やバーンアウトなどが引き起こされ、生産性低下のリスクが発生します。
日数の目安は3日から7日程度となっており、勤続年数に応じて変動するケースが多くあります。仕事の節目で休憩できるタイミングに休暇を付与すれば、長期間の勤務に区切りがつけられるので、心身共にリフレッシュすることで業務効率の向上も見込めます。
3-7. 夏季休暇
夏季休暇とは、夏に従業員が取得できる休暇を指します。一般的には8月13日から15日までの3日間が多いですが、企業により日数や期間は異なります。特にお盆の時期に設定されることが多く、この時期に休暇を付与することで従業員が帰省などを行いやすくなり、福利厚生の充実につながります。
また、この期間に多くの企業が一斉に休業することから、自社も同様の期間に休業することで業務効率が向上しやすいという利点もあります。従業員のリフレッシュの機会を提供するだけでなく、企業全体の効率的な運営にも寄与するため、夏季休暇の導入は重要です。
3-8. 教育訓練休暇
教育訓練休暇は、労働者が教育訓練を受けるために、有給で一定の期間職場を離れることを認める制度です。業務能力の向上促進に役立つ教育訓練を実施することで、企業は人材育成、従業員はキャリア形成ができるというメリットが得られます。
日数の目安は数日間の場合から数か月間の場合もあり、企業によって花広く設定されています。スキルアップのためのセミナーやコンサルティングを受けたい、という従業員を積極的にアシストすれば、企業への信頼度も高まり業績アップに貢献してくれるでしょう。
3-9. 病気休暇
病気休暇は、長期治療が必要な病気や継続的な治療をおこなっている労働者のために付与される休暇です。治療や通院のためには、休みを取らなければないらないことがあります。治療の頻度によっては、有給休暇でまかないきれないこともあるので、時間単位や半日単位で取得できる病気休暇を設けて従業員をサポートします。日数の目安は症状によって変動しますが、最大90日と上限を設けている場合が一般的です。
年次有給休暇とは別に使うことができる病気休暇は、いざというときのためのセーフティネットとなるので、従業員も安心して働く環境を整えることができる休暇です。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 | e-Gov法令検索
3-10. コロナ休暇
新型コロナウイルス感染症に関連して取得できるコロナ休暇は、従業員およびその家族が新型コロナウイルスに感染した、または感染の疑いがある場合に特別に付与される休暇です。厚生労働省の新型コロナウイルス感染症による特別休暇等の規定例によれば、全従業員、子の世話をする従業員、家族の介護をする従業員、妊娠中の従業員に対する付与が想定されています。
企業によっては、従来の病気休暇に含めている場合もあり、無給休暇がない従業員も安心して療養や看病に専念できます。一般的に、コロナ休暇の付与日数は5日から7日程度となっており、柔軟な制度設計が求められます。このような制度の導入は、従業員の健康と安全を第一に考える企業の姿勢を示す重要な要素です。
参考:新型コロナウイルス感染症による特別休暇等の規定例 |秋田労働局
3-11. 公務員の特別休暇
公務員には多様な特別休暇制度が設けられており、人事院規則によって公民権行使や官公署出頭に関する特別休暇が認められています。特定の業務や個人のライフイベントに対応するための休暇もあり、例として骨髄ドナーやボランティア活動、結婚や出生サポートが挙げられます。また、産前や産後の休業、保育時間や妻の出産に際しての休暇も保障されています。
さらに、男性の育児参加や子の看護、短期介護といった家族への配慮に基づく休暇も用意されています。忌引や父母の追悼といった感情的に重要な行事についても特別休暇が適用されます。季節によって異なる要求に対応するための夏季休暇や自然災害による現住居の減失等に対する特別休暇、出勤困難や退勤途中の事態に対する休暇も含まれます。
4. 特別休暇を導入するメリット
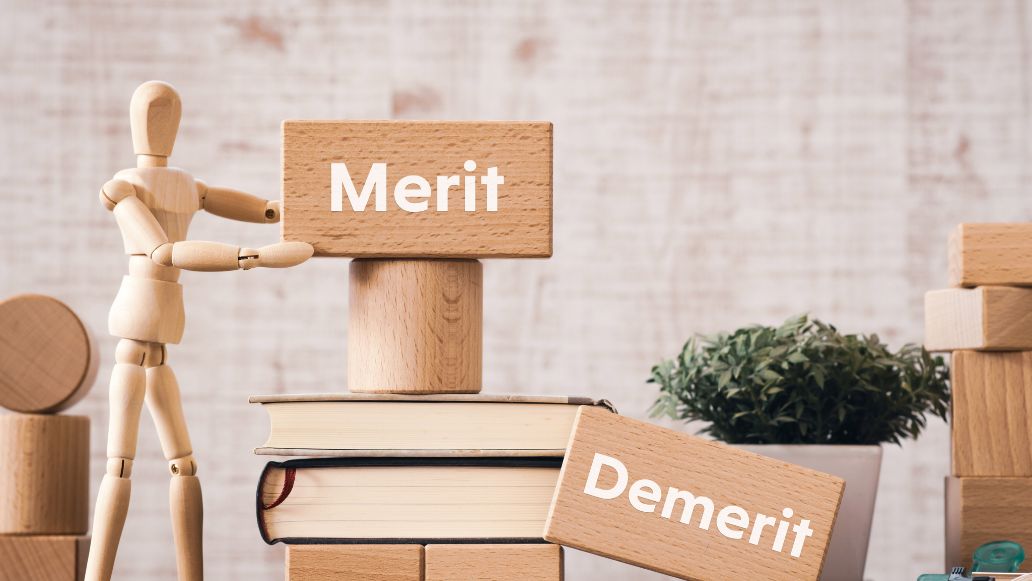
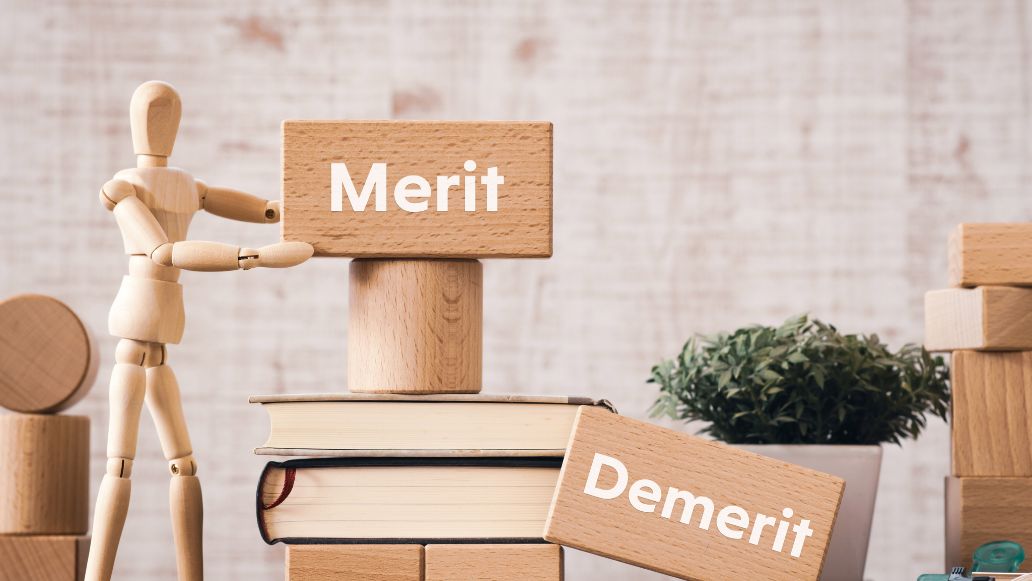
特別休暇を導入することで、企業と従業員の双方に多くのメリットがあります。例えば、特別休暇を提供することで、従業員のモチベーションが向上し、生産性も上がります。また、従業員が心身をリフレッシュできるため、長期的な健康維持にも役立ちます。さらに、特別休暇制度を整えることは、企業のダイバーシティを推進し、優秀な人材の確保や離職率の低減にも効果があります。このように、特別休暇を導入することで、企業全体の業績向上や職場環境の改善につながるため、人事担当者や管理職にとって重要な施策となります。
4-1. 従業員の心身リフレッシュに繋がる
特別休暇は従業員が業務から離れ、心身をリフレッシュする機会を提供します。特に連日の休日出勤や時間外勤務が続くと、従業員の心身に疲労が蓄積しがちです。特別休暇を導入することで、従業員はプライベートの活動を充実させたり、自宅で休養をとったりできます。このように、特別休暇は従業員の健康維持やストレス軽減に役立ちます。
4-2. 従業員のモチベーションを向上させる
特別休暇の導入は、従業員のモチベーション向上に大いに効果があります。企業において従業員のモチベーションが低下すると、生産性やパフォーマンスが大きく減少し、早期離職といった深刻な問題へと発展する可能性があります。しかし、特別休暇を付与することで、従業員は仕事による疲労をリフレッシュし、プライベートの充実を図ることができます。これにより、再び業務に戻った際に高い意欲を持って仕事に取り組むことができ
、結果として企業全体の効率が向上します。特に仕事が忙しい月や個人的な事情が重なるタイミングで特別休暇を活用できる環境を整えることは、従業員のモチベーション向上に直結します。したがって、特別休暇の導入は、企業の長期的な利益向上にも寄与する重要な施策となります。
4-3. 離職率の低下・退職率の改善に繋がる
特別休暇を導入することで、企業は従業員の働きやすさを大幅に向上させることができます。特別休暇の各種制度が充実している企業では、従業員が休みをしっかりと取得できるため、離職率の低下が期待できます。代表的な退職理由として「休みが取りづらい」や「労働時間が長い」といった問題が挙げられますが、これらは従業員のプライベートを犠牲にすることで職場環境のストレスを高めてしまいます。
特に管理職や人事担当者にとって、特別休暇の導入は従業員満足度を高める有力な手段です。企業が独自に定めた特別休暇があれば、従業員は必要な休息を得て、仕事と私生活のバランスを取りやすくなります。その結果、従業員は長く働き続けたいと感じ、離職率の改善に繋がります。特別休暇の導入は、人材の定着を促進し、企業の競争力を高めるための効果的な方法です。
4-4. 企業としての生産性を向上させる
企業の生産性向上には、特別休暇の導入が効果的です。従業員が疲労やストレスを感じたままでは、仕事の成果は上がりません。しかし、特別休暇を付与することで、従業員は心身の疲労をリフレッシュし、仕事へのモチベーションを高めることができます。これにより、生産性の向上が期待できます。特に人事担当者や企業の管理職にとっては、従業員の健康と生産性を両立させる重要な手段として、特別休暇の導入が有益であることを理解していただけるでしょう。
4-5. 企業としてのブランドイメージをアップさせる
特別休暇制度を設けることで、従業員に優しい企業としてのイメージを確立できます。例えば、病気休暇やボランティア休暇などの特別休暇が制度として整備されている場合、企業は従業員のライフワークバランスを重視していることをアピールできます。
このような制度が多くの従業員に利用されている企業は、働きやすい職場として評価され、その結果、ブランドイメージの向上に繋がります。また、特別休暇が整備されていることは、人材確保の観点でも大きなメリットとなり、優秀な人材の採用活動においても有利に働きます。
特別休暇を導入することで、企業のブランド価値を高め、従業員満足度を向上させると同時に、新たな人材を引きつける力を強化できるのです。
5. 特別休暇の導入方法

ここからは、特別休暇を新設するときのポイントを紹介します。効果的な特別休暇の導入を実現するためにも、しっかりとチェックしておきましょう。
5-1. 特別休暇の目的を検討する
まずは、新設する特別休暇の目的を検討しましょう。目的によって、最適な特別休暇は異なります。
たとえば従業員の長時間労働が問題になっている企業では、3日連続して取れるリフレッシュ休暇を1年に1回義務付けるといったアイデアが浮かぶかもしれません。
企業のPRをするためであれば、ほかの企業にはないユニークなアイデアを盛り込んだ特別休暇がおすすめです。ユニークな特別休暇は話題になりやすいので、企業への注目度が一気に上げられるでしょう。
大切なのは、人事だけではなく現場社員の声を踏まえて今の課題を把握し、特別休暇を新設する目的について考えることなので、広い視野を持つことを心がけてください。
5-2. ルールを就業規則に規定して周知する
特別休暇の目的と具体的な内容が決定したら、就業規則に記載しましょう。ここで決めておきたいのは、以下の内容です。
- 特別休暇の目的
- 取得できる日数対象者
- 申請方法
- 取得期限
- 有給か無給か
ルールを決める際に重要となるのは、「従業員に寄り添って考える」ということです。例えば、社員のリフレッシュを促進する休暇であるのに、申請方法が難しかったり取得期限が長かったりすると、休暇の取得促進ができません。ルールは管理のしやすさも大切ですが、休暇を取りやすいルールにすることを意識しましょう。
就業規則を変更したら、社員に周知して導入の準備を整えておきます。
関連記事:無給休暇とは?欠勤・有給休暇との違いや給料の有無を分かりやすく解説
5-3. 特別休暇に関する変更を届け出て運用開始
就業規則を変更して特別休暇を設けた場合は、必ず管轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。ちなみに届出は、持参でも郵送でもできます。都合のいい方法を利用してください。
届出が完了したら、特別休暇の運用を開始しましょう。せっかく設けた特別休暇なのですから、従業員がしっかりと利用できるように周知を徹底するとともに、企業や上司が休暇の取得を促進するよう働きかけることが大切です。
6. 特別休暇を導入する際の注意点

最後に、特別休暇を導入する際の注意点について2つ見ていきます。特別休暇を「ただあるだけの制度」にしないためにも、しっかりと注意点を押さえておきましょう。
6-1. 形骸化させない意味でルールや規則を作成する
特別休暇は、社員のモチベーションアップや企業のPR、労働環境の課題解決などのために設けられることが多いかもしれません。こういった明確な目的をもって特別休暇を設置するのであれば、制度を形骸化させないことがとても大切です。
例えば、今まで有給休暇が取りにくい環境であった企業の場合、特別休暇を導入しても取得率は低くなってしまうでしょう。また、従業員が特別休暇を申請したときに、周囲の同僚や上司が気持ちよく休暇を取らせなければ、誰も特別休暇を申請しなくなるかもしれません。「特別休暇を新設したものの、形だけの制度で誰も利用しない」といった課題を抱える企業は、決して珍しくないのです。
こういった事態を防ぐためには、単に特別休暇を設けるだけではなく、休みを取りやすい労働環境や勤務体制を整えることが非常に大切です。まずは、現場にいる社員にヒアリングすることで業務上の課題や問題点を改善することからはじめましょう。
特別休暇が企業の自己満足にならないよう、適切に運用していくことを意識してください。
6-2. 査定へ反映させないことが望ましい
特別休暇は企業が自由に定めて付与できる休暇です。そのため、休暇の取得を給与や賞与、人事査定などに反映させるかどうかも、企業の判断で決められます。
しかし、福利厚生であるという特別休暇の性質上、こういった査定への反映は避けておいたほうがいいでしょう。査定に影響することになれば、休暇の取得をためらう従業員が増えてしまい、休暇の本来の目的を果たせなくなってしまうためです。
休暇の取得をあらゆる査定や評価に影響させず、従業員が安心して制度を利用できる評価制度を整えることが重要です。
6-3. 有給休暇の取得義務5日と差別化を徹底する
法定休暇となる年次有給休暇は、従業員の働き過ぎや有休の取得率向上のため、年に5日の取得が義務化されています。そのため、従業員は付与されている年次有給休暇のうち、5日以上を取得しなければなりませんし、会社側にも取得させることが義務が付けられています。
一方、特別休暇は法定外休暇です。そのため、法定休暇となる年次有給休暇の5日取得義務とは別に考えなければなりません。
例えば、年次有給休暇を3日、特別休暇を2日取得したとしても、5日取得義務は果たせていないので、取得義務違反となってしまいます。取得義務違反には、企業側経営者に対して30万円以下の罰則が課せられるため、年次有給休暇と特別休暇の差別化を徹底しましょう。
7. 特別休暇を取得する際の給料について


特別休暇というのは法律で規定されている休暇ではないため、会社が自由に設定できます。そのため、有給にするか無給にするかに関しても会社が自由に決めらるので、特別休暇の給料については会社の就業規則に従い、支払いの有無を判断します。
つまり、特別休暇を有給としている場合は休暇を取得した日数分の給料を支払う、無給としている場合は支払わないということになるので、就業規則を確認しましょう。
7-1. 特別休暇は無給にできる?
一般的に「特別休暇=有給休暇」というイメージがありますが、前述したように有給無給は会社が決めるので、無給にすることも可能です。
ただし、「有給」というイメージを持っている人が多いため、「無給」の場合は特別休暇の恩恵を感じられないというのが実情です。「労働環境が整っている」「休暇以外の福利厚生が充実している」などの魅力があれば無給でも人材は集まるかもしれませんが、企業のイメージアップや人材確保のために特別休暇を設けるのであれば、有給にするのが望ましいでしょう。
また、就業規則で「有給」としているのに、給与計算で「無給」として取り扱うのは労働基準法に違反する可能性があるので注意してください。
8. 特別休暇を正しく扱い社員のエンゲージメント向上を目指そう!
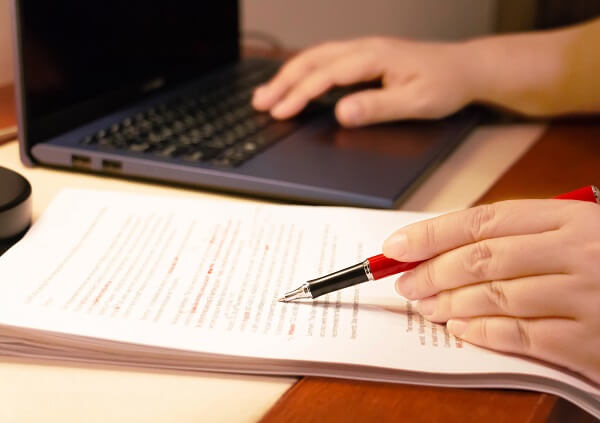
特別休暇は、企業が独自に設けられる休暇です。有給休暇のような取得義務はありませんが、導入することで企業のイメージアップや社員のモチベーション向上など多くのメリットが得られる制度です。
ただし、特別休暇の制度を導入しても、実際に取得できる環境が整っていなければ、形だけの制度になってしまいます。休みを取りやすい労働環境を整えるのはもちろんのこと、休暇があらゆる査定に影響を与えない評価制度にするなど、会社全体で特別休暇を取得しやすい環境に整備することが肝心です。
特別休暇の検討をする際には、労働環境や評価制度も見直して、社員のエンゲージメント向上を目指しましょう。
関連記事:休日と休暇の違いとは?休みの種類や勤怠管理のポイント
【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK
人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?
従業員に休日労働をさせた場合、休日はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。
そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、休日・休暇の決まりを徹底解説した資料を無料で配布しております。
「休日休暇の違いや種類、ルールを確認したい」という人事担当者の方はこちら「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25