産休はいつから?産前産後の取得期間や双子の場合・手当の計算方法を解説

従業員から「産休はいつから取得できますか?」と質問されたとき、説明できるよう準備しておくことが大切です。労働基準法第65条に定められた産前産後休業は、開始日の計算、多胎妊娠の特例、社会保険料の免除、各種手当の申請など、実務で押さえるべき情報は多岐にわたります。
本記事では、従業員が安心して出産に臨み、会社が円滑な労務管理をおこなうために必要な知識を解説します。
目次

育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。
本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。
◆この資料でわかること
- 育児・介護休業法の基本と最新の法改正について
- 給付金・社会保険料の申請手続きと注意点
- 法律で義務付けられた従業員への個別周知・意向確認の進め方
- 子の看護休暇や時短勤務など、各種両立支援制度の概要
2025年10月施行の改正内容も詳しく解説しています。「このケース、どう対応すれば?」といった実務のお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 産休(産前産後休業)とは?


産休(産前産後休業)とは、労働基準法65条で定められた休業制度です。出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産まで取得できる「産前休業」と、出産の翌日から8週間の「産後休業」を合わせて産前産後休業と呼びます。
(産前産後)
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
|
|
概要 |
|
産前休業 |
出産に備えるための期間 |
|
産後休業 |
産後の体を回復させるための期間 |
産前休業の開始日は従業員本人が自由に決められ、出産直前まで勤務を希望するケースもあります。また、出産が予定日より遅れた場合、その日数分だけ産前休業期間が延長される仕組みです。なお、出産日当日も産前休業の期間に含まれます。
産後休業は、出産日の翌日から8週間で、この期間は本人が希望しても原則就業できません。これは産後の回復期(産褥期)を確保することが目的です。ただし例外として、産後6週間を過ぎ、本人の希望と医師の許可があれば就業が可能です。
なお、産前産後休業の「出産」とは妊娠4ヵ月以上の分娩をいい、死産や流産も含まれます。
1-1. 産休を取得する条件
会社に雇用されている女性従業員は、雇用形態や勤続年数にかかわらず産休(産前産後休業)を取得できます。正社員だけでなく、アルバイト、パート、派遣社員、契約社員など全ての従業員が対象です。
ただし、産休中の給与保障である「出産手当金」を受給するためには、会社の健康保険の被保険者であることや、産休中の給与の支払いがないこと(一部支払われた場合はその分を減額)などの条件があるため、事前に確認しましょう。
1-2. 産休を取得する方法と必要な書類
産前産後休業を取得する際、休業期間(産前・産後それぞれ)や出産予定日を確認できる社内フォーマットを用意しておくと、社会保険手続きがスムーズになります。
申請は休業開始前までにおこなえば問題ありませんが、妊娠中の体調変化や業務引き継ぎを考慮し、できるだけ早めの申請を促すことが望ましいでしょう。
産前産後休業期間と出産予定日の確認ができたら、会社は産前産後休業期間中の社会保険料の免除手続きをおこないます。「産前産後休業取得者申出書」を作成し、所轄の年金事務所へ持参・郵送、または電子申請のいずれかの方法で書類を提出しましょう。
参照:産前産後休業を取得し、保険料の免除を受けようとするとき|日本年金機構
1-3. 育児休業制度との違い
産後休業を取得した後には、続けて育休を取得するケースがほとんどです。
育休は、正式には「育児休業」といい、育児・介護休業法に基づいて定められた、子どもを養育するための休業制度です。産休と育休の違いは次のとおりです。
|
産休(産前産後休業) |
育休(育児休業) |
|
|
取得期間 |
出産予定日の6週間前から出産翌日より8週間まで |
子どもが1歳になる前日まで |
|
対象者 |
女性労働者(パート・アルバイト・派遣労働者を含む全ての労働者) |
1歳に満たない子を養育する労働者(勤続1年未満の場合など、対象外となることもある) |
|
根拠法 |
労働基準法 |
育児介護休業法 |
|
延長 |
産前休業に限り出産が遅れた場合は延長される |
やむを得ない理由がある場合にのみ最長2年間まで延長可能 |
育休は、条件を満たせば母親だけでなく父親も取得できるのが産休との大きな違いです。原則として子どもが1歳になるまでの期間内で休業が認められています。例外として、「保育所等の申込みをおこなっているが見つからない」などのやむを得ない事情がある場合は、最長で2年間延長できます。
関連記事:育児休業期間(育休)はいつからいつまで?延長や期間変更はできる?
2. 産休の期間はいつからいつまで?


産休は、産前休業と産後休業のことで、それぞれ取得期間が定められています。
|
産前休業 |
出産予定日の6週間前から取得可能 |
|
産後休業 |
出産翌日から8週間まで |
産前休業の開始日は、産前の6週間前以降、任意で決められます。
また、産前休業の開始前であっても、体調不良や就業への不安がある場合は、休業開始日を早められないか、従業員から相談されるケースも少なくありません。母体の安全と健康を守る観点から、従業員の希望に配慮した対応をおこないましょう。
2-1. 産休期間の計算例
例として、出産予定日が「令和7年12月31日」の場合を計算しましょう。
産前休業は、出産予定日の6週間前(42日前)から取得できます。そのため、「令和7年11月20日〜令和7年12月31日」の期間が産前休業の期間です。
産後休業は、出産日の翌日から8週間(56日間)の取得となります。そのため、「令和8年1月1日〜令和8年2月25日」の期間が産後休業の期間です。
なお、厚生労働省のWebサイトには、出産予定日を入力するだけで産前・産後休業期間を自動計算できるツールがあります。正確な期間を知りたい場合は、こちらを利用しましょう。
参考:産休・育休はいつから?産前・産後休業、育児休業の自動計算|厚生労働省
2-2. 出産予定日よりも前後に生まれた場合
出産予定日はあくまでも予定であるため、予定日の前後に出産がずれることも珍しくありません。
出産予定日よりも早く産まれた場合は、産前休業はそのまま前倒しで短くなり、出産日の翌日から産後休業が開始されます。一方で、出産予定日よりも遅く産まれた場合は、予定日から実際の出産日までの期間も産前休業となります。休業期間が前後するのは「産前休業」のみであり、産後休業の「8週間」は延長されません。
なお、社会保険料の免除期間は、出産予定日より早く出産し、その期間に休業している日がある場合には、前月分まで前倒しとなることがあります。予定日と異なる日に出産した場合は、必ず確認し再申請しましょう。
参考:産前産後休業を取得し、保険料の免除を受けようとするとき|厚生労働省
2-3. 双子の場合の産休期間
双子または三つ子など、多胎妊娠の場合には、産前休業の期間は14週間(98日)と定められています。社会保険料免除の申請の際にも、単胎妊娠か多胎妊娠かの情報が必要となるので必ず確認しましょう。
(産前産後)
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
3. 産休中の給与と産休に関わる手当の計算方法


産休期間中は、会社から給与を支給しないケースが一般的です。産休の期間中の社会保険上の制度には、産前産後期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除、健康保険から支給される「出産手当金」と「出産育児一時金」があります。
ここでは、それぞれの制度の詳細を説明します。
3-1. 産休中の給与と社会保険料について
産休中は通常、会社からの給与は支払われません。会社によっては一部給与が支払われるケースもありますが、ごくわずかです。
このような状況でも安心して生活を送れるよう、健康保険から「出産手当金」が支給されます。これは、産休中の生活を保障するための制度で、休業中の給与を補填する目的があります。
また、産休中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は免除されます。産休の取得期間が決まったら「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」を申請しましょう。
関連記事:産休を取得した従業員の給与計算の方法は?ルールや注意点を解説
関連記事:住民税は産休・育休中でも支払う必要はある?納付方法や納付書がいつ届くのかを解説
参考:産前産後休業を取得し、保険料の免除を受けようとするとき|厚生労働省
3-2. 出産手当金
出産手当金は、産休中の生活を保障することを目的とした制度です。被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合、産休期間中の範囲内で会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
出産手当金の1日あたりの金額は次の計算式により算出されます。
|
1日あたりの金額 【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3) (※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
|
会社の健康保険制度が健康保険組合の場合には要件や金額が異なる可能性があるので確認しましょう。
関連記事:出産手当金の申請方法とは?いつまでにどこに申請する?必要書類や書き方、申請期間を解説
関連記事:従業員が出産手当金をもらえないケースとは?支給条件や対応策を解説
3-3. 出産育児一時金
出産育児一時金は、出産にかかる経済的負担を軽減することを目的とした制度です。健康保険や国民健康保険の加入者が出産した際、一児につき一律の金額が支給されます。この制度により、まとまった出費となる出産費用を実質的に補助してもらえるのです。
多くの病院では、この一時金を直接医療機関に支払う「直接支払制度」を利用できるため、本人が多額の現金を準備する負担を避けられます。
4. 従業員の産休にあたって人事が対応すべきこと


従業員から妊娠の報告を受けてから産休に入るまでに、人事担当者がおこなうべき対応について解説します。
ここでは協会けんぽ(全国健康保険協会)の手続きを例に説明しますが、会社が健康保険組合に加入している場合は、必ず会社や加入先の保険組合に内容をご確認ください。
4-1. 対象者への産休の説明と意向確認・必要書類の回収
妊娠した報告を受けたら、産休制度の説明をおこないましょう。
すでに出産予定日がわかっている場合は、産休の開始日と終了日を算出し、その時点での従業員の取得の意向を確認します。
なお、休業届がなくても、産前産後休業を取得することは法的に可能です。しかし、会社の規定で休業届の提出を求める場合は、休業開始までに回収しましょう。
4-2. 産休中の社会保険料の免除手続き
産休に入ったら、会社は産休中の社会保険料免除の手続きをおこないます。「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構に提出しましょう。
手続きは産前・産後休業中のいずれでも可能ですが、産前休業中に申請して実際の出産日が予定日と異なった場合は、産後に再申請が必要です。
参考:産前産後休業を取得し、保険料の免除を受けようとするとき|厚生労働省
4-3. 産休に関連する手当の申請
出産後、出産手当金と出産育児一時金の申請をおこないます。協会けんぽの場合、出産手当金と出産育児一時金の申請書には、医師の証明が必要です。そのため、出産前に従業員に書類を渡しておくと、スムーズに申請書が用意できます。
また、出産手当金の支給決定は産後休業期間が過ぎた後になるため、従業員へ支給されるのは出産から2~4ヵ月程度後となることも併せて従業員に伝えておくとよいでしょう。
参考:健康保険出産手当金支給申請書|全国健康保険協会
参考:出産育児一時金等について|全国健康保険協会
関連記事:出産手当金の申請方法とは?支給額やもらうための条件についても解説
4-4. 生まれた子を扶養に入れる手続き
生まれた子を社会保険の扶養に入れる手続きをおこないます。申請には、氏名(漢字・よみがな)・性別・生年月日・マイナンバーなどの情報が必要です。
健康保険証は、産後の検診や乳児健診などでも必要となるため、通院に支障が出ないよう、早急に対応しましょう。なお、税法上の扶養に関する手続きは年末調整時におこないます。
4-5. 対象者の部署の業務調整やサポート
産休による欠員で部署への負担が過度にかからないよう、業務の分担や優先順位の見直しを
おこなうことも重要です。必要に応じて、他部署からの応援や派遣の活用、外部委託などを検討し、運営を維持できる体制を整えましょう。
5. 産休に関連するよくある質問
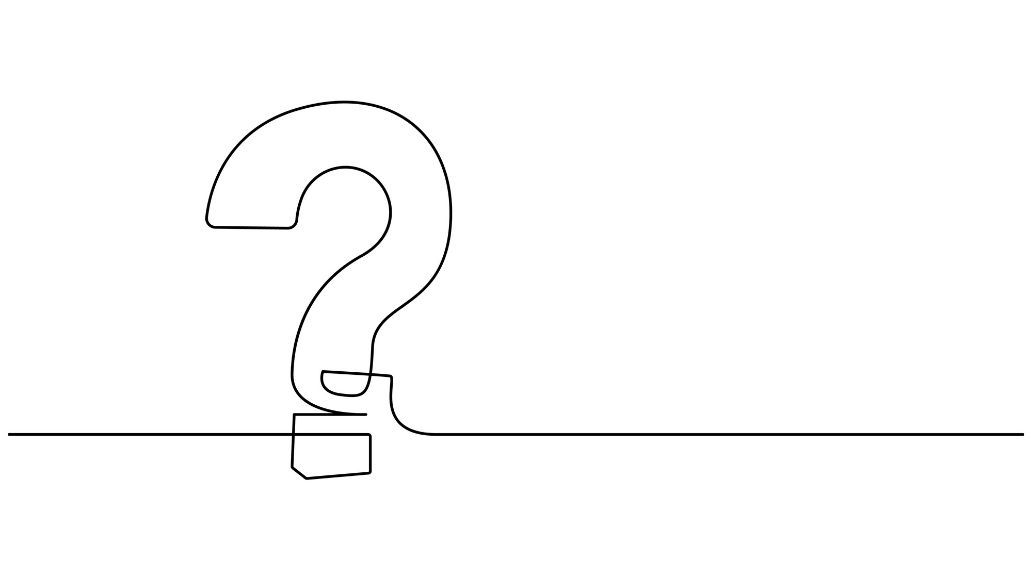
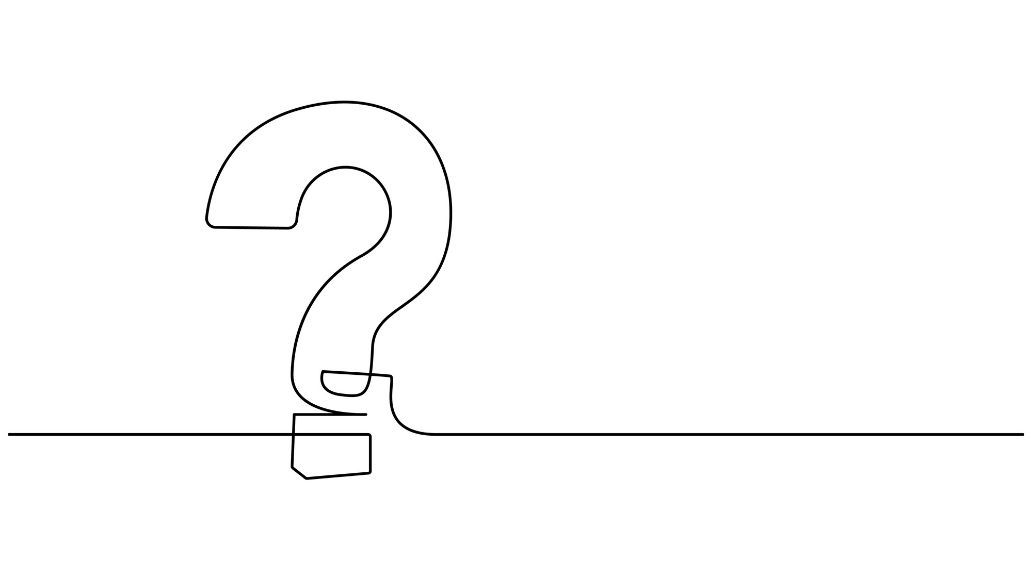
産休に関して、従業員からのよくある質問をまとめました。実務の参考にしてください。
5-1. 派遣社員も産休を取得できる?
派遣社員の場合でも、正社員や契約社員と同様に産休を取得できます。雇用契約は派遣元との契約となるため、まずは派遣元に報告・申請をおこないましょう。
派遣先との直接調整は必要最低限にとどめ、休業期間や引き継ぎなどの連絡は派遣元を通じておこなうのが原則です。
5-2. 産休や育休を理由に従業員を解雇することはできますか?
産休・育休中の不利益取り扱いは、男女雇用機会均等法第9条により禁止されています。そのため、産休や育休を理由とした解雇も当然禁止です。
(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
ー中略ー
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
関連記事:男女雇用機会均等法とは?禁止事項と違反時の罰則、実施すべき措置をわかりやすく解説
5-3. 復職希望者においてフルタイム勤務が難しい場合はどう対応すべき?
復職後にフルタイム勤務が難しい従業員には、育児休業終了後も利用できる制度の活用を検討しましょう。労働基準法や育児・介護休業法では、子どもの年齢に応じて次のような柔軟な勤務形態が認められています。
- 育児時間(1日2回・各30分)
- 短時間勤務制度
- 子の看護休暇
- 時間外労働・深夜業の制限
これらの制度は申出制であるため、本人の希望や家庭状況を確認し、制度利用の可否や社内の運用ルールを明確にしておくことが重要です。
関連記事:復職とは?判断基準・タイミングや手続きの流れについて解説!
5-4. 転職後すぐに産休を取ることはできる?
産前・産後休業の取得に勤続期間の条件はないため、転職直後であっても取得できます。採用して間もない従業員から産休取得の申出を受けた際、これを拒むことはできませんので注意しましょう。
5-5. 法律で決められた産前休業より早く産休は取得できる?
原則として、産前休業は出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週間前)より前に開始することはできません。
ただし、妊娠中の体調不良などで早めに就業を控える必要がある場合、産休前でも年次有給休暇や会社独自の病気休暇、傷病手当金の利用が可能なケースがあります。まず、従業員からの申出内容を確認し、就業規則に定められた内容と照らし合わせ確認しましょう。
また、男女雇用機会均等法では、妊婦健診のための時間確保や医師の指示に基づく業務軽減措置を事業主に義務づけています。対応の際は、医師の診断書を提出してもらうことで、必要な措置や休暇の判断がしやすくなります。状況に応じて柔軟に対応できるよう、社内関係者とも情報を共有しましょう。
5-6. 公務員や教員の産休はいつから入れる?
公務員や教員の産休も、会社員と同様、出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合98日前)から取得可能です。労働基準法第65条に準じて、国家公務員・地方公務員それぞれの育児休業関連法や人事規則に規定されています。
6. 従業員が安心して産休を取得できる職場環境を整えよう


産休は「産前休業」と「産後休業」に分かれており、出産予定日の6週間前(42日前)から、出産の翌日から8週間後(56日)までの期間が法律で定められています。
従業員が安心して産休を取得できる職場環境は、法令遵守だけでなく会社の信頼性や定着率向上にもつながります。制度の正しい理解と円滑な手続きを心がけ、休業中も復帰後も安心して働ける体制を整えていきましょう。



育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。
本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。
◆この資料でわかること
- 育児・介護休業法の基本と最新の法改正について
- 給付金・社会保険料の申請手続きと注意点
- 法律で義務付けられた従業員への個別周知・意向確認の進め方
- 子の看護休暇や時短勤務など、各種両立支援制度の概要
2025年10月施行の改正内容も詳しく解説しています。「このケース、どう対応すれば?」といった実務のお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
労務管理の関連記事
-



【2025年12月最新版】労働施策総合推進法が改正!カスハラ対策の義務化や治療と仕事の両立支援を解説
人事・労務管理公開日:2026.01.20更新日:2026.01.19
-


育児休暇の給料は有給・無給?制度設計ポイントや育児休業との違いを解説
人事・労務管理公開日:2025.12.26更新日:2025.12.26
-


L字カーブとは?M字カーブとは違う?原因と解消に向けた取り組みを解説
人事・労務管理公開日:2025.12.12更新日:2025.12.10





















