住民税はいつから天引きして納付する?時期や手続き方法をわかりやすく解説
更新日: 2024.7.24
公開日: 2021.11.15
OHSUGI

住民税は前年の1~12月分が翌年に課税され、支払い義務が発生する税金です。特別徴収の場合は、6月~翌年5月にかけて毎月納付するようになっています。基本的に事業主には特別徴収の義務が課せられますが、特例によって特別徴収をしなくても良いケースがあるので、注意が必要です。
ここでは住民税特別徴収の仕組みや流れ、特例やパターン別の対応方法をみていきましょう。
▼給与計算における住民税の記事はこちら
給与計算における住民税とは|住民税の計算・納付・注意点について解説
目次
社会保険の手続きガイドを無料配布中!
社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 住民税とは?


2. 住民税はいつから納税する?天引きする時期


住民税の納税は社会人として勤務しはじめ、2年経過した6月から発生するのが一般的です。住民税の対象となる前年1月から12月までに一定の所得税があった場合です。一般的に社会人1年目は前年に一定の所得がないため、住民税が発生することはありません。しかし、社会人1年目であっても前年にアルバイトなどで一定以上の所得が発生していれば、住民税の納付が必要です。
2-1. 住民税の納付が対象外になるケース
住民税が課税されないケースもあります。例えば、以下のようなケースが該当します。
- 年間所得が一定額以下の場合
- 生活保護を受けている場合
- 障害者
- 未成年者
- 寡婦(夫)
- ひとり親の場合
このようなケースでは住民税が非課税となることがあります。住民税の非課税条件は、各自治体により若干異なるため、お住まいの自治体の公式ウェブサイトで詳細を確認することが必要です。
3. 徴収方法「普通徴収」と「特別徴収の違い」


住民税の納付方法は普通徴収と特別徴収の2種類あります。
普通徴収とは、納税義務者が市区町村から送付された納付書(納税通知書)によって年4回住民税をおさめる方法です。
特別徴収とは、納税義務者の給与支払者が従業員にかわって毎月給与から住民税を差し引いたうえで納入する方法です。
普通徴収と特別徴収にはほかにも細かな違いがいくつかあるので、本章で詳しく解説します。
参考:東京都主税局 | 特別徴収Q&A
3-1. 徴収の回数
特別徴収は、原則として毎月の給与から住民税を差し引きます。
普通徴収は年4回であるのに対して特別徴収は年12回であるため、特別徴収の場合、納税義務者の1回あたりの負担が少なくて済むでしょう。
1年間の住民税が30万円だった場合、特別徴収なら1ヵ月25,000円の住民税が給与から差し引かれます。一方普通徴収の場合、年に4回、6月・8月・10月・1月となり、1回あたりの税額が多くなるでしょう。実際の納税額は変わりませんが、1回あたりの税額に違いがあります。
3-2. 業務の負担
「住民税を特別徴収することで業務量が増えるのでは…」という不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、住民税の特別徴収は所得税と異なり、税額の計算や年末調整の必要はありません。計算は給与支払報告書を確認した市区町村がおこないます。
納付書が送付されて住民税額が各市町村から通達されたら、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月10日までに金融機関を通じて市区町村に納入するだけです。
また特別徴収をすると従業員が金融機関に出向いて自ら納税する手間も省くことができます。従業員の手間を軽減するという意味でも特別徴収はメリットが大きいです。
3-3. 徴収方法
特別徴収は給与から差し引いて事業主側が払います。そのため、事業主側が適切に処理していれば、納税義務者が支払い忘れることなどは発生しないでしょう。
一方で、普通徴収の場合は納税義務者が適切に管理をして納付しなければなりません。中には支払いを忘れてしまったり住民税分の給与も別のことに使ってしまったりする可能性があります。
普通徴収は納付期限までに納付ができないと、住民税の滞納とみなされるでしょう。督促がおこなわれ、それでも納付されない場合は滞納者の財産が差し押さえられます。
会社としても従業員が滞納者となってしまうことで様々なデメリットが生じる恐れがあります。
4. 住民税の納付額について


住民税の納付額は所得割と均等割の2つから成ります。それぞれの割合と負担する額は次のとおりです。
- 所得割の割合:10%(道府県民税、都民税4%+区市町村民税6%)
- 均等割の負担:4,000円(2014~2023年までは5,000円)
所得割は所得に対しての割合になるため、所得が高い方が納税額は増えます。一方、均等割りは4,000円です。しかし、2014年から2023年は東日本大震災からの復興税として1,000円プラスした5,000円を負担します。
4-1. 住民税の計算方法
住民税は次のような方法で算出します。
- 所得-所得控除=課税所得金額
- 課税所得金額×税率10%-税額控除額=所得割額
- 所得割額+均等割5,000円=住民税
会社員の場合、税金の対象となるのは収入ではなく所得です。課税の対象となる所得は、次のとおり収入金額に応じた所得控除を引いた額です。
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 162万5,000円まで | 550,000円 | |
| 162万5,001円~180万円まで | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万1円~360万円まで | 収入金額×30%+8万円 | |
| 360万1円~660万円まで | 収入金額×20%+44万円 | |
| 660万1円~850万円まで | 収入金額×10%+110万円 | |
| 850万1円以上 | 195万円(上限) | |
4-2. 定額減税により住民税が1万円の減税された
また2024年6月以降、定額減税が適用され、1人あたり住民税が1万円減税されることとなっています。これは特別措置であり、物価高による家計負担を軽減するためのものです。通常の住民税徴収とは異なり、会社勤めの人は6月の住民税が0円になり、残りの11か月分で調整されます。個人事業主に関しても、最初の6月分から控除が始まり、引ききれなかった場合は次期以降に控除が適用されます。
4-3. ふるさと納税とは?住民税の負担を軽減する?
ふるさと納税は、特定の自治体に寄附を行うことで、その寄附金額の一定部分が所得税や住民税から控除される仕組みです。寄附金額の2,000円分を超える部分については全額が控除対象となり、寄附を行う自治体を選択することができます。これにより、自分が応援したい地域へ直接支援ができると同時に、自身の税負担も軽減されるメリットがあります。ふるさと納税の手続きを行うには、確定申告または「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用が必要です。
5. 住民税の納付手続きと流れ


住民税特別徴収による納付までの手続きと流れは以下の通りです。
5-1. 給与支払報告書を提出する
前年1~12月までの1年間に各従業員へ支払った給与支払額を1月31日までに「給与支払報告書」にまとめて市区町村に提出します。この給与支払報告書が住民税を算定する基準です。
5-2. 特別徴収税額の通知と住民税納付書の送付がされる
給与支払報告書を受け取った各市区町村は、給与支払額やふるさと納税やその他控除を加味したうえでそれぞれの住民税額を計算します。最終的な住民税額が記載された「特別徴収税額の決定通知書」が毎年5月ごろに事業主宛てに送付されます。事業主は通知を受け取ったら、記載されている内容や金額が正しいかどうかをチェックしましょう。
関連記事:住民税決定通知書とは?見方や再発行の方法、ふるさと納税との関係も解説!
5-3. 住民税を徴収する
通知された従業員ごとの住民税は、月額の給与計算に反映させて給与から天引きします。毎年5月に通知された分は、翌月の6月から反映させなければいけません。
ほとんどの場合、住民税の金額が変わるので、徴収する住民税金額が正しいのかをしっかりと確認しましょう。
5-4. 住民税を市町村に納付する
給与から天引きしている住民税を、給与支払いの翌月10日までに納付します。金融機関や市区町村の窓口で納付可能です。
住民税はクレジットカードで納付できる??
個人で住民税を納付する場合にのみ、クレジットカードを使用することも可能です。クレジットカードで納付する際は、自治体の公式ウェブサイトや「地方税お支払サイト」を利用することが一般的です。ただし、手数料が発生する場合もあるため、事前に確認することが重要です。
6. 住民税特別徴収の特例
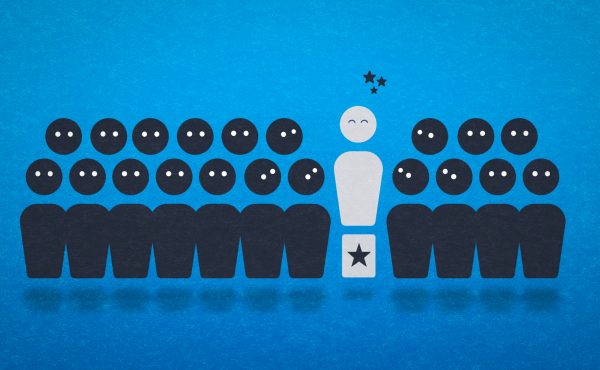
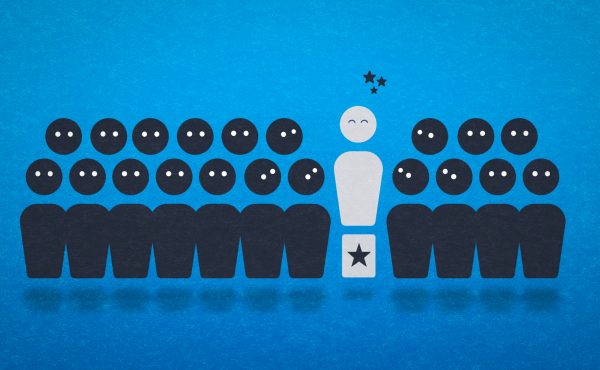
住民税特別徴収は地方税法で定められている義務ですが、会社や従業員に事情がある場合は、特別徴収から普通徴収への切り替えが可能です。
- 会社の総従業員数が2名以下
- 常時2名以下の家事使用人に対してのみ給与を支払っている
- 他の会社で特別徴収をおこなっている
- 5月31日までに退職する予定がある
- 給与が毎月支払われていない
- 給与が少なく特別徴収ができない
これらの理由がある場合「個人住民税の普通徴収の切替理由書」を「給与支払報告書」とともに1月31日までに市区町村へ提出しましょう。
6-1. 住民税特別徴収の納期の特例
住民税特別徴収をする場合でも、給与支払を受ける従業員が常時10人未満の場合は希望する場合、特例で納期を年2回にまとめておこなうことができます。
納期の特例適用を希望する場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出する必要があります。
審査の上、承認された場合、特別徴収義務者に、市区町村から承認書・納入書が送付されます。なお、従業員数が変わった場合などで納期の特例の適用要件に該当しなくなった場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」の提出が必要になります。
参考:東京都主税局 | 個人住民税特別徴収の事務手引き
7. 住民税を納入する際の注意点


住民税を納入する際に注意すべきことはいくつかあります。
本章では注意点を3つにまとめてわかりやすく解説します。
7-1. 納付書の内容と徴収額を確認する
住民税特別徴収は、給与支払報告書を提出することで市区町村が税額を計算してくれますが、その通知が正確だとは限りません。通知を受け取ったら、徴収額や内容に間違いがないかどうか、特別徴収対象外の人は含まれていないかなどを確認しましょう。
また、チェックしてミスが見つかった場合は、すぐに市区町村の窓口に連絡を入れてください。会社側で勝手に訂正すると、一部未納になってしまうことがあります。
その他にも事務手続きが遅れていたり、引っ越し・転勤で従業員の住所が変わったりすると5月に通知が届かないケースもあるので、なかなか届かないときは市区町村に問い合わせなければなりません。
7-2. 住民税の納付書を紛失してしまった場合
住民税の納付書を紛失した場合、管轄の役所や事務所の納税課などに連絡して再発行してもらう必要があります。
再発行手続きなどは通常よりも時間がかかる可能性があるため、納付書の管理はしっかりとおこないましょう。また、住民税の納付は従業員の納税にかかわる重要な業務なので、万が一納付書をなくした際などは早急に再発行手続き・納入をおこないましょう。
7-3. 住民税の納付期限を過ぎてしまった場合
住民税の特別徴収の納付期限を1日でも過ぎてしまった場合、滞納とみなされます。
納付期限を1日でも過ぎた場合・過ぎてしまう場合には、まずは管轄の市区町村の税金窓口に連絡しましょう。
なお、納付期限に間に合わなかった場合は、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。
納付期限を過ぎてしまった場合、納税義務者(事業主)に向けて督促状が送付されます。
督促状が届いてもなお、納入しない場合は財産調査がおこなわれ、滞納処分(差押え)が執行されます。
そのため、会社の信用喪失にもつながりかねません。
それだけでなく、特別徴収税の納入は事業主の義務なので、適切におこなわれなかった場合、罰則が科される可能性があります。
事業者に特別徴収税額決定通知書が送付されたにもかかわらず、特別徴収をおこなわなかった場合、滞納処分の対象となるとともに、地方税法第324条第3項の罰則(10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は懲役及び罰金の併科)の対象となるため、確実に対応することが求められます。
住民税の滞納をすると、延滞金が発生し、滞納処分がおこなわれます。特別徴収は従業員の給与からの預り金であるため、より責任をもって期限までに納入しなければなりません。
参考:e-Gov法令検索 | 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
8. 住民税特別徴収のパターン別納付対応


住民税の特別徴収にあたり、様々な事情でどう対応するべきかわからないというケースも多々発生します。ここでは住民税特別徴収のパターン別納付対応を見ていきましょう。
8-1. 社員が入社した
入社した社員が普通徴収だった場合、特別徴収をおこなうためには特別徴収切替届出書を市区町村に提出する必要があります。入社する時期によりますが、すでに納付期限を過ぎている税額は切り替えられないため、社員が個人で納付しなければなりません。社員が特別徴収されていると勘違いしてしまう恐れがあるので、会社側から通知しておくと良いでしょう。
また中途入社で特別徴収を引き継ぐ場合は、前の会社から届く異動届出書があれば転勤・転職の該当部分に追加で記載し、市区町村に届け出るだけで手続きは完了です。社員が勤めていた前の会社から異動届出書が送られてこない場合は、普通徴収であった場合と同様の流れで切り替えましょう。
8-2. 社員が退職した
退職した社員が再就職した場合、翌月10日までに転職先に対して給与所得者異動届出書を送りましょう。そのまま特別徴収を引き継ぐことができます。
一方で退職したものの再就職をしない、もしくは再就職が決まっていない場合は、退職した月によって取り扱いが異なります。
- 1~4月:残りの分を一括徴収
- 5月:特別徴収(通常通り)
- 6~12月:翌月より普通徴収
6~12月に退職した場合、退職金を超えない範囲であれば本人の希望によって一括徴収が可能です。
また退職時の退職所得で、退職所得控除を超える分は住民税が課税されます。従業員が退職する際は退職所得の課税に関しても気を付けましょう。
8-3. 休職や転勤をした
従業員の転職によって納税地が変更になったり、休職によって給与が発生しなくなった場合は、給与所得者異動届出書の該当欄に記入し、市区町村の窓口に提出します。
休職となるとまとまった期間で給与が発生しなくなるので、特別徴収の取り扱いは退職時と同様です。残りを給与から一括徴収か、納税者本人が普通徴収で納めるかのどちらにするかを選択しましょう。
9. 住民税納付の仕組みを理解してミスなく支払おう


住民税は会社が従業員の分を天引きして代わりに納付する、特別徴収が基本です。住民税額は市区町村が決定するため、会社側の負担はそれほどありません。
とはいえ、会社側は通知が届いたら内容が間違っていないかどうかをしっかりと確認する必要があります。
また事情によっては特別徴収に当てはまらないケースがあるため、特例に該当するかどうかを確かめたうえで特別徴収をおこないましょう。
社会保険の手続きガイドを無料配布中!
社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08





















