労働者災害補償保険法とは?対象や給付金をわかりやすく解説
更新日: 2025.11.21 公開日: 2025.1.3 jinjer Blog 編集部
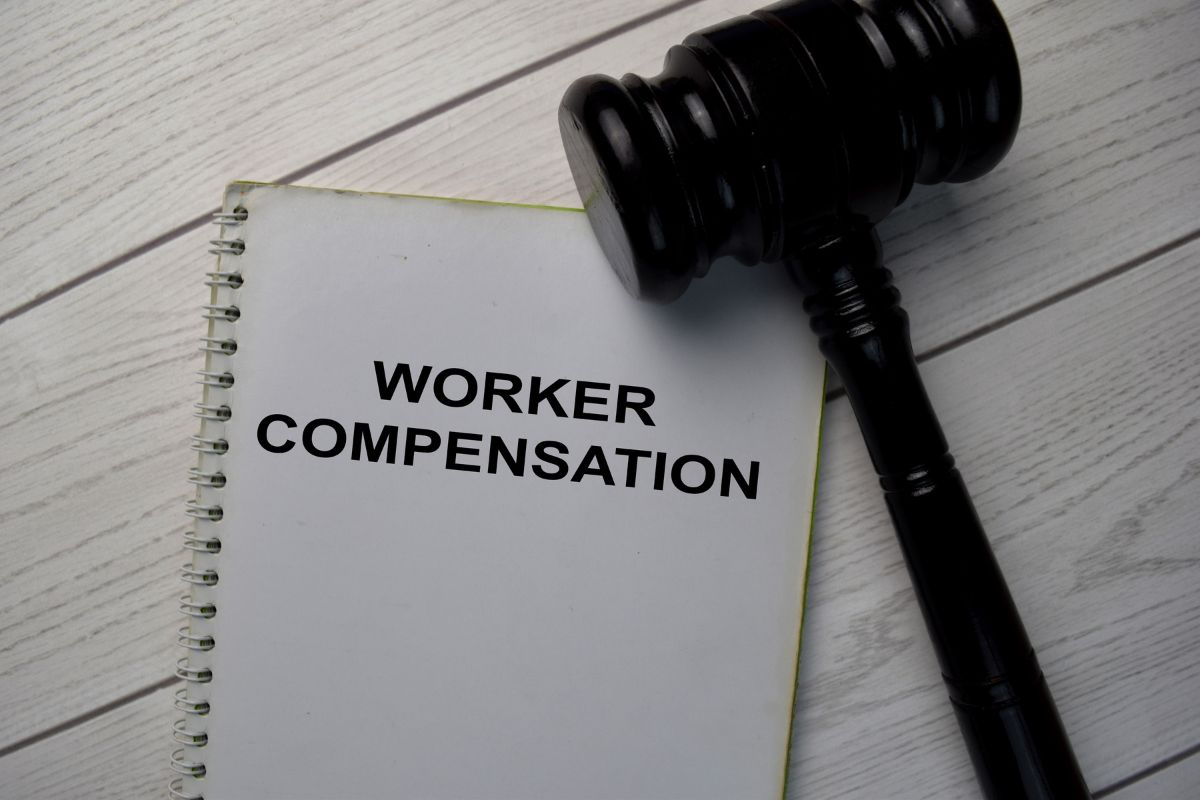
労働者災害補償保険法とは、労災保険制度を定めた法律です。労災保険制度は、従業員が業務中の災害で負傷や死亡した場合、被災した従業員や遺族を支援することを目的としています。
労働者災害補償保険法は正社員に限らず、アルバイトや契約社員など賃金が支払われるすべての従業員が対象です。ただし、国や地方の事業に従事する人など、対象外となるケースもあ。
本記事では、労働者災害補償保険法の概要や労働者災害補償保険法の対象、適用条件について詳しく解説します。令和2年(2020年)の労働者災害補償保険法の一部改正についても触れているため、ぜひ参考にしてください。
目次

人事担当者であれば、労働基準法の知識は必須です。しかし、その内容は多岐にわたり、複雑なため、全てを正確に把握するのは簡単ではありません。
◆労働基準法のポイント
- 労働時間:36協定で定める残業の上限時間は?
- 年次有給休暇:年5日の取得義務の対象者は?
- 賃金:守るべき「賃金支払いの5原則」とは?
- 就業規則:作成・変更時に必要な手続きは?
- 40年ぶりの大改正:人事担当者が押さえておきたい項目は?
これらの疑問に一つでも不安を感じた方へ。
当サイトでは、労働基準法の基本から法改正のポイントまでを網羅した「労働基準法総まとめBOOK」を無料配布しています。
従業員からの問い合わせや、いざという時に自信を持って対応できるよう、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 労働者災害補償保険法とは


まずは労働者災害補償保険法とはどのような制度なのか、目的や労働基準法との違いについて知っておきましょう。
1-1. 業務や通勤中などに被災した場合の支援を目的とした制度
労働者災害補償保険法は労災保険制度について定められた法律で、労災保険法ともよばれています。従業員が業務災害や通勤災害で傷病または死亡した場合、被災した従業員や遺族を支援することが目的です。
労働者災害補償保険法では、保険者を国(政府)、加入者を事業主として定めており、労災が発生した際は、国が補償をおこなう仕組みとなっています。また、加入者である事業主は、強制適用事業に該当する場合、必ず労災保険に加入しなくてはいけません。
労働者災害補償保険法では、労災認定にあたって業務起因性・業務遂行性がポイントです。労災として認められた災害は、大きく業務災害と通勤災害に分けられます。この災害の種類については後ほど詳しく解説していきます。
また、労働者災害補償保険法における労災保険は、賃金が支払われる従業員すべてに適用されます。職種や雇用形態(有期雇用・パート・アルバイトなど)も関係ありません。
1-2. 労働者災害補償保険法と労働基準法の違い
労働基準法は、労働者を不当な労働から守るために、賃金や労働時間、休日など、事業主が守るべき労働条件のルールを定めたものです。その中に災害補償に関する規定が設けられています。
労働基準法第75条では、労災が発生した際、会社が治療費や療養費を負担して労働者に補償をおこなうことを義務付けています。ただし、第84条において、労働者災害補償保険法等に基づいて補償がおこなわれる場合は、事業主側の補償を免責にするとしています。
つまり、労働基準法で労災時の事業主の責任を原則として定め、労働者災害補償保険法でその責任を国の保険制度によって担保する仕組みとすることで、労災時に労働者が確実に補償を受けられる体制を整えているのです。
1-3. 2020年に労働者災害補償保険法が一部改正された
令和2年(2020年)9月に、労働者災害補償保険法の一部改正がおこなわれました。改正の対象となるのは複数の企業に勤務する従業員で、改正された内容は労災保険給付額の決定方法と労災認定の判断基準です。
改正前は、労働災害が発生した勤務先の賃金のみを基に労災保険給付額を決めていました。改正後はすべての勤務先の賃金を合算した額を基に労災保険給付額を決定します。
また、改正前はそれぞれの勤務先ごとに負荷を評価して労災認定の可否を判断していました。改正後は個別評価しても労災認定できない場合、すべての勤務先の負荷を総合的に評価して判断します。
| 改正前 | 改正後 | |
| 労災保険給付額の決定方法 | 労災が発生した勤務先の賃金のみで給付額を決定 | すべての勤務先の賃金を合算して給付額を決定 |
| 労災認定の基準 | 勤務先ごとに負荷を評価して労災認定の可否を判断 | すべての勤務先の負荷を総合的に評価して労災認定の可否を判断 |
複数事業で働く従業員の保護を強化し、兼業や副業など多様化する働き方に対応することが目的と考えられます。
1-3-1. 2024年11月からフリーランスも労災保険の「特別加入」の対象に
2024年11月からはフリーランスも労災保険の特別加入の対象になっています。従来フリーランスは労災保険の加入対象者ではありませんでした。しかし、以下のようなフリーランスを除き、労災保険特別加入の対象となりました。
- 企業等から業務委託を受けていない
- 企業等から委託を受けている業務が特定フリーランス事業以外の特別加入の事業または作業に該当する
参考:令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました|厚生労働省
2. 労働者災害補償保険法に規定されている内容


労働者災害補償保険法は、労働中の災害に対する補償をおこないます。どのような人や状況が対象になるのか解説していきます。
2-1. 労働者災害補償保険法が適用される事業者
従業員を1人でも雇用する事業者はすべて、労働災害補償保険法が適用となり、労災保険への加入が義務付けられます。業種や規模は関係ありません。
ただし、国の直営事業や官公署の事業に関しては適用除外となります。国の直営事業に使用される人は国家公務員災害補償法、地方の事業に使用される人のうち、常勤の職員や一部の非常勤職員は地方公務員災害補償などが適用されます。
また、暫定任意適用事業となっている事業者に関しては、労災保険の加入は任意とされています。暫定任意適用事業は、一定の条件を満たす個人経営の農林水産業などが該当します。ただし、労働者の過半数以上が加入を希望する際は、労災保険の加入が必要です。
2-2. 労働者災害補償保険法の対象になる人
労働者災害補償保険法の対象は、賃金が支払われる従業員すべてです。正社員に限らず、以下のような業務形態の従業員に対しても適用されます。
- アルバイト
- パートタイマー
- 契約社員
- 派遣社員
- 日雇い労働者
給付内容に関しても、正社員と変わりはありません。
ただし、労働者災害補償保険法の対象になるのは労働基準法における「労働者」に該当する人のみです。労働基準法が定める労働者とは「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」であるとされています。
そのため、以下の職位や働き方の人は基本的には労働者災害補償保険法の対象にはなりません。
- 経営者
- 社長
- 役員
- 自営業者
- 個人事業主
他にも、使用従属性がない場合や指揮監督下にない働き方などの場合は、労働者に該当しないことがあります。
2-3. 特別加入制度によって対象が拡大される
労働基準法における労働者に該当しない場合は、労働者災害補償保険法の対象にならないと説明をしました。
しかし、特別加入制度を利用することで、労働者災害補償保険法の対象になり労災保険が適用されることがあります。特別加入制度を利用できるのは、労働者に準じて保護することがふさわしいと判断される人です。
一例としては、以下のような業務についている人が挙げられます。
- 中小事業主
- 一人親方
- 自営業者
- 特別作業従事者
- 海外派遣者
- 芸能関係者
- アニメーション作成作業従事者
- 柔道整復師
- 創業支援等に基づき事業をおこなう者
芸能関係者以下は、2021年から新たに特別加入制度の対象になりました。多様化する働き方や職種に対応するために、今後も対象は拡大される可能性があります。
関連記事:人事担当者必見!労働保険の対象・手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解説
3. 労働者災害補償保険法が適用される災害
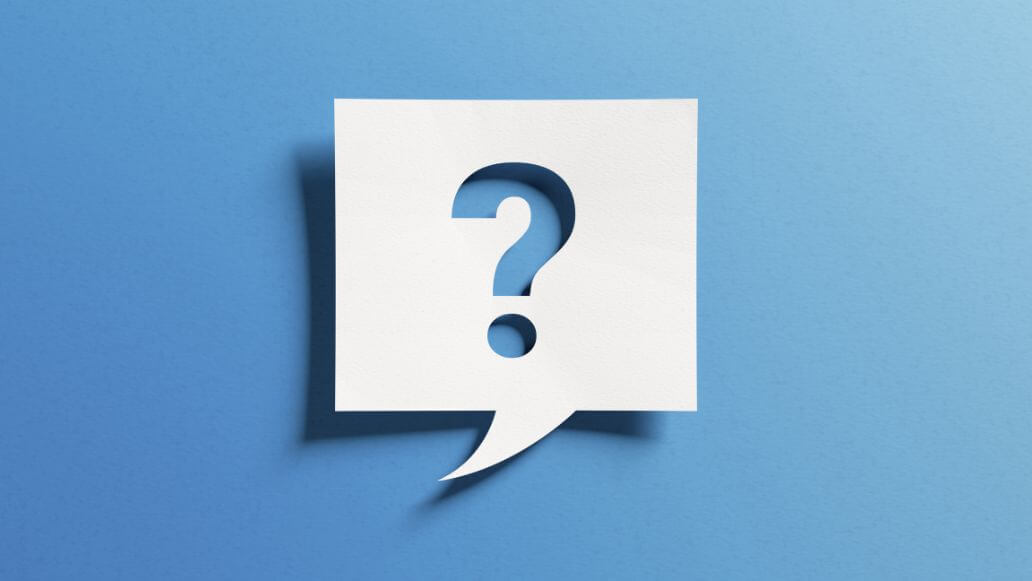
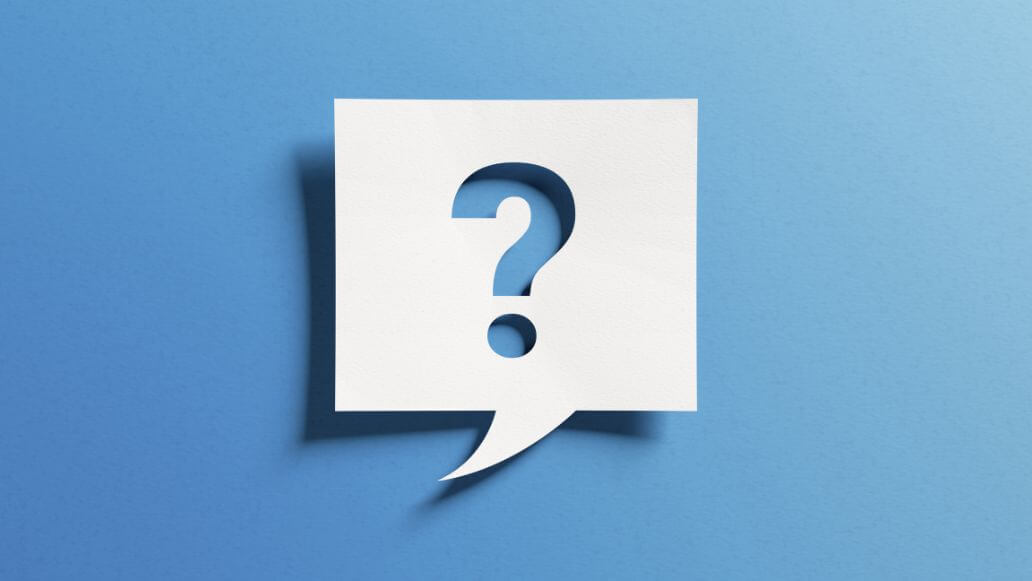
労働者災害補償保険法が適用される災害は、業務遂行性と業務起因性に大きく分けることができます。また、そこから業務災害と通勤災害に分かれます。それぞれどのような災害が該当するのか確認していきましょう。
3-1. 労働者災害補償保険法における災害とは
まずは労働者災害補償保険法における災害がどのように考えられているのか、認定を受ける際の前提部分である「業務遂行性」と「業務起因性」について解説します。
労働災害として認められるには、まずは業務遂行性に基づく業務起因性が認められなければなりません。
業務遂行性
業務遂行性とは、「労働者が契約に基づいて事業主の支配・管理下にある状態」で発生した災害を指します。
- 企業側からの指示や命令に従って労働をしているとき
- 労働契約に基づいた休憩時間
- 業務に付随する通勤・移動時間
- 企業側からの命令による出張中
これらはすべて事業主の支配・管理下にある状態であるとされるため、この間に発生した災害はいずれも業務遂行性の災害だと判断されます。
業務起因性
業務起因性とは、従業員が受けた傷病と業務とに因果関係があることを指します。
「業務をしていたことが原因で被災した」ということが医学的に認められている状態です。
企業側の指示による業務に就いている間に発生した怪我や、通勤中の事故などに加え、業務に有害因子があると判断され、その有害因子が原因で傷病が発生した場合も業務起因性とされます。
3-2. 労働災害は大きく2種類に分けられる
発生した傷病や死亡が労働災害として認められた場合は、そこから「業務災害」と「通勤災害」に分けられます。
業務災害
業務災害とは、従業員が業務中の事由により傷病または死亡することです。就業時間中は事業主による支配下と考えられるため、休憩時間や昼休みでも業務災害となります。
出張や外出など事業主の管理下を離れた環境であっても、事業主の命を受けて業務に従事しているため業務災害の対象です。
ただし、以下のようなケースは就業時間中であっても業務災害とは認められません。
- 就業中の私的行為によって災害を被った場合
- 故意に災害を発生させた場合
- 個人的なうらみや怨恨が原因で、第三者から暴行を受けた場合
- 地震や台風などの天災で被災した場合
なお、従業員が被った疾病については、以下の3つの条件を満たした場合が業務上疾病と認定されます。
- 事業内に有害な物質が存在していた場合
- 健康障害を被るほどの有害因子にばく露した場合
- 発症の時期が医学的に妥当であること
就業中に発生した疾病であっても、業務との間に因果関係が認められなければ業務災害とは認められません。例としては、加齢や生活習慣が原因による脳卒中や心筋梗塞などが挙げられます。
参考:業務災害とは|厚生労働省
通勤災害
通勤災害とは、従業員が通勤中の事由により傷病または死亡することです。通勤災害と認められるためには、以下の3つを合理的な経路または方法で移動したことが条件となります。
- 住居と勤務地との往復
- 勤務地からほかの就業場所への移動
- 単身赴任先住居と帰省先住所との間の移動
特段の理由がなく著しく遠回りをした場合や、映画館や居酒屋などに寄り道をした場合は合理的な経路とはみなされません。
ただし、以下のような場合は例外とされています。
- 日用品の購入
- 職業訓練や教育訓練を受ける行為
- 病院や診療所での診察または治療
- 選挙投票
- 要介護状態にある家族の介護
日常生活を送るための必要最低限の行為であれば、合理的な経路に戻った後の災害について通勤災害と認められます。
3-3. 労災保険の適用に加えて賠償金が発生する労災
業務災害と通勤災害は、労災保険が適用されてその範囲で補償を受けることができます。それに加えて、以下の災害では賠償金が発生します。
事業主責任災害
事業主責任災害とは、事業主(企業)の重大な過失や故意によって発生した災害を指します。
事業主責任災害に被災した労働者は、労災保険の保険金給付に加えて民事による賠償請求をすることが可能です。さらに、労働者災害補償保険法第31条では、保険給付にかかる費用の全額または一部を国が事業主に請求できる権利を認めています。加えて、事業主側は労働基準法により補償責任を負うことになります。
第三者行為災害
第三者行為災害とは、企業や従業員ではない無関係の人物による災害を指します。
交通事故や他人からの暴行などに加え、動物による怪我や飛来したものによる怪我なども該当します。この場合も労災保険の保険金に加えて損害賠償請求をすることができます。
ただし、労働者災害補償保険法第12条により、保険金の給付より先に第三者から損害賠償がおこなわれた場合、その価額の範囲内で国からの給付はありません。一方、保険金の給付が損害賠償より先におこなわれた場合には、国が第三者に対して求償することができます。
また、第三者行為災害が発生した場合は、管轄の労働基準監督署に「第三者行為災害届」を提出しなければなりません。
4. 労働者災害補償保険法に規定されている給付金の種類


労働者災害補償保険法が適用された場合は、以下のような給付金を受け取ることができます。
- 療養補償給付
- 休業補償給付
- 障害補償給付
- 遺族補償給付
- 傷病補償年金
- 介護補償給付
- 葬祭料
それぞれ詳しく見ていきましょう。労働者災害補償保険法に規定されているのはどれか分かるようにしておけば、従業員になにかあった際に迅速な対応が可能です。
4-1. 療養補償給付
療養補償給付は、労災病院または労災保険指定医療機関などで療養を受ける場合に受けられる給付です。
現物給付の「療養の給付」と現金給付の「療養の費用の支給」の2種類に分けられていますが、原則として「療養の給付」がおこなわれます。
療養の給付は、労災保険指定医療機関などで受診した場合に傷病が治癒するまでの間無料で治療を受けられるという制度です。
療養補償給付の範囲は、治療費や入院費など、療養に必要な費用に加えて移送費用も含まれます。
4-2. 休業補償給付
休業補償給付は、療養のため働けず、給料が支給されない場合に受けられる給付です。休業した4日目から、1日あたり給付基礎日額の60%相当額を受け取れます。
給付基礎日額とは、労働災害が発生した日以前の3ヵ月の賃金の総額を期間中の総日数で除した金額です。
ただし、業務災害による休業の場合、休業初日から3日間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償をおこなわなくてはなりません。
4-3. 障害補償給付
傷害補償給付とは、労働災害で被った傷病が治った後、所定の障害が残った際に受けられる給付です。支給内容は障害の等級に応じて以下のように定められています。
| 障害等級 | 障害補償給付 |
| 1~7級 | 障害補償年金、障害特別支給金、障害特別年金 |
| 8~14級 | 障害補償一時金、障害特別支給金、障害特別一時金 |
なお、労働者災害補償保険法において「傷病が治る」は、治療を続けても効果が期待できなくなった状態を意味します。
障害等級は、労働者災害補償保険法施行規則の別表第一に示されており、身体の障害の程度に応じて該当する等級が一覧で確認できるようになっています。
4-4. 遺族補償給付
遺族補償給付は労働災害によって亡くなった従業員の遺族が受けられる給付で、遺族補償年金と遺族補償一時金の2種類があります。
遺族補償年金は、死亡当時、被災した従業員の収入で生計を維持していた遺族に支払われます。対象となるのは以下のとおりです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
配偶者以外の遺族については、被災した従業員が死亡した当時に高齢または年少であるか、障害の状態にあることが条件となります。
遺族補償年金の対象者がいない場合は、受給資格のある遺族のうち最優先者に遺族補償一時金が支払われます。
4-5. 傷病補償年金
傷病補償年金とは、労働災害による傷病について、療養を開始後1年6ヵ月を経過しても治癒しない場合に受けられる給付です。傷病等級1級から3級に該当する場合が対象となります。
給付基礎日額の313日~245日分が年金として支給されます。
4-6. 介護補償給付
介護補償給付とは、障害補償年金または傷病補償年金の受給者のうち、介護を受けている場合に受けられる給付です。
月単位で支給されるもので、常時介護か随時介護によって支給額が異なります。
4-7. 葬祭料
葬祭料は、労災事故により亡くなった労働者の葬儀にかかる費用を補助するための給付です。支給額は、「315,000円+給付基礎日額の30日分」と「給付基礎日額の60日分」のいずれか高い方が支給されます。。
葬祭料は、実際に葬儀をおこなった遺族や関係者に支給され、申請には死亡の事実や死亡年月日の証明が必要です。
参考:遺族(補償)等給付・葬祭料等(葬祭給付)の請求手続|厚生労働省
5. 労働者災害補償保険法における支給手続き


労働者災害補償保険における支給を受けるためには、以下の手続きが必要となります。
- 労働災害が発生したことを報告する
- 労災指定病院で治療を受ける
- 労働基準監督署へ労災申請書を提出する
5-1. 労働災害が発生したことを報告する
労働災害が発生した際、被災した従業員は直ちに企業へ報告しましょう。企業の事業主には労災発生報告義務があるためです。
企業へ報告する際は、以下の点をできるだけ明確に伝えます。
- 労働災害が発生した日時
- 労働災害の発生状況
- 傷病を被った従業員
- 傷病の状態
ただし、傷病の状況によっては企業への報告より病院での受診を優先しても問題はありません。
5-2. 労災指定病院で治療を受ける
従業員から労働災害の報告を受けた場合、企業は被災した従業員にできるだけ早く労災指定病院で治療を受けるように伝えましょう。早期に受診することは、従業員の回復はもちろん、労災保険を適切に受給することにもつながるためです。
労災指定病院であれば費用を立て替える必要がなく、無償で治療を受けられます。労災指定病院以外で受診する場合、健康保険が使えないため治療費の全額を一時的に立て替える必要があることを伝えておきましょう。
5-3. 労働基準監督署へ労災申請書を提出する
労災保険の給付を受けるためには、労働基準監督署に労災申請書を提出する必要があります。労災申請書の種類は申請する給付金によって異なるので注意しましょう。
労災申請書は原則被災労働者または遺族が作成しますが、傷病の状況によっては企業に任せられます。企業には労災申請時の助長義務があるためです。
労災申請書を労働基準監督署へ提出すると、労働基準監督署による調査が始まります。必要に応じて事情聴取がおこなわれるため、関係者は協力するようにしましょう。
6. 労災リスクに備える社内教育とマニュアル整備の重要性
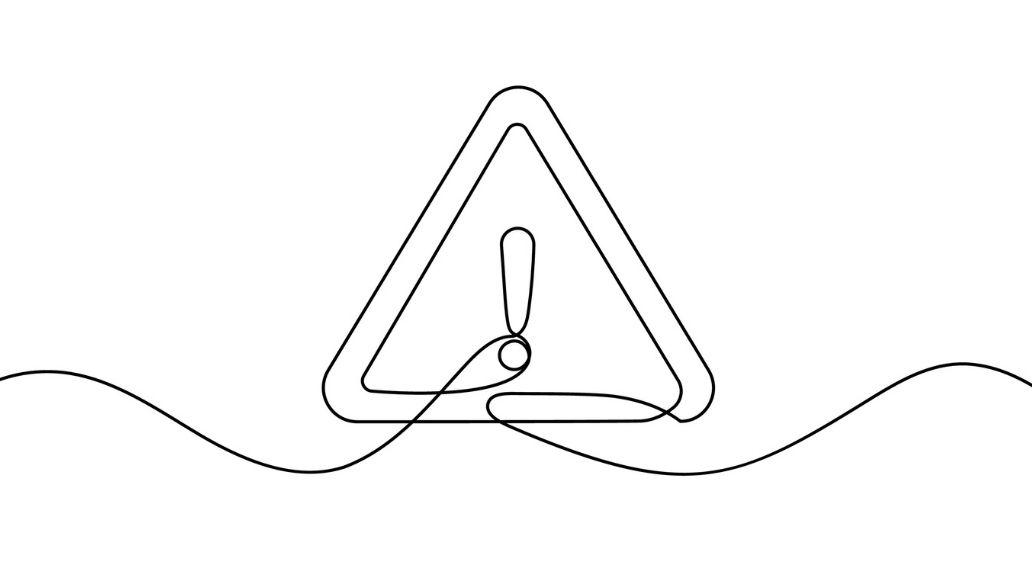
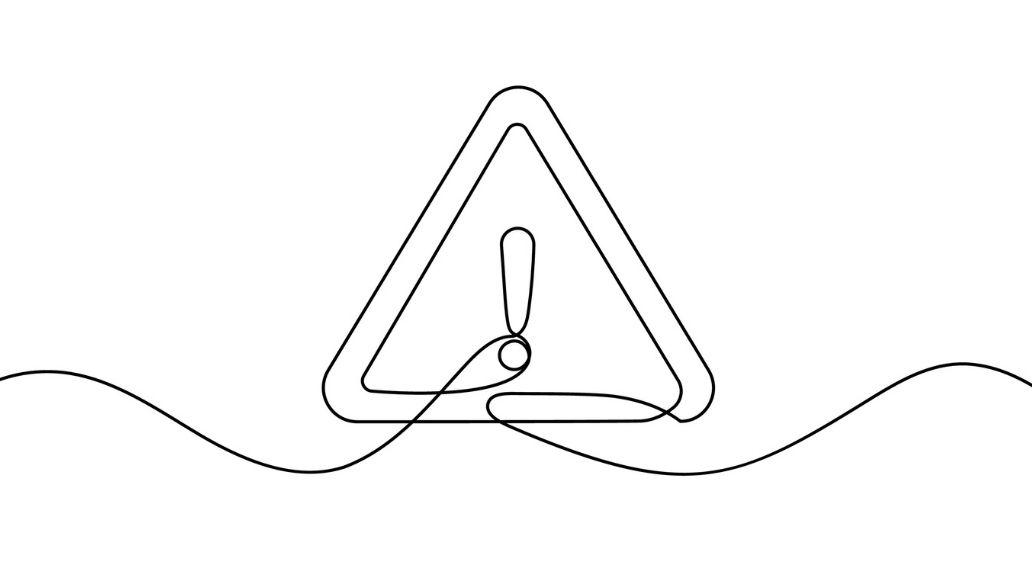
労災リスクを最小限に抑えるには、現場での安全意識の向上と、全社員が共通認識を持てる仕組みづくりが不可欠です。社内教育で危険予知能力を高め、マニュアル整備で対応手順を明確化することで、緊急時にも的確な判断ができる組織体制を構築できます。
6-1. 労災が発生しやすい業務の洗い出し方
労災防止の第一歩は、リスクの高い業務を正確に把握することです。過去の事故記録やヒヤリハット報告を分析し、現場ごとの危険箇所を抽出します。
さらに、実際に従事する社員へのヒアリングを行い、潜在的なリスクも洗い出しましょう。こうした情報を基に優先順位を付け、改善策を計画的に実施することが重要です。
6-2. 新人・中堅社員向けに伝えるべき労災知識
新人や中堅社員には、労災の基本概念や発生メカニズム、報告義務などを理解させることが欠かせません。特に現場作業では、安全装備の着用ルールや危険予知トレーニング(KYT)を習慣化させる教育が効果的です。
また、労災が起きた際の初動対応や通報手順も繰り返し指導することで、現場での的確な判断力を養えます。
6-3. 労災対応フローを社内マニュアル化する方法
労災発生時の混乱を防ぐには、対応手順をマニュアルとして明文化しましょう。負傷者の救護から関係機関への連絡、再発防止策の策定までを時系列で整理します。
誰が、どの段階で、何を実行するかを明確にし、全社員が閲覧できる形で共有することで、緊急時の対応スピードと正確性を向上させられます。
7. 万一のトラブルに備えて労働者災害補償保険法を理解しておこう


労働者災害補償保険法は、労災保険制度について定めた法律です。従業員が業務中の災害で負傷や死亡した場合、被災した従業員や遺族を守ることを目的としています。労働基準法が定める事業主の災害補償責任を、国が運営する保険制度で担保し、労働者が確実に補償を受けられる仕組みです。近年では、フリーランスの特別加入や複数事業労働者の保護強化など、多様な働き方への対応が進んでいます。
従業員の安心と安全を確保するためには、労働者災害補償保険法に関する正しい知識を持ち、労災発生時の初動対応や申請手続きを適切に進めることが不可欠です。
従業員の安心と安全を確保するためには、労働者災害補償保険法に関する正しい知識を持ち、適切に活用しなければいけません。
労働者災害補償保険法について理解を深め、労働災害が発生した場合に備えましょう。



人事担当者であれば、労働基準法の知識は必須です。しかし、その内容は多岐にわたり、複雑なため、全てを正確に把握するのは簡単ではありません。
◆労働基準法のポイント
- 労働時間:36協定で定める残業の上限時間は?
- 年次有給休暇:年5日の取得義務の対象者は?
- 賃金:守るべき「賃金支払いの5原則」とは?
- 就業規則:作成・変更時に必要な手続きは?
- 40年ぶりの大改正:人事担当者が押さえておきたい項目は?
これらの疑問に一つでも不安を感じた方へ。
当サイトでは、労働基準法の基本から法改正のポイントまでを網羅した「労働基準法総まとめBOOK」を無料配布しています。
従業員からの問い合わせや、いざという時に自信を持って対応できるよう、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
労務の関連記事
-


年収の壁はどうなった?2025年最新動向と人事が押さえるポイント
勤怠・給与計算公開日:2025.11.20更新日:2025.11.17
-


2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ
勤怠・給与計算公開日:2025.11.19更新日:2025.12.22
-


人事担当者必見!労働保険の対象・手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.09.05更新日:2026.01.30






















.png)