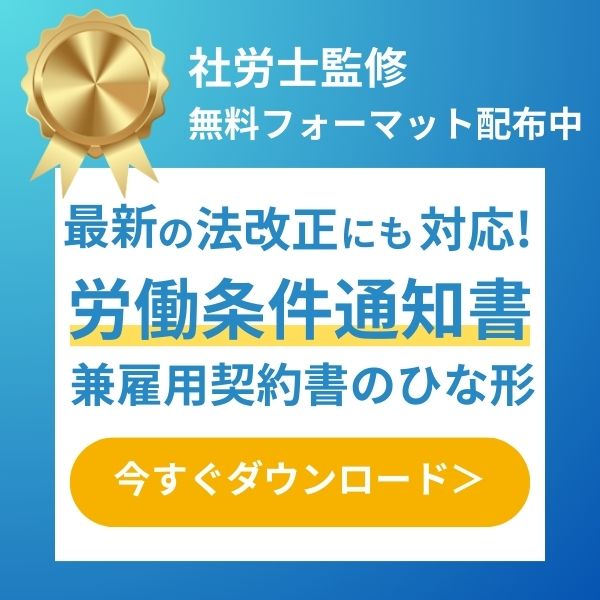労働条件の明示とは?労働条件の明示義務や法改正による明示ルールの変更内容を解説
更新日: 2025.9.29 公開日: 2022.1.22 jinjer Blog 編集部

労働条件の明示は、労働基準法第15条によって義務付けられています。そのため、賃金や労働時間・休日のように、労働者が働く上で重要な要素となる労働条件は、雇用形態に関係なく、採用時に必ず明示しなければいけません。
中でも、賃金のように特に重要とされる項目は、書類など形に残る方法で明らかにする必要があります。また、明示しなかった場合には罰則が課せられるので、担当者の方は注意が必要です。
この記事では、採用時に義務付けられている労働条件の明示に関する基礎知識や明示するタイミング、労働条件通知書の書き方などについて解説します。
目次
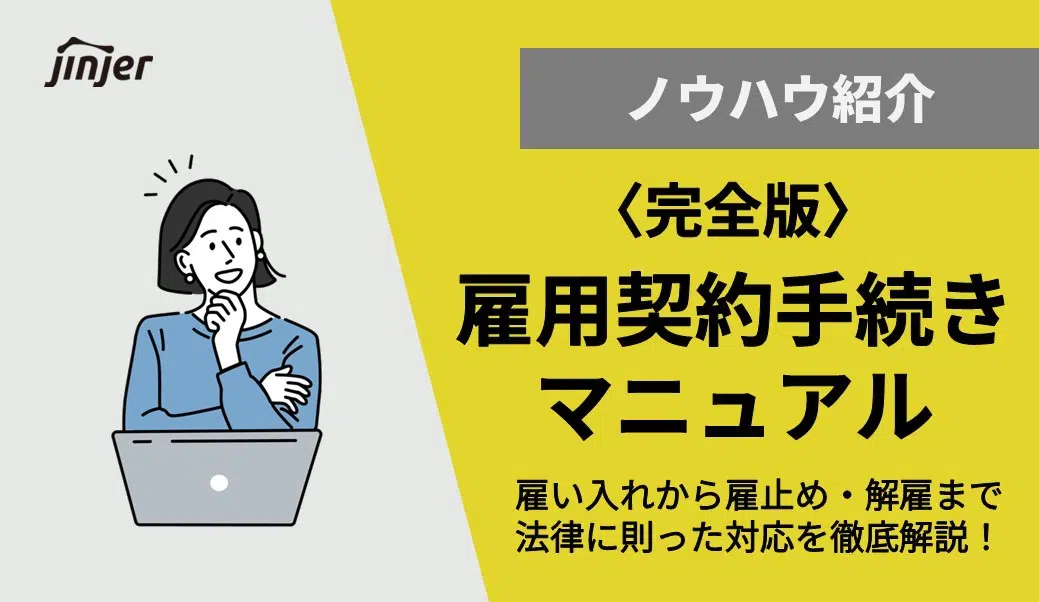
「長年この方法でやってきたから大丈夫」と思っていても、気づかぬうちに法改正や判例の変更により、自社の雇用契約がリスクを抱えているケースがあります。
従業員との無用なトラブルを避けるためにも、一度立ち止まって自社の対応を見直しませんか?
◆貴社の対応は万全ですか?セルフチェックリスト
- □ 労働条件通知書の「絶対的明示事項」を全て記載できているか
- □ 有期契約社員への「無期転換申込機会」の明示を忘れていないか
- □ 解雇予告のルールや、解雇が制限されるケースを正しく理解しているか
- □ 口頭での約束など、後にトラブルの火種となりうる慣行はないか
一つでも不安な項目があれば、正しい手続きの参考になりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 労働条件の明示とは

労働条件の明示義務とは、労働基準法第15条1項に基づき、使用者が労働者と労働契約を締結する際に賃金や労働時間などの労働条件を明確に伝える義務のことです。この義務は正社員だけでなく、パート・アルバイトなどの非正規雇用者を含む全ての労働者に適用されます。
例えば、多くの企業は労働条件通知書の交付や雇用契約書の作成をすることで、この明示義務に対応しています。これにより、労働者は自分の権利を理解し、トラブルを未然に防ぐことができます。
ここでは、労働条件の明示に関する法令や罰則などについて解説していきます。
[注1]労働基準法|e-Gov法令検索
1-1. 労働基準法15条とは
労働基準法第15条とは、企業が労働契約を締結する際に、労働者に対して必ず労働条件を明示する義務を課す条文です。
① 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。引用:労働基準法第15条
この法律を遵守することで、従業員とのトラブルを未然に防ぐことができます。
1-2. 労働条件の明示(労働基準法第15条)に違反した場合の罰則
労働基準法第15条では、使用者が労働条件を明示する義務があります。
この義務に違反し、労働条件を明示しない、もしくは法令で定められた方法で明示しない場合は労働基準法第120条第1号に基づき、30万円以下の罰金が科せられます。また、特定事項の明示義務に違反した場合にも罰則があります。これは、パートタイム・有期雇用労働法第31条によって定められているもので、10万円以下の過料が科せられる可能性があるので注意しましょう。
この罰則は、労働者の権利保護と公正な労働環境の維持を目的としています。
参考:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律|条文|法令リード
1-3. 労働条件は原則書面で明示する
労働条件の明示は、原則として口頭での説明ではなく、書面でおこなうことが法律で義務付けられています。
これは労働基準法に定められた要件であり、労働者の権利を保護するための重要な取り組みです。具体的には、労働条件通知書や契約書などの形式で、賃金や労働時間、休日などの主要な労働条件を明示することが求められます。
書面にすることで、労働者は自身の労働条件を明確に理解し、後のトラブルや誤解を防ぐ手助けとなります。
ただし例外として、労働者の希望があれば、メールやFAXを用いて労働条件を明示することも可能です。この場合も、労働基準法施行規則第5条の第4項にある但し書きに従い、労働者の意向を尊重した形で情報を提供することが重要です。
これにより、適切な手段を用いて労働条件を明示し、法的義務を果たすことができます。
参考:労働基準法施行規則|e-GOV法令検索
条件を満たせば書面以外でも明示できる
労働条件の明示というのは、原則として書面の交付が義務となりますが、条件を満たせば書面以外も可能です。
その条件とは、「従業員本人から電子化の希望がある」です。つまり、「従業員が希望」すれば、書面ではなく電子化で交付できるということです。
電子データで交付する場合は、EメールやSNS、FAXを利用するのが一般的ですが、どの方法であっても「出力して書面化できる」というのが重要になります。文字数制限があったり、ファイルが添付できなかったりするような電子媒体では、正確な明示ができません。そのため、電子化をするとしても、必ず書面化できるもので交付しましょう。
また、電子データを送付した場合、従業員に届いているか、開封してしっかり内容を確認しているかが把握できません。こちらが送っていても、従業員が気が付いていない、迷惑フォルダなどに振り分けられているなどの可能性があるので、送付後には必ずデータの到着を確認してください。
なお、これらの注意点を満たして労働条件通知書の交付を電子化する際は、システムを活用するのがおすすめです。労働条件通知書の交付を電子化できるシステムでは、法律の要件に対応しているのはもちろんのこと、入職者が通知書を見たか確認できるうえ、対象者に一括で書類を送付することができます。
実際に雇用契約を電子化できるシステムがどのようなものか気になる方は、労働条件通知書の交付を電子化できるシステム「ジンジャー人事労務」のサービス紹介ページを以下のリンクよりご覧ください。
クラウド型人事管理システム「ジンジャー人事労務」の雇用契約サービス
2. 2024年「労働条件明示のルール」が改正された背景

労働条件の明示事項は、2024年4月の法改正により変更されたものです。改正前と改正後の明示事項の違いを正しく理解しておくためにも、まずは労働条件の明示ルールが改正された背景を説明します。
労働条件明示のルールが改正された背景の一番の目的は、労働者の権利をより保護し、企業と労働者の信頼関係を強化することです。
新しい法改正により、労働条件の透明性が一層求められるようになり、企業は詳細な労働条件通知を義務づけられました。ここでは、これらの背景について具体的に解説します。
2-1. 有期契約労働者の無期転換への対応強化
有期契約労働者の無期転換への対応強化は、企業にとって重要な課題です。
無期転換とは、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者が申込みをおこなうことで、期間の定めのない無期労働契約に転換される制度のことです。この無期転換ルールは2013年の改正労働契約法で規定されましたが、実際には無期転換申込権を行使する労働者の割合は低迷しています。
2021年におこなわれた実態調査では、無期転換申込権が生じたにもかかわらず、申込む権利を行使した人の割合は3割未満でした。特に企業規模が1,000人以上の大企業でも、無期転換を申込む人の割合は約4割に留まっています。この現状は、無期転換ルールに対する認知と理解が不足しているためと考えられます。
そのため、今回のような改正をおこない、無期転換制度の詳細を従業員に周知することで、この適用を促進させるのが目的となっています。
参考:無期転換ルールに関する参考資料|厚生労働省
2-2. 雇用ルールの明確化
労働条件明示のルールの改正は、雇用ルールを明確化することも目的となっています。
昨今、働き方の多様化により、「勤務地限定」や「職務限定」といった契約形態を採用する企業が増えています。このような状況に伴い、労働条件の明確化が一層重要になっています。
労働条件を明示する法的義務は企業にとって不可欠であり、これにより労働者との認識違いや説明不足によるトラブルを未然に防ぐことができます。
このような取り組みは企業の信頼性向上にも寄与し、人材の定着率向上させる目的があります。
参考:パートタイム・有期雇用労働法とは|厚生労働省
2-3. 同一労働同一賃金の明確化
同一労働同一賃金は、無期労働契約の従業員と有期労働契約の従業員の間で基本給や賞与などで不合理な待遇差を設けることを禁止する(パートタイム・有期雇用労働法第8・9条)法律で、2021年以降全ての企業に適用されています。
これに基づき、従業員に対して有期労働契約と無期労働契約の違いを適切に説明することが求められます。
また、無期転換ルールを促進するためには、労働者が無期転換後の労働条件に対する理解を深めることが重要です。賃金や各種手当てだけでなく、福利厚生や教育・キャリアプランも同一労働同一賃金の範囲に含まれるため、将来のキャリアプラン等を踏まえた労働条件の明示も改正の目的となっています。
3. 労働条件の明示事項【最新版】

労働条件の明示義務に関しては、法改正がおこなわれましたが、記載する「明示事項」というのは変わっていません。明示事項は、下記の2つになります。
- 絶対的明示事項
- 相対的明示事項
ここでは、これらの明示事項について詳しく解説します。
3-1. 絶対的明示事項
賃金や労働時間など、労働者が働く上で特に重要とされる内容は、書面などにより明示しなければいけません。(昇給に関する事柄は口頭でもよい)
以下の項目は、雇用形態にかかわらず、採用時は労働者に明らかにして伝える必要があります。
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(3)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項(複数拠点あるときは住所まで具体的に。また、業務内容も「経理」など明確に記載)
(4)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
(5)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
(6)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)(2)については期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合がある者の締結に限り、明示する必要があります。
引用:採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。|厚生労働省
また、パート・有期労働者は上記の事項に加えて、下記の事項を書面等により明示する必要があります。
- 昇給の有無
- 賞与の有無
- 退職金の有無
- 相談窓口
これらの事項に関しては、口頭での説明だけでは違反となってしまうので注意してください。
3-2. 相対的明示事項
次の内容は会社で取り扱いがある場合に限り、労働者に明かす必要があります。ただし、相対的明示事項は書面を交付しなくても問題ありません。
(7)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
(8)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
(9)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
(10)安全及び衛生に関する事項
(11)職業訓練に関する事項
(12)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(13)表彰及び制裁に関する事項
(14)休職に関する事項
ただし、書面の交付が義務付けられていないとしても、何らかのトラブルになった場合、説明したことを証明できないので、採用時には書面で明示する方が安全です。
4. 法改正後の「労働条件の明示項目」

労働条件の明示に関して、労働基準法施行規則は「全ての労働者」を対象としています。
これは、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどの非正規雇用者も同様に含まれることを意味します。企業の人事担当者や経営者にとって、この法的義務を理解し、適切に対応することは非常に重要です。
特に最近の法改正では、非正規雇用者への対応が厳格化されています。そのため、パートやアルバイトにも正社員と同等に労働条件を明示することが重要です。
企業がこの点に注意を払い、労働基準法施行規則を遵守することで、トラブルを未然に防ぎ、公正な労働環境を維持することが可能です。また、労働基準法施行規則(労基則)の改正と同時に、「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」も改正されます。これに伴い、労働条件の明示項目に新たな項目が追加されるので、人事担当者や経営者は早急な準備が求められます。
ここでは、新たに追加された以下の3項目と法改正によるモデル労働条件通知書の変更点について解説します。
4-1. 就業場所・業務の変更の範囲の明示
労働条件の明示項目として「就業場所・業務の変更の範囲」が新たに追加されます。
「就業場所・業務」は、労働者が通常出勤することが想定されている就業場所と、通常従事することが想定されている業務のことです。これには、出向や配置転換の場所や業務も含まれますが、出張や研修など一時的な変更先や業務は含まれません。
「変更の範囲」は、労働契約期間中に変更する可能性がある就業場所や業務のことです。
この改正により、従来の就業場所や業務の内容だけでなく、今後の変更の範囲についても具体的に明示する必要があります。例えば、配置転換や在籍型出向が命じられた場合の就業場所や業務内容、その際に配置転換先や在籍型出向先がどこになるかといった詳細までを明記することが求められます。
4-2. 更新上限の有無と内容の明示
労働条件の明示項目には、「更新上限の有無とその内容の明示」という項目も追加されます。
有期労働契約の締結時や契約更新時には、更新上限があるかどうかを明確に示さなければなりません。この上限が存在する場合、例えば「契約期間は通算4年を上限とする」や「契約の更新回数は3回まで」といった具体的な内容を記載する必要があります。
これらの事項はパート・アルバイト、契約社員、派遣労働者、定年後の再雇用労働者など、幅広い有期契約労働者が対象となるので漏れがないようにしましょう。
更新上限を定めているにも関わらず、書面による明示がおこなわれない場合は労働基準法15条違反となるため注意しましょう。また、更新上限の新設や短縮をおこなう場合、その変更理由を労働者に説明することも求められます。
4-3. 無期転換申込機会・無期転換後の労働条件の明示
労働契約法の改正により、無期転換後の労働条件に関する明示もより重要な項目となっています。今回の改正では、「更新上限の有無と内容の明示」が新たに追加されました。
これにより、企業は無期転換申込機会の際に、更新上限がある場合はその具体的な内容を明確に提示しなければなりません。つまり、無期転換申込機会が発生するたびに、対象となる有期労働者に対して無期転換申込権の存在と共に、無期転換後の労働条件を明示する必要があるということです。
この労働条件の明示には、更新上限の有無とその詳細も含まれます。具体的には、最大勤務年数や契約更新回数が制限されるのか、またその制限内容がどういったものであるかを労働者に示さなければなりません。
さらに、無期転換後の労働条件が無期雇用フルタイム労働者や正社員と比較して均衡が取れているかも説明する必要があります。ただし、無期転換後の労働条件が転換前と同じ場合は、「前回の明示内容と同一である」と明示することが認められています。
4-4. 法改正によるモデル労働条件通知書の変更点
厚生労働省が公開しているモデル労働条件通知書は、働き方改革や最新の法改正に対応しています。
そのため、基本的には明示事項を満たしていれば問題ありませんが、その他の法令へも対応するために確認しておくと良いポイントを紹介します。
賃金に関する追加事項
労働条件の変更に関する法改正は、特に賃金に関わる追加事項について企業にとって重要な影響を及ぼします。
具体的には、パートタイム・有期雇用労働法の改正により、短時間労働者や有期雇用労働者に対して「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」を明示することが法的に求められています。
例えば、昇給がある場合はその基準や条件、賞与が支給される場合はその計算方法や支給時期、退職手当がある場合はその詳細を具体的に記載しましょう。
創業支援等措置による追加事項
2021年に施行された改正高年齢者雇用安定法に関連し、労働条件通知書には「賃金に関する追加事項」を新たに記載する必要があります。
この法改正によって、企業は70歳までの就業機会確保を努力義務とし、その一環として高年齢者の創業支援等措置を導入することが推奨されています。そのため、モデル労働条件通知書にも最新の法改正に適応する形で、賃金に関する明示事項が更新されています。
自社で労働条件通知書を作成する場合、退職に関する事項として、新たに「創業支援等措置に関する情報を明示すること」が求められます。これは高年齢者が70歳まで働くことが可能となるための措置であり、将来的には義務化される可能性があるため、今の段階で対応しておくことが推奨されます。
中小企業退職金共済制度・企業年金制度による追加事項
中小企業退職金共済制度や企業年金制度(企業型確定拠出年金制度・確定給付企業年金制度)を利用した退職金制度がある場合、労働条件として口頭または書面で明示しなければなりません。
これに伴い、モデル労働条件通知書にも中小企業退職金共済制度、企業年金制度に関する事項が追加されました。明示する書面は、「労働契約書、労働条件通知書又はこれに準ずるもの」とされています。
そのため、必ずしも労働条件通知書での明示が必要ではないものの、労働条件通知書にこれらの事項を追加することで、複数の書面での明示を避けることができます。
就業規則を確認出来る場所や方法の追加
就業規則の周知方法については労働基準法で義務付けられているものの、必ずしも労働条件通知書に具体的に記載する必要はないとされています。それでも、労働者に対する周知の重要性を踏まえ、企業としてはわかりやすく明確に就業規則の場所を示すことが望ましいです。
ここまで記載すべき事項を押さえたところで、実際に労働条件通知書(兼雇用契約書)を作成する際に参考にできるサンプルがほしいという方向けに、当サイトでは社労士が監修した労働条件通知書のフォーマットを配布しています。
令和6年に労働条件の明示ルールが変更された点も反映した最新のフォーマットで、雇用契約書として兼用することもできる雛形です。「これから作る雇用契約書の土台にしたい」「労働条件通知書を更新する際の参考にしたい」という方は、ぜひこちらからダウンロードの上、お役立てください。
5. 労働条件を明示するタイミング
 労働条件の明示が義務付けられるタイミングは、労働基準法第15条1項により、「労働契約の締結」の時と定められています。
労働条件の明示が義務付けられるタイミングは、労働基準法第15条1項により、「労働契約の締結」の時と定められています。
具体的には、従業員に採用の内定を出した時点で労働契約の締結と見なされ、内定時に労働条件の明示義務が発生します。内定の段階で労働条件を明示することは、入社後ではなく事前に従業員との間で明確な合意を形成し、将来的なトラブル防止に役立ちます。
ただし、雇用する状況によってタイミングが異なるので、ここではそれぞれのタイミングを解説していきます。
参考:労働基準法の基礎地域
参考:採用内定時に労働契約が成立する場合の労働条件明示について|厚生労働省
5-1. 有期雇用契約を更新する場合
有期雇用契約を更新する際には、労働基準法15条1項に基づき、新規雇用と同様に労働条件の明示をおこないましょう。
契約更新の場合、最初に労働契約を結ぶ際に労働条件を明示しているので、更新の時には「明示する必要はない」と思うかもしれません。しかし、賃金や労働時間、勤務場所などの条件に変更がないこと(もしくは変更があること)を明確にするためには、契約更新のタイミングで再度明示をおこなう必要があるのです。
担当者の方の手間がかかりますが、改めて明示をすることで、従業員も労働条件の確認ができるので、労働争議の予防にもつながります。
5-2. 定年後の再雇用をする場合
労働基準法15条1項には、「労働契約の締結に際し」という規定がありますが、これには正社員として雇用していた従業員が定年に達した後、再雇用する場合も含まれます。つまり、定年後再雇用の際にも、使用者は従業員に対して労働条件を明示する必要があります。
この明示義務には、給与や勤務時間、職務内容などの基本条件だけでなく、再雇用後の試用期間や解雇条件についても含まれます。
また、最新の法改正情報を踏まえて、企業の人事担当者や経営者は適切なタイミングで労働条件を再確認し、従業員に明確に伝えることが重要です。再雇用契約を円滑に進めるためにも、事前にこれらの条件を従業員に説明し、合意を得ることが求められます。
5-3. 在籍出向の場合
在籍出向というのは、企業が従業員を自社に在籍させたまま他社に出向させるという就業形態になります。在籍出向に関しては、すでに「就業場所・業務の変更の範囲の明示」で従業員に伝えているため、自社で労働条件を再度明示する必要はありません。
しかし、出向先と出向者の間でも新たな労働契約が成立するので、出向先では労働基準法15条1項に基づいて労働条件の明示をおこなう義務があります。
具体的には、通常と同じく出向開始前に賃金や労働時間、休憩時間、休日、業務内容、労働契約の期間などの詳細な労働条件を出向者に対して明示しなければなりません。
6. 労働条件通知書の書き方
 労働条件通知書は、労働条件明示ルール改正に伴い、その内容と記載方法が重要性を増しています。この通知書は、労働条件を明確に記載しなければならないと定められていますが、様式や形式には規定がありません。
労働条件通知書は、労働条件明示ルール改正に伴い、その内容と記載方法が重要性を増しています。この通知書は、労働条件を明確に記載しなければならないと定められていますが、様式や形式には規定がありません。
しかし、厚生労働省のホームページには、最新の法改正に対応した労働条件通知書のモデル様式が公開されています。このモデル様式を参考にすれば、全ての明示事項を漏れなく記載できるので、法的なリスクの回避につながります。
ここでは、労働条件明示ルール改正に対応した労働条件通知書の書き方を解説します。
参考: モデル労働条件通知書|厚生労働省
6-1. 労働条件通知書のモデル様式例
2024年度の法改正により、労働条件通知書に追加された3つの明示事項は「契約期間」「就業の場所」「業務の内容」です。これらを記載する際の注意点は、以下のようなものが挙げられます。
契約期間
労働条件の明示に関する法的義務には、契約期間に関する詳細な情報の提供が求められています。
特に「期間の定めあり」とする場合、更新上限の有無を明確に記載する必要があります。例えば、「契約期間は通算4年を上限とする」や「契約5回まで(1回目/5回目)」などと具体的に記載することで、労働者に正確な条件を伝えることができます。
さらに、無期転換申込権が労働者によって行使されなければ、更新のたびに明示が必要となります。そのため、モデル労働条件通知書に倣い、無期転換申込機会の明示をあらかじめフォーマット化するのが望ましいでしょう。
就業の場所・業務の内容
「就業の場所・業務の内容」については、変更の範囲を具体的に指定することが重要です。
例えば、「●●営業所」「○○県内」「会社の定める○○」といった範囲を明示することで、労働者との認識を共有しやすくなります。
特に就業場所や業務内容に限定がない場合には、国内外すべての可能性について包括的に記載する必要がありますが、この際、労働者から具体性を求められることも考慮し、可能な限り詳細に記述することが求められます。
また、テレワークの可能性がある場合や、明らかに変更がないと想定される場合も、その旨を明記することで労働者とのトラブルを未然に防ぐことができます。
具体例としては、「雇入れ直後の就業場所を「仙台営業所」とし「変更の範囲」を「会社の定める営業所」とする」「業務内容を「広告営業」として「社内でのすべての業務」へ変更可能である」、というようにしっかり明記しましょう。
6-2. 雇用契約書との違い
従業員を雇用する際には、労働条件通知書だけでなく雇用契約書を交付する企業もあります。
雇用契約書は労働条件を記載するため、労働条件通知書と同じというイメージがあるかもしれませんが、交付義務の有無や役割に違いがあるので、正確に理解しておくことが重要です。
労働条件通知書は法律で作成および交付が義務づけられており、労働者に対して一定の労働条件を明示するために使用されます。これは、労働基準法第15条に基づいて労働者に対する基本的な権利を守るためのもので、企業側が一方的に作成する書類です。
一方、雇用契約書は、労働者と企業の双方が合意した契約を明文化した書類であり、双方の同意が必要です。このため、労働条件通知書とは異なり、法律上の義務ではなく、企業の内部ルールや労働者との合意に基づいて作成されます。
つまり、労働条件通知書は企業から労働者への一方的な通知、雇用契約書は双方の合意が反映された書類という違いがあるのです。
これらの違いを理解することは、人事担当者や企業経営者が法的義務を遵守し、適切な労働環境を整えるために非常に重要です。
7. 労働条件を明示してトラブルを防ごう
 従業員を雇用する際は、新規であっても契約更新であっても、再雇用であっても労働条件の明示が必須となります。これは、労働基準法で定められていることなので、必ず書面で交付しなければなりません。
従業員を雇用する際は、新規であっても契約更新であっても、再雇用であっても労働条件の明示が必須となります。これは、労働基準法で定められていることなので、必ず書面で交付しなければなりません。
また、2019年4月1日の法改正により、書面だけでなく電子化での対応も可能にはなりましたが、電子化の場合には「従業員が希望している」という条件があるので自社の判断で電子化することはできません。
このように、労働条件の明示については、法律によってさまざまな規定があるので、担当者の方は対応を間違えないように注意しましょう。また、不定期ですが法改正もおこなわれるため、交付する際には必ず内容をチェックしてください。
労働条件の明示は面倒かもしれませんが、書面として残すことでトラブルの回避にもつながるので、法に則って正確に作成しましょう。
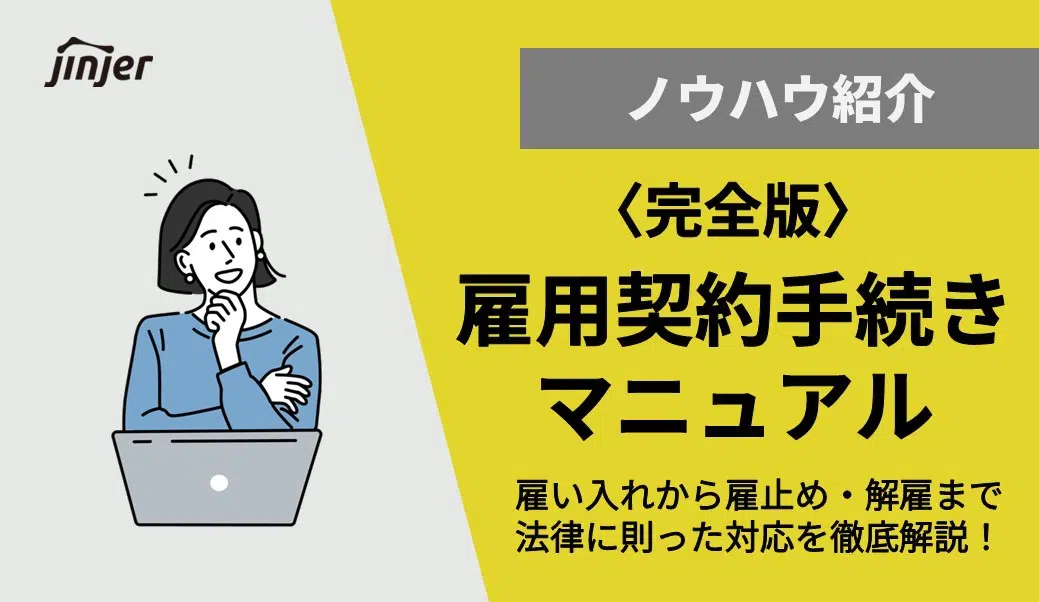
「長年この方法でやってきたから大丈夫」と思っていても、気づかぬうちに法改正や判例の変更により、自社の雇用契約がリスクを抱えているケースがあります。
従業員との無用なトラブルを避けるためにも、一度立ち止まって自社の対応を見直しませんか?
◆貴社の対応は万全ですか?セルフチェックリスト
- □ 労働条件通知書の「絶対的明示事項」を全て記載できているか
- □ 有期契約社員への「無期転換申込機会」の明示を忘れていないか
- □ 解雇予告のルールや、解雇が制限されるケースを正しく理解しているか
- □ 口頭での約束など、後にトラブルの火種となりうる慣行はないか
一つでも不安な項目があれば、正しい手続きの参考になりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
労働条件の関連記事
-

労働条件明示のルールが2024年4月に改正!企業の対応や注意点を解説
人事・労務管理公開日:2023.10.27更新日:2026.01.28
-

労働条件変更同意書の記載事項や記入のポイントについて
人事・労務管理公開日:2022.01.23更新日:2025.09.29